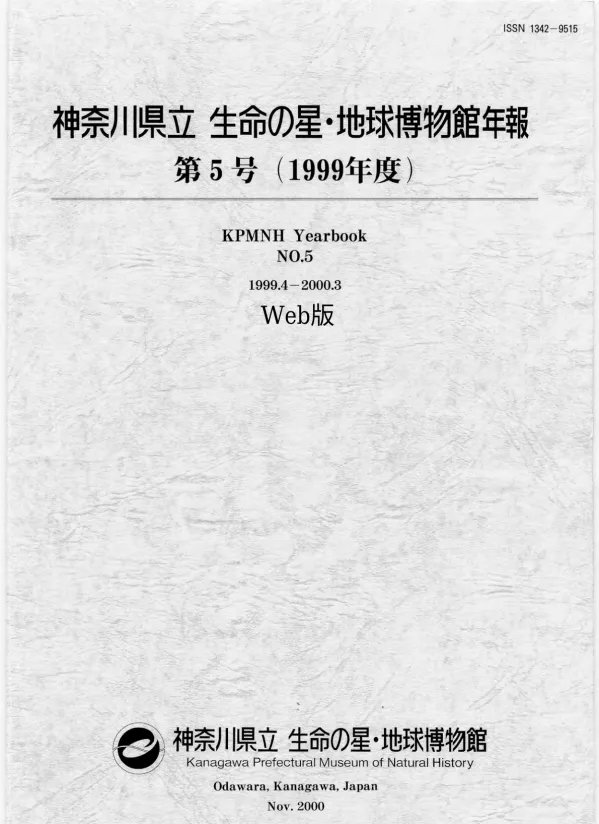
神奈川県立生命の星・地球博物館年報
文書情報
| 著者 | 神奈川県立生命の星・地球博物館職員 |
| 学校 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 |
| 専攻 | 博物館学、自然史、地球科学等 |
| 場所 | 小田原市 |
| 文書タイプ | 年報 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 9.62 MB |
概要
I.調査 研究活動と博物館の現状
神奈川県立生命の星・地球博物館を含む日本の多くの博物館は、厳しい経済状況下、調査・研究活動、特に【特別展】や【企画展】の開催に影響を受けています。しかし、学芸員の【研究発表会】での成果や【学会賞】受賞など、質の高い研究活動は継続されており、自由な研究環境の重要性が示唆されています。開館5周年を迎え、自己意識の【刷新】と【復元】の機会として、今後の発展に向けた取り組みが求められています。 経済不況の影響は、イベント開催数の減少という形で現れていますが、各館は独自の工夫で対応しています。
1. 社会情勢と博物館活動への影響
学芸員の主要業務である調査研究は、社会情勢の影響を大きく受けています。特に、空前の経済不況は各博物館の活動後退・縮小を招き、特別展や企画展開催への影響は顕著です。財政難の中、事務当局との連携による運営努力と、各個人の資金繰り努力によって活動を維持しているのが現状です。博物館活動の成果は厳しい社会的評価の対象となるため、マイナス評価を最小限に抑えるための努力が不可欠です。近年増加する社会的不祥事の影響も避けられず、当館でも常設展示物の盗難事件が発生しました。これは館運営への警告と捉えつつ、一方で館員の学会賞受賞のような吉報は、今後の発展への励みとなります。開館5周年を機に、これまでの活動を反省し、自己意識を見直し、博物館の復元と刷新を図る必要があります。日々の地道な活動が、博物館の大きなメカニズムを支えていることを忘れてはなりません。
2. 博物館における研究活動の現状と課題
近年の学芸員研究発表会では、多くの質の高い研究成果を目の当たりにし、自然史研究の中心を担う博物館の本来の姿を改めて実感しました。発表された研究の質の高さと、それを可能にする博物館の雰囲気に安心感を覚えました。しかしながら、自由な研究活動が制限されている博物館も多いのが現状です。理想的な環境とは言い難いものの、学芸員一同、研究への情熱を持ち続け、日本の博物館界の発展に貢献していきたいと考えています。 このことは、研究活動の自由度が、博物館の活性化に大きく影響することを示唆しています。 研究成果の発表の場として年報なども活用されており、その充実が求められています。
3. 経済状況と博物館活動の現状
日本の博物館界は、深刻な経済不況の影響を受けており、多くの博物館が活動の後退や縮小を余儀なくされています。特に、博物館活動の対外的なイベントの中核を担う特別展や企画展の開催には大きな影響が出ています。様々な工夫や努力がなされているものの、厳しい財政状況は依然として博物館活動を圧迫しています。この状況は、当館に限らず、多くの博物館が共通して抱える問題です。限られた予算の中で、質の高い展示やイベントを継続していくためには、効率的な運営と創意工夫が求められます。 この困難な状況下でも、学芸員たちは質の高い研究を続け、その成果を社会に発信し続けています。
II.情報発信機能 常設展と特別展
当館は「生命の星・地球」を基本テーマとした【常設展】(4つのサブテーマ、ジャンボブック、ツク)と、年2~3回の【特別展】を開催し、来館者への情報発信を行っています。 インタラクティブなクイズ番組「怪人ネイチャーランドの挑戦」は、地球科学、植物、魚類、動物、ヒトに関するクイズを通して来館者を引き込んでいます。これらの展示やイベントは、博物館の【情報発信機能】を効果的に果たしています。
1. 常設展 生命の星 地球
当博物館の常設展は、「生命の星・地球」を基本テーマとし、46億年にわたる地球の歴史と生命の営み、そして神奈川の自然を分かりやすく展示しています。 実物資料を基にストーリー性を持たせた展示構成となっており、4つのサブテーマ、ジャンボブック、ツクなど多様な展示方法を用いて、来館者へ情報を効果的に伝達しています。 これらの展示は、来館者に地球科学、生物学、そして地域固有の自然に関する理解を深めてもらうことを目的としています。 博物館の常設展示は、教育的要素とエンターテイメント性を両立させている点が特徴的です。 この常設展示は、博物館の主要な情報発信手段の一つとして機能しています。
2. 特別展 特定テーマによる情報発信
常設展に加え、当館では特定のテーマに焦点を当てた特別展を年2~3回開催し、来館者への情報発信を強化しています。 特別展は、常設展では扱いきれない専門的な内容や、時事的な話題を取り上げることで、来館者の多様なニーズに対応することを目指しています。 特別展は、常設展示と同様に、実物資料や分かりやすい説明を用いて構成されますが、より深く、特定のテーマに特化した内容となっています。 さらに、特別展に合わせてポスターやチラシを作成し、県内外の様々な機関に配布することで、広報活動も積極的に行っています。 これらの特別展は、博物館の学術研究成果を一般の人々に伝える重要な役割を担っています。
3. インタラクティブな情報発信 クイズ番組
当館では、来館者参加型のインタラクティブな情報発信にも力を入れています。その一例として、「怪人ネイチャーランドの挑戦」というクイズ番組があります。 この番組は、怪人が盗み出した水晶玉を、来館者がクイズに答えることで取り戻していくというストーリー仕立てになっており、来館者の回答によってストーリー展開が変化する、独特のインタラクティブ性を持っています。 クイズのテーマは「地球は生きている」「植物は変身の天才だ」「魚のサバイバル」「動物の足跡捜査隊」「ヒトの謎を科学する!」の5種類で、地球科学、生物学、そして人類学に関する知識を楽しく学べるよう工夫されています。 このようなインタラクティブな展示は、来館者の積極的な参加を促し、より深い理解を促す効果が期待できます。
III.開館5周年記念事業 講演会と資料活用
2000年の開館5周年記念事業として開催された講演会では、【博物館資料の活用】がテーマでした。 収集された資料は研究や展示に利用されるだけでなく、生涯学習の場としての博物館の役割においてますます重要となっています。特に、ダイバー撮影による【水中写真】の収集とデータベース化は、魚類研究に役立つ新しい試みとして紹介されました。講演では、【博物館資料】の有効活用、バーチャルと実物の資料のバランス、植物標本の利用法などが議論されました。講演者には潰田隆士氏、勝山輝男氏が含まれます。
1. 開館5周年記念講演会 博物館資料の活用
1995年3月の開館以来、2000年3月に開館5周年を迎えた当館は、これを記念して講演会と展示会を開催しました。講演会は「博物館は宝の山 博物館資料の活用」をテーマに、博物館資料の活用事例、問題点、そして将来展望について議論されました。博物館資料は、研究材料や展示物として利用されるだけでなく、生涯学習の場としての博物館の役割においてますます重要性が増しています。展示物だけでなく、バックヤードに保管されている膨大な資料をどのように活用していくのかが重要な課題となっています。講演では、最新の試みとして、ダイバーが撮影した水中写真の収集とデータベース化が紹介され、その客観性と美しさ、そして研究への活用可能性が強調されました。水中写真は、研究者にとってまさに「埋もれた宝の山」であり、データベース化によって魚類研究が大きく進展する可能性を示唆しています。 潰田隆士氏による講演では、博物館資料の有効活用が改めて強調されました。
2. 博物館資料の活用 新たな視点と課題
講演会では、博物館資料の活用に関する様々な視点が提示されました。潰田隆士氏による講演「博物館資料と博物館活動理念」では、バーチャルなデジタルミュージアムではなく、実物の資料(「物」)が不可欠であると主張し、電子情報はあくまで補佐役であるべきと強調しました。 また、資料を収蔵庫に抱え込んでいるだけでは、博物館資料の真価は発揮されないと指摘し、生涯学習の時代において、資料を最大限に活用していく必要性を訴えました。勝山輝男氏による「植物標本のススメ」では、植物の同定に図鑑だけでは限界があることを指摘し、植物標本庫(ハーバリウム)の利用を推奨しました。欧米では国立ハーバリウムが植物研究の中枢を担っていますが、日本では大学や博物館で小規模に維持されているのが現状です。日本のハーバリウム整備の遅れを指摘しつつも、アマチュア植物研究家の存在と、彼らが博物館のハーバリウムを活用することで日本の植物研究が発展していく可能性を示唆しました。
IV.シンクタンク機能 学芸員の研究活動
当館の学芸員は、県内外の【シンクタンク】として、様々な研究活動を行っています。 具体的な研究テーマとしては、フィリピン海プレートの深部岩石、高温高圧実験によるキンパライトマグマの成因、植生バイオマス推定のためのアルゴリズム開発、博物館における視覚障害者の学習活動に関する調査研究などが挙げられます。これらの研究成果は、学会発表や論文発表を通じて公表されています。
1. シンクタンクとしての博物館の役割
博物館は研究機関としての側面を持ち、学芸員は県内のみならず、国内外にわたるシンクタンクとして多様な活動を展開しています。この文書では、当館を中心に活動する項目について、各学芸員の自己申告に基づいて記述されていますが、記録の困難さから網羅できていない活動も多いとされています。特に、資料の同定依頼などのレファレンス業務には相当な時間が費やされていると推察されます。このことは、学芸員の業務の多様性と、その負担の大きさを示唆しています。博物館が地域社会や学術研究に貢献する上で、学芸員の専門知識と研究活動の重要性が改めて認識されます。 今後の博物館のあり方において、学芸員の専門性を活かしたシンクタンク機能の更なる強化が求められます。
2. 学芸員の研究活動事例
文書では、複数の学芸員による具体的な研究活動事例が紹介されています。小出良幸氏によるフィリピン海プレートの深部岩石に関する研究、山下浩之氏による高温高圧実験を用いたキンパライトマグマの成因に関する研究、新井田秀一氏による植生バイオマス推定のためのアルゴリズム開発、奥野花代子氏による博物館における視覚障害者の学習活動に関する調査研究などが挙げられます。これらの研究は、地質学、地球科学、植物生態学、博物館教育など多様な分野に広がり、それぞれの専門性を活かした質の高い研究が行われていることを示しています。これらの研究成果は、学会発表や論文発表を通じて公表され、学術界への貢献だけでなく、博物館の社会的な役割を担う上でも重要な役割を果たしています。 これらの研究は、博物館が単なる展示施設ではなく、学術研究の中心的役割を担っていることを示しています。
3. 研究活動の記録と課題
学芸員の研究活動は多岐に渡りますが、全ての活動を記録することは困難であり、文書には記載されていない活動も多いとされています。特に、資料の同定依頼などのレファレンス業務は、多くの時間を費やしながらも、記録に残りにくい側面があります。これは、博物館における研究活動の現状を正確に把握する上で、大きな課題となっています。 今後、研究活動の記録方法の改善や、レファレンス業務の効率化などを検討していく必要があります。 より正確な情報把握のためには、「産地」の定義の明確化なども課題として挙げられています。
V.学習支援機能 博物館の教育的役割
当館は【学習支援機能】を重視し、年間約90回の講座や講演会などを開催しています。 ミューシアムライブラリーによる自発的な学習機会の提供や、団体利用者への学習指導員の派遣なども行っています。【特別展】に合わせたポスターやチラシの作成・配布による【広報活動】も活発に行われています。配布先は、県内自治体、観光協会、学校、全国の大学、博物館、旅行代理店、メディアなど多岐に渡ります。
1. 学習支援プログラムの提供
博物館は県民の生涯学習活動を多角的に支援する重要な役割を担っています。当館では、企画情報部が事務職員と研究職員(学芸員)の協力体制の下、円滑な学習支援体制を構築しています。年間約90回もの様々な行事を実施しており、その半数は当館主催の講座や講演会です。多様なニーズに対応した学習支援プログラムを提供することで、県民の生涯学習活動を積極的に支援しています。 これらのプログラムは、博物館が持つ専門知識や資料を最大限に活用し、教育的効果を高めることを目的としています。 学習支援プログラムは、単なる知識の伝達だけでなく、体験を通して学習できる機会を提供するなど、多様な学習方法を取り入れています。
2. 学習環境の整備 ミューシアムライブラリーと学習指導員
自発的な学習を促進するため、当館はミューシアムライブラリーを設置し、来館者が自由に学習できる環境を整備しています。 また、団体利用者に対しては、要望に応じて学習指導員による学習支援を提供しています。学習指導員は、専門的な知識を有し、来館者の学習内容や理解度に応じて適切な指導を行うことで、より効果的な学習をサポートしています。 ミューシアムライブラリーと学習指導員の連携は、来館者の学習意欲を高め、より深い理解を促す上で重要な役割を果たしています。 このような環境整備によって、博物館は単なる展示施設ではなく、学習の場としての機能を強化しています。 これらの取り組みは、博物館が生涯学習社会に貢献するための重要な要素となっています。
3. 広報活動 特別展への積極的なPR
夏と秋に開催された2回の特別展に合わせて、ポスターとチラシを作成し、県民への周知を図るための広報活動を実施しました。これらの印刷物は、来館者への直接的なPR媒体としてだけでなく、県内外の様々な機関へ配布されました。配布先は、各自治体の広報窓口、観光協会、旅館・保養所、公立図書館、小中高等学校、盲ろう養護学校、全国の大学(図書館・博物館学講座)、各種博物館園、旅行代理店、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・Webサイトなど、多岐にわたっています。 この積極的な広報活動は、博物館の認知度向上と来館者数の増加に繋がる効果が期待できます。 特別展のテーマに合わせた効果的な広報戦略によって、より多くの県民に博物館の活動内容を伝え、参加を促すことを目的としています。
VI.連携機能 神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会
「神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会」(略称:WESCAMS)は、地域の博物館間の連携を強化し、新しい博物館のあり方を模索する目的で設立されました。 この連絡会では、定期的な意見交換会や【ミュージアム・リレー】など、共同事業を実施しています。【ミュージアム・リレー】は、西部地域の自然と文化を紹介する持ち回りイベントで、当館も積極的に参加しています。
1. 神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会 WESCAMS の設立
神奈川県西部地域の博物館のネットワーク化と、今後の博物館のあるべき姿について議論するため、賓田隆士前館長(平成12年3月31日退職)の呼びかけにより、平成8年7月に「神奈川県西部地域の博物館(園)長等意見交換会」が開催されました。 この意見交換会がきっかけとなり、平成9年9月に「神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会」(愛称:WESCAMS)が発足しました。 WESCAMSは、神奈川県立生命の星・地球博物館が当面の間、とりまとめ役を務めることになりました。この連絡会は、地域連携による博物館活動の活性化を目指し、各館の特色を活かした連携事業の展開を目指しています。 地域博物館間の連携強化は、資源の共有や効率的な運営、そして地域社会への貢献を促進する上で重要な役割を果たします。
2. 連携事業 館長等意見交換会とミュージアム リレー
WESCAMSでは、年2回「館(園)長等意見交換会」を開催し、情報交換や連携強化を図っています。平成11年度は、8月25日に箱根町立箱根湿生花園で第7回、平成12年2月24日に小田原市郷土文化館で第8回を開催しました。 また、連携・協調事業の一つとして、「ミュージアム・リレー 神奈川県西部地域の自然と文化」が平成9年10月にスタートしました。これは、西部地域の自然と文化を理解してもらい、博物館への関心を高めることを目的とした持ち回りイベントで、毎月1回、各館園が協力して開催しています。 平成11年度は当館で年2回開催され、演田隆士館長が「地球物語」と題した講演を行いました。参加者は一般、高校生、博物館関係者など合計95名に上りました。 このミュージアム・リレーは、地域住民と博物館との繋がりを強化する上で重要な役割を果たしています。
3. ミュージアム リレーと連携による取り組み
ミュージアム・リレーは、南関東地域の自然を「大地」と「水」の視点から捉え、特色あるテーマで活動する7つの博物館(神奈川県立生命の星・地球博物館(コア館)、江ノ島水族館(コア館)、川崎市青少年科学館、相模原市立ふれあい科学館、伊豆大島火山博物館、奇石博物館、東海大学海洋科学博物館)が連携して実施しています。 これらの博物館は、子どもたちのための自然科学に関するエデュテインメント性豊かな学習機会の創出と学習プログラムの作成を目指してネットワークを組んでいます。 平成11年10月6日には、ミュージアム・リレー2周年記念として「ミュージアム・エデュテインメント(博物館楽修)」が開催され、箱根ガラスの森岩田正雀館長と演田隆士館長による講演が行われました。 この連携事業は、地域の博物館の連携強化と、より効果的な学習機会の提供を目指した取り組みです。
VII.研究設備
当館は、岩石薄片作成装置、偏光顕微鏡、実体顕微鏡、デジタルフォースゲージなど、様々な【研究設備】を備えています。 これらの設備は、学芸員の研究活動や資料の分析に利用されています。
1. 研究設備の概要
文書の最後には、当館が保有する研究設備の一覧が記載されています。これらは、学芸員の研究活動や資料の分析に不可欠な機器です。具体的には、自動メノウ研磨機(日本電産シンポ製)、撮影装置付き偏光顕微鏡(ニコン製)、撮影装置付き双眼実体顕微鏡(オリンパス製)、岩石薄片作成装置(マノレトー製)、精密研磨台(Struers製)、岩石切断研磨装置(Discoplan-Struers製)、エポキシ樹脂真空含浸装置(Evac Struers製)、真空装置(G-50S他)、自動染色装置(サクラファインテック製)、ミクロトーム(ツアイス社製)、荷重計(日本電産シンポ製)、デジタルフォースゲージ(日本電産シンポ製)、培養器など多様な機器が挙げられています。これらの設備は、地質学、生物学、その他の自然科学分野の研究を支える上で重要な役割を果たしており、質の高い研究成果を上げるために不可欠なインフラです。 これらの設備の維持管理は、博物館の研究活動を支える上で重要な要素であり、継続的な投資と適切な運用が必要です。
