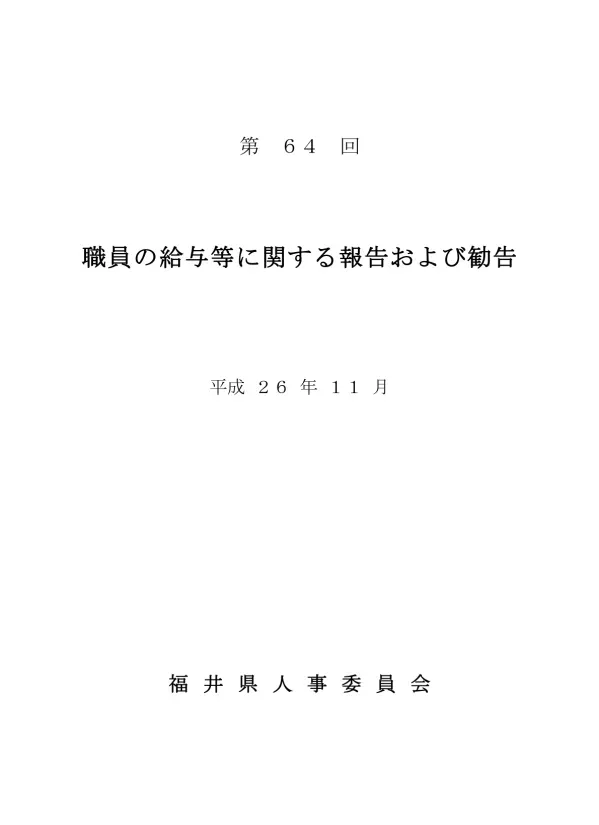
福井県職員給与報告:平均給与と実態調査
文書情報
| 著者 | 野村 直之 |
| 学校 | 福井県人事委員会 |
| 専攻 | 公務員給与 |
| 場所 | 福井県 |
| 文書タイプ | 報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.56 MB |
概要
I.福井県職員給与実態調査 平成26年度 の給与水準と官民比較
本調査は、福井県職員(技能労務職員を除く)13,307名の平成26年4月時点の給与実態を把握するため実施されました。平均年齢は42.6歳、男性比率は58.1%でした。月例給、特別給、諸手当(地域手当、扶養手当等)を含む詳細な給与データが分析され、同時に、給与改定状況や各種手当の支給状況も調査されました。民間企業との比較では、企業規模50名以上の県内112事業所を対象とした「平成26年職種別民間給与実態調査」の結果を用いて、官民給与比較が行われました。その結果、行政職に類する職種では、民間給与が福井県職員給与をわずかに上回ることが明らかになりました。
1. 福井県職員給与実態調査の概要
本委員会は、福井県一般職職員の給与実態を把握するため、平成26年4月に「平成26年福井県職員給与実態調査」を実施しました。調査対象は、技能労務職員を除く13,307名の職員で、平均年齢は42.6歳、男性比率は58.1%でした。調査項目は、平成26年4月分の給与月額、給与改定状況、諸手当(地域手当、扶養手当など)の支給状況など、多岐に渡ります。個々の職員への給与実態を詳細に把握するため、実地調査を実施しました。この調査結果に基づき、福井県職員の給与水準、特に月例給、特別給、そして各種手当の支給状況に関する詳細な分析がなされました。再任用職員は今回の調査対象から除外されています。調査データは、給与水準の現状把握、今後の給与改定に関する重要な基礎資料となります。
2. 民間給与実態調査と比較対象
職員給与と民間の給与水準を正確に比較するため、「平成26年職種別民間給与実態調査」を実施しました。調査対象は、企業規模50名以上かつ事業所規模50名以上の県内民間事業所112社です。層化無作為抽出法を用いて選定されたこれらの事業所において、公務と類似する職務に従事する事務・技術関係22職種3,642名、研究員・医師等54職種379名の給与データが収集されました。この民間給与データは、福井県職員給与との比較分析に用いられ、官民間の給与格差を明らかにするための重要な要素となりました。特に、役職段階、学歴、年齢が同等とみなせる職員と民間従業員を比較することで、より精緻な給与比較が可能となりました。
3. 福井県職員給与と民間給与の比較分析 月例給を中心に
福井県職員給与実態調査と民間給与実態調査の結果を基に、行政職に相当する職種について、役職段階、学歴、年齢が同等な職員と民間従業員の4月分の給与額をラスパイレス比較法を用いて比較しました。その結果、民間給与が職員給与を948円(0.26%)上回っていることが明らかになりました。この差は、春季賃金改定における民間企業のベースアップ実施率増加と、職員の平均給与額減少(給与構造改革等による影響)が要因と考えられます。この分析結果は、福井県職員給与の現状と民間給与との比較を示すものであり、今後の給与改定に関する重要な示唆を与えています。特に、月例給におけるわずかながらも民間給与を下回っている状況は、今後の給与政策を考える上で重要な課題となります。
II.人事院勧告と福井県職員給与改定 給与制度 の総合的見直し
人事院勧告を踏まえ、福井県は職員給与の改定を決定しました。勧告では、民間賃金水準の低い地域における官民給与差、50歳代後半層の官民給与差、職務・勤務実績に応じた給与配分などの課題が指摘されています。福井県は、これらの課題を考慮し、月例給と特別給の引上げ、地域手当・単身赴任手当等の諸手当の改定を実施しました。具体的には、単身赴任手当の基礎額と加算額の引き上げ、広域異動手当の増額などが含まれます。地方公務員法の「均衡の原則」に基づき、国家公務員の給与制度を参考にしながら、福井県独自の事情も考慮した改定が行われました。
1. 人事院勧告の内容と福井県への影響
人事院は、国家公務員の給与制度の総合的見直しを勧告しました。その柱は、①民間賃金水準の低い地域における官民給与差への対応、②50歳代後半層の官民給与格差への対応、③職務や勤務実績に応じた給与配分の見直しです。 これらは、公務員給与の高騰に関する批判への対応、世代間の給与格差の是正、そして人材確保・組織の効率的な運営といった課題解決を目指しています。 福井県においても、これらの課題は共通しており、人事院勧告の内容は県職員の給与制度見直しに大きな影響を与えました。 特に、50歳代後半層の給与水準は民間と比較して高くなっているという指摘は、今後の給与改定において重要な考慮事項となりました。また、地域間の給与格差についても、福井県独自の状況を踏まえた対応が求められました。
2. 福井県職員給与改定 月例給と特別給の改定
人事院勧告と福井県の実情を考慮し、月例給および特別給の引上げ改定を行うことが決定されました。 これは、前述の調査で明らかになった、福井県職員の月例給与が民間給与をわずかに下回っている状況を踏まえたものです。 具体的には、人事院勧告における国家公務員俸給表の改定状況、そして県内の民間給与水準との均衡を考慮し、公民較差を踏まえた適切な引上げ改定を行う必要がありました。 また、期末手当・勤勉手当についても、民間の特別給支給状況や人事院勧告を考慮し、支給割合の引き上げが検討されました。 これらの改定は、職員の士気向上と人材確保、ひいては効率的な行政運営に資することが期待されています。 改定の実施時期は、多くの項目が平成26年4月1日から、単身赴任手当と寒冷地手当については平成27年4月1日からとされました。
3. 福井県職員給与制度の総合的見直し 諸手当の改定と今後の課題
給与制度の総合的見直しとして、諸手当の改定も実施されました。地域手当については、人事院勧告に準じ、級地区分と支給割合の見直しが行われました。ただし、県内特定地域勤務職員への地域手当は、国の見直しで変更がないため、現状維持となりました。単身赴任手当は、人事院勧告に準じて基礎額と加算額が改定され、増加しました。管理職員特別勤務手当は、災害対応などの深夜勤務に対する支給要件が明確化されました。 これらの改定は、人事院勧告を基本にしながら、福井県独自の状況も考慮して行われました。 さらに、国と他都道府県の状況を踏まえ、昇給停止措置などの経過措置も検討されました。 これらの改定は、職員の処遇改善と、県民サービスの向上に貢献することが期待されています。しかしながら、長時間労働の削減や、女性職員の活躍推進、高齢期雇用への対応など、今後も継続的な給与制度の見直しが必要とされています。
III.その他重要な施策 長時間労働対策 女性活躍推進 高齢期雇用
福井県は、長時間労働の削減に向けた取り組み、女性職員の仕事と家庭の両立支援、高齢期雇用の確保など、多岐にわたる人事施策にも言及しています。長時間労働対策として、業務のスリム化・効率化、超過勤務の事前命令・実績管理の徹底などが挙げられています。女性活躍推進では、育児休業取得促進、ハラスメント防止対策の強化などが推進されています。また、国家公務員の年金支給開始年齢の引き上げを踏まえ、再任用職員の給与や雇用についても検討されています。これらの施策は、公務員の適正な給与の確保と、効率的な行政運営に資するものです。
1. 長時間労働対策
福井県では、職員の総実勤務時間短縮に向け、様々な対策が講じられています。任命権者による業務のスリム化・効率化、意思決定の迅速化といった取り組みが継続されており、これにより超過勤務の削減と適正な人員配置を目指しています。職場管理者においては、職員の業務進捗状況の的確な把握、所属内業務の平準化、超過勤務の事前命令および実績管理の徹底など、職員の勤務管理の適切化が求められています。さらに、職員一人ひとりが、タイムマネジメント意識とコスト意識を持って、計画的かつ効率的に業務に取り組むことが重要であるとされています。これまで、全庁一斉消灯退庁日(ライトダウンデー)やライトダウンウィークの実施など、一定の効果を上げてきたものの、依然として長時間労働が課題として残っています。
2. 女性活躍推進と仕事と家庭の両立支援
女性の活躍推進は重要な課題であり、女性職員の仕事と家庭の両立支援を推進する必要があります。 第2期特定事業主行動計画に基づき、各任命権者による様々な取り組みが行われており、一定の成果が見られています。しかしながら、男性職員の育児休業や配偶者出産休暇の取得率向上のためには、制度の周知徹底、意識啓発、休暇取得しやすい職場環境整備が不可欠です。仕事と家庭の両立支援は、職員の福祉増進、公務能率向上、県民サービス向上、そして将来の人材確保にも繋がる重要な施策です。 県は、計画に掲げられた数値目標の達成に向けた努力を継続し、男女が家庭・地域・会社で活躍できる社会の構築に向けて、先導的な役割を果たしていくことが期待されています。
3. 高齢期雇用 再任用職員の給与と雇用政策
国家公務員の年金支給開始年齢の段階的引き上げに伴い、雇用と年金の接続のための措置が重要となっています。 現状では、公務の再任用は短期間の補完的な業務が約7割を占めています。 平成28年度の年金支給開始年齢の62歳への引き上げを受け、再任用希望者の増加が見込まれることから、職員の能力・経験の公務外活用、業務運営の柔軟化による公務内活用、そして60歳前からの人事管理の見直しが必要となっています。 人事院は人事行政の公正確保と労働基本権制約の代償機能を担い、適切な制度整備に向けて積極的に取り組んでいます。 再任用職員への単身赴任手当の支給など、民間の状況も踏まえた対応が求められ、再任用職員の給与や雇用制度の在り方について、継続的な検討が必要とされています。
