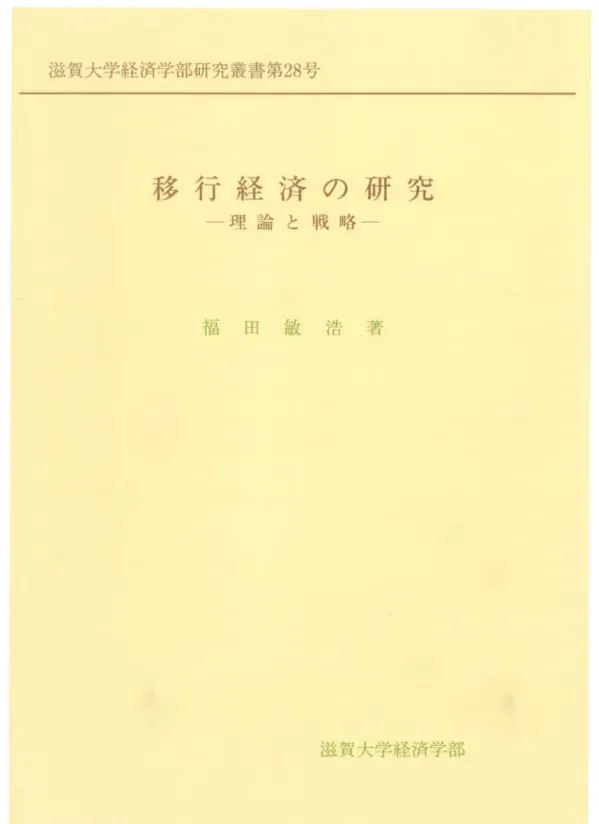
移行経済の研究:理論と戦略
文書情報
| 著者 | 福田敏浩 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 研究叢書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 5.27 MB |
概要
I.社会主義体制からの移行 体制転換 の経済政策
本書は、ポスト社会主義諸国における急激な体制移行、特に社会主義から資本主義への転換を分析しています。ソ連・東欧諸国における短命に終わった社会主義実験を考察し、管理社会主義(国有化・中央管理経済・指令経済)の失敗を解明します。ポーランドの市場社会主義実験の挫折や、ハンガリーにおける市場社会主義から誘導資本主義への移行過程を分析することで、所有構造と調整メカニズムの重要性を強調しています。特に、国有化と市場経済の両立不可能性、私有化の必要性、そして効率性を向上させるための所有と調整のセットとしての考察が重要視されています。
1. 短命に終わった社会主義実験と管理社会主義
ソ連と東欧諸国における社会主義実験は、わずか40~74年で終焉を迎えました。これは期間の短さだけでなく、その性質に特徴があります。共産主義という理想像を目指した能動的な実験ではなく、むしろ場当たり的な問題解決に追われた受動的な実験だったと言えるでしょう。これは、生産手段の固有制、中央管理経済(物財バランスと固定価格による需給調整)、そして指令方式(ノルマ制)を基盤とする管理社会主義が制度化されたためです。各国政府は既存の経済体制を急速に解体しながら管理社会主義を導入しようとしましたが、結果としてソ連邦の崩壊を招くこととなりました。この管理社会主義体制は、市場経済の効率性とは程遠いものでした。経済の停滞、物不足、低品質といった問題を抱え、持続不可能な体制であったことが示されました。 この章では、社会主義実験の失敗要因を分析し、その後の体制転換への布石となった管理社会主義の構造的な問題点を明らかにします。
2. ポーランドにおける市場社会主義実験の挫折
1982年以降、ポーランドはヤルゼルスキ統一労働者党第一書記の下で管理社会主義の改革に着手しました。ハンガリー型市場社会主義をモデルに、固有企業体制(労働者自主管理の導入)、市場経済、誘導的マクロ経済政策を柱とする改革を目指しました。しかし、市場社会主義の導入は予想以上に困難を極め、1988年には経済改革の第二段階が実施されましたが、事態の改善には至らず、深刻なショーティジフレーション(極度の物不足とハイパーインフレーションの同時発生)が発生しました。市場社会主義実験は頓挫し、1989年の東欧革命の震源地となった一因となりました。このポーランドの失敗例は、市場経済の導入が必ずしも容易ではなく、計画経済からの脱却には様々な困難が伴うことを示しています。また、労働者自主管理の導入が必ずしも効率性を高めるわけではないことも示唆しています。
3. ハンガリーにおける市場社会主義と競争政策の限界
ハンガリー政府は、市場経済の機能にとって競争市場が重要であることを認識し、競争政策を推進しました。しかし、1960年代初頭の大規模企業合併により高度に集中していた産業構造は、競争促進策にもかかわらずなかなか解消されませんでした。1980年代には固有企業の分割という大胆な措置が取られましたが、固有企業と監督省の抵抗に阻まれ、ほとんど効果を発揮しませんでした。ハンガリーの経験は、固有方式が省帝国を生み出し、市場参入の自由が制限されることで、企業家的行動が阻害されることを示しています。国家による生産手段の所有と市場経済の組み合わせ、すなわち市場社会主義は、効率性という観点からは「弱い結合」であり、持続不可能であることが示されました。 この章では、競争政策の限界と、市場参入の自由の重要性、そして国有化と市場経済の両立不可能性について論じています。
4. 所有と調整の問題 ワンセット思考の必要性
効率性の観点から、所有の問題と調整の問題はセットとして考察する必要があることが明らかになりました。ハンガリーの実験は、国有と市場の組み合わせから始まりましたが、国有化のブレーキ効果が顕在化したため、政府は固有企業の株式会社化・私有化、そして私企業の設立を余儀なくされました。これは、市場導入が国有化を排除し、私有化を促進することを示しています。著者は、このようなハンガリーの経験に基づき「ワンセット思考」の必要性を主張しています。この考え方は、ミーゼスやオイケンといった先駆者も既に指摘していたもので、合理的経済計算には市場と私有のセットが必要であり、所有形態と調整メカニズムは密接に関連しているというものです。コルナイも、「強い結合」(私有と市場)と「弱い結合」(国有と市場)という概念を用いて、この点を強調しています。 この章では、効率的な経済体制を構築するために、所有形態と調整メカニズムを一体的に考えることの重要性が論じられています。
II.東欧革命とソ連崩壊 体制移行 の契機
1989年の東欧革命と1991年のソ連崩壊は、本書の中心テーマである体制移行を促す決定的な出来事でした。ゴルバチョフのペレストロイカとグラスノスチ政策が、オートクラシー、マルクス・レーニン主義、管理社会主義といったソ連体制の統合要因を崩し、結果としてソ連の解体をもたらしました。東欧諸国においても、ソ連の変革が共産党独裁の崩壊を加速させました。これらの出来事が、多様な体制移行戦略の採用を余儀なくさせた背景となっています。
1. 1989年の東欧革命 連鎖する共産党独裁の崩壊
1989年は東欧革命の年でした。6月のポーランドにおける共産党独裁の終焉を皮切りに、10月にはハンガリーと東ドイツで、11月にはブルガリアとチェコスロバキアで、そして12月にはルーマニアで、相次いで共産党政権が崩壊しました。この革命の直接の原因は、ソ連の内政・外交政策の変化、特にペレストロイカとグラスノスチ政策、そしてブレジネフ・ドクトリンの放棄にあります。ペレストロイカは政治の民主化を含んでおり、ソ連における民主化の動きは、東欧諸国にも大きな影響を与え、ゴルバチョフは東欧諸国の共産党指導部に対し、政治改革を強く求めました。これにより、東欧諸国では体制転換が不可避なものとなり、社会主義体制は急速に崩壊していきました。この革命は、後のポスト社会主義諸国における体制移行の大きな契機となりました。
2. ソ連崩壊 ペレストロイカの意図せざる結果
1991年12月21日、ソ連邦は消滅しました。国土面積2240万平方キロメートル、人口2億8600万人という巨大な国家が、建国からわずか74年で消滅したことは、歴史上類を見ない出来事でした。本書では、ソ連崩壊の直接の原因をペレストロイカにあると指摘しています。ペレストロイカは政治の民主化、情報規制の緩和、経済改革を柱としていましたが、これらの改革が、ソ連を支えていた統合要因(オートクラシー、マルクス・レーニン主義、管理社会主義)を逆に崩壊させる結果となりました。民主化はオートクラシーを、情報規制の緩和はマルクス・レーニン主義を、そして市場経済導入は管理社会主義を弱体化させました。ゴルバチョフの意図とは裏腹に、ソ連邦は解体へと向かっていったのです。このソ連崩壊は、東欧革命と同様に、世界的な体制転換の重要な契機となり、多くの国々が社会主義体制からの脱却を模索するようになりました。
III.東ドイツ 体制移行 の特殊事例
東ドイツは西ドイツとの統一という特殊な体制移行を経験しました。西ドイツによる吸収合併という形で、西ドイツの誘導資本主義と社会的市場経済が導入されました。信託公社 (Treuhandanstalt)による迅速な私有化政策は、管理社会主義体制からのスクラップを短期間で完了させました。この過程は、他のポスト社会主義諸国とは異なるラディカリズムを示す重要な事例です。西ドイツからの巨額な財政援助も、東ドイツの体制移行を成功に導いた要因の一つです。
1. 西ドイツによる吸収合併 アウトサイダー主導の体制移行
東ドイツの体制移行は、西ドイツとの国家統一という独特の経緯を辿りました。これは、西ドイツによる東ドイツの吸収合併であり、東ドイツ国民にとって「アウトサイダー」による体制移行であった点が他のポスト社会主義諸国とは大きく異なります。ロシアやチェコなど、国家解体・分離独立を経て体制移行を進めた国々と異なり、東ドイツは西ドイツの体制をそのまま受け継ぐ形となりました。西ドイツ政府主導で、西ドイツの市場経済制度と専門家の支援、そして巨額の財政援助(国家統一から6年間で約7000億ドル)が提供され、体制移行が推進されました。このアウトサイダー主導の体制移行は、東ドイツ独自の特殊な事例として、他の国々の経験とは比較検討する必要がある重要なポイントです。
2. 信託公社 Treuhandanstalt による迅速な私有化
東ドイツにおける私有化は、信託公社(Treuhandanstalt)によって主導されました。国有資産や国営企業の返還、競売、直売などが行われ、1994年末までにほぼ完了しました。特に競売では約3万の小規模資産が民間人に渡り、鉱工業の国営企業8000社のほとんどが国内外の投資家に売却されました。わずか数年で管理社会主義の経済システムを解体し、資本主義の制度的枠組みを構築したこの迅速な私有化は、他の国々とは対照的な「ビッグバン」型の体制移行であり、その成功と課題を分析する上で重要な事例となっています。信託公社の役割、私有化の速度、そしてその経済的・社会的な影響については、更なる詳細な検討が必要です。残された農地や森林の返還といった課題も、この私有化政策の完全な成功を阻む要素として考慮されるべきでしょう。
3. 国家社会主義との連続性 東ドイツの特殊な歴史的文脈
東ドイツの管理社会主義とナチス時代の国家社会主義との関係性については、異なる見解が存在します。国家社会主義との連続性を否定する説と、連続性を認める説です。後者の立場では、東ドイツがソ連型管理社会主義を導入したとはいえ、その経済管理システムの形成過程において、国家社会主義時代の経済管理方式(価格・賃金統制、物資割り当て、国家指令など)が引き継がれたと主張します。一方、西ドイツでは国家社会主義体制が徹底的に破壊され、社会的市場経済との連続性はありませんでした。この東ドイツの特殊な歴史的文脈は、その体制移行の過程を理解する上で不可欠な要素であり、国家社会主義の遺産が東ドイツの経済システムに及ぼした影響を分析することは、体制移行研究において重要な課題と言えます。この歴史的文脈を踏まえることで、東ドイツの体制移行が他の東欧諸国と比べてどのような特徴を持っていたのか、より明確に理解することができるでしょう。
4. 閉鎖的な知的風土とSEDの市場社会主義
東ドイツの経済学者たちは、他の東欧諸国(ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーなど)と異なり、西側諸国への留学よりもソ連への留学が多かったとされています。これは、東ドイツがソ連の影響下にあり、知的風土が比較的閉鎖的であったことを示しています。1969年の経済学研究科学会議設立による党の統制強化により、東ドイツの経済学界はマルクス主義教条に支配され、改革経済学はほとんど登場しませんでした。SED(社会主義統一党)は1989年10月の「穏やかな革命」直前まで市場社会主義を提唱していましたが、それは国民からの支持を得られず、西ドイツの社会的市場経済導入へと急速に転換しました。このSEDの市場社会主義政策の失敗は、国民の支持を得られない政策は成功しないという重要な教訓を示しています。また、閉鎖的な知的風土が経済改革を阻害する要因となりうることも示唆しています。
IV. 体制移行 戦略 グラデュアリズム対ラディカリズム
ポスト社会主義諸国の体制移行戦略は、漸進的なグラデュアリズムと、急進的なラディカリズム(ショック療法)の二つのアプローチに大別されます。コルナイやハイエクらの理論を背景に、それぞれの戦略の有効性と限界が論じられています。ポーランドのバルツェロヴィチによるラディカルなショック療法や、チェコスロバキアのパウチャー方式による私有化、ハンガリーの漸進的な市場経済への移行などが具体的な事例として分析され、初期条件や社会心理状況が戦略選択に影響を与えることが示唆されています。 経済改革の成功には、国民の支持獲得が不可欠であることも強調されています。
1. グラデュアリズムとラディカリズム 二つの体制移行戦略
1990年代のポスト社会主義諸国では、社会主義から資本主義への体制移行が劇的に進みました。東欧革命、ドイツ統一、ソ連崩壊など、歴史的な出来事が相次ぎ、各国は資本主義への移行を目指した体制転換に着手しました。この体制移行戦略には、大きく分けて二つのアプローチが存在します。一つは漸進的な改革を重視する「グラデュアリズム」、もう一つは急激な改革を目指す「ラディカリズム(ショック療法)」です。グラデュアリズムは、市場メカニズムを徐々に導入し、私企業の創出を促進することで、資本主義への移行を有機的に進めようとするアプローチです。一方、ラディカリズムは、短期間で市場経済を導入し、国有企業の私有化などを一気に実行することで、迅速な体制転換を目指します。この章では、これらの異なるアプローチの特徴を詳細に検討し、それぞれのメリットとデメリットを分析します。
2. ラディカリズム バルツェロヴィチのポーランドにおける経験
ポーランドでは、1989年9月、マゾヴィエツキ政権発足と同時にバルツェロヴィチが副首相兼蔵相に就任し、ラディカルな体制移行戦略を主導しました。この戦略の背景には、過去の漸進的な経済改革の失敗と、社会心理学者フェスティンガーの理論に基づく、急激な環境変化への対応という二つの理由があります。バルツェロヴィチは、安定化、自由化、制度転換を同時に、かつ迅速に進めるべきだと考えました。これは、社会心理的な状況が体制移行に有利に働く期間は限られているという認識に基づいています。ラディカルな改革は、短期間で目に見える成果を上げ、国民の支持を得るための政治的な必要性も背景にありました。しかし、ラディカリズムは、国民生活への影響も大きく、社会的な混乱や抵抗を招くリスクも伴います。ポーランドのケースは、ラディカリズムの成功と限界を示す重要な事例となっています。
3. グラデュアリズム コルナイとハイエク的アプローチ
コルナイは、ハンガリーにおける体制移行を経験した経済学者であり、ハイエク的グラデュアリズムを支持しています。コルナイは、1990年代前半にいくつかのポスト社会主義国で実施されたラディカルな移行戦略は失敗したと主張します。彼は、サックスらによる「市場へのジャンプ」戦略の失敗を指摘し、その原因をショック・セラピストの社会工学的スタンスにあると分析します。ショック・セラピストは、資本主義的な経済制度や行動規範を、準備が整っていない社会に短期間で導入できると考えていたと指摘します。コルナイは、資本主義が自生的秩序であることを強調し、ポスト社会主義諸国ではグラデュアリズムが最適な戦略だと主張します。しかし、グラデュアリズムは、初期条件が異なる各国で一律に適用できるわけではありません。初期条件によっては、グラデュアリズムは体制移行を長期化させ、経済的混乱を招く可能性も秘めているのです。
4. ハイエク説への批判と体制移行戦略の現実性
近年のポスト社会主義諸国における体制移行論では、ハイエクの説が頻繁に引用されています。しかし、本書ではハイエク説の二つの点、すなわち資本主義を自発的秩序、社会主義を設計された秩序とする二分法、そしてハイエクが批判する設計主義について批判的に検討しています。著者は、資本主義自体が常に自発的に生成した秩序ではなく、特に20世紀以降は政府による介入が強い影響を与えていると指摘します。西ドイツにおける戦後の社会的市場経済の構築や、日本における戦後の経済民主化政策などを例に挙げ、政府による積極的な経済システムの設計と制度化が歴史的に存在したことを強調します。したがって、すべてのポスト社会主義諸国でグラデュアリズムが最適な戦略であるとは限らず、各国の具体的な状況に合わせて柔軟な戦略選択が必要であると結論づけています。
V. 私有化 戦略と今後の課題
本書は、既存の国有企業の私有化と新規私企業の創出という二つのアプローチを検討しています。私有化においては、政府主導による迅速な私有化が有効であると結論づけています。チェコスロバキアのパウチャー方式は、私有化の有効な手段として提示されています。しかし、経済改革は容易ではなく、企業経営の効率性向上、コーポレート・ガバナンスの確立、そして国民の支持獲得が今後の課題として示されています。また、市場社会主義の概念についても批判的に検討されています。 Analytical Marxismによる市場社会主義の提唱とその限界についても議論されています。
1. 私有化戦略 既存国有企業の私有化と新規私企業の創出
ポスト社会主義諸国における私有化政策は、既存の国有企業の私有化と、新規私企業の創出という二つの側面から構成されます。既存国有企業の私有化については、所有権の民間への移転が主要な課題となり、返還、売却、配分といった方法が用いられました。小規模資産の私有化は比較的スムーズに進みましたが、中規模、大規模企業の私有化は困難を極めました。特に、資本市場での株式売却を戦略とする場合、私有化の遅延と高額な社会的コストが課題となります。一方、新規私企業の創出は、市場経済の導入と市場参入の自由化によって促進されますが、基幹産業においては国有企業が依然として支配的な地位を占めているため、新規企業による国有企業の淘汰は容易ではありません。ポーランドでは、1992年半ば時点で約70万の私企業が登場しましたが、その多くは零細・小規模企業であり、基幹産業への浸透は限定的でした。
2. チェコスロバキアのパウチャー方式 国民への株式配分と第二市場の創設
チェコスロバキア政府は、パウチャー方式を採用しました。これは、国民に株式取得権利を付与するバウチャーを配布し、国民が自由に企業の株式を購入できる仕組みです。この方式は、国有企業の所有権を迅速に民間へ移転する上で有効であることが示されました。一人当たり1万ポイントのパウチャーが配布され、国民はそれを用いて国有企業の株式を取得することが可能となりました。さらに、株式のリセールを可能にする第二市場を創設し、投資会社の参入を促進することで、株式の分散化を防ぎ、私有化を促進する好循環を生み出しました。この結果、チェコスロバキアでは436もの投資会社が登場し、資本市場の急速な拡大につながりました。このパウチャー方式は、国民参加型の私有化モデルとして注目に値し、その成功と課題は、他のポスト社会主義諸国の私有化政策を考える上で貴重な示唆を与えます。
3. 私有化戦略の提言 政府主導と市民主導の組み合わせ
中欧諸国の私有化政策の実践を踏まえ、著者は、既存国有企業の私有化は政府主導で、新規私企業の創出は市民主導で行うという戦略が最適であると提案しています。既存国有企業の私有化については、チェコスロバキアのパウチャー方式のように、国民に株式を配分し、第二市場を整備することで、効率的な私有化を促進できると考えられます。しかし、大規模国有企業の私有化においては、企業の赤字体質を是正する必要があると共に、資本市場の発展と機関投資家の参入を促進することで、コーポレート・ガバナンスを強化し、企業の営利会社化を加速させる必要があります。一方、新規私企業の創出については、市場メカニズムの整備と市場参入の自由化が重要であり、市民による自主的な事業活動の促進を支援する政策が必要です。この政府主導と市民主導の両輪によるアプローチが、効率的な私有化と経済発展を実現するための鍵となります。
4. 市場社会主義論の限界と今後の課題
ローマー、バードハン、ワイスコフらが提唱する市場社会主義は、公有と市場の組み合わせを特徴とするもので、マルクス主義の立場からの新たな試みと言えるでしょう。しかし、著者は、公有が私有よりも効率的に優れていることを論証しない限り、市場社会主義は多くの支持を得られないと主張しています。公有には「万人のものは誰のものでもない」という逆説的な特性があり、所有意識の欠如が経営の放漫化、イノベーションの停滞につながる点を指摘しています。また、社会主義の実験は、効率的な企業経営には所有の人格化と責任の所在の明確化が不可欠であることを示しています。市場社会主義は、これらの要件を満たす現実的なモデルを示せていない限り、机上の空論にとどまるでしょう。今後の課題として、効率的な所有構造と調整メカニズムの確立、そして持続可能な経済システムの構築が挙げられます。
