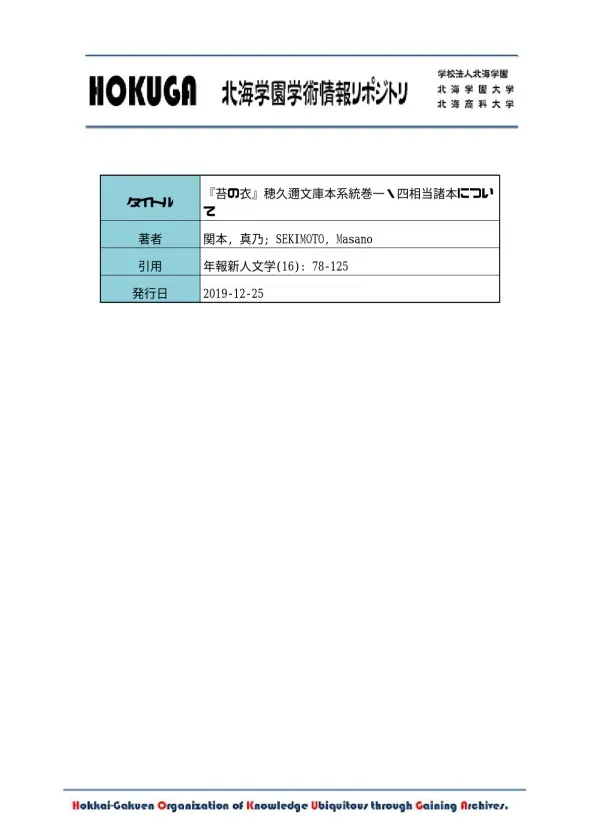
穂久邇文庫本系統『苔の衣』諸本研究
文書情報
| 学校 | 大学名(不明) |
| 専攻 | 国文学、古典文学など |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文、研究報告など |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 715.02 KB |
概要
I. 苔の衣 諸本の本文系統と優劣に関する研究
本稿は、中世王朝物語『苔の衣』の諸写本(写本)の本文系統(穂久邇文庫本系統、前田家本系統、伊達本など)を分析し、その優劣を検討した研究論文の要約です。複数の本文の比較を通じて、各系統の異同(誤脱、改変、潤色など)を明らかにし、特に穂久邇文庫本と前田家本の本文の相違点、春冬本の特徴、そして各写本の成立年代と本文の質の関連性について論じています。特に神宮文庫本と青山本は、他の写本と比べて本文の質が劣ると結論付けています。 本文比較の結果、系統間の優劣は一概に断定できないものの、穂久邇文庫本系統の本文が比較的優れている可能性を示唆しています。
1. 諸本の本文系統と特徴
この節では、『苔の衣』の様々な写本を、本文系統に基づいて分類・分析しています。特に、穂久邇文庫本系統と前田家本系統の二大系統に焦点を当て、それぞれの本文の特徴を比較検討しています。宮田京子らの研究を参照し、穂久邇文庫本系統は前田家本系統に比べて本文が節略されている傾向があるものの、一概に優劣を決められない点を指摘しています。また、伊達本についても言及し、意味の通る箇所が多い点からその優位性を示唆する記述が見られます。一方、穂久邇文庫本系統については、前田家本系統と比較して激しい異同があり、誤脱だけでなく意識的な改変や潤色も見られるとされています。これらの分析から、各系統の本文の特性と、それらがもたらす解釈上の違いが浮き彫りになっています。様々な写本間の細かな相違点の分析を通して、各系統の本文の成立過程や特徴が明らかになり、今後の研究に重要な知見を提供する内容となっています。
2. 各系統本文の優劣に関する議論
『苔の衣』の本文系統の優劣については、研究者間で意見が分かれている現状が示されています。 『鎌倉時代物語集成』の解題では、穂久邇文庫本系統が本文的に優れていると評価されていますが、一方で、前田家本系統の方が善本と評価されてきた歴史的背景も紹介されています。宮田京子は、精密な本文の比較検討がなされていない現状では、性急に優劣を論じるべきではないという慎重な姿勢を示しています。 本文系統の優劣判断には、写本の書写年代の古さとは必ずしも一致しない点に注意すべきであると指摘されており、本文の質と年代の関連性について、より詳細な検討が必要であることが示唆されています。これらの相反する意見や、慎重な見解を通して、本文系統の優劣判定の複雑さと、更なる研究の必要性が強調されています。
3. 神宮文庫本 青山本の本文の評価
神宮文庫本と青山本は、他の諸本と比較して本文の質が劣ると結論付けられています。 両写本は江戸中期成立の可能性が高く、他の写本より後に成立したと考えられます。本文の内容においても、他の写本と比較して誤りや脱落が多く、また、独自の改変も見られることから、本文の正確性や信頼性において劣ると評価されています。具体例として、「今はのおり」という箇所が、神宮文庫本では「今はのほり」、青山本では「今はのほか」と異なっており、本文の変容過程が示唆されています。これらの記述から、神宮文庫本と青山本は、他の優良な写本を写した際に誤りを犯したり、原文を正しく理解できなかったりした結果、本文が劣化した可能性が高いことが示唆されています。この分析は、写本の信頼性評価において、年代や系統だけでなく、本文の正確性を重視する必要があることを示しています。
4. 諸本間の関係性と本文の伝播
この節では、『苔の衣』の諸本間の関係性と、本文の伝播について考察しています。 特に、榊原本と内閣文庫本の関係が非常に緊密であることが指摘されています。両写本の異同が極めて少なく、改行位置や表記まで一致する箇所が多いことから、強い関連性があることが示唆されています。 また、島原松平文庫本との関係についても触れられており、榊原本と内閣文庫本が共通の祖本を写した可能性が示唆されています。さらに、春冬本の本文についても分析が行われ、穂久邇文庫本に近似するものの、独自の誤りを持つ系統が存在することが明らかになっています。これらの分析を通して、写本間の系統関係や本文の伝播経路について、より詳細な考察がなされる必要性が示されています。 各写本の本文の比較検討から、写本の成立過程や本文の伝播経路に関する新たな知見が得られています。
II. 苔の衣 絵巻と本文の関係
『苔の衣』の絵巻と本文の関係についても考察しています。絵巻の本文は、島原松平文庫本、榊原本、内閣文庫本と類似する部分が多い一方で、他の春冬本とは異なる独自性の高い異文も多数存在することが判明しました。絵巻の本文が、既存の本文系統とは異なる独自の系統に属する可能性も示唆されています。 絵巻の成立時期や制作に関わった絵師については、土佐派の絵師による可能性などが考察されています。
1. 絵巻の本文と他の写本との比較
この節では、『苔の衣』の絵巻本文と、他の写本本文との比較検討が行われています。絵巻本文は、島原松平文庫本、榊原本、内閣文庫本の本文と類似する傾向がある一方、他の春冬本とは異なる独自異文が約600箇所も存在することが指摘されています。このことから、絵巻本文が、それら他の春冬本とは異なる独自の系統に属する可能性が示唆されています。 絵巻本文と他の写本本文の比較を通して、本文の変遷や系統樹の構築に繋がる重要な情報が得られています。 特に、複数の写本を比較することで、それぞれの本文の正確性や信頼性の違い、また本文成立過程における改変や誤脱の可能性などが論じられています。これらの分析から、『苔の衣』の本文の多様性と複雑性が改めて浮き彫りになっています。
2. 絵巻の本文の特徴と成立過程に関する推測
絵巻本文の特徴として、島原松平文庫本、榊原本、内閣文庫本と類似する点が多いことが挙げられていますが、それらと異なる独自異文も多数存在することが強調されています。 このことから、絵巻本文は、それらの写本と共通の祖本をもつ可能性もあるものの、独自に改変・加筆された可能性も示唆されています。 また、絵巻それ自体が、特定の本文系統を基に制作されたものである可能性も考えられる一方で、巻一と巻四の内容を持つ春冬本が他に五本知られていることから、巻一と巻四の本文を有することが絵巻固有の特徴ではない可能性が示唆され、絵巻が基づいた本文自体が巻一と巻四のみのものであったという解釈も提示されています。これらの分析から、絵巻本文の成立過程や、本文と絵巻の関係性について様々な可能性が考察されています。
3. 絵巻の装丁と制作時期に関する考察
絵巻の装丁についても言及があり、金泥で草花が散らし書きされた豪華なもので、詞書は漢字まじりの平仮名書きで書かれており、土佐派の絵師による可能性が示唆されています。 全九巻すべて同じ仕立て方であること、絵巻を除く諸本すべて遊紙が前後一丁ずつであること、⑦から⑩は一面十行書きであることなど、共通の特徴が挙げられています。 これらの共通点から、絵巻を含む複数の写本が近世初期から中期にかけて、比較的短期間に集中して制作された可能性が推測されています。 特に、榊原本に榊原忠次の蔵書印、島原松平文庫本に松平忠房の蔵書印があることから、これらの写本が特定の蔵書家と関連している可能性が示唆されています。この考察は、絵巻の制作背景や、当時の文化状況を理解する上で重要な手がかりを与えています。
III.榊原忠次と 本朝通鑑 編纂における 苔の衣
榊原忠次(榊原本に蔵書印あり)と林羅山らとの交流、および『本朝通鑑』編纂における榊原忠次の役割に焦点を当てています。忠次は多くの和書を所有しており、その中には『苔の衣』も含まれていた可能性が高いと推測されています。『国史館日録』などの史料に基づき、忠次と林羅山、松平忠房との親交、そして彼らが和書(歌書、説話など)の貸借を通して、学問交流をしていた様子が記述されています。特に、忠次が鵞峰(林羅山)に和書を貸与していた可能性、その中に『苔の衣』が含まれていた可能性についても言及されています。松平忠房との関係も深かったことが、蔵書印や史料から明らかになっています。
1. 榊原忠次と林羅山 鵞峰との関係
この節では、榊原忠次と林羅山、鵞峰(林家の関係者)との親密な関係が、『国史館日録』(以下『日録』)などの史料に基づいて詳細に記述されています。 『日録』の記述から、両者の交流は寛永十四年頃から始まり、寛文五年(1665年)時点で28年に及ぶ深い交友関係にあったことが明らかになります。 漢詩や和歌の贈答、書物の貸借など、具体的な交流の様子が示されており、鵞峰が忠次の死後に碑文を作成したという事実からも、その親密さがうかがえます。 また、不忍池文芸圏あるいは上野・神田文芸圏と呼ばれるような文芸サークルが存在し、林家がその中心にあったという記述もあり、忠次もその一員として重要な役割を果たしていた可能性が示唆されています。これらの記述から、忠次が所属していた文芸ネットワークとその活動状況が詳細に描かれています。
2. 本朝通鑑 編纂への協力と和書の貸借
『本朝通鑑』の編纂において、榊原忠次が林羅山(鵞峰)に多大な協力をしていた様子が、『日録』の記述から明らかになっています。忠次は膨大な和書を所有しており、それらを鵞峰に貸与していたと考えられます。 『日録』には、忠次が『千載佳句』『足利李世記』などの書物を鵞峰に貸し出していた記録が残されています。 また、『菟玖波集』の貸借記録からは、迅速な書写と返却が行われていたことがわかります。 これらの事例から、忠次は『本朝通鑑』の編纂にあたり、自らの蔵書を惜しみなく提供し、積極的に協力していたことが分かります。 特に、忠次の死後も鵞峰は彼を深く悼んでおり、その深い友情と協力関係が強調されています。この節では、史料に基づいた具体的な事例を通して、忠次の『本朝通鑑』編纂への貢献が明示されています。
3. 榊原忠次の蔵書と 苔の衣 の所在可能性
この節では、榊原忠次の膨大な蔵書の中に『苔の衣』が含まれていた可能性が示唆されています。 『日録』には、忠次が多数の和書を鵞峰に提供した記録があり、その中には歌書や説話といったまとまった量の和書が含まれていました。 特に、榊原本と内閣文庫本の関係が非常に緊密であること、改行位置や表記までが一致することから、『苔の衣』も忠次から鵞峰に貸し出された可能性が推測されています。 忠次が亡くなった後も、その蔵書の一部は鵞峰に寄贈され、その中には『苔の衣』が含まれていた可能性も否定できません。 これらのことから、当時の文人たちの書物への関心の高さと、蔵書家同士のネットワークを通して書物が流通していた様子が伺えます。 この分析では、『苔の衣』という特定の書物が、当時の文人社会における知識・情報の共有において、重要な役割を果たしていた可能性が示唆されています。
4. 松平忠房との関係と蔵書の一致
この節では、榊原忠次と松平忠房の親密な関係と、両者の蔵書内容の類似性について述べられています。 『日録』の記述や、忠次の家集『一掬集』などの資料から、両者の深い親交が確認できます。 忠次と忠房の蔵書に共通する私撰集・私家集が多いことから、両者間の頻繁な書物の貸借や書写が示唆されます。 『苔の衣』は、系譜が詳述されるなど『栄花物語』に似た特徴を持つことから資料として収集された可能性があり、忠次・忠房両者、そして鵞峰が所有していた可能性が示唆されています。 しかし、作り物語など、両者の蔵書に違いも見られ、個人の好みや関心が反映されている部分もあると考察されています。 これらの分析から、当時の文人たちの蔵書とそのネットワーク、そして『苔の衣』の位置づけが、より明確になります。
IV.榊原忠次と松平忠房の蔵書と 苔の衣
榊原忠次と松平忠房の蔵書を比較検討し、両者の親密な関係と、和書(特に私家集)の頻繁な貸借・書写が、両者の蔵書内容の類似に大きく影響していることを示しています。 『御書物虫曝帳』、『肥前島原松平文庫目録』などの文献を用いて、両者の蔵書に含まれる私撰集、私家集、作り物語などの重複率が高かったこと、それが緊密な交流と和書の貸借によることを示唆しています。そして、忠次と忠房の蔵書に『苔の衣』が存在した可能性、それが鵞峰にも伝わっていた可能性も示唆されています。
1. 榊原忠次と松平忠房の親交と蔵書の関係
この節では、榊原忠次と松平忠房の親密な関係と、その関係性が両者の蔵書内容に及ぼした影響について考察しています。『日録』寛文四年十月二十八日条の記述「忠房嗜倭書与姫路拾遺交義殊厚」や、忠次の家集『一掬集』、『福知山藩日記』などからも、両者の親密な交友関係が伺えます。 特に、忠次と忠房の蔵書印のある私家集を比較することで、両者の蔵書内容に高い一致率が見られることが示されています。『肥前島原松平文庫目録』によると、忠房の蔵書印「尚舎源忠房文庫」のある私家集は104部にも及び、その多くが榊原本私家集と一致するなど、両者の蔵書が密接な関係にあることが示唆されています。 この高い一致率は、両者が歌道を嗜み、蒐書に強い関心を持ち、頻繁な貸借や書写を行っていたことを示唆する重要な証拠となります。 これらの分析から、当時の文人たちの蔵書とそのネットワーク、そして書物の流通状況について、貴重な知見が得られています。
2. 御書物虫曝帳 と 肥前島原松平文庫目録 による分析
榊原忠次の後代、政邦の代に成立した『御書物虫曝帳』と『肥前島原松平文庫目録』の記述から、榊原家と松平家の蔵書内容を詳細に比較検討しています。『御書物虫曝帳』には書名、冊数が記され、版本・写本が区別されている一方、『肥前島原松平文庫目録』では書型、編著者、出刊書写年次が精査され分類されています。 両目録を比較した結果、私撰集では22点、私家集では67点が一致し、それぞれ57%、64%の高い一致率を示しています。この高い一致率は、忠次と忠房が歌道を好み、蒐書に強い関心を持ち、親しい交友関係にあったことから、互いに頻繁な貸借と書写を行っていたことを裏付ける証拠として示されています。 これらの目録データの分析を通して、両者の蔵書内容の類似性とその背景にある人的ネットワークの重要性が浮き彫りになっています。 特に、私家集という特定の種類の書物に注目することで、当時の文人たちの交流や文化的背景をより詳細に解明する試みが見られます。
3. 苔の衣 を含む蔵書内容の比較と解釈
前述の分析に基づき、榊原忠次と松平忠房の蔵書内容、特に私撰集・私家集の一致率の高さと、両者の親交の深さから、両者間での書物の貸借や書写が頻繁に行われていた可能性が改めて強調されています。 そして、その蔵書の中に『苔の衣』が含まれていた可能性が示唆されます。 忠次と忠房の蔵書内容の一致率は私撰集・私家集においては高い一方、作り物語などには違いも見られ、個人の嗜好も反映されていると指摘されています。 『苔の衣』が、系譜が詳述されるなど『栄花物語』に似た特徴を持つことから資料として収集された可能性、あるいは歴史物語としての面白さから読まれた可能性も示唆されています。 これらの分析を通して、『苔の衣』という作品が、当時の文人社会においてどのように認識され、どのように扱われていたのかについて、新たな視点が提供されています。
