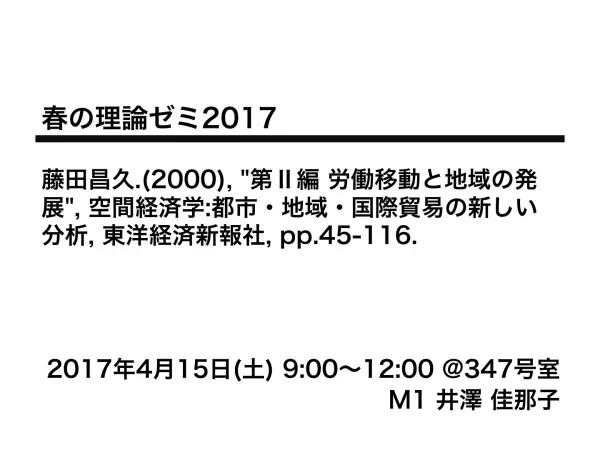
空間経済学:労働移動と地域発展
文書情報
| 著者 | 藤田昌久 |
| 専攻 | 空間経済学 |
| 会社 | 東洋経済新報社 |
| 文書タイプ | 書籍の章 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.25 MB |
概要
I.独占的競争と空間経済地理学 規模の経済と地域発展
本論文は、空間経済地理学の枠組み、特にクルーグマンらによる「新しい空間経済地理学」の視点を用いて、労働移動と地域発展の関係を分析しています。特に、Dixit-Stiglitzモデルを拡張した空間経済モデルを用いて、規模の経済、輸送費用、財の多様性が地域間の産業集積や賃金格差に及ぼす影響を考察しています。独占的競争市場における企業の立地選択、実質賃金、そして地域間格差のメカニズムが中心的なテーマです。東日本大震災によるサプライチェーン寸断問題も事例として挙げられています。
1. 新しい空間経済地理学とDixit Stiglitzモデルの導入
このセクションでは、1990年代以降にクルーグマンらによって発展した「新しい空間経済地理学」の概念が紹介されています。この理論は、製造業における個々の企業レベルでの規模の経済を重視し、空間的な均衡状態を分析するための枠組みを提供します。特に、製品の差別化と代替性を考慮した独占的競争モデル、具体的にはDixit-Stiglitzモデルが、空間経済分析の中核として用いられています。 東日本大震災によるサプライチェーン寸断問題が、このモデルの適用性を示唆する現実的な背景として提示されています。 自動車産業など、特定の産業における規模の経済と地域経済への影響が、分析の出発点となっています。 モデルでは、工業品消費の合成指数M、農業品消費の合成指数A、工業品支出割合μといった変数が定義され、消費者の効用最大化問題が定式化されます。 この定式化を通して、提供される工業品の範囲が内生変数となり、Dixit-Stiglitzモデルを用いることで財の種類数nがモデル内で決定される変数となることが強調されています。 このモデルの利点は、財の種類数nの変化が消費者に与える効果を分析できる点にあります。例えば、nの増加は価格指数Gを低下させ、各財の需要関数を下方にシフトさせる効果があると示唆されています。この効果の大きさは、財の種類間の代替弾力性σに依存し、σが小さい(財の差別化度合いが大きい)ほど、価格指数Gの低下は大きくなると説明されています。
2. 複数の立地点と輸送費用 空間的均衡の分析
このセクションでは、経済が離散的な有限個の立地点から構成されるという仮定の下、空間経済モデルが拡張されます。 それぞれの立地点では、特定の種類の財が生産され、すべての財は同一の生産技術と価格を持つと仮定される対称性が設定されています。 立地点間での財の輸送には費用がかかり、「氷塊輸送」というモデルが導入されています。これは、輸送距離に応じて一定の割合で製品が「融ける」という仮定です。 立地点rで生産される財の種類数nr、工場渡し価格pMr、消費地点sにおける送達価格pMrs、および輸送量TMrsといった変数が導入され、各立地点における工業品の価格指数Gsが式によって表現されます。 生産者の行動は利潤最大化に基づいて分析され、所与の賃金率wMrの下で、企業は生産量q*を決定します。 この均衡状態において、企業の生産量は式で表され、市場規模は限界費用を上回るマークアップや生産規模に影響を与えないことが示されています。 実質賃金は、名目賃金と工業品価格指数によって決定され、地域間の賃金格差が空間経済における重要な要素として取り上げられています。 分析の簡略化のため、適切な測定単位を選択することで、限界労働費用cMrを基準化し、労働者数と賃金に関する分析を容易にしています。
3. 核 周辺モデルによる地域間格差の分析
このセクションでは、地域間の産業集積と賃金格差のメカニズムを解明するために、核・周辺モデルが用いられています。 まず、相対的な需要が工業の立地に与える影響が分析され、工場への労働供給が完全に弾力的な場合、工業品需要の変化が雇用量に与える影響が検討されています。 次に、企業の集積と消費者の集積、そして財のバラエティ増加による需要と労働力の増大といった現象が議論されています。 この過程で、工業規模の拡大と所得の上昇傾向に上限を設定する仮定(Z=1)が導入されています。 農業品価格を一定と仮定し、実質賃金の変化と工業シェアの関係が分析されます。 経済全体での農業労働者LAが存在し、各地域にはその一定割合が賦与されているという仮定の下、工業労働力は時間経過とともに移動可能であると仮定されています。 地域rの工業労働シェアをλrとして、地域間の賃金格差と工業シェアの関係を図表を用いて示し、工業が一方の地域に集中する核・周辺パターンの発生メカニズムを説明しています。 この集中パターンは、輸送費用が十分に高い場合に、工業が地域間に均等に配分される安定均衡がただ一つ存在するという点と対比的に提示されています。 核・周辺パターンの持続可能性についても検討され、輸送費用と実質賃金格差の関係が詳細に分析されています。
II.多様な財と消費者の選択行動
消費者は、多様な工業製品と農業製品から、効用最大化を目指して消費量を決定します。工業製品は差別化されており、その消費量は合成指数Mで表されます。このモデルでは、提供される工業製品の種類数nが内生的に決定される点が重要です。nの増加は価格指数Gを低下させる可能性があり、消費者の余剰に影響を与えます。代替弾力性σは、財の差別化度合いと価格指数への影響に大きく関わります。
1. 消費者の効用最大化問題と予算制約
このセクションでは、消費者の選択行動が中心的に扱われています。消費者は、農業品と多様な工業品からなる財の束を消費します。消費者の問題は、所与の所得Y、農業品価格pA、そして各工業品価格piの下で、効用関数を最大化することです。ここで重要なのは、工業品は差別化されており、その消費量は合成指数Mによって表現される点です。この合成指数Mは、財どうしの差別化が連続的に変化する財空間で定義される部分効用関数として仮定されています。消費者はまず、Mを達成する費用を最小にするように各財の消費量miを選択し、次に総予算を農業品と工業品全体に配分します。効用関数は、MとAの組合わせで表現され、工業品への支出割合μが効用関数に含まれています。(4.1)式で示される効用関数は、消費者の選好と予算制約を統合したモデルの中心となります。このモデルでは、Dixit-Stiglitzモデルの適用により、提供される工業品の範囲が内生変数となり、財の種類数nが体系内で決定される変数となります。このことは、従来の空間経済モデルとは異なり、財の種類数が外生的に与えられるのではなく、モデル内部で決定されることを意味しており、分析の複雑さと同時に、より現実的なモデル化に繋がる重要なポイントです。
2. 財の種類数と価格指数 代替弾力性の影響
このセクションでは、財の種類数nの変化が消費者に与える影響が分析されています。 特に、価格指数Gと代替弾力性σの関係が重要視されています。 価格指数Gは、消費者が支払う平均的な工業品価格を表しており、財の種類数nと代替弾力性σの関数として表現されます。 具体的には、価格指数Gは財の種類数nの減少関数であり、nが増加するとGは減少することが示唆されています。これは、多様な製品が提供されることで、消費者はより好みに合った製品を選択できるようになり、平均的な価格が低下することを意味します。 さらに、この価格指数Gのnへの感応度は、異なる種類間の代替の弾力性σに依存します。σが小さい(財の差別化度合いが大きい)ほど、価格指数Gはnの変化に対してより敏感に反応し、大きく低下します。 これは、製品間の差別化が大きいほど、製品の種類数の増加が価格に与える影響が大きくなることを示しています。 全ての工業品が同一価格で購入できると仮定した場合の価格指数Gの式(4.13)も示され、モデルの簡略化と分析の容易化のための仮定が提示されています。 これらの分析を通じて、財の多様性と消費者の効用、そして価格指数間の複雑な関係が明らかにされています。
III.複数の立地点と輸送費用 空間的均衡
モデルは複数の立地点を仮定し、輸送費用が地域間の産業分布に影響を与えることを示しています。各立地点で生産される財の種類数、工場渡し価格、輸送費用などを考慮することで、空間的均衡における産業配置と賃金が決定されます。氷塊輸送という仮定に基づき、距離に応じた費用を計算しています。生産者は利潤最大化を目指し、消費者は効用最大化を目指します。これらの相互作用が、空間経済における均衡状態を形成します。
1. 空間経済モデルの基本仮定と輸送費用
このセクションでは、空間経済モデルにおける基本的な仮定が提示されています。まず、経済は離散的な有限個の立地点(R:立地点数)から構成されると仮定されます。 各立地点では、特定の種類の財が生産され、すべての財は同一の生産技術と価格を持つという対称的な状況が想定されています。 重要な点は、農業品と工業品は立地点間を費用をかけて輸送できるという点です。この輸送費用は、「氷塊輸送」というモデルを用いて表現されます。氷塊輸送とは、輸送距離に応じて一定の割合で製品が「融ける」という仮定で、輸送費用が距離とともに増加することを示しています。 この仮定の下で、立地点rで生産される財の種類数nr、立地点rで生産される財の工場渡し価格pMr、立地点rで生産される財の消費地点sにおける送達価格pMrs、そして到着する工業品1単位あたりに必要な発送数量TMrsといった変数が定義されます。 これらの変数は、後続の分析において、空間的な均衡状態を決定する重要な要素として機能します。立地点sの工業品の価格指数Gsは、これらの変数を用いた式(4.7)によって表現され、輸送費用が価格指数にどのように影響するかを明確に示しています。
2. 生産者行動 利潤最大化と均衡状態
このセクションでは、生産者の行動が利潤最大化に基づいて分析されています。 所与の賃金率wMrに直面する立地点rにおける企業は、ある特定の種類の財を生産します。企業は利潤を最大化する生産量を決定し、その均衡状態での生産量q*は式(4.22)で表されます。 この式は、固定インプットF、代替弾力性σ、限界労働費用cMrを用いて表現されています。 また、工業品の価格は、限界労働費用、賃金率、そして代替弾力性を用いた式(4.20)で表されます。 重要な点として、市場規模は限界費用を上回るマークアップや個々の財が生産される生産規模に影響しないことが示されています。 このことは、空間的均衡における企業の規模決定に、市場規模が直接的な影響を与えないことを示唆しています。 さらに、均衡状態での価格(pMr)と代替弾力性(σ)、そして定数μの関係式も提示され、空間的均衡における価格決定メカニズムが明確に示されています。 これらの分析を通じて、生産者の行動と空間的均衡の関係が明らかにされます。
3. 実質賃金と空間的均衡 基準化と簡略化
このセクションでは、実質賃金と空間的均衡の関係、そして分析の簡略化のための基準化について説明されています。 実質所得は、生計費指数によって調整された名目所得に比例すると仮定されます。 そのため、立地点rにおける工業労働者の実質賃金は、名目賃金と工業品価格指数を用いて計算されます。 分析の簡略化のため、適当な測定単位を選択することで、限界労働費用cMrを基準化します。これにより、賃金方程式と工業品価格指数の関係がより明確に分析できるようになります。 また、企業数(0, n)に関しても単位を選び、固定インプットFを基準化することで、モデルの取り扱いを容易にしています。 これらの基準化は、複雑な空間経済モデルの分析を簡略化し、主要な経済変数の関係をより明確に理解するための重要なステップとなります。 特に、労働者数と賃金に着目するための基準化は、後続の地域間賃金格差の分析に大きく貢献します。
IV.実質賃金 工業集積 地域間均衡
実質賃金は、工業品価格指数によって調整されます。工業集積は、規模の経済と輸送費用のバランスによって決定されます。モデルでは、地域間の実質賃金格差と工業の地域間分布の関係を分析し、核一周辺モデルを用いて、工業が特定の地域に集中するパターン(核・周辺パターン)の発生メカニズムを解明しています。輸送費用の高低が、均衡状態の安定性、特に工業集積のパターンに大きく影響することが示されています。 労働者の移動は実質賃金の高い地域への移動を促し、地域間均衡への調整過程を形成します。
1. 実質賃金と工業分布の均衡 多地域モデル
このセクションでは、実質賃金と工業分布の空間的均衡関係が、多地域モデルの文脈で分析されています。 実質賃金は、名目賃金と工業品価格指数によって決定され、地域間の賃金格差が、労働者の地域間移動を誘発する重要な要因となります。 モデルでは、労働者は平均以上の実質賃金を提供する地域へ移動し、平均以下の地域からは移動するという仮定が置かれています。 この仮定に基づき、実質賃金と工業分布の均衡関係が検討され、4R個の解が存在すると仮定して分析が進められます。 この多地域モデルは、地域間の相互作用をより詳細に捉えることを目指しており、単一の地域に焦点を当てたモデルよりも複雑な均衡状態を想定しています。 しかし、4R個の解を直接分析するのは困難なため、簡略化されたモデルを用いた分析が必要となります。 その簡略化されたモデルとして、後に2地域モデル(核・周辺モデル)を用いた分析が展開されます。
2. 核 周辺モデル 工業集積と地域間格差
2地域モデル(核・周辺モデル)を用いて、工業集積と地域間格差の関係が分析されています。 2地域間の工業部門の実質賃金の差と地域1の工業シェアの関係がグラフで示され、工業シェアが極端に高い、もしくは低い初期値から出発すると、全ての工業が一方の地域に集中する核・周辺パターンに収束することが示されています。 これは、いずれかの地域における工業シェアが2/1を超えると、その地域がさらに魅力的になり、工業集積が加速していくことを意味します。 一方、ある地域が過半数の工業労働力を有する場合、その地域は労働者にとって他の地域よりも魅力が薄れ、集積はそこにとどまると示唆されています。 この核・周辺パターンの形成は、規模の経済と輸送費用のバランス、そして労働者の移動によって生み出される現象として捉えられています。 輸送費用が十分に高い場合、工業が地域間に均等に配分される安定均衡がただ一つ存在するという点も示されています。 この均衡状態は、輸送費用が低い場合の核・周辺パターンとは対照的な結果となっています。
3. 核 周辺パターンの安定性と持続可能性
このセクションでは、核・周辺パターンの安定性と持続可能性が検討されています。 工業が一方の地域(地域1)に集中している場合、それが安定均衡であるかどうかが分析されます。 この分析では、地域1から地域2へ労働者が移動する際に、地域1に残る労働者よりも高い実質賃金を得ることができるかどうかが重要なポイントになります。 この検討を通じて、地域間の工業集積が、労働者の移動と実質賃金格差によってどのように維持されるか、あるいは崩壊するかが分析されます。 非常に小さな輸送費用や、代替弾力性σと他のパラメーターの関係性(σ = ρ > μ)が、安定性条件に影響を与える要因として示唆されています。 最終的には、2地域モデルでの分析結果を踏まえ、より一般化された多地域モデルへの拡張が示唆されます。 この拡張を通じて、集積の経済が、規模の経済、輸送費用、要素移動の相互作用によってどのように生まれるのかをより深く理解することが期待されています。
V.農業部門との相互作用と都市発展
モデルは、農業部門と工業部門の相互作用を考慮することで、より現実的な空間経済モデルを構築しています。農業部門は完全競争市場を想定し、農業品価格と工業品価格の相対的な関係が地域発展に影響を与えます。特に、農業品の輸送費用が都市の発展に対して抑制効果を持つことを示唆しています。この部分では、地域間の農業労働力分布、農業賃金なども考慮されます。
1. 二部門モデルの導入と基本的な仮定
このセクションでは、工業部門(独占的競争)と農業部門(完全競争)の二部門モデルが導入されます。 資源は労働者のみであり、工業部門と農業部門はそれぞれ労働者を雇用します。 工業労働者の名目賃金をwr、実質賃金をωrと定義し、労働者の地域間移動が地域経済に与える影響を分析する枠組みが提示されています。 労働者の移動は、実質賃金に基づいて決定されると仮定され、労働者は平均以上の実質賃金を提供する地域へ移動し、平均以下の地域からは移動するというシンプルな仮定が置かれています。この仮定は、労働者の合理的な行動に基づいており、モデルの簡略化に寄与しています。 この二部門モデルは、工業集積と農業部門の相互作用を考慮することで、より現実的な地域経済モデルを構築することを目指しています。農業部門は完全競争市場を想定しており、農業品価格が一定であるという仮定も、分析を容易にするために導入されています。 これらの仮定の下で、農業部門と工業部門の相互作用が、地域経済の空間構造にどのように影響するかを分析していきます。
2. 農業品輸送費用と都市発展のブレーキ効果
このセクションでは、農業品の輸送費用が都市の発展に与える影響が分析されています。 これまでのモデルでは、農業品の輸送費用は考慮されていませんでしたが、このセクションでは、その費用を考慮することで、より現実的なモデルを構築しようとしています。 具体的には、地域rの農業賃金をw^T_rとして、農業賃金は農業品価格に等しいものの、農業品に輸送費用がかかるため、地域間で均等化されない点を指摘しています。 農業品の供給が所与であるという仮定の下、核・周辺モデルにおける工業集積と地域間賃金格差の分析が、農業品輸送費用を考慮した上で再検討されています。 特に、工業が特定の地域に集中している場合(λ=1)、その状態が安定均衡であるかどうかを、農業品輸送費用を含めて検証することで、都市の発展にブレーキをかける効果が示されています。 地域1が農業品を移入しなければならない状況を例として、地域2の労働を価値尺度として、農業品輸送費用が都市の発展に与える制約要因として機能することを示唆しています。
