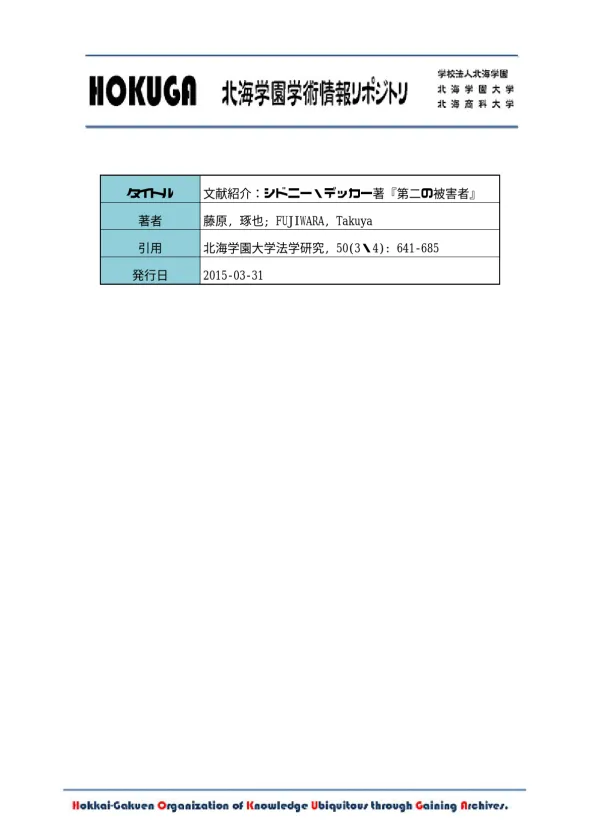
第二の被害者:医療事故と心のケア
文書情報
| 著者 | Sydney Decker |
| 学校 | Griffith University |
| 専攻 | 心理学 (Psychology) |
| 文書タイプ | 文献紹介 (Book Review) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.07 MB |
概要
I.セカンドビクティムのトラウマと責任追及の問題点
本論文は、医療事故や航空事故におけるセカンドビクティム(事故に間接的に巻き込まれた者、例えば医療過誤に関わった医療従事者)が、過剰な責任追及によって深刻なトラウマを負う問題点を指摘しています。事故調査における公正性と、セカンドビクティムへの配慮の欠如が、組織学習を阻害し、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の発症リスクを高めることを示唆しています。特に、事故後の情報公開や情報共有の遅延、周囲からの非難、そして自己批判が、セカンドビクティムの心理的苦痛を増幅させる要因として挙げられています。 医療過誤や航空事故といった分野におけるセカンドビクティムへの支援体制の構築が喫緊の課題として提示されています。
1. セカンドビクティムへの過剰な責任追及
本論文は、事故を起こした者に対する過度の責任追及が、組織学習の阻害を始めとする様々な問題を引き起こすことを指摘しています。特に、日本の航空事故や医療事故における過失犯処罰に関する議論において、新たなアプローチとして重要な知見を提供しています。 具体的には、医療機関に落ち度がないと認められた事例や、研修医が医療過誤と説明責任に関わっているかについての3年間の研究結果が提示されています。これらの事例を通して、セカンドビクティムが、自己批判と他人からの非難の間で苦悩し、重大な罪悪感や後悔の念を抱えている実態が浮き彫りになっています。 過剰な責任追及は、セカンドビクティムの心理的負担を大きく増加させ、ひいては組織全体の安全文化の醸成を阻害する大きな要因となっていると結論づけられます。
2. セカンドビクティムの心理的影響とトラウマ
セカンドビクティムは、罪悪感や後悔の感情だけでなく、フラッシュバック、回避行動、自信喪失といったPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状を示すことが指摘されています。 これらの症状は、事故への責任を感じていることの表れであり、トラウマ経験を示す重要な指標です。さらに、他人の被害を防ぐためにできることをしなかったという罪悪感が生じることも問題視されています。 このようなトラウマ体験は、自己や生存への脅迫的な認識につながり、自己の価値観に関する混乱や、事故における自身の役割に関する否定的な感情を引き起こします。 結果として、人生の意味の再構築や、後悔の感情への適切な対処が困難となり、医学的介入が必要となる可能性も示唆されています。
3. 事故調査におけるセカンドビクティムへの配慮不足
事故調査において、セカンドビクティムが周囲の人々との議論を明確に禁止される事例が挙げられています。これは、PTSDの形成および予防という観点から推奨されない対応です。 調査の過程で、セカンドビクティムが失業や名声の損失といった結果を実際に引き起こす恐れがあり、その不名誉による不安が生じていることが懸念されています。 また、事故調査が完了する前に、セカンドビクティムにとって重大で取り返しのつかない結果を伴う行動が取られるべきではないと強調されています。 調査を行う者には、事故発生当時の状況を自由に利用する権利が与えられていますが、その一方で、調査に偏見を持たせることは容易であるため、セカンドビクティムへの配慮が欠けている点が問題視されています。
4. 組織学習と安全文化における課題
報告された事例から広く学ぶことを周知することが重要であり、その検討には事件関係者である専門家も参加すべきです。しかし、事故は次第に意味のない、物理的に場所と時間が偶然一致したものへと置き換えられ、関係専門家への刑事責任追及が広まることはありませんでした。 40年間で事故に関する社会的な解釈が変わっていることを踏まえ、関係者へ事故に関する第二の詳細な筋書きを描く能力を示すことは、組織学習と改善の援助に対する根本的な前提条件と考えられます。 公平な法執行がほとんどない現状では、第一の被害者と第二の被害者を生み出す過誤の処罰をなくすことができないという問題が提起されています。 通常の業務中に起こった過誤を犯罪とすることについては、その公平性と予測不可能性に疑問が呈されています。
II.セカンドビクティムの症状と心理的影響
セカンドビクティムは、過剰な罪悪感、後悔、フラッシュバック、回避行動、自信喪失といった症状を経験します。これらの症状は、事故の責任を感じていることの表れであり、トラウマの深刻さを示しています。 他者の被害を防ぐことができなっかったという罪悪感(第二の被害者特有の罪悪感)も大きな問題です。 自己の価値観の混乱や、事故における自身の役割への否定的な感情も伴います。これらのトラウマからの回復には、人生の意味の再構築、自己許容、そして専門的な医療介入が必要不可欠です。
1. 罪悪感 後悔 および関連症状
セカンドビクティムは、事故への関与に対する強い罪悪感や後悔の念を経験します。これは、日常的なレベルから極めて強いものまで様々です。 さらに、フラッシュバック、回避行動、自信喪失といった症状も、責任を感じていることの表れとして現れます。これらの症状は、事故に関わったことによる心理的な苦痛を反映しており、トラウマの深刻さを示唆しています。 特に、他人の被害を防ぐためにできることをしなかったという罪悪感は、セカンドビクティム特有の苦悩であり、専門的なサポートが必要となる重要なポイントです。
2. トラウマ体験と自己認識への影響
事故に関する情報やトラウマ体験は、セカンドビクティムにとって自己や生存への脅迫的なものとして受け止められる可能性があります。 これにより、自己の価値観に関する混乱が生じ、事故における自身の役割に関する否定的な感情が強まります。 混乱した前提を調和させる必要があり、出来事と自身の役割に関する否定的な感情の適切な処理が求められます。 人生の意味の再構築や、後悔という感情への対処が困難となるため、専門的な医学的介入が必要となるケースも多いと予想されます。
3. 自己許容と回復への道のり
セカンドビクティムは、自身の行動を許容し、心の平静を取り戻す必要があるかもしれません。 後悔という感情は、通常の社会関係における正当なものではなく、医学的介入が必要な状態であるという認識を徐々に植え付けることが重要です。 個人的な自律性とコントロールは、安全の基礎として考えられており、セカンドビクティムが自身の行動を客観的に評価し、自己を許容するプロセスは回復への重要なステップとなります。 所属する業界や社会における自律心と個性を現実として受け止め、自己肯定感を回復させることが、トラウマからの回復に繋がる可能性を示唆しています。
III.事故調査における課題と改善策
事故調査においては、セカンドビクティムへの配慮が欠けている点が問題視されています。調査過程での情報開示の遅延や、セカンドビクティムへの過剰な責任追及は、二次的な被害を招きます。 セカンドビクティムの証言を制限するなど、調査方法そのものが、PTSDの発生や回復を阻害する可能性があります。 迅速かつ技術的な調査基盤の構築、利害関係者の影響排除、そして公正な手続きが求められます。 セカンドビクティムへの重大な結果を伴う行動は、事故調査完了前に取られるべきではありません。調査は、第一の被害者と第二の被害者の両方の視点を取り入れ、原因の複雑さを解明する必要があるとされています。
1. セカンドビクティムへの配慮の欠如と二次被害
事故調査においては、セカンドビクティムへの配慮が不足している点が大きな課題です。 例えば、セカンドビクティムが周囲の人々と事故について議論することを明確に禁止されるケースがあり、これはPTSDの形成や予防の観点から適切な対応とは言えません。 また、調査過程においてセカンドビクティムが失業や名誉毀損といった重大な結果を被る可能性があり、調査中であっても不名誉による不安が生じているという問題も指摘されています。 これらの二次被害を防止するためには、事故調査における手続きの見直しと、セカンドビクティムへの適切なサポート体制の構築が不可欠です。
2. 事故調査プロセスの改善
事故調査においては、迅速かつ技術的な基盤を整備し、利害関係者の影響を明確に排除するための抑制と均衡を図ることが重要です。 セカンドビクティムにとって重大で取り返しのつかない結果を伴う行動は、事故調査が完了する前に取られるべきではありません。 調査は、第一の被害者と第二の被害者の両方の視点を取り入れ、事故の結果に対する原因の複雑さを調査することで、セカンドビクティムの役割を理解する必要があります。 技術的に調査を行い、客観的な分析に基づいて結論を出すことで、公平性を担保する必要があります。
3. 情報公開と透明性の確保
報告された事象から広く学ぶためには、関係者への事故に関する詳細な情報提供が不可欠です。 事件に関係した専門家が参加する検討を行い、その結果を周知することで、組織学習と改善を促進することができます。しかし、過去には関係専門家への刑事責任追及が組織学習を阻害した事例もあり、その点への配慮が必要です。 関係者への事故に関する第二の詳細な筋書きを描く能力を示すことは、組織学習と改善の援助に対する根本的な前提条件と考えられます。 情報開示と情報共有を一時的に延期することは、セカンドビクティムが弁護士以外に事故のことを有効に話すことを不可能にする可能性があり、注意が必要です。
4. 公平性とバランスの取れた事故調査
事故調査においては、公平性が確保され、第一の被害者と第二の被害者を生み出す過誤の処罰をなくすことが理想です。しかし、通常の業務中に生じた過誤を犯罪とすることの公平性と予測不可能性には疑問が呈されています。 事故調査における偏見を排除し、客観的な事実解明に努めることが重要です。 セカンドビクティムへの配慮がないまま、事象の再体験を悪化させる可能性のある公式報告書の公開は避け、継続的な管理段階において重要な機会を提供する必要があります。 組織は、セカンドビクティムだけでなく、第一の被害者と組織自身をも不公平に扱うこと、そして組織にとって最も信頼できる安全に関する重要な情報を切り捨てることに等しい行動を避けるべきです。
IV.組織学習と安全文化の醸成
事故から広く学ぶためには、関係者への詳細な情報提供が不可欠です。 専門家の参加を得た客観的な事故分析と、その結果の共有が、組織学習と改善に繋がります。 しかし、過去の事故においては、専門家に対する刑事責任追及が組織学習を阻害した事例も存在します。 公正な情報公開と、安全文化の醸成が、セカンドビクティムを含む全ての関係者にとって重要です。 組織は、セカンドビクティムを公平に扱い、信頼できる安全情報を共有する必要があります。 安全文化の構築、説明責任の明確化、そして継続的な改善のための努力が求められます。
1. 事故調査からの組織学習の促進
報告された事象から広く学び、その知見を組織全体に周知させることが、組織学習の促進に不可欠です。 事故調査には、事件に関係する専門家も参加させるべきであり、客観的な分析に基づいた検討を行うことが重要です。 関係者に対して、事故に関する詳細な情報を提供し、組織全体の理解を深めることで、より効果的な学習と改善につなげることが期待できます。 過去には、事故関係者への刑事責任追及が組織学習を阻害した事例も存在しており、公正な調査と情報公開の重要性が改めて強調されます。 関係者への事故に関する詳細な筋書きを描く能力を示すことは、組織の学習と改善を支援するための根本的な前提条件と考えられます。
2. 安全文化の醸成と情報公開の重要性
事故に関する社会的な解釈は時代とともに変化しており、過去40年間における変化を踏まえ、より効果的な組織学習と安全文化の醸成のための対策が求められます。 公平な法執行がほとんどない現状では、第一の被害者と第二の被害者を生み出す過誤の処罰をなくすことができないという問題があります。 通常の業務中に生じた過誤を犯罪とすることの公平性と予測不可能性に疑問が呈されており、より柔軟でバランスの取れた対応が求められています。 製品やサービスに関する品質や安全性を継続的に改善することを目的とした、正直な情報公開を促進することが重要です。 透明性のある情報公開は、安全文化の醸成に大きく貢献し、同様の失敗を防ぐことにつながります。
3. セカンドビクティムへの配慮と組織の責任
組織は、セカンドビクティムを公平に扱い、信頼できる安全に関する重要な情報を共有する必要があります。 セカンドビクティムへの配慮なく、事象の再体験を悪化させる可能性のある公式報告書の公開は避けなければなりません。 事故調査においては、セカンドビクティムの心理的な負担を軽減するための配慮が不可欠です。 組織は、事故発生時の自身の目標と組織の目標を追求し続けるという矛盾を解決し、セカンドビクティムを公平に扱う必要があります。 セカンドビクティムへの適切な対応は、組織全体の安全文化の醸成に不可欠であり、組織の信頼性向上にも繋がります。
V.支援体制とトラウマへの介入
セカンドビクティムへの効果的な支援には、ソーシャルワーカーや医療従事者による専門的な介入が不可欠です。 第一の被害者と第二の被害者間の対話促進も重要な要素です。 しかし、訓練を受けていない同僚による安易な介入は、かえってセカンドビクティムを傷つける可能性があり、個人情報の保護対策も必要です。 トラウマへの効果的な介入は、早期介入と継続的な支援によって、PTSDなどの二次的被害を軽減することができます。 セカンドビクティムと支援者の関係性の変化への対応も重要です。
1. 専門家による支援の必要性と限界
セカンドビクティムへの支援には、ソーシャルワーカーや医療従事者といった専門家の介入が不可欠です。 彼らは、セカンドビクティムと周囲の地域社会のニーズに焦点を当て、第一の被害者と第二の被害者間の対話を促進する役割を担います。 この支援は、刑法や不法行為法に対する代替的な手段であり、安全を重視する制度における学習と説明責任のバランス達成に貢献します。 しかし、訓練を受けていない同僚による安易な介入は、かえってセカンドビクティムのトラウマを悪化させる可能性があり、個人情報の保護対策も必要です。 専門家による適切な介入と、プライバシー保護の両立が求められます。
2. 早期介入と継続的な社会支援
トラウマへの効果的な介入は、早期介入と継続的な社会支援によって、PTSDなどの二次的被害を軽減することができます。 特に、トラウマ後の社会的な支援が保証されている状況下での迅速な介入と緩和が重要です。 セカンドビクティムと支援者の関係性の変化は予測しにくく、セカンドビクティム個々の状況に合わせた対応が必要です。 支援者は、セカンドビクティムの正直さなど、人の経験の根拠となるものに対する恐怖感を理解し、トラウマ後の症状に対して適切な対応を行う必要があります。 継続的なサポート体制の構築が、セカンドビクティムの回復に大きく貢献します。
3. 組織の責任と安全文化の醸成
事故発生時に航空会社のマークを遺体から消し去ろうとしてペンキの入ったバケツと刷毛の準備をしている人員を配置する航空会社のような対応は、セカンドビクティムだけでなく、第一の被害者と組織自身をも不公平に扱い、組織にとって最も信頼できる安全に関する重要な情報を切り捨てることになります。 これは、組織が安全文化の醸成に真剣に取り組んでいないことを示すものであり、改善が必要です。 ストレスによる反応をコントロールできると判断されてから介入を開始するべきであり、インシデント発生後、関係者の技術や才能について言及することは、セカンドビクティムに期待される能力や正常性を示すものではありません。 組織は、安全文化の醸成に積極的に取り組み、セカンドビクティムへの適切な支援体制を構築する責任を負っています。
