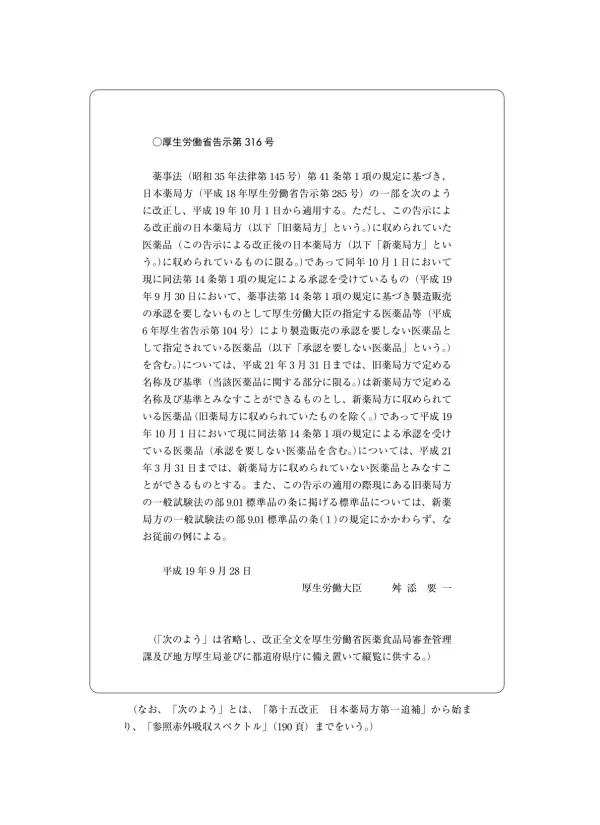
第十五改正日本薬局方第一追補
文書情報
| 著者 | 厚生労働省 |
| 文書タイプ | 告示 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 5.84 MB |
概要
I.日本薬局方改正に関する告示の概要
本告示は、日本薬局方(平成18年厚生労働省告示第285号)の一部改正を定めています。平成19年10月1日から適用され、アルプロスタジル、イソクスプリン塩酸塩、エナラプリルマレイン酸塩、クロラゼプ酸二カリウム、シラザプリル、セファゾリンナトリウムなど多くの医薬品の名称及び基準が変更されました。既存医薬品については、平成21年3月31日までは改正前の基準も認められます。改正は、保健医療上重要な医薬品の全面的収載、最新の学問・技術の導入、国際化の推進などを目的としています。液体クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィーなどの分析方法の規定も更新されています。
1. 日本薬局方改正の目的と施行日
本告示は、昭和35年法律第145号薬事法第41条第1項に基づき、平成18年厚生労働省告示第285号である日本薬局方の一部改正を定めています。改正後の日本薬局方は平成19年10月1日から適用されます。改正の目的は、保健医療上重要な医薬品の全面的収載、最新の学問・技術の積極的導入による質的向上、国際化の推進、必要に応じた速やかな部分改正及び行政によるその円滑な運用、日本薬局方改正過程における透明性の確保及び日本薬局方の普及という「5本の柱」に基づいています。これらの目標達成に向け、関係部局の協力を得て、保健医療の現場で日本薬局方が有効に活用されるよう努めることが明記されています。日本薬局方は、医薬品の品質確保に必要な公的基準を示すものであり、医薬品全般の品質保証のための規格・試験法の標準を示し、医療上重要な医薬品の品質に関する判断基準を明確にする役割を担います。多くの医薬品関係者の知識と経験が結集された公共の規格書としての性格を持ち、国民への情報公開と説明責任を果たすことも重要な役割です。
2. 改正前の日本薬局方との整合性
告示では、平成19年10月1日時点で薬事法第14条第1項に基づく承認を受けている医薬品(承認を要しない医薬品を含む)については、平成21年3月31日までは、改正前の日本薬局方(旧薬局方)で定める名称及び基準を、改正後の日本薬局方(新薬局方)で定める名称及び基準とみなすことができると規定しています。これは、旧薬局方に収載され、新薬局方にも収載されている医薬品に適用されます。ただし、新薬局方に新たに追加された医薬品については、平成21年3月31日までは新薬局方に収められていない医薬品とみなすことができます。また、旧薬局方の一般試験法の部9.01標準品の条に掲げる標準品については、新薬局方の規定にかかわらず、従前の例によることが明記されています。この措置は、改正による混乱を最小限に抑え、円滑な移行を図るための配慮を示しています。
3. 日本薬局方の役割と位置づけ
日本薬局方は、その時点での学問・技術の進歩と医療需要に応じた、わが国の医薬品の品質を確保するために必要な公的基準を示すものとして位置づけられています。医薬品全般の品質を総合的に保証するための規格および試験法の標準を示すとともに、医療上重要とされた医薬品の品質等に係る判断基準を明確にする役割を有します。多くの医薬品関係者の知識と経験が結集されており、関係者に広く活用されるべき公共の規格書としての性格を有する一方、国民に医薬品の品質に関する情報を公開し、説明責任を果たす役割も担っています。このため、改正は、最新の科学的知見や技術を取り入れ、国際的な基準との整合性を図りながら、国民の健康と安全を確保するために不可欠な役割を果たすことを目指しています。
II.医薬品の定量法と純度試験
このセクションでは、様々な医薬品の定量法と純度試験の方法が詳細に記述されています。液体クロマトグラフィーを用いた定量法が多数記載されており、内標準法を用いた分析例も含まれます。純度試験では、類縁物質の確認や、過酸化物、ヒ素などの不純物の定量方法が医薬品名ごとに示されています。重要なキーワードとして、アルプロスタジル、イソクスプリン塩酸塩、エナラプリルマレイン酸塩、クロラゼプ酸二カリウム、シラザプリル、セファゾリンナトリウム、ペプロマイシン硫酸塩、マニジピン塩酸塩、ミゾリビンなどが挙げられます。それぞれの医薬品に対し、薄層クロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーを用いた分析方法が詳細に示されています。
1. 定量法 液体クロマトグラフィーを中心とした分析
本セクションでは、医薬品の定量分析に焦点を当て、主に液体クロマトグラフィー(LC)を用いた手法が多数記載されています。 アルプロスタジル、イソクスプリン塩酸塩、エナラプリルマレイン酸塩、クロラゼプ酸二カリウム、シラザプリルなど、様々な医薬品について、それぞれに適したLC条件(移動相、カラム、検出器など)が詳細に規定されています。多くの定量法では、内標準法が用いられており、分析の精度と再現性を高める工夫がなされています。内標準物質として、被検成分と保持時間が近く、他のピークと完全に分離する安定な物質が選択されます。標準溶液を段階的に調製し、検量線を作成することで、試料中の目的成分の濃度を算出します。 具体的な操作手順として、試料の調製方法、LC装置の設定、ピーク面積やピーク高さの測定、検量線を用いた計算方法などが詳細に説明されています。これらの手順に従うことで、正確で信頼性の高い定量分析を行うことが可能になります。
2. 純度試験 類縁物質 不純物等の確認 定量
純度試験では、医薬品中に含まれる類縁物質、不純物などの量を定量し、品質基準を満たしているかを評価する方法が示されています。 アルプロスタジル、セファゾリンナトリウムなど、多くの医薬品について、類縁物質の試験方法が記載されており、薄層クロマトグラフィー(TLC)や液体クロマトグラフィー(LC)を用いた分析が中心となっています。TLCを用いる場合、展開溶媒の種類、展開距離、検出方法などが詳細に指定され、得られたスポットの色調やRf値を標準品と比較することで類縁物質の存在を確認します。LCを用いる場合は、それぞれのピーク面積を自動積分法で測定し、面積百分率法で類縁物質の量を求めます。 その他、過酸化物、ヒ素などの不純物の定量方法も記載されており、医薬品の種類に応じて適切な試験方法を選択する必要があります。これらの試験を通して、医薬品の純度と安全性に関する重要な情報を提供しています。
3. 溶出性試験 製剤からの薬物溶出速度の評価
溶出性試験は、固形製剤(錠剤など)から薬物が溶出する速度を評価する試験です。本セクションでは、パドル法を用いた溶出性試験の方法が記載されています。試験液の種類(水、溶出試験第2液など)、回転数(毎分50回転など)、試験時間(15分、30分、45分など)が医薬品の種類に応じて規定されています。溶出液をろ過し、適切な試薬を加えることで試料溶液を調製し、その中の薬物濃度を測定します。 クロラゼプ酸二カリウム、シラザプリルなどの医薬品について、規定時間における溶出率(80%以上など)が基準値として示されています。これは、製剤の品質管理において重要な指標であり、一定以上の溶出率を確保することで、薬物の体内吸収を保証する役割を果たします。溶出性試験の結果は、製剤の設計や製造工程の改善に役立ちます。
III.生薬に関する確認試験と純度試験
生薬に関するセクションでは、キョウニン、ボタンピ、カンゾウ、サンシシ、ショウキョウ、ビャクジュツ、ソウジュツなどの生薬について、それぞれ確認試験と純度試験の方法が詳細に記述されています。これらの試験では、薄層クロマトグラフィーが主要な分析手法として用いられ、特定の成分(例:アミグダリン、リクイリチン、[6]-ギンゲロール、ペオニフロリン、ノダケニン、(±)-プラエルプトリンAなど)の存在を確認、定量することで生薬の品質を評価しています。乾燥エキスを用いた試験方法も多く含まれています。
1. 生薬の確認試験 薄層クロマトグラフィーによる成分特定
本セクションでは、キョウニン、ボタンピ、カンゾウ、サンシシ、ショウキョウ、ビャクジュツ、ソウジュツなどの生薬について、その成分を特定するための確認試験が記述されています。確認試験では、主に薄層クロマトグラフィー(TLC)が用いられています。まず、生薬から試料溶液を調製します。これは、生薬の粉末を溶媒(メタノールなど)に溶解・抽出するなど、生薬の種類によって異なる方法で行われます。次に、調製した試料溶液と、それぞれの生薬に特有の成分(例:キョウニンであればアミグダリン、カンゾウであればリクイリチンなど)を含む標準溶液を、シリカゲルを担体としたTLCプレートにスポットします。適切な展開溶媒を用いて展開を行い、風乾後、紫外線照射や試薬噴霧などによりスポットを検出します。試料溶液から得られたスポットの色調、Rf値を標準溶液のスポットと比較することで、対象生薬に特有の成分の存在を確認し、生薬の真偽を判定します。
2. 生薬の純度試験 類縁物質や不純物の確認と定量
生薬の純度試験は、生薬中に含まれる不要な成分や不純物の量を評価し、品質を保証するための試験です。このセクションでは、いくつかの生薬について、類縁物質や不純物の確認、定量方法が記述されています。確認試験と同様に、薄層クロマトグラフィー(TLC)が主要な分析手法として用いられています。乾燥エキスを用いる場合、エキスを溶媒(水、メタノール、ブタノール、ジエチルエーテルなど)に溶解または抽出を行い、試料溶液を調製します。試料溶液と標準溶液をTLCプレートにスポットし、展開後、適切な試薬を噴霧・加熱することで、特定の成分(例:ショウキョウの[6]-ギンゲロール、カンゾウのリクイリチンなど)を検出し、その存在や量を評価します。 また、ボタンピの確認試験では、乾燥エキスをジエチルエーテルで抽出後、ペオノールを標準物質としてTLC分析を行い、だいだい色のスポットを比較しています。これらの試験法は、生薬の品質管理において重要な役割を担い、安全で有効な生薬の使用を保証する上で不可欠です。
3. ブシ 附子 の純度試験 ブシジエステルアルカロイドの定量
ブシ(附子)は、アコニチンなどのブシジエステルアルカロイドを含む有毒生薬です。このため、純度試験では、これらのアルカロイドの含有量を正確に測定することが非常に重要となります。このセクションでは、アコニチン、ジェサコニチン、ヒパコニチン、メサコニチンの4種類のブシジエステルアルカロイドを液体クロマトグラフィー(LC)を用いて定量する方法が示されています。まず、ブシの粉末をジエチルエーテルで抽出し、その後、ブシ用リン酸塩緩衝液/アセトニトリル混液で溶解して試料溶液を作製します。この試料溶液と、標準物質混合溶液をLCで分析し、各アルカロイドに対応するピークの高さを測定します。得られたピーク高さから、それぞれのアルカロイドの含有量を算出し、それぞれの基準値(アコニチン60 µg/g以下など)を満たしているかを判定します。これらのアルカロイドの総量についても上限値が設定されており、ブシの安全性確保に重要な役割を果たしています。
IV.ブシ 附子 に関する純度試験
ブシ(附子)の純度試験では、アコニチン、ジェサコニチン、ヒパコニチン、メサコニチンといったアルカロイド類の含有量を液体クロマトグラフィーを用いて定量する方法が示されています。これらのアルカロイドは毒性を持つため、含有量の上限値が厳しく規定されています。本セクションでは、これらのアルカロイドの含有量を正確に測定する分析法と基準値が重要な情報となります。
1. ブシジエステルアルカロイドの定量分析 液体クロマトグラフィーによる測定
ブシ(附子)の純度試験において最も重要な項目は、アコニチン、ジェサコニチン、ヒパコニチン、メサコニチンの4種類のブシジエステルアルカロイドの定量です。これらのアルカロイドは毒性を有するため、その含有量を正確に測定し、安全な範囲内にあることを確認する必要があります。本試験法では、液体クロマトグラフィー(LC)を用いた定量分析が採用されています。まず、ブシの粉末を水とアンモニア試液、ジエチルエーテルを用いて抽出を行い、アルカロイド成分を抽出し、その後、ブシ用リン酸塩緩衝液/アセトニトリル混液で溶解して試料溶液を調製します。この試料溶液と、既知濃度のブシジエステルアルカロイド混合標準溶液をLCに注入し、それぞれのアルカロイドに対応するピークの高さを測定します。ピーク高さから各アルカロイドの量を算出し、乾燥物1gあたりの含有量を算出します。それぞれのアルカロイドの含有量の上限値が設定されており、それらの総量についても上限値が規定されています。これらの基準値を超える場合は、品質が不合格となります。
2. ヒ素の定量 5 ppm以下の基準値
ブシの純度試験では、ヒ素の含有量も重要な指標となります。ヒ素は、人体に有害な重金属であり、その含有量を厳しく管理する必要があります。このセクションでは、日本薬局方一般試験法の第4法を用いたヒ素定量試験が記述されています。具体的には、ブシの粉末0.4gを採取し、規定の方法に従って検液を調製します。その後、日本薬局方に規定されている方法に従ってヒ素の定量試験を行い、その結果を5ppm以下という基準値と比較します。この基準値を超えた場合は、ヒ素の含有量が許容範囲を超えているため、品質が不合格となります。ヒ素定量試験は、ブシの安全性評価に不可欠な試験であり、その結果に基づいて、ブシの品質が評価されます。
