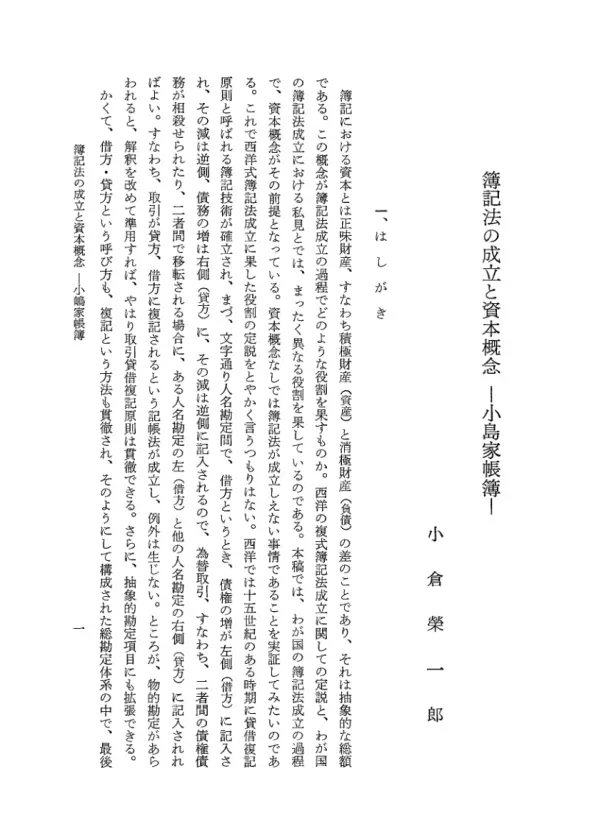
簿記成立と資本概念:小島家帳簿から探る
文書情報
| 著者 | 小倉榮一郎 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.99 MB |
概要
I.近江商人の簿記法と資本概念 中井家帳合を中心とした考察
本論文は、日本の独自の簿記法の成立過程、特に資本概念の役割を解明することを目的とする。西洋の複式簿記とは異なり、日本、特に近江地方の商人の間では独自の会計手法が発展した。中井家帳合を代表例として、その会計システムと貸借対照表、損益計算書に相当する決算報告の構造を分析する。中井家(日野町)は、近江国蒲生郡の椀問屋で、八代目の清右衛門光治の代に店卸勘定帳を作成。これは営業用資産の原価計算を目的としたもので、現在の仕入高とは異なる概念である。 中井源左衛門良祐は、独自の資本計算的成果計算を導入し、期首期末の正味身代(元手)の差額を損益とした。これは、現代の貸借対照表に相当する財産計算を重視した手法である。
1. 西洋複式簿記との比較と日本の簿記法成立における資本概念の重要性
本稿では、日本の簿記法成立における資本概念の決定的な役割を実証することを目的とする。西洋の15世紀に確立された貸借複記原則(借方・貸方の記帳法)を簡単に紹介した後、日本の簿記法では、二面形式の勘定を用いなかったため、貸借対照表のような体系的な財産計算がなかったことを指摘する。そのため、西洋の簿記法のように、人名勘定間の債権債務の相殺や移転を明確に記録する仕組みが欠けていた。 しかしながら、著者は最近発見した古い決算書を分析し、日本の簿記法が成立するためには、資本概念(簿記的資本、正味財産)が不可欠であることを発見した。この資本概念の欠如が、西洋式簿記法と日本の簿記法の根本的な違いを生み出している。後世における貸借対照表の役割(財政状態表示、財産表示)とは異なり、外部への報告を必要としない個人企業においても、資本概念に基づいた損益計算が行われていたことを明らかにする。
2. 中井家帳合 複式決算構造と資本計算的成果計算
中井家帳合は、日野商人中井源左衛門家の簿記法で、貸借対照表と損益計算書に相当する決算報告を産生する複式決算構造を有している。しかし、近江全域への普及は確認できず、日本全体で見ても、同種の簿記法は散在するものの、近江からの伝播を断言できない。八代目の清右衛門光治が相続した際の『店卸勘定帳』は、営業用資産(漆、木地、仕入原料等)の原価計算を目的としていたことが江頭恒治博士によって指摘されている。仕入高は、今日の仕入費用累計ではなく、仕入原価を意味していた点に注目する必要がある。中井源左衛門良祐は、独自の資本計算的成果計算を導入し、期首期末の正味身代(元手)の差額を損益とした。これは、固定資産を計算外に置き、営業用運転資本の両端比較による成果計算と言える。良祐の『店卸記』は、行商開始時ではなく、結婚前年の延享3年頃のものと推定される。
3. 中井家帳合の資本概念と損益計算 独自の成果計算手法
中井家における損益計算は、年度末に残存する資産と負債の額から算定される「結果にもとづく損益計算」である。収益・費用の比較計算ではなく、期首期末の正味身代(元手)の差額を損益とする計算方法であり、固定資産の調達も損失として扱われた。これは、良祐が独自に考案したものではなく、行商開始から10年以上経過した段階で導入された手法であると考えられる。同時代の薬商、小谷庄三郎の事例から、期首期末の正味身代の比較による損益計算は、当時の常識であった可能性を示唆する。小谷庄三郎の事例は『近江商人』、『近江蒲生郡志』、『近江日野町志』に類似の記述があり、資本概念の増殖を祖先の遺業の継承と捉える考え方を示している。しかし、この考え方の表現は多様であり、誤解を生じやすい点にも注意が必要である。
4. 中井家帳合の普及範囲と限界 今後の研究課題
中井家帳合は、日本の独自の簿記法として、貸借対照表と損益計算書に相当する複式決算構造を持ち、巧妙な管理会計システムをなしていた。しかし、学校教育や教科書が存在しなかった当時において、この会計手法が広く普及していたとは考えにくい。アンケート調査の結果では、江戸時代の簿記法は単式構造のものが大部分を占める。日野商人同士の情報交換があった可能性はあるものの、その普及範囲は日野商人集団に限られていたと推察される。 今後の研究課題としては、日野商人だけでなく、八幡商人、高島商人、湖東商人など、近江商人全体の簿記法を網羅的に調査し、その地域差や独自性を明らかにすることが重要である。また、中井家帳合に類似した帳簿史料を精査し、その伝播経路や影響範囲を解明していく必要がある。
II.小嶋家帳簿 日野商人とは異なる会計システム
八日市中野の魚肥問屋、小嶋家の帳簿を分析した結果、中井家とは異なる単式決算構造を採用していることが判明した。小嶋家は、大晦日勘定記と呼ばれる貸借対照表に相当する決算報告書を作成していたが、損益計算書は作成していない。これは、地理的にも時代的にも中井家と近いが、会計原理においては異なることを示している。取引商品の流通経路や商法が異なるため、会計システムも異なっている。小嶋助次郎家は天保以来約百年にわたる連続した商業帳簿を残しており、地方商人の経営史研究に貴重な資料となっている。
1. 小嶋家帳簿の概要と資料の特徴
本稿では、八日市中野の魚肥商人である小嶋助次郎家の帳簿史料を分析する。この史料は、天保以来約100年にわたる完全に連続した商業帳簿であり、地方商人の経営史研究にとって貴重な資料となる。著者は昭和56~57年に文部省科学研究費を受けてこの史料の調査と引渡しに携わったが、現在、八日市市史編纂のため市役所が保管しており、利用には制限がある。小嶋家文書の中心は商業帳簿であり、小嶋屋本家、分家共に広範な商圏を持っていたことがわかる。地理的に近く、時代的にも後発であることから、中井家帳合の影響を受けている可能性が考えられたが、実際には簿記原理においては大きな違いが見られた。
2. 小嶋家の会計システム 単式決算構造と 大晦日勘定記
小嶋家の決算報告書は『大晦日勘定記』と呼ばれ、その内容は貸借対照表に相当する。しかし、損益計算書は作成されておらず、単式決算構造であることが明らかになった。期末棚卸商品(在庫品)は品目別に数量計算され、残高、単価、金額(銀)が明記され、附帯費用も記載されている。仕入帳が存在したことから、仕入原価の算出は可能であったと考えられる。現金や債権は概数で表示され、附属明細書で詳細な記録計算がなされているものの、決算書には概数で集計されていた。在庫評価も概数で表示され、債権額についても概数でまとめられている点は注目に値する。この会計方法は、詳細な計算よりも、幾通りもの意味を持つ金額を求められる形式の方が都合が良かった可能性を示唆している。
3. 小嶋家と中井家の簿記法の比較 会計原理における相違点
小嶋家の帳簿は、中井家帳合と地理的に近く、時代的にも後発であることから、当初は中井家帳合からの影響を受けていると予想された。しかし、帳簿の形式や種類は共通点があるものの、会計原理、すなわち簿記の原則においては大きな違いがあった。小嶋家の会計システムは、中井家のような複式決算構造ではなく、単式決算構造である。取引商品の流通経路や商法も大きく異なっており、このことが会計システムの相違に繋がっていると考えられる。小嶋家の会計システムは、八幡商人あるいは湖東商人の簿記法とより関連性が高い可能性があり、今後の研究で詳細な検証が必要である。 特に小嶋助次郎家の膨大な史料は八日市市史編纂のために市役所が保管しており、その詳細な分析は今後の課題である。
4. 小嶋家帳簿の分析から得られる知見と今後の研究方向
小嶋家帳簿の分析から、近江商人の中でも、地域によって簿記法に多様性があったことが示唆される。中井家のような複式決算構造が、近江全域、あるいは全国に広く普及していたわけではない。小嶋家の単式決算構造は、その地域特有の産業構造や商業形態を反映していると考えられる。小嶋家の帳簿史料は、天保以来約100年にわたる連続したデータであり、地方商人の経営実態を詳細に解明する上で非常に貴重な資料である。今後の研究では、小嶋家帳簿の徹底的な分析を通して、その会計システムの特徴を明らかにし、近江商人の簿記法の地域的多様性と、その背景にある経済・社会構造との関連性を解明していく必要がある。また、他の近江商人の帳簿史料との比較検討も不可欠である。
III.近江商人における簿記法の普及と地域差
近江商人の中でも、日野商人、八幡商人、高島商人、湖東商人など、地域によって簿記法に違いが見られる。中井家帳合のような複式決算構造は、日野商人において一定程度普及していた可能性があるものの、近江全域、更には全国へ広く普及したとは言い切れない。 会計システムの発展は、地域特有の産業構造や商業形態と密接に関連していると考えられる。アンケート調査(昭和57年、約25社から回答)の結果では、多くの企業が単式簿記を採用していた。 北海道産魚肥の流通における近江商人の役割や、湖東五郡肥物仲間の成立なども、地域経済と簿記法の発展に影響を与えたと考えられる。
1. 近江商人の分類と簿記法の地域差
近江商人を、高島商人、八幡商人、日野商人、湖東商人の4つに分類し、それぞれの簿記法の差異について考察する。 高島商人は江戸時代初期、八幡商人は江戸時代初期、日野商人は江戸時代初期と元禄頃、湖東商人は江戸時代後期に発祥しており、発祥時期の違いが商法の違い、ひいては簿記法の違いに繋がっている可能性を示唆する。中井家帳合のような複式簿記構造は、日野商人においては一定程度普及していた可能性はあるものの、近江全域への普及は確認できない。 また、日本全体で見ても、中井家帳合と類似した簿記法が散見されるものの、近江からの伝播を断定することは困難である。このことから、近江商人の簿記法は均一ではなく、地域によって独自の進化を遂げていたことがわかる。
2. 複式決算構造の普及状況と貸借対照表の作成
近江商人の決算報告書において、貸借対照表に相当する財産計算は例外なく行われていた。これは複式簿記構造が完全に普及していたことを示唆するものではないものの、財産計算、つまり資本計算的成果計算が、当時の商人の経営判断において重要な役割を果たしていたことを示している。 しかし、昭和57年に実施された近江系企業600社へのアンケート調査(有効回答25社)では、多くの企業が単式簿記を採用していたことが明らかになった。これは、明治以降、特に太平洋戦争以降に創業した企業が多いため、古い簿記法の情報が得られにくかったことが要因として考えられる。 この調査結果は、複式決算構造が近江商人全体に広く普及していたという仮説を裏付けるものではない。
3. 北海道産魚肥と近江商人の交易 湖東五郡肥物仲間
北海道との交易において、近江商人は重要な役割を果たしていた。北海道産の魚肥は、産地から消費地まで近江商人の手で直接運ばれるルートと、敦賀港で魚肥問屋を経由するルートの2つが存在した。近江商人の販売力と、全国に広がる配給網が、他の地域からの商人よりも優れていたことが、交易における成功要因として挙げられる。 しかし、近江商人の交易における優位性は、時代とともに変化した。敦賀の問屋仲間の独占力は、近江商人の勢力拡大とともに弱まり始め、文化の頃には、昆布などは専門問屋化し、加工も兼業するようになり、敦賀、長浜、京都、大阪を結ぶルートを確立した。 文政元年に設立された湖東五郡肥物仲間は、魚肥の値崩れを防ぐために、敦賀問屋仲間と近江の魚肥商人が結んだ組合である。これは、近江商人の交易における競争と協力の両面を示す重要な事例である。
4. 近江商人の発展と簿記法 地域経済の変化と会計システム
近江商人の活動は、江戸時代初期に八幡、日野から輩出した商人によって始まり、その後、元禄頃より新規参入が目立ち始める。日野商人においては、享保前後に多くの新規参入があり、地場産業から全国的な産業への転換が見られた。日野椀、日野売薬などは、その例として挙げられる。 八幡商人においては、畳表や蚊帳などの地場産業が衰退していく中で、新たな商材への転換を余儀なくされた。 このような経済界の激動期の中で、日野商人、八幡商人、そして湖東商人の間で、独自の簿記法が発展し、地域差が生じていったと考えられる。 日野商人集団においては、貸借対照表と損益計算書に相当する二つの計算が一致するという考え方が普及した可能性が高く、これは他の地域では見られない特徴である。
IV.結論 日本の簿記法の多様性と資本概念の重要性
本研究を通じて、日本の簿記法は西洋の複式簿記とは異なる独自の発展を遂げ、地域差も存在したことが明らかになった。資本概念は、日本の簿記法成立において不可欠な要素であり、各商家の会計システムの差異を理解する上で重要な視点となる。今後の研究では、より多くの帳簿史料の分析を通して、地域ごとの簿記法の特徴を更に解明し、日本会計史における資本計算の役割を詳細に検討していく必要がある。
1. 日本の簿記法の多様性 地域差と独自性の存在
本論文の分析から、日本の簿記法は西洋の複式簿記とは異なり、多様な形態が存在し、地域差が顕著であったことが明らかになった。特に近江商人を例に、日野商人、八幡商人、高島商人、湖東商人といった地域集団ごとに、簿記法に差異が見られることを指摘する。 中井家帳合に見られるような複式簿記に類似したシステムは、日野商人において一定の普及を見せていた可能性があるものの、近江全域、さらには全国へ広範に普及したという証拠は得られていない。 小嶋家帳簿の分析からも、地理的にも時代的にも近い中井家とは異なる会計システムを採用していることが確認され、地域ごとの独自の簿記法の発展を示唆している。これらの地域差は、それぞれの地域の産業構造や商業形態、経済活動の特性と密接に関連していると考えられる。
2. 資本概念の重要性 日本の簿記法成立における基盤
本研究において最も重要な発見は、日本の簿記法の成立過程において「資本概念」が不可欠な要素であったという点である。 西洋の複式簿記が債権債務の記録を重視するのに対し、日本の簿記法は、資本(元手、正味財産)の変動を軸とした損益計算を行う傾向がある。中井家帳合における「資本計算的成果計算」や、小嶋家帳簿における「大晦日勘定記」は、この資本概念を基盤とした会計システムの一例である。 これらの会計手法は、現代の貸借対照表や損益計算書とは異なる独自の構造を持っており、当時の経済状況や商人の経営判断を反映したものである。 したがって、日本の簿記法を理解するためには、西洋の簿記法とは異なるこの「資本概念」を重視したアプローチが必要不可欠である。
3. 今後の研究課題 史料分析の継続と多角的アプローチ
本論文では、中井家帳合と小嶋家帳簿を中心に日本の簿記法の多様性と資本概念の重要性を論じたが、今後の研究では、より多くの史料の分析が必要となる。特に、近江商人以外の地域における簿記法についても調査を進め、日本全体の簿記法の発展過程を明らかにする必要がある。 また、地域ごとの簿記法の特徴を詳細に比較検討し、その違いを生み出した要因を経済的、社会的、文化的側面から多角的に分析する必要がある。 さらに、アンケート調査で得られた情報をより詳細に分析し、仮説の検証を行うことで、より正確な歴史的解明を進める必要がある。 これらの継続的な研究を通して、日本の簿記法の独自性と多様性をより深く理解し、日本会計史におけるその意義を明らかにすることが期待される。
