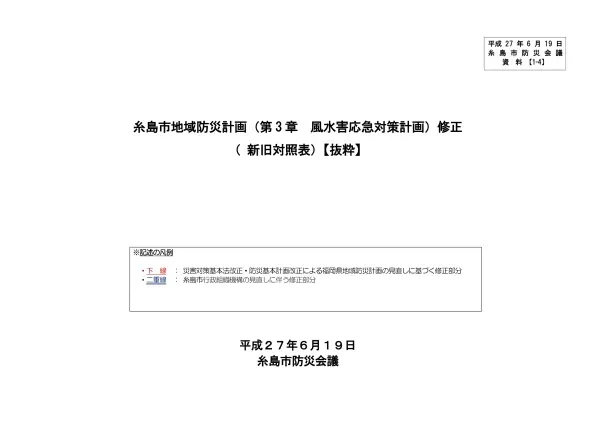
糸島市風水害応急対策計画
文書情報
| 著者 | 糸島市防災会議 |
| 場所 | 糸島市 |
| 文書タイプ | 防災計画 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.81 MB |
概要
I.市民への気象情報等の周知
糸島市は、気象予警報(大雨、暴風、土砂災害等を含む)の発令時、報道機関(テレビ・ラジオ)や広報車、市防災行政無線などを活用し、市民に迅速に情報を伝達します。特に要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児等)への情報伝達には細心の注意を払います。避難勧告・避難指示の発令時には、避難準備、避難方法等を明確に周知します。インターネットやFM放送なども活用し、多様な手段による情報発信体制を整えています。 福岡管区気象台の注意報・警報は市町村ごとに発表され、福岡県、福岡地方、北九州地方といった地域名称も用いられます。
1. 報道機関を通じた情報伝達
気象予警報、警報、注意報等の情報は、まず報道機関(テレビ、ラジオ等)を通じて市民に伝えられます。市町村ごとに発表される情報も、放送においては簡潔かつ効果的に伝えるため、市町村をまとめた地域名称(例:福岡地方、北九州地方)を用いる場合があります。糸島市は福岡地方に含まれます。この方法は、多くの市民に迅速に情報を届けるための第一ステップとして機能します。情報伝達の効率性を高めるために、地域名称を用いるという工夫がなされている点が重要です。これは、特に緊急性の高い情報の場合、詳細な市町村名まで伝えるよりも、広い範囲をまとめて伝えることで迅速性を優先する戦略と言えます。この方法のメリットは、情報伝達のスピードと広範囲へのカバーです。一方で、個々の市町村への詳細な情報は、二次的な情報伝達手段に頼ることになります。
2. 広報車 警鐘等を活用した直接的な情報伝達
被害を及ぼす可能性のある状況が予想される場合は、広報車や警鐘などを用いて直接的に市民に予警報を伝達します。さらに、自主防災組織等の住民組織と連携することで、より効果的な情報伝達を目指します。これは、報道機関による情報伝達だけではカバーできない地域や状況に対応するための、重要な補足手段です。特に、高齢者や障害者など、情報伝達手段へのアクセスが制限されている要配慮者への配慮が強調されています。広報車や警鐘は、直接的な音と視覚的な情報によって、情報伝達の確実性を高める効果があります。住民組織との連携は、地域の特性や事情に合わせた柔軟な情報伝達を可能にします。この方法が効果的なのは、災害発生が迫っているなどの緊急時、または報道機関のカバーが困難な地域です。住民組織による地域密着型の情報伝達によって、要配慮者への配慮も強化できます。
3. 避難勧告 指示の発令と周知
浸水やがけ崩れなどの被害のおそれがあり、事態の推移によっては避難勧告または指示が必要となる場合、危機管理班と秘書広報班(または企画秘書班)は関係各班と連携して、市民に対し避難準備を周知します。これは、単なる警報・注意報の発令とは異なり、具体的な行動を促すための重要な情報伝達です。避難勧告・指示は、市民の生命と安全を守るために最も重要な情報であり、その周知には万全を期す必要があります。関係各班との連携は、情報伝達における正確性と迅速性を担保するため、不可欠な要素です。この段階では、避難場所、避難経路、避難方法といった具体的な情報が市民に伝えられる必要があります。また、要配慮者への配慮も引き続き重要であり、これらの情報が要配慮者に的確に伝わるよう、特別な配慮が求められます。この周知方法は、避難勧告・指示という法的根拠に基づくものであり、市民の協力と理解が不可欠です。
4. 市地域防災計画に基づく周知
糸島市は、市地域防災計画に基づき、関係住民に対し、必要と認められる予警報だけでなく、予想される事態と取るべき避難のための措置(避難準備、立ち退き等)を伝達・周知します。大雨や暴風等の特別警報の場合は、直ちに多様な手段を用いて住民に伝達します。特に、要配慮者が避難勧告・指示を受けた際に、円滑に避難できるよう配慮します。これは、市独自の防災計画に基づいた、包括的な情報伝達戦略を示しています。計画に基づく情報伝達によって、体系的で抜け目のない情報発信を可能にします。多様な手段を用いることは、情報伝達の確実性と効率性を高める上で、非常に重要です。要配慮者への配慮は、災害対策における重要な要素であり、情報伝達においても、そのニーズに合わせた対応が求められます。この方法では、計画に基づいた、事前に準備された情報伝達システムが活用されることになります。そのため、緊急時の対応が迅速かつ的確に行われることが期待できます。
5. 緊急時の情報伝達手段
緊急を要する場合、電気通信事業者等の設備を優先利用したり、インターネットポータルサイト・サーバ運営業者に情報提供を依頼するなど、様々な手段を用いて迅速な情報伝達を行います。これは、通常の手段では情報伝達が困難な場合に備えた、緊急時のバックアップ体制です。法律に基づいた権限を用いて、優先的に通信回線を確保できる体制が整えられています。インターネットを活用することで、広範囲の住民に同時に情報を届けることが可能です。様々な手段を組み合わせることで、災害状況や情報伝達手段の障害といった不測の事態にも対応できる、柔軟性の高い情報伝達システムが構築されていることがわかります。この方法は、極めて緊急性の高い状況下において、情報伝達の遅延を防ぐための重要な戦略となります。
II.気象情報等の監視体制
危機管理班および企画秘書班(または秘書広報班)は、防災関係機関と連携し、テレビ、ラジオ、ホームページ等で気象情報、河川情報等を常時監視。警報等の迅速な伝達に備えます。福岡管区気象台の注意報・警報、福岡県土砂災害危険度情報等も重要な情報源です。
1. 危機管理班と企画秘書班 または秘書広報班 による監視
危機管理班と企画秘書班(または秘書広報班)は、防災関係機関と連携して、災害対策に係る気象情報、河川情報などをテレビ、ラジオ、ホームページなどで監視します。これは、災害発生の兆候を早期に察知し、迅速な対応を可能にするための重要な活動です。防災関係機関との連携は、情報の共有や迅速な意思決定を可能にする上で不可欠であり、複数部署による情報収集と分析は、より正確な状況把握に繋がります。テレビ、ラジオ、ホームページといった多様な情報源を利用することで、情報の偏りを防ぎ、より信頼性の高い情報を収集することができます。監視活動を通じて得られた情報は、警報等の迅速な伝達に役立てられます。この監視体制は、災害発生前に適切な対策を講じ、被害を最小限に抑えるために不可欠です。特に、気象情報や河川情報の変化は、災害発生リスクを評価する上で重要な指標となります。
2. 福岡管区気象台の情報と地域名称の使用
福岡管区気象台の注意報・警報は市町村ごとに発表されます。しかし、気象情報は市町村名に加え、福岡県、福岡地方、北九州地方といった地域名称を用いる場合があります。糸島市は福岡地方に属します。地域名称の使用は、情報伝達の効率性向上のために行われます。広範囲の地域に共通する情報を簡潔に伝えることで、住民への理解を促し、迅速な行動を促す効果が期待できます。市町村単位での情報提供と地域単位の情報提供の併用は、住民の居住エリアや情報入手手段の多様性に対応した戦略です。より広い範囲の住民に、共通の危険性を迅速に伝える必要性が高い場合、地域名称の使用が効果的です。一方で、詳細な情報を必要とする住民には、市町村単位の情報が提供される仕組みとなっています。この地域名称の使い分けは、情報伝達の正確性と迅速性の両立を目指した、柔軟な対応策と言えるでしょう。
III.避難体制と緊急輸送
避難勧告・指示が出された場合、危機管理班とシティセールス班(または商工振興班)は関係各班と連携し、市防災行政無線、広報車、消防団等を通じて速やかに周知します。避難所開設時には、水産商工班(または商工振興班)が事前に定めた計画に基づき、人員、食糧、飲料水、生活物資等の緊急輸送を行います。輸送業者への搬送要請も検討します。避難所運営サポート職員は避難者への物資配布を担当します。
1. 避難勧告 指示の発令と周知
避難勧告・指示が必要と判断された場合、危機管理班とシティセールス班(または商工振興班)は関係各班、関係機関、施設管理者と連携し、市防災行政無線、広報車、消防団などを活用して迅速に避難準備情報、勧告、指示を周知します。直接住民に伝える場合もあります。特に、情報伝達が困難な要配慮者への配慮が重要視されています。避難勧告・指示は、市民の生命・身体を守る上で極めて重要な情報であり、その迅速かつ正確な伝達は避難体制の要となります。関係機関との連携は、情報伝達の円滑化と信頼性向上に大きく貢献します。防災行政無線、広報車、消防団などは、情報伝達手段としての多様性を確保し、住民へのリーチを高める役割を果たします。また、避難準備に必要となる具体的な情報(避難場所、避難経路など)も合わせて周知される必要があると理解できます。この避難体制は、市民の安全確保を最優先事項として、関係者全員が連携して取り組む体制となっています。
2. 緊急輸送体制
避難所開設時には、水産商工班(または商工振興班)とシティセールス班は、あらかじめ定められた災害時の輸送計画に基づき、人員、食糧、飲料水、生活物資、資機材などを搬送します。避難所が多数ある場合は、輸送業者に搬送を要請します。市職員や公有車両による輸送は原則として行わず、外部業者への委託が基本となります。これは、効率的な輸送体制の構築と、市職員の人的資源の有効活用という観点から重要な方針です。あらかじめ定められた計画に基づいて行動することで、混乱を避け、迅速な対応が可能になります。食糧、飲料水、生活物資などは、避難生活において不可欠なものであり、その安定供給は避難体制の維持に不可欠です。輸送業者への委託は、大規模災害時における輸送力の確保に繋がる重要な戦略です。避難所運営サポート職員は、避難者への生活物資の配分を行う役割を担い、避難者の生活支援の中核となります。
IV.要配慮者への支援
福祉支援班、介護・高齢者支援班、危機管理班は、自主防災組織、民生委員・児童委員等の協力を得て要配慮者の安否確認、安全な避難所への誘導を行います。災害時要援護者に対する福祉サービス(ホームヘルパー派遣、手話通訳者派遣等)も迅速に提供します。福祉避難所の開設も検討します。
1. 災害時要援護者 要配慮者 の安否確認と避難誘導
福祉支援班、介護・高齢者支援班、危機管理班は、自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉関係団体、消防団、社会福祉協議会などの協力を得て、災害時要援護者(要配慮者)の安否確認を行います。これは、災害発生直後から行われる緊急措置です。要配慮者とは、災害の危険を察知したり、救助を申請したり、災害情報への理解や対応に困難を抱える人たちです。安否確認は、名簿を作成し、系統的に実施されます。避難行動要支援者名簿も活用されます。安全で適切な避難所への誘導も、これらの班が連携して行います。この安否確認と避難誘導は、要配慮者の生命と安全を守る上で最も重要な活動です。関係機関との連携によって、迅速かつ的確な対応が可能となります。要配慮者への配慮は、災害対策における倫理的な側面からも極めて重要です。避難所への誘導に加え、必要に応じて福祉避難所も確保されます。また、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿を効果的に利用できるようになっています。
2. 福祉避難所の開設と要配慮者の移送
要配慮者が避難所や在宅で介護等が困難な場合、福祉支援班と介護・高齢者支援班は福祉避難所を確保するか、市内福祉施設に緊急受け入れを要請します。福祉避難所が確保されれば、福祉関係団体やボランティアの協力を得て、要配慮者を速やかに移送します。必要に応じて、要配慮者の家族も福祉避難所へ避難させることができます。これは、要配慮者にとってより適切な環境を提供するための措置です。福祉避難所は、要配慮者にとってより安全で快適な避難生活を送るための、重要な支援施設となります。福祉関係団体やボランティアとの連携によって、円滑な移送と避難生活の支援が実現します。家族同伴の配慮は、精神的なサポートの観点からも非常に重要です。福祉避難所の開設や要配慮者の移送は、災害時における人道的な配慮に基づいた、重要な支援活動です。 市内福祉施設との連携体制も、事前に構築されていることが想定されます。
3. 災害により新たに発生した要配慮者への対策
災害発生時には、避難行動要支援者支援名簿に登録されている要配慮者以外にも、災害を契機に新たに要配慮者となる人が発生します。これらの人々への的確なサービス提供が重要です。発災後2~3日目から、全ての避難所を対象に要配慮者の把握調査を開始し、発災1週間を目途に福祉サービス(ホームヘルパー、手話通訳者派遣、補装具提供等)を組織的・継続的に開始できるようにします。これは、災害による新たなニーズへの対応を迅速に行うための体制です。災害発生直後から、新たな要配慮者の状況把握とニーズの的確な把握が求められます。福祉サービスの提供開始までの期間を明確に示すことで、迅速な対応体制が構築されています。在宅での生活が可能な場合の在宅福祉ニーズの把握にも配慮し、多様な状況に対応できるようになっています。この対策は、災害による影響を最小限に抑え、被災者の生活再建を支援するための、重要な取り組みと言えます。
V.外国人への対応
地域振興班とシティセールス班は、県、警察署、国際交流協会、ボランティア団体等と連携し、外国人への被災情報提供、相談対応を行います。(公財)福岡県国際交流センターの相談窓口、インターネット、FM放送等による多言語情報提供も活用します。
1. 被災情報の把握と相談対応
地域振興班とシティセールス班は、県、警察署、国際交流協会、ボランティア団体など関係機関と連携し、市内の外国人住民の被災情報の把握と相談対応を行います。これは、外国人住民が災害時に必要な情報や支援を受けられるよう、多言語対応を含むサポート体制を構築するための取り組みです。関係機関との連携は、情報収集の効率化と、正確な情報の提供に不可欠です。ボランティア団体などの協力も得ることで、より広範囲なサポートが実現します。被災情報の把握は、外国人住民の状況を正確に理解し、適切な支援を行うために重要です。相談対応においては、言語の壁や文化的な違いなどに配慮した対応が必要です。この活動は、外国人住民が災害時にも安心して暮らせるよう、行政が責任を持って対応する姿勢を示すものです。
2. 多言語情報提供メディアの活用
外国人住民および関係者に対して、県が実施する(公財)福岡県国際交流センターでの外国人県民相談、インターネット、FM放送などによる多言語での情報提供メディアを積極的に広報します。これは、外国人住民への情報伝達を円滑に行うための重要な手段です。多言語での情報提供は、情報伝達における言語の壁を取り除き、正確な理解を促進する効果があります。インターネットやFM放送は、広い範囲の外国人住民に情報を届けるのに適した手段です。(公財)福岡県国際交流センターは、専門的な相談窓口として機能します。多様な情報提供手段の活用によって、様々な状況にある外国人住民への情報伝達が円滑に行われるように配慮されています。この広報活動は、外国人住民が災害時にも必要な情報を適切に得られるよう、行政が積極的に支援を行う姿勢を示しています。
VI.災害後の対応
税務班は住家被害認定調査を行い被災台帳を作成します。シティセールス班は被災状況、応急対策、住民への対策等を積極的に広報します。健康づくり班は、PTSD等の精神的不安への対策としてカウンセリングやメンタルケア資料の作成を行います。ごみ処理については、委託業者に協力を要請し、必要に応じて市職員が清掃部隊を編成します。災害廃棄物の処理においては環境対策に配慮します。
1. 住家被害認定調査と被災台帳の作成
税務班は、住家被害認定調査の実施体制を早期に確立し、被災台帳を作成します。県には家屋被害調査指導員の派遣を要請し、調査要員が不足する場合は建築士等の協力を要請します。大規模災害時にはGISを活用して、判定結果の妥当性確認と作業の迅速化に努めます。被災台帳の作成は、災害による被害状況を把握し、今後の支援策を検討する上で重要な基礎データとなります。県からの支援と専門家の協力は、迅速かつ正確な調査を行う上で不可欠です。GISの活用は、大規模災害時における効率的な情報処理に大きく貢献します。この調査活動は、災害からの復旧・復興に向けた最初のステップであり、正確なデータに基づいた迅速な対応が求められます。被災状況の把握は、今後の支援策を決定する上で非常に重要です。
2. 被災状況等の広報活動
シティセールス班と関係各班は、気象情報だけでなく、被災状況、応急対策の実施状況、住民のとるべき措置などについて積極的に広報活動を行います。災害時の風評被害による人権侵害防止のための広報も実施します。要配慮者への配慮も徹底します。広報活動は、市民への正確な情報提供と安心感の醸成に役立ちます。被災状況の迅速な伝達は、関係機関や住民間の連携強化に貢献します。風評被害防止のための広報は、社会全体の安定維持に不可欠です。要配慮者への配慮は、災害時における支援の重要な柱となります。この広報活動全体を通して、市民の安全と安心を確保するための積極的な姿勢が示されています。
3. 心のケア対策
大規模災害発生時や避難生活が長期化する場合は、健康づくり班が福岡県精神保健福祉センター、糸島保健福祉事務所、精神科医療機関、児童相談所職員などの協力を得て、カウンセリングやメンタルケア資料の作成を行い、被災者や要配慮者のPTSD等の精神的不安への対策を行います。これは、災害による精神的な影響への対策として重要な取り組みです。専門機関との連携によって、被災者への的確な支援が実現します。カウンセリングやメンタルケア資料の作成は、被災者の心のケアに役立ちます。PTSDなどの精神的疾患への対策は、災害後の社会回復にも大きく貢献します。この取り組みは、災害後の心のケアを重視する、人道的な姿勢を示すものです。
4. 災害廃棄物処理
災害廃棄物処理計画を策定し、ごみの収集は委託業者に協力を要請、必要に応じて市職員が清掃部隊を編成し、ごみ処理場で焼却または埋め立て処理します。市だけでは対応できない場合は、近隣市町村や筑紫保健福祉環境事務所(または県廃棄物対策課)に応援を要請します。仮置場の開設、がれき処理における環境対策(大気汚染防止等)、アスベスト等の有害廃棄物の適正処理も実施します。住民への広報も行います。災害廃棄物の処理は、衛生面と環境保全の両面から重要な課題です。委託業者への依頼と市職員による対応の併用は、効率的な処理体制の構築を目指しています。近隣市町村や関係機関との連携は、処理能力の不足に対応するための重要なバックアップ体制となります。環境対策や有害廃棄物への配慮は、環境保全と住民の健康を守る上で不可欠です。
5. 遺体の収容 安置
福祉保護班と市民班(または環境施設班)は、警察署と協力して身元不明者の特徴をまとめ、問い合わせに対応します。遺族等の引き取り人がいれば遺体を引き渡します。身元識別が困難な場合や死亡者多数の場合は、遺体を遺体安置所に搬送し一時安置します。これは、尊厳ある扱いを確保するための重要な活動です。警察署との連携は、身元不明者の特定に不可欠です。遺族への配慮は、災害後の心のケアにおいて非常に重要です。遺体安置所の確保と適切な管理は、災害時における重要な対応となります。この活動は、災害後も継続して行われる必要のある、人道的な取り組みです。
