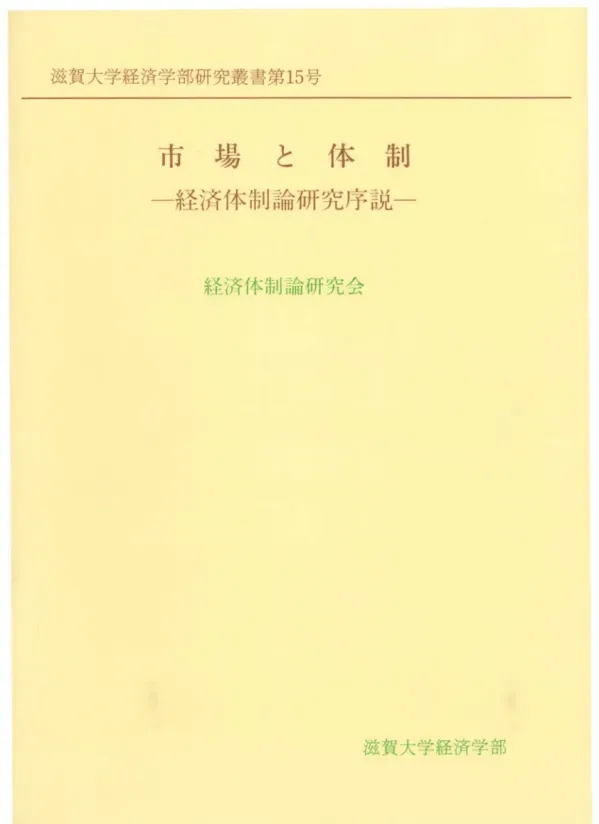
経済体制論:市場と体制
文書情報
| 著者 | 経済体制論研究会 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 研究叢書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 6.28 MB |
概要
I.市場経済と社会主義計画経済の比較 ハンガリー経済改革の焦点
本論文は、戦後社会主義圏における経済システム、特にハンガリーにおける経済改革を分析し、市場経済と社会主義計画経済の比較検討を行っています。マルクスの市場制度観に基づき、抽象性による具体性の抑圧、貨幣への依存、個人の自由と制度的制約の問題点を指摘。計画経済の問題点は、莫大な情報の処理と個々のインセンティブの確保にあると論じ、ハンガリーにおけるコルナイやポーランドのレフ・ルールなどの実践的な改革アプローチ(市場メカニズムの導入)を取り上げています。 自由主義と社会主義の対比を通して、経済計算問題や、効率性と平等性のバランスといった重要な課題を考察しています。
1. 社会主義計画経済の限界と経済計算問題
このセクションでは、社会主義計画経済の根本的な問題点が論じられています。集権的な物財バランス法では、莫大な情報の処理と、個々の生産単位へのインセンティブの欠如という困難に直面していたと指摘されています。1960年代に入ると、計画と市場の結合という分権的な計画が注目を集めるようになり、社会主義計画経済の問題は、情報処理とインセンティブの確保という点に集約されると述べられています。ハンガリーのコルナイやポーランドのレフ・ルールといった経済学者は、市場均衡モデルを参照しつつ、計画経済の枠組みに市場メカニズムを取り込むという実践的な、妥協的な立場を取らざるを得なかったと解説されています。これは、計画経済における「経済計算問題」の解決という観点からすれば、当然のことだったとされています。さらに、経済的目標達成のための「自由」の意味についても考察されており、個人の経済活動の自由が、ホップズ主義的な自然状態の投影となり、無政府的な経済的自由が貧困と道徳的退廃をもたらす可能性が指摘されています。リカードやマルサスが予見したような、恒常的な貧困と道徳的退廃への懸念が示されています。これは、自己中心的利己心や制御されない個人の行動がもたらす結果だと結論付けられています。
2. 19世紀の理性主義と社会主義計画経済
この部分では、19世紀の理性主義が、市場経済のメカニズムを活用する方法と、社会主義的な計画によって平等を実現しようとする二つの方向で展開されたと説明されています。興味深いことに、市場均衡論者の自由放任主義と社会主義的計画経済の理想は、ワルラスやJ.S.ミルなどの例からもわかるように、容易に両立可能であったとされています。これは、市場経済と計画経済が、必ずしも相容れないものではないという示唆を与えています。しかし、この両立可能性は、後の社会主義計画経済の実践において必ずしも実現されなかったことを示唆しており、理想と現実のギャップが示唆されています。また、このセクションでは、ブキャナンの指摘する「授権理論」の難点も言及されています。具体的には、「過去の不正」を是正するための国家による干渉は、個々の行為としては正当でも、累積的には容認できない結果をもたらす可能性があるという点です。外部不経済の存在や富の集中による政治権力への影響などが例として挙げられており、市場メカニズムだけでは「保証」と「ただ乗り」の問題が発生する可能性が示唆されています。
3. マルクスの市場制度観と現代社会への示唆
マルクスの市場制度観は、抽象性による具体性の抑圧として表現されています。市場経済では、貨幣(抽象性)の獲得が優先され、労働が手段化され、人間の社会的存在としての側面が軽視されるという批判がなされています。さらに、「自由」という観点からも問題提起されており、市場における個人の選択は、実際には市場という制度によって強制されたものでしかないという指摘があります。つまり、個人が自ら作り出した制度に縛られ、自らの本性に反する行動を強いられているという問題意識が示されています。このマルクスの批判は、現代社会における寡占化された経済や、労働の営利活動化、消費の享受化といった現象にも通じるものがあります。現代社会では、利得の機会があれば資本が介入し、生産と消費が過度に分割され、消費を準備する活動の重要性が軽視されていると指摘されています。マルクス的労働観の観点から、労働内容が各人の個性の発現を許容する程度に豊かであることが重要だと結論付けられています。
II.ハンガリー経済改革 計画と市場の結合
1956年のハンガリー動乱後、過度に集権的なソ連型計画経済システムからの脱却を目指した改革が試みられました。初期の改革は限定的でしたが、1968年の改革は計画指令の廃止を目指しました。しかし、アンタル・ラースローらの指摘するように、完全な市場経済への移行には至らず、「二重経済」構造(社会主義セクターと非社会主義セクターの共存)が生まれました。この「二重経済」は経済にとどまらず、ハンキシュ・エレメールが指摘する「二重社会」という社会構造にも反映されています。改革派は、市場調整の支配と計画の有機的な統一による「市場を土台とした社会主義経済」の確立を主張しました。
1. 1956年ハンガリー動乱後の改革 計画指令システムからの脱却
1956年のハンガリー動乱は、政治的にはスターリン批判、そしてソ連型経済管理システムへの批判でもありました。過度に集権的な計画指令システムからの脱却を目指し、カーダールの指導の下、9つの委員会が組織され、詳細な改革プログラムが作成されました。しかし、政治的・イデオロギー的理由から、このプログラムは日の目を見ることはありませんでした。一部は部分的な改革として実施され、農産物の強制供出の廃止と卸売商業化、工業企業の計画指標の削減、利潤分配制の導入、資産使用料の徴収などが挙げられます。これらの初期の改革は、計画経済の枠組みの中で、市場メカニズムの一部を取り込む試みと言えるでしょう。しかし、これらの改革は、ソ連型計画経済システムの根本的な問題点を解決するまでには至りませんでした。特に、投資配分における中央規制、コルナイが指摘する官僚調整の問題は依然として残っており、企業レベルでの投資決定は限定的なものでした。
2. 1968年経済改革 計画と市場の有機的関係の模索
1968年の経済改革は、義務的計画指令の廃止を目指しました。しかし、アンタル・ラースローらの改革派は、中央計画と市場の有機的関係の下での分権化された経済メカニズムの確立に成功しなかったと主張しています。代わりに導入されたのは、金融・財政規制、刺激、所得分配を重視した間接的経済管理システムでした。このシステムは、一見、分権的モデルと似ていますが、利潤に関する刺激は依然として細かく規制されており、中央からの指示や期待が企業に与えられていました。従来の計画交渉が、経済規制をめぐる交渉に変わったものの、企業の経済活動の内容に根本的な変化は生じなかったとアンタルは指摘しています。つまり、計画指令システムから間接的規制への変化は、表面的なものであり、目指した改革目標には到達できなかったという見解を示しています。この結果、ハンガリー経済は「二重経済」(dual economy) 構造、社会主義セクターと非社会主義セクターの共存という状態に陥りました。
3. 二重経済と二重社会 改革の現状と課題
ハンキシュ・エレメールは、ハンガリー社会を「二重社会」(dual society)と捉えています。これは、支配的な組織原則とは異なる原則によって統治される「第二社会」の存在を示唆しています。この「第二社会」は、経済だけでなく、公共、文化、社会組織、社会・政治相互作用など様々な領域に及んでいます。しかし、「第二社会」は、第一社会とは対立するポジティブな作用によるのではなく、第一社会の支配的な特徴を欠いているという点で特徴づけられています。例えば、垂直的構造への依存度が低いという点が挙げられますが、独自のネットワークを形成しているわけではありません。党中央委員会付属の経済作業委員会も、同様の現状認識に基づき、競争分野における社会主義市場経済原則の徹底、計画と市場の有機的な統一による改革の必要性を訴えています。しかし、市場が規制できない分野も存在することを認めており、計画と市場のバランスが課題となっています。さらに、本格的な資本市場形成に向けた動き(債券発行、商業銀行開設など)も述べられていますが、株式市場の復活など、課題は依然として残されています。
4. ビハリ ミハーイによる改革提案 新たな社会主義モデル
政治学者ビハリ・ミハーイは、ハンガリー社会の危機は、社会主義以前の遺産や外的影響ではなく、社会主義社会の再生産メカニズムそのものの構造、組織、制度、権力メカニズムの欠陥、民主的政治機構の欠如に起因すると指摘しています。この危機の解決には抜本的な改革が必要であり、社会主義か資本主義かという二項対立を超えて、どのような社会主義を目指すのかが重要だと主張しています。ビハリは、効率的な市場経済、民主的政治権力システム、そして歴史的に蓄積された人道的価値の尊重という三原則を備えた社会主義を提唱しています。これは、ハンガリー経済改革における計画と市場の統合、そして民主主義の深化が不可欠であることを示唆しています。多くの改革論者が同意する可能性のある条件を提示していますが、その実現方法こそが最大の課題であると結論付けられています。
III.ハンガリーにおける資本市場の発展と課題
改革過程において、ハンガリーでは徐々に資本市場が形成されていきました。債券発行に続き、株式市場の復活に向けた動きも見られます。しかし、完全な市場経済への移行には依然として課題が残っており、ビハリ・ミハーイは、効率的な市場経済、民主的な政治権力システム、そして人道的価値の尊重という三原則に基づく新たな社会主義モデルを提唱しています。これは、社会主義経済における計画と市場の最適なバランスを見つける必要性を示唆しています。
1. 資本市場形成に向けた段階的進展
ハンガリー経済改革においては、計画経済から市場経済への移行という大きな転換期において、資本市場の発展が重要な役割を果たしました。1983年には債券の発行が始まり、企業間の資本移動や商業銀行の開設など、本格的な資本市場の成立に向けた動きが着実に進展しました。企業の活動領域拡大や資本市場の発展は、経済の活性化に寄与する重要な要素でした。当初は「今日は債券、明日は株券、明後日は株式市場か」という冗談めいた表現が用いられていた株式市場も、経済組織が購入できる状態となっており、その実現が現実味を帯びてきました。この段階的な進展は、計画経済からの脱却と市場メカニズムの導入という改革の方向性を示しています。しかし、この発展は、計画経済の要素を完全に排除したわけではなく、依然として国家による規制や介入は存在していたと推察されます。債券や株券といった証券市場の発展は、市場経済の仕組みを導入する上で重要な一歩でしたが、同時に、既存の社会主義経済システムとの共存という複雑な状況が示唆されています。
2. 株式市場復活への動きと残された課題
1988年3月には、40年前に廃止された「株式市場」(tőzsdé)の復活を目指し、世界各国の経験を学ぶための株式市場会議が開催されるなど、本格的な株式市場の導入に向けた動きが加速しました。しかし、この時点でも株式の購入は経済組織に限定されており、完全な自由化には至っていません。これは、社会主義経済体制の下での市場導入が、段階的に、慎重に進められていたことを示しています。株式市場の形成を可能とする制度や活動形態(債券、株券、手形など)が既に存在していたことから、完全な株式市場の導入は時間の問題と見なされていた可能性があります。しかし、党と国の機関の役割分担、市場メカニズムの適切な範囲、そして社会主義経済と市場経済の統合方法などは、依然として重要な課題として残されていました。完全な市場経済への移行には、さらなる改革と制度整備が必要であったと推測されます。
3. 社会主義的市場経済 ビハリ ミハーイの提言
政治学者ビハリ・ミハーイは、ハンガリー社会全体の危機的状況を分析し、その原因を、社会主義体制固有の再生産メカニズム、構造、組織、制度、権力メカニズムの欠陥、そして民主主義の欠如にあると指摘しました。この危機の解決には、抜本的な改革が必要であると主張し、社会主義か資本主義かという単純な二項対立を超えた、新たな社会主義モデルの必要性を訴えています。ビハリは、効率的な市場経済、民主的な政治権力システム、そして歴史的に蓄積された人道的価値の尊重という三原則に基づいた社会主義を提唱しています。この提言は、資本市場の発展を単なる経済的な側面だけでなく、社会全体、政治システム、そして人道的価値と関連付けて考える必要性を強調しています。効率的な市場経済の導入と、民主主義の深化、人道的価値の尊重を同時に達成することが、真の改革、そして持続可能な社会主義の実現に繋がると主張していると言えるでしょう。しかし、これらの要素をどのように統合するかは、依然として大きな課題として残っています。
IV.社会主義計画経済の経済管理 理想と現実
論文では、マルクスの歴史理論に基づき、生産力の発展段階と商品交換の発展を分析することで、商品経済の衰退と社会主義計画経済の成立可能性を探っています。具体的な経済管理システムとして、中央計画局によるマクロ計画と、個々の生産単位の自主性を尊重した経済運営のモデルを提案しています。このモデルは、価格、資源配分、労働インセンティブ、消費などの要素をどのように調整するかを詳細に検討しており、公共財や自由財の役割も考慮しています。 しかし、理想的な社会主義計画経済を実現する上での困難さや、インセンティブ・コンパティビリティーの問題、外部経済効果への対応なども議論されています。
1. 社会主義計画経済の経済管理モデル 理想像
このセクションでは、社会主義計画経済における理想的な経済管理システムのモデルが提示されています。マルクスの歴史理論に基づき、生産力の発展と商品交換発展の観点から、商品経済の衰退と社会主義計画経済の成立可能性が議論されています。提示されているモデルでは、中央計画局がマクロ計画(投資、雇用、分配、科学技術、公共事業、環境、租税、財政など)の大枠を策定し、中央議会で承認を得るという仕組みです。中央計画局は、資源・エネルギー局、地方計画局、公的資金の融資機関などとの調整を行い、下部機関の自主性を尊重した大綱的で誘導的な計画を策定します。この計画に基づき、生産は消費者のニーズを反映し、計画の枠組みの中で行われ、「消費のための生産」という性格が強調されます。交換は、私的利益追求のための手段ではなく、社会的物質代謝過程を媒介する共同的行為となります。ただし、この理想的なシステムを実現するためには、十分な供給能力、需要構造に合致した供給構造、生産期間の短縮、高度な情報通信手段、迅速な意思決定機構などが不可欠であるとされています。消費者のニーズを的確に捉え、効率的に資源配分を行うことが、このモデルの根幹となっています。
2. 理想モデルにおける価格設定と評価システム
理想的な経済管理モデルでは、価格設定と評価システムが詳細に検討されています。標準労働時間、基本給与などの分配様式は中央議会が決定し、土地や資源の価格は政府が決定します。標準的な生産技術を持つ工場が、利潤ゼロとなるように価格を設定し、生産技術の格差から生じる剰余金は産業管理委員会が分配します。投資費用は価格に転嫁されます。公共サービスは、基礎的なものは自由財として提供され、選択的なものは有料となる場合があります。環境税などの間接税や、累進課税なども検討されています。小売や卸売業者は、一定のマージンを設定することが認められ、中央流通局が規制します。このシステム全体を支えるのは、徹底的な監査システム、情報公開、そして国民の審査権の保証です。このシステムでは、市場メカニズムを完全に否定するのではなく、計画経済と市場経済の要素を組み合わせ、効率性と平等性を両立させようとする試みが見て取れます。しかし、このシステムは、高度な情報処理能力と、国民全体の協力、そして透明性ある行政運営を前提としており、実現には多くの困難が伴うことが予想されます。
3. 社会主義計画経済の現実と課題 インセンティブと共同性
このセクションでは、社会主義計画経済の現実的な問題点、特にインセンティブと共同性の問題が取り上げられています。マルクスの歴史理論に基づいた社会主義論は、社会主義経済の具体的な運営方法や計画化、政治制度などについては、一般的な命題しか示しておらず、ソ連型の集権的な計画経済が様々な弊害や不効率を生み出した事実を踏まえています。ミゼスやハイエクは、集権的計画経済を全体主義と同一視し、その不効率性を指摘しました。これに対し、ランゲやブルスは、分権的・市場的社会主義計画経済を提唱しましたが、その後ハンガリーなどの経験から、分権的市場モデルにも批判が出てきました。社会主義は市場経済の否定の上に成り立つべきなのに、市場メカニズムを取り入れることへの矛盾や、インセンティブ・コンパティビリティの問題、功利主義的な人間像の限界が指摘されています。この問題は、外部経済効果に関心の無い非共同的な人間像を前提とした功利主義的モデルでは解決できず、より多元的な評価体系を持つ共同的な人間行動様式、そして社会的合意に基づくマクロ計画の形成が不可欠であることを示唆しています。このセクションでは、社会主義が将来、商品経済を克服できるかという、非常に困難な問題提起が行われています。
