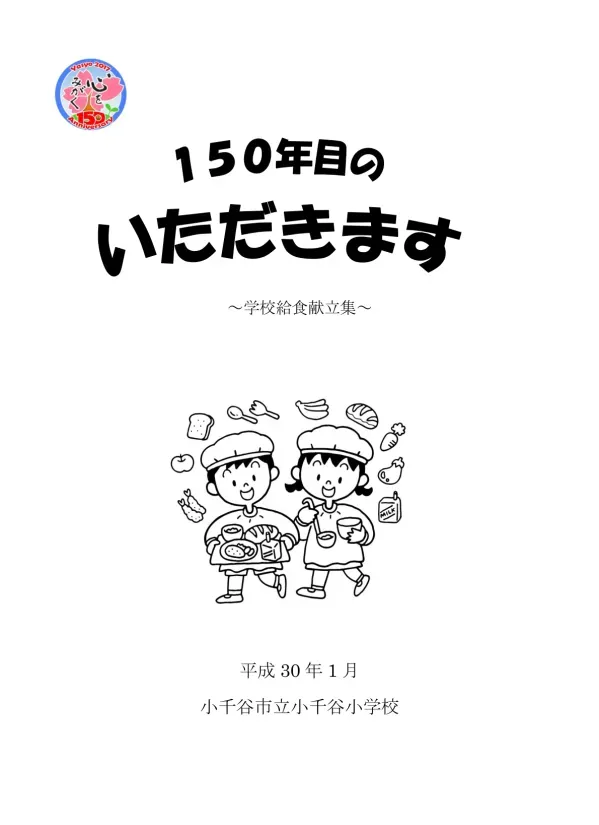
給食レシピ集:簡単主菜副菜
文書情報
| 学校 | 小千谷市立小千谷小学校 |
| 専攻 | 学校給食 |
| 出版年 | 平成30年(2018年) |
| 場所 | 小千谷市 |
| 文書タイプ | 献立集 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.57 MB |
概要
I.小千谷小学校の人気給食レシピ集 簡単で美味しい子供向けメニュー
このレシピ集は、新潟県小千谷小学校で長年愛されてきた人気給食メニューをまとめたものです。【簡単レシピ】を多く掲載しており、家庭でも手軽に作れる【子供向けレシピ】が満載です。魚料理、肉料理、野菜料理など、バランスの良い献立が豊富で、郷土料理も紹介しています。特に、揚げ物料理(揚げる)や煮物料理(煮る)が多く、170~180度の油で揚げる料理が多数登場します。 鮭のみそマヨ焼き、梅じゃこごはん、ひじきツナ佃煮など、子どもたちに人気の定番メニューから、とりのレモンあえ(燕市吉田地区のB級グルメ)など、地域色豊かな料理まで幅広く網羅。忙しいお母さんにも役立つ、時短調理に最適な小学校給食のレシピです。昭和7年開設の小千谷小学校は、今年で開校150周年を迎えました。長年に渡り地域に貢献する給食を通して、食育の重要性を再確認できます。
1. 揚げ物料理
このレシピ集には、様々な揚げ物料理が掲載されています。定番のカツレツは、鶏肉、椎茸、人参、筍などを煮込んだ具材を使用し、パン粉を付けて170~180度の油で揚げます。タレは、調味料を煮詰めて作り、揚げたてのカツに絡めてご飯にのせて提供されます。給食では、タレにバターを加えることでまろやかな風味に仕上げている点が特徴です。他に、高野豆腐を片栗粉でまぶして揚げる料理や、カレイを二度揚げするなど、様々な揚げ方、食材の組み合わせが紹介されています。 170~180度という揚げ油の温度は、多くのレシピで共通しており、カリッとした食感を出すためのポイントとなっています。また、さんまのかば焼きは、焼くだけでなく揚げる方法も紹介されており、カリカリとした食感を好む子供たちにも人気です。素揚げした野菜や、鶏肉、豚レバーなどを組み合わせた、彩り豊かな揚げ物料理も含まれています。揚げ物の調理においては、揚げ時間を調整することで、食材の食感や状態をコントロールするコツも解説されています。
2. 煮物料理
煮物料理は、様々な食材と調味料を組み合わせ、じっくり煮込んだ家庭料理が中心です。鶏肉と野菜を煮込んだ料理は、シンプルな味付けながらも、野菜の甘みと鶏肉の旨みが調和した、子供にも受け入れやすい一品となっています。ひじきツナ佃煮は、ひじきの食物繊維とカルシウムを摂取できる栄養価の高い料理で、小女子、アーモンド、ゴマの香ばしい風味と、甘じょっぱい味付けが食欲をそそります。さばの煮付けは、青魚特有のDHAやEPAが豊富で、健康にも良いとされるメニューです。落とし蓋を使用することで、食材に均一に味が染み込み、ふっくらと仕上がります。また、調味料をさっと煮立たせて作る簡単なタレは、様々な料理に活用できます。 電子レンジでの調理も可能であり、時間短縮にも繋がります。これらの煮物料理は、日本の家庭料理の基本を学ぶ上で非常に有効なレシピです。 子供たちが喜んで食べることを考慮した、工夫された味付けや調理法が特徴です。
3. その他の料理と郷土料理
このレシピ集には、揚げ物や煮物以外にも、様々な調理法の料理が掲載されています。焼き物として、さんまのかば焼きは、片栗粉をまぶして焼くことで、カリッとした食感が楽しめます。また、調味料を絡めることで、風味豊かに仕上がります。炒め物では、炒り大豆を使ったご飯や、豚肉と様々な野菜を炒めた料理など、シンプルながらも栄養満点なメニューが紹介されています。和え物では、梅干しと鰹節を組み合わせた和え物や、糸瓜を使ったごま酢和えなど、子供たちが好む工夫が凝らされています。 さらに、小千谷地域の郷土料理も紹介されており、地域の食文化を学ぶことができます。例えば、燕市吉田地区でB級グルメとして人気のある「とりのレモンあえ」は、給食から生まれた料理で、レモンのさわやかな風味と鶏肉の組み合わせが絶妙です。 これらの料理は、子供たちがバランスの良い食事を摂る上で重要な役割を果たしており、家庭でも簡単に作れるレシピとして役立ちます。
II.カテゴリー別レシピ概要 和食 洋食 揚げ物など
レシピは、和食中心ですが、洋食風のメニューも含まれています。主食は米飯給食が中心です。調理方法は、揚げる、煮る、焼く、炒めるなど様々で、食材も魚介類、肉類、野菜など多岐に渡ります。 各レシピは簡潔な手順で記述され、家庭で再現しやすいように工夫されています。 例えば、揚げ物料理では、多くのレシピで170~180度の油温度が指定されています。また、電子レンジ調理も活用することで、調理時間を短縮する工夫が見られます。 給食レシピとして、栄養バランスと子供たちの嗜好性を考慮した献立となっています。
1. 和食中心の献立
このレシピ集に掲載されている料理の多くは、日本の伝統的な和食です。ご飯を主食とした献立が多く、煮物、焼き物、揚げ物など、様々な調理法の料理がバランス良く含まれています。 例えば、梅じゃこご飯は、カリカリとした梅と小魚、炒り大豆の食感が楽しい、夏にぴったりのご飯です。ひじきツナ佃煮は、ひじきの栄養価の高さに加え、ツナの旨味と小魚、アーモンド、胡麻の香ばしさが食欲をそそる一品。鮭のみそマヨ焼きは、簡単に作れる定番メニューで、子供達にも人気の高い料理です。 これらの和食メニューは、日本の食文化を学ぶ上で重要な役割を果たしており、子供達にも親しみやすい味付けが特徴です。 また、郷土料理である「とりのレモンあえ」も掲載されており、地域の食文化を知る上でも貴重な資料となっています。これらの料理は、家庭でも簡単に作れるよう、分かりやすい手順で説明されています。
2. 揚げ物料理の多様性
このレシピ集では、揚げ物料理が非常に多く掲載されています。 カツレツ、高野豆腐、カレイ、鶏肉など、様々な食材を170~180度の高温で揚げる調理法が中心となっています。二度揚げすることで、カレイは骨まで食べられるほどカリッと仕上がります。一方、高野豆腐は揚げすぎるとスポンジ状になるため、適切な揚げ時間のコツが説明されています。 また、さんまのかば焼きは焼くだけでなく揚げる方法も提案されており、カリカリとした食感が楽しめる点が強調されています。ツナぎょうざは、サクッとした食感が魅力で、包んだらすぐに揚げることで、中から水分が出てくるのを防ぐ工夫が説明されています。このように、様々な食材と揚げ方のバリエーションが豊富で、子供たちの好みに合わせた調理法が提案されています。揚げ物料理は、子供たちに人気のあるメニューの一つであることがうかがえます。
3. 洋風料理とその他
和食が中心ではありますが、洋風テイストの料理もいくつか含まれています。例えば、パンプキンスープは、かぼちゃの甘みが口の中に広がる、子供たちに人気のメニューです。クリームコーンを加えることで、より濃厚な味わいに仕上がります。 また、ミートソースは、ひき肉、玉ねぎ、にんじんを炒めて作るシンプルなレシピで、子供にも食べやすい味付けとなっています。 その他、電子レンジを活用した調理法や、簡単に作れるサラダ、和え物なども掲載されています。 これらのレシピは、家庭で手軽に作れるように工夫されており、忙しいお母さんにも役立つ内容となっています。 子供たちの食生活の幅を広げる上で、和食だけでなく洋風料理や簡便な調理法の料理も取り入れることが重要であることを示唆しています。
III.小千谷小学校給食の歴史と食育
小千谷小学校の給食は昭和7年、お弁当を持参できない児童のために始まりました。地元住民の協力のもと提供されてきた給食は、80年以上もの間、子どもたちの健やかな成長を支え、正しい食習慣の育成に貢献してきました。現在ではリクエスト献立やセレクト献立を取り入れるなど、多様化が進み、郷土料理や地産地消の食材も積極的に活用されています。開校150周年を記念して発行されたこのレシピ集は、その歴史と食育への取り組みを象徴するものです。 小学校給食の歴史と食育の重要性が、このレシピ集を通して伝わってきます。
1. 小千谷小学校給食の始まりと地域貢献
小千谷小学校の給食は、昭和7年、お弁当を持参できない児童のために始まりました。当初は、地域住民の方々が米を栽培し寄付するなど、多くの協力によって支えられていました。このことは、給食が単なる食事提供ではなく、地域全体で子供たちの健やかな成長を願う取り組みであったことを示しています。 80年以上を経た現在も、当時の地域住民の思いを引き継ぎ、子供たちの健康な体作りと正しい食習慣の育成を目指した給食運営が続けられています。 このレシピ集の発行は、地域住民の協力の歴史と、長年にわたる食育への取り組みを象徴する出来事です。 地域住民の温かい支援と、学校側の継続的な努力が、小千谷小学校の給食を支えていることが分かります。
2. 給食を通じた食育の変遷と現状
昭和42年には脱脂粉乳から牛乳への切り替え、昭和43年にはソフト麺の導入など、時代の変化とともに給食の内容も進化してきました。昭和53年には米飯給食が開始され、現代ではリクエスト献立やセレクト献立など、子供たちのニーズに合わせた多様なメニューを提供できるようになりました。 近年では、給食を通じた食育の重要性がますます高まり、郷土料理や地産地消の食材を取り入れるなど、食文化の継承と地域社会との連携が強化されています。 この変化は、子供たちの健康増進と食に関する知識・理解を深めるための教育的側面が、給食において重視されていることを示しています。 食育は、単に栄養バランスの良い食事を提供するだけでなく、食への関心を高め、正しい食習慣を身につけることを目的としていることがわかります。
3. 開校150周年記念レシピ集の意義
小千谷小学校は、今年度開校150周年を迎えました。このレシピ集は、150年の歴史の中で培われてきた食育に対する保護者や地域住民の理解と協力への感謝の気持ち、そしてその歴史を未来へ繋ぐための取り組みとして発行されました。 掲載されているレシピは、小千谷小学校の給食の中でも特に人気のあるメニューや、家庭で簡単に作れるメニューが厳選されています。 このレシピ集を通して、学校給食で作られている料理を家庭で再現することで、子供たちは給食で学んだことを日常生活に活かすことができます。また、保護者も給食の取り組みを理解し、家庭での食育に役立てることができます。 レシピ集は、学校と家庭、そして地域社会を繋ぐ役割を果たし、小千谷小学校の食育の取り組みの継続と発展に寄与することが期待されます。
