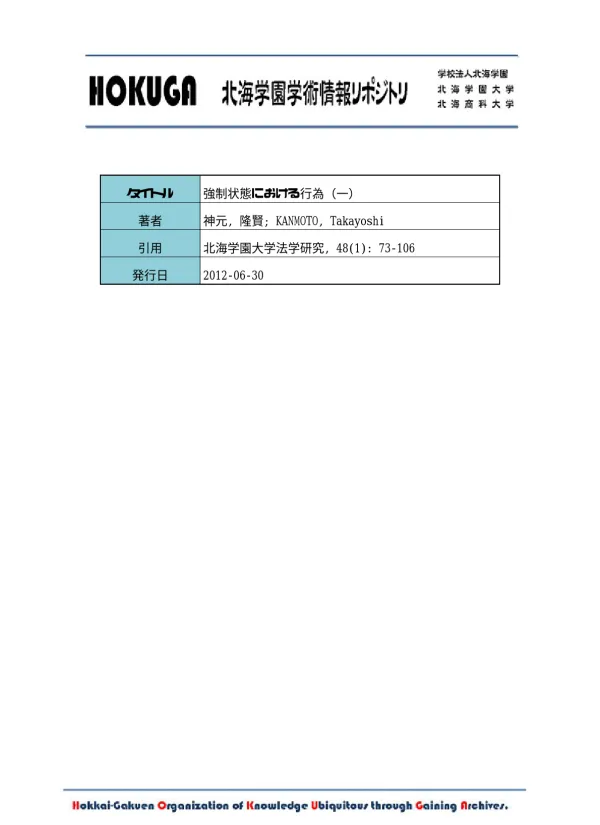
緊急避難と強制状態:違法性阻却の検討
文書情報
| 学校 | 北研 (Hokuken) |
| 専攻 | 法学 (Law) |
| 出版年 | 平成八年 (1996) |
| 場所 | 東京 (Tokyo) |
| 文書タイプ | 判例解説 (Case Commentary) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 593.29 KB |
概要
I.オウム真理教関連事件における緊急避難と期待可能性
この判決は、オウム真理教関連事件における被告人の行為が、緊急避難として認められるか否かを検討したものです。具体的には、教団施設内で脅迫を受け、協力者を殺害した被告人の責任能力について、脅迫(kyōhaku)の状態下での行為の違法阻却(ihō sokyaku)、**責任阻却(sekinin sokyaku)の成否が争点となりました。特に、被告人が他の適法な行動(期待可能性、kitai kanōsei)**をとることが可能であったか否かが重要な論点となっています。判決は、被告人の置かれた状況を詳細に検討した上で、緊急避難を認めず有罪判決を下しました。
1. 緊急避難の主張と棄却
本件は、オウム真理教信者である被告人が、教団施設内で教祖からの脅迫(「できなければお前を殺す」)の下、協力者を殺害した事件に関するものです。被告人は、自身の生命・身体に対する現在の危難を回避するためやむを得ず行った行為として、緊急避難を主張しました。しかし、判決は、この主張を退けました。判決は、被告人の供述内容を精査し、自己の生命・身体に対する現在の危難を回避するためにやむを得ず行った行為であるという緊急避難の成立要件を満たしていないと判断しました。具体的には、他の回避可能な方法が存在した可能性、つまり期待可能性(kitai kanōsei)を否定できる証拠が不足している点などが理由として挙げられています。 判決は、脅迫を受けていたとはいえ、被告人が状況を脱する現実的な可能性を検討すべきであったと指摘しています。
2. 期待可能性の有無と緊急避難の要件
判決において、緊急避難が認められるためには、現在の危難を避けるため、他に現実的な回避方法が存在しなかったこと(期待可能性の欠如)が不可欠な要件となります。この事件においては、裁判所は被告人の行動について、他の現実的な回避方法があった可能性を検討しました。被告人が教団施設から脱出する、あるいは当局に助けを求めるなどの行動をとる可能性が検討されています。 判決は、被告人が置かれていた状況下においても、これらの行動をとることは十分に可能であったと判断しました。そのため、緊急避難の成立要件である「他に回避方法が存在しなかった」という点を満たしていないとして、被告人の緊急避難主張を退けました。この判断においては、被告人の主観的な心理状態だけでなく、客観的な状況証拠も考慮されています。
3. 脅迫と心理的圧力 責任阻却の可能性
被告人は、教祖からの脅迫により強い心理的圧力下に置かれていたと主張しました。この心理的圧力は、責任阻却(sekinin sokyaku)の根拠となりうる可能性がありました。しかし、裁判所は、脅迫の存在を認めながらも、それが緊急避難を成立させるほどの「現在の危難」を構成するとは認めませんでした。 判決では、被告人が教祖からの脅迫によって強い心理的圧迫を受けていたことは認めつつも、それでもなお、他の適法な行動をとることが可能な状況であったと判断しました。つまり、期待可能性(kitai kanōsei)が存在したと結論付けたのです。この判断は、脅迫の程度、被告人の状況、そして脱出の可能性など、複数の要素を総合的に考慮してなされたものと考えられます。単なる脅迫だけでは、緊急避難や責任阻却を認めるには不十分であると判断されたと言えます。
4. 具体的な状況証拠の検討と判決
判決は、被告人の行動に至るまでの具体的な状況証拠を詳細に検討しています。これは、緊急避難の成立要件である「現在の危難」と「期待可能性」の有無を判断する上で不可欠なプロセスでした。 例えば、被告人が教団施設から脱出できる機会があったか、当局に助けを求めることができたか、といった点について、具体的な証拠に基づいて検討が行われました。 裁判所は、これらの点を総合的に判断し、被告人が緊急避難状態にあったとは認めず、期待可能性(kitai kanōsei)を否定できませんでした。つまり、被告人は、違法行為に訴えることなく、自らの危険を回避できる他の手段があったと判断されたわけです。この詳細な状況証拠の検討が、最終的な判決に大きく影響を与えていることがわかります。
II.暴力団関係事件における強制と責任
複数の暴力団関係事件において、被告人が組長の命令に従って違法行為を行った場合の責任が問われています。これらの事件では、被告人が**強制状態(kyōsei jōtai)**下にあり、期待可能性(kitai kanōsei)が欠如していたか否かが争点となっています。判決は、被告人が暴力団から脱退する機会があったにも関わらず、それをしなかった点を重視し、緊急避難や責任阻却を認めず、有罪判決を下しました。被告人の置かれた状況と、適法な代替行動の可能性が詳細に分析されています。
1. 暴力団の強制力と違法行為
この判決では、暴力団員が組長の命令によって違法行為(例:銃器製造)に関与した場合の責任が問われています。被告人は、組長の命令に逆らえば報復を受けることを恐れ、強制的に違法行為に加担したと主張しました。この主張は、強制状態(kyōsei jōtai)下での行為であり、責任を問われるべきではないという責任阻却(sekinin sokyaku)の主張と捉えることができます。判決は、暴力団の威圧的な状況を認めつつも、被告人が常に組長の命令に従わざるを得ない状態にあったとは判断しませんでした。 具体的には、被告人が暴力団事務所や犯罪現場から逃れる時間的、物理的な余裕があった可能性、もしくは警察に通報するなどの他の選択肢があった可能性が指摘されています。 つまり、期待可能性(kitai kanōsei)が否定できないと判断されたのです。
2. 期待可能性の検討 逃亡 通報の可能性
判決は、被告人の「期待可能性(kitai kanōsei)」、すなわち、違法行為以外の法的・現実的な回避手段があった可能性について詳細に検討しています。 具体的には、被告人が暴力団事務所や犯罪現場から離脱し、本件犯罪の実行を回避する時間的余裕または可能性があったのか、また警察に通報して保護を求めることができたのかどうかが検討されました。 判決は、これらの可能性を否定できず、被告人が違法行為を回避する現実的な選択肢を持っていたと結論付けました。この結論は、被告人が暴力団の威圧的な状況下におかれていたとしても、完全に自由を奪われていたわけではないという判断に基づいています。従って、責任阻却を認めるには至らなかったと判断されたのです。
3. 強制状態と責任の関連性 客観的状況の評価
本件では、暴力団による強制状態(kyōsei jōtai)が被告人の責任を阻却できるかという点が争点となっています。 判決は、被告人が暴力団の組長や幹部からの命令に従わざるを得ない状況にあったことをある程度認めたものの、それだけで責任を免れることはできないと判断しました。 判決は、被告人の主観的な恐怖や不安だけでなく、客観的な状況証拠も重視して検討されています。具体的には、被告人が暴力団事務所や犯罪現場から離脱する機会があったかどうか、警察に通報する可能性があったかどうかといった客観的な要素が、責任の有無を判断する上で重要な要素として考慮されています。 つまり、単なる強制状態だけでは責任阻却を認めず、客観的に見て他の法的・現実的な選択肢があったかどうかの検討が不可欠であると判断されたと言えるでしょう。
4. 犯罪の重大性と回避義務
判決は、犯罪の重大性と、配下組員としての被告人の回避義務のバランスについても言及しています。 具体的には、もし犯罪行為がより重大なものであればあるほど、配下組員である被告人は、その実行を回避する義務がより大きくなるとされています。 この点は、被告人が暴力団の命令に従わざるを得なかったという主張に対して、犯罪の性質と被告人の立場を考慮して判断がなされていることを示しています。 判決は、被告人が犯罪行為を回避するための時間的余裕や現実的な選択肢を持っていたと判断し、その結果、責任阻却を認めず、有罪判決に至ったと考えられます。
III.心理的束縛と身体的危険 緊急避難の要件
本判決では、心理的束縛下での行為が緊急避難(kin'kyū hinan)に該当するか否かが重要な争点となっています。被告人が加害者からの脅迫(kyōhaku)や暴行を受け、身体的自由を脅かされていた状況下での行為について、**現在の危難(現在性の有無)が存在したか、そして、他の適法な回避手段(期待可能性、kitai kanōsei)**があったか否かが検討されました。判決は、被告人が自力で危険な状況から脱出できる可能性があったと判断し、緊急避難を認めませんでした。
1. 心理的束縛と身体的危険の現状
この判決で扱われるケースでは、被告人は心理的束縛と身体的危険の両方を受けていたと主張しています。具体的には、脅迫や暴行といった直接的な身体的危険に加え、加害者からの継続的な支配や監視による心理的圧力も存在していた可能性が示唆されています。判決は、このような心理的束縛と身体的危険の程度、そしてそれらが緊急避難(kin'kyū hinan)を認めるに足る「現在の危難」を構成するかどうかを詳細に検討しています。過去に暴行を受けていた事実や、将来的な暴行の再開可能性も考慮されていますが、それだけでは現在の危難を満たすと断定するには至らなかったと推察できます。
2. 緊急避難の成立要件 現在の危難と期待可能性
緊急避難が認められるためには、「現在の危難」と「期待可能性(kitai kanōsei)」の両方の要件を満たす必要があります。「現在の危難」とは、直ちに生命・身体に危険が迫っている状況を指し、「期待可能性」とは、違法行為以外の、危険を回避するための現実的な方法が存在しなかったことを意味します。判決では、被告人の置かれた状況において、これらの要件が満たされているかどうかが厳しく審査されています。 被告人が加害者から脱出する可能性や、当局に助けを求めることができた可能性などが検討され、それらの可能性を否定できないと判断したと推測されます。つまり、期待可能性(kitai kanōsei)が認められたため、緊急避難は成立しないと結論付けられたのです。
3. 他の法的 現実的な回避手段の存在可能性
判決は、被告人が違法行為に訴えることなく、自らの危険を回避できる他の現実的な手段を持っていた可能性について、詳細な検討を行っています。これは、緊急避難の成立要件である「期待可能性(kitai kanōsei)」の有無を判断する上で非常に重要な要素です。 具体的には、被告人が加害者との関係を断ち切る、あるいは警察や他の関係機関に通報するなどの行動をとる可能性が検討されました。 これらの行動をとることは、被告人の心理状態や状況を考慮しても、十分に可能であったと判断されたと推測されます。 そのため、緊急避難を認めるには至らなかったと結論付けられています。
4. 心理的束縛と客観的状況のバランス
判決においては、被告人の心理的束縛の程度と客観的な状況証拠が総合的に評価されています。単に被告人が心理的に強い圧力を感じていたというだけでは、緊急避難を認めるには不十分であると判断されたと考えられます。 判決は、被告人の主観的な心理状態と、客観的に見て他の回避手段があった可能性を慎重に比較検討した結果、緊急避難の要件を満たしていないと結論付けたものと推測されます。 つまり、心理的圧力や脅迫の存在は考慮されたものの、それらを上回る客観的な脱出・回避の可能性が認められたため、緊急避難は認められなかったと解釈できます。
