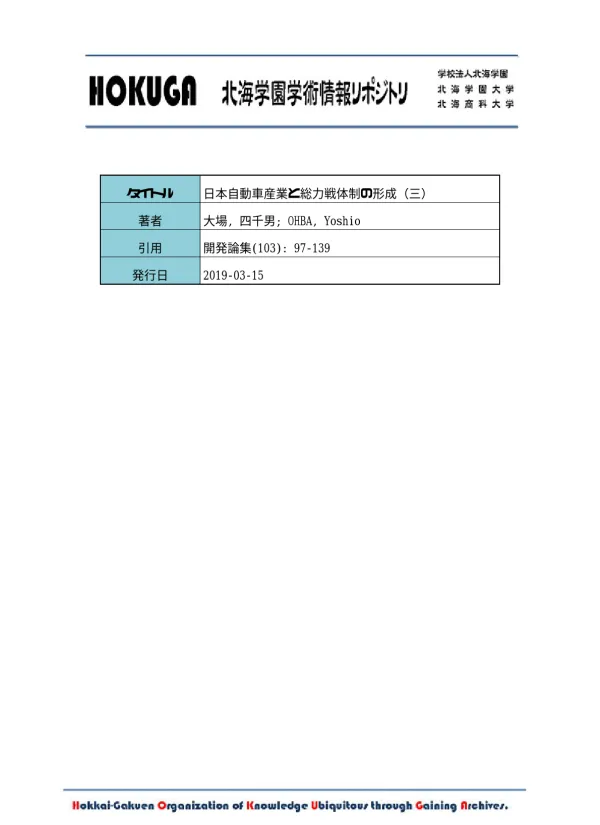
総力戦と日本自動車産業:大衆車構想から軍需へ
文書情報
| 著者 | 大場 四千男 |
| 専攻 | 歴史学、経済学、または日本近現代史 |
| 文書タイプ | 論文または紀要掲載論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.96 MB |
概要
I.満州支配と日米関係 日露戦争後の満鉄と国家経済主義
日露戦争後の【ポーツマス条約】により日本が獲得した南満州鉄道(【満鉄】)は、国家経済主義に基づく【満州】経営の中核となった。児玉源太郎大将は既に日露戦争前から満州経営をイギリス東インド会社になぞらえ、その戦略的価値を認識していた。満鉄は鉄道事業だけでなく、撫順炭鉱などの経営も手がけ、コンツェルン化することで【満州経済】の自立を目指した。しかし、この【満州】における日本の優越的地位は、アメリカ合衆国など列強からの反発を招き、日米関係を複雑化させた。特にアメリカは、ハリマンによる満鉄買収策を支援するなど、日本の【満州支配】を牽制しようとした。
1. 日露戦争後の満州経営 児玉源太郎と東印度会社モデル
日露戦争後、満州の帰属は日本の生命線として認識され、その後の大東亜戦争、太平洋戦争へと繋がる重要な転換点となります。この節では、特に児玉源太郎大将の満州経営への関与に焦点を当てています。 鶴見祐輔の『後藤新平伝』からの引用が示すように、児玉大将は既に日露戦争当時から、イギリス東インド会社のインド植民地経営をモデルとして満州経営を構想していたことが示唆されています。これは、イギリスがインド支配において重商主義政策を軸に、インドをイギリス製品の市場とし、本国との貿易を経済成長の原動力とした戦略と類似しています。東インド会社は三角貿易(イギリス→インド→中国)を推進し、軍事力と地租改正による地主制確立によってインド支配を強化しました。このイギリスの成功例を踏まえ、児玉大将は満州における同様の戦略を想定していたと推測できます。この戦略的思考が、後の満州における日本の国家経済主義に基づく政策に影響を与えたと考えられます。 ただし、この節では、具体的な政策やその後の展開には触れられておらず、児玉大将の戦略的思考を理解するための、重要な導入部となっています。
2. ポーツマス条約と満鉄 国策私営鉄道と国家経済主義
ポーツマス条約により日本がロシアから譲り受けた東清鉄道南部線、すなわち南満州鉄道(満鉄)は、文書において重要な役割を担っています。条約第7条で満鉄は「軍略の目的を以て之経営せざること」と規定されながらも、実際には国策私営鉄道として位置づけられ、国家経済主義に基づく経営が行われました。満鉄は長春から旅順口間の鉄道とその支線、さらに撫順炭鉱を含むコンツェルン形態として発足し、満州における日本の経済的支配を強固なものにしました。この満鉄の設立と運営は、日本の満州における植民地経営、そして国家経済主義を象徴する出来事として位置付けられます。この節では、満鉄の設立経緯と、その国家経済主義に基づく経営形態が詳細に説明されており、満州における日本の経済的支配の基盤を理解する上で重要な情報が含まれています。特に、満鉄が単なる鉄道会社ではなく、炭鉱経営なども含む巨大なコンツェルンであった点が強調されています。
3. ハリマンと満鉄買収計画 日米経済摩擦の始まり
アメリカの鉄道王ハリマンによる満鉄買収計画は、日米関係における経済摩擦の始まりを象徴する出来事です。日本政府は、ポーツマス条約後、満鉄の経営に苦慮しており、一時、ハリマンに満鉄を売却する内約を結んだこともありました。しかし、小村寿太郎外相の反対により、この契約は破棄されました。この出来事は、日本が満州における経済的支配を維持しようとする一方で、アメリカがその支配に挑戦しようとしたことを示しています。ハリマンの計画は、世界横断鉄道構想の一環として、満州におけるアメリカの経済的影響力を拡大しようとする試みでもありました。この節では、ハリマンの満鉄買収計画と、それを巡る日本政府内部の葛藤、そして小村寿太郎外相による強硬な反対によって契約が破棄されたことが詳細に記されています。これは、満州における日本の経済的支配と、アメリカ合衆国の対抗策という構図を理解する上で重要な要素です。ハリマンの計画は、単なる経済的な問題ではなく、日米関係の将来に大きな影響を与える地政学的要素を孕んでいたことを示しています。
4. 米国の満州鉄道中立提議と日本の対応 機会均等主義と国家経済主義の対立
この節では、アメリカの満州鉄道中立提議とその後の日本の対応が詳細に記されています。アメリカは、満州における鉄道を列国共同事業とし、門戸開放・機会均等を主張しました。これは、日本の満鉄による支配を弱体化させ、アメリカを含む諸外国の経済的影響力を拡大しようとする試みでした。しかし、日本政府は、この提議を拒否しました。その理由は、満州における日本の経済的利益、そして日本の安全保障上の懸念に基づいていました。日本政府は、満鉄を国家経済主義に基づき運営し、満州の開発・発展を自国の利益のために活用しようとしていました。アメリカ合衆国の機会均等主義と、日本の国家経済主義は、満州問題において直接的に対立する立場にあったことがわかります。この節では、アメリカ大使オブライエンと小村外相間の書簡を通して、両国の立場と主張が明確に示されています。 この対立が、後の日米関係悪化へと繋がっていく重要な局面であることが理解できます。
II.対支二十一条と山東問題 日中関係と国際批判
第一次世界大戦中、日本は【対支二十一条】を突きつけ、山東省における利権獲得を図った。この強硬姿勢は国際社会から激しい批判を浴び、アメリカからは【日本帝国主義】の侵略行為と見なされた。【二十一条】は満鉄の租借権延長や日本の優越的地位の確立などを目的としたが、山東問題に関しては、パリ講和会議やワシントン会議で最終的に中国への返還が決まり、日本の特殊権益は否定された。この山東問題における日中対立は、日米関係悪化の大きな要因となった。
III.西原借款と日支経済協力 日支親善と国家経済主義
西原亀三による【西原借款】は、日中経済協力と日支親善を目的とした政策であった。借款は中国の経済発展に貢献すると同時に、日本の経済成長にも寄与することを目指した。鉄道整備や産業発展への投資は、【国家経済主義】の下、日本政府の主導で行われ、東亜経済圏構想の一環として位置づけられた。しかし、この政策も、アメリカによる中国支援と日本の【満州】政策への批判と相まって、日米関係の悪化を阻止するに至らなかった。
1. 西原借款の目的 日支親善と経済協力
西原借款は、第一次世界大戦期に西原亀三によって推進された日中経済協力政策の中核をなすものでした。その目的は、単なる資金援助にとどまらず、日中両国の経済的結びつきを強め、ひいては日支親善を促進することにありました。西原亀三の掲げた「東亜民族の康寧福祉」論は、この政策の理念的基盤であり、中国の資源を日本の企業によって加工・輸出することで、両国の富国強兵を図り、最終的には東アジア全体の繁栄を目指すという壮大な構想が背景にあります。この政策は、交通銀行への融資や鉄道借款などを含み、中国経済の近代化と発展に貢献することを目指していました。 西原借款は、大蔵省と三大銀行(朝銀、台銀、横銀)を介して実施され、その規模は1億4000万円に達しました。これは、当時の日本経済規模からすれば相当な額であり、国家主導による経済政策の強力な推進力を示しています。また、中国側の経済構造においては、交通銀行の日支貨幣混一併用制度を下部構造とし、鉄道の効率化を媒介とした経済好循環を目指した点が特徴的です。
2. 西原借款と国家経済主義 国家主導の経済発展
西原借款は、単なる民間投資ではなく、国家経済主義に基づく国家主導の経済政策として推進されました。 借款の大部分は、中国への融資として活用され、鉄道建設や産業発展などのプロジェクトに投入されました。これは、日本の経済的影響力を中国に拡大し、自国の経済的利益を追求する戦略と同時に、日中間の経済的結びつきを強化することで、政治的安定をもたらすという狙いがあったと考えられます。 この国家経済主義に基づくアプローチは、満州における南満州鉄道(満鉄)の経営と同様の側面を持っており、国家が積極的に経済活動を主導し、その発展をコントロールしようとする姿勢が見て取れます。 西原借款は、第一次世界大戦という特殊な状況下で、日本の経済的・地政学的目標を達成するための重要な手段として活用されました。その成功は、日本の経済的台頭を促進し、東アジアにおける日本の影響力を高めるという、国家的な目標と密接に関連しています。
3. 山東問題と西原借款 日支親善と国際関係
山東問題は、西原借款と密接に関連する重要な問題でした。西原亀三は、山東問題の解決を日支親善の重要な鍵と捉え、青島港を日中両海軍の共同軍港とする提案を行いました。これは、山東鉄道の延長による欧州への直通鉄道構想と組み合わさり、東アジアの発展に貢献するという、日支協力に基づく構想でした。この提案は、中国の国務総理段祺瑞とも共通認識として共有されていました。しかし、日本国内においては、山東省における日本の優越権を重視する立場も存在し、西原亀三の提案は必ずしも容易に受け入れられるものではありませんでした。 この山東問題をめぐる日中の対立は、アメリカ合衆国を含めた国際関係にも影響を与え、最終的にはパリ講和会議やワシントン会議での議論へと発展することになります。 西原亀三の提案は、日支親善を促進し、東アジアの平和と繁栄をもたらすという理想に基づいていましたが、その実現には、日本国内の政治的思惑や、アメリカ合衆国の介入といった様々な障害が立ちはだかっていたことを示しています。
4. 未実現の計画と日支経済協力の限界 国営製鉄廠借款と日米関係
西原借款以外にも、中国における国営製鉄廠借款などの計画がありましたが、様々な要因により実現に至らなかったことが記されています。 国営製鉄廠借款は、東洋における鉄の自給を目指したものでしたが、大倉組や林公使の反対、中国国内の政治的混乱、そして日本側の自国本位な要求などにより、最終的に頓挫しました。 さらに、団匪賠償金還付や中国の関税引上、幣政改革など、日中経済協力のために必要な様々な協定が、完全な実現に至らなかったことも記されています。これらの未解決事項は、西原亀三が目指した日支親善と経済協力という理想に、大きな影を落としました。 これらの未実現の計画は、日中経済協力の難しさ、そして日本政府内部の様々な思惑や、国際的な政治情勢がいかに日中関係に影響を与えていたかを浮き彫りにしています。これらの未達成事項は、結果的に日中関係の悪化と、大東亜戦争への道を辿る一因となったと考えられます。
IV.主要人物と組織
この文書には、以下の重要な人物と組織が登場します。【児玉源太郎】大将、【後藤新平】(満鉄総裁)、【小村寿太郎】、【大隈重信】、【加藤高明】、【西原亀三】、南満州鉄道(【満鉄】)、アメリカ合衆国政府、ハリマン(アメリカ鉄道王)、交通銀行。これらの関係者や組織の行動と政策が、【満州】問題と日米関係に大きな影響を与えた。
1. 西原亀三 日支親善と東亜経済圏構想の提唱者
西原亀三は、日支親善を基軸とした経済政策、特に西原借款を推進した中心人物です。彼の経済思想は「東亜民族の康寧福祉」論に集約され、中国の資源開発と日本の工業力を組み合わせることで、日中両国の発展、ひいては東アジア全体の繁栄を目指すものでした。西原借款は、この理念に基づき、中国への多額の融資を通して、鉄道建設や産業発展を支援するものでした。西原借款は、中国における日本の経済的影響力の拡大を狙う一方で、日中間の経済的協調を通じて、政治的安定と親善関係の構築を目指すという、複雑な目的を持っていました。彼の政策は、交通銀行の改革や日支貨幣混一併用の構想も含まれており、中国経済に深く関与しようとする日本政府の姿勢を象徴しています。 しかし、彼の計画は常に日本国内の政治的思惑や、アメリカ合衆国の対中政策という国際情勢に影響を受け、その実現は困難を極めました。西原亀三の行動と思想は、この時代の日本外交を理解する上で重要な視点となります。
2. 後藤新平 満鉄総裁と国家経済主義
後藤新平は満鉄総裁として、満州における日本の経済的支配を確立する上で重要な役割を果たしました。彼は、十ヶ年計画に基づき、満鉄を鉄道・炭鉱事業を両輪とする巨大コンツェルンへと発展させました。これは、国家経済主義に基づく政策の典型例であり、満州経済の自立と日本の経済的利益を追求するものでした。後藤新平の満州経営は、北海道開拓使による幌内炭鉱鉄道の成功例を参考にされ、鉄道と炭鉱の連携による経済発展が目指されました。彼の政策は、満州の経済的発展に貢献しましたが、同時に、日本の満州支配を強化し、アメリカや他の列強からの反発を招く要因ともなりました。後藤新平は、満州における日本の政策における国家経済主義の強力な推進者であり、彼の功績と責任は、この時代の歴史における重要なテーマとなります。彼の十ヶ年計画の成功は、満州経済の自立化に貢献した一方で、日本が満州を自国の生命線として捉え、その支配を維持しようとしたことを物語っています。
3. 小村寿太郎 対米外交と保守的な立場
小村寿太郎は、日本の対外政策、特にアメリカ合衆国との関係において、保守的な立場を堅持した人物として描かれています。 彼は、ハリマンによる満鉄買収計画に強く反対し、その契約破棄に尽力しました。また、満州における門戸開放や機会均等主義にも否定的であったと考えられます。彼のこうした姿勢は、日本の国家経済主義に基づく満州支配を維持しようとする意図と関連しており、アメリカ合衆国との摩擦を招く要因にもなりました。小村寿太郎の政策は、日本の国家利益の優先を重視するものでしたが、結果的に、国際的な批判を招き、アメリカとの関係悪化の一因ともなりました。彼の保守的な姿勢は、日本政府内部における対米政策をめぐる様々な意見の対立を浮き彫りにする上で重要な要素となります。
4. 大隈重信 加藤高明 対支21ヶ条要求と国際批判
大隈重信と加藤高明は、第一次世界大戦中に、日本の優越的地位の確立を目指して対支21ヶ条要求を突きつけました。この要求は、満州における日本の支配を強化し、その経済的利益を確保することを目的としていましたが、国際社会から強い批判を受け、アメリカからは侵略行為と見なされました。この要求は、山東問題を含む様々な問題を内包しており、日本の対外政策における強硬姿勢を象徴する出来事でした。彼らは、ポーツマス条約の不備や、中国における欧米列強の影響力拡大への危機感から、日本の権益を守るためにこの要求を行ったと考えられます。しかし、この強硬姿勢は、アメリカ合衆国との関係悪化を招き、後の太平洋戦争へとつながる重要な契機となりました。大隈重信と加藤高明の行動は、日本の対外政策における強硬派と穏健派の対立、そして国際社会との摩擦といった問題を理解する上で重要な視点です。
5. その他の主要人物 袁世凱 段祺瑞 そしてアメリカ合衆国政府
この文書では、袁世凱や段祺瑞といった中国側の指導者も重要な役割を果たしています。袁世凱は、対支21ヶ条要求の交渉に臨んだ人物であり、日本の要求の一部を受け入れました。一方、段祺瑞は、西原亀三と日中親善に基づく政策を協議した人物です。彼らの行動は、中国側の立場と、日本との関係性、そしてアメリカ合衆国の影響力など、様々な要素が絡み合った複雑な状況を示しています。また、アメリカ合衆国政府は、満州問題や山東問題において、日本の政策に批判的な姿勢を取り、中国を支援しました。ハリマンのようなアメリカの実業家も、満州における日本の支配に挑戦する動きを主導しました。これらの登場人物の行動は、この時代の複雑な国際関係を理解する上で不可欠な要素となっています。
