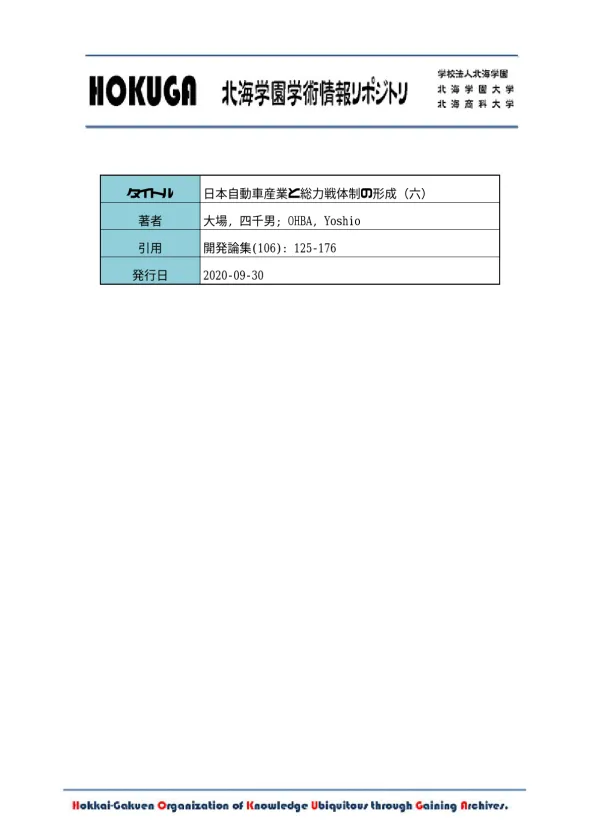
総力戦と日本自動車産業
文書情報
| 著者 | 大場 四千男 |
| 専攻 | 日本経済史、軍事史、自動車産業史など |
| 文書タイプ | 論文、紀要論文など |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 8.41 MB |
概要
I.軍用自動車補助法と国産自動車産業の発展
本稿は、大正期から昭和初期にかけての日本の【自動車】産業、特に【軍用自動車】に焦点を当て、その発展と【輸送革命】への影響を分析する。特に【軍用自動車補助法】の複数回の改正が、国産【自動車】メーカー(いすゞ、日野、日産、三菱など)の育成と自立化に大きく貢献した点を強調する。 法改正により【軍用自動車】の多様化から大型車(特に【六輪自動車】)への集約化が進み、性能向上と量産体制の確立が図られた。【満州事変】における【六輪自動車】の活躍は、その実用性を証明し、日本の【軍用自動車】技術の進歩を示している。 同時に、この過程で【国鉄】の経営に影響を与え、日本の交通構造を大きく変えた【輸送革命】が起きたことも論じる。
1. 軍用自動車補助法の改正と輸送革命
満州事変での軍用自動車の活躍が、日本の軍用自動車政策、ひいては自動車産業発展の転換点となった。関東軍の電光石火の占領劇は、自動車部隊の重要性を如実に示し、陸軍自動車学校の卒業生を中心とした自動車部隊の編成が成功要因の一つとして挙げられている。 複数回にわたる軍用自動車補助法の改正は、多様な軍用自動車を大型車に集約する方向へ進んだ。特に、六輪自動車と大型貨物自動車への集約化は、その後の国産自動車産業の発展に大きな影響を与えた。フランスの軍用自動車補助法を参考に、日本の補助法は製造補助金制度を導入。これは国産自動車メーカーの自立化を促進する政策目的を達成し、結果として輸送革命を担うことになった。国産軍用自動車は、平時には貨物トラックや乗用バスとして利用され、戦時には徴用されるという制度設計がなされ、アメリカ・ビックスリーとの競争に挑む土台を築いた。この輸送革命は、国鉄の旅客・貨物輸送を奪い、国鉄経営を危機に陥れるほど大きな影響を与えたとされる。このように、軍用自動車補助法の改正は、軍需産業の発展のみならず、日本の経済や交通システム全体に大きな変化をもたらした。
2. 満州事変と軍用自動車の性能向上
満州事変(昭和6年~昭和12年)における実戦経験は、軍用自動車の改善に繋がる重要なデータとなった。約4年間の戦争を通して、軍用自動車は性能向上を重ね、北支事変や日中戦争に対応できるレベルに進化した。この実戦経験を基に、陸軍と陸軍自動車学校は軍用自動車の改良に積極的に取り組み、大正10年から昭和11年までの間に複数回の軍用自動車補助法改正を実施した。改正の目的は、軍用自動車の性能向上と多様性への対応にある。具体的には、泥土、砂浜、山岳地帯、寒冷地帯といった過酷な環境でも運用可能な六輪自動車の開発が成功した点が挙げられる。 満州事変での六輪自動車の運用実績は、その高い実用性を証明し、日本の軍用自動車技術の進歩を象徴する出来事となった。 この実戦データと技術的改善は、後の日中戦争、さらには太平洋戦争における軍用自動車の改良に大きく貢献したと考えられる。
3. 軍用自動車補助法改正の具体的な内容と効果
軍用自動車補助法の改正は、主に以下の3点に焦点を当てている。第一に、軍用自動車の車種を絞り込み、大型車に集約すること。第二に、製造補助金制度を活用して国産自動車メーカーの自立化を図ること。第三に、あらゆる環境に対応できる性能を持つ六輪自動車の開発である。 改正によって、製造補助金の額や対象範囲が変更され、国産自動車メーカーの育成と自立化を支援する政策が強化された。 特に、六輪自動車は、その高い走破性と安定性から、満州事変を始めとする様々な戦場で活躍し、軍用自動車の性能向上に大きく貢献した。また、軍用自動車の生産能力を高めることで、平時における国内経済の活性化にも寄与した。 これらの改正は、単に軍用自動車の性能向上にとどまらず、国産自動車産業全体の技術力向上や、経済発展に繋がったと考えることができる。 具体的な数値データ(予定車両数、補助金金額など)も改正内容と共に示されている。
4. 自動車製造事業法制定と軍用自動車の特化
昭和11年には自動車製造事業法が制定され、500cc以上の自動車製造には商工大臣の許可が必要となった。これにより、軍用自動車補助法は特殊車(大型牽引車、大型軍用自動車)へ特化し、戦時体制下の自動車製造を担うための法整備へと移行したと言える。 これは、軍用自動車の需要増大と、国産自動車産業の戦時体制への転換を意味する重要な転換期であった。 軍用自動車補助法は、当初から国産自動車産業の育成を目的としていたが、この時点からは、より明確に軍事的必要性と結びついた政策へと変化したと言える。 この事業法の制定は、国産自動車メーカーの生産計画や経営戦略に大きな影響を与えたと考えられる。
II.自動車価格と市場競争
アメリカ・ビックスリー(フォード、GM、クライスラー)の【自動車】価格戦略は、日本の【自動車】産業に大きな影響を与えた。フォード社の低価格大量生産戦略とGMのフルライン戦略の対比を通して、価格競争の激しさがわかる。 特に、GMの1トン半トラックの価格(約9500円)は、日本の【軍用自動車】価格と関連付けられ、石川島自動車製作所がイギリスのウーズレー社との提携を通して国産【軍用自動車】生産に乗り出した背景を説明する。 この価格帯は、当時高価であった【自動車】が、小規模な荷牛馬業者(馬1匹あたり約1000円)の存続を許容する経済的要因にもなった。
1. アメリカ ビックスリー各社の価格戦略と日本の自動車産業
アメリカ・ビックスリー(Ford, GM, Chrysler)の自動車価格戦略は、日本の自動車産業に大きな影響を与えた。Fordは、大量生産による「規模の経済」を活かした低価格戦略で成功を収めた。一方、GMは、小型車から高級車まで幅広い車種を展開する「範囲の経済」に基づく多角化戦略を採り、1920年代後半にはFordを抜き去った。 具体的には、Fordの一トン車の価格は1600円~2256円と低価格帯に設定されていたのに対し、GMのChevroletは、幌型2790円、箱形3600円、一トン四分の一積貨物自動車2650円と、Fordよりも高価格帯に設定されていた。さらに、GMのトラック部門では、一トン貨物自動車が6280円、2.5トン積貨物自動車が9500円と高価格であった。このGMの2.5トン積貨物自動車の価格は、日本の軍用自動車価格と関連付けられ、国産自動車メーカーの戦略に影響を与えたと推測できる。
2. 石川島自動車製作所と軍用自動車
日本の石川島自動車製作所は、イギリスのウーズレー社の自動車製造販売権を獲得し、大正期にウーズレー号(乗用車・貨物車)を製造開始。大正13年には軍用自動車補助法の適用を受け、本格的な軍用自動車の生産を開始した。 石川島自動車が軍用自動車製造に注力できた背景には、軍用自動車の価格設定がGMの2.5トン積貨物自動車の価格(9500円)とほぼ同等であったことが挙げられる。この価格帯は、当時としては非常に高価であったが、軍用としての需要と、国産自動車産業育成という政策的背景が相まって、生産が可能になったと推測できる。 この事例は、当時の高い自動車価格が、国産自動車産業の成長と、軍需産業への貢献を両立させるための重要な要素であったことを示している。
3. 自動車価格と伝統的輸送機関の存続
高い自動車価格が、伝統的な荷牛馬業の存続を許容する経済的要因にもなった。軍用自動車が9500円程度であったのに対し、荷牛馬業者は馬1匹あたり1000円程度の投資で済んだ。この価格差は、自動車と荷牛馬という異なる輸送手段の共存を可能にしたと言える。 荷牛馬業者の多くは、馬と荷車を各一匹、一台所有する零細企業であり、運賃も個数建や重量建で、低価格帯で競争を展開していた。 自動車の高価格という市場環境が、伝統的輸送機関の存続に意外な形で貢献したという点は注目に値する。この状況は、日本の道路事情や都市計画の未発達という地理的要因と相まって、伝統的な輸送手段が容易に駆逐されなかったことを示している。
III.営業用自動車の普及と小運送業への影響
第一次世界大戦後の戦争特需や関東大震災による鉄道網の被害は、日本の【自動車】普及を促進した。アメリカからの【自動車】大量輸入(特にフォードとGM)と、KDノックダウン生産の開始は、市場の拡大と国産【自動車】メーカーへの経営圧力をもたらした。 営業用【自動車】の普及は、【輸送革命】の重要な側面であり、従来の人力車、馬車、荷車などの伝統的輸送手段に大きな影響を与えた。特に【小運送業】は、【自動車】との競争に直面し、その影響の度合いが分析される。東京では、水運と【自動車】輸送の共存が描かれる。東京都によるアメリカからの緊急輸入(10,776輌)も重要なデータとなる。
1. 第一次世界大戦と関東大震災の影響
日本の自動車普及は、第一次世界大戦による戦争特需と成金ブーム、そして大正12年の関東大震災による山手線を中心とした鉄道網の壊滅的被害が大きな推進力となった。震災後、東京都はアメリカ・ビックスリーから1000台の自動車を緊急輸入し、都営バスを中心に公共交通網の再建を図った。この大量注文に驚いたFordとGMは、日本市場への進出を本格化させ、KDノックダウン生産の可能性を探った。さらに、震災後の都市計画における幹線道路の整備、自動車税の軽減、ガソリン価格の下落なども、自動車普及を加速させた要因である。これらの要因が複雑に絡み合い、日本の自動車市場が急速に拡大していく基盤が形成されたと言える。
2. 営業用自動車の二面性と輸送革命
営業用自動車は、乗合自動車(バス)、ハイヤー、タクシーなどの発展によって、主に人の移動を担う役割を担った。これにより、従来の人力車や乗用馬車は、新たな競争に直面することとなった。一方、貨物自動車は物流を担い、「大運送」(大量輸送・長距離)と「小運送」(近距離・少量輸送)の二つの形態に分かれた。大運送は従来から鉄道や船舶が担っていたが、小運送は荷車、牛馬車、リヤカーなどが担っており、営業用自動車の台頭はこれらの伝統的な輸送手段に大きな影響を与えた。 この営業用自動車を中心とした輸送手段の変化は、「輸送革命」と位置づけられ、伝統的な輸送手段の衰退と近代的な輸送機関の発達を同時に意味する重要な社会変革であったと記述されている。 一里当たりの運賃は、従来の5銭から10銭と高料金であったことも示されている。
3. 営業用自動車と荷車 都市部と農村部の対比
営業用自動車は、道路事情の良い都市部ではその威力を発揮し、高速性と短時間配達を可能にした。しかし、坂道の多い地域や、狭い道路、路面状態の悪い農村部では、荷車の方が有利な場合が多かった。日本の道路事情や都市計画の未発達は、荷車の優位性を長く維持する要因となった。全国の荷車数は、大正10年の2,203,406輌から昭和元年の1,963,107輌へと11%減少したに過ぎず、大都市である東京と大阪でも、減少率はそれぞれ16%と11%にとどまった。これは、人力車や乗用馬車とは異なり、荷車が比較的長く存続したことを示している。 この事実は、自動車による輸送革命が、地域特性や道路事情によって、その影響の度合いが大きく異なったことを示している。
4. 自動車普及と輸入依存 国産化への動き
大正10年から昭和元年の間に、自動車保有台数は12,122輌から40,070輌へと3.3倍に増加した。関東大震災の翌年には、アメリカ・ビックスリーからの緊急輸入によって10,776輌増加し、増加率は6.2倍弱に達した。その後も輸入自動車の増加が続き、日本経済は貿易収支の赤字に苦しむようになった。 この輸入依存による経済的脆弱性を克服するため、国産化が急務となり、国産車の開発は商工省の国策として本格的に推進されることになった。 この状況は、自動車の普及が、日本経済に大きな影響を与えただけでなく、国産化政策という新たな産業政策を推進する契機になったことを示している。
IV.国産自動車政策と産業振興
輸入【自動車】の増加による貿易赤字対策として、国産【自動車】の開発と生産が国策として推進された。商工省は国産車育成政策(ローカル・コンテント法)を策定し、標準自動車の製造や自動車製造事業法による大衆車生産を促進した。伊藤久米蔵博士の提言は、国産【自動車】の需要拡大と、軍用【自動車】の保護を通じた産業振興の必要性を説いている。 【軍用自動車補助金】の増額や、部分品の輸入税率改正など、国産【自動車】産業の育成に向けた具体的な政策が検討された。これらの政策は、日本の【自動車】産業の自立化と発展に貢献したと同時に、保護主義的な側面も持っていた。
1. 国産自動車育成政策と輸入依存からの脱却
輸入自動車の増加による貿易赤字は、日本の経済的脆弱性を露呈させ、国産自動車の開発・生産促進が国家政策として重要課題となった。商工省は、輸入自動車に依存する現状を打破するため、国産車育成政策(ローカル・コンテント法)を策定した。この政策は、輸入品に頼らず、国内生産による経済的自立を目指すものであった。 具体的には、まず商工省型標準自動車の製造を複数の国産自動車メーカーの協力体制の下で実現し、その後、昭和11年の自動車製造事業法に基づく大衆車の大量生産へと発展させる計画が立てられた。これは、単なる国産化だけでなく、大量生産体制の構築によるコスト削減と、市場競争力の強化を目指した戦略であったと言える。
2. 伊藤久米蔵博士の国産自動車論
工学博士である伊藤久米蔵は、国産自動車の発展策として、需要と供給両面からのアプローチを提言した。供給面では、軍用自動車の保護・奨励を強化し、製造補助金を大幅に増額することで大量生産体制の確立を目指す。需要面では、国道利用の許可制度などを活用して営業用乗用車の全国普及を促進する政策を提唱した。 伊藤博士は、自動車台数が10万台に達し、償却期間を5年と仮定した場合、年間の更新需要と新規需要を合わせれば、国産自動車メーカーは十分な生産量を確保でき、自立的拡大が可能になると主張した。しかし、この需要拡大論は、低価格・高性能なアメリカ・ビックスリーとの競争を考慮していないという点で、保護主義的な側面も指摘できる。
3. 国産化政策の具体策と課題
国産化政策の一環として、部分品の輸入税率を自動車と同一税率に改正することが提案された。これは、Ford社などが横浜に組立工場を設立し、完成品を輸入することで低税率を享受する現状への対策である。 また、軍用保護自動車に対する保護金の増額も重要な政策課題として挙げられた。当時、年額40万円程度の保護金は、自動車工業の発展には不十分であり、少なくとも200万円への増額が必要だと主張されている。 さらに、官庁による国産品の使用促進や、自動車類似品の民間企業への製造委託なども、国産自動車産業の振興策として検討された。これらの政策は、国産自動車産業の基盤を確立し、将来的な東洋市場への進出を目指す戦略の一部であったと推測できる。
4. 商工省の国産自動車政策とローカル コンテント法
商工省は、国産化を国家政策として推進し、国産自動車育成政策(ローカル・コンテント法)を展開した。 この政策は、第一段階として商工省型標準自動車の製造を複数の国産自動車メーカーによる共同作業として実現し、第二段階として昭和11年の自動車製造事業法に基づく大衆車の大量生産を目指す計画であった。 星子勇の国産自動車論も、軍用自動車補助法を中心とした供給政策と、国道利用許可制度による需要拡大策を組み合わせた戦略を示しており、商工省の政策と共通する部分も多い。しかし、低価格競争力の高いアメリカ製自動車との競争という課題は、これらの政策が抱える大きな問題点であったと推測される。
V.東京における物流と交通
東京への物流の一極集中は、海運と鉄道、そして【自動車】による陸上輸送網の構築によって支えられていた。 東京鉄道局運輸課の報告書「運輸より観たる東京」は、東京が世界的な大都市として、国内外からの物流の中心地であることを示している。 東京への入貨は、工業原料、工業製品、生活必需品、建築資材など多岐に渡り、特に石炭の大量輸送が、九州、本州、北海道からの専用船による水運を介して行われていたことがわかる。
1. 東京への物流の一極集中と交通網
東京は、世界的な大都市であり、国内外からの物流が集中する中心地であった。この一極集中は、日本が海に囲まれた島国であるという地理的条件、そして国鉄による南北を繋ぐ縦断的な鉄道網によって支えられていた。関東大震災後には、自動車による東西方向への水平的な輸送網が整備され、東京駅を中心とした横断的な物流網が構築された。 東京鉄道局運輸課の報告書「運輸より観たる東京」では、東京が世界第7位(大東京圏では世界第3位)の大都市であることを指摘し、国内経済だけでなく国際経済の影響も大きく受けていると説明している。 東京への入貨貨物は、工業原料、工業製品、生活必需品、建築資材など多岐にわたり、その量は膨大であったことがわかる。特に、資源不足の日本において重要な資源である石炭は、九州、本州、北海道などから専用船を用いた水運で大量に東京へ輸送されていた。
2. 水運と陸運の役割分担
日本は島国であるため、水運は物流において重要な役割を果たしていた。東京への貨物輸送においても、京浜間や千葉県沿岸からの艀船による輸送が盛んであった。利根川、江戸川、中川、荒川などの河川を航行する艀船や汽船も頻繁に往来していた。 月島や芝浦の埠頭では、北は北洋、南は台湾に至る多くの船舶が行き交い、活気のある荷役作業が行われていた。横浜港からの貨物も艀船によって東京へ運ばれていた。 このように、水運は大量の貨物を輸送する上で重要な役割を担い、鉄道や自動車と並んで、東京の物流を支える重要なインフラであったと言える。東京港の役割も重要視されている。
3. 東京の入貨内容と工業都市としての特性
東京への入貨内容は、工業原料(石炭、セメント、鉄材など)、工業製品、生活必需品(米、魚、野菜、果物など)、土木・建築材料、ガラス・工芸品など多岐にわたる。 東京は約1200万人の人口を抱え、世界有数の大都市であったため、大量の生活必需品が農村部や海外から供給される必要があった。また、東京は京浜工業地帯の中心地であり、多くの工場を抱える生産都市でもあったため、工業資源や原料の輸入・移入も不可欠であった。 そのため、入貨額の上位を石炭、セメント、鉄材などが占めていたことは、東京の工業都市としての特性をよく反映している。特に石炭は、工場の燃料、エネルギー源、化学素材、発電所への燃料として大量に使用され、専用船による安価な水運輸送が利用されていた。
