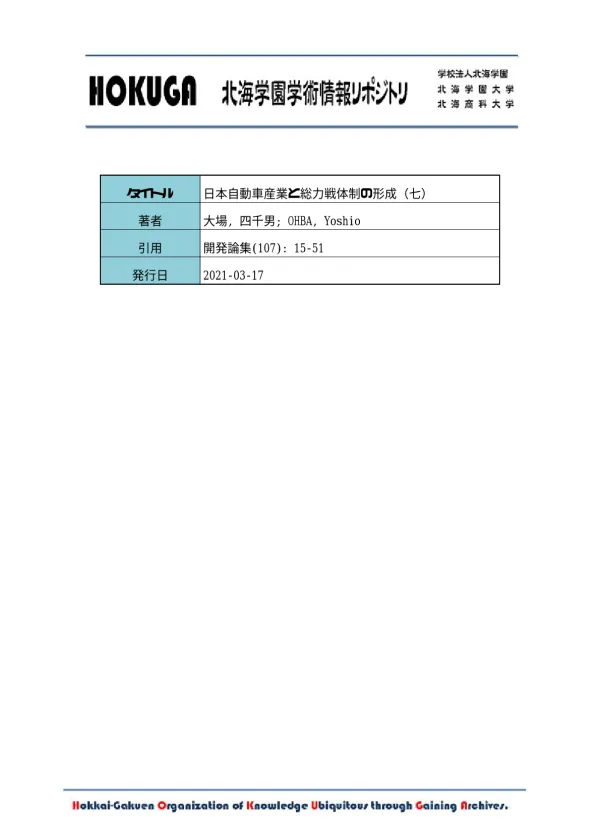
総力戦と自動車産業:国防国家への道
文書情報
| 著者 | 大場 四千男 |
| 専攻 | 歴史学、経済学 (推定) |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.07 MB |
概要
I.明治維新と国防国家体制の確立 Meiji Restoration and the Establishment of the National Defense State System
土屋喬雄の指摘するように、明治維新は国防国家建設として位置づけられる。アヘン戦争後の中国の危機が、徳川幕府と薩長を動かし、開国や条約締結といった対応策を余儀なくさせた。その後、天皇制絶対主義に基づく上からの半封建的市民革命を経て、国防国家が構築される。伊藤博文による明治憲法制定、大隈重信の対支24ヵ条要求による中国への進出、そして近衛文麿、東条英機による戦争への突入と敗戦まで、日本の運命を決定づけたのはこの国防国家体制であった。ポツダム宣言受諾後の昭和憲法成立は、下からの民主主義革命であり、天皇制は象徴天皇制へと移行した。
1. 国防国家建設としての明治維新
土屋喬雄は『日本国防国家建設の史的考察』において、明治維新を「国防国家」建設の起点と位置づけています。この主張は、中国におけるアヘン戦争による領土分割と植民地化の惨状を目の当たりにした徳川幕府と薩長藩が、国家存亡の危機感を共有し、対抗策として国防国家建設という新たな道を歩むことを余儀なくされたという歴史的背景に基づいています。具体的には、幕府による函館、下田の開港、和親条約、通商条約の締結といった一連の外交努力は、世界経済への編入を意味し、同時に、列強の進出という外部からの圧力に対処するための、内政改革の必要性を浮き彫りにしました。そして、この危機への対応策として、天皇制絶対王政を基軸とした上からの半封建的市民革命が勃発し、国家の強靭化が目指されたのです。 明治維新は単なる体制転換ではなく、日本の存続をかけた、まさに国防国家建設という国家的プロジェクトであったと解釈できるでしょう。この時点での国防国家像は、列強に対抗できるだけの軍事力と経済力を構築することを目指したものであったと考えられます。
2. 明治憲法と国防国家体制の展開
明治維新後の国防国家建設は、伊藤博文による立憲主義に基づく明治憲法(欽定憲法)の制定によって法的基盤を確固たるものとしました。天皇の大権を背景に、国家の統一と近代化が推進されたのです。さらに、第一次世界大戦下の国際情勢を巧みに利用し、大隈重信による対支24ヵ条要求は、中国(支那)、満州を日本の生命線として位置づけ、日本の国際的地位を飛躍的に向上させました。結果として、世界五大強国の仲間入りを果たすほどの強力な国防国家へと発展を遂げます。しかし、この発展は、近衛文麿による北支事変からの日中戦争への拡大、そして国家総動員法に基づく高度国防国家体制へと発展していく過程を示しており、その後の東条英機による大東亜戦争への突入と敗戦へと繋がる、大きな転換点であったと言えます。この期間、万世一系の天皇制が国防国家体制の中枢を担い、明治天皇が上からの市民革命の担い手として重要な役割を果たしたことは特筆に値するでしょう。 この節は、明治維新後の国防国家体制の具体的な展開と、その過程における重要な歴史的出来事、そして主要人物の役割を詳しく説明しています。
3. ポツダム宣言受諾と天皇制の変容
第二次世界大戦の終結、ポツダム宣言の受諾は、日本の歴史、そして国防国家体制に大きな転換をもたらしました。アメリカ軍、特にマッカーサー将軍による主権在民を謳う昭和憲法の制定は、下からの民主主義革命として捉えられます。この革命によって、絶対王政下の天皇は現人神から人間宣言によって近代的立憲君主制へと移行し、象徴天皇として新たな役割を担うことになります。明治維新以来、日本の運命を決定づけてきた明治維新の国防国家体制は、この時点で終焉を迎えたと言えるでしょう。この節は、戦争終結後の日本の政治体制の劇的な変化と、それによって引き起こされた天皇制の変容、そして長きに渡り日本の政治・社会構造を支えてきた国防国家体制の終焉を明確に示しています。 ポツダム宣言と昭和憲法の制定は、日本が民主主義国家へと転換する上で、極めて重要な転換期であったと示唆しています。
II.大正期の総力戦構想と産業育成 Total War Conception and Industrial Development during the Taisho Period
日露戦争後から、総力戦構想が議論され始めた。田中義一、山縣有朋、奥保鞏、東郷平八郎らは、財政と資源を考慮した国防方針を策定。速戦即決戦略が定着する中、第一次世界大戦の長期化を受け、近代的総力戦の実態調査が行われた。鈴村吉一は、全国動員計画の欠落、軍需供給能力の不足、外国市場への依存を指摘し、対策として軍需工業動員法の制定、軍需局の発足へとつながった。この過程で、自動車産業を含む軍需工業の育成、特に国産自動車メーカー(ガス電、三菱神戸造船所、川崎造船所など)への委託生産が始まった。
1. 日露戦争後の総力戦構想の萌芽
日露戦争後の「戦後方針」策定において、日本の総力戦構想の萌芽が見られます。参謀本部歩兵中佐の田中義一は、明治39年、「戦略と政略の一致、兵備と経済の緩和」を基に、ロシア極東兵力を55師団と想定、陸軍兵力を45師団(常設20、第一種予備20、第二種予備5)と算定し、山縣有朋参謀総長と共に長期計画に基づく編成準備を提案しました。山縣有朋は既に明治38年、「戦後経営意見書」を桂太郎内閣に提出しており、これらの提案を受け、奥保鞏参謀総長と東郷平八郎海軍軍令部長は明治40年、「帝国国防方針、国防に要する兵力、帝国軍の用兵綱領」を西園寺公望内閣に提案し、元帥府会議で決定されました。この国防方針は、日本の財政と資源を考慮し、資源の培養に努めることを重視しており、昭和20年まで軍事戦略と軍備の基本方針として踏襲されました。「速戦即決」という帝国軍の伝統的戦略は、満州事変以降の長期戦を予感させるものであり、経済力よりも精神力動員を重視する日本的総力戦の特徴を示唆しています。この初期段階では、総力戦への備えは、まだ兵力数と資源確保の観点からの限定的なものであったと考えられます。
2. 第一次世界大戦と総力戦構想の制度化
第一次世界大戦の長期戦は、ヨーロッパ諸国の国家経済力を総動員した実態を浮き彫りにし、日本陸軍は近代的総力戦の実態調査を通して総力戦構想の策定と制度化を緊急課題としました。鈴村吉一は、この調査研究において、①全国動員計画の欠落、②軍需供給能力の不十分さ、③外国市場への依存という日本の軍需工業の脆弱性を指摘しました。この指摘は、帝国軍の根本方針として対策を講じる必要性を訴えるものでした。具体的な対策として、陸軍は大正9年の砲兵工廠条例改正で小倉兵器製造所、名古屋兵器製造所を新設し、大正10年の改正では大阪砲兵工廠の民間工場利用を制度化、軍用自動車をガス電など複数の企業に委託生産するなど、国産自動車産業育成に乗り出しました。しかし、鈴村吉一が起案した「全国動員計画必要ノ議」は、欧米との比較において日本の工業力の遅れを痛感しており、平時からの国防充実、軍需品供給能力の強化が喫緊の課題であることを改めて示しています。この危機意識が、大正10年の「軍需工業動員法」制定と軍需局の発足へと繋がっていったのです。軍需局は、国家総動員体制の準備と、陸海軍の軍備近代化・機械化を推進する役割を担いました。
3. 軍需局 国勢院 そして資源局 総動員体制の中央機関の変遷
第一次世界大戦とシベリア出兵への対応として、政府は戦時体制と動員を緊急課題としました。陸海軍は明治40年の「帝国国防方針」を改訂し、戦時40師団、八八艦隊編成に対応する軍備整備を目標とする新国防方針を策定しました。この新方針は、平時19師団の軍需生産能力では戦時40師団の需要をまかなえないというギャップを埋める必要性を明確に示しています。このギャップを埋めるための工業動員こそが総力戦構想であり、「軍需工業動員法」はその具体化です。軍需局は、軍需工業の自給自足と保護育成を主要な任務とし、民間工場の調査や資源調査を積極的に行いました。しかし、その業務拡大に伴い、内閣統計局と統合されて国勢院が設立されます。国勢院は総動員中央機関として位置づけられましたが、大正末期の恐慌や軍縮、民主化運動などの影響を受け、廃止されました。その役割はその後、昭和12年に設立された資源局が引き継ぎ、松井春生を筆頭に、国家総資源の調査と動員計画の策定、資源の培養助長が中心課題となりました。この機関の変遷は、時代の変化と国家政策の転換を反映しており、総力戦体制構築に向けた日本の模索がうかがえます。各機関の設立目的と業務内容、そしてその成功と失敗を分析することで、当時の日本の政治・経済状況をより深く理解することができます。
III.総動員体制の整備と変遷 Development and Transformation of the Total Mobilization System
大正期には、軍需局、その後国勢院が総力戦に向けた資源動員の中心機関となった。国勢院は内閣統計局と軍需局を統合した機関だったが、大正末期の恐慌や軍縮、護憲運動などにより廃止された。その後、昭和に入ると資源局が設立され、松井春生を中心に資源調査、資源保育政策が推進された。資源局は、平戦時を問わない総動員計画の策定に尽力し、第二次総動員期間計画(赤本)を作成。これは、後の企画院、軍需省の計画の基礎となった。しかし、支那事変の拡大により、陸軍主導の企画院への移行が進み、経済への直接介入が強まった。
1. 軍需局 総力戦体制構築に向けた初期段階
第一次世界大戦とシベリア出兵を背景に、政府は戦時体制と動員を緊急課題としました。陸海軍は明治40年の「帝国国防方針」を改訂、戦時40師団、八八艦隊に対応する軍備整備を目標とする新国防方針を策定。平時19師団の生産能力では戦時40師団の需要をまかなえないという問題を解決するため、軍需工業動員法が制定され、総力戦構想が具体化されました。 この法に基づき設立された軍需局は、軍需工業の自給自足と保護育成を主要任務としました。陸軍工政課は「民間工場資本金五万円以上工場」の調査を行い、軍需局は民間工場、官庁の民需・軍需、資源に関する総合調査を実施。「軍需調査令」も制定され、国家総動員計画の基礎作りが始まりました。寺内正毅内閣総理大臣は、軍需局の設立に際し、工場動員の広範囲さと各省庁間の事務の煩雑さを指摘、軍需局を各省庁の統一機関として位置づけました。軍需局の設立は、総力戦に必要な軍需品の安定供給体制構築に向けた最初の大きな一歩でした。しかし、この時点では、まだ体系的な全国動員計画は存在しておらず、資源調査も本格的な国力調査には至っていなかったと考えられます。
2. 国勢院 総動員体制の中央機関としての機能強化
軍需局の業務拡大と総動員業務の増加を受け、政府は内閣統計局と軍需局を統合した国勢院を設置しました。国勢院は総動員中央機関として位置づけられ、国家資源の総動員とその物動計画の策定に取り組みました。各省庁への業務委任と統轄も不可欠な課題となり、国家総動員計画とその準備が本格化しました。しかし、国勢院は第一部と第二部の対立、平和官庁との摩擦、内部の軍需局と統計局の対立なども抱えていました。大正末期の恐慌と不況、ワシントン軍縮条約に基づく軍縮、護憲運動、労働組合運動、普通選挙運動なども国勢院廃止の背景にあります。河辺虎四郎の指摘するように、大正末期の「デモクラシーと軍縮」という風潮が、国防の要諦を把握する妨げとなった可能性も示唆されています。国勢院の経験は、総動員体制構築における組織運営、官僚機構間の調整、そして国民的コンセンサスの獲得の難しさを示すものです。この期間、軍需調査令の重要性は白川義則や井出謙治らによって強調され、軍需調査の継続が強く求められていました。
3. 資源局 資源調査と保育政策の推進 そして企画院への移行
国勢院の後継機関として昭和12年に設立された資源局は、内閣総理大臣の管理下にあり、「人的及物的資源の統制運用計画に関する事項の統轄」を担いました。資源局は、国家資源の調査に基づく平戦時の総動員計画の策定と資源の培養助長を二本柱とし、松井春生を中心に資源調査と保育政策が推進されました。年間単位での総動員期間計画の策定、工場・事業場の資源現況調査、戦時供給力調査、戦時需要額調査、国民生活必要最小限度需要額調査などが実施されました。第二次総動員期間計画(赤本)は、その精緻さから後の企画院、軍需省の計画の基礎となりました。しかし、支那事変の拡大により、陸軍は戦時体制への移行を加速。資源局と調査局を合併して企画院を設立し、内閣の実体掌握を目指しました。松井春生は、資源の調査・保育、資源の統制運用準備という立場から、軍需工業動員法の改正や国家総資源論を展開しましたが、陸軍の戦時体制構築の動きには抗しきれませんでした。この過程で、資源の国内保有政策が重要となり、「日本製鉄株式会社法」、「石油業法」などの立法措置がとられました。
IV.日満支経済圏と東亜国防国家論 Japan Manchuria China Economic Bloc and the East Asian National Defense State Theory
支那事変の拡大に伴い、国防資源の不足、日本経済の脆弱性が顕在化した。参謀本部は、日満支経済圏を東亜経済圏へ拡大することで国防資源の確保を目指した。石原莞爾は、第二次総力戦計画の問題点を指摘し、「重要産業五ヶ年計画陸軍省案」などを提案した。軍需工業の拡大、大陸への移転が目指され、特に航空機産業と自動車産業(日産、トヨタ、いすゞなど)が軍需工業の中心となった。大陸への進出を背景に、自動車製造事業法などが制定され、国防国家の強靭化政策が推進された。
V.重要産業5ヵ年計画と国防国家強靭化 Five Year Plan for Important Industries and Strengthening of the National Defense State
本格的な軍備充実のため、陸軍は「軍需品製造工業五年計画要綱」を策定し、航空機産業の拡大と、必要に応じて自動車産業からの転換を検討。軍需工業の保護、育成政策が強化された。澤本理吉郎による「重要産業五年計画陸軍案」は、資本主義経済機構の転換を図り、軍需品生産のための資源動員を徹底しようとした。整備局は、軍用自動車補助法などを活用し、民間工場との連携を強化し、特に自動車産業を育成した。この計画は、企画庁にも影響を与え、最終的に大東亜戦争へとつながる総力戦体制構築を加速させた。
1. 軍需工業動員法と総動員体制の構築
大正期、第一次世界大戦下の長期戦やシベリア出兵を踏まえ、日本の軍需工業の脆弱性が露呈しました。この問題意識から、鈴村吉一らの提言に基づき、大正10年に「軍需工業動員法」が制定され、総動員準備の中央機関として軍需局が発足しました。この法律は、軍需品の安定供給を目的とし、特に「内地自給」を重視した資源保育政策を基軸としていました。 軍需局は、軍需工業動員法に基づき民間工場の設備や製造力の調査を実施し、軍需品の自給自足と軍需工業の保護育成政策を推進しました。具体的には、民間工場の設備投資促進や技術指導を行い、軍需品の生産能力向上を目指しました。また、資源調査も大規模に行われ、国力調査に匹敵する広範なデータが収集されました。 この軍需局の活動は、平時からの準備を重視した国家総動員体制構築への重要な第一歩となりましたが、省庁間の調整や情報の共有といった課題も抱えていたことが分かります。特に、工場動員の広範囲さと各省庁間の事務担当の煩雑さという点が、寺内正毅によって指摘されています。
2. 国勢院の設立と廃止 総動員体制の課題と限界
軍需局の業務拡大と総動員業務の増加を背景に、大正12年、内閣統計局と軍需局が統合され、国勢院が設立されました。国勢院は、総動員計画策定の中心機関として、国家資源の総動員と物動計画に取り組みました。しかし、国勢院は、内部対立や平和官庁との摩擦、そして大正末期の恐慌・不況、軍縮、民主化運動といった社会情勢の影響を受け、大正11年には廃止されました。 国勢院の廃止は、総動員体制構築における様々な課題と限界を示しています。松井春生は、国勢院内部の対立や平和官庁との対立を廃止原因の一つとして指摘しており、総力戦体制という軍事的な計画が、平和主義的な官庁との間で大きな摩擦を生んだことがわかります。また、河辺虎四郎の指摘にあるように、軍縮や民主化の流れが、国防の要諦を把握することを困難にした可能性も示唆されています。 国勢院の設立と廃止は、総力戦体制構築のための組織運営や、社会全体の合意形成の難しさを示す事例と言えるでしょう。この失敗は、後の資源局設立にも影響を与えたと考えられます。
3. 資源局 資源保育と総動員計画の高度化 そして企画院への移行
国勢院の後を継ぎ、昭和4年に設立された資源局は、国家総資源の調査と動員計画の策定を主要任務としました。松井春生をリーダーに、資源の調査・企画、保育策が推進され、総動員期間計画は5ヶ年単位で策定されました。資源局は、工場・事業場の人的・物的資源の現況調査、戦時供給力調査、戦時需要額調査、国民生活必要最小限度需要額調査を行い、内地だけでなく朝鮮、満州、台湾も対象としました。第二次総動員期間計画(赤本)は、その精緻さで知られ、後の企画院、軍需省の計画の基礎となりました。 資源局は「軍需工業動員法」の資源保育政策を受け継ぎ、国内保有策を重視しました。しかし、支那事変の拡大により、陸軍は戦時体制への移行を強行。資源局は企画院に統合され、内閣の実体掌握を目指した陸軍の経済介入が強まりました。 資源局の活動は、国家総資源の把握と効率的な運用、そして資源の保育という点で一定の成果をあげましたが、軍部の圧力と拡大する戦争によって、その独立性は失われ、計画経済への移行を加速させる役割を担うことになっていきました。
