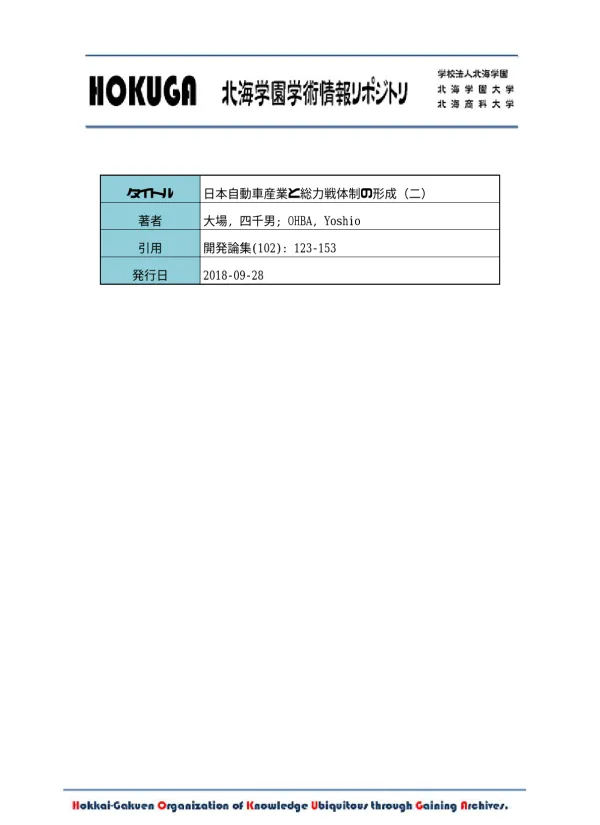
総力戦と自動車産業:日本経済の変貌
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.02 MB |
| 著者 | 大場四千男 |
| 文書タイプ | 論文 |
概要
I.戦前日本の自動車産業と国家経済主義 4000cc中型トラックの集中生産
商工省は、国家経済主義政策の一環として、国産3社(具体的な社名は後述)による4000ccクラスの1.5~2トン中型トラックの集中生産を推進した。これは陸海軍の軍用保護自動車計画と歩調を合わせ、第一次産業再編を強力に推し進める動きの一部であった。この政策は、製造奨励補助金と保護関税の設定によって支えられた。 主要なキーワード: 4000ccトラック, 軍用自動車, 国家経済主義, 産業政策, 保護関税, 製造奨励補助金, 国産車
1. 4 000ccクラス中型トラックの型式設定と量産化
このセクションでは、商工省が主導した4,000ccクラスの1.5~2トン中型トラックの集中生産に向けた取り組みが詳細に記述されています。 国家経済主義政策の一環として、国産3社による合同生産体制の構築を目指し、その具体的な方策としてトラックの型式標準化と量産化が挙げられています。これは、単なる民需拡大ではなく、陸海軍の軍用保護自動車計画と密接に関連しており、国家戦略としての側面が強調されています。 この計画は、日本の自動車産業の第一次再編成を加速させる重要な要素であり、今後の国産自動車産業の基盤を形成する目的があったと推測できます。 文書からは、具体的な国産3社の名称は明示されていませんが、後のセクションで言及される可能性があります。この段階では、4,000ccという排気量と、1.5~2トンという積載量というスペックが、国家の戦略的ニーズを反映していることが伺えます。 型式標準化と量産化によるコスト削減と効率化が、この計画の成功に不可欠な要素であったと考えられます。
2. 製造奨励補助金と保護関税の設定
国家による自動車産業育成政策の具体的な手段として、製造奨励補助金と保護関税の設定が挙げられています。この政策は、国産自動車メーカーが、当時市場を支配しつつあった外国メーカー(特にアメリカメーカー)と競争できるよう、経済的な優位性を提供することを目的としています。補助金は、国産トラックの生産量増加を直接的に促し、保護関税は輸入トラックの価格競争力を弱めることで国産車の市場シェア拡大を支援したと考えられます。 これらの政策の効果は、国産自動車産業の成長と、外国製品に対する依存度軽減に大きく貢献したと考えられますが、同時に、市場の歪みを生む可能性や、競争の抑制につながるリスクも孕んでいたと言えるでしょう。 このセクションでは、補助金の金額や関税率などの具体的な数値は示されていませんが、後のセクションで詳細が明らかになる可能性があります。補助金と関税の組み合わせが、国家経済主義政策における重要なツールとして機能していたことが示唆されています。
3. 共同設計に基づく1 000台規模の生産一体化
このセクションは、4,000cc中型トラックの生産体制確立における、国産3社間の協力体制の構築に焦点を当てています。 1,000台規模の生産一体化という目標を達成するため、国産3社は共同設計というアプローチを取ったことが記述されています。これは、各社の技術や資源を共有することで、効率的な生産体制を構築し、コスト削減や技術向上を目指した戦略であったと考えられます。 共同設計による生産一体化は、単に生産能力の増強だけでなく、技術標準の統一や、将来的な技術開発における協力関係の構築にもつながる重要なステップであったと考えられます。 しかし、この共同設計・生産がどの程度円滑に進められたのか、各社間の利害調整に困難はなかったのかといった点は、このセクションからは読み取れません。 この共同設計の具体的な内容や、各社の役割分担といった詳細は、後のセクションでさらに詳しく解説されるものと推測できます。
II.大衆車時代と農工間格差の拡大
大正12年の関東大震災から昭和6年の満州事変にかけて、近代的輸送機関の確立と機械化により「大衆車」時代が到来した。これは重化学工業への転換と同時に起こり、農村から都市への人口移動を加速、四大工業地帯を中心に近代的都市の発展をもたらした。しかし、農工間賃金格差の拡大という格差経済も同時に生み出した。主要なキーワード: 大衆車, 近代的都市, 四大工業地帯, 農工間格差, 人口移動
1. 近代的都市の発達と大衆車時代の到来
このセクションでは、大正12年の関東大震災から昭和6年の満州事変までの期間における、日本の近代的都市の発達と「大衆車」時代到来の背景が説明されています。関東大震災後の復興と、昭和初期の経済成長を背景に、近代的輸送機関の整備、特に自動車の普及が急速に進みました。 この自動車中心の輸送手段の機械化は、「大衆車」時代を出現させると同時に、軽工業から電力エネルギー中心の重化学工業への産業構造転換をもたらしました。 中小企業群と重化学工業の同時併存的な発展が、この時代の大きな特徴として挙げられており、その結果として農工間の生産力格差、すなわち賃金格差が拡大しました。1920年代の農産物価格の下落は、都市部への人口移動を促進し、四大工業地帯を中心とした近代的都市の発展を促したと説明されています。 この都市化は、大衆消費社会、そして「クルマ社会」の形成へと繋がっていく重要な社会変容であったと捉えることができます。
2. 近代的交通機関の発展 バス タクシー ハイヤーの普及
近代的都市の発展に伴い、バス、タクシー、ハイヤーなどの近代的交通機関が急速に普及した様子が記述されています。特に、鉄道省は昭和5年に東京―上野―両国間で直営自動車小荷物運搬を開始し、岡崎―多治見間で省営バスを運行開始するなど、国家主導による交通網の近代化を積極的に推進しました。 東京市電気局の円太郎バスなども言及されており、これらの事業は地方都市や農村地域にも新しい交通運輸事業を拡大する契機となりました。 タクシー、ハイヤーについても、米田穣によるタクシー自動車株式会社の設立などが紹介され、距離別運賃制度の確立や、時間制運賃のハイヤーとの競争が、それぞれの発展を促したことが説明されています。日本自動車合資会社、山口勝蔵商店、エンパイヤ自動車商会、東京市街自動車株式会社などが、ハイヤー業界を代表する企業として挙げられています。 これらの交通機関の普及は、人々の移動手段を大きく変え、都市の発展に大きく寄与したと考えられます。
3. 大衆車時代と格差経済の展開 農村と都市の所得格差
第一次世界大戦後から昭和6年の満州事変までの約10年間、四大工業都市圏は農村からの急激な人口流入により急速に発展しました。 中小企業群と重化学工業の同時併存的発展は、動力革命と輸送革命をもたらし、産業構造の高度化を促進しましたが、同時に農村と都市間の所得格差を著しく拡大させました。 この農工間賃金格差は、昭和恐慌期に特に顕著となり、農業従事者の所得は鉱工業従事者の所得の28%にまで減少したと記述されています。 この格差拡大は、近代的都市における大衆消費社会、クルマ社会の発展と密接に関連しており、自動車の普及が都市部経済を活性化させる一方で、農村部を相対的に停滞させる要因の一つになったと推測できます。 このセクションでは、「農工間有業者一人当所得とその格差」という図表が参照されていることから、具体的な数値データに基づいた分析が行われていることがわかります。
III.トラック産業の発展と初期の主要企業
トラック産業は乗用車より遅れて発展し、大正期に小倉八三郎による大和運輸株式会社設立などがその始まりであった。 千代田、極東、五玉などの企業もトラックによる大量輸送を開始した。 主要なキーワード: トラック, 貨物自動車, 大和運輸, 輸送革命
1. トラック産業の黎明期 大正時代の状況
このセクションでは、乗用車に比べて遅れて発展した日本のトラック産業の黎明期、特に大正時代の状況について述べられています。 乗合自動車やタクシー、ハイヤーの普及とは対照的に、貨物輸送を担うトラックの普及は比較的遅れており、大正8年に小倉八三郎が大和運輸株式会社を設立して木炭や石炭の運搬を開始したのが、その始まりとして挙げられています。 その後、鮮魚輸送やデパートの商品配達など、トラックによる輸送は徐々に拡大し、千代田、極東、五玉、旭組、国際通運などの企業が大量輸送に乗り出し、戸口から戸口への新しい運搬業務を開始しました。 これらの企業は、手挽荷車や荷物牛馬車に代わる新たな輸送手段としてトラックを導入し、次第に地方都市にも普及させていきました。この記述から、大正時代においても、トラックによる効率的な貨物輸送の需要が高まっていたことが窺えます。大和運輸株式会社の設立は、トラック輸送の商業化において重要な一歩であったと言えるでしょう。
2. トラック輸送の拡大と新たな輸送形態の確立
大正時代に始まったトラック輸送は、次第に拡大し、新たな輸送形態を確立していった様子が記述されています。 大和運輸株式会社による木炭・石炭運搬に始まり、鮮魚輸送、デパートの商品配達など、トラックは多様な貨物輸送に対応できる汎用性を示しました。 千代田、極東、五玉などの企業は、トラックによる大量輸送を展開し、「戸口から戸口への新しい運搬業務」を開始したと記述されており、これは従来の輸送手段では困難であった、より直接的で効率的な配送システムの確立を意味します。 この記述からは、トラックの普及が、単に輸送手段の近代化にとどまらず、物流システム全体の効率化に貢献したことが分かります。 また、トラック輸送の拡大は、地方都市にも及んだとされており、手挽荷車や荷物牛馬車といった従来の輸送手段を徐々に置き換えていったことが示唆されています。このことは、トラックが経済活動の活性化に大きく寄与したことを示しています。
IV.鉄鋼飢饉と鉄鋼自立化政策
第一次世界大戦により鉄鋼輸入が途絶えた「鉄鋼飢饉」を受け、政府は八幡製鉄所増産や民間製鉄所の育成、そして「製鉄業奨励法」の制定など、鉄鋼自立化政策を推進した。 中国からの鉄鉱石供給が不可欠となり、対支二十一カ条要求はその背景にある。主要なキーワード: 鉄鋼飢饉, 八幡製鉄所, 鉄鋼自立化, 対支二十一カ条, 資源確保
1. 鉄鋼飢饉の発生と緊急性の高まり
このセクションは、第一次世界大戦勃発による鉄鋼輸入の途絶、もしくは激減という「鉄鋼飢饉」の深刻な状況から始まります。 日本軍は、染料、ソーダ、鉄鋼といった重要な物資の自給化と増産を閣議に請願し、その緊急性を訴えました。 参謀総長長谷川好道は、陸軍大臣岡市之助に製鉄能力の拡大を要請しており、国家レベルでの危機意識の高さがうかがえます。 大正2年時点での銑鉄生産量は官営八幡製鉄所が23万トン、民間の生産量を合わせても120万トンの需要に対し約4分の1の供給力しかなかったとあり、鉄鋼不足が国家存亡に関わる問題であったことが強調されています。 この鉄鋼不足は、日本経済の基盤を揺るがすものであり、その解決策が喫緊の課題であったことが分かります。 この危機的状況が、政府による鉄鋼自立化政策の推進を強く後押ししたと言えるでしょう。
2. 鉄鋼自立化政策 官民連携による増産計画
鉄鋼飢饉への対応として、政府は官民連携による鉄鋼増産計画を策定し、実行に移しました。 具体的には、官営八幡製鉄所の増産計画と、民間製鉄所の育成・発展が推進されました。 大正5年には製鉄業調査会が設置され、翌年には「製鉄業奨励法」が公布されました。この法律は、一定規模以上の製鉄能力を持つ企業に対し、輸入税、営業税、所得税の免除や土地収用の優遇措置といったインセンティブを提供することで、鉄鋼生産の拡大を促進することを目指しました。 この政策の結果、八幡製鉄所に加え、三菱製鋼、満鉄(鞍山)、本渓湖、東洋製鉄などの新興製鉄所が設立、もしくは設備拡張を行い、日本の鉄鋼生産能力は飛躍的に向上しました。 また、中国からの鉄鉱石供給が不可欠となり、対支二十一カ条要求もこの鉄鋼自立化政策と深く関わっていることが示唆されています。日本興業銀行や横浜正金銀行による大規模な融資も、この政策を支える重要な要素であったと考えられます。
3. 対支二十一カ条と国家経済主義
このセクションでは、鉄鋼自立化政策と密接に関連する「対支二十一カ条」の要求について説明されています。 この要求は、特に山東省、南満州・東部蒙古、漢冶萍公司に関する経済的要求を主軸としており、鉄鋼資源の確保を最重要課題としていたことが明確に示されています。 「鉄綱は国家なり」という言葉が示すように、鉄鋼資源の確保は日本の国家経済主義政策の中核をなすものであり、中国からの鉄鉱石供給が日本経済の生命線として認識されていたことが分かります。 西原借款も、対支二十一カ条要求を実現するための重要な資金源として利用されたと記述されており、政府による経済的支援が、鉄鋼産業の自立化に大きく貢献したことがわかります。 このセクションは、日本の鉄鋼産業が、植民地支配と資源獲得を前提とした国際的分業体制の中に位置付けられていたことを示しており、国家経済主義が日本の産業政策に及ぼした影響を明らかにしています。
V.化学工業の発展と自給自足経済への志向
第一次世界大戦下の染料不足を契機に、三井鉱山は化学工業に進出し、アリザリンブルーSなどの染料国産化に成功した。また、ハーバー・ボッシュ法によるアンモニア合成技術の導入も進んだ。これは、臨時産業調査会が推進した「鉄、石炭、ソーダ」を中心とした自給自足経済(大東亜共栄圏構想と関連)を目指す政策と軌を一にする。主要なキーワード: 化学工業, 染料, ハーバー・ボッシュ法, 自給自足経済, 大東亜共栄圏
1. 戦時下の染料不足と三井鉱山の化学工業進出
このセクションは、第一次世界大戦によるドイツからの染料輸入の途絶という問題から始まります。 それまでドイツのIG社などからの輸入に依存していたアリザリンブルーSなどの染料が不足したことで、日本の化学工業の発展が急務となりました。 三井鉱山は、石炭コークスの副産物であるベンゾール、ナフタリンなどを利用した化学工業への進出を図り、副産物であるアンスラセンから染料の原料となるアリザリンの製造に成功しました。 大正2年には、東京工業試験所との協力の下、アリザリンの製造実験に成功し、大正5年には三井染料(三井鉱山の関連会社)でアリザリン工場が建設され、製品が市場に出されました。 三井鉱山はその後も量産化と品質改善に取り組み、クロム電解室の新設なども行っています。この事例は、資源の有効活用と技術開発によって、輸入に依存していた重要な産業分野における自立化を達成したことを示しています。
2. ハーバー ボッシュ法の導入と肥料化学工業の発展
第一次世界大戦下の資源確保政策の中で、アンモニア合成のハーバー・ボッシュ法の導入と肥料化学工業の発展が重要な位置を占めていました。 大正7年には臨時窒素研究所が設立され、ハーバー・ボッシュ法によるアンモニア合成の実験が行われました。 この研究所の研究成果は、後に東京工業試験所に吸収合併されましたが、森矗昶の昭和肥料(後の昭和電工)のアンモニア合成技術に繋がる重要な成果をもたらしました。 農商務大臣牧野伸顕は、「ソーダ灰の自給」とハーバー・ボッシュ法の実施に全力を注いでおり、肥料生産の自立化が国家政策として重視されていたことが分かります。 このセクションでは、ハーバー・ボッシュ法の導入が、日本の肥料化学工業の発展に大きく寄与したことが示されています。また、政府による研究開発への積極的な投資と支援が、技術革新を促進した重要な要因であったことが分かります。
3. 臨時産業調査会と自給自足経済 大東亜共栄圏構想
このセクションでは、「鉄と石炭とソーダ」を基幹産業とした自給自足経済を目指した臨時産業調査会と、その国家経済主義的政策が解説されています。 第一次世界大戦中に発展した重化学工業を基盤に、満州・支那の資源を活用して自給自足経済を構築しようとする「戦後経営」構想、ひいては大東亜共栄圏構想が、この調査会の主要な目的でした。 仲小路廉農商務大臣は満州・支那での資源調査に重点を置き、小磯國昭砲兵少佐の「帝国国防資源」と同様な、日満支ブロックによる自給経済圏の構想が、この調査会に反映されていると説明されています。 植村甲午郎の証言から、この調査会には最初から戦時体制を見据えたアウタルキー的な思想があったことが示唆されています。 このセクションは、日本の国家経済主義が、資源確保と自給自足経済を目指した政策と深く結びついていたことを示しています。そして、その政策が、後の大東亜共栄圏構想へと繋がっていく重要なステップであったことが分かります。
VI.商工省設立と産業政策
米騒動や第一次大戦後の不況を背景に、大正14年、農商務省から商工省が分離独立。重点は重化学工業を中心とした産業政策、輸出振興策、中小企業対策に置かれた。商工大臣 高橋是清、次官 四条隆英 などが重要な役割を果たした。主要なキーワード: 商工省, 産業政策, 輸出振興, 中小企業, 重化学工業
VII.昭和恐慌期の自動車産業 ビッグスリーと国産メーカーの危機
昭和恐慌期には、日本フォード、日本GMなどのビッグスリーによる輸入組立車の増加が国産メーカー(石川島自動車、ダット自動車、ガス電など)を圧迫した。「軍用自動車補助法」等による政府支援が国産メーカーの生き残りに重要な役割を果たした。主要なキーワード: 昭和恐慌, ビッグスリー, 国産車メーカー, 軍用自動車補助法, 日本フォード, 日本GM, 石川島自動車, ダット自動車, ガス電
VIII.標準型式自動車と国産3社の連携
昭和7~9年、商工省は国産自動車工業確立対策として「標準型式自動車」を推進。国産3社(石川島、ダット、ガス電)と鉄道省が共同設計・生産を行い、製造奨励金が支給された。この取り組みは軍用自動車の供給にも貢献した。主要なキーワード: 標準型式自動車, 共同設計, 国産3社, 製造奨励金, 軍用自動車
1. 標準型式自動車の構想と委員会の設立
このセクションでは、昭和恐慌期における国産自動車産業の振興策として、商工省が主導した「標準型式自動車」の開発計画が説明されています。 当時、国産自動車産業は、アメリカを中心とした外国メーカーの進出によって大きな打撃を受けており、その対策として、国産自動車の標準化と量産体制の確立が不可欠とされていました。 そのため、関係省庁や陸軍関係者を含む18名からなる委員会が設置され、「標準型式自動車」の開発、生産・販売体制、政府による保護・助成策などが検討されました。 この委員会では、単一車種の標準化によって、生産効率の向上とコスト削減を目指すと同時に、政府による支援によって国産自動車産業の競争力を強化しようという狙いがありました。 陸軍整備局の林桂と鉄道省工作局車輌課長の朝倉希一が、この「標準型式自動車」構想をリードしたことが記述されています。この委員会の設立は、政府主導による国産自動車産業の保護育成政策の始まりを示しています。
2. 国産3社と鉄道省の共同設計と生産
「標準型式自動車」の開発においては、国産3社(具体的な社名は本文中に明記されている)と鉄道省が緊密に連携し、共同設計と生産体制が構築されたことが説明されています。 鉄道省の島秀雄を中心とした技術陣と、各社の技師陣(楠木直道(石川島)、小西晴二(ガス電)、後藤敬養(ダット)、陸軍上西甚蔵など)が共同で設計を行い、エンジンやフレーム、トランスミッションなどの主要部品の製造分担が行われました。 この共同設計は、各社の技術ノウハウの共有と、効率的な資源配分を実現するための重要な戦略でした。 共同生産組合方式を採用したことで、競争ではなく協力による生産体制の構築が図られています。 この協力体制は、個々の企業では困難な大規模生産を可能にし、国産自動車産業全体の競争力強化に大きく貢献したと考えられます。 6気筒4,390ccの1.5トンと2トントラック、およびバスの共通シャシーという具体的な仕様も記述されています。
3. 商工省の支援と標準型式自動車の生産 販売
商工省は、昭和7年から9年にかけて、国産自動車工業確立対策として、工業組合法を骨格とした標準型式自動車の生産・販売を推進しました。 具体的には、製造奨励金制度が導入され、昭和8年には1台あたり500円の奨励金で150台、昭和9年には1台あたり250円の奨励金で700台の生産が命令されました。 この政府による財政的支援は、国産自動車メーカーの生産活動を大きく後押ししたと考えられます。 商工省による標準型式自動車の生産・販売体制の確立は、国産自動車産業の自立化において重要な成果でした。 また、陸軍は、この標準型式自動車の生産によって、「軍用自動車補助法」の限界を克服し、満州国への中級車配備など、総力戦体制の整備に繋がったと評価されています。 このセクションでは、政府の積極的な介入と、国産自動車メーカー間の協力が、国産自動車産業の成長に大きく貢献したことが示されています。
IX.ディーゼルエンジンの導入と自動車産業再編
陸海軍の需要と燃料節約の観点からディーゼルエンジンの導入が進んだ。鉄道省は省営バスにディーゼルエンジン車を導入し、三菱などのメーカーがディーゼルエンジンの開発・生産に貢献した。これは後の自動車産業再編、日野自動車やイスズ自動車の台頭を促した。主要なキーワード: ディーゼルエンジン, 省営バス, 燃料節約, 自動車産業再編, 日野自動車, イスズ自動車
