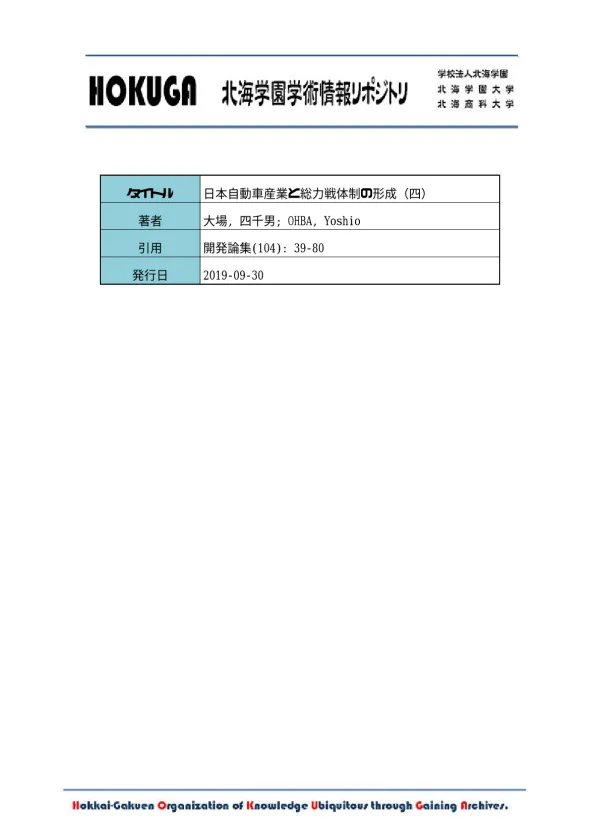
総力戦体制と自動車産業
文書情報
| 著者 | 大場 四千男 |
| 専攻 | 開発論 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.50 MB |
概要
I.日本における総力戦体制と日支共同経営
本資料は、太平洋戦争に向けた日本の総力戦体制構築とその歴史的意義、特に日支共同経営構想を中心に論じています。田中義一と寺内正毅といった主要人物の役割、そして対支21ヵ条要求がその礎となった点が強調されています。石油資源の不足を補うため、インドネシア石油獲得を目指した日蘭会商の失敗や、アメリカの石油禁輸政策が戦争への道を加速させたことも記述されています。この体制は天皇制国体論を日本資本主義のエトスとして発揮させ、日本の歴史を世界史との協調と対立の根源として位置づけています。
1. 石油危機と総力戦体制への突入
本節は、日本の国防資源における石油の不足という問題から始まります。インドネシアの石油獲得を目指した日蘭会商の失敗は、アメリカによる石油禁輸政策と相まって、日本を太平洋戦争、そして総力戦体制への道へと突き進ませました。この石油危機が日米開戦、ひいては太平洋戦争勃発の直接的な引き金の一つとなったことが強調されています。 文章全体を通して、この石油危機が、日本の資源戦略、ひいては総力戦体制構築の背景として重要な位置を占めていることが分かります。 この体制は単なる軍事力強化だけでなく、日本資本主義のエトスとして天皇制国体論と深く結びつき、国家の存亡をかけた総力戦へと導くための包括的な戦略であったことが示唆されています。
2. 対支21ヵ条要求と総力戦構想の基盤
この節では、大隈重信と加藤高明が推進した対支21ヵ条要求が、日本の総力戦構想と総力戦体制の基礎を築いたと論じています。対支21ヵ条要求は、単なる領土的野心ではなく、資源確保や経済圏拡大という国家戦略の一環として位置付けられています。この要求が、後の総力戦体制へと繋がる重要なステップであり、その歴史的意義が強調されています。 文章では、六章の内容を踏まえて七章で三人の総力戦構想を分析するという記述から、この対支21ヵ条要求が、続く章で分析される三人の軍人による総力戦構想の出発点、いわば「礎」として機能していたことが分かります。資料の解釈と分析を通じて、その歴史的意義と役割が明確にされることが、この節の主要な目的となっています。
3. 天皇制国体論と日本資本主義のエトス
総力戦構想と総力戦体制は、天皇制国体論というイデオロギーと密接に関連していることが指摘されています。天皇制国体論は、単なる政治体制ではなく、日本資本主義の精神的支柱、エトスとして機能し、国民を総力戦へと駆り立てる役割を果たしました。 この節では、天皇制国体論が、日本の歴史における世界との協調と対立という二面性を生み出す根本原因の一つとして捉えられています。このイデオロギーが、国家のアイデンティティと、世界情勢における日本の立ち位置を規定する上で重要な役割を果たしていたことが示唆されています。総力戦体制の構築には、このようなイデオロギー的背景を理解することが不可欠であることが強調されています。
II.資源確保と兵要地誌の限界
資料では、開戦に備えた資源確保の必要性が強く訴えられています。既存の兵要地誌が、天候や地形といった情報に偏り、長期的な資源調達や需給調整の仕組みを欠いていた点が批判されています。特に、鉄鉱石や石油といった資源の不足が深刻な問題として認識されており、国内自給自足の限界と、支那からの資源獲得の必要性が強調されています。
1. 兵要地誌の現状と限界
この節では、当時の兵要地誌の内容と限界が詳細に分析されています。兵要地誌は、各地方の天候、気象、地形、人口、生産量などの情報を網羅し、作戦遂行に役立つ詳細な記述を特徴としていました。しかし、その内容は、戦闘、行軍、宿営、給養といった軍事作戦に直接関連する事項に限定されており、内地からの長期的な補給体制、資源調達、軍需品の生産体制、需給調整といった、戦争継続に不可欠な要素に関する記述は著しく不足していました。長期的な資源確保や、平時からの需給調整システムの構築が、当時の兵要地誌には全く考慮されていなかった点が、この節で強く批判されています。 これは、戦争遂行に必要な資源の安定供給という観点から、兵要地誌がその役割を果たせていなかったことを示しています。この不足が、後の資源不足問題へと繋がる重要な要因であったことが示唆されています。
2. 資源自給の困難さと兵要地誌の役割転換
ドイツが資源自給によって長期にわたる戦争を継続している事例を紹介することで、日本の資源自給能力の限界が示唆されています。ドイツの事例を参考に、大規模な戦争に直面した場合、日本の生産資源では国民の生存と作戦の継続が困難であることが指摘されています。そのため、兵要地誌の役割を、単なる情報収集から、資源の確保・生産計画策定へと転換させる必要性が主張されています。 具体的には、不足する資材の数量を究明し、兵要地誌が整備する地域から、どのような資源を、どの程度、どのようにして調達・生産するのかを検討し、将来の戦時における具体的な計画を策定することが、兵要地誌班の新たな任務として提示されています。これは、既存の兵要地誌の機能を拡張し、戦争遂行に必要な資源確保の戦略を担わせる必要性を示す重要な主張です。
3. 軍事調査会の機能不全と新たな対策
大正3年に設立された陸軍省内の軍事調査会は、情報収集には務めていたものの、計画立案や戦争遂行に直接的な貢献はできていなかったと批判されています。この軍事調査会の不十分さを背景に、兵要地誌の役割転換の必要性が改めて強調されています。 既存の軍事調査会の機能不全を克服するため、国民の生存と作戦軍の活動力維持という観点から、国家機能を最大限に発揮しつつ、不足する資材の数量を精査し、その不足を補うための具体的な方策を策定することが重要視されています。この節では、単なる情報収集にとどまらない、より実践的で戦略的な資源管理システムの必要性が、軍事調査会の失敗例を通して明確に示されています。
III.田中義一の対支政策と日支製鉄事業
田中義一は、第一次世界大戦勃発を好機と捉え、日支共同経営、特に日支製鉄事業の共同経営を提唱しました。代表的な政策文書として「対支経営私見」と「日支製鉄事業の共同経営に就て」が挙げられます。彼は、大冶鉄山をはじめとする支那の豊富な鉄鉱石資源に着目し、日本側の資本と技術、支那側の資源を組み合わせることで、鉄の自給自足を目指す戦略を展開しました。張勲の清朝復辟運動への対応や、馮国璋への警告文なども記述されています。重要な企業として、**漢冶萍公司(Han-Yeh-Ping)**が挙げられ、その国有化問題なども触れられています。
1. 田中義一の経歴と軍における役割
この節では、田中義一の経歴と軍における重要な役割が概説されています。日清戦争、日露戦争への従軍経験、参謀本部勤務、陸軍大学校教官、陸軍省軍事課長などを経て少将に昇進した彼のキャリアは、軍部における彼の影響力の大きさを示しています。明治44年には大隈重信を歩兵第三連隊に招き、在郷軍人会を組織するなど、軍内部の改革にも取り組んでいたことがわかります。また、総力戦体制の一環として自動車部隊の重要性をいち早く認識し、軍用自動車調査委員長に就任したことも記されています。これらの事実は、田中義一が軍部の中枢において、近代戦に対応した軍事体制の整備に積極的に関わっていたことを示しています。 第一次世界大戦勃発後は、陸軍中将補参謀次長として二コ師団増設問題や対独戦に関わり、その中で「対支経営私見」と「日支製鉄事業の共同経営に就て」を発表しました。これは、彼の対中政策、ひいては日中関係における彼の役割を理解する上で重要な要素となります。
2. 対支経営私見 と 日支製鉄事業の共同経営
本節の主題である田中義一の二つの主要な政策文書、「対支経営私見」と「日支製鉄事業の共同経営に就て」の内容が解説されています。「対支経営私見」では、第一次世界大戦下の国際情勢を背景に、日中両国の協力による東亜の自立(自活)を強く主張しています。欧米列強からの圧迫からの解放と、将来的な欧米列強からの脅威への備えとして、日中提携の必要性を訴えています。一方、「日支製鉄事業の共同経営に就て」は、鉄鋼資源の重要性と、日中協力による鉄の自給自足体制の構築を目的としています。この文書は、後述される具体的な日中合弁製鉄会社設立構想へと繋がる重要な論拠となっています。 これらの文書は、田中義一が第一次世界大戦という国際情勢の変化を捉え、日本と中国の連携による東アジアの自立と発展、そして資源確保を重視した政策構想を描いていたことを示しています。
3. 張勲復辟運動と馮国璋への警告 日中関係の複雑さ
田中義一は、張勲による清朝復辟運動に反対し、共和政治体制の維持を図っていました。しかし、張勲の復辟運動は田中義一の「東亜救済の政策」と衝突し、欧米列強の介入を招く可能性を危惧した田中は、馮国璋に警告文を送っています。この警告文では、中国国内の行政組織の統一と経済発展の必要性を訴え、日本の経済的親善政策の重要性を強調しています。多賀宗之助中佐が、田中義一と馮国璋の間を取り持つ役割を果たしていたことも記述されています。 このエピソードは、田中義一の対中政策が、単なる経済協力にとどまらず、中国の政治情勢の安定にも深く関わっていたことを示しています。また、この出来事は日中関係の複雑さ、そして欧米列強の影の存在を改めて浮き彫りにしています。大冶鉄山などの資源開発を巡る日中間の利害関係、そして欧米列強の思惑が複雑に絡み合っていた状況が見て取れます。
4. 漢冶萍公司と日支合弁製鉄会社の構想
この節では、漢冶萍公司(Han-Yeh-Ping) と、日中合弁による大製鉄会社設立の構想が解説されています。大冶鉄山の豊富な鉄鉱石資源に着目し、日中両国の資源と技術を統合することで鉄の自給自足を図ろうとする田中義一の戦略が示されています。漢冶萍公司の国有化問題や、日本側の資本提供、そして枝光製鉄所の提供による合弁事業の推進が検討されています。 日中両国のそれぞれの欠点(中国:資本不足、化学工業の不振、日本:鉄鉱石の産出不足)を補完し合うことで、日中経済提携の基礎を築き、鉄の独立自給を達成しようとする構想が詳細に記述されています。この合弁会社設立構想は、田中義一の対中政策の核心であり、日中両国の経済的、そして政治的な結びつきを強めるための重要な戦略であったことがわかります。
IV.経済的親善提携の課題と朝鮮 満蒙の開発
日中経済提携の推進において、日本商人の不正行為や、支那側の不信感・猜疑心といった障壁が指摘されています。その克服のためには、精神的な親睦と相互信頼の構築が不可欠であると主張されています。また、朝鮮と満蒙の開発も、日本にとって重要な資源確保策として位置付けられています。寺内正毅は、朝鮮における「特殊施設」(モノカルチュア型農業など)による資源生産と日本への輸出を重視し、「母国に裨益する」という政策目標を掲げていました。東洋拓殖株式会社や朝鮮銀行といった機関が、この政策の中心的な役割を果たしていました。
1. 日中経済提携の障害と真の親善の必要性
この節では、日中経済提携を阻む要因として、日本の奸商による不正行為や、中国側における日本人への不信感、猜疑心、悪感といった問題が指摘されています。中国の実業家の証言を引用し、日本に対する負の感情が蓄積している現状が示されています。 単なる経済的な協調だけでなく、両国民間の精神的な親睦、形而上の結合が、真の親善と誠意ある提携の土台となることが強調されています。表面的な協調ではなく、根底的な信頼関係の構築なしには、経済的提携は成功しないという警鐘が鳴らされています。特に、小資本で中国に進出する日本人による不正行為が、日中関係全般に悪影響を与えていることが懸念されています。阿片密売やモルヒネの不正販売といった深刻な問題も取り上げられ、これらの問題が解決されない限り、経済的共同発展は期待できないと断言されています。
2. 朝鮮における 特殊施設 と資源開発
朝鮮における総督府の経済政策である「特殊施設」が紹介され、その歴史的役割と意義が論じられています。「特殊施設」とは、米穀、食塩、綿花などの生産を促進し、日本への資源供給を目的とした政策です。東洋拓殖株式会社、朝鮮銀行、満鉄といった機関が、この政策の推進に重要な役割を果たしていました。 寺内正毅は「特殊施設」によって生産された資源を日本へ移出することで「母国に裨益する」と主張し、長期的な視点での朝鮮開発の必要性を訴えています。朝鮮への21ヵ条要求の達成も、この「特殊施設」による資源開発政策と密接に関連していることが示唆されています。この節では、朝鮮の資源が日本の経済発展に貢献するという考え方が、明確に示されています。同時に、モノカルチュア型農業の促進による食糧増産や、鉱山開発による雇用創出なども、「特殊施設」の政策目標として挙げられています。
3. 朝鮮における農業 鉱山開発の現状と課題
朝鮮の人口の多くが農業に従事していることを踏まえ、農業生産性の向上、耕地面積の拡大が朝鮮開発における急務であるとされています。模範農場や伝習所の設置による農業技術の普及、作物や家畜の改良、副業の奨励などの取り組みが紹介されています。これにより、朝鮮の生産物総額が倍増し、米穀の余剰生産も可能になったと報告されています。 しかし、耕地面積は全土の12%に過ぎず、その利用も十分ではないという課題も指摘されています。大地主による土地兼併の問題や、内地人による土地の濫買なども問題視されており、自作農の保護が重視されています。さらに、朝鮮の豊富な鉱山資源の開発についても言及されており、内地有力者や外国人の開掘権回収による鉱山経営の促進を通じて、雇用創出が図られたとされています。この節では、朝鮮の農業と鉱山開発の現状と将来の可能性、そしてその中で存在する課題が示されています。
V.金融 放資機関の整備と軍需工業動員
寺内内閣は、日支共同経営を推進するため、東亜興業株式会社などの金融・放資機関の整備強化を行いました。台湾銀行や朝鮮銀行の役割拡大、そして海外投資銀行団の設立などが挙げられます。支那への借款供与も積極的で、交通銀行への借款や、鉄道建設、水害救済のための借款などが実施されています。さらに、戦争に備えた軍需工業動員の必要性も強く訴えられ、軍用自動車の製造・使用促進のための補助法案なども提出されています。
1. 寺内内閣による金融 放資機関の整備強化
この節では、寺内内閣が対支投資を促進するため、金融・放資機関の整備強化に力を入れていたことが述べられています。具体的には、東亜興業株式会社の資本金増資、組織・業務の刷新、台湾銀行と朝鮮銀行の保証準備・資本金の増加、日本興業銀行による政府保証債券の発行、そして海外投資銀行団の設立などが挙げられています。これらの施策は、中国への投資を促進し、日本経済圏の拡大を図るための重要な取り組みとして位置づけられています。 特に、海外投資銀行団の設立は、政府保証付きの興業債券発行を主要銀行が共同で支援するというものであり、国家を挙げての対支投資促進策であったことが伺えます。 これらの金融機関の整備強化は、単なる資金供給にとどまらず、中国への経済的影響力を拡大し、日中経済圏構築という国家戦略を支える基盤として機能するものでした。
2. 中国への経済借款と主要な融資事例
中国への借款は、政治借款と経済借款に分類でき、その中でも経済借款が詳しく説明されています。 交通銀行への借款(2500万円)、吉長鉄道、米支運河、四鄭鉄道、京畿水災救済、有線電信、吉会鉄道、黒吉両省金鉱・森林、満蒙四鉄道といった具体的な事業への融資が事例として挙げられています。 米支運河借款は、アメリカン・インターナショナル・コーポレーションとの共同投資という点で、日米資本家間の経済提携の第一歩を示すものとして注目されています。これらの融資は、中国の経済発展を支援するという名目で実施されていましたが、同時に日本の経済的影響力を拡大し、中国の資源や市場を日本の経済圏に組み込むための戦略的な側面も持っていたと考えられます。 特に、第一次世界大戦への参戦により財政難に陥っていた中国政府にとって、日本の借款は不可欠な条件となりつつあったことが強調されています。
3. 軍需工業動員法案と軍用自動車補助法案
この節では、戦争に備えた軍需工業動員の必要性と、そのための法案が紹介されています。軍需工業動員法案は、戦時の軍需品供給を迅速かつ確実に確保するために、平時から工場能力の調査・準備を行うことを目的としています。 日本の機械工業の不足を補うために、軍用自動車の製造・使用を民間レベルで促進させるための補助法案も提出されました。この法案は、戦時における輸送手段の確保を目的とし、民間企業への補助金支給によって自動車の生産と普及を促進しようとしています。 これは、戦争を長期的に戦うためには、民間の産業力を国家動員する必要があるという認識が、政府内にあったことを示す重要な証拠となっています。これらの法案は、総力戦体制における軍需品の安定供給を確保するための重要な政策であり、平時からの準備の重要性を示しています。
