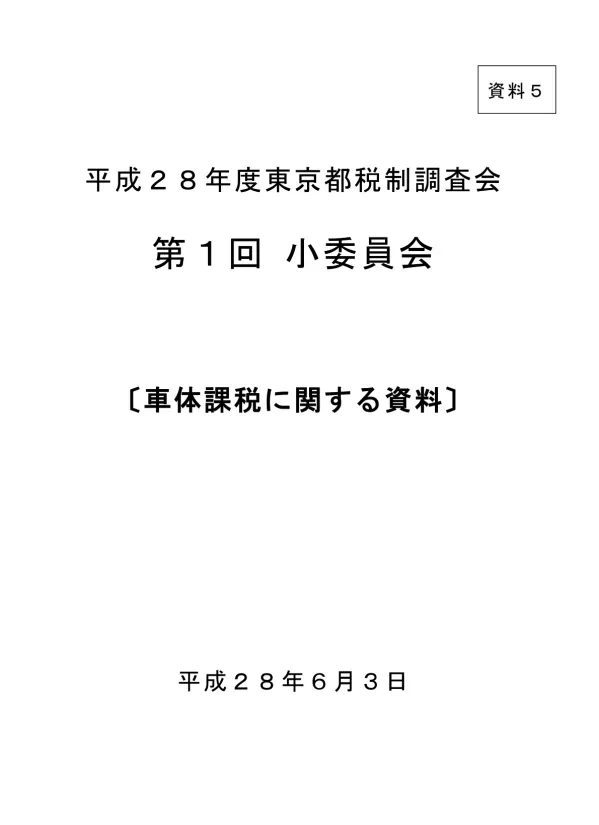
自動車税制改革:環境性能割の現状と課題
文書情報
| 著者 | 東京都税制調査会 |
| 場所 | 東京都 |
| 文書タイプ | 資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.74 MB |
概要
I.自動車税の概要と税率
本資料は、日本の自動車に関する主要な税金である自動車税(Jidoshazei)、自動車取得税(Jidosha Shutokuzei)、自動車重量税(Jidosha Juuryouzei)、および軽自動車税(Keijidoshazei) の概要と税率について説明しています。 自動車税は、自家用車、営業用車の種別、排気量等により税率が異なり、平成26年度の税収は1兆5,562億円に上ります。取得価額に基づく自動車取得税は、エコカー減税の対象車種も存在し、平成26年度の税収は1,075億円でした。一方、自動車重量税は車検時に支払われ、税収は6,476億円(平成28年度予算)です。軽自動車税は、軽自動車の所有者に課税され、環境性能に応じて税率が異なる軽自動車税環境性能割が含まれています。これらの税金は、道路整備や地方財政に充当されています。
1. 自動車税の基礎情報
昭和25年に創設された自動車税は、二輪の小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車を除く自動車を課税対象としています。平成26年度の税収は1兆5,562億円に達し、都道府県と市町村の道路に関する費用に充当されています。税率は自動車の種別、排気量などによって異なり、例えば自家用乗用車(1,500cc超2,000cc以下)は39,500円とされています。納期は5月中とされており、都道府県の条例で定められています。歴史的には、昭和33年に軽自動車が課税対象から除外され軽自動車税が創設され、昭和54年には普通乗用車の税率区分の変更(軸距→排気量)が行われています。昭和28年以降、11回の税率改正が行われ、最終改正は平成元年度でした。近年では、平成21年の道路特定財源の一般財源化に伴い、自動車税は目的税から普通税に変更され、使途制限が廃止されました。 この税金は地方公共団体の財政基盤を支える重要な役割を担っています。
2. 自動車取得税の概要
昭和43年に創設された自動車取得税は、二輪の小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車を除く自動車の取得を課税対象としています。課税標準は自動車の取得価額で、本則税率は取得価額の3%です。平成26年度の税収は863億円でした。自家用自動車(軽自動車を除く)は3%の税率が適用され、営業用自動車と軽自動車は2%(暫定措置、本則は3%)となっています。免税点は50万円(平成30年3月31日まで、本則は15万円)とされています。納税義務者は主たる定置場の所在地において当該自動車を取得した者であり、都道府県に納付された税額の95%のうち、70%は市町村(特別区含む)に交付されます。政令指定都市には国・県道管理分として、政令市特例分がさらに交付されます。平成21年度の税制改正により、自動車取得税も目的税から普通税に改められ、使途制限が廃止されました。
3. 自動車重量税の仕組み
昭和46年に創設された自動車重量税は、車検時(自動車の種類に応じて1~3年ごと)に支払われる税金です。納付方法は自動車重量税印紙納付(臨時検査等にあっては現金納付)で、納税地は車検証の交付等の事務をつかさどる運輸支局等となります。平成28年度の予算額は6,476億円(国税分3,850億円、譲与税分2,626億円)です。平成22年度以降は、国と市町村への譲与割合が、国:593/1000、市町村:407/1000となっています。自動車リサイクル法に基づき、適正に解体された自動車については、自動車検査証の残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。また、公害健康被害の補償等に関する法律により、国の一般財源分の一部が公害補償対策に充当されています。この税金は、自動車の保有・利用に関連した費用を負担させる仕組みとして機能しています。
II.エコカー減税と燃費基準の達成状況
資料では、エコカー減税対象車の割合や、平成27年度および平成32年度燃費基準達成状況の推移を示しています。低燃費・低排出ガス車の普及促進を目的としたエコカー減税は、新車販売台数に占める割合を増加させています。燃費基準達成車は年々増加傾向にあり、環境性能の向上が進んでいることが分かります。具体的な数値はグラフや表を参照ください。
1. エコカー減税の対象台数と割合
このセクションでは、新車販売台数に占めるエコカー減税対象台数の割合の推移について記述されています。資料は、一般社団法人日本自動車工業会ホームページの資料に基づいており、登録車と軽自動車を合わせた数値を示しています。具体的な数値やグラフは提示されていませんが、エコカー減税による環境配慮型車両の普及促進効果を検証するための重要な指標であることがわかります。この割合の推移を見ることで、エコカー減税政策の効果や、今後の方向性について考察することができます。さらに、このデータは、燃費基準達成車や低排出ガス車の販売台数増加と関連付け、環境政策の効果を多角的に分析する上で役立ちます。 軽自動車を含む様々な車種におけるエコカー減税の適用状況を詳細に分析することで、より効果的な環境政策の策定に貢献できるでしょう。
2. 平成27年度および平成32年度燃費基準達成状況
本セクションは、新車販売台数における平成27年度および平成32年度燃費基準達成状況について、総務省自治税務局資料および日本自動車工業会ホームページのデータを基に分析しています。平成27年度の達成状況は販売台数ベースで、平成26年度は4月~8月の台数を元に算出されています。一方、平成32年度の達成状況は国土交通省データ(平成26年4月~8月の登録台数ベース)を元に総務省が試算したものです。この分析から、それぞれの年度における燃費基準達成車の割合や、その推移を把握することができます。 このデータは、日本の自動車産業における燃費向上技術の進歩や、政府の燃費基準達成に向けた施策の効果を評価する上で重要な指標となります。 さらに、達成状況の地域差や車種別の違いを詳細に分析することで、より効果的な環境政策の立案に繋がる可能性があります。
III.次世代自動車の普及と諸外国の動向
次世代自動車(Jidasei Jidosha)である電気自動車、ハイブリッド自動車等の普及台数の推移が示されています。日本市場における普及台数は増加傾向を示していますが、諸外国と比較した際の普及率や政策の比較分析も必要です。 諸外国では、CO₂排出量を基準とした自動車税や、ボーナス・ペナルティ制度といった環境配慮型の課税制度が導入されており、日本の制度との比較検討が必要となっています。例えば、ドイツでは自動車流通税にCO₂排出量を基準に設定し、イギリスでは自動車税の税率をCO₂排出量基準に変更しています。
1. 日本市場における次世代自動車の普及推移
このセクションでは、日本市場における次世代自動車の普及台数の推移を、一般社団法人日本自動車工業会「環境レポート2016」を元に示しています。具体的には、電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル乗用車、天然ガス自動車といった次世代自動車の種類別に、普及台数の推移が記述されていると考えられます。ただし、具体的な数値やグラフは提示されていません。このデータは、日本の自動車市場における環境技術の普及状況や、政府の環境政策の効果を測る上で重要な指標となります。 さらに、各車種の普及率の比較や、普及を阻む要因の分析を行うことで、今後の環境政策や技術開発の方向性を検討する上で役立つ情報となります。 電気自動車や燃料電池自動車といった、特に環境負荷の低い次世代自動車の普及促進に向けた政策効果の検証が重要となります。
2. 諸外国の車体課税におけるCO₂排出基準導入の動き
このセクションは、環境省ホームページや関連報告書などを参照し、諸外国における車体課税の改革、特にCO₂排出基準導入の動向についてまとめています。具体的には、ドイツ、イギリス、ノルウェー、フィンランド、アイルランドなどの国々におけるCO₂排出量を基準とした課税制度や、ボーナス・ペナルティ制度などの導入時期や内容が記述されていると考えられます。ドイツでは自動車流通税にCO₂排出量を基準に設定、イギリスは自動車税の税率をCO₂排出量基準に変更、ノルウェーは自動車登録税にCO₂排出量基準を追加し車両税を導入、アイルランドはボーナス・ペナルティ制度を導入するなど、各国で異なるアプローチがとられていることがわかります。これらの諸外国の取り組みを分析することで、日本の自動車税制におけるCO₂排出量への対応や、環境政策の有効性について検討する上で役立つ示唆が得られます。 特に、CO₂排出量が少ない車両への優遇措置や、排出量の多い車両へのペナルティといった具体的な政策効果の分析が重要です。
IV.燃料課税と車体課税の国際比較
資料は、日本と諸外国における燃料課税と車体課税の年間税負担額を比較しています。2,000ccクラスの自家用車を例に、日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国における税負担額を試算し、比較しています。比較においては、ガソリン価格、為替レート等の影響も考慮されています。具体的な数値は、資料の表を参照ください。 この比較から、日本の自動車関連税制の国際的な位置付けや、改善点が見えてきます。
1. 比較対象国の選定と条件設定
このセクションでは、燃料課税と車体課税の国際比較を行うための対象国と比較条件が設定されています。2,000ccクラスの自家用車を例に、日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国(デンマーク、オランダ、フィンランド、イギリス、フランス、ドイツ)を対象に比較が行われています。車体価格(税抜本体価格)を同一として、年間の税負担額を試算しています。取得時に課税される税金については、平均保有期間(7年)を考慮し、年間の税負担額を算出しています。燃料価格については、各国の税込み価格を用いており、為替レートは2014年12月の平均値(1ドル=120円、1ポンド=187円、1ユーロ=147円、1デンマーク・クローネ=20円)が用いられています。アメリカ、フランス、オランダの税率については、それぞれニューヨーク州・ニューヨーク市、パリ地方、北ホランド州の税率を用いています。これらの条件設定に基づいて、各国の税負担額の比較が行われています。 この比較分析においては、各国の税制上の差異や、為替レートの変動といった要因が結果に影響を与える可能性がある点に注意が必要です。
2. 燃料課税と車体課税の年間税負担額比較
このセクションでは、前述の条件に基づいて算出された、各国の燃料課税と車体課税の年間税負担額が比較されています。日本については、自動車取得税を取得課税として、自動車税と自動車重量税を保有または利用課税として分類しています。 比較結果から、日本と諸外国との間の税負担額の差異、そしてその要因について分析が行われていると推測されます。具体的な数値は提示されていませんが、この比較を通じて、日本の自動車関連税制の国際的な位置づけや、他の国々の税制の特徴を理解することができます。さらに、それぞれの税負担額に影響を与える要因(燃料価格、為替レート、税率、課税対象)について分析することで、より詳細な比較検討を行うことが可能です。フランスの社用自動車税や車軸税、アメリカの一般道路自動車利用税といった、日本にはない課税制度についても言及されている可能性があります。
