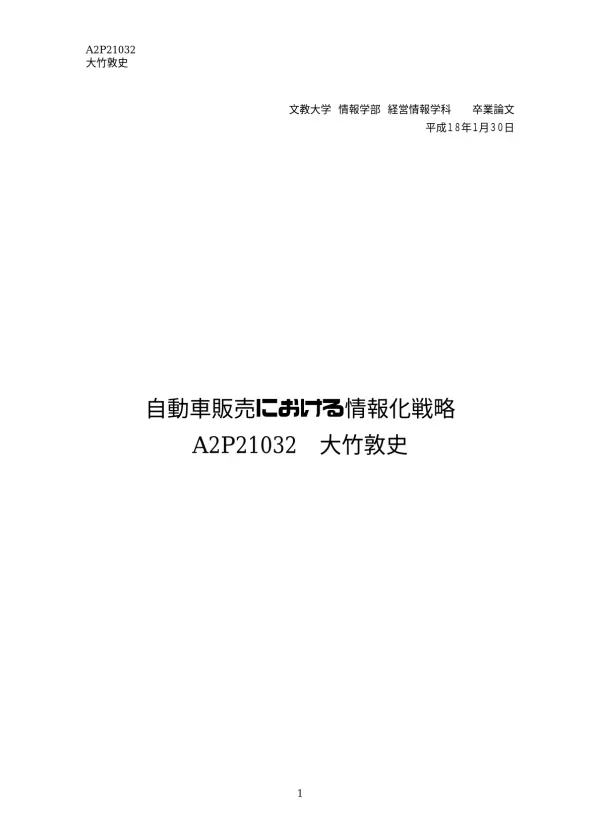
自動車販売の成功戦略:ECと顧客対応
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.95 MB |
概要
I.第一章 新車販売における価格交渉とディーラー支援
日本の新車販売は、ディーラーでの価格交渉が必須であり、顧客の交渉力によって価格が大きく変動する独特のシステムです。オートバイテルのようなオンライン中古車販売仲介プラットフォームは、このシステムに適合したローカライズを行い、ディーラーの営業支援に重点を置いています。新車販売仲介に加え、中古車、自動車パーツ、ローン紹介などのサービスを提供することで、メーカー、ディーラー、ユーザーの三方にメリットをもたらすビジネスモデルを構築しています。加盟ディーラーには、専任のマネージャーとスタッフの配置、オートバイテルによる研修などが義務付けられています。01年2月時点で加盟ディーラー数は450社、主要収益源は加盟費用と成約件数に応じた手数料収入です。新車販売仲介が総収益の約8割を占めています。
1. 日本の自動車販売における価格交渉の特殊性
日本の新車販売は、メーカー希望小売価格が形式的なものであり、実際の販売価格は顧客との交渉によって決定されるという特殊性を持っています。スーパーなどでの値引き販売とは異なり、ディーラー店頭での価格表示はあくまで交渉の出発点であり、顧客の交渉力によって値引き額が大きく変動するシステムです。交渉力のある顧客には大きな値引きが、交渉に不慣れな顧客には小さな値引きしかされないのが現状です。この価格交渉の慣習は、日本の自動車販売における重要な特徴の一つとなっています。
2. オートバイテルの日本市場におけるローカライズ戦略
米国発祥のオンライン自動車販売仲介プラットフォームであるオートバイテルは、そのビジネスモデルをそのまま日本市場に導入することは困難でした。そのため、日本の自動車流通システムと顧客心理を考慮したローカライズ戦略が実施されました。米国のモデルとは異なり、日本のオートバイテルではディーラーへの営業支援に重点が置かれています。新車販売仲介に加え、中古車、自動車パーツ、ローン紹介などのサービスを提供することで、メーカー、ディーラー、ユーザーの三者全てにメリットをもたらすことを目指しています。この情報提供機能の充実が、日本のオートバイテルの大きな特徴となっています。
3. オートバイテルのビジネスモデルとディーラー支援策
2001年2月時点で450社の加盟ディーラーを擁するオートバイテルは、新車販売仲介(17メーカー)、中古車販売仲介、アフターパーツ販売仲介、ローン紹介など、多様な仲介サービスを提供しています。主要な収益源は、ディーラーからの加盟費用と、仲介情報による成約件数に応じた手数料収入です。総収益の約8割を新車販売仲介が占めており、ディーラーの成約率向上支援がオートバイテルにとって重要な課題となっています。そのため、Webシステムやコンテンツの充実だけでなく、加盟ディーラー向けのネットビジネス教育による営業支援を重視しています。具体的には、集合研修や10名のフィールドサポートスタッフによる継続的なコンサルティングを提供し、ディーラーの販売員の成約率向上を技術面と営業面の両方から支援する体制を構築しています。これにより、ディーラーは従来の営業方法よりも精度の高いピンポイント営業が可能になり、年間120台近くの成約を達成する販売員も出てきています。
II.レクサスの事例 顧客満足度向上のための情報武装と統合システム
高級車ブランドであるレクサスは、顧客満足度向上のため、高度な情報システムを導入しています。ETCセンサーによる顧客識別、車載テレマティクスシステム「G-Link」による顧客情報取得と24時間対応、精巧なCGによるバーチャルショールーム「レクサスギャラリー」、そして全国の在庫を共有する認定中古車システム(数年後導入予定)などがその例です。これらのシステムにより、顧客へのきめ細やかなサービス提供、効率的な在庫管理、そして販売プロセスの迅速化を実現しています。名古屋トヨペットのレクサス高岳店は、オーナー専用のクラブルームや中古車展示場を併設するなど、大規模な設備を備えています。
1. 顧客の来店から対応までの効率化 ETCとG Linkを活用したシステム
レクサス店では、駐車場入り口に設置されたETCセンサーで顧客の車種、氏名、顔写真、予約状況などを自動的に検知し、営業スタッフやサービススタッフの携帯電話にメールで通知するシステムが導入されています。これにより、顧客がカウンターに到着する前に点検の準備を進めることが可能になり、迅速な対応を実現しています。さらに、レクサス車に標準搭載されているテレマティクスシステム「G-Link」を活用し、ボタン一つで「レクサスオーナーズデスク」に接続できます。カーナビの目的地設定からレストランの紹介、トラブル時の対処まで、オペレーターが代行してくれるため、顧客満足度の大幅な向上に繋がっています。事故発生時にはエアバッグ作動を自動でオペレーターに通報する機能も備え、万一の際にも迅速な対応が可能です。ディーラー側も、オイル交換や車検時期をメールで通知し、顧客の来店を促進できるなど、大きなメリットを得ています。
2. バーチャルショールームとオーダーメイドシステム 精巧なCGと見積もり作成システム
レクサスでは、商談デスクに設置された液晶モニターで、トヨタの新車設計時に使用される3次元データを用いた精巧なCGを映し出す「レクサスギャラリー」システムを導入しています。顧客は、このシステムを使って外観や内装の色、オプションなどを自由に選択し、自分好みのオーダーメイドカーを設計できます。選択内容に基づいて見積書が自動的に作成され、ローンやリースなどの金融商品の提案も同端末で行うことが可能です。注文データはトヨタの生産管理システムと直結しているため、納車日もその場で提示できます。この一気通貫のサプライチェーンによって、無駄な在庫を削減し、効率的な生産体制を実現しています。各店舗がバラバラに情報システムを使うのではなく、店舗、商品、生産システム全体を再構築することで、従来では不可能だったレベルの顧客対応と効率化を実現している点が重要です。
3. 認定中古車システムと顧客対応の強化 店舗と顧客を繋ぐ新たな仕組み
レクサスの今後の展開として、独自の認定中古車制度の導入が計画されています。全国のレクサス店が在庫を共有する新しいシステムを開発中で、各店舗が在庫を持たなくても、専用端末を通じて全国の中古車在庫を検索し、購入できる仕組みが構築されようとしています。中古車が市場に出回る3~5年後をメドに新制度が開始される予定です。この取り組みは、ディーラーからも歓迎されており、従来のバリューチェーンの限界を超える革新的な試みとして期待されています。また、レクサス帯広店では、顧客への24時間対応体制を構築し、顧客専用携帯電話と専用トレーラーをスタッフが交代で自宅に持ち帰ることで、迅速なトラブル対応を実現しています。北海道東部で唯一の店舗であるため商圏が広く、遠方からの顧客も多いことを考慮した、きめ細やかな顧客サービスの提供体制が構築されています。これは、G-Linkと連携した顧客位置情報の把握を基にした、店舗独自のサービス提供の一例です。
4. トヨタグループ統合システム ai21 とアフターサービス情報ネットワーク
トヨタグループの販売店では、「ai21」という業務統合システムが稼働しており、車両販売、サービス、保険、経理、人事など、基幹業務アプリケーションが統合されています。このシステムは、販売店本社と各拠点間、トヨタ自動車本体や保険会社間での情報共有を円滑に行うための基盤となっています。ai21のバーコード読み取り機能を活用し、トヨタサービスカードを顧客に配布することで、車両情報データベースに整備履歴などの情報を蓄積しています。このデータベースは、顧客情報と紐づくものではなく、車両単位で情報を管理することで、プライバシー保護にも配慮されています。ユーザーは、カードのバーコードを販売店や整備工場で読み取ってもらうことで、必要な情報にアクセスできます。このシステムは、2000年にICカードを用いたシステム構想も検討されていましたが、普及スピードや導入コスト、作業負担などの問題から、バーコードシステムが採用されました。
III.第二章 中古車販売市場の活性化と新たなビジネスモデル
近年、中古車販売市場は活性化しており、メーカーや正規ディーラーも参入を拡大しています。年間登録台数は約800万台(実際の販売台数は約500万台)と横ばいですが、新車販売よりも高い利幅が見込めるためです。中古車は、仕入れ値と売り値の裁量が大きく、在庫管理や売れ筋の把握が重要になります。日産自動車のカレスト座間は、広大な敷地内に多様な中古車を展示していますが、顧客の検索や手続きに時間がかかる課題がありました。そこで、PDAと無線ICタグを利用した新システムを導入し、顧客の来店から成約までの時間を30%以上短縮することに成功しました。ヤナセはアフターサービスと中古車部門の強化により、2001年9月期の61億5800万円の赤字から、2004年9月期には41億1400万円の黒字に転換しました。特にアフターサービス・中古車部門は売上総利益で53%を占めています。
1. 中古車市場の現状と活性化の要因
近年の中古車市場は、年間登録台数約800万台(業者間登録を含む、実際の販売台数は約500万台程度)と横ばい状態が続いていますが、自動車メーカーや正規ディーラーが本格的に参入し、市場は活況を呈しています。新興業者も参入し、事業モデルの競争が激化しているため、「安心して買える」市場へと変化しつつあります。新車販売が低迷する中、中古車販売は堅調に推移しており、事業モデルによっては新車販売よりも高い利益率が見込めるため、各社が力を入れているのです。中古車は新車とは異なり、仕入れ値と売り値の裁量が大きく、在庫管理や売れ筋の把握などの業者のノウハウが利益に直結するビジネスモデルであることが、市場活性化の背景にあります。
2. 日産カレスト座間の事例 中古車販売における効率化システムの導入
日産自動車のカレスト座間は、広大な敷地に多様な中古車を展示する販売店ですが、車両数の増加に伴い、顧客が目的の車を探す時間や試乗などの手続きに時間がかかるという課題がありました。そこで、2003年夏から新システムの構築に着手し、同年11月に導入を決定しました。このシステムはPDAと無線ICタグを活用し、顧客は敷地内どこからでも車両情報を検索でき、車両の詳細情報、概算見積もり、試乗申し込みなどを迅速に行えるようになりました。日産自動車グローバル情報システム本部が開発したこのシステムは、2004年5月30日と6月2日の仮導入で、顧客の来店から成約までの時間を30%以上短縮できる効果を実証しました。既存の中古車検索システム「Get-U」のデータベースを流用し、効率的なシステム構築を実現しています。このシステム導入により、顧客の利便性向上と販売効率の改善に大きく貢献しました。
3. ヤナセの事例 アフターサービスと中古車部門強化による黒字転換
ヤナセは、長年にわたり収益が見込める顧客を囲い込む戦略の一環として、小売業の強化、特にアフターサービスと中古車部門の強化に注力しました。それ以前は、オイル交換に丸一日預かることもあったため、顧客満足度向上のため、サービス工場の作業効率向上による納期短縮、顧客満足度向上を目指した改革を行いました。整備実績データベースを分析し、効率の悪い作業を特定し改善することで、作業時間を短縮することに成功しました。例えば、ある作業工程では平均2.4時間かかっていた作業時間が1.7時間まで短縮されました。また、オートラインによる情報の一元管理により、顧客単位で部門を超えた情報検索が可能になり、サービス工場の業務改善にも役立てられました。これらの3年間におよぶ営業改革の結果、経常損益は2001年9月期の61億5800万円の赤字から、2004年9月期には41億1400万円の黒字に転換し、アフターサービス・中古車部門は売上総利益の53%を占めるまでに成長しました。中古車部門では、下取り車を商品化することで顧客層の拡大にも成功しています。
IV.USSとオークネットの事例 オートオークション市場の進化
USSは、中古車オークションの最大手として、衛星端末「USS-JAPAN」によるライブ中継システムを導入し、業界シェア拡大を目指しています(2009年3月期目標:出品300万台、シェア40%、経常利益300億円)。オークネットは、衛星通信を利用したバーチャルオークションの先駆けとして、地理的制約の除去、コスト削減、商談機会の最大化を実現しました。オークネットは高額車両の取引に強みを持っていますが、中・低価格車市場への参入も計画しています。USSとオークネットは、それぞれ現車オークションとバーチャルオークションという異なるアプローチで、中古車販売業界に革新をもたらしています。USS東京会場は、毎週木曜日に7000~8000台のセリを開催し、厳格な車両検査とアフターケアを提供することで、高い成約率(約60%)を実現しています。
1. USSの事例 オートオークション業界のリーダーとしての戦略と挑戦
USSは中古車オークション会場運営の最大手であり、2005年3月期には2006年3月期目標であった出品200万台、業界シェア30%、経常利益200億円を前倒しで達成しました。常に新たな挑戦を続けるUSSは、近年では衛星端末「USS-JAPAN」による現車会場のライブ中継を導入し、USSグループ15会場と提携先14会場の計29会場、364万台の中継を実現しています。週間1万台以上の取引実績を誇り、現車ライブ中継においてトップの実績を上げています。さらに、リーダーとしての存在感と更なる飛躍を目指し、「プロジェクト3・4・3」を掲げ、2009年3月期までに、出品300万台、業界シェア40%、経常利益300億円という新たな中期目標を設定しています。中古車市場においてオークション取引が年間登録台数の約6割を占めることから、USSのようなオークション会社には公正性と中立性が強く求められています。USS東京会場では、毎週木曜日に7000~8000台ものセリが行われ、厳格な車両検査と充実したアフターケアによって、高い顧客信頼と6割という高い成約率を実現しています。セリ時間は1台あたり約13秒と非常に効率的です。
2. オークネットの事例 衛星通信を活用したバーチャルオークションのパイオニア
1985年設立のオークネットは、衛星通信を利用したバーチャルオークションのパイオニア企業として、2000年5月に東証1部に上場し、7000社を超える取引会員数を有しています。従来の現車オークション会場とは異なり、中古車販売店の展示場で出品車の検査を行い、検査結果と車両映像を衛星を通じて会員各社の専用端末に送信することで、全国の中古車販売業者がどこからでも出品・落札できるシステムを構築しました。このバーチャルオークションは、現車オークション会場と比較して、オークション開設コストと時間の削減、商談機会の最大化、地理的制約の除去という4つの大きなメリットを提供しています。特に、高額車両において高い成約率を維持していますが、中・低価格車市場への進出も視野に入れ、第二オークションの創設を中期計画に掲げています。これは、高額車両の出品台数が年々減少していくという課題への対応策です。現車オークション会場に比べ、バーチャルオークションは開設コスト、開設時間、柔軟性において優位性があるとしています。しかし、高額車両以外の成約率向上には課題が残ります。
V.ガリバーインターナショナルの事例 中古車買取専門店の成功要因
ガリバーインターナショナルは、中古車買取専門店として急成長を遂げました。本部による価格査定、シンプルな査定システム、短期間の研修、そして顧客対応力の高い接客スキルが成功の鍵となっています。フランチャイズ方式による多店舗展開も成功要因の一つですが、店舗数の増加に伴い、管理体制の強化が課題となっています。中古車の買取価格競争が激化している現状も踏まえると、今後の戦略が重要です。
1. 中古車買取専門店の台頭とガリバーインターナショナルの急成長
1990年代後半、中古車業界に新たな業態として台頭してきたのが中古車買取専門店です。ガリバーインターナショナルはその代表的な企業として、多店舗展開による急成長を遂げました。従来の新車ディーラーの下取りシステムは、顧客にとって不利な条件提示が一般的でした。値引き額を下取りで調整するなど、ユーザーにとって不透明な部分も多くありました。そのため、ディーラーよりも高く買取ることでユーザーの支持を集め、業者間オークションで転売することで利益を上げる買取専門店は、ユーザーにとって魅力的な選択肢となりました。ガリバーインターナショナルの成功は、このユーザーニーズを的確に捉えたビジネスモデルと、効率的なシステムによるところが大きいです。
2. ガリバーのシステムと成功要因 本部による価格査定と接客スキル
ガリバーのシステムは、経験や専門知識がなくても運営できるよう設計されています。査定は店舗で30項目程度のチェックを行い、10段階のランクで評価した査定票を本部へFAX送信。価格付けは本部担当者が行うため、店舗スタッフは査定票の作成と顧客対応に集中できます。短期間の研修で業務を習得できるため、異業種からの参入が容易でした。しかし、成功の鍵は車の専門知識よりも、むしろ接客や商談における営業スキルにあります。日本では車は単なる機械ではなく、思い出が詰まった愛車として捉えられることが多いです。そのため、いくら高額買取をしても、顧客への対応が悪ければ、顧客は離れてしまいます。ガリバーの成功は、高額買取に加え、丁寧な接客と顧客との良好な関係構築による顧客満足度の高さにあると言えます。
3. フランチャイズ方式による多店舗展開と今後の課題
ガリバーはフランチャイズ方式を採用することで急成長を遂げました。資金力の乏しい本部でも、加盟店オーナーの資金を活用して多店舗展開が可能となり、短期間で多くの店舗数を確保できました。また、「中古車販売経験がないこと」を加盟条件とすることで、既存の中古車業界の既成概念にとらわれない、フレッシュな経営者を積極的に採用しました。これは、ガリバー独自の革新的なビジネスモデルをスムーズに導入するためには、既存の業界慣習にとらわれない人材が必要だと考えたためです。店舗は展示スペースが不要なため、ビルの一室などでも営業が可能で、開業費用も比較的低額に抑えられました。しかし、フランチャイズ方式による急拡大は、管理体制の整備という新たな課題を生み出しています。今後、ブランドイメージの統一性や、システム変更時の対応など、フランチャイズ店の増加に伴う管理上の問題への対策が求められます。平均的な店舗の開業費用は約1850万円、月間のランニングコストは約300万円程度でした。
VI.第五章 まとめ 日本の自動車販売業界の構造変化と今後の展望
日本の自動車販売業界は、中古車市場の活性化、消費者のライフスタイル変化、新車販売の頭打ちなど、大きな構造変化に直面しています。系列ディーラーは、従来の営業戦略の見直しを迫られています。高級車ブランドは、認定中古車や充実したアフターサービスによって顧客囲い込みを強化しています。オートバイテルのようなオンライン仲介サービスは、既存ディーラーとの共存関係を維持しつつ、今後の成長によっては、販売そのものへの参入も視野に入れています。中古車買取専門店の増加による過当競争も懸念材料です。中国市場への進出も、今後の成長戦略の重要な要素となり得ます。
1. 日本の自動車販売業界の構造変化
近年の日本の自動車販売業界は、中古車市場における新勢力の台頭や消費者のライフスタイル変化など、大きな構造変化に直面しています。従来の系列ディーラーは、訪問販売や価格交渉といったセールスマン中心の営業戦略では、消費者のニーズに合致せず、非効率な運営を強いられています。国内の新車販売は頭打ち傾向にあり、メーカーや販売店はアフターサービスや中古車事業に力を入れるようになっています。特に、レクサス、BMW、メルセデス・ベンツといった高級車ブランドでは、認定中古車制度(レクサスは数年後導入予定)や充実したアフターサービスメニューを提供することで、ブランドイメージの維持と顧客の囲い込みを図っています。今後、日産のインフィニティやホンダのアキュラといったブランドも日本市場に参入する予定であり、同様の顧客囲い込み戦略が展開されると予想されます。
2. オートバイテル等の仲介サービスの今後の展望と課題
オートバイテルのようなオンライン自動車販売仲介サービスの今後の展望は不透明です。現状では、自動車ディーラーから仲介手数料を得るビジネスモデルで、既存の自動車販売と共存していますが、将来的な成長を考えると、販売仲介から販売そのものへの参入も視野に入れている可能性があります。ディーラーにとっても顧客獲得コストの削減というメリットがあるため、現状では共存関係が保たれていますが、オートバイテルの成長次第では、競合関係へと変化する可能性も秘めていると言えるでしょう。
3. 中古車買取専門店の現状とオークション事業の展望
近年、中古車買取専門店が増加していますが、それに伴い中古車の買取市場は過当競争に陥っている可能性があります。一方、中古車オークション事業は、ここ数年横ばいではあるものの、新車販売よりも安定した市場であり、事故車オークションやリサイクル事業への参入も進んでいます。また、輸出や海外進出を検討する企業も多く存在し、特に中国市場は今後の成長が期待されているものの、市場規模はまだ小さく、参入のタイミングを見極めている状況です。国内で培ったシステムやノウハウを活かせば、海外市場においても成功する可能性は高いと考えられます。
