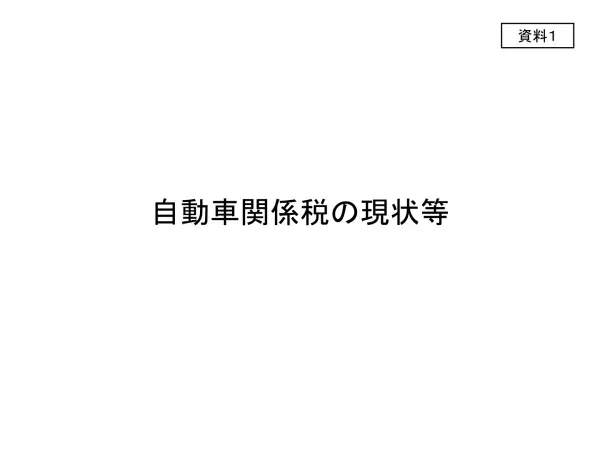
自動車関係税の税収分析
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.19 MB |
概要
I.自動車取得税の沿革と現状 History and Current Status of Automobile Acquisition Tax
本資料は、日本の自動車取得税(shutokuzei)の歴史と現状を概説しています。昭和22年の創設以来、昭和25年の廃止、昭和43年の再創設を経て、平成21年には目的税から普通税へと移行しました。平成21年度には、**エコカー減税(ekokā gensui)**制度も導入され、環境性能の高い車の取得を促進しています。現在、自動車取得税は、地方公共団体の財源として重要な役割を果たしています。 近年は、環境問題への関心の高まりを受け、**排出ガス(haishutsu gasu)規制や燃費(nenpi)**基準の強化が進められています。
1. 昭和時代の自動車取得税
昭和22年、旧地方税法改正により自動車取得税が創設されました。自動車またはその取得に対し、主たる定置場所のある都府県で所有者または取得者に課税されることになりました。しかし、昭和25年にはシャウプ勧告を受けた地方税制改革により、現在の地方税法が制定され、自動車の取得は課税対象から除外されました。その後、地方財政の悪化と財政再建の必要性から、昭和43年には、地方道の整備の遅れや道路整備の緊急性を背景に、自動車取得税が再創設されました。政府税調の答申では、自動車の増加と道路整備の必要性、自動車による道路使用と道路整備の密接な受益関係が指摘され、自動車取得者に取得時の担税力に応じた負担を求めることが提言されました。昭和43年当時、三重県、京都府、徳島県、愛媛県が課税を行っていました。
2. 平成時代の変遷とエコカー減税
平成21年、政府・与党決定による「道路特定財源の一般財源化等について」に基づき、自動車取得税は目的税から普通税へ変更され、使途制限が廃止されました。同時に、自動車の買換え・購入需要の促進と低炭素社会の実現を目指し、環境性能の優れた新車の取得に対して3年間の時限的軽減措置であるエコカー減税が創設されました。これは、環境性能の高い車の購入を促す政策です。その後、平成22年には自動車取得税の暫定税率が廃止されました。これらの変更は、地方財政の状況や社会情勢の変化、環境問題への対応などを反映したものです。 消費税導入時の議論(昭和63年)では、道路特定財源の一般財源化や自動車関係諸税の簡素化について検討が行われましたが、自動車関係諸税については、現行税制に理由があると判断され、見送られました。
3. 自動車税のグリーン化と税率調整
平成13年には、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車の税率を重くする「自動車税のグリーン化」制度が創設されました。これは、税収中立を前提とした政策です。しかし、軽減措置による減収額が当初見込みを大幅に上回ったため、平成15年、16年、18年、22年とグリーン化対象の見直しが行われ、軽減対象の重点化が図られました。平成18年には、制限税率が標準税率の1.5倍に引き上げられ、徴収方法も証紙徴収から普通徴収に変更されました。これらの調整は、地方分権の推進、課税自主権の拡大、そして環境政策の有効性向上を目指したものです。 平成17年には、県域を越える自動車の転出入に係る月割計算が廃止され、継続検査時だけでなく構造等変更検査時にも自動車税の納税確認が行われるようになりました。
II.自動車税の概要と徴収 Overview and Collection of Automobile Tax
**自動車税(jidōshazei)**は、都道府県が課税する地方税で、自動車の所有者に課せられます。その性格は、固定資産税に代わる財産税的な側面と、道路損傷負担金的な側面を併せ持ちます。自家用車と営業用車で税率が異なり、営業用車は公共輸送機関としての役割を考慮して税率が低く設定されています。徴収は普通徴収で行われ、**滞納(tainō)**対策として、督促状の送付、財産調査、差押え、さらにはタイヤロックによる運行停止処分などが行われています。平成20年度の徴収率は96.1%でした。課税件数は膨大で、徴収事務には多大な労力を要します。
1. 自動車税の課税対象と性格
自動車税は都道府県が徴収する地方税で、自動車の所有者に課税されます。課税根拠は、自動車の所有という事実から担税力を見出し、所有者に課税するという点にあります。その性格は、固定資産税に代わる財産税的な側面と、道路の損傷に対する負担金的な側面を併せ持っています。 自動車の種別や排気量などによって税率が設定されており、同一の自動車であっても、営業用自動車の税率は自家用自動車よりも低く設定されています。これは、営業用自動車がタクシーやバスなどの公共輸送機関として社会的役割を担っており、税負担の増加が運賃・料金の値上げにつながり、物価に悪影響を与える可能性があるためです。一部の自家用車については、奢侈税的な側面を持つものもあります。
2. 自動車税の徴収方法と課題
自動車税は、膨大な納税義務者(所有者)から普通徴収によって徴収されます。自動車の所有権の移転が多いことから、納税義務者の把握が難しく、賦課・徴収事務に多くの労力を要しています。一件あたりの税額は比較的少額である一方、納税通知書の発行数が多いこと、滞納件数が多いことから、督促状や警告書の発行、電話催告、臨戸訪問などの事務負担が大きく、徴収コストの非効率性が指摘されています。平成20年度の実績では、徴収率は96.1%(現年・滞納繰越分合計)でした。現年分は98.7%、滞納繰越分は28.6%となっています。都道府県では、クレジットカード払い、コンビニ収納の導入による期限内納付の勧奨や、滞納者に対するタイヤロックによる運行停止処分、インターネット公売による強制換価などの対策を実施しています。
3. 自動車税滞納対策の具体例
A県における自動車税の滞納対策の例として、納期限後の督促状(7月)や財産調査を行う旨の警告書(8月)の送付が挙げられます。さらに、平成20年度には、11月25日に滞納者5万4千人(7万件)に差押予告書を一斉送付し、12月1日から2ヶ月間を自動車税集中差押期間に設定しました。12月2日から5日にかけては、滞納者宅への訪問による納付催告を実施し、タイヤロック装着前に滞納額全額を納付した者もいました。12月11日以降は、全滞納者に対して勤務先への訪問や連絡による給与調査・給与差し押さえ、既に差押え処分を行っている約500台を対象としたタイヤロックの実施、自動車の引揚げ及びインターネット公売による換価などが行われました。これらの対策により、徴収率の確保に努めています。
III.自動車重量税の概要 Overview of Automobile Weight Tax
**自動車重量税(jidōsha jūryōzei)**は、国が課税する国税で、車検時(新規検査、継続検査等)に納付されます。車検を受けることによって初めて自動車の運行が可能になるという法的地位に着目した、権利創設税の性格を持っています。**エコカー減税(ekokā gensui)の一環として、環境性能の高い車については減免措置が講じられています。軽自動車についても軽自動車税(keijidōshazei)**が別途課税されます。
1. 自動車重量税の基礎情報
自動車重量税は国税であり、昭和46年に第6次道路整備5か年計画に伴う道路財源の必要性から創設されました。課税主体は国で、課税客体は新規検査、継続検査、臨時検査、分解整備検査、構造等変更検査などによって自動車検査証の交付や返付を受ける自動車です。 軽自動車の場合は、車両番号の指定を受ける軽自動車が対象となります。納税義務者は、自動車検査証の交付または返付を受ける者、および車両番号の指定を受ける者です。納付方法は、車検時(自動車の種類に応じて1~3年ごと)に自動車重量税印紙納付(臨時検査などでは現金納付)で行われ、納税地は車検証の交付などの事務をつかさどる運輸支局などとなります。自動車重量税は、車検等によって初めて自動車の運行が可能になるという法的地位に着目して課税される権利創設税と説明されています。自動車リサイクル法により適正に解体された自動車については、自動車検査証の残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。
2. エコカー減税と減免措置
平成21年度から23年度までの間に、一定の排ガス性能・燃費性能を備えた自動車について、新規・継続車検等(当該期間内に最初に受ける車検1回分に限る)において自動車重量税の減免措置が講じられました。電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車などは免除となり、その他の車両については、燃費基準達成度合いに応じて75%または50%の軽減措置が適用されました。 具体的には、「★★★★車かつ平成22年度燃費基準+25%達成車」は75%、「★★★★車かつ平成22年度燃費基準+15%達成車」は50%の軽減が適用されました。バス・トラック(2.5t超3.5t以下)については、平成21年ディーゼル車排出ガス規制適合車が対象となっています。この減免措置は、エコカー減税の一環として、環境性能に優れた自動車の普及促進を目的としています。
IV.環境対策と税制 Environmental Measures and Tax System
日本の自動車税制は、環境問題への対応を重視しています。エコカー減税(ekokā gensui)制度のほか、排出ガス(haishutsu gasu)基準や燃費(nenpi)基準の強化、低排出ガス車認定制度などが実施されています。これらを通して、環境負荷の少ない自動車の普及促進と、環境保護への貢献が図られています。★★★★車や燃費基準+15%達成車などの具体的な基準も設定されています。
1. 排出ガス規制と燃費基準
環境対策として、排出ガス基準と燃費基準の強化が挙げられます。排出ガス基準に関しては、国土交通省が排出ガス基準よりも有害物質を低減させた自動車を「低排出ガス車」として認定し、ステッカーを貼付することで普及を図っています。燃費基準は省エネ法に基づき、目標年度以降に国内向けに出荷される自動車について、区分ごとに下回らないようにすべき燃費の目標基準値が設定されています。平成27年度燃費基準が策定されており、ガソリン乗用車(乗車定員10人以下)、2.5t以下のガソリン貨物車などについては、平成22年度または平成17年度燃費基準が特例として用いられています。電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス、被けん引車はこれらの基準の対象外です。 一定の排出ガス要件を満たす天然ガス自動車やプラグインハイブリッド自動車についても、独自の基準が設けられています。
2. 自動車税のグリーン化
平成13年に導入された自動車税のグリーン化制度は、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車の税率を重くする特例措置です。これは税収中立を前提としています。具体的には、新車新規登録から11年超のディーゼル車、13年超のガソリン車などは標準税率より概ね10%重課される一方、環境性能の高い車両は軽減措置が適用されます。しかし、軽減措置による減収額が当初見込みを大幅に上回ったため、平成15年度、16年度、18年度、22年度と軽減対象の見直しが繰り返し行われ、重点化が図られました。平成18年度には制限税率が標準税率の1.5倍に引き上げられ、徴収方法も変更されました。環境負荷の小さい自動車の普及状況を踏まえ、具体的な軽減対象として「★★★★車かつ燃費基準+15%達成車」などが挙げられています。 「★★★★」は平成17年ガソリン車排出ガス基準75%低減達成車、「★★★」は同50%低減達成車です。
3. エコカー減税とその他の環境対策
平成21年度から23年度までの間、一定の排出ガス性能・燃費性能を備えた新車の取得について、自動車取得税の軽減措置(エコカー減税)が講じられました。電気自動車・天然ガス自動車・ハイブリッド自動車などは非課税となり、その他の車両も燃費基準達成度に応じて75%または50%の軽減措置が適用されました。この制度は、自動車の買換え・購入需要を促進するとともに、低炭素社会の実現を目指すものです。 さらに、環境性能の良い新車の購入促進策としてエコカー補助金制度があり、環境対策と景気対策の両立を目指しています。経年車(車齢13年超)の廃車を伴う新車購入補助なども実施されています。
