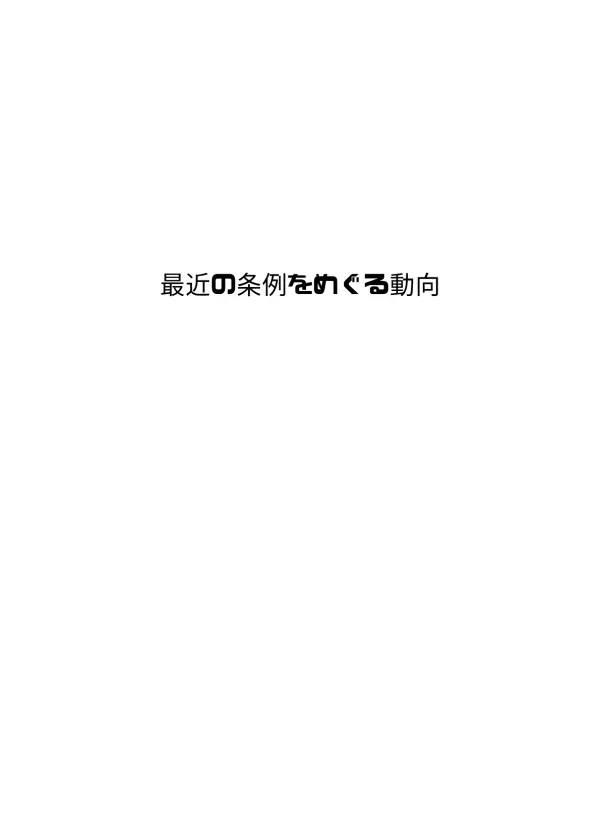
自治体条例集: 情報公開・住民参加
文書情報
| 学校 | 大学名不明 |
| 専攻 | 行政法、地方自治法、公法など関連分野 |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 講義資料、レジュメ |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 243.66 KB |
概要
I.職員倫理と贈与規制に関する条例案
複数の自治体で、職員の倫理向上と市民の信頼確保を目的とした条例案が検討・施行されています。主な内容は、職員による利益供与の受領報告の義務化(贈与等報告書提出)、倫理監督職員・職員倫理委員会の設置です。特に、贈与等報告書の提出義務化や、市民による閲覧可能なシステム構築が、政治倫理、情報公開の観点から重要視されています。長野県木曽広域連合では、既に情報公開条例を施行し、連合情報公開及び個人情報保護審査会を設置しています。個人情報保護に関しても、各地で条例制定に向けた動きが活発です。
1. 条例案の目的と構成
条例案は全10条で構成され、職員の倫理保持、職務執行の公正さに対する市民の疑惑・不信の防止、市民の信頼確保を目的としています。これは、職員の倫理規定を明確化し、市民からの信頼を得るための重要な第一歩です。条例案では、具体的な措置として、事業者などから受けた利益、報酬、支払いに関する情報を記載した「贈与等報告書」の任命権者への提出が義務付けられています。この報告書には、受け取った利益の内容、金額、日付、事業者の名称、住所などが詳細に記録されることになります。これは、利益誘導や不正行為の抑止に繋がる重要な要素です。さらに、倫理違反の発生を未然に防ぎ、公正な行政運営を確保するために、任命権者のもとに職員倫理を監督する職員を1名配置すること、そして有識者3名から成る「職員倫理委員会」を設置することも規定されています。これにより、倫理的な問題が発生した場合でも、迅速かつ公正な対応が可能となります。
2. 政治倫理基準と贈与規制
答申によると、政治倫理条例は町長ら3役、教育長、教育委員、農業委員、町議、土地開発公社役員を対象としています。この条例では、権限・地位による影響力を利用した金品授受の禁止、公共工事の請負契約や業務委託・物品納入契約に関する特定業者の推薦や有利な取り計らいの排除などが政治倫理基準として明確に規定されています。さらに、本人や親族が役員を務める企業による工事受注も禁止されています。これらの規定は、政治における透明性と公正性を高めるための重要な措置です。また、一般職員についても、課長以上の職員が1件5000円以上の贈与等(接待を含む)を受けた場合は報告を義務付けることとなり、その報告書は市民が閲覧できるようにする仕組みが導入される見込みです。これは、市民の監視機能を高め、不正行為に対する抑止力となります。さらに、条例施行後は、職員だけでなく市民や業者にも規則などを周知徹底することで、便宜供与の機会を減らす努力がなされます。
3. 長野県木曽広域連合の情報公開条例
長野県木曽広域連合では、情報公開条例が1月から施行されました。これは、連合を構成する町村で情報公開条例が出揃ってきたことを背景に、連合としても情報公開を進める必要性から制定されました。連合内町村は個々の情報公開審査会を持たないため、条例制定に伴い連合で設置された「連合情報公開及び個人情報保護審査会」に各町村が事務委託できるというメリットがあります。これは、効率的な情報公開体制の構築に繋がります。他の長野県内広域連合(北アルプス広域、上伊那広域、上田地域広域)も、2001年度中の情報公開条例施行を目指しており、情報公開への取り組みが加速していることが分かります。木曽広域連合の事例は、他の自治体にとっても、情報公開を進める際の参考となるでしょう。
II.情報公開条例と個人情報保護
情報公開条例では、情報公開と個人情報保護のバランスが課題となっています。那覇市では、海上自衛隊那覇基地の建築資料開示をめぐる裁判で国が敗訴し、情報公開の範囲拡大が示唆されました。一方、個人情報の取り扱いについては、北海道江別市や佐賀市が個人情報保護条例の制定に向け、個人情報の開示・是正請求権や自己情報コントロール権を盛り込んだ条例案を検討しています。個人情報保護は、行政の透明性と市民の権利保護の両立が求められています。
1. 情報公開条例をめぐる裁判と判決
沖縄県那覇市では、市情報公開条例に基づき、海上自衛隊那覇基地の対潜水艦戦作戦センター(ASWOC)の建築資料開示が決定されました。しかし、国は「国防上の支障」を理由に決定取り消しを求める訴訟を起こしました。この訴訟は、最高裁まで争われ、最終的に最高裁は国の請求を退け、那覇市の決定を支持しました。これは、情報公開条例に基づく開示請求に対し、国防上の理由だけでは開示拒否できないという重要な判例となりました。この判決は、情報公開の範囲を拡大する方向を示唆するものであり、今後の情報公開請求に関する議論に大きな影響を与える可能性があります。12年にも及ぶ訴訟を経ての判決は、情報公開の重要性を改めて認識させるものです。
2. 情報公開条例の改正と拡大
ある県では、情報公開条例が改正され、公開請求権者の範囲が県民から「何人も可」に拡大されました。これは、情報公開へのアクセスをより広範な国民に提供する重要な一歩です。また、新たに決裁供覧前の「組織的共用文書」やフロッピーディスクなどの「電磁的記録」が開示対象に追加されました。これは、従来開示対象とならなかった情報も、一定の条件下で公開される可能性を示唆しています。さらに、県が現在取り扱っている指導要録、県立病院のカルテ、運転免許証、恩給支給などの各種個人情報も開示対象となる可能性があります。ただし、個人情報保護の観点から、県職員の守秘義務の明確化、情報不正流通防止策、個人の情報チェック・管理システム構築、苦情対応窓口設置などの検討が必要となるでしょう。この改正は、情報公開の範囲を広げつつ、個人情報保護の対策も強化するバランスの取れた改定を目指していると考えられます。
3. 各地の個人情報保護条例案
北海道江別市では、市が保有する個人情報の取り扱いルールなどを定める個人情報保護条例の制定に向け、検討委員会が中間報告をまとめました。この報告書では、本人情報の開示や是正などの権利を明記するとともに、非開示事項についても広範に検討されています。パブリックコメントの募集を経て、10月に最終報告がまとめられ、2002年4月の条例施行を目指しています。一方、佐賀市では、「佐賀市個人情報保護制度懇話会」が4月から議論を重ね、9月下旬に市長に提言を行いました。この提言には、故人に関する情報の請求権(財産や損害賠償請求権を相続した遺族なども含む)、自己情報コントロール権(自分の情報について閲覧し、間違いがあれば訂正できる権利)が盛り込まれています。市はこれらの提言を盛り込んだ個人情報保護条例案を議会に提出する予定です。これらの条例案は、個人情報の適切な管理と、個人の権利保護の両立を目指しています。
III.税制 財政関連条例
いくつかの自治体で税制に関する条例改正や新税導入が検討されています。東京都では、自動車交通量抑制のためのロードプライシング導入が検討されており、平日の午前7時~午後7時の都心部への車両課金が提案されています。北海道旭川市では、国民健康保険料の告示方法をめぐる裁判で、市が敗訴しました。また、地方自治体の財政状況を反映し、税収の使途や政策減税の活用に関する議論が活発に行われています。
1. 東京都心の交通量抑制に向けたロードプライシング構想
東京都では、東京都心の自動車交通量を抑制するため、都心部への流入車両に課金する「ロードプライシング」の導入が検討されています。検討委員会は、平日の午前7時から午後7時まで、一定の地域内に入る車両に課金すべきだとする報告書をまとめました。対象地域は都心部から次第に広がる4案が提示されており、今後、産業界や都民の意見を聞きながら、課金額や対象地域などを具体的に詰めていく予定です。2003年度以降の早い時期に導入を目指しており、交通渋滞の緩和と環境問題への対策として期待されています。このロードプライシングは、東京都の交通政策における大きな転換点となる可能性があります。課金額や対象地域の設定には、経済的な影響や社会的な公平性の観点からの慎重な検討が不可欠です。
2. 国民健康保険料に関する裁判判決
北海道旭川市では、国民健康保険料の告示方法をめぐる裁判において、札幌高裁は一審判決を支持し、原告の控訴を棄却しました。旭川市は、議会の議決を経ない告示で保険料率を示していましたが、これは憲法に違反するとして訴えられました。判決は、課税は法律に基づいて行うべきであるという憲法の規定を根拠としており、旭川市のやり方は違法であると判断されました。この判決は、地方自治体における保険料率の決定方法について、法的根拠の明確化を改めて促すものとなりました。国民健康保険料は実質的に税金と同様の性質を持つため、その決定方法の透明性と法令遵守が強く求められます。この判決は、今後の地方自治体の税制運営に大きな影響を与える可能性があります。
3. 地方自治体の税制改正と財政問題
鳥取県では、市町村税制担当を県内の地方課から専門部署に移管する組織改正を行いました。これは、税制の専門性を高め、より効率的な運営を目指すための措置です。また、固定資産税の研究会を設置し、体制強化を図っています。知事は以前から、家屋の固定資産評価基準に市町村の裁量の余地を持たせるべきだと主張しており、今回の改正はこの主張に基づいたものと考えられます。さらに、ある町では、町税滞納額が累計で約1億2000万円に上っており、滞納者への制裁措置を検討しています。制裁内容は、弁護士らから成る有識者の懇話会で決定される予定ですが、行政サービスの制限や名前の公表などが検討されています。これらの事例は、地方自治体における税制や財政運営の課題と、それに対する取り組みを示しています。厳しい財政状況下、税収の確保と公平な税制運営の両立が求められています。
IV.男女共同参画と生活安全条例
男女共同参画社会の実現に向けた条例制定や改正が各地で行われています。具体的には、性差別禁止、被害者救済のための相談機関設置、男女共同参画推進会議の設置などが挙げられます。また、防犯意識の向上や生活安全確保を目的とした条例も制定されており、長野県南佐久郡の8町村では、強盗事件やオウム真理教関連事件を受け、生活安全条例を提案しています。男女共同参画推進と生活安全確保は、地域社会の安心・安全に不可欠です。
1. 男女共同参画推進条例案の内容
ある町の男女共同参画社会推進審議会が答申した条例案は、全19条で構成されています。この条例案は、男女平等推進の基本理念として、「男女がその性別にかかわりなく、個々人がその個性と能力によって評価されること」などを明示しています。性差別を禁止する規定も盛り込まれ、「何人もあらゆる場において、性別による差別的扱い、性的行為の強要または性的言動による生活環境の侵害、個人の尊厳を踏みにじる暴力や虐待を行ってはならない」と明確に定めています。被害者救済のため、相談員やカウンセラーらからなる苦情相談機関の設置や、一時的避難施設の確保も計画されています。これは、男女間の平等な権利と機会を保障し、性差別や暴力から女性を守るための重要な取り組みです。条例案の具体的な内容については、今後さらに詳細な議論が行われるでしょう。
2. 男女共同参画推進会議設置条例案
福岡県直方市では、男女共同参画プランの進捗状況などをチェックする第三者機関として、男女共同参画推進会議の設置を検討しています。このための条例案を6月定例市議会に提案し、可決されれば9月にも設置する予定です。推進会議は、有識者、市民団体代表、市議らで構成され、計画のチェックだけでなく、建議機能も持ちます。男女共同参画に関する施策を調査・研究したり、市長に提言したりする役割を担います。当面は、男女共同参画プランの見直し、特に家庭内暴力の防止策に重点を置く予定です。この会議の設置は、市民参加型の男女共同参画推進体制の構築に繋がる重要な一歩です。会議の具体的な活動内容や成果は、今後の市政運営に大きな影響を与えるでしょう。
3. 生活安全条例案と南佐久郡の取り組み
長野県南佐久郡の全8町村は、防犯や事故防止への啓発活動推進などを盛り込んだ「生活安全条例」を提案する予定です。近年、郡内では強盗容疑事件やオウム真理教(アレフ)による不正土地取得などの事件が多発しており、地域を挙げて防犯意識を高める必要性からこの条例案が作成されました。条例案には、具体的な防犯対策や啓発活動の推進に関する内容が盛り込まれる予定です。推進団体設置についても検討されていましたが、各町村にある既存の団体を活用する方が効率的という見解から、条例案には明記されていません。近年発生した強盗事件やオウム真理教関連事件は、地域住民に大きな不安を与えていると考えられます。この条例は、そうした不安を解消し、地域住民の安全・安心を確保するための重要な取り組みとなります。今後、条例の具体的な内容が注目されます。
V.環境保全と地域振興に関する条例
環境問題への対応として、環境保全条例や関連条例が見直されています。滋賀県では、ごみ散乱防止条例を改正し、違反者への指導条項を設けました。京都府網野町は、鳴り砂の保護を目的とした条例を制定しました。佐賀県では、地球温暖化対策などに対応する環境総合条例案を検討中であり、埼玉県では生活環境保全条例を制定する予定です。さらに、北海道では希少野生動植物の保護条例制定が検討されており、観光振興を目的とした条例制定も進められています。環境保全、観光振興、地域振興は、持続可能な社会の構築に重要な役割を果たします。
1. 京都府網野町の鳴り砂保護条例案
京都府網野町は、鳴り砂で有名な琴引浜の保護のため、たばこのポイ捨てや花火を禁じる条例を制定する方針を決めました。違反者には環境保全講習の受講か現場の清掃を命じ、従わない場合は氏名を公表する予定です。3月の議会に条例案を提出、7月施行を目指しています。日本ナショナルトラストによると、鳴り砂保護の条例は全国初とのことです。これは、貴重な自然環境を守るための積極的な取り組みであり、全国的なモデルケースとなる可能性があります。条例案の施行効果や、違反者に対する罰則の妥当性などが注目されます。
2. 滋賀県のごみ散乱防止条例改正案
滋賀県では、県内のごみ散乱防止を徹底するため、ごみ散乱防止条例の改正案が9月定例県議会に提出されました。改正案では、ごみを捨てて景観を著しく損ねた者に対し、知事が指定する清掃活動への参加を指導できること、そして捨てたごみの回収に従わない者に対し2万円以下の罰金を科すことが盛り込まれています。可決されれば、都道府県で初めて違反者への指導条項が条例で定められることになります。2002年4月から施行予定です。これは、ごみ問題への対策強化を図る重要な改正であり、他の自治体にとっても参考となる事例となります。罰則規定の有効性や、清掃活動への参加指導の実際的な運用方法などが、今後の課題として挙げられます。
3. その他の環境保全条例
石川県辰口町では、空き缶などのごみ散乱や犬のふんの放置を防ぐため、「まちをきれいにする条例」を制定し、2002年1月から施行しています。この条例では、公共施設や他人の土地・建物へのごみ投棄の禁止、犬の散歩時のふん処理義務、自動販売機設置事業者への包装ごみ回収容器設置・管理義務などが規定されています。また、佐賀県では、地球温暖化や環境ホルモンなどに対応する新たな環境総合条例案が県環境審議会に諮問され、来年4月以降の施行を目指しています。埼玉県では、工場などの公害対策を主眼としていた「公害防止条例」を抜本改正し、「生活環境保全条例」を制定する予定です。事業者による環境負荷低減目標の作成、ディーゼル車の運行規制なども盛り込まれています。これらの条例は、環境保全への意識を高め、より良い生活環境を構築するための重要な役割を果たします。各条例の具体的な効果や、地域特性に合わせた対策が注目されます。
4. 北海道の希少野生動植物保護条例と鳴砂保護条例
北海道では、高山植物など北海道の特性を踏まえ、希少野生動植物の保護に積極的に取り組むため、新たな条例を制定することにしました。この条例では、絶滅の恐れのある野生動植物の保護を通じた生物多様性の保全、自然環境の監視活動や調査研究、普及啓発などが盛り込まれる予定です。京都府網野町では、鳴り砂で知られる琴引浜の保護のため、たばこのポイ捨てや花火を禁じる条例を制定する方針を決めました。違反者には環境保全講習の受講か現場の清掃を命じ、従わない場合は氏名を公表する意向です。自然保護に取り組む日本ナショナルトラストによると、鳴り砂保護の条例は全国初とのことです。これらの条例は、地域の自然環境保全に貢献する重要な役割を担っています。条例による効果や、保護活動の進捗状況などが注目されます。
VI.その他条例案
その他、特定の地域課題への対策として様々な条例案が提案されています。例えば、ぼったくり防止条例(福岡県)、個別労使紛争あっせん条例(広島県)、障害者支援条例(全国初)、都市づくり基本条例(東京都)、墓地条例などです。これらの条例は、それぞれの地域特性や課題を反映した、きめ細やかな対策を盛り込んでいます。特に、環境問題への対応や、地域社会の課題解決に貢献する条例が目立ちます。
1. ぼったくり防止条例案
福岡県では、客に料金を不当に請求する行為を防ぐため、「ぼったくり防止条例案」が6月定例県議会に提出され、可決されれば10月1日から施行される予定です。条例案では、福岡市の中洲、北九州市小倉駅前など4地区のファッションヘルス店や飲食店を規制対象としています。これらの店では、料金や違約金を客に見やすく表示することが義務付けられます。また、料金を実際より低く誤認させるような表示や告知、乱暴な言動や所持品を隠すなどして料金を無理やり取り立てる行為などが禁止されます。これは、消費者保護の観点から重要な条例であり、観光客の安心・安全な滞在に大きく貢献するでしょう。罰則規定の内容や、規制対象となる店舗の範囲などが、今後の議論の焦点となる可能性があります。
2. 個別労使紛争あっせん条例案
広島県は、9月定例議会に、個別労使紛争のあっせん制度創設についての条例案を提出する予定です。要綱で制度を設けている県は6県ありますが、条例として制定するのは全国初です。これは、10月1日に施行される国の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に合わせて制定されるものです。使用者、労働者を含む県民に対し、県の業務として個別労使紛争のあっせんに取り組むことを明確にするため、要綱や規則ではなく条例として制定されることになります。あっせんはノウハウのある地方労働委員会が行い、これまでのあっせんと同様の手続きとなる見込みです。広島市中区の歓楽街など県内の6市8地区が規制対象となり、不当な勧誘や乱暴な言動による料金請求などが禁止されます。違反行為に対する罰則も検討されています。
3. 障害者支援に関する条例案
ある市では、後見的支援を必要とする障害者に対する支援を目的とした条例案が12月議会に提案され、来年4月施行を目指しています。同種の条例化は全国初です。条例骨子によると、後見的支援を要する障害者の範囲は、「福祉サービス等を選択して利用することが困難なため、日常生活を営むことができない障害者で、親などがいない、または養護を行うことができないもの」と規定されています。市の責務として、「後見的支援を要する障害者が地域において安心して生活を営むことができるよう、必要な施策を講じる」ことが明示され、市民に対しても協力が求められています。これは、障害者の自立支援と地域社会での共生を促進する上で、極めて重要な条例となります。条例案の具体的な施策内容や、その効果が注目されます。
4. その他の条例案
東京都では、独自の都市づくりを円滑に進めるための「都市づくり基本条例(仮称)」が、早ければ来年の2月定例議会に提案される予定です。この条例案では、都市計画決定の段階で住民や企業、NPOの意見を求める仕組みや、公共事業への民間資金・ノウハウ活用などが盛り込まれる見込みです。また、ある県では、青少年が集まる施設周辺での特定営業の規制を強化する条例改正が行われています。さらに、青森市では、青森ねぶた祭の秩序維持と健全化を目的とした条例の制定が検討されています。これらの条例案は、それぞれの地域社会の課題に対応した多様な内容となっています。これらの条例が地域社会にどのような影響を与えるのか、その効果と課題が注目されます。
