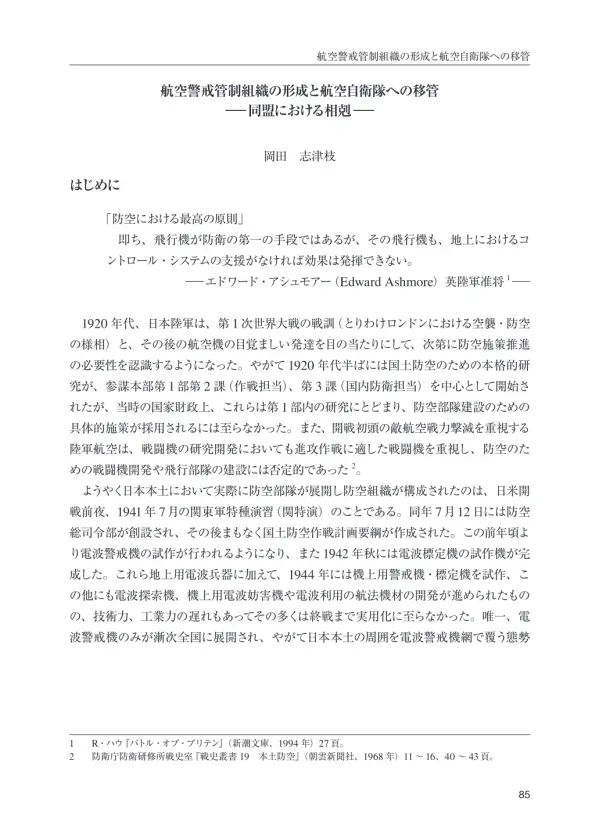
航空警戒管制組織:日米移管と防衛協力
文書情報
| 著者 | 岡田 志津枝 |
| 専攻 | 歴史学、軍事史、国際関係論など |
| 文書タイプ | 論文、紀要論文など |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 678.79 KB |
概要
I.戦前期の日本防空体制 関特演 と初期の電波兵器開発
日米開戦前夜、1941年7月の関東軍特種演習(関特演)で初めて日本本土に防空部隊が展開、防空組織が本格的に構築されました。同年7月12日には防空総司令部が創設され、国土防空作戦計画要綱も策定されました。 1942年秋には電波標定機の試作機が完成するなど、電波警戒機、電波標定機、電波探索機等の開発が進められましたが、技術力・工業力の不足から終戦までに実用化されたのは電波警戒機のみでした。この電波警戒機網は、徐々に全国に展開され、日本本土周辺を覆う体制が整いつつありました。
1. 関東軍特種演習 関特演 と日本本土防空体制の確立
日米開戦前夜となる1941年7月、関東軍特種演習(関特演)の実施により、日本本土において初めて本格的な防空部隊の展開と防空組織の構成が実現しました。この演習は、それまで断片的だった防空体制を強化する転換点となりました。同年7月12日には防空総司令部が創設され、間もなく国土防空作戦計画要綱が作成されるなど、組織的・計画的な防空体制構築に向けた動きが加速しました。 このことは、当時の日本が、増大する航空戦力への脅威を深刻に認識し、国家的な対策を講じ始めたことを示しています。関特演は、単なる軍事演習以上の意味を持ち、日本の防空体制の出発点として歴史に刻まれています。
2. 電波兵器の開発と実用化への道のり
1940年前後から電波警戒機の試作が始まり、1942年秋には電波標定機の試作機が完成するなど、地上用電波兵器の開発が進展しました。さらに1944年には機上用警戒機・標定機を試作するなど、航空機搭載型の電波兵器開発にも着手しています。電波探索機や機上用電波妨害機、電波を利用した航法機材の開発も進められていましたが、当時の日本の技術力と工業力の不足により、これらの多くは終戦までに実用化に至りませんでした。唯一、電波警戒機のみが全国へ展開され、日本本土周辺を警戒網で覆う態勢が徐々に整えられていった点が注目されます。このことは、日本の技術開発が戦争遂行に追いつかず、戦局に大きな影響を与えたことを示唆しています。
3. 戦前期防空体制における課題と陸軍航空の姿勢
1920年代、第一次世界大戦でのロンドン空襲の経験や航空技術の急速な発展を踏まえ、日本陸軍は防空の必要性を認識し始めました。1920年代半ばからは、参謀本部を中心とした国土防空の研究が始まりましたが、国家財政の制約から具体的な施策の導入には至りませんでした。特に、開戦当初の敵航空戦力の撃滅を優先する陸軍航空部は、攻撃的な戦闘機開発に注力し、防空用の戦闘機開発や飛行部隊の増強には消極的な姿勢を示していました。この陸軍航空部の姿勢は、日本の戦前期防空体制における大きな課題の一つであり、防空体制の遅れの一因となったと考えられます。 資源配分における優先順位のずれが、後の戦争遂行に大きな影響を与えたことが分かります。
II.戦後の航空警戒管制組織の形成と 日米安保条約
サンフランシスコ講和条約締結後の再軍備と在日米軍縮小・撤退に伴い、航空警戒管制組織の日本への移管が実現しました。しかし、この移管過程や日米間の交渉については、これまで十分な研究が進んでいませんでした。本稿では、特に1950年代後半の移管期に焦点を当て、日米間の交渉、課題(指揮権、交戦規定、運用手順の整合)、そして残された問題点を明らかにします。 この移管は、将来の有事における日米航空部隊の共同作戦の試金石ともなりました。
1. サンフランシスコ講和条約と航空警戒管制組織の移管
サンフランシスコ講和条約の締結により日本は主権を回復し、再軍備と在日米軍の縮小・撤退が進みました。この流れの中で、それまで米軍が運用していた航空警戒管制組織が日本に移管されることとなりました。この移管は、戦後の日本における防空体制の再構築、ひいては航空自衛隊創設の重要な一歩となりました。しかし、この航空警戒管制組織の形成過程や、米軍から航空自衛隊への移管に関する詳細な記録や議論は、これまで十分に研究されておらず、その歴史的経緯は不明瞭な部分が多く残されています。特に、国会での議論も断片的で、「対領空侵犯措置」や「松前・バーンズ協定」といったキーワードが散見されるのみでした。
2. 航空警戒管制組織移管における日米間の課題
航空警戒管制組織の移管は、日米両国にとって容易では無い課題を数多く提示しました。特に、日米が共通の防空システムを使用する上で、指揮権(作戦統制)、交戦規定、運用手順の整合性をどのように図るかが大きな焦点となりました。これらの問題は、単なる技術的な問題にとどまらず、将来的な有事における日米航空部隊の共同作戦のあり方、つまり日米安全保障体制の根幹に関わる重要な問題でした。 この移管は、単なる組織やシステムの移行ではなく、日米両国の安全保障政策、特に軍事協力体制のあり方を決定づける重要な局面であったと言えます。
III.米空軍による日本の防空 第5空軍 と JADF の役割
1945年9月、第5空軍が日本に進駐し、日本の航空優勢確保、輸送、警戒管制等を担当しました。その後、日本防衛空軍(JADF)が設立され、朝鮮戦争停戦(1954年)までの間、日本の防空と航空自衛隊の創設に貢献しました。JADF初代司令官デマール・スパイヴィー准将は、空軍力の重要性を強調し、航空自衛隊の創設に大きな影響を与えたとされています。 また、米空軍は「チェリーブロッサム・プロジェクト」で日本人技術者を育成し、レーダーサイトの維持管理、航空警戒管制組織の運営に不可欠な技術基盤を構築しました。
1. 第5空軍の進駐と日本防衛空軍 JADF の創設
1945年9月、日本の降伏直後、米陸軍極東空軍所属の第5空軍が、埼玉県狭山市稲荷山(旧陸軍航空士官学校修武台飛行場)に司令部を置き、占領軍として活動を開始しました。当初の任務は、日本への米軍輸送、日本および朝鮮半島(北緯38度線以南)上空の航空優勢確保、海上輸送の護衛、偵察・写真撮影、レーダー警戒管制、遭難救助など多岐に渡りました。終戦直後は、降伏命令伝達のため、日本機の飛行が一時的に許可されていましたが、10月10日にはその任務も第5空軍に引き継がれ、日本機による自国上空の飛行は禁止されました。1947年9月の米空軍創設後、極東空軍は第43航空師団に改編され、JADFの隷下となりました。朝鮮戦争停戦後の1954年9月、第5空軍が日本から撤退するまで、JADFは日本の防空を担当し、同時に航空自衛隊の創設に深く関与しました。JADF初代司令官、デマール・スパイヴィー准将は、空軍力が日本防衛の要であると主張し、後の航空自衛隊創設にも影響を与えたとされています。第5空軍は日本、朝鮮半島とその周辺域の防衛を任務とした一方、JADFは日本の防衛に特化していました。
2. チェリーブロッサム プロジェクトと日本人技術者の育成
1952年4月、対日講和条約発効により日本が主権を回復し、保安隊・警備隊が創設された頃、米空軍は航空警戒管制組織の維持に不可欠なレーダーや通信網の運用・維持を担う日本人技術者の育成に着手しました。この計画は「チェリーブロッサム・プロジェクト」と呼ばれ、約50~60名の日本人が青森県三沢市内の旧海軍将校クラブ跡に集められ、約2年間、米空軍の航空警戒管制組織に関する技術や知識を習得しました。これらの技術者たちは、その後各地のレーダーサイトに赴任し、航空自衛隊発足と同時に隊員として入隊した者、年齢制限などで米軍に残留し部隊建設に貢献した者など、様々な形で日本の防空体制構築に貢献しました。このプロジェクトは、戦後の日本における航空警戒管制技術の移転と人材育成において重要な役割を果たしたと言えます。 三沢基地は、このプロジェクトの中心地として重要な役割を果たしました。
IV.航空警戒管制組織の移管と 松前 バーンズ協定
1950年代後半、航空警戒管制組織は米空軍から航空自衛隊に移管されました。この移管にあたり、1957年6月13日の覚え書き(門叶宗雄防衛庁次長事務代理とバーンズ空軍中将)、そして1958年4月、津島防衛庁長官とスミス第5空軍司令官間の交換文書、**源田實航空集団司令官(のち航空総隊司令官)とスミス司令官の間の「対領空侵犯措置に関する取極」(いわゆる松前・バーンズ協定)**等が締結されました。 これらの合意は、レーダーサイトの移管、運用手順、交戦規定に関する調整を定め、日米間の緊密な防空協力体制の構築に繋がりました。しかし、指揮権の問題は、政治的理由から最後まで正式な合意に至りませんでした。 この問題は、日米安全保障委員会やアドホックな委員会での協議を通じて検討されました。 移管された主要レーダーサイトには、御前崎、下甑島、襟裳が含まれます。
1. 航空警戒管制組織の移管プロセスと段階的移行
1950年代後半、米空軍から航空自衛隊への航空警戒管制組織の移管が行われました。この移管は、一挙に行われたのではなく、段階的なプロセスを経て実施されました。1946年頃からレーダーサイトの整備と航空警戒管制組織の編成・配置が開始され、朝鮮戦争勃発(1950年6月)を機に、より本格的な固定レーダーサイトの建設が進められました。1951年からこれらのレーダーサイトが順次運用開始され、1957年頃には現在の体制に近い状態が整いました。 この過程で、米空軍は最終的な完成図を念頭に置いて整備を進め、初期の簡易なレーダーサイトから恒久的なものへと段階的に更新していったことが伺えます。航空自衛隊は、米空軍から防空組織を引き継ぐため、三沢、入間、春日などの基地で訓練を受け、その後各レーダーサイトに配属され、OJT(On-the-Job Training)を通して実践的な訓練を行いました。1954年9月には浜松(のち名古屋)に中部訓練航空警戒隊(通称9000部隊)も編成され、航空自衛隊の教育・訓練体制が整備されていきました。御前崎、下甑島、襟裳などのレーダーサイトは、航空自衛官が配置され、1957年末には米軍による運用態勢評価試験にも合格するなど、移管への準備が着々と進められました。
2. 1957年覚え書きと日米間の調整 専門家委員会の設置
航空警戒管制組織の移管に向けた最初の具体的な合意として、1957年6月13日、門叶宗雄防衛庁次長事務代理とバーンズ極東軍司令部幕僚長(空軍中将)の間で「覚え書き」が締結されました。この覚え書きは、航空基地とレーダーサイトの移管計画を定めていましたが、あくまで現地レベルでの合意であり、両国政府や軍当局の正式な承認を得たものではありませんでした。 この覚え書きの後、岸首相の訪米を機に日米安全保障委員会が設置され、防空システムに関する問題が議題となりました。アメリカ側は合同委員会での検討を提案しましたが、日本側は国内の政治状況と世論を考慮し、新たにアドホックな委員会を設置することを強く希望しました。 この結果、防衛庁・航空自衛隊と第5空軍から選抜されたメンバーによるアドホックな委員会が極秘裏に設置され、幕僚研究が行われることになりました。この委員会は、日本の防空に関する日米間の協定締結を目指し、1957年12月に「幕僚研究 日本の防空に対する責任」と題する報告書をまとめました。
3. 松前 バーンズ協定の締結と残された課題
1958年4月、スミス在日米軍司令官と津島防衛庁長官の間で書簡交換が行われ、レーダーサイトの引き継ぎ、設備・資材の供与、具体的な調整開始などが正式に合意されました。 その後、5月23日には佐薙毅航空幕僚長とスミス第5空軍司令官の間で「レーダーサイト移管に関する細部取極」が締結され、5月31日には下甑島、6月には襟裳と御前崎のレーダーサイトが航空自衛隊に移管されました。しかし、レーダーサイトの移管後も、共通の防空システム下での運用開始には、手順や対領空侵犯措置の相違をどう調整するのかという課題が残っていました。 この問題に対処するため、源田實航空集団司令官(のち航空総隊司令官)とスミス第5空軍司令官の間で「対領空侵犯措置に関する取極」(松前・バーンズ協定)が締結されました。この協定によって、実務レベルでは緊密な連携が図られるようになりましたが、最大の懸案事項であった指揮権の問題は、政治的理由から正式な合意に至りませんでした。
V. 行政協定 と指揮権問題 総司令官任命問題
1952年の行政協定締結時にも、総司令官任命や統合司令部設置をめぐり日米間で激しい議論がありました。国務省と国防省(JCS、極東軍司令部)の間でも意見対立があり、特にJCSは日本の主権を軽視する姿勢が見られました。アリソンらの反対にもかかわらず、統合司令部の設置や米軍による指揮権については、曖昧なまま残されました。 吉田首相は、有事においては米軍による司令官任命を容認するも、それを秘密にすることを条件としました。
1. 1952年行政協定締結時における指揮権問題
1952年2月の日米行政協定締結時、総司令官の任命や統合司令部の設置を巡り、激しい議論が交わされました。この問題は、航空警戒管制組織の移管問題とは別に、より広範な日米両軍の指揮権に関するものでした。交渉は日米間だけでなく、アメリカ国内でも国務省と国防省(JCSや極東軍司令部を含む)の間で意見の相違がありました。特に、JCSは、刑事裁判権の問題でも示されたように、日本を被征服国とみなすような姿勢を示し、日本政府との協議の上での総司令官任命を拒否しようとする動きがありました。 このJCSの姿勢に対し、アリソンなどから強い反発があり、日本の主権を尊重する必要性が訴えられました。最終的には、「日本政府と協議の上」という文言は残されましたが、総司令官任命問題、統合司令部設置問題は、曖昧なまま残された点に注目すべきです。これは、日米間の安全保障における指揮権のあり方が、未だ明確に合意に至っていなかったことを示しています。
2. 防空システム移管と指揮権問題の再燃
行政協定締結から約5年後、防空システム移管を巡って、総司令官と統合司令部設置の問題が再び浮上しました。これは、航空警戒管制組織の移管に伴い、日米両国がどのように指揮の一元化を図るのかという、極めて現実的で重要な問題でした。 この問題については、1957年6月13日の覚え書きで、米軍指揮官の作戦統制下での防空システム運用が必要であると暗に認めつつも、具体的な実行方法については言及を避けていました。レムニッツァー極東軍司令官は、政府レベルでの協議(合同委員会など)を強く求めていましたが、日本側は政治的理由からこれを回避しようとしていました。レムニッツァー司令官の意見には、有事においては日米の部隊が互いの指示下に入る可能性を示唆する内容が含まれていましたが、この考えは日本側の政治的立場から最終的に受け入れられませんでした。 このことは、当時の日本政府が、国民感情や政治的リスクを強く意識しながら、安全保障政策を決定していったことを示唆しています。
3. 吉田首相の口頭合意と秘密保持
1957年、日米安全保障委員会設置後、岸首相出席の夕食会において、スミス在日米軍司令官(スタンプ太平洋地区米軍総司令官代理)から防空システムに関する問題が提起されました。 日本側は、専門家委員会での検討を希望し、アドホックな委員会が設置されました。この委員会での検討と並行して、有事における指揮権の問題が、日米安全保障委員会でも繰り返し議論されました。この際、吉田首相はクラーク極東軍司令官やマーフィー駐日大使との会談で、有事においては単独の司令官が必要であり、現状ではアメリカが司令官を任命すべきであると口頭合意しました。ただし、この合意は、国民への政治的影響を考慮し、秘密裡に行われるべきであるとされました。この口頭合意は、後年、アリソン駐日大使にも再確認され、日本の政治的状況下における現実的な対応であったと言えます。しかし、この秘密裏の合意は、指揮権問題の透明性を欠き、その後の外交・安全保障上の課題を残すことにもなりました。
VI.防空問題の継続と NORAD との比較
1958年以降も、領空侵犯への対応、松前・バーンズ協定の内容、指揮権の問題などが国会で繰り返し取り上げられました。 航空自衛隊は、米軍のSOP(標準運用手順)を参考にしながらも、独自の運用体制を構築しました。 日米間の防空協力は、**北米防空司令部(NORAD)**の設立と比較検討され、国家主権を考慮した上で、それぞれの指揮系統の下での運用が最終的に決定されました。 松前・バーンズ協定は、日米の機密事項として扱われ、その詳細な内容は長らく公開されませんでした。
1. 航空自衛隊設立後の防空問題と国会での議論
航空警戒管制組織の移管が完了した後も、日本の防空問題は国会で繰り返し取り上げられました。特に、航空自衛隊が創設された後も、1953年1月の岡崎・マーフィー往復書簡に基づく米軍による対領空侵犯措置の扱いが問題となりました。 津島防衛庁長官は、航空自衛隊の能力向上にも関わらず、往復書簡を完全に廃止する段階には至っていないと答弁しています。これは、航空自衛隊の防空能力がまだ十分に整備されておらず、米軍の支援が必要であったことを示唆しています。1958年3月には、津島長官からスミス在日米軍司令官への書簡で、航空自衛隊への領空侵犯対応の指示、米空軍との交戦規定の調整、レーダーサイトの順調な移管などが報告されましたが、指揮権の問題は深く議論されませんでした。 3月には、参議院予算委員会で、社会党の議員から岡崎・マーフィー往復書簡に関する質問が出され、防空問題が改めて注目を集めました。 米大使館は、日本の国会や世論の防空問題への意識が必ずしも統一されておらず、指揮権の問題には特に敏感に反応すると分析していました。
2. 松前 バーンズ協定と日米間の防空協力体制
航空警戒管制組織の移管に伴い、日米両国は共通の防空システムでの運用を開始する必要がありましたが、具体的な手順や対領空侵犯措置の相違をどう調整するのかという差し迫った問題が残されていました。 1958年2月には航空自衛隊の対領空侵犯措置要領が示されましたが、法律や政治上の制約から米空軍の基準とは異なっていました。この状況を踏まえ、津島長官は、米空軍との円滑な調整を図るため、第5空軍作戦指揮所(COC)に航空自衛隊から当直幹部を派遣することなどを決定しました。 また、源田實航空総隊司令官とバーンズ第5空軍司令官の間で締結された「松前・バーンズ協定」は、レーダーサイトの運用や対領空侵犯措置について、日米双方が共通のSOP(標準運用手順)に従い、緊密に連携した防空体制を構築することを目指しました。しかし、この協定においても、指揮権の問題は日米間の政治的状況から、正式には解決されませんでした。 この協定は、日米間の防空協力の枠組みを示す一方で、指揮権という根本的な課題は残されたままとなりました。
3. 指揮権問題とNORADとの比較検討
防空システムの運用においては、複数の国が関与する場合でも、指揮権の一元化が軍事的合理性から求められます。 しかし、安保改定協議中の日本政府は政治的理由から、この問題を正式に協議することを避けました。 少なくとも米側関係者はそう認識していました。最終的には、日米両国の国家方針として、それぞれの国の指揮系統を通じてのみ部隊指揮が行われることが明記され、統合司令部設置や総司令官任命の可能性は否定されました。 この決定は、日本の主権と指揮権を重視した結果であり、日米間の安全保障協力における微妙なバランスを示しています。 この状況は、同時期に設立された北米防空司令部(NORAD)と比較検討されました。NORADは米加両国の防空組織の統合を図りましたが、日本とアメリカの場合は、国家主権の観点から、完全な統合は避けられました。 これは、日米関係における歴史的背景や政治的状況の違いを反映した結果といえます。
