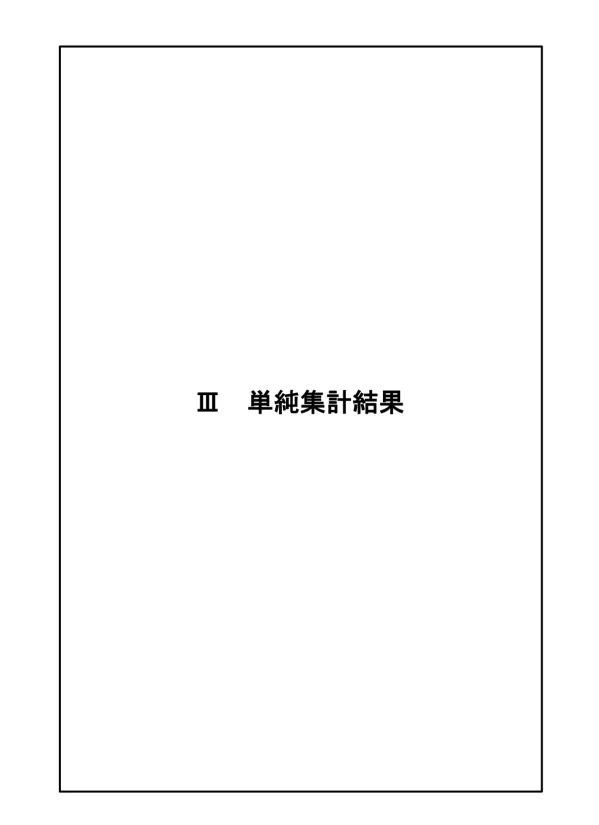
船橋市子育て調査:就労状況分析
文書情報
| 学校 | 大学名不明 |
| 専攻 | 社会学、統計学、または幼児教育関連 |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 8.40 MB |
概要
I.保育施設の利用状況と希望
この調査では、保育施設(幼稚園・保育所・学童保育など)の利用状況と、保護者の希望について分析しています。保育園の所在地、土曜日・日曜日・祝日の利用状況、夏休みなどの長期休暇中の利用希望、病児保育・病後児保育の利用状況などが詳細に調査されています。特に、一時預かりサービスの利用状況や、放課後の過ごし方に関する希望は、ワークライフバランスの実現において重要な要素となっています。保護者は、少人数保育や教育方針の明確な施設を希望する傾向が高いことが示唆されています。
1. 保育施設の所在地に関する希望
調査では、お子さんが通う幼稚園や保育所等の所在地に関する希望について質問が行われています。 現在の利用施設にかかわらず、希望する所在地(船橋市内であれば町名、市外であれば市区町村名まで)を回答するよう求めています。 この質問は、保護者の居住地や通勤経路との関係性、希望する保育施設の種類との関連性などを分析する上で重要なデータとなります。 回答結果からは、保護者の保育施設選択における地理的要因の影響度合いを把握することができ、地域ごとの保育ニーズの把握や、今後の保育施設整備計画策定のための重要な情報となります。 また、このデータは、保育施設のアクセス性や地域特性との関連性などを分析することで、より効果的な保育サービス提供のための戦略立案に役立ちます。 例えば、特定の地域に保育施設が集中している場合、その地域における需要の高さを示唆し、新たな施設の整備や既存施設の増設の必要性を示す可能性があります。
2. 土曜日 日曜日 祝日 長期休暇中の保育施設利用希望
この項目では、土曜日、日曜日、祝日、そして夏休みや冬休みといった長期休暇中の保育施設の利用希望について調査しています。 週末や祝日、長期休暇中は、保護者の就労状況や家庭環境によって保育ニーズが大きく変動するため、この項目のデータは、保育施設の運営計画やサービス提供体制の検討に重要な指針となります。 特に、21時以降の利用希望や、長期休暇中の利用希望に関するデータは、共働き世帯や、特別な事情を抱える家庭のニーズを反映していると考えられます。これらのニーズに応えるためには、夜間や長期休暇中の保育サービスの提供体制の強化、あるいは、柔軟な時間帯設定などが検討課題として挙げられます。 また、無回答の割合も分析することで、これらの時間帯や期間における保育サービスの認知度や利用への障壁を推測し、今後の周知活動やサービス改善に役立てることができます。 これらのデータは、保育施設の運営における柔軟性や対応力の向上、ひいては保護者のワークライフバランス実現に大きく貢献する可能性を秘めています。
3. 病児 病後児保育の利用状況と希望
お子さんの病気やケガで学校を休んだ場合の対応方法、特に病児・病後児保育の利用状況と利用意向について調査しています。 この項目では、お子さんが病気やケガをした際に保護者がどのように対応しているか、そして、病児・病後児保育施設の利用を希望しているかどうかを把握することを目的としています。 具体的には、母親が休んだ、父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた、親族・知人にみてもらった、病児・病後児保育を利用した、ベビーシッターを利用した、子どもだけで留守番させた、などの選択肢が用意されています。 これらの選択肢から、保護者の対応状況や、病児・病後児保育の利用状況、そして利用へのアクセシビリティに関する課題などを明らかにすることができます。 さらに、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利用したかった」という項目への回答状況を分析することで、病児・病後児保育に対する潜在的なニーズを把握し、保育サービスの充実に向けた政策提言を行うための重要な情報となります。 利用状況と希望を比較することで、現状の保育サービスの不足や課題を明確化し、より質の高い、そしてアクセスしやすい病児・病後児保育の提供体制の構築に繋げることが期待できます。
4. 一時預かりサービスの利用状況と希望
私用、保護者・家族の病気やケガ、就労などの目的で一時的に子どもを預けるサービスの利用状況と、今後の利用意向に関する調査です。 この項目では、一時預かりサービスの利用実態と、今後利用したいと考えている保護者のニーズを把握することを目的としています。 具体的には、利用しているサービスの種類や、年間の利用日数、利用目的(私用、保護者・家族の病気やケガ、就労など)について質問しています。 これらのデータから、一時預かりサービスに対する需要の大きさ、利用目的の多様性、そしてサービスの利用における課題などを明らかにすることができます。 例えば、利用日数の分布や、利用目的ごとの内訳を分析することで、サービスの需要を時間帯や時期別に予測し、より効率的なサービス提供体制の構築に役立てることができます。 また、利用したいと考えている人の回答から、今後需要が高まる可能性のあるサービスや、新たなサービス開発のニーズを把握することもできます。 これらのデータは、一時預かりサービスの充実・改善、ひいては保護者のワークライフバランスの向上に貢献する重要な情報となります。
II.育児休業取得状況と職場環境
育児休業の取得状況とその理由、職場環境との関連性が調査されています。多くの回答者が、育児休業取得を妨げる要因として、職場の雰囲気、仕事の忙しさ、収入減などを挙げています。一方で、配偶者の協力や育児休業制度の利用なども影響していることがわかります。育児休業取得期間や、復帰時期についても調査されており、保育園の入所状況が復職のタイミングに大きく影響していることが示されています。企業における仕事と家庭の両立支援の現状や、今後の整備予定についても調査が行われています。特に、育児休業制度、短時間勤務制度、在宅勤務などの制度の有無や、利用可能性が分析されています。
1. 育児休業取得状況と理由
この調査では、育児休業の取得状況とその理由について詳細に分析しています。 回答からは、育児休業を取得しなかった主な理由として、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」(39.3%)、「仕事が忙しかった」(44.3%)、「収入減となり、経済的に苦しくなる」(28.7%)などが挙げられています。 これらの結果は、育児休業制度の利用を阻む要因として、職場環境、経済的不安、そして仕事量などが大きく影響していることを示唆しています。 一方、「配偶者が育児休業制度を利用した」(21.2%)、「配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえた」(40.3%)といった回答も存在し、家庭環境や配偶者の協力体制も育児休業取得に影響を与えていることがわかります。 これらの結果は、育児休業制度の更なる普及・促進のためには、職場環境の改善、経済的な支援策の充実、そして配偶者を含む家族全体の協力を促すための啓発活動などが重要であることを示唆しています。 また、育児休業取得期間や、希望取得期間に関するデータも収集されており、これらのデータは、より効果的な育児支援政策の立案に役立つと考えられます。
2. 職場復帰のタイミングと保育所入所
育児休業からの職場復帰時期と、保育園・保育所等の入所時期との関連性について分析しています。 多くの回答者(84.1%)は、年度初めの保育所入所に合わせたタイミング以外で職場復帰していることが明らかになっています。 これは、希望する保育施設に入所できない場合や、希望する時期に保育所に入所できないという状況下で、やむを得ず希望しない時期に職場復帰せざるを得ないケースが多いことを示唆しています。 この結果から、保育所の待機児童問題や、保育施設の定員不足が、女性の職場復帰時期に大きな影響を与えていることがわかります。 また、年度初めの保育所入所を希望するものの、入所が叶わず、一時的に認可外の保育施設を利用せざるを得ないケースなども含まれており、認可外保育施設の利用状況についても把握する必要があります。 この問題は、保育施設の整備促進、待機児童問題の解消、そして保護者の仕事と育児の両立支援政策を検討する上で重要な課題となっています。 希望する保育施設に入所できる体制づくりが、女性の職場復帰を円滑に進める上で不可欠な要素であることがわかります。
3. 企業における仕事と家庭の両立支援制度
企業における仕事と家庭の両立支援制度の整備状況と、今後の整備予定について調査が行われています。 調査では、育児休業制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度など、様々な制度の有無や、今後の整備予定について質問しています。 回答結果からは、多くの企業において、仕事と家庭の両立支援策が十分に整備されていない現状が明らかになっています。「整備する予定はない」と回答した企業の割合が高いことから、企業側の意識改革や、具体的な支援策の導入促進が喫緊の課題であることがわかります。 また、情報通信技術(IT)を利用した場所・時間にとらわれない働き方の導入についても質問されており、この項目の回答は、今後の働き方改革や、テレワーク推進の動向を把握する上で貴重なデータとなります。 さらに、行政からの支援や補助があれば、企業として仕事と家庭の両立支援策やワークライフバランスの取り組みがしやすくなるという意見も寄せられており、行政による支援の重要性が示唆されています。 これらのデータは、企業における仕事と家庭の両立支援制度の整備促進、そして働き方改革の推進に向けた政策立案に役立つと考えられます。
III.子育てしやすい環境整備への期待
子育てしやすい環境整備のために、国や自治体への期待が調査されています。母子健康手帳の充実、多様な保育サービスの充実、仕事と家庭の両立を支援する制度の整備などが挙げられています。また、ワークライフバランスの推進、子育てに関する社会通念の変化への期待も示されています。調査対象者は、仕事と家庭の両立を支援する行政からの支援や補助を必要としていることが示唆されています。
1. 子育てしやすい環境整備への期待 国 自治体への要望
この調査では、子育てしやすい環境を整備するために、国や自治体に期待することについて質問しています。 回答からは、母子健康診査(妊娠中や乳幼児の健診・ママ教室など)の充実、多様な保育サービスの充実、勤務時間や制度など子育てする者に特化した支援などが求められていることがわかります。 特に、多様な保育サービスの充実という意見が多く寄せられており、これは、多様なニーズに対応できる保育サービスの必要性を示唆しています。 また、仕事と家庭の両立を支援する制度整備や、子育てしやすい社会風土づくりへの期待も示されており、単に保育サービスの充実だけでなく、社会全体の意識改革も必要であるという認識がうかがえます。 これらの回答は、国や自治体による具体的な政策立案において、重要な参考情報となります。 例えば、母子健康診査の充実に関しては、検診体制の強化や、より質の高いサービスの提供が求められるでしょう。 また、多様な保育サービスの充実には、病児保育、一時預かり、学童保育などの整備促進、そしてそれらへのアクセス向上のための施策が重要になります。
2. 仕事と家庭の両立支援 社会全体の取り組み
このセクションでは、仕事と家庭の両立を支援していくために社会全体でどのような取り組みが必要かについての意見を収集しています。 回答からは、夫や家族が家事や育児を分担し、協力すること、子育ては女性がするものという固定的な社会通念を変えること、多様な保育サービスを充実すること、勤務時間や制度など子育てする者に特化した支援策の整備などが挙げられています。 特に、「子育ては女性がするもの」という固定的な社会通念を変えることの重要性が指摘されており、これは、男女共同参画社会の実現に向けた社会全体の意識改革の必要性を示しています。 また、多様な保育サービスの充実や、子育てする者への特化した支援策の整備は、育児と仕事の両立を支援する上で重要な要素であることを示しています。 これらの回答は、企業や行政による具体的な施策の検討、そして社会全体の意識改革を促進するための貴重な情報となります。 例えば、企業は、柔軟な働き方や育児休暇制度の充実、そして育児と仕事の両立を支援する人事制度の導入などを検討する必要があるでしょう。 一方、行政は、多様な保育サービスの充実、そして経済的な支援策の提供などを通して、子育てしやすい環境づくりに貢献していくことが求められます。
3. ワークライフバランスに関する認識と期待
この調査では、ワークライフバランスという言葉の認知度と、その推進に対する意見を収集しています。 ワークライフバランスという言葉を知っているかという質問に対しては、回答者の全員が知っているという結果が得られています。 しかしながら、ワークライフバランスの推進に関して、費用や人材の不足を指摘する意見も多数あり、具体的な取り組みには資源の確保が課題となることが示唆されています。 また、「仕事と家庭の両立支援」は少子化対策であり、行政が行うべきであるという意見や、出産・育児は個人生活に関わることであるという意見も見られました。 これらの意見は、ワークライフバランスの推進における様々な立場や考え方の存在を示しています。 今後、ワークライフバランスを推進していくためには、これらの多様な意見を踏まえ、費用や人材の確保、そして行政と企業、個人のそれぞれの役割を明確化していくことが重要になります。 さらに、社会全体の意識改革や、より効果的な政策立案を行うための更なる調査・分析が必要となります。
