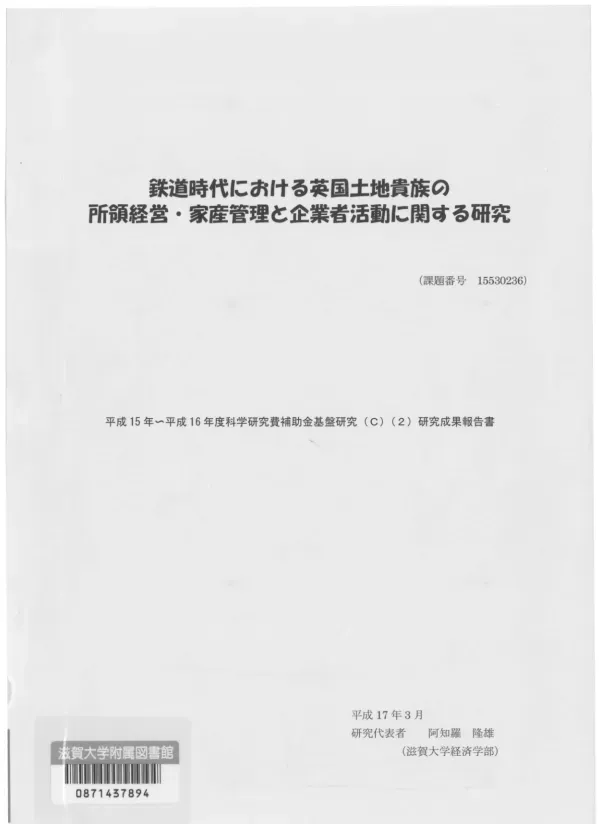
英国土地貴族の企業活動と産業革命
文書情報
| 著者 | 阿知羅隆雄 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 経済学 |
| 出版年 | 2003-2004 |
| 文書タイプ | 研究成果報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 54.73 MB |
概要
I.デヴオンシア公爵家の産業革命期における企業活動と土地所有の変遷
本研究は、19世紀英国における土地貴族(Landed Aristocracy)の代表例として、**デヴオンシア公爵家(Cavendish family)を取り上げ、その企業活動と土地所有構造の変遷を分析する。特に、産業革命の影響下で、従来の所領経営(Estate Management)から資本経営(Capital Management)へと移行していく過程に焦点を当てている。研究対象は、公爵家の広大な所領、特にパロウ・イン・ファーニス(Barrow-in-Furness)**における鉄鉱石開発、製鉄・製鋼業、鉄道建設などを中心とする「産業帝国」の形成と発展、そして「大不況」後の「株式・債券保有貴族(Stock-and-Bond Holding Aristocracy)」への転身である。主要な資料は、パロウの公文書館、チャッツワース・ハウス、ロンドンの事務所などに保管されている同時代の手書き資料であり、これら未開拓の一次資料に基づいた本格的な研究となる。
1. 研究目的と分析方法
本研究は、デヴオンシア公爵家の「ファミリー・ヒストリー」に基づき、同家の企業活動を英国史における現実的役割という観点から明らかにすることを目的とする。単なる家系史にとどまらず、パロウ・イン・ファーニスを中心とした地域史(リージョナル・ヒストリー)の枠組みを用いて分析を行う点が特徴である。特に、産業革命という新たな条件下で、土地貴族が所領経営(Estate Management)から資本経営(Capital Management)への移行をどのように行ったのかを解明する。さらに、パロウ・イン・ファーニスにおける19世紀初頭から20世紀にかけての産業的地域開発と新興工業都市の形成・発展過程、そして「大不況」以降の「株式・債券保有貴族」への転身とその背景にある「シティ・インタレスト」との利害の一体化を分析する。本研究は、パロウの公文書館やチャッツワース・ハウスなどに保管されている、これまでほとんど未開拓であった同時代の手書き資料を本格的に分析することで独自性を確保する。
2. 先行研究の批判的検討
先行研究では、イギリス資本主義の発展を「小生産者的発達の経路」と捉える見解や、ヴィクトリア中期における土地貴族の財政状態回復を過大評価するSpringの見解などが存在する。本研究では、これらの見解を「資本主義発展と土地所有」という視点から批判的に検討する。Springの見解は産業革命と土地貴族の事業活動という視点から意義を持つものの、19世紀後半以降の財政状態を考慮していない。一方、Cannadineの見解は19世紀から20世紀前半の財政状態の推移を明らかにしているが、イギリス資本主義の構造変化との関連を十分に考慮していない。本研究は、これらの先行研究の欠点を克服し、より包括的な歴史像を提示することを目指す。特に、土地所有と資本関係のダイナミックな相互作用に焦点を当て、土地所有者の能動的な役割を明らかにする必要があると指摘している。
3. デヴオンシア公爵家の家産管理と財政状況
1873年の「新ドウムデイ・ブック」によれば、デヴオンシア公爵家は土地所有規模で第7位、地代粗収入で第2位を占める大土地所有貴族であった。第7代公爵は積極的な所領経営を行い、改良地主として知られた。しかし、莫大な負債を抱えており、その返済のため、土地売却を検討した時期もあった。ベッドフォード公爵との書簡からは、公爵の財政状況の苦しさ、土地売却による家名の低下への懸念、そして所領の維持・開発による財政再建への模索が読み取れる。1858年の公爵位継承以降、パロウを中心とした積極的な所領経営と開発は、一時的に財政状況を改善したものの、1880年代以降の「大不況」によって経営危機に陥った。これは、ヴィクトリア繁栄期における高収益連鎖の崩壊、鉄鉱石資源の枯渇、鉄道以外の投資の負担増大などが原因として挙げられる。
4. 土地所有から株式 債券保有貴族への転身と資本 土地所有コンプレックス
1890年代中頃までに、デヴオンシア公爵家はパロウの産業資産をほとんど売却し、資産を土地から有価証券へと転換した。配当収入が地代収入を上回るようになり、「株式・債券保有貴族」へと転身した。これは、19世紀の英国における「古典的帝国主義」の時代、すなわち「工業国家」から「金利生活者国家」への転換期において、自らの経済的利害を「シティ・インタレスト」に同化させる戦略であった。この転身は、それまでの「資本=土地所有コンプレックス」の変容を意味し、土地所有という伝統的な富の源泉から、金融資本への依存を高めたことを示している。しかし、パロウにおける積極的な企業活動は、土地所有を基盤とした機能資本としての活動であり、「株式・債券保有貴族」への転身とは異なる性格を持つ。両者の共通点は、家産管理の危機への対応であるが、そのアプローチは根本的に異なっていた。
II.パロウ イン ファーニスにおける 産業帝国 の形成と発展
パロウ・イン・ファーニスでは、デヴオンシア公爵とパックルー公爵が鉄鉱石資源を独占し、ファーニス鉄道会社の設立を起点に、製鉄・製鋼(Barrow Haematite Steel Co. Ltd.)、造船、港湾開発などを含む垂直統合的な「産業帝国」を構築した。J.ラムスデンなどの実務家と公爵家の連携が鍵となり、高収益を上げた時期もあったが、鉄鉱石資源の枯渇や世界市場の競争激化により、1880年代後半から経営危機に陥り、最終的に経営権を譲渡した。この過程で、地域社会の形成にも大きな影響を与え、熟練労働者と不熟練労働者の階層構造、移民労働者の流入、企業による住宅供給などが明らかになる。
1. 鉄鉱石資源の独占と初期の産業構造
パロウ・イン・ファーニス地域は、英国産業革命期においては後進地域であったが、高品位の鉄鉱石資源をデヴオンシア公爵とパックルー公爵が独占していた。鉄鉱石の採掘は、小土地保有者や小屋住農民を中心とする鉱夫集団によって行われ、「鉄鉱石商人」と呼ばれる借地鉱山業者が鉱区を又貸しすることで鉱夫を支配していた。この構造は、古い地主・借地人関係の名残を残しており、デヴオンシア公爵とパックルー公爵は、この地域における「土地寡頭制」の頂点に君臨していたと言える。 ファーニス鉄道会社の設立は、この鉄鉱石資源開発を促進する重要な契機となった。設立時の取締役会には、両公爵の差配人が含まれており、公爵家の利害が強く反映されていた。B.Curryが初代会長を務め、その後デヴオンシア公爵が1887年に息子のハートントン侯爵に譲るまでその地位にあった。パックルー公爵も1866年に取締役に就任している。このように、両公爵は鉄道経営に直接関与していた。
2. ファーニス鉄道会社を中心とした 産業帝国 の勃興と繁栄
ファーニス鉄道会社は、少なくとも1880年代初頭までは経営的に成功し、高い利益率と配当を記録した。これは、原料や労働力へのコスト削減、大規模生産、そして富裕な株主による積極的な投資が要因として挙げられる。1870~73年の鉄道建設ブーム期には、同社の繁栄を背景に、デヴオンシア公爵とファーニス鉄道会社は、鉄鋼製品の輸出拠点として港湾開発を進め、海運会社や造船会社などの関連産業も発展させた。Barrow Haematite Steel Co. Ltd.の鋼レール生産と輸出を軸に、相互に連携した工場群が形成され、パロウ港と圏内市場を結ぶファーニス鉄道によって、地域経済の高度な発展を促した。この「相関連する諸産業の複合体」は、地域的生産力構造の高まりを示すものと言える。
3. 産業帝国 の崩壊と経営危機
鉄鉱石資源の独占が崩壊し、世界市場における競争が激化する中、パロウ・イン・ファーニスの企業群は経営危機に直面した。1880年代半ばをピークに鉄鉱石生産高が減少、鉄鋼会社の業績は90年代不況で更に低迷した。結果、キャベンディッシュ家とファーニス鉄道会社は、90年代半ばに経営権を「北東岸インタレスト」に譲渡、パロウの諸企業から撤退した。これは、同家の「地主企業家」としての活動の終焉を意味する。 鉄鉱石生産量の減少、近隣に石炭やコークスの供給地がなかったことによる競争力低下が経営危機の主要因であったと指摘されている。ヴィクトリア繁栄期には有効に機能した開発投資は、「大不況」期には逆に大きな負担となり、高収益連鎖は崩壊した。ファーニス鉄道会社は、1923年の英国鉄道の統合まで存続したが、1890年代には観光開発への転換を余儀なくされた。
4. パロウにおける地域支配と労働市場
パロウの「産業帝国」は、地域社会の形成にも大きな影響を与えた。労働市場は熟練労働者と不熟練労働者の階層構造を示し、持続的な産業拡大による労働不足から賃金水準は高かった。労働力供給は移民労働者、特に熟練職種には先進地域から、不熟練職種には周辺地域やアイルランドからの移民に依存していた。多くの移民は当初は単身で移住し、その後家族を呼び寄せる傾向があったものの、単身就労も根強く残っていた。 鉄道会社、鉄鋼会社、造船会社、ジュート会社などの主要企業は、多くの労働者住宅を所有しており、1866年当時から1870年代初めにかけてその数を拡大していた。デヴオンシア公爵家もパロウの土地の3分の1を所有し、住宅所有を拡大していた。J.ラムスデンの証言によると、住宅不足が労働者確保の制約になっていた。パロウは、1867年の市自治体結成以来、近代都市として発展したが、「産業帝国」の企業が地方行政を牛耳っていた。
III.土地所有から金融資本への転換 株式 債券保有貴族への移行
「大不況」期以降、デヴオンシア公爵家は、パロウの産業資産を売却し、資産を土地から株式・債券へと転換。地代収入から配当収入へのシフトにより、「金利生活者国家」の頂点に位置する「シティ・インタレスト」との利害の一体化を果たし、貴族としての地位を維持した。これは、土地所有を基盤とした**資本=土地所有コンプレックス(Capital=Landownership Complex)**の変容を象徴する重要な転換点である。この過程で、高額な負債を抱えながらも、所領の適切な管理と開発によって財政問題に対応した時期もあったことが、ベッドフォード公爵との書簡からも確認できる。
1. 大不況 と土地貴族の資産構成変化
19世紀後半、いわゆる「大不況」により、英国は世界市場での優位性を失い始めた。土地貴族は「農業恐慌」や「土地問題」、1894年の相続税創設など、厳しい状況に直面した。この危機的状況を打開するため、土地貴族は土地資産の売却を進め、その資金を株式や債券などの有価証券に投資するようになった。この資産構成の変化により、彼らは「株式・債券保有貴族(Stock-and-Bond Holding Aristocracy)」へと転身していった。この転換は、単なる経済的な変化ではなく、土地貴族が「古典的帝国主義」の時代において、自らの経済的利害を「シティ・インタレスト」と結びつける戦略的な行動であったと言える。これにより、従来の政治的・社会的地位を維持し、貴族としての存続を図ることができた。
2. パロウにおける産業資産の売却と財政状況の推移
1890年代中頃までには、キャベンディッシュ家はパロウの産業資産(鉄道会社を除く)をほぼ全て売却した。これは、19世紀末から始まった「所領の崩壊と譲渡の時代」における大きな転換点であった。1920年代の中頃までには、配当収入が地代収入を上回り、全収入額の3分の2を占めるようになった。このことは、キャベンディッシュ家の資産構成が根本的に変化し、「土地貴族」から「株式・債券保有貴族」への転換が完了したことを示している。 チャッツワースのデヴオンシア・コレクションには、1834年から1880年代にかけての公爵家の財政状況を示す複数の総括表が存在する。これらの資料からは、積極的な所領経営と開発が財政状況の改善に貢献した一方、「大不況」期には深刻な経営危機に陥ったことがわかる。特に1888年の財政状況は、負債がピークに達し、収入が激減したことを示している。
3. 地主企業家 と 株式 債券保有貴族 異なる資本主義への対応
パロウにおけるデヴオンシア公爵家の企業活動は、「土地所有の資本化」という点では「株式・債券保有貴族」への転身と共通点を持つが、本質的には異なるものである。19世紀におけるパロウでの活動は、鉄鉱石資源の開発を起点に、鉄道経営を基礎として鉄鋼生産や輸出までを掌握する垂直統合的な「産業帝国」の構築であり、土地所有を基盤とした機能資本としての活動だった。一方、「株式・債券保有貴族」への転身は、貨幣資本としての機能を担い、土地所有という性格を止揚するものである。両者の違いは、土地所有への依存度と資本主義への関わり方の違いにある。しかし、両者の背景には家産管理の危機が存在し、1840年代には「支出削減と土地改良」による家産維持と「土地売却と純粋レンティエ化」という対立する二つの見解が存在していた。「株式・債券保有貴族」への転身は、後者の立場に基づくものであったと言える。
4. 資本 土地所有コンプレックスと英国資本主義の変容
デヴオンシア公爵家の「株式・債券保有貴族」への転身は、英国資本主義の構造変化を反映している。それは、「工業国家」から「植民地帝国主義・金利生活者国家」への編成替えの時代、まさに「金利生活者国家」の頂点に位置する「シティ・インタレスト」の利害に同化することで、貴族としての延命を図る戦略であった。 この転身は、エンパイアのエスタブリッシュメントに特有の「資本=土地所有コンプレックス(Capital=Landownership Complex)」の変容を示すものであり、英国金融資本が土地売却資金による土地所有の「富」を動員して海外膨張を進めたことを示唆している。 デヴオンシア公爵家の事例は、19世紀英国における土地貴族の経済的・社会的役割の変化、そして英国資本主義の発展過程における土地所有と金融資本の複雑な関係を理解する上で重要な示唆を与えている。
IV.地域経済と資本による地域支配
本研究は、地域経済の構造を土地資源と人的資源の存在形態、それらの結合と掌握の諸形態という視点から捉え、地域支配を論じる。パロウにおけるデヴオンシア公爵家の活動は、企業による住宅供給、都市インフラ整備、地方行政への関与などを通じて、地域社会を広く支配する「資本による地域支配」の一例として考察される。この資本による地域支配においては、労働者に対する資本の所有権の実現が重要な要素であり、ブルジョア民主主義的形態を通じた統治が分析される。
1. 地域経済の概念規定と分析枠組み
本研究における「地域経済」とは、地域的「富の源泉」(土地と人)の存在形態、それらの結合と掌握の諸形態の発展を軸に捉えられる構造である。この構造は自足的なものではなく、国内外の分業構造や資本主義の世界史的段階に制約される。したがって、地域経済の発展は資本主義の世界史的諸段階と関連付けて捉える必要がある。この枠組みを用いて、大土地所有貴族の経済活動を分析することで、彼らが英国史において果たした現実的な役割を明らかにすることを目指す。 本研究は、ファミリー・ヒストリーで示された史実をリージョナル・ヒストリーに位置づけることで、土地貴族の企業活動の役割を詳細に分析することを試みる。地域における富の源泉、その結合と掌握形態の発展を軸に地域経済を捉え、資本主義の世界史的段階との関連性も考慮する点が重要となる。
2. 資本による地域支配 パロウ イン ファーニスの事例
パロウ・イン・ファーニスにおけるデヴオンシア公爵家の活動は、「資本による地域支配」の典型例として分析される。資本による地域支配は、まず「富の源泉」である土地と人への支配から始まる。パロウでは、デヴオンシア公爵家は、鉄鉱石資源を独占し、ファーニス鉄道会社設立を起点に、鉄鋼、造船、港湾開発など広範な産業を支配する「産業帝国」を築いた。この「産業帝国」は、労働者の雇用、住宅の賃貸、さらには治安判事や市会議員への関与を通じて、地域社会全体を支配していた。 この支配構造は、労働者の生活、仕事、税金、そして自由までもが企業に依存する状態を生み出し、労働者クラブさえも家賃徴収の代理機関のような役割を果たしていた。この事例は、ブルジョア社会における社会的共同業務の本質が、労働力に対する資本の所有権の実現にあることを示唆している。
3. 地方政府と資本によるパターナル支配からの転換
1867年の市自治体結成は、ファーニス鉄道会社による直接統治から地方政府による統治への転換、すなわち私的企業によるパターナルな支配から近代的な住民支配への転換を意味する。しかし、市議会、教育制度、新聞、労働者の諸制度などの主要な組織には「産業帝国」のメンバーが深く関与しており、資本による地域支配は依然として強い影響力を持っていた。 S. Pollardは、パロウの地域支配について、「土地は、すべてを支配する現在の支配者たちによって独占されている」と指摘している。この支配構造の下では、労働者の仕事、住宅、税金、そして自由さえもが企業の掌握下にあり、労働者は企業への依存から逃れることが困難な状況にあった。この様な「資本による地域支配」は、地域独占利潤の獲得と安定的再生産を確保するためのメカニズムとして機能していたと言える。
4. 地域支配 概念の経済学的考察
本研究では、「地域支配」概念を経済学的視点から考察する。資本による地域支配は、地域経済における「富の源泉」への支配、すなわち土地と人への支配を基礎としている。 ブルジョア社会における社会的共同業務は、労働力に対する資本の所有権の実現という点で理解されるべきであり、自立した個人の共同業務ではない。しかし「賃労働者の独立」という外観は、個人的消費が単純流通の形式に包摂されている限り維持される。この形式を介して、資本の所有権が実現されるのである。この資本による地域支配は、一定の限界内にとどまる傾向がある。地方政府による社会的共同業務も、この資本による地域支配との関係において位置付ける必要がある。
