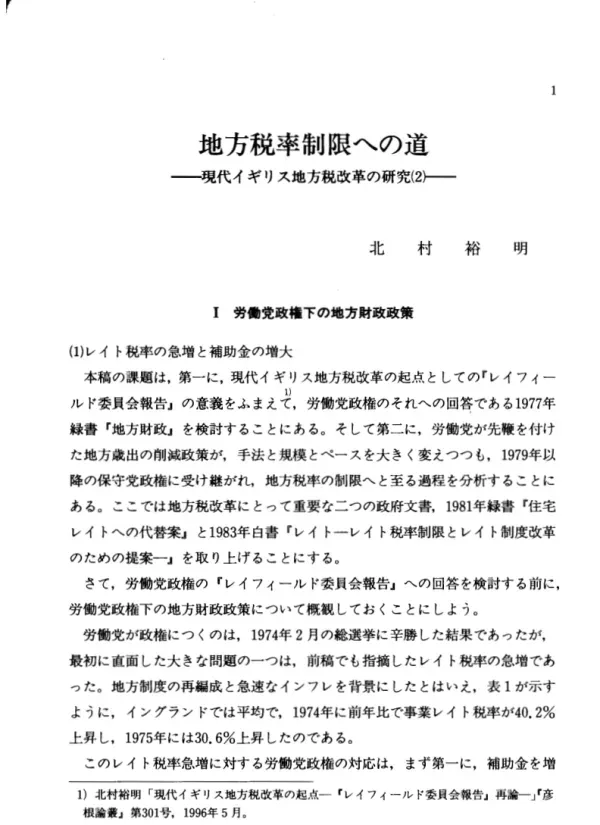
英国地方税改革:税率制限への道
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 879.01 KB |
概要
I.労働党政権下の地方財政改革と レイフィール ド委員会報告 への対応
本稿は、1970年代後半のイギリスにおける【地方財政改革】を分析します。特に、画期的な報告書である【レイフィール ド委員会報告】と、それに対する労働党政権の回答である1977年緑書『地方財政』に焦点を当てます。1977年緑書は、【単一補助金】導入を提案しましたが、地方自治体の強い反対に遭い頓挫しました。この緑書は、【財政責任】を地方住民の税負担の自覚という観点から論じており、中央政府と地方自治体の関係において、【パートナーシップ】を強調しつつも、実質的には【集権化】への道を歩み始めたと批判されています。労働党政権は、IMFからの借入を背景とした【歳出削減】政策を推進し、【地方歳出】の抑制に努めました。補助金の比率の減少や【キャッシュ・リミット】導入などがその具体策です。
1. レイフィール ド委員会報告と1977年緑書 地方財政
本節は、現代イギリス地方税改革の出発点として位置づけられる『レイフィール ド委員会報告』の内容と意義を検証し、労働党政権によるその受け止め方である1977年緑書『地方財政』を詳細に分析します。レイフィール ド委員会報告は、地方財政改革の抜本的なプランを提示しましたが、1977年緑書は、地方所得税導入などの報告書の主要提案を受け入れず、代わりに単一補助金導入を提案しました。しかし、この単一補助金は地方自治体からの強い反対を受け、実現には至りませんでした。緑書における中央政府と地方自治体の関係は、「パートナーシップ」という用語を用いながらも、地方自治体の役割を明確にすることなく、実質的な集権化への道を開いたと批判されています。この緑書は、財政責任論を、地方財政の住民への分かりやすさという観点から論じており、『レイフィール ド委員会報告』が提起した中央政府と地方自治体の責任の明確化というメッセージを消し去ったとも解釈できます。 また、地方歳出の統制の必要性、地方税納税者間の公平性、地方有権者の財政責任、政府の政策統制といった観点から、中央政府と地方自治体が緊密な協議を行う必要性が強調されています。
2. 労働党政権の歳出削減政策と財政責任論
この節では、労働党政権が先鞭をつけた地方歳出削減政策の具体的な手法、規模、ペース、そしてその政策がもたらした結果について分析します。経済危機の深刻化とIMFからの借入を背景に、歳出削減は不可避となり、優先順位の高い政策課題として位置づけられました。そのため、地方基準歳出に占める補助金の比率は減少に転じ、1976年度より導入されたキャッシュ・リミットは補助金の追加的歳出を大きく制限しました。1977年11月の『レイト援助交付金報告』では、中央政府と地方自治体の歳出統制により財政見通しが改善したと報告されています。しかし、政府と地方自治体の責任分担が明確でなかった点を政府自身も認めており、国民経済や社会的優先度の短期的な変化への対応が、政府と地方自治体の関係変化を余儀なくさせたとの説明がなされています。 政府は責任の明確化は望ましいものの、基本的な責任関係の再定義は地方財政問題解決に必要ないという立場を示しました。この中央政府と地方自治体の関係、そして財政責任論に対する認識は、ジョーンズ教授とスチュアート教授らから厳しい批判を受けました。彼らは、77年緑書がパートナーシップという言葉を使いながらも地方自治体の役割を明確化せず、集権化に道を開いたと指摘しています。
3. 1977年緑書における地方税改革とレイト制度
1977年緑書における地方税改革の具体的な内容、特にレイト制度の改革に関する提案を分析します。緑書は、レイトは様々な問題点を抱えつつも継続されるべきであり、事業レイトの課税ベースは賃貸価額のままで良いが、住宅レイトは資本価額を課税ベースとするべきだと提唱しました。しかし、課税ベースの再評価は1982年まで先延ばしされました。この節では、1977年緑書がレイフィール ド委員会報告の基本的立場を否定している点を明らかにし、地方財政責任が地方で調達される歳入の割合に依存するという考え方を批判的に検討します。 また、緑書は単一補助金を提案しましたが、これは歳出評価以上の歳出を行う地方自治体への補助金を削減するための政府への手段を与えるものでした。地方団体の反対により実現しなかった単一補助金の仕組みと、その背景にある地方自治体への統制強化の意図を分析します。さらに、政府が特定のサービスを促進しようとする手段として特定補助金の存続を主張している点にも注目します。
II.保守党政権下の地方歳出削減と レイト 制度改革
1979年以降の保守党政権は、労働党政権の政策を引き継ぎつつ、より大規模な【歳出削減】と【レイト】(地方固定資産税)制度改革を進めました。1980年地方自治・計画・土地法による【包括補助金】導入がその中心です。しかし、1981年5月の地方選挙で労働党が主要都市を制圧したことで、歳出削減は失敗に終わります。保守党は、過剰な【地方歳出】を抑制するため、1982年地方財政法で【レイト】の年度途中での追加徴収を禁止し、税率の上限規制を設けるに至ります。これは【レイト】制度改革の一部であり、住宅【レイト】の課税ベースを賃貸価額から資本価額に変更することなども検討されました。
1. 包括補助金導入と歳出削減政策
この節では、保守党政権下における地方歳出削減政策の中心施策であった、1980年地方自治・計画・土地法による包括補助金導入について詳述します。労働党政権下で既に始まっていた歳出削減政策は、保守党政権下でさらに大規模に進められ、その規模はIMFからの借入があった1976年度の労働党政権下の削減率と比較しても非常に大きいものでした。保守党政権はまず、補助金の額を削減し、1979年6月にはレイト援助交付金3億ポンドの削減が宣言され、1981年度には地方基準歳出に対する補助率がイングランドで59.1%にまで切り下げられました。 包括補助金導入は補助金制度そのものの変更であり、地方自治体への財政支援の仕組みに大きな変革をもたらしました。しかし、この包括補助金による歳出削減は失敗に終わります。その主な理由は、1981年5月の地方選挙で多くの主要都市が労働党の支配下に転じ、大規模な超過歳出が行われたこと、特に大ロンドン都における低運賃政策などが挙げられます。当初60.1%であったイングランドの補助率は、保守党支配下の自治体への影響を考慮し59.1%への切り下げにとどめられましたが、政府は包括補助金の基本メカニズムによる歳出削減に自信を失い始めました。
2. レイト税率制限への道 地方財政法の制定と1981年緑書
保守党政権は、包括補助金による歳出削減の失敗を受け、レイト税率の制限へと向かいます。その過程で重要な役割を果たしたのが、1981年緑書『住宅レイトへの代替案』と1982年地方財政法です。1981年緑書は、保守党内におけるレイト改革への強い圧力への対応策として発表されました。この緑書は、従来の枠組みを超えるものではありませんでしたが、後の政策を予測させる分析と提案が含まれています。緑書は、地方税の必要条件として実行可能性、公平性、財政責任、徴税コスト、国税との調整、税収の予測可能性、普遍性を挙げ、住宅レイトの問題点を指摘し、代替案を検討しています。 また、政府は地方財政法の制定を通じて、レイトの年度途中での追加徴収禁止、一定水準を超える税率が必要な場合の住民投票義務化、補助金撤回制裁措置の合法化などを試みました。住民投票については保守党内からの批判で撤回されましたが、レイトの年度内追加徴収禁止は法律として成立し、地方自治体の財政運営上の裁量性は縮小しました。この地方財政法は、レイト税率制限への道を切り開く重要な一歩となりました。
3. 1983年白書 レイト と選択的税率制限
1983年白書『レイト』は、1981年緑書と1982年環境委員会報告への政府の正式な回答であり、地方自治体のレイト税率設定権限への法的制約を明確に打ち出した政府文書です。白書は、地方自治体の歳出が国民経済に占めるべき割合は中央政府の経済管理の戦略的領域であり、政府は地方歳出に影響力を及ぼさなければならないと主張し、レイト税率制限を提案するに至った理由として、地方自治体の過剰な歳出、事業レイトの重い負担、高いレイト税額による賃金上昇への圧力などを挙げています。 代替案として検討された地方売上税、人頭税、地方所得税は、それぞれ問題点や政治的状況から導入が見送られ、レイトは地方自治体の収入の主要源泉として存続すべきだと結論づけられました。具体的なレイト税率制限としては、選択的税率制限が提案されました。これは、超過歳出を行っている自治体に対して、歳出と税率の両方に制限を加えるもので、補助金関連歳出と実際の歳出額の差を基準に税率制限を行う自治体が事前に選定され、歳出水準とレイト税率の上限を中央政府が決定するという仕組みです。予算総額が1000万ポンド以下の自治体は対象外とされました。
III.住宅レイトの代替案と地方税改革の難航
1981年緑書『住宅レイトへの代替案』では、住宅【レイト】の代替案として、【地方所得税】や【人頭税】が検討されましたが、それぞれ実行上の困難や政治的制約から導入は見送られました。【地方所得税】導入は、政府の直接税負担削減政策に反するとの懸念がありました。【人頭税】は、税負担の自覚という点では優れているものの、低所得者への影響や徴収コストが課題でした。最終的に、保守党政権は、【レイト】制度の維持と税率制限という現実的な選択をします。この過程で、【財政責任】の問題は、税負担と投票権の関係に焦点が絞られていきます。これは、後の【地方税率制限】政策へとつながる重要な転換点です。
1. 1981年緑書 住宅レイトへの代替案 住宅レイト問題と代替案の検討
この節では、保守党政権下で発表された1981年緑書『住宅レイトへの代替案』の内容を分析します。この緑書は、保守党内におけるレイト改革への強い圧力への政府の対応策として位置づけられます。 緑書は、住宅レイトが受益と負担の関係、支払い能力への対応、課税ベースの情報不足といった点で問題を抱えていることを認め、代替案の検討に入ります。しかし、この緑書は、1971年の保守党政権下の緑書『地方財政の将来像』や1976年の『レイフィール ド委員会報告』の枠組みを超えるものではなく、いくつかの点で後の政策を予測させる分析と提案にとどまっています。住宅レイトの代替案として、地方所得税や人頭税が検討されていますが、緑書は地方税の必要条件として実行可能性、公平性、財政責任、徴税コスト、国税との調整、税収の予測可能性、普遍性を提示し、それらの観点から代替案を評価しています。具体的には、住宅レイトを他の税に一挙に置き換えることは不可能であり、住宅レイトの改善を移行期の手段として検討すべきだと結論づけています。
2. 地方所得税 人頭税 地方売上税の評価
本節では、住宅レイトの代替案として検討された地方所得税、人頭税、地方売上税のそれぞれについて、緑書における評価を詳細に分析します。地方所得税については、『レイフィール ド委員会報告』を基本的に踏襲しつつ、源泉徴収制度を活用した国税所得税との統合モデルや、年末の所得評価方式変更の場合の地方所得税への影響について詳細な検討を加えています。しかし、地方所得税導入には、コンピュータ化への移行といった技術的な課題や、政府の直接税負担削減政策との矛盾といった政治的課題が指摘され、1990年代までは導入不可能と判断されています。人頭税については、税の支払い自覚という点で優れているものの、低所得者への影響や徴収上の問題点が指摘され、導入には消極的な見解を示しています。地方売上税についても、取引の定義、消費と企業の消費の区分、付加価値税との関係、税率の違いによる越境買い物、支払い自覚の欠如、税収予測の困難さといった問題点が指摘され、補完税としてカウントイレベルの税として実行可能という結論に留まっています。
3. 住宅レイト改革と財政責任 資本価額への移行とカウンスル税への布石
この節では、緑書における住宅レイト改革の提案、特に後のカウンスル税につながる提案に焦点を当てます。レイト負担の公平性の観点から、所得はあってもレイトを支払っていない層への課税や、レイト割引制度の改善が検討されましたが、実行上の困難や費用面から消極的な判断が下されています。一方、『レイフィール ド委員会報告』が提起した課税ベースを賃貸価額から資本価額に変更することについては、客観的なデータが多く存在し、納税者にも理解しやすいという理由から支持されています。 注目すべきは、カウンスル税につながる二つの提案です。一つは、レイトを直接支払っていない稼得者への課税よりも、単一稼得者の家計への割引の方が実行可能性が高いという指摘であり、これはカウンスル税における単身家計への割引の原型と考えられます。もう一つは、事業レイトの課税を通じて商業・産業への地方自治体の要求を制限するために、中央政府に事業レイト税率決定権を与えるという提案です。これは、全国事業レイト税率導入の先行事例として捉えることができます。これらの提案は、財政責任論が地方税納税者の保護という視点に置き換えられ、納税者の税負担の自覚を重視する方向へと転換していく過程を示しています。
IV.地方税率制限と地方自治体の対応
保守党政権は、過剰な【レイト】税率を抑制するため、1984年レイト法で【地方税率制限】を導入しました。当初、制限の適用を受けた自治体の多くは労働党支配下であり、強い反発を受けました。しかし、法律で定められた期限までに税率を設定せざるを得ない状況に追い込まれ、労働党支配下の自治体は、歳出カットではなく【リザーブ】の巧妙な活用という新たな戦略に転換していきました。【地方税率制限】は、中央政府による地方自治体への【集権化】をさらに推し進める結果となりました。1985年地方自治法による大都市の簡素化もこの流れの中で実施されました。
1. 地方税率制限の導入と1984年レイト法
この節では、保守党政権によるレイト(地方固定資産税)税率制限の導入と、その根拠となった1984年レイト法について詳述します。政府は、地方自治体の過剰な歳出、事業レイトの重い負担による企業競争力の阻害、高いレイト税額による賃金上昇への圧力などを理由に、地方自治体のレイト税率設定権限に法的制約を加えることを決定しました。1981年地方財政法案で提案された例外的に高い歳出や税率設定時の住民投票は実現しませんでしたが、税率制限は、地方歳出の直接統制への移行、そして財政の集権化をさらに進める政策として位置づけられました。税率制限の適用基準は、1984年度予算額が補助金関連歳出の20%を超え、かつ歳出目標の4%を超えている地方自治体と設定され、最初に18の自治体が選定されました。しかし、政府は適用にあたって慎重な行動を取り、いくつかの自治体の上限は緩和されました。この税率制限は、多くの労働党支配下の自治体(16自治体)に適用され、それらの自治体は税率制限に反対し、税率を設定しない共同声明を発表しました。しかし、法律で税率設定期限が定められていたため、最終的にはほとんどの自治体が税率を設定せざるを得ませんでした。
2. 地方自治体の対応とリザーブの活用
本節では、レイト税率制限導入に対する地方自治体の対応と、特に労働党支配下の自治体におけるリザーブの活用について分析します。税率制限の適用を受けた自治体の多くは労働党支配下にあったため、強い反発が予想されました。当初、労働党支配下の自治体は税率を設定しないという抵抗策をとりましたが、地方監査人の警告(期限までに税率を設定しなければ課徴金と解職手続きに入る)により、ほとんどの自治体が税率を設定せざるを得ませんでした。その後、労働党支配下の自治体は戦略を転換し、歳出をカットせずにリザーブを巧妙に活用するようになりました。 このリザーブの巧妙な活用は、政府の歳出削減政策の意図を阻害する効果がありました。1986年度には12団体が税率制限の適用を受け、そのうち10団体は前年度からの継続で、新規に2団体が適用されました。 この節では、地方選挙のサイクルの問題点も指摘されています。イギリスでは、国政レベルの政権党が地方選挙で政治的支配を失いがちな傾向があり、1981年5月の地方選挙で労働党が多くの都市団体を掌握したことが、政府の歳出削減政策に大きな影響を与えたことがわかります。
3. 大都市の簡素化と広域共同行政機関の設立
この節では、保守党政権下の地方自治体改革において、大都市の簡素化と広域共同行政機関の設立という政策の背景、過程、結果について解説します。1985年地方自治法による大都市の簡素化は、浪費的で不要な大都市カウンティと大ロンドン都を廃止し、その機能をバラやディストリクトに再配分することを目的としていました。広域的な処理を要する警察、消防、都市交通などの機能については、機能別の広域共同行政機関が新たに設立され、それらに移行されました。 しかし、この改革によって設立された広域共同行政機関は、既存の内ロンドン教育庁と共に3年間、税率制限の適用を受けました。これは、1985年地方自治法で規定されていた点であり、大都市簡素化政策が、地方自治体への中央政府による統制強化と密接に関連していることを示しています。 この節は、地方税率制限が、地方自治体の「パートナーシップ」という名の下に否定され、財政責任論が地方税納税者の税負担の自覚という点に限定され、最終的には投票権の関係へと焦点が絞られていった過程を説明しています。
