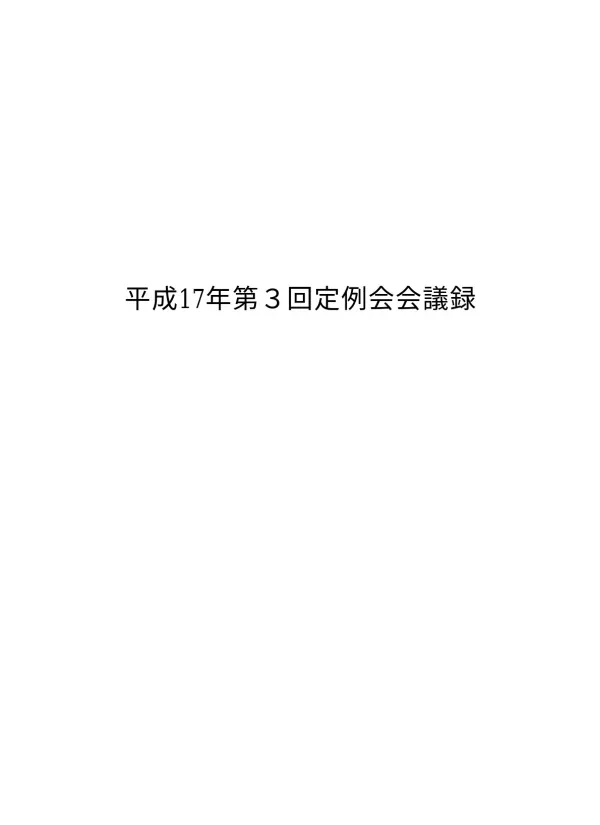
菊池市議会定例会会議録:議事日程と議案
文書情報
| 学校 | 菊池市議会 |
| 専攻 | 地方議会 |
| city | 菊池市 |
| 文書タイプ | 議事録、会期日程表 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.92 MB |
概要
I.平成17年度菊池市一般会計補正予算の概要と課題
この議案では、菊池市の平成17年度一般会計補正予算(歳入歳出計242億5,847万3,000円、増額分9,970万9,000円)が説明されています。主な補正内容は、人事院勧告に基づく職員給与改定、新庁舎建設に向けた基本計画策定業務委託、介護保険制度改正に伴うシステム改修費、道路・橋梁整備、都市整備、住宅整備、教育施設整備など多岐に渡ります。特に、赤北花房中央地区換地確定に伴う用地購入(416万7,000円)や隈府地区回遊道路の測量設計委託(1,119万円)、隈府中央線の建物・立木補償(3,414万2,000円)などが挙げられます。しかし、国の三位一体改革による財政悪化が深刻な課題として指摘されており、合併後の改革の必要性が強調されています。
1. 平成17年度一般会計補正予算の概要と総額
議案第120号として提出された平成17年度菊池市一般会計補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ9億9700万9000円を追加し、歳入歳出とも242億5847万3000円とするものです。この大幅な予算増額の理由と、その使途の内訳が詳細に説明されています。補正予算の規模の大きさと、その財源の確保方法、そしてその後の財政状況への影響が重要な論点となります。資料によると、この補正予算は、市町村合併後の新たな菊池市における行政運営の基盤整備と、市民サービスの向上を目的としていることが示唆されています。しかし、この予算規模の妥当性と、財政健全化とのバランスが問われる点、そして具体的な歳入確保策が明確に示されているかどうかも重要な検討事項です。今後の財政運営に大きな影響を与える可能性があるため、詳細な内訳と財源の確保方法、そして財政状況への影響予測などが求められます。
2. 人事院勧告に基づく給与改定と人件費補正
補正予算の大きな部分を占めるのが、人事院勧告に基づく職員給与改定です。国家公務員の給与改定に準じた形で、菊池市の一般職職員の給与改定と異動に伴う人件費の補正が行われます。これは、職員の待遇改善とモチベーション向上を目的としていますが、同時に、財政負担の増加も避けられないため、その財源の確保方法や、他の事業への影響が重要な検討事項となります。この人件費補正の具体的な金額や、職員数、そして給与改定率などのデータが提示されているかどうか、また、この改定が職員の士気向上に繋がるかどうかについても検証が必要です。さらに、この人件費増加分を吸収するための財政措置や、将来的な財政への影響についても詳細な分析が求められます。
3. 新庁舎建設関連費用と庁舎周辺整備
新庁舎建設に向けた費用も補正予算に含まれています。具体的には、庁舎周辺整備の基本構想と新庁舎基本計画の策定業務委託費用が含まれます。これは、新庁舎建設という大規模事業に向けた準備段階の費用であり、将来的な巨額の財政支出を伴うことから、その計画の妥当性と費用対効果が議論の焦点となります。この委託費用の金額、委託先の選定方法、そして事業計画の進捗状況などが重要な情報です。また、新庁舎建設全体の事業計画、予算、そして建設場所の選定についても、市民への説明と合意形成が不可欠です。特に、財政負担の大きさを考慮すると、建設場所の選定における市民参加や意見聴取のプロセスが透明性を持って行われているかどうかも検証が必要です。
4. 介護保険制度改正に伴う費用とその他の事業費
介護保険制度の改正に伴い、電算システムの改修費として介護保険特別会計への繰出金が計上されています。これは、制度改正への対応に不可欠な費用ですが、同時に、財政負担の増加につながるため、その必要性と費用対効果が検証されます。この改修費用の詳細な内訳、改修内容、そして導入するシステムの安全性や効率性などが重要な検討事項となります。また、重度心身障害者医療費や乳幼児医療費の増額、水道事業会計への負担金、建設部の道路・橋梁整備費、都市整備関係、住宅関係、教育関係の事業費確定に伴う補正なども含まれており、これらの事業の必要性と優先順位、そして財源の確保方法について議論が行われます。各事業の費用と、その効果、そして財政への影響を総合的に評価する必要があります。
5. 個別事業における補正内容の詳細と財政状況への影響
補正予算には、赤北花房中央地区の換地確定に伴う用地購入費(416万7000円)、隈府地区回遊道路の測量設計委託料(1119万円)、隈府中央線の建物・立木補償費(3414万2000円)、公営住宅の維持修繕費用(419万5000円)、戸崎小学校の資料室改修工事費(900万円)、要保護・準要保護児童生徒数の増減に伴う教育振興費の増減など、具体的な事業内容と費用が示されています。これらの事業の必要性と優先順位、そして財政状況への影響について、詳細な説明と分析が必要となります。特に、事業の費用対効果や、他の事業との整合性、そして財源の確保方法などを検証する必要があります。また、これらの事業が、合併後の菊池市の発展にどのように貢献するのか、具体的な効果を示すことが求められます。そして、財政状況が厳しい中で、これらの事業をどのように優先順位をつけて進めていくのか、その判断基準が明確に示されるべきです。
6. 合併後の財政 組織改革の必要性と展望
文書の最後では、市町村合併後の菊池市における財政状況の厳しさ、そして今後の財政・組織改革の必要性が強調されています。国の三位一体改革による財政悪化が深刻な課題であり、合併を機に、財政・組織・事業の改革を進める必要性が指摘されています。この改革の具体的な方向性、そしてその実現に向けた具体的な計画やスケジュールを示すことが重要となります。また、市民の立場に立った効率的かつ有益な市政運営のあり方、そして合併によるメリットを最大限に活かすための改革案が提示される必要があります。市民への説明と理解を得ながら、透明性のある改革を進めることが不可欠です。財政改革だけでなく、組織改革や事業の見直しなども含めた、具体的な改革案と、その進捗状況の報告が求められます。
II.大牟田リサイクル発電事業への福岡県支援要請
大牟田リサイクル発電事業は、RDF搬入量の減少、サイロ爆発事故を受けての安全対策強化、原油高騰によるランニングコスト増加など、深刻な財政負担を抱えています。そのため、事業を計画段階から推進してきた福岡県に対し、参加自治体の実情を踏まえ、経営責任を果たすべく誠意ある対応を求める意見書が提出されました。
1. RDF搬入量の減少と発電所の経営悪化
大牟田リサイクル発電事業は、RDF(廃棄物固形燃料)搬入量の減少により、発電所の収入源が減少していることが大きな問題となっています。この減少は、発電所の経営を圧迫し、財政的な困難を引き起こしていることが指摘されています。具体的に、収入減少により、発電所の維持管理や運営に必要となる費用を確保することが困難になっている状況が説明されています。この問題に対処するためには、新たな収入源の確保や、コスト削減策の検討が必要不可欠であると同時に、RDF搬入量の減少の背景にある原因究明も重要となります。原因を特定し、適切な対策を講じることで、発電所の経営安定化と、ひいては地域経済への貢献を維持することができるかが問われます。現状のままでは、事業の継続が危ぶまれるため、抜本的な対策が求められます。
2. サイロ爆発事故と安全対策強化の必要性
三重県でのサイロ爆発事故を踏まえ、RDF貯蔵サイロの安全対策強化が喫緊の課題として挙げられています。事故の発生を予防し、安全性を確保するための対策には、多大な費用が必要となることが予想されます。この安全対策のための費用負担は、RDF処理委託料の大幅な改定という形で、発電事業参加自治体に大きな負担として押し付けられる可能性が高いと懸念されています。具体的な安全対策の内容、その費用規模、そして費用負担の公平性などが重要な論点となります。参加自治体の財政負担を軽減するための対策や、安全対策の費用分担方法、そして事故発生時の責任分担などを明確にする必要があります。安全対策の費用だけでなく、将来的に同様の事故を防ぐためのシステム整備にも投資が必要となるでしょう。
3. 原油高騰とランニングコスト増加の影響
原油高騰をはじめとするランニングコストの増加も、参加自治体の財政を圧迫する大きな要因となっています。原油価格の高騰やその他の燃料費の高騰は、発電所の運営コストを増加させ、事業の採算性を悪化させています。このコスト増加分をどのように吸収するか、そして参加自治体の財政への影響をいかに軽減するかが、重要な問題となります。具体的なコスト増加分、その内訳、そして自治体への財政的影響を数値で示すことが求められます。コスト削減策の検討や、燃料価格の変動リスクへの対応策、そして安定的な運営を確保するための対策が、この問題解決のために必要不可欠となります。現状のままでは、自治体の財政負担が限界に達する可能性があるため、抜本的な対策が求められています。
4. 福岡県への支援要請と今後の対応
以上のような状況を踏まえ、意見書では福岡県に対し、大牟田リサイクル発電事業を計画段階から一貫して指導・推進してきた役割と責任を認識し、筆頭株主としての経営責任を果たすよう、誠意ある対応を求めています。具体的には、RDF処理委託料の改定や、ランニングコスト増加への対応、そして安全対策強化のための費用負担について、福岡県の支援を強く求めています。福岡県の具体的な支援策、そしてその実現可能性、そして今後の事業運営における福岡県の役割などが重要な検討事項となります。福岡県がどのような対応を示すか、そしてその対応が参加自治体の財政負担軽減にどれだけ貢献するのかが、この事業の将来を左右する重要なポイントとなります。福岡県との具体的な協議内容と、その結果が公表される必要があります。
III.在宅医療廃棄物の適正処理と安全対策
在宅医療廃棄物の増加に伴い、使用済み注射針などの適正処理と収集作業における事故防止が喫緊の課題となっています。医療機関への委託が中心ですが、ごみステーションへの混入事例も報告されており、医師会等との連携による処理ルートの早期確立が求められています。菊池市においても、過去の事故報告や現在の廃棄物収集状況の報告が求められています。
1. 在宅医療廃棄物の現状と市町村の責任
在宅医療の進展に伴い、注射針、輸液セット、ガーゼなど、在宅医療廃棄物の増加が予想されています。これらの廃棄物は一般廃棄物に分類され、その処理責任は市町村にあります。厚生労働省は1998年、市町村に対し在宅医療廃棄物の適正処理を通知していますが、現状では使用済み注射針の回収は主に医療機関に委ねられており、医療機関から産業廃棄物処理施設への搬入というルートが一般的です。しかしながら、一部のごみステーションでは使用済み注射針が混入したゴミが発見されるなど、問題が発生しています。この現状を踏まえ、安全な廃棄物処理体制の構築が喫緊の課題となっています。具体的には、廃棄物の適切な分別と収集方法、そして処理施設への搬入方法の改善が求められます。また、住民への啓発活動や、医療機関との連携強化、そして安全な廃棄物処理システムの構築なども重要な対策となります。
2. 事故防止のための対策と処理ルートの確立
増加する在宅医療廃棄物に対応するため、収集業者や住民の事故防止対策として、処理ルートの早期確立が不可欠です。近隣地域では収集作業中に注射針が刺さる事故が発生しており、菊池市においても同様の事故の発生リスクは無視できません。そのため、安全な収集・運搬体制の構築、そして住民への啓発活動の強化が求められます。具体的には、使用済み注射針の回収方法の改善、安全な容器の使用、そして収集作業員の安全教育などの対策が必要です。また、医師会や医療機関との連携強化により、医療廃棄物の発生源から適切な処理までの一貫したシステムを構築する必要があります。このシステム構築には、関係機関との協力体制の構築と、適切な予算の確保が不可欠です。迅速かつ安全な処理システムの確立が、市民の安全と安心を確保するために求められます。
3. 菊池市の過去の事故報告と現在の廃棄物収集状況
菊池市において、過去に在宅医療廃棄物による事故が発生したことがあるかどうか、そして現在までの廃棄物収集状況について、詳細な情報が求められています。過去の事故例があれば、その原因と対策、そして再発防止策を明確にする必要があります。また、現在の収集状況については、収集量、収集方法、そして処理方法など、具体的なデータの提示が必要です。これらの情報を基に、菊池市における在宅医療廃棄物処理の現状を正確に把握し、今後の対策を検討していく必要があります。特に、安全対策の強化と、住民への啓発活動の充実を図るための具体的な方策が求められます。現状のシステムの課題を洗い出し、より安全で効率的なシステムを構築するための提案を行う必要があります。
IV.市施設におけるアスベスト対策
菊池市の237ヵ所の施設のうち、5施設でアスベストの使用が確認され、3施設が調査中です。平成18年度には一部施設のアスベスト除去工事が予定されていますが、調査中の施設も含めた今後の対応と、市民の健康被害・不安への対応、相談体制の整備について説明が求められています。過去には、ピーク時に年間35万トン以上のアスベストが使用されていました。
1. 市施設におけるアスベストの存在と現状
菊池市では、市内の施設におけるアスベストの有無について調査が行われています。その結果、237カ所の施設のうち、5カ所ではアスベストの使用が確認され、3カ所については現在調査中です。過去には、日本のアスベスト使用量は1974年にピークを迎え、35万トンを超えていたとされ、その危険性が指摘されています。アスベストは、ビルや住宅の急増期である1960~70年代に、建材や水道管、煙突などに広く使用され、その後、WHOによる発ガン性の指摘を受け、規制が始まりましたが、日本においては代替が困難であるという理由で、その後も使用が続けられてきました。そのため、現在多くの公共施設でアスベストが使用されている可能性があり、その除去や対策が急務となっています。現状、使用が確認された施設と調査中の施設の具体的な名称、そしてアスベストの種類や使用量などの詳細な情報が求められます。
2. アスベスト除去工事の予定と今後の対応
平成18年度当初には、本庁舎、旭志総合支所、七城総合グラウンド倉庫、特別養護老人ホーム「つまごめ荘」など複数施設でのアスベスト除去工事が予定されています。しかし、これは確認済みの施設の一部であり、調査中の施設については、調査結果を待ってから対応するとのことです。旧クリーンセンターについては、跡地利用も含めて解体について検討中とのことです。アスベスト除去工事の具体的なスケジュール、費用、そして工事方法などの詳細な計画が提示される必要があります。また、調査中の施設についても、調査方法、スケジュール、そして結果の公表時期などを明確にする必要があります。市民の健康被害や不安への対応、そして相談体制の整備について、具体的な内容が説明されるべきです。 アスベスト問題への対応は、市民の健康と安全に直結する重要な課題であるため、迅速かつ適切な対応が求められます。
3. 市民への健康被害や不安への対応と相談体制
アスベストによる市民の健康被害や不安への対応として、相談体制の整備が求められています。具体的には、アスベストに関する相談窓口の設置、相談内容の把握、そして専門家による適切な対応などが含まれます。どのような相談窓口が設置され、どのような体制で対応するのか、具体的な情報が求められます。また、過去にアスベストに関する相談がどれくらい寄せられ、どのような内容であったか、その実績データも重要な情報となります。市民の不安を解消し、適切な情報提供を行うことで、健康被害の予防と、安心安全な生活環境の確保に繋がるため、相談体制の充実と情報公開が不可欠です。市民からの問い合わせや相談への迅速な対応、そして適切な情報提供体制の確立が、信頼関係の構築に繋がります。
V.菊池市次世代育成支援行動計画と少子化対策
菊池市次世代育成支援行動計画は、少子化対策として策定されましたが、近隣市町村との比較において、専門家の関与や計画の質に差があることが指摘されています。少子化は先進国共通の課題であり、地方自治体の自立と競争が求められる中で、菊池市は、子育て支援、教育環境整備、住環境整備、仕事と家庭の両立支援など、多様な施策を推進していく必要があります。しかし、現状の体制や専門職の確保に課題が残されています。
1. 菊池市次世代育成支援行動計画の策定と背景
少子化対策として、菊池市次世代育成支援行動計画が策定されました。この計画は、国から2005年4月までに作成するよう義務付けられたものであり、市町村合併の事務と重なったことで担当部署は多大な苦労を強いられたとされています。計画の内容は、子育て支援、親子の健康確保、教育環境整備、住環境整備、仕事と家庭の両立支援など多岐に渡ります。しかし、近隣の市町村の計画と比較すると、専門家や専門職の関与の度合い、計画の質に大きな温度差があることが指摘されています。特に、熊本市の計画は専門家が多く関わっており、菊池市の計画との違いが問題視されています。この計画策定における課題や、今後の改善策が議論される必要があります。特に、専門家の知見をどのように計画に反映していくのか、そして計画の質を高めるための具体的な方策が求められます。
2. 少子化の現状と地方自治体の課題
少子化は、先進諸国に共通する現象であり、日本においても深刻な問題となっています。ある学者は、社会発展の法則から少子化は必然であると述べていますが、物質文明の維持のためには、早急な対策が必要であるとされています。少子化対策は、国だけでなく地方自治体にとっても重要な課題であり、地方の自立と分権の時代において、選ばれる街になるためには、独自の取り組みが求められます。少子化対策のための具体的な施策、その費用、そして効果などが明確に示される必要があります。また、少子化対策と、地方自治体の財政状況や行政運営との整合性も重要な検討事項となります。少子化対策の推進体制、そして必要な人員や予算の確保方法などが示されるべきです。国の政策に依存しない、地域独自の少子化対策が求められています。
3. 次世代育成支援のための施策と体制の課題
次世代育成支援のための施策は、教育環境整備、住環境整備、働き方の見直し、児童虐待防止対策、ファミリーフレンドリー企業の育成、啓発活動など多岐に渡り、その規模は国家的な大事業と言えるほどです。しかしながら、現状の体制では十分ではないとの懸念が示されています。特に、組織機構や人員配置、そして専門職の確保などが課題として挙げられています。新規事業や補完事業には高い専門性が求められるため、専門職の確保が不可欠です。市町村合併による専門職の確保という当初の目標が、実際に達成できているのかどうかが検証される必要があります。また、自治体が率先して子育てしやすい働き方を示すことが求められており、菊池市もその点について検討する必要があると指摘されています。具体的な施策の進捗状況、そして課題への対応策が求められます。
4. 人材確保と組織体制の強化 行政改革との関係
次世代育成支援行動計画を着実に推進するためには、組織体制の強化が不可欠です。しかし、国の新地方行革指針に基づく行政改革により、人員削減が求められている状況です。そのため、組織改革を含めた削減計画の策定が必要となっており、合理化と増配のバランスを考慮した慎重な検討が必要とされています。現状の人員体制、そして組織構造、そして今後の組織改革の方向性などが示される必要があります。また、新規事業の専門職の確保についても、具体的な計画と、その実現可能性が問われます。人員削減と新規事業の両立という難しい課題に対し、どのように対応していくのか、その具体的な戦略と、そのリスク管理についても説明が求められています。国の政策と、地域のニーズをどのように両立させていくのかが重要な論点となります。
VI.新庁舎建設に関する財政問題と市民意見
新庁舎建設は、合併特例債を活用した事業ですが、経常収支比率の上昇(83.3%)が懸念されています。財源確保の目途と、他の事業との優先順位、建設時期について執行部の考え方が問われています。また、市民アンケートの結果が新庁舎建設検討特別委員会で協議され、広報やホームページで公表されました。建設場所についても市民からの意見が反映されるべきです。
1. 新庁舎建設事業の財政的課題
新庁舎建設は、3年を目途に計画されていますが、その財源確保に大きな課題が見られます。財政白書によると、平成16年度の経常収支比率は83.3%であり、85%を超えると危険な運営に入るとされていることから、財政状況の悪化が懸念されます。新庁舎建設には、合併特例債を活用するものの、18億円から20億円もの一般財源が必要と試算されています。しかし、三位一体改革による交付税の減少、固定資産税の均一課税による税収減など、財政状況は年々厳しくなっており、一般財源の確保は困難です。さらに、福祉政策における扶助費の増加や、教育・文化・観光関係への財源需要も増加傾向にあるため、新庁舎建設以外の事業への影響も懸念されます。新庁舎建設事業の財源確保策、そして他の事業との優先順位付け、そして財政健全化との両立が重要な論点となります。具体的な財源確保策と、その実現可能性、そして事業計画の妥当性が問われます。
2. 新庁舎建設に関する優先順位と事業計画
新庁舎建設事業は、他の事業を削減してでも優先的に行われるのか、その優先順位と事業計画について、執行部の考え方が問われています。3年という比較的短い期間での建設を目指していますが、財政状況を考慮すると、より長期的な視点での検討が必要ではないかという意見も出ています。新庁舎建設以外の事業への影響、そして市民サービスの維持とのバランスをどのように取っていくのかが重要となります。新庁舎建設に係る具体的なスケジュール、費用、そしてその根拠となるデータなどの詳細な説明が必要とされます。また、建設場所の選定についても、市民からの意見をどのように反映していくのか、そのプロセスが明確に示される必要があります。新庁舎建設は、市民にとって重要な事業であるため、透明性のある計画と、市民への丁寧な説明が不可欠です。
3. 市民アンケートと市民意見の反映
新庁舎建設に関する市民アンケートが実施され、その結果が新庁舎建設検討特別委員会で協議された後、広報やホームページで公表されています。このアンケートは、市民の意見を反映させるための重要な手段ですが、アンケートの内容や実施方法、そして結果の分析方法などが、適切であったかどうかが問われます。アンケートの結果が、どのように新庁舎建設の計画に反映されるのか、その具体的なプロセスと、市民への説明責任を果たすための取り組みが求められます。特に、建設場所の決定において、市民意見がどの程度考慮されているのか、その透明性が問われます。アンケートの結果だけでなく、その他パブリックコメントや意見交換会など、市民参加を促進するための様々な手法を用いることが重要となります。市民の意見を尊重し、合意形成を図るための努力が、今後の建設事業を円滑に進めるために不可欠です。
4. 総合支所の活性化と自由な予算の必要性
総合支所の活性化のためには、イベントなど自由に使える予算が必要ではないかという意見も出ています。目的予算のみに重点を置くのではなく、総合支所が主体的に活動できるような、自由度のある予算措置が検討されるべきであるとされています。総合支所における具体的な活動内容、そして活性化のための具体的な施策、そしてそのために必要な予算規模などが示される必要があります。財政状況が厳しい中でも、総合支所の活性化は重要な課題であるため、そのための予算措置をどのように確保していくのか、その方策が問われています。また、支所長権限で利用できる予算の検討についても、その範囲や管理体制などを明確にする必要があります。総合支所の活性化は、地域住民にとって重要な課題であるため、そのための具体的な施策と予算措置について、丁寧な説明と、市民への理解を得るための努力が求められます。
VII.文教菊池の精神と教育行政のあり方
菊池市は、「文教菊池」の再生を標榜していますが、その精神(菊池一族の向学の家風、菊池五山の建立、孔子堂の建造など)を踏まえた教育行政のあり方が問われています。教育長は、知育・徳育・体育のバランスのとれた教育、学力向上、道徳教育、環境教育、部活動の充実などを目指すと説明していますが、新市総合計画に「文教菊池」が明確に反映されていない点を指摘されています。また、教育特区の申請については、現状では予定がないとされています。
1. 文教菊池 の精神と歴史的背景
菊池市は「文教菊池」の再生を標榜しており、その精神を理解することが教育行政を考える上で重要です。旧菊池市では古くから「文教菊池」という言葉が用いられており、熊本教育の源流と言われるほど、教育が盛んだった歴史があります。旧菊池市史によると、菊池一族の向学的な家風、菊池五山の建立による住民の教化、武芸だけでなく学芸の盛んな状況、そして21代当主・重朝公による孔子堂の建立などが、その根拠として挙げられています。特に、重朝公の向学心と菊池の文教奨励を象徴する孔子堂、そして13代当主・武重公による菊池家憲(国指定重要文化財)は、「文教菊池」の精神を理解する上で重要な歴史的資料と言えます。これらの歴史的背景を踏まえ、現代の教育行政にどのように活かしていくのか、具体的な方策が示される必要があります。単なる標語ではなく、具体的な教育理念や方針として、どのように「文教菊池」の精神を継承していくのかが問われます。
2. 教育長の 文教菊池 に対する認識と今後の教育方針
教育長は就任にあたり「文教菊池」について触れていますが、新市建設計画にはその精神が具体的に反映されていない点が問題視されています。教育長は、知育、徳育、体育のバランスのとれた教育、学力向上、道徳教育、環境教育、部活動の充実などを今後の教育方針として挙げています。具体的な方策としては、数値目標の設定による学力向上、地域資源を活用した体験学習、家庭学習の手引き作成、そして授業日数の確保などが挙げられています。しかし、これらの施策が「文教菊池」の精神とどのように繋がるのか、その具体的な説明が不足しています。教育長は「文教菊池」の精神をどのように受け止め、今後の教育行政に活かしていくのか、その具体的なビジョンと、それを実現するための具体的な計画が求められます。また、新市総合計画の基本構想に「文教菊池」の精神が反映されていない点についても、具体的な改善策が示される必要があります。
3. 教育特区制度の活用可能性と菊池市の教育課題
教育のあり方が大きく変わろうとしている現在、構造改革特区制度を活用する可能性が議論されています。旧菊池市では、韓国人に対するビザ免除の申請を行い、全国的なビザ免除の先駆けとなりました。この積極的な姿勢を踏まえ、教育分野における特区制度の活用について検討が求められています。しかし、教育長は、現状では特区申請の予定はないとしています。その理由として、合併による学校数の増加、そして十分な実態把握や分析ができていない点を挙げています。菊池市では、学力向上を最重要課題と捉えており、特区制度を活用せずとも、現行法の範囲内で対応できると考えているようです。しかし、教育特区制度のメリットやデメリットを十分に検討し、菊池市独自の特色を活かした教育のあり方を模索することが重要です。中高一貫教育の研究なども行われている中で、菊池市の教育の現状と課題、そしてその解決策について、より具体的な議論が必要です。
4. 文教菊池 の精神を踏まえたまちづくりへの展望
新市総合計画の基本構想には「文教菊池」という言葉は含まれていませんが、菊池の伝統・文化・歴史を継承すると明記されています。この点を踏まえ、「文教菊池」の復興の思いをどのように具体化していくのかが問われています。教育長は、健康で心身ともに健全で文化教養の高い市民育成を目指すと述べていますが、「文教菊池」の精神を具体的にどのように教育に反映していくのか、具体的な方策が必要です。学校教育における知育、徳育、体育の充実、地域資源を活用した教育、家庭教育の充実、そして教員の指導力向上など具体的な方策が示されていますが、「文教菊池」の精神とどのように整合性をとっていくのかが重要です。単なる理念の表明ではなく、具体的な施策と、その実施計画、そして評価指標を示すことが必要です。歴史と伝統を活かした、菊池市独自の教育モデルの構築が期待されます。
VIII.学校給食の民間委託に関する検討
菊池市の学校給食は、給食センター方式と自校方式が併存しており、施設の老朽化や職員配置の問題が課題です。民間委託については、保護者等の理解を得ながら、住民サービスの低下を招くことなく総合的に検討していく必要があるとされています。旧七城町と旧泗水町には給食センターがあり、旧菊池市と旧旭志村は自校方式です。職員数は正規72名、臨時・嘱託47名です。
1. 学校給食の現状と課題 センター方式と自校方式の併存
新市における学校給食の運営は、旧市町村の状況を引き継いでおり、センター方式と自校方式が併存しています。旧七城町と旧泗水町は給食センター方式、旧菊池市と旧旭志村は自校方式を採用していました。このため、給食センター2カ所と13の小中学校で、正規職員25名、臨時・嘱託職員47名、計72名の職員が調理業務に従事しています。しかし、旧菊池市では学校給食施設の老朽化が進んでいるという課題があり、平成15年度から民間委託について検討が行われてきました。新市においては、センター方式と自校方式の併存、施設の老朽化、職員配置、学校規模適正化など、様々な課題を考慮した上で、学校給食のあり方について総合的な検討が必要となります。現状の給食提供体制、そしてその課題、そして今後の改善策について詳細な説明が必要です。特に、老朽化した施設の改修や建て替え、そして職員配置の最適化などが重要な検討事項となります。
2. 学校給食の民間委託に関する検討の必要性と方向性
学校給食の民間委託は、行財政改革の一環として検討されていますが、住民サービスの低下を招くことなく、安心・安全な給食の確保を前提に進めるべきであるとされています。民間委託を行う際のメリット・デメリット、そしてその影響について、保護者を含む住民への説明と理解を得ることが重要です。具体的には、委託によるコスト削減効果、給食の質の維持、そして食の安全確保のための体制などについて、詳細な検討が必要です。また、民間委託を行う場合の委託先の選定基準、そして契約内容、そして監督体制なども重要な検討事項となります。行政改革大綱及びその実施計画への掲載も視野に入れつつ、住民サービスの維持を最優先事項として、慎重かつ丁寧な検討を進めることが求められます。 住民の意見を十分に聞き入れ、合意形成を図りながら、最適な給食システムを構築することが重要となります。
3. 行政改革と学校給食 住民サービスと安全確保の両立
学校給食は、子どもたちの健全な育成に不可欠な要素であり、行政改革においても住民サービスの低下を招くことなく、安心・安全な給食の提供を確保する必要があるとされています。そのため、民間委託の検討にあたっては、コスト削減とサービス維持、安全確保のバランスをどのように取るのかが重要な課題となります。現状の給食体制における課題、そして民間委託によるリスクとメリット、そして住民への影響などについて、客観的なデータに基づいた分析が必要です。行政改革大綱及びその実施計画への掲載は、その検討過程の一環として位置付けられていますが、最終的な決定に際しては、住民への十分な説明と合意形成が不可欠となります。子どもたちの健康と安全を最優先に考え、適切な判断が求められます。安全で質の高い給食を確保するための具体的な方策、そしてその財源確保についても明確に示される必要があります。
IX.菊池温泉の泉源枯渇対策と入湯税の活用
菊池温泉の泉源枯渇のリスクに対し、入湯税の一部を基金化し、泉源保護や温泉街活性化などに活用する案が提案されています。他の自治体の事例(八代市、天草町)も参考に、早急な対策と基金の運用方針(使途の明確化、審議会設置など)の策定が求められています。四季の里旭志と温泉ドームは第三セクター運営です。
1. 菊池温泉の現状と泉源枯渇リスク
菊池温泉は、昭和29年の湧出以来約50年間、観光産業として発展を続け、菊池市の産業構造の一翼を担ってきました。しかし、近年、温泉の泉源枯渇が懸念されています。他の自治体では、泉源の枯渇により温泉街が衰退したり、給湯システムの改修に多大な費用が必要となる事例も報告されています。例えば、天草町では、かつて28本あった泉源のうち25本が枯渇し、給湯システムの改修に約1億円の財政支出が行われました。菊池市においても、四季の里旭志や温泉ドームなどの第三セクター運営の温泉施設が泉源枯渇に直面した場合、運営の維持は困難となり、莫大な緊急財政支出が必要となる可能性があります。そのため、早急な対策が必要不可欠です。現状の泉源の状況、そして枯渇リスクの程度、そして将来的な予測などが示される必要があります。また、類似事例の分析や、専門家の意見なども参考にすべきです。
2. 入湯税の現状と活用方法の検討 基金化による対策
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、そして観光振興に充てることを目的としています。しかし、現状では、旅館やホテルなどの宿泊施設にしか課税されておらず、その活用範囲が限定されています。そのため、入湯税の一部を毎年基金化し、泉源の保護や温泉街の活性化などに活用する案が提案されています。この基金の運用方法については、使途や用途を明確化し、審議会を設けることなどが提案されています。また、入湯税の課税対象を拡大し、銭湯や公衆浴場などからも協力金を募ることで、基金の財源を確保する方法も検討されています。この基金の具体的な運用方法、そしてその財源規模、そして運用における透明性などが重要となります。また、法令上の問題点や、他の財源との整合性なども考慮する必要があります。持続可能な温泉街の維持発展のために、効果的で効率的な基金運用方法の検討が求められます。
3. 危機管理対策と今後の対策方針
泉源枯渇は、菊池温泉の存続に関わる重大な危機であり、早急な対策が必要不可欠です。そのため、提案されている基金案以外にも、様々な対策が検討される必要があります。特に、四季の里旭志や温泉ドームなどの第三セクター運営の温泉施設は、泉源枯渇による影響を受けやすいことから、それらの施設に対する危機管理対策が重要です。具体的な対策としては、泉源の保全のための設備投資、そして温泉街周辺の活性化のための施策などが考えられます。これらの対策には、多額の費用が必要となる可能性があるため、財源の確保方法や、費用対効果の検証なども重要となります。また、住民への説明と理解を得ながら、将来にわたって菊池温泉を守り、発展させていくための長期的な計画の策定が必要となります。そして、その計画に基づいた具体的な対策と、その進捗状況の報告が求められます。
X.九州産廃問題と最終処分場の操業期間短縮
九州産廃の産業廃棄物処理施設をめぐっては、市民による反対運動が継続しており、溶融キルンの操業差し止め裁判も係争中です。市・県・九州産廃・区長会による協議が行われており、最終処分場の操業期間短縮と増設規模の縮小を目指しています。最終処分場の埋立期間は平成30年まで(環境保全協定書)。
1. 九州産廃問題の現状と市民の反対運動
昭和56年から菊池市の柏区で産業廃棄物の埋立処分業を行っている九州産廃は、度重なる増設拡張や溶融キルン焼却施設の建設に対し、市民から大規模な反対運動が起こり、現在も溶融キルンの操業差し止めを求める裁判が係争中です。近年は、埋立処分場や焼却施設に加え、破砕・選別処理施設、RPF処理施設、建設廃材リサイクル施設、堆肥化処理施設、メタン発酵処理施設などの中間処理施設も建設されています。平成10年には市と九州産廃の間で環境保全協定書が締結され、環境保全が謳われていますが、市民は最終処分場の操業期間短縮を求めています。 この反対運動の背景、そしてその規模、そして訴訟の現状などを詳しく説明する必要があります。また、環境保全協定書の内容と、その遵守状況についても検証が必要です。長年にわたる問題の経緯と、その過程で生じた様々な問題点を明らかにすることが重要です。
2. 最終処分場操業期間短縮に向けた協議と課題
最終処分場の操業期間短縮に向けて、市、県、九州産廃、そして区長会代表者による四者協議が行われています。協議事項は、最終処分場の操業期間短縮、増設規模の縮小、そして補償問題、そして農振除外の手続きなどが中心となっています。最終処分場の増設計画は約120万㎥でしたが、その縮小規模や、操業期間の短縮時期、そしてそのための具体的な方策などが協議されています。また、操業期間短縮に伴う補償問題についても、市と県が負担することになっていますが、その具体的な負担割合や、補償方法などが示される必要があります。さらに、農用地の転用に関わる農振除外の申請手続きについても、手続きの進捗状況や、その課題などが説明されるべきです。協議の進捗状況、そしてその課題、そして今後の展望などが明確に示される必要があります。
3. 協議内容の詳細と中間処理施設の扱い
四者協議では、以下の4点が中心となっています。1. 最終処分場の操業期間短縮と、新たな増設・拡張計画に関する協議、2. 既設処分場の嵩上げ規模の制限と、短縮期間までの処分場確保のための方法(リニューアル改修または一部拡張)に関する協議、3. 操業期間短縮に伴う補償の市と県による負担、4. 農業振興地域整備計画における農用地の農振除外手続き。重要なのは、この協議に溶融キルン焼却施設などの中間処理施設が含まれていない点です。中間処理施設の現状と、今後の扱いについても明確に説明されるべきです。 協議の進捗状況、そして合意形成に向けた取り組み、そして今後の展望などが詳細に説明される必要があります。市民の意見をどのように反映していくのか、そのプロセスも重要です。また、最終処分場の閉鎖後の跡地利用計画についても、具体的な計画が示されることが望まれます。
XI.行財政改革と職員給与の不均衡是正
菊池市は、合併による行財政改革を進めていますが、経済不況や少子高齢化、国の財政政策などの影響から、組織のスリム化や民間委託などの必要性が指摘されています。また、合併前の市町村間の職員給与の不均衡是正についても、早急な対応が求められています。具体的には、継続採用の職員の給与調整基準の作成と、その内容の明確化です。
1. 合併後の行財政改革の必要性と現状
市町村合併から9ヶ月が経過し、合併のうたい文句であった「負担は低い方へ、サービスは高い方へ」という目標達成への不安が指摘されています。合併後も、経済不況の影響、民間企業のリストラや給与カット、そして地方における少子高齢化の進行など、厳しい状況が続いています。さらに、国の政策として交付税の削減、三位一体改革、税源移譲などが進められており、地方自治体の事務・事業は多様化・複雑化の一途を辿っています。このような状況下において、政府の改革に合わせ、地方自治体もいち早く行財政改革に取り組む必要があるとされています。具体的には、組織のスリム化、民間委託の拡大、そしてサービス向上などが検討課題として挙げられています。現状の組織体制、そして財政状況、そして今後の改革の方向性などが明確に示される必要があります。特に、財政負担の軽減と、市民サービスの向上を両立させるための具体的な方策が求められます。
2. 職員給与の不均衡是正と調整基準
合併に伴い、旧市町村間の給与体系の違いによる職員給与の不均衡が問題となっています。旧七城町では、合併前の定例会でこの問題が取り上げられ、職員の士気と住民サービス向上のため、給与体系の均衡化が求められていました。合併協議会では、職員の給与を現行保証し、適正化を図ると決定されています。新市においては、一般職の給与に関する条例と規則が制定されていますが、継続採用の職員間で、旧市町村間の給与制度の違いによる不均衡がどのように調整されたのか、そしてその調整基準がどのようなものなのかが問われています。具体的な調整方法、そしてその基準、そしてその妥当性などが説明される必要があります。また、調整プロセスにおける透明性と、職員への説明責任についても配慮する必要があります。公平で公正な給与体系の確立が、職員のモチベーション向上と、ひいては住民サービスの向上に繋がるため、その実現に向けた具体的な取り組みが求められます。
XII.宿泊通学と心の相談体制の充実
菊池市では、不登校児童生徒への支援として「きくち教室」と「こうし教室」を開設し、スクールカウンセラーの配置、子どもと親の相談員の配置など、充実した心の相談体制を構築しています。しかしながら、宿泊通学制度についても、施設の活用方法や送迎の問題など、更なる検討が求められています。
1. 宿泊通学制度の必要性と検討状況
少子化や人口減少が進む中、特に通学距離が長い地域において、子どもたちが安全に通学できる環境を整備することが重要です。隣接する山鹿市では、平成18年度からモデル事業として宿泊通学制度を実施する計画があるとのことです。菊池市においても、教育長はモデル的な取り組みも含め検討する姿勢を示していますが、施設の確保、既存施設の活用、通学距離や送迎の問題など、多くの課題が指摘されています。 宿泊通学制度導入の可能性、そしてそのための具体的な方策、そして必要な費用や人員などが示される必要があります。特に、既存の施設(七城町の研修交流施設、各地区の公民館や福祉センターなど)の有効活用について、その可能性や課題が検討されるべきです。また、保護者や地域住民の協力を得ながら、制度の早期実現を目指すための具体的な方策が求められます。通学方法の多様化による安全対策の充実が、子どもたちの未来を守るために重要です。
2. 心の相談体制の現状と課題 不登校対策の充実
児童生徒の心の問題への対応として、菊池市では、スクールカウンセラーの配置、子どもと親の相談員の配置(隈府小学校と旭志小学校)、そして不登校児童生徒のための「きくち教室」と「こうし教室」の開設など、様々な取り組みが行われています。これらの取り組みは、児童生徒だけでなく、保護者や教師の悩みにも対応できる体制を目指しており、特に近年増加している低学年の不登校にも対応できるよう、小学校へのサポート体制も強化されています。しかし、現状の体制について、更なる充実が必要であると指摘されています。特に、相談体制の充実、そして不登校児童生徒への支援体制の強化が求められています。現状の相談件数、そして相談内容、そして支援体制の課題などが明確に示される必要があります。また、より効果的な支援体制を構築するための具体的な方策が、今後の検討課題として挙げられます。心の健康を守るための継続的な取り組みと、そのための体制強化が、子どもたちの健やかな成長にとって重要です。
XIII.学校防犯カメラ設置に関する検討
近年発生した児童殺害事件を受け、学校における安全対策強化、特に防犯カメラ設置の必要性について議論されています。地域住民による防犯活動も重要ですが、学校現場の安全確保のためには、より強固な監視体制の構築が求められています。
1. 広島 栃木での児童殺害事件と学校安全確保の必要性
広島や栃木での小学校女児殺害事件を受け、学校における安全対策の強化が喫緊の課題となっています。これらの痛ましい事件を受け、学校を取り巻く安全環境は年々厳しくなっており、同様の事件が菊池市で起こらないという保証はないと認識されています。そのため、学校現場における犯罪防止と、校内の監視体制強化が求められています。地域住民による防犯活動も重要ですが、現実的に、学校現場の安全確保のためには、より強固な対策が必要であるとされています。具体的には、学校周辺の防犯対策の強化、そして校内への監視カメラ設置の是非が議論の焦点となっています。 広島・栃木での事件の詳細、そしてそれらの事件から得られる教訓、そして菊池市における現状の安全対策などが示される必要があります。また、防犯カメラ設置のメリット・デメリット、そして設置に係る費用や運用方法なども検討課題となります。
2. 学校防犯カメラ設置の是非と費用対効果
学校現場における犯罪防止と校内監視体制強化のため、防犯カメラの設置が検討されています。しかし、設置には多額の費用が必要となるため、その費用対効果や、他の安全対策とのバランスが議論の焦点となるでしょう。地域住民による防犯パトロールなども行われており、それらの活動との連携なども考慮する必要があります。防犯カメラ設置による効果、そしてその費用、そして他の安全対策とのバランスなどが詳細に示される必要があります。また、カメラの設置場所や台数、そしてプライバシー保護の観点からの配慮なども考慮されるべきです。 防犯カメラ設置の是非に関する具体的な検討内容、そしてその根拠となるデータ、そして費用対効果などが提示されることが求められます。安全対策の充実と、財政状況の制約とのバランスが、重要な検討事項となります。
XIV.老人福祉センター建設と特別養護老人ホームの改築
老人福祉センター建設と特別養護老人ホームつまごめ荘の改築工事について、事業計画の妥当性と財政負担(特に、借入金の償還計画)が問われています。建設場所の選定についても、市民意見の反映が求められています。つまごめ荘改築工事は約20億円。
1. 老人福祉センター建設の場所設定とチェック体制
老人福祉センター建設の場所設定において、「負担は低く、サービスは高く」という項目が適切にチェックされたかどうかが問われています。この場所設定は9月議会で既に決定済みであり、その過程で市民の意見が十分に反映されたのか、そして計画の妥当性について疑問が呈されています。 具体的に、建設予定地の選定プロセス、そしてその選定基準、そして市民への説明責任の履行状況などが詳細に説明される必要があります。また、建設地選定において、既存の施設や、周辺環境との整合性が考慮されたかどうかも重要な検討事項です。建設地選定における透明性と、市民参加の機会の有無が、計画の妥当性を判断する上で重要な要素となります。
2. 特別養護老人ホーム つまごめ荘 改築工事の妥当性
特別養護老人ホーム「つまごめ荘」の改築工事についても、計画の妥当性が問われています。特に、地方債(13億1900万円)の償還計画について、一般会計からの繰り入れが問題視されています。これまでの広域行政では1700万円の償還が行われていましたが、今回の約20億円の事業では、一般会計からの繰り入れが疑いなく行われる計画となっている点に懸念が示されています。 改築工事の必要性、そしてその費用、そして償還計画の詳細などが明確に説明される必要があります。また、償還計画における財源の確保方法、そしてその妥当性などが検証されるべきです。 「負担は低く、サービスは高く」という合併協議会での合意が、この事業においても適切に反映されているかどうかが、重要な検討事項となります。
XV.敬老会事業補助金に関する説明
菊池市の敬老会事業補助金は、合併協議会で旧菊池市の例を参考に決定されました。補助対象は、満70歳以上の住民を対象とする自治会主催の敬老会であり、特別養護老人ホーム入所者は対象外です。補助額は、一人あたり1,200円。
1. 敬老会事業補助金の目的と実施状況
菊池市では、各区への敬老会費用の一部を助成する事業を行っています。この事業は、合併前の旧菊池市、旧旭志村、旧泗水町でそれぞれ実施されていましたが、運用面、対象年齢、補助額などに違いがありました。合併協議会では、平成17年度から旧菊池市の例にならって実施することが決定されました。旧菊池市では、満70歳以上の人数に1人あたり1200円を単位として補助が行われていました。新市においても、合併協議の調整方針に基づき、同様の要綱で事業が実施されています。この事業の目的は、敬老意識の高揚と老人福祉の増進です。行政区や市長が適当と認める自治会が主催する敬老会事業に、その経費の一部を補助するものです。補助金の対象となる敬老会事業の範囲、そして補助額の算定方法、そしてその根拠などが明確に示される必要があります。また、事業の実施状況や、その効果についても検証されるべきです。
2. 特別養護老人ホーム入所者への補助対象外について
敬老会事業補助金の対象から、特別養護老人ホームなどの入所者は除外されています。その理由について、合併協議に基づき旧菊池市の例にならったためであり、旧菊池市、旧旭志村、旧泗水町においても、施設入所者は対象外であったと説明されています。 しかし、特別養護老人ホーム入所者に対する敬老のお祝いについても、同様の目的を持つ事業であることから、補助対象に含めるべきではないかという意見も存在します。 特別養護老人ホーム入所者を除外する理由、そしてその妥当性、そして他の自治体の事例などが示される必要があります。また、補助金の対象範囲を拡大することによる影響、そして財政的な負担についても検討されるべきです。 高齢者福祉の増進という観点から、より公平かつ効果的な補助金制度のあり方が問われています。
XVI.PFI事業の活用可能性
効率的な行財政運営のため、PFI(Private Finance Initiative)事業の活用可能性が検討されています。しかし、事業リスクへの十分な対応が必要であり、慎重な検討が求められています。
1. 敬老会事業補助金の目的と対象
菊池市では、高齢者を敬う意識の高揚と老人福祉の増進を目的として、地区敬老会事業の一部を補助する事業を行っています。この事業は、合併前の旧菊池市、旧旭志村、旧泗水町でそれぞれ実施されており、合併協議会において、平成17年度から旧菊池市の例にならって実施することが決定されました。旧菊池市では、満70歳以上の住民1人あたり1200円を基準に補助が行われていました。新市においても、この方針に基づき、要綱が整備され、行政区や市長が適当と認める自治会が主催する敬老会事業が補助対象となります。補助金の交付対象となる敬老会事業の具体的な要件、そして補助金の算出方法、そしてその根拠などが明確に示される必要があります。また、この補助金制度の目的、そしてその効果、そして今後の改善点なども検討されるべきです。
2. 特別養護老人ホーム入所者への補助対象外理由
特別養護老人ホーム等の入所者は、敬老会事業補助金の対象外となっています。これは、合併協議において、旧菊池市、旧旭志村、旧泗水町いずれにおいても、施設入所者は対象外であったため、旧菊池市の例にならって決定されたものです。しかし、特別養護老人ホーム入所者についても敬老の意識高揚や老人福祉の増進という目的は同様であることから、補助対象に含めるべきではないかという疑問が呈されています。 特別養護老人ホーム入所者を対象外とする理由、そしてその妥当性について、より詳細な説明が必要です。また、補助金の対象範囲を拡大した場合の影響や、財政的な負担についても検討が必要です。高齢者福祉の観点から、より包括的で公平な補助金制度のあり方が議論されるべきです。
3. 補助金制度の改善と対象範囲の拡大可能性
現在の補助金制度は、合併前の旧市町村の状況を踏まえて決定されたものであり、その運用面や対象年齢、補助額などに差異があったことが指摘されています。そのため、敬老のお祝いを目的とした事業であれば、対象範囲を拡大する可能性も検討されるべきです。 補助金制度の改善点、そして対象範囲の拡大可能性、そしてその財源確保方法などが検討される必要があります。 高齢者福祉の向上という観点から、より多くの高齢者に配慮した、効果的な補助金制度のあり方が求められます。また、地域の実情に合わせた柔軟な運用についても検討すべきです。
XVII.行政改革と住民サービスの向上
職員の電話応対における氏名表示、総合案内窓口の業務効率化など、住民サービス向上のための具体的な方策が提案されています。礼儀礼節に関する研修やワンストップサービスの推進も重要な課題です。
1. 行政改革の必要性と現状 合併後の課題
市町村合併後、行財政改革の必要性が改めて強調されています。合併によって期待される「負担は低い方へ、サービスは高い方へ」という目標達成に向けて、現状の行政運営を精査し、効率化を図る必要があるとされています。しかし、経済不況や少子高齢化、そして国の三位一体改革による交付税削減など、厳しい財政状況が課題となっています。民間企業ではリストラや給与カットが行われているように、地方自治体も厳しい財政状況に対応するため、組織のスリム化や民営化などを含む抜本的な改革が必要とされています。 現状の組織体制、そして財政状況、そして今後の改革の方向性、そしてそのための具体的な計画などが示される必要があります。特に、財政負担の軽減と市民サービスの向上を両立させるための具体的な方策が求められています。 効率的で効果的な行政運営のための具体的な方策、そしてそのための体制整備が重要となります。
2. 住民サービスの向上 具体的な取り組みと改善点
住民サービスの向上に向けた具体的な取り組みとして、職員の電話応対における氏名表示、そして総合案内窓口の業務効率化などが提案されています。 電話応対では、職員が氏名を名乗ることで、より丁寧で親しみやすい対応ができ、住民からの信頼感向上に繋がるとされています。総合案内窓口については、庁内案内のみならず、他の窓口業務との兼務なども検討することで、効率的な運営が可能となるとされています。 しかし、現状の総合案内窓口の対応に課題があることが指摘されており、その改善策として、ワンストップサービスの推進や、職員の礼儀礼節に関する研修などが挙げられています。 住民サービスの向上のための具体的な方策、そしてその実施計画、そしてその効果などが示される必要があります。 市民目線に立った、より質の高い住民サービスの提供が求められます。
3. 業務改革と職員の意識改革
業務改革の一環として、職員の意識改革も重要視されています。具体的には、礼儀礼節に関する研修の実施や、ISO9001認証取得に向けた取り組みが挙げられています。旧菊池市では既にISO14001認証を取得しており、これを全公共機関に導入する努力が行われています。さらに、サービス面の評価・側面評価が可能なISO9001認証の取得を通じて、住民サービスの質の向上を目指しています。 受付窓口の対応についても、ワンストップサービスの推進や職員研修を通じて改善していく方針が示されています。しかし、現状の受付対応には改善の余地があると指摘されており、市民からの評価を高めるための具体的な取り組みが求められています。 職員の意識改革、そして業務改善のための具体的な施策、そしてその効果測定などが示される必要があります。 市民からの信頼を得られる、質の高い行政サービスの提供のために、継続的な努力が求められます。
XVIII.食育基本法に基づく食育の推進
食育基本法の制定を受け、学校教育における食育の推進が課題となっています。朝食を食べない児童生徒の割合(全国20%、菊池市15%)、孤食の増加、偏食や肥満傾向の増加など、現状が示されています。学校給食指導、家庭科、総合的な学習、農業体験活動など、様々な取り組みが行われていますが、より総合的な視点からの推進が求められています。養生園なども参考に。
1. 食育基本法の制定と食習慣の乱れ
平成17年6月に食育基本法が制定されました。これは、国民の食生活の乱れが社会問題化していることを受け、健全な食生活の実践を促すことを目的としています。具体的には、朝食を抜く子どもの増加、偏食や肥満傾向の増加、そして体力低下などが問題視されています。 食育基本法は、国民に望ましい食生活の実現を求めるだけでなく、国や自治体における食育施策の推進を義務付けています。また、生産者や食品業者には安全な食品の提供、教育関係者には学校給食を通じた食育の啓発が求められています。 食育基本法の主要な内容、そして食習慣の乱れの現状、そしてその背景などが説明される必要があります。 国民の健康増進と、食文化の継承という観点から、食育の重要性が改めて強調されています。
2. 学校教育における食育の現状と課題
食育基本法の目的を達成するためには、学校教育の場での取り組みが重要です。現状では、学校給食における指導が中心となっていますが、家庭科での栄養教育、総合的な学習の時間における農業体験、そして道徳教育における食への感謝の教育なども行われています。 しかし、これらの取り組みは個別的なものであり、食育という視点から総合的に捉えられていない点が課題として挙げられています。朝食を食べない児童生徒の割合は全国で20%、菊池市では15%、孤食の割合は全国で31%に上るとされています。これらの現状を踏まえ、より効果的な食育を推進するための具体的な方策が検討される必要があります。 学校における食育の現状、そしてその課題、そして今後の改善策などが詳細に説明されるべきです。特に、学校、家庭、地域が一体となって取り組むための具体的な方策が求められます。
3. 食育推進のための具体的な取り組みと今後の展望
菊池市では、農林振興課が中心となり、市内小学校を対象とした農業関係施設研修が計画されています。JAの集荷場や農業高校、農園などを視察し、食育への理解を深めることを目的としています。旧市町村においても、地域食材を活用した料理の普及活動や、農業体験活動などが行われてきました。 しかし、食育は学校教育の場だけでなく、家庭や地域社会全体で取り組む必要があるとされています。また、生活習慣病の増加や、食文化の衰退なども問題視されています。 食育基本法の趣旨を踏まえ、菊池市独自の推進計画を策定し、生産者への配慮も欠かすことなく、具体的な施策を推進していく必要があります。 今後の食育推進に向けた具体的な計画、そしてその実施体制、そして評価方法などが示されるべきです。 特に、地産地消の推進や、伝統的な食文化の継承なども重要な課題となります。
XIX.農畜産物の自給率向上と生産者への配慮
農畜産物の自給率向上と食育の推進は不可分な課題ですが、減反政策や輸入農畜産物との競合など、生産者への配慮が不足しているとの指摘があります。堆肥の地域外搬出問題(52%)も深刻な課題です。耕畜連携による堆肥処理の可能性を検討するプロジェクトチームの設置が求められています。
1. 食育基本法の制定と社会問題としての食習慣の乱れ
平成17年6月10日、食育基本法が成立しました。これは、国民の食生活の乱れ、特に朝食を抜く子どもの増加、偏食や肥満傾向、体力低下といった問題に対応するためです。国民の食の安全への関心の高まり、そして食習慣の乱れが社会問題化している現状を踏まえ、食育基本法は、健全な食生活を実践できる人間を育成することを目的としています。 法制定に伴い、内閣府に食育推進会議が設置され、国や自治体、生産者、食品業者、教育関係者などに食育に関する施策が義務付けられました。具体的には、学校給食を通じた食育の啓発、安全な食品の提供、農山漁村の活性化などが求められています。 食育基本法の成立背景、そして具体的な内容、そして現状における食習慣の課題などが説明される必要があります。 国民全体の健康増進と、食文化の継承を目的とする食育の重要性が、改めて強調されています。
2. 食育の現状と課題 学校教育を中心とした取り組み
食育基本法の成果を最も上げられるのは学校教育の場だと考えられています。菊池市では、学校給食指導を中心に、家庭科での栄養教育、総合的な学習の時間での農業体験、そして道徳教育における食への感謝の指導など、多様な取り組みが行われています。しかし、これらの取り組みはまだ個別的なものであり、食育をトータルな視点で捉えた、総合的な取り組みには至っていないのが現状です。朝食をきちんと摂る子どもの学力が高い、偏食や肥満傾向の子どもの体力低下が著しいといった指摘があり、子どもの食生活と健康、そして学力との関連性が示唆されています。 学校教育における食育の現状、そしてその課題、そして今後の課題などが詳細に説明される必要があります。 学校、家庭、そして地域社会が一体となって取り組むための具体的な方策が求められます。
3. 地域連携と伝統的食文化の継承 今後の食育推進の方向性
食育の推進にあたっては、学校・家庭・地域が一体となって取り組む必要があるとされています。 菊池市では、「菊池うまかもん衆」による地域食材を使った料理の普及活動や、ファームステイ、農業体験活動など、地域と連携した取り組みが行われています。 しかし、食育基本法の制定に対し、本当に法まで制定する必要があるのかという疑問も存在しています。 また、生活習慣病の増加、朝食をとらない子どもの増加、そして外食の増加といった問題が指摘されています。 菊池市では、農林振興課が中心となり、小学校を対象とした農業関係施設研修を計画しています。 さらに、地産地消の推進や、伝統的な食文化の継承も重要視されています。 今後の食育推進のための具体的な計画、そしてその実施体制、そして地域との連携方法などが示される必要があります。 特に、生産者への配慮も重要な要素となります。
XX.七城町における継続事業 土木関係
旧七城町の継続事業、特にウォーキングトレイル事業における人道橋建設の必要性について疑問が呈されています。既に完成している高島橋の存在も考慮し、計画の妥当性が問われています。県道139号線旭志鹿本線のバイパス改良工事も継続中です。
1. 県道139号線 旭志鹿本線 の現状と課題
県道139号線(旭志鹿本線)は、西郷橋から荒牧地区を経て国道325号線に繋がる主要道路ですが、幅員が狭く、大型車両の通行による離合困難や、交通事故の多発といった問題を抱えています。特に、通学路として利用されていることから、子どもたちの安全確保が大きな課題となっています。平成11年の熊本国体開催に合わせて、七城町では女子サッカーの大会会場が設けられ、大型車両の通行による支障が問題となり、県によってバイパス改良工事が着手されました。用地買収はほぼ完了していますが、一部未買収地が残っており、今後の用地交渉の継続が必要となっています。 道路の現状、そして交通事故の発生状況、そして通学路としての安全性などが詳しく説明される必要があります。また、バイパス改良工事の進捗状況、そして残された課題、そして今後の対応策などが明確に示されるべきです。特に、未買収地の状況と、今後の用地交渉の計画などが重要となります。
2. ウォーキングトレイル事業における人道橋建設の必要性
七城町では、ウォーキングトレイル事業が継続事業として引き継がれていますが、その事業計画、特に人道橋建設の必要性について疑問が呈されています。 この計画について、地元住民からの要望や陳情は一切ないにもかかわらず、事業が進められている点が問題視されています。 この人道橋のすぐ上流には平成13年に完成した高島橋があり、立派な歩道も完備されているため、人道橋の必要性自体が疑問視されています。 この計画の妥当性、そしてその必要性、そして住民への説明責任などが問われています。 計画の経緯、そしてその決定プロセス、そして費用対効果などが詳細に説明される必要があります。 地元住民の意見を十分に反映した、より効果的で効率的な事業計画の策定が求められています。
.堆肥の利用状況と流通促進
菊池市における堆肥の利用状況に関するアンケート結果が示されています。堆肥を使用していない農家の多くは、散布作業の困難さを理由に挙げており、散布組織の育成と散布機械の共同利用などが課題となっています。水稲が堆肥利用の約70%を占めています。
1. 堆肥の利用状況に関するアンケート結果
菊池市では、堆肥の利用状況に関するアンケート調査が行われました。その結果、作物別では水稲が約70%、野菜類が約15%を占めています。堆肥を使用している農家は全体の約8割に上り、その入手先は市内の畜産農家(97%)が圧倒的です。堆肥の種類別では、酪農が39%、肉用牛が33%、養豚が6%となっています。10aあたりの使用量は、2トン以上が44%、1~1.5トンが22%、0.5トン以下が9%、1.5~2トンが6%です。堆肥の価格は、稲わら交換と散布作業込みで無料が19%、受け取りのみ無料が7%、1000円~2000円が5%、5000円以上が4%となっており、39%が無回答、17%が無記入でした。散布方法は手作業が29%、機械使用が28%、畜産農家への委託が20%で、21%が無回答でした。堆肥を使用していない理由としては、「堆肥散布が大変」が41%と最も多く、次いで「必要がない」が20%でした。堆肥利用促進のためには、散布作業の容易化が重要な課題であることがわかります。
2. 堆肥流通促進のための課題と対策
アンケート結果からは、堆肥を使用していない農家の多くが、堆肥の散布作業の困難さを理由に挙げていることが明らかになりました。そのため、堆肥流通促進を図るためには、散布作業の容易化が急務であり、散布組織の育成が重要な課題となっています。 具体的には、散布モデル地区を選定し、必要なハード事業についても検討する必要があるとされています。 また、堆肥の価格についても、稲わらとの交換や無料提供など、様々な形態が見られますが、より多くの農家が利用しやすい価格体系の検討も必要です。 堆肥の散布方法の改善、そして散布機械の共同利用、そして散布組織の構築などが、堆肥流通促進のための具体的な対策として挙げられます。 これらの対策の実施には、関係機関との連携や、適切な予算の確保が不可欠となります。
3. 畜産糞尿処理問題と耕畜連携の可能性
菊池市では、生産された堆肥の約52%が地域外に搬出されているという現状があります。これは、堆肥の処理能力が不足していることを示しています。 市長は、将来的な耕畜連携による堆肥処理の可能性に言及し、環境問題や農業・畜産的見地からの検討が必要であるとしています。 旧菊池市では、ドイツへの職員派遣によるバイオテクノロジーを活用した糞尿処理の視察も行われています。 この問題に対応するためには、環境問題、農業、畜産という複数の観点からの総合的な検討、そしてプロジェクトチームによる研究が必要とされています。 また、国の事業を活用するための体制づくりも重要です。 耕畜連携による持続可能な堆肥処理システムの構築に向けた取り組み、そしてそのための具体的な計画と、関係機関との連携などが求められます。
