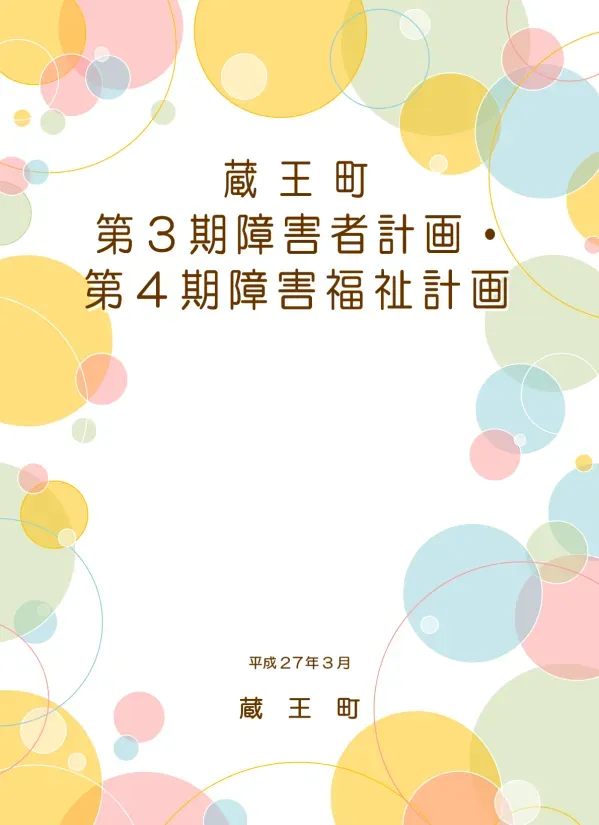
蔵王町障害者計画: 包摂的地域社会の実現
文書情報
| 著者 | 蔵王町 |
| 場所 | 蔵王町 |
| 文書タイプ | 計画書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.21 MB |
概要
I.計画の基本理念と目的 蔵王町第3期障害者計画 第4期障害福祉計画
本計画は、『障がいのある人が自分らしく生活できる蔵王町』を基本理念とし、ノーマライゼーションの理念をさらに発展させ、障がいのある人が地域で自立し、社会参加できるよう支援することを目的としています。障害者総合支援法に基づき、社会的な障壁を除去し、共生社会の実現を目指します。計画対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等に起因する障害を持つ人、発達障害者を含みます。 宮城県「みやぎ障害者プラン」や蔵王町の関連計画(第4次蔵王町長期総合計画、第6期蔵王町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画など)と整合性を図り策定されています。
1. 計画策定の背景と基本理念
第四次蔵王町長期総合計画『健やかなまちづくり~みんなが心も体も健康になる~』の基本方針を踏まえ、『障がいのある人が自分らしく生活できる蔵王町』を基本理念として、蔵王町第3期障害者計画・第4期障害福祉計画が策定されました。平成25年6月の障害者差別解消法成立など、障害福祉制度の大きな変化を背景に、ノーマライゼーションの理念をさらに発展させ、地域で障がいのある人が自分らしく生き生きと生活できる社会づくりを目指しています。計画の実現には、町民、関係機関、団体、行政の協働が不可欠であり、計画推進体制の整備と施策・事業の推進に努めていくことが強調されています。 この計画は、障がいのある人が必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会参加できる主体として捉え、その能力を最大限に発揮し自己実現できるよう支援することを目指しています。同時に、障がい者の社会参加を阻む社会的障壁の除去にも重点が置かれています。障害者基本法第1条の理念に基づき、障がいのある人もない人も等しく尊重され、共生する社会の実現を目指しています。
2. 関連計画との整合性と計画の対象
本計画は、宮城県の「みやぎ障害者プラン」、上位計画である「第4次蔵王町長期総合計画」、「第6期蔵王町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「健康ざおう21プラン」、「蔵王町子ども子育て支援事業計画(次世代育成支援行動計画を含む)」など、関連計画との整合性を図り策定されています。これは、蔵王町における障がいのある人のための施策を総合的に推進するための基本方針を示すものです。計画の対象となる障がいのある人は、障害者基本法に基づく身体障害、知的障害、精神障害があるため継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける人、同法改正時の付帯決議にある難病等に起因する身体または精神上の障害を有し継続的に生活上の支障がある人、発達障害者支援法に基づく自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)の人などです。これらの多様な障がいを持つ人々を包括的に支援する計画となっています。
3. 国の障害者基本計画との関連性
平成25年9月に閣議決定された「第3次障害者基本計画」との関連性が示されています。この基本計画は、障害者基本法に基づき、障がい者の自立と社会参加を支援するための施策を総合的かつ計画的に推進するためのものであり、政府の障害者施策の基本計画として位置付けられています。具体的には、障害者が可能な限り、生活の場や意思疎通手段を選択できること、地域社会で共生できることを妨げられないことなどが、第3次障害者基本計画で謳われています。また、第4期障害福祉計画の策定にあたり、国の基本指針の見直しが行われ、パブリックコメントを経て平成26年5月15日に基本指針が告示されたことも触れられています。これらの国の動向を踏まえ、蔵王町独自の計画が策定されていることがわかります。
II.サービス提供体制の整備 障害者福祉サービス の充実
計画では、障害者福祉サービスの充実を図るため、居宅介護などの訪問系サービスの拡充、地域移行支援の強化、計画相談支援の充実、基幹相談支援センターの機能強化を重点的に推進します。障害者虐待防止のため、関係機関との連携を強化し、相談体制を充実させます。 意思疎通支援として、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。また、移動支援事業も強化し、外出ヘルパーによる支援体制を整備します。
1. 訪問系サービスの充実と地域移行支援
計画では、障害者福祉サービスの充実を図るため、訪問系サービスの拡充を重点項目としています。具体的には、居宅介護事業の利用者増加傾向を踏まえ、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護などのサービスの更なる充実が図られます。 また、障害者総合支援法の趣旨に基づき、障害者支援施設から地域生活への移行を促進するため、地域移行支援が強化されます。これは、施設や病院に長期入所している人が地域生活に移行できるよう、住居の確保支援、障害福祉サービス事業所の見学、グループホームの体験ステイなどの支援を行うことを意味します。これらの支援を通して、安定した地域生活を送れるようサポート体制の構築を目指しています。 さらに、計画相談支援の充実にも取り組み、必要な障害福祉サービスが利用できるように生活実態を明らかにし、利用計画を作成、サービス事業所との連絡調整を行います。既存サービス利用者のモニタリングも定期的に実施し、適正なサービス利用を促進します。基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制の強化も重要な柱となっています。
2. 相談支援体制の強化と障害者虐待防止
地域における相談支援体制の強化は、計画の重要な要素です。基幹相談支援センターの事業充実を図ることで、中心的な役割を果たせるよう体制を整えます。平成23年6月に施行された障害者虐待防止法に基づき、市町村虐待防止センターを基幹相談支援センターに併設することで、関係機関との連携を強化し、相談支援体制を充実させます。 これは、障がい者虐待の予防と早期発見、そして養護者への支援を目的としています。 虐待の未然防止と早期発見に努めるため、関係者との連携強化による相談支援体制の充実が図られます。また、障がいのある人やその家族が悩みを共有し、情報交換できる交流活動、災害対策活動、見守り活動への支援なども行われ、より包括的な支援体制の構築を目指しています。意思疎通支援事業においては、聴覚、言語機能、音声機能などに障がいのある人に対し、必要に応じて手話通訳者や要約筆記者の派遣を「宮城県聴覚障害者協会」と連携して行います。
3. 移動支援とヘルスケアに関する支援
移動支援事業では、屋外での移動に困難のある身体・知的・精神障がいのある人や障がいのある児童を対象に、「白石陽光園」「蔵王町社会福祉協議会」などとの連携の下、外出ヘルパーによる移動支援を実施します。 さらに、健康管理面では、妊産婦や乳幼児を対象とした保健指導や健診、育児相談を実施し、異常や疾病の早期発見と早期療育指導の充実に努めます。生活習慣病の増加に対応するため、特定健康診査やがん検診なども実施し、生活習慣の改善、疾病予防、重症化防止に取り組みます。精神疾患の増加にも対応し、精神保健福祉相談(こころの相談)を実施し、精神科医による相談体制を強化し、医療機関との連携の下、医療受診、社会復帰、生活に関する支援を行います。 町内医療機関だけでは対応できない緊急な医療ニーズに対応するため、町外の医療機関との連携・協力体制の整備も課題となっています。 アンケート調査(n=95)の結果を踏まえ、医療費負担の軽減、専門医療機関へのアクセス向上、適切な医療情報の提供など、具体的な課題解決に向けた取り組みが検討されます。
III.就労支援と 障がい者雇用 促進
障がい者雇用の促進のため、大河原公共職業安定所白石出張所(ハローワーク白石)や県南障害者就業・生活支援センター(コノコノ)と連携し、就労相談、職場開拓、トライアル雇用、ジョブコーチなどの支援を行います。特例子会社制度などの活用促進、企業への相談体制充実、職親制度の周知・普及にも力を入れます。企業へのメンタルヘルス研修なども行い、うつ病などの精神疾患への理解と予防を図ります。
1. 就労相談 職場開拓支援とトライアル雇用
蔵王町では、障がいのある人の就労支援を強化するため、大河原公共職業安定所白石出張所(ハローワーク白石)や県南障害者就業・生活支援センター(コノコノ)と連携しています。具体的な支援としては、就労相談、職場開拓、トライアル雇用、ジョブコーチの活用などが挙げられます。 トライアル雇用は、障がいのある人が一定期間、事業所で試行的に雇用される機会を提供し、本格的な雇用につながるきっかけづくりを支援するものです。 ハローワーク白石との連携を通して、企業や事業主への特例子会社制度や各種助成制度の周知・活用促進にも取り組んでいます。 継続的な雇用を促進するため、企業への障害者雇用推進者の設置促進も図られています。 これらの取り組みによって、障がいのある人が地域で安定した雇用を得られるよう支援体制の構築を目指しています。 しかしながら、障がいのある人の就労をめぐる環境は依然として厳しい状況にあることも認識されており、更なる環境整備が必要とされています。
2. 職親制度の普及と企業への相談体制充実
障がいのある人が事業経営者のもとで生活し、職業訓練を受けて一般雇用を目指す「職親制度」の周知と普及にも力を入れています。これは、障がいのある人が、より実践的な職業訓練を受けながら、社会参加へのステップを踏み出すための支援策です。 企業に対する相談体制の充実も図られています。ハローワーク白石や県南障害者就業・生活支援センター(コノコノ)と連携し、企業が障がいのある人を雇用する際の相談窓口を強化することで、雇用促進を支援します。 関係機関との連携による就労支援の充実も重要な柱であり、事業主への働きかけを通じて、障がいのある人の雇用の機会拡大を目指しています。企業内におけるメンタルヘルス研修の推進なども行われ、うつ病などの精神疾患への理解促進と予防にも取り組んでいます。
3. 就労支援の課題と今後の取り組み
平成26年度のアンケート調査(n=95)では、今後参加したい活動として「趣味等のサークル活動」、「旅行」、「スポーツ、レクリエーション」などが挙げられており、これらのニーズを踏まえた支援策も検討する必要があります。 町内での就労促進のためには、関係機関との連携強化に加え、地元企業への啓発活動など、障がいのある人の雇用促進に向けた環境づくりが不可欠です。 現状では、障がいのある人の就労をめぐる環境は依然として厳しい状況にあると認識されており、継続的な雇用確保に向けた取り組み、企業内での障害者雇用推進者の設置促進、そして企業に対する相談体制の更なる充実が今後の課題となっています。 これらの課題に対応するため、関係機関との連携強化、企業への積極的な働きかけ、そして各種制度の周知徹底を継続的に行っていくことが重要です。
IV.地域理解と 社会参加 促進 障がい者 への理解促進
障がい者への理解促進のため、学校における福祉教育の充実、障がいのある人との交流機会の提供、啓発イベントの実施、福祉団体への支援などを実施します。防災対策として、要援護者台帳を活用し、関係機関と連携した避難支援体制の整備を図ります。ハートビル法、交通バリアフリー法等の関連法令に基づき、移動環境の整備にも取り組みます。アンケート調査結果(n=95)を基に、障がいのある人のニーズに応じた支援策を検討・実施していきます。
1. 障がい者への理解促進のための啓発活動
地域住民の障がい者への理解促進のため、様々な啓発活動が計画されています。具体的には、障がい者や障がい者福祉に関する関心や理解を深めるための啓発活動、学校における福祉教育の充実などが挙げられます。 また、障がいのある人との交流を通して理解を促進するための機会の提供、ボランティア活動やボランティア人材育成への支援、福祉的な就労や生産活動の機会の提供なども計画されています。さらに、障がいに関する講演会や学習会の開催、障がいのある人の地域活動への参加機会の促進、福祉施設の地域住民への開放なども含まれます。これらの活動を通して、地域全体で障がいのある人を理解し、支え合う共生社会の実現を目指しています。 平成26年度実施のアンケート調査(n=95)では、障がいのある人への周囲の理解について、「理解がある」と「どちらかといえば理解がある」の回答は約5割にとどまり、更なる理解啓発が必要であるとされています。
2. 学校教育における福祉教育の推進と地域ネットワークの構築
小中学校における福祉教育の推進は、障がい者理解を深める上で重要な取り組みです。児童が社会福祉に対する理解と関心を深められるよう、学校教育全体を通じて実践的な教育が行われます。 地域で活動する福祉団体への支援も重要視されており、交流の場(集いの場や情報交換の場など)の確保、活動や広報活動の情報提供、団体間のネットワーク化促進などが行われます。 これらの取り組みは、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域社会全体で支えるための基盤を築くことを目的としています。 障がいのある人を地域で支えるネットワークの整備も検討されており、地域住民による見守り活動などの強化を通して、安心して暮らせる環境づくりを目指しています。 防犯・災害対策においても、地域住民、行政区長、民生委員・児童委員、警察、消防団など関係機関が連携したネットワークづくりを支援し、防災時の対応を強化することで、障がいのある人も安心して暮らせる地域社会を目指しています。
3. 災害対策と移動環境の整備
平成26年度のアンケート調査(n=95)では、災害時における不安として、「避難場所の設備(トイレ等)や生活環境が不安」、「安全なところまで、すぐに避難することができない」といった意見が多く寄せられています。 このため、東日本大震災レベルの大規模災害に備え、地域と行政が協力して災害対策に取り組む必要があります。 具体的な対策として、講習会や防災訓練を通じた防災意識の向上、防災に関するパンフレットの作成・配布、避難誘導版の設置などが継続して実施されます。 緊急時における避難支援体制の整備においては、要援護者台帳を活用し、行政区長、民生委員・児童委員、警察署、消防署などと連携した支援体制を構築します。 また、障がい者が支援を求めやすいよう、支援の必要な事項を明記したヘルプカードの作成と普及啓発にも力を入れます。 移動環境の整備として、身体障害者手帳または療育手帳の所持者を対象にタクシー料金、JR、路線バス運賃の割引等の支援も行われ、ハートビル法、交通バリアフリー法などの関連法令に基づいた環境整備も進められます。
