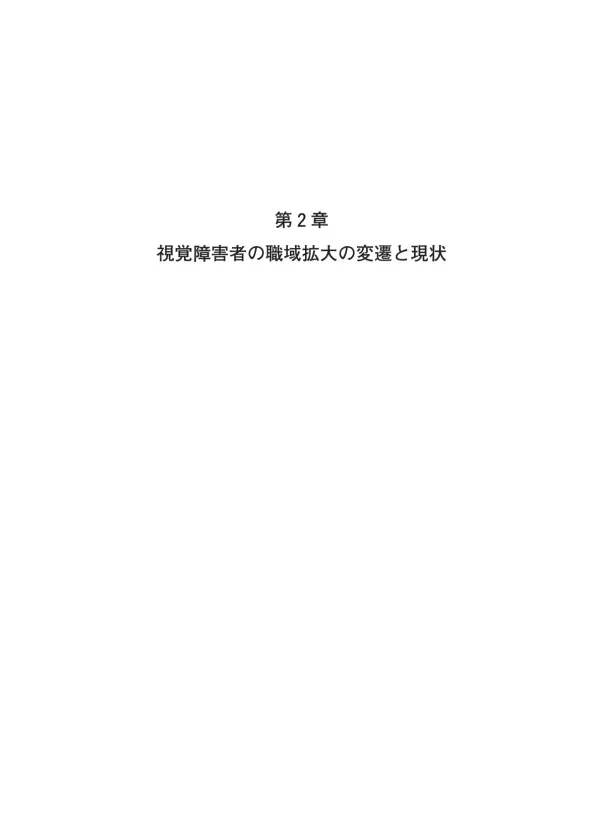
視覚障害者就労支援:職域拡大の現状と課題
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 626.12 KB |
| 専攻 | 視覚障害者就労支援 |
| 文書タイプ | 学術論文の一部 |
概要
I.視覚障害者の就職状況と職業能力開発
本資料は、視覚障害者のための就職状況と職業能力開発の変遷を分析したものです。 特に、電話交換手、録音タイプ速記者、コンピュータプログラマ、ピアノ調律師、教員、地方公務員といった職種における視覚障害者の雇用状況、職域拡大の取り組み、そしてアクセシビリティの向上に向けた努力について詳細に述べられています。300名以上の視覚障害者が電話交換手として就職した実績がありますが、ダイヤルインの普及や企業の合理化によってこの分野の就職は困難になっています。 近年は、情報技術の発達により、コンピュータプログラマや録音タイプ速記者といった新たな職業分野への進出も進んでいます。 しかし、ピアノ調律師のように、社会経済情勢の変化によって就職が困難になっている職種もあります。重度視覚障害者の就職についても、試験における点字受験や拡大文字の導入など、制度的な整備が進んでいます。
1. 電話交換手の現状と課題
300名以上の視覚障害者が電話交換手として就職した実績があり、特に1・2級の重度視覚障害者が多いことが示されています。昭和56年(国際障害者年)から数年は就職者数が急速に増加しましたが、ダイヤルインの普及や企業の合理化による人員削減のため、電話交換業務自体が廃止・定数減、あるいは他の事務との兼務となり、退職を余儀なくされたケースも出ています。そのため、今後の電話交換手への就職を促進するには、他の技能と組み合わせた形での取り組みが必要だと結論づけられています。昭和40年には日本ライトハウスが生活・職業訓練センターを開設し、昭和42年から電話交換の訓練を開始、昭和44年から厚生省、昭和56年からは労働省の委託事業として本格的な訓練が行われています。 この訓練を受けた視覚障害者が電話交換手として就職し、社会に貢献しています。
2. 録音タイプ速記と新たな職業分野
視覚障害者用ワープロの発達により、録音タイプ速記という新たな職業分野が開拓されました。昭和51年設立の日本盲人職能開発センターや、昭和55年に同センター内に設置された東京ワークショップが中心となり、録音タイプ速記者の養成が進められています。平成14年には社会福祉法人あかねがワークアイ・船橋を開設し、同様の訓練を実施しています。現在、この分野では10数名が雇用され、授産関係では40数名が従事しています。録音タイプ速記は、「録音タイプ速記者」、「医用トランスクライバー」、「オーディオ・タイピスト」の3種類に分類され、それぞれ異なる業務内容を担っています。 視覚障害者用ワープロの進歩により、従来のカナ文字から漢字仮名混じり文への変換工程を省略できるようになり、作業効率の向上に繋がっています。音声ワープロの改良も進み、仕事のスピードアップも実現しています。
3. コンピュータプログラマの現状と技術革新の影響
1963年にスターリング博士が視覚障害者のコンピュータプログラマとしての就労可能性を提唱し、1965年からアメリカ、イギリス、カナダで養成訓練が始まりました。日本でも昭和46年に日本ライトハウスで養成が始まり、翌年には最初のプログラマが誕生しました。初期はパンチカードや紙テープによるデータ入出力、オプタコンによる出力確認といった制約がありましたが、パソコンとネットワーク技術の発達により、スクリーンリーダーや点字ディスプレイを用いたプログラミング、ネットワーク経由での汎用機との連携が可能となり、作業効率が大幅に向上しました。 欧米では数百人規模の視覚障害者情報処理技術者が活躍しており、日本の視覚障害者プログラマもその実績を踏まえて育成されています。しかし、NC工作機械操作といった製造業分野での雇用機会は、産業構造の変化により減少しています。
4. ピアノ調律師の現状と職業教育の変遷
昭和36年に文部省の新職業研究指定を受け、ピアノ調律師の職業教育が始まりました。約80名が卒業し、半数以上が楽器店に就職、家庭訪問での調律が主な業務となっています。ピアノ製造会社での出荷調律や検査、音楽大学の専属調律師、楽器店経営なども行われています。しかし近年は楽器業界の不振により就職が困難になっており、求人数の減少に加え、調律以外の修理やセールスが求められること、運転免許の保有が困難であることなどが視覚障害者にとって不利な点となっています。大阪府立盲学校では10年ほど前にピアノ調律科が廃止されました。 音楽大学への就職や独立開業といった成功事例も存在しますが、社会情勢の変化への対応が課題となっています。
II.公務員採用試験における視覚障害者への配慮
地方公務員と国家公務員の採用試験においては、視覚障害者への配慮として、点字試験や拡大文字試験の導入、試験時間の延長などが行われています。東京都は昭和49年から福祉職において点字試験を実施しており、現在では他の職種にも拡大しています。 神奈川県も一般職の全級で点字試験を実施しています。国家公務員試験については、当初は点字試験に否定的でしたが、技術革新と視覚障害者団体による働きかけによって、平成3年から一部職種で点字試験が実施されるようになりました。 各都道府県における試験の実施状況は様々で、受験資格、採用予定人数、倍率なども掲載されています。(例:東京都Ⅰ類事務、平成17年度受験者4070名、合格者354名、倍率11.5倍)。
1. 地方公務員試験における点字 拡大文字試験の導入
地方公務員試験においては、東京都が昭和49年から福祉職にC枠を設け、視覚障害者向けに点字試験を先駆けて実施しました。その後、ほぼ毎年1名ずつ重度視覚障害者を採用しています。神奈川県では、一般職の全級と障害者特別採用枠で点字試験を実施しており、一般職上級・中級の合格者だけでなく、福祉専門職や電話交換業務などの技術職にも多くの視覚障害者が雇用されています。平成17年度には23都府県で視覚障害者向けに点字試験または拡大文字による試験が実施されており、東京都は当初福祉職のみだった点字試験を、現在ではⅠ類の他の職種やⅡ類にも拡大しています。具体的な採用例として、青森県(一般事務、平成16年度倍率14倍)、岩手県(一般事務、平成17年度倍率4倍)、宮城県(事務、学校事務)、千葉県(図書編集)などが挙げられ、それぞれ年齢制限、身体障害者手帳の有無、通勤・職務遂行能力などの受験資格が設定されています。
2. 国家公務員試験における点字試験導入の経緯と課題
国家公務員試験については、当初人事院は文書業務の特性から強度の視力障害者には不向きと判断し、点字試験の実施に否定的でした。しかし、視覚障害者用音声ワープロの普及や官庁のOA化の進展、視覚障害者団体による陳情活動などを経て、平成3年から国家公務員試験Ⅰ種およびⅡ種の一部(行政職のみ)で点字試験が実施されるようになりました。最大の障壁は国家公務員法第78条第2号の「心身の故障」に関する規定で、職務遂行に支障がある場合、本人の意思に反して降任や免職とすることができるというものでした。この規定は中途視覚障害者の継続雇用や新規採用にも大きな影響を与えていました。音声ワープロなどの技術革新と社会情勢の変化が、国家公務員試験における点字試験導入の背景となっています。
III.教員採用試験と視覚障害者
教員は視覚障害者にとって適職の一つとされており、多くの視覚障害者が教員を目指しています。昭和47年に大阪市が初めて点字試験を実施して以来、多くの自治体が視覚障害者への配慮を行っています。点字試験に加え、拡大文字試験も実施されています。 盲学校や普通学校で教員として働く視覚障害者は増加傾向にあり、職場復帰した中途失明者もいます。 しかし、校務分掌における支援策の具体的な状況については、まとまった調査が不足しています。
1. 教員採用試験における視覚障害者への配慮の拡大
昭和47年、大阪市が初めて教員採用試験で点字試験を実施したのを皮切りに、東京都、埼玉県、大阪府、神戸市などでも点字試験が導入され、普通学校で視覚障害者が教員として採用される事例が増えました。試験方法も点字だけでなく、拡大文字による試験も実施されるようになり、視覚障害者への受験上の配慮が進みました。平成17年度の文部科学省資料によると、多くの都府県市で筆記試験において視覚障害者への配慮が行われています。現在、地方自治体の教員採用試験に合格した視覚障害者は7名、さらに教員になった後に中途失明した10数名が職場復帰し、教職を継続しています。平成2年以降、重度視覚障害者が新任教員として赴任した学校をみると、盲学校7名、普通学校4名となっており、視覚障害者への理解と支援がしやすい環境が考慮されていることがわかります。盲学校や普通学校では、事務処理、生徒指導、安全指導など多様な校務分掌がありますが、視覚障害教員への具体的な支援策(業務分担、複数担任制、教材作成助手配置など)の実態は、まとまった調査が不足しているのが現状です。
2. 中途視覚障害者の教員としての復職と支援
小学校、中学校、高等学校で教員として働いていた人が中途失明した場合、盲学校や養護学校に転勤して教鞭をとる事例は以前からありました。しかし近年は、現職の教員が中途失明後、リハビリテーションを経て、様々な支援を受けながら職場復帰するケースが増加し、普通学校で教鞭をとる視覚障害者教員は約20人に達しています。 これらの復職事例は、視覚障害者に対する理解と支援体制の充実を示しており、社会全体のインクルーシブな教育環境の醸成に貢献しています。ただし、視覚障害教員が担う校務分掌の多様さ、そしてそれに対する具体的な支援策の実態把握には、更なる調査が必要と考えられます。 多くの学校で、視覚障害教員は他の教員と業務を分担したり、複数担任制を導入するなど、個々の状況に応じた支援が実施されていると推察されます。
3. 障害者雇用への意識と具体的な取り組み事例
文書からは、障害者雇用に対する意識の高さがうかがえる事例が紹介されています。具体的には、ある学校では、仏教系の宗教法人を母体としており、障害者に対する特別な意識を持つことなく、職務能力に基づいて採用を行っているため、自然な形で教職員への障害者雇用を実現しているという事例が挙げられています。また別の学校では、大学院の新設に伴い、障害者を含む教官が複数採用された事例が紹介されています。この学校は、これまで障害者枠を設定した募集を行ったことはありませんでしたが、今後は状況に応じて考慮する必要があると考えているとのことです。 具体的な配慮として、点字鋲の設置、学内車両乗り入れの許可、付添人の許可などが挙げられており、ノートテイカー養成講座の開設も計画されています。
IV.IT技術と視覚障害者の就職
情報技術(IT)の進歩は、視覚障害者の就職に大きな影響を与えています。スクリーンリーダー、ワープロ、ブラウザ、表計算ソフト、電子メールなどのソフトウェアの活用により、視覚障害者も多くの職種で活躍できるようになりました。 アンケート調査では、視覚障害者は印刷文書や電子メールによる文書作成に困難を感じていないことが示されています。しかし、会議資料の提示方法については、点字や拡大文字での提供が依然として重要です。 視覚障害者のITスキルの向上と、職場における情報アクセシビリティの確保が、更なる雇用促進に繋がります。
1. IT技術の進歩と視覚障害者の業務効率化
情報技術(IT)の発展は、視覚障害者の就労環境を大きく変えています。特に、スクリーンリーダー、ワープロ、ブラウザ、表計算ソフト、電子メールといったソフトウェアの普及により、視覚障害者もパソコンを利用した事務処理が可能になりました。 これにより、視覚障害者は文書作成やデータ処理といった業務を、晴眼者と遜色ないレベルで行えるようになり、作業効率の向上にも繋がっています。 かつては、汎用機へのアクセスにオプタコンが必要だった時代と比べ、パソコンとネットワーク技術の進歩は、視覚障害者にとって大きな福音となっています。 文書のやり取りに関しては、アンケート調査の結果、印刷文書や電子メールが主要な手段として広く利用されていることが示され、視覚障害者にとって文書作成と提出に大きな困難はないことがわかります。
2. 会議資料の提示方法とアクセシビリティの課題
会議資料の提示方法については、アクセシビリティの確保が依然として課題となっています。アンケート調査によると、会社から視覚障害者への会議資料の提示方法は、印刷文書、電子メール、点字文書、口頭説明、拡大文書、フロッピーと多岐に渡ります。しかし、会議中に視覚障害者自身が資料を参照できるのは、点字文書と拡大文書のみです。 このことから、会議への参加を円滑に進めるためには、点字文書や拡大文書による資料提供が不可欠であることが示唆されています。IT技術の進歩によって多くの業務が効率化されている一方、会議資料のアクセシビリティについては、更なる改善の余地があると言えるでしょう。 視覚障害者にとってITツールは必須であるものの、会議資料の点字化や拡大文字化は、企業側にとって追加的な負担となる可能性があります。
3. 視覚障害者採用事業所の状況と採用方法
視覚障害者を採用した事業所の状況に関する調査では、採用方法としてハローワークの紹介が12社と最も多く、合同面接会7社、学校紹介6社、リハビリ・職業訓練センター紹介5社、知人紹介4社と続いています。 視覚障害者側のアンケートでは知人紹介が多い傾向が見られ、特に施設関係への就職において顕著です。一方、民間企業の場合は、ハローワークや合同面接会などの公的な雇用斡旋サービスが重要な役割を果たしていることがわかります。 このことから、視覚障害者の就職活動においては、公的な雇用支援機関と、個人ネットワークの両方が重要な役割を担っていることがわかります。 企業側としては、ハローワークなどの公的機関を通じた採用が主流である一方、視覚障害者側は、既存のネットワークを活かした就職活動も盛んに行われていると言えます。
V.医療分野における視覚障害者の就労
医療分野においても、欠格条項の改正により、視覚障害者の職域拡大の可能性が広がっています。精神科医、中毒専門医など、既に31人の視覚障害医師がいるとされています。 医師国家試験の受験条件の整備も進み、重度視覚障害者の合格事例も出ています。 看護師や放射線技師など、他の医療関係職種への就労可能性も高まっています。伝統的な職業であるあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師に加え、新たな可能性が模索されています。
1. 欠格条項の改正と医療関係職への就労可能性
医師法をはじめ、看護師、薬剤師など他の医療関係職種における障害を理由とする欠格条項の見直しが行われ、視覚障害者も従事できる可能性が高まっています。 精神科医、中毒専門医、カイロプラクティック療法士、呼吸療法士といった分野では既に31人の視覚障害者が従事していると言われています。あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師は視覚障害者の伝統的な職業ですが、それ以外にも、放射線技師や看護師として相当の視力低下まで勤務していた中途視覚障害者の事例も報告されています。 欠格条項の改正は、視覚障害者にとって医療分野でのキャリア形成の可能性を広げる大きな一歩と言えるでしょう。 しかし、具体的な就労事例の数はまだ限定的であり、更なる制度整備や社会の理解促進が必要とされています。
2. 医師国家試験における視覚障害者への配慮と合格事例
医師国家試験の受験条件についても、平成14年に検討結果が公表され、平成15年3月には医学部在学中に失明した3名の重度視覚障害者が受験し、1名が合格、同年8月に医師免許を取得しました。 さらに、平成17年3月には大学卒業時点で強度弱視であった視覚障害者が、その後重度視覚障害者となり点字を使用する状態になったにも関わらず、欠格条項改正を機に再度挑戦し、3回目の受験で合格、同年9月に医師免許を取得し、12月から研修医として勤務を開始した事例も紹介されています。 これらの事例は、視覚障害者であっても医師国家試験に合格し、医療現場で活躍できることを示すものです。 これらの成功事例は、視覚障害者にとって医療分野への進出の可能性を示す重要な指標となっていますが、試験におけるアクセシビリティの確保や、就職後の職場環境整備等の継続的な努力が求められます。
VI.図書館における視覚障害者雇用
公共図書館は、視覚障害者にとって雇用機会となる可能性を秘めています。コンピュータ技術の発展により、レファレンス対応なども含め、視覚障害者でも十分に業務をこなせる可能性があります。 しかし、視覚障害者向けのサービスを実施している図書館は全国で150館を超えるにもかかわらず、雇用されている視覚障害者は約20名にとどまっています。点字図書館における視覚障害者職員の状況を示すデータも提示されています。 パソコン点訳の普及などにより、点字出版事業は縮小傾向にありますが、視覚障害者の雇用機会確保のための質的転換が必要です。
1. 公共図書館における視覚障害者雇用の現状と課題
全国で150館を超える図書館が視覚障害者向けのサービスを実施しているにも関わらず、雇用されている視覚障害者は約20名にとどまっています。 コンピュータ技術の進歩により、レファレンス対応を含む図書館業務を視覚障害者も十分にこなせる可能性があります。 また、障害者サービスは当事者である視覚障害者が従事することのメリットが大きく、より質の高いサービス提供が期待できます。 視覚障害者向けのサービス業務には、図書の貸出・レファレンス業務のほか、墨字本の点訳や録音、点訳者・音訳者向けの講習会開催なども含まれ、視覚障害者職員の活用は非常に有効です。 しかし、現状の雇用数の少なさは、社会全体の意識改革や、図書館におけるアクセシビリティ向上のための具体的な取り組みの不足を示しています。日本図書館協会にも障害者サービス委員会が設置されているものの、具体的な雇用促進策の実施状況は不透明です。
2. 点字図書館における視覚障害職員の状況とパソコン点訳の影響
資料には、平成15年度の点字図書館における視覚障害職員の状況を示す表が掲載されています。この表からは、各施設における正規職員、非常勤職員の数、日常点字を使用している職員数、司書(補)の職員数などがわかります。 しかし、具体的な施設名や職員数については、数値のみの提示となっており、詳細な分析は困難です。 パソコン点訳の普及とボランティアによるデータ製作システムの構築によって、従来型の点字出版事業は縮小傾向にあり、視覚障害者の安定した雇用を支えてきたこの分野の質的転換が求められています。 新しい技術に対応した雇用形態や業務内容の開発、そして雇用促進に向けた具体的な施策が、今後必要となるでしょう。 点字図書館は、視覚障害者にとって重要な情報アクセス拠点であると同時に、安定した雇用機会を提供してきた歴史があるため、その将来像を検討することが重要です。
