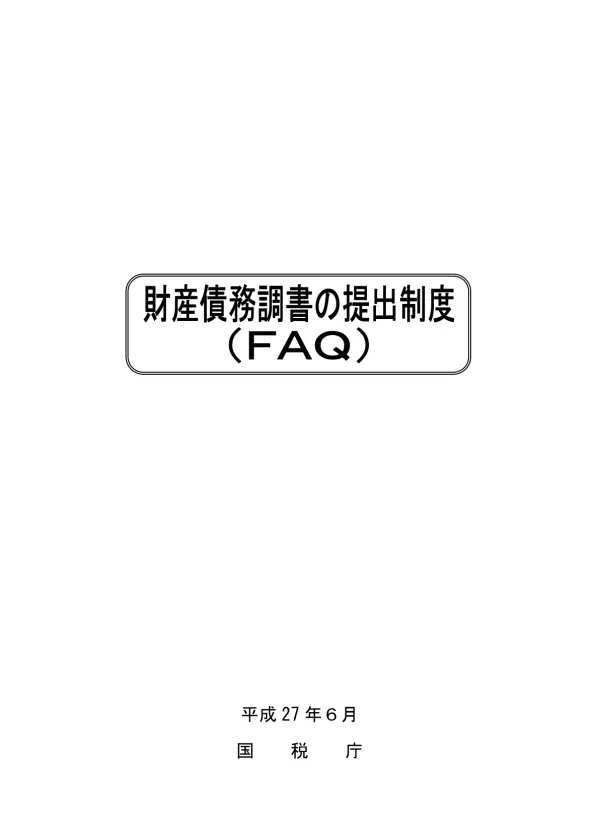
財産債務調書FAQ:記載事項と価額の算定
文書情報
| 学校 | 大学名(不明) |
| 専攻 | 税法、会計学関連 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | FAQ |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.06 MB |
概要
I.財産債務調書の提出義務と対象財産
この文書は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方のうち、年間総所得金額が2,000万円超かつ12月31日現在の財産の価額合計額が3億円以上(または1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合)に、財産債務調書の提出が義務付けられていることを説明しています。対象となる財産には、土地、建物、有価証券(上場株式、非上場株式など)、預貯金、デリバティブ取引に係る権利、匿名組合契約の出資の持分、貴金属類、その他の動産、その他の財産などがあります。含み損のあるデリバティブ取引に係る権利の価額も財産の価額合計額に含める必要があります。
1. 財産債務調書の提出義務
所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な個人で、年間総所得金額(山林所得を含む)が2,000万円を超え、かつ、12月31日現在で財産の価額合計が3億円以上、または国外転出特例対象財産の価額合計が1億円以上の場合は、翌年3月15日までに財産債務調書を提出する義務があります。これは国外送金等調書法6の2①本文に基づきます。確定申告の必要性の判断基準についても言及されており、給与収入が2,000万円以下で、1か所からの給与支払いのみで源泉徴収され、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要となるケースなどが例示されています。また、年の中途で死亡した場合は、その年の12月31日時点の財産債務調書の提出は不要と明記されています。所得税の申告義務の有無については国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)を参照するよう促しています。
2. 対象となる財産の範囲
財産債務調書の対象となる財産は幅広く、土地、建物、有価証券(上場株式、非上場株式を含む)、預貯金、デリバティブ取引に係る権利、匿名組合契約の出資の持分、貴金属類、その他の動産(現金、書画骨とう、美術工芸品、貴金属類を除く家具、什器備品、自動車など)、その他の財産(保険契約に関する権利、民法上の組合契約に基づく出資、信託受益権など)などが含まれます。特に、12月31日時点で決済されていないデリバティブ取引に係る権利は、見積価額として算出し、含み損がある場合でも他の財産の価額と通算して計算する必要があります。また、有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済信用取引等に係る権利、未決済デリバティブ取引に係る権利については、取得価額の記入も必要となります。 国外財産調書を提出する場合は、国外財産の価額合計額と国外転出特例対象財産の価額合計額を財産債務調書にも記入する必要があります。
3. 財産価額の算定における含み損と見積価額
12月31日時点で保有する財産の価額合計額が3億円以上かどうか、または国外転出特例対象財産の価額合計額が1億円以上かどうかを判定する際には、含み損のあるデリバティブ取引に係る権利の価額も考慮する必要があります。決済していない信用取引等やデリバティブ取引に係る権利の価額については、12月31日に決済したとみなして算出した利益または損失の額を見積価額とすることができます。含み損がある場合、その価額(見積価額)が負(マイナス)であっても、他の財産の価額と通算して計算します。 財産債務調書では、その年の12月31日における財産の時価または時価に準ずる価額として「見積価額」を記入することになっており、時価の算定が困難な場合でも見積価額によることを認めています。見積価額は、取得価額や売買実例価額などを基に合理的かつ客観的な方法で算定する必要があります。
II.財産債務調書の記載方法
財産債務調書の記載事項は、財産の種類、数量、価額、取得価額(有価証券、匿名組合出資など)、用途(事業用・一般用)、所在などを含みます。 価額は12月31日時点の時価または見積価額を記載します。事業用の債権・債務で100万円未満のものは、所在別区分を省略できます。土地と建物は、面積や戸数を記載し、リゾートマンションのように土地と建物が一体になっている場合は備考欄に明記します。有価証券は銘柄別に区分し、預貯金は金融機関名と種類を記載します。その他の財産については、具体的な記載方法が文書に詳しく説明されています。
1. 財産の記載事項
財産債務調書には、財産の「種類」、「数量」、「価額」、そして特定の財産(有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済信用取引等に係る権利、未決済デリバティブ取引に係る権利)については「取得価額」も記載する必要があります。価額は、12月31日時点の時価、または時価に準ずる見積価額を記載します。 財産は「事業用」と「一般用」に分類され、さらに所在別に区分されます。 具体的には、土地は地所数と面積、建物は戸数と床面積を記載します。土地と建物が一体となっているリゾートマンションなどについては、備考欄にその旨を記載する必要があります。有価証券は種類(株式、公社債など)と銘柄を区別し、上場株式と非上場株式は分けて記載します。預貯金は種類(当座預金、普通預金など)と金融機関名、支店名を明記します。貴金属類、その他の動産、その他の財産についても、種類、数量、所在を明確に記載する必要があります。事業用の債権・債務で100万円未満のものは、所在別区分を省略できます。
2. 債務の記載事項
債務についても、種類別(前受金、預り金など)、用途別(事業用・一般用)、所在別に記載する必要があります。これは国外送金等調書規則別表第三に規定されています。 具体的には、未払金や預り保証金など、多数の債務がある場合でも、所在別に記載する必要があります。ただし、事業用の財産債務で「未収入金」「その他の財産」「未払金」「その他の債務」に区分され、その価額または金額が100万円未満のものは、所在別に区分することなく、件数と総額を記載しても差し支えありません。 また、売掛金など事業上の債権についても、相手方の住所または本店・主たる事務所の所在地を明記する必要があります。 国外財産調書を提出する場合は、国外財産調書に記載した国外財産の価額合計額と国外転出特例対象財産の価額合計額を財産債務調書にも記入する必要があります。 例として、記載例に東京都千代田区、港区、品川区にある土地と建物、○○銀行△△支店、△△証券△△支店、株式会社B、××証券××支店などの所在地や名称が記載されています。
3. 特定財産の取得価額と記載上の留意事項
有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済信用取引等に係る権利、未決済デリバティブ取引に係る権利などについては、その年の12月31日時点の価額に加え、取得価額の記載が求められます。 特定口座内で上場株式等の信用取引や発行日取引を行い、12月31日時点で決済されていないものについては、「未決済信用取引等に係る権利」に区分されますが、銘柄別の記載は不要で、所在別、株式、公社債、投資信託等の別に一括して価額と取得価額を記載できます。 事業上の債権(例:売掛金)は、相手方の所在地を記載する必要がありますが、未収入金やその他の財産で、不動産所得、事業所得、山林所得を生む事業・業務に供する債権で、12月31日時点の価額が100万円未満の場合は、所在別記載を省略し、件数と総額を記載できます。 複数の財産債務調書を作成・提出する場合でも、合計額は1枚目の調書に記載します。 記載例では、事業用と一般用、そして所在別に区分された財産の価額が示されています。
III.見積価額の算定方法
財産債務調書に記載する財産の価額は、時価が不明な場合でも見積価額を記載できます。見積価額の算定方法は、財産の種類によって異なります。例えば、株式は決算書に基づいて算出、土地は固定資産税評価額、その他の動産は取得価額から償却費を控除した金額などを用います。デリバティブ取引に係る権利の見積価額は、決済したとみなして算出した利益または損失の額とすることができます。ストックオプションの価額算定方法も記載されています。
1. 見積価額の算定 一般原則
財産債務調書に記載する財産の価額は、原則として12月31日時点の時価です。しかし、時価の算定が困難な場合、時価に準ずる「見積価額」を記載することができます。この見積価額は、財産の取得価額、売買実例価額などを基に、合理的な方法で算出する必要があります。 文書では、様々な財産の種類について見積価額の算定方法が示されています。例えば、土地については固定資産税評価額、山林についても固定資産税評価額を基準に算出する方法が挙げられています。上場株式は市場価格、非上場株式は発行法人の決算書に基づく純資産価額に持株割合を乗じて算出する方法が示されています。デリバティブ取引に係る権利については、12月31日に決済したとみなして算出した利益または損失額、または銀行や証券会社から入手した価額に基づいて算出する方法が示されています。 その他の動産(現金、書画骨とう、美術工芸品、貴金属類を除く家具、什器備品など)については、取得価額から経過年数に応じた償却費を控除した金額を見積価額とすることができます。
2. 見積価額の算定 具体的な財産例
文書では、具体的な財産の種類ごとに、見積価額の算定方法について詳細な説明がなされています。株式については、上場株式と非上場株式で算定方法が異なります。上場株式は市場価格を、非上場株式は発行法人の決算書に基づいた純資産価額を参考に算出します。 決算書の確定が財産債務調書の提出期限(翌年3月15日)を過ぎる場合、一つ前の事業年度の決算書を用いて見積価額を算出することも認められています。 デリバティブ取引に係る権利の見積価額は、決済したとみなして算出した利益または損失額、または金融機関からの提示額に基づいて算出できます。 ストックオプションの価額算定方法も具体的に記載されており、上場株式の場合は市場価格、非上場株式の場合は純資産価額に持株割合を乗じる方法が例示されています。 匿名組合契約の出資の持分は、組合の純資産価額または利益の額に自己の出資割合を乗じて計算する方法が示されています。 生命保険契約の価額は、解約返戻金を基に算出する方法が示されていますが、解約返戻金の額を入手している場合は、その額を価額とすることができます。
IV.過少申告加算税等の加重措置
財産債務調書の提出期限を過ぎた場合、または記載漏れがあった場合、過少申告加算税に5%の加重措置が適用されます。これは、財産債務に関する所得税等の申告漏れがあった場合に課せられます。逆に、期限内に正しく提出した場合、過少申告加算税等が5%軽減されます。平成28年中に保有していた財産を譲渡した場合、過少申告加算税等の加重措置の適用判断は、その前年(平成27年)の財産債務調書に基づいて行われます。
1. 過少申告加算税等の加重措置の概要
財産債務調書の提出期限内に提出されない場合、または提出された調書に記載すべき財産債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分な場合を含む)、その財産債務に関する所得税等の申告漏れ(死亡者を除く)が生じたときは、その申告漏れ部分の過少申告加算税等に5%の加重措置が適用されます。これは、国外送金等調書法6②、6の3②に基づきます。 加重措置の対象となるのは、所得税および復興特別所得税の申告漏れです。 財産債務調書に記載すべき事項を正確に記載することで、この加重措置を回避することが可能になります。 逆に、期限内に正しく財産債務調書を提出した場合には、財産債務に関する所得税等または相続税の申告漏れがあったとしても、過少申告加算税等が5%軽減される特例措置が適用されます(国外送金等調書法6①、6の3①)。この特例措置は、財産債務調書の適正な提出を促すためのインセンティブとして設けられています。
2. 加重措置の適用と申告漏れ
過少申告加算税等の加重措置は、財産債務調書の不備または未提出によって生じる所得税等の申告漏れに対して適用されます。 具体的には、提出期限内に財産債務調書が提出されない場合、または提出された調書に記載すべき重要な財産債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産債務に関する所得税等の申告漏れがあった場合に、5%の加算税が加重されます。 この加重措置は、死亡者には適用されません。 財産債務調書制度の目的は、財産債務に関する情報の正確な提出を求めることであり、この制度によって、税務調査における更正や決定を円滑に進めることが期待されています。そのため、財産債務調書への記載は正確であることが求められます。 提出期限後であっても、調査によって更正や決定があるべきことを予知して提出されたものでない限り、提出期限内に提出されたものとみなされ、特例措置が適用される場合もあります(国外送金等調書法6④、6の3③)。
3. 年の中途で財産債務を有しなくなった場合の取扱い
年の中途で修正申告等の原因となる財産債務を譲渡などによって有しなくなった場合、過少申告加算税等の加重措置の適用判断は、その年の前年の財産債務調書に基づいて行われます。 例えば、平成28年中にB社株式を全て譲渡し、所得の申告漏れがあった場合、過少申告加算税の加重措置の適用を判断する財産債務調書は、平成27年12月31日時点のものです。これは、その年の12月31日時点では既に当該財産を保有していないため、その年分の財産債務調書には記載されないことから、前年分の調書を参照する必要があるためです(国外送金等調書法6③、6の3③)。 同一銘柄の株式であっても、預入先の証券会社が異なったり、用途が異なったりする場合は、それぞれ個々の財産として記載する必要がある点に注意が必要です。
