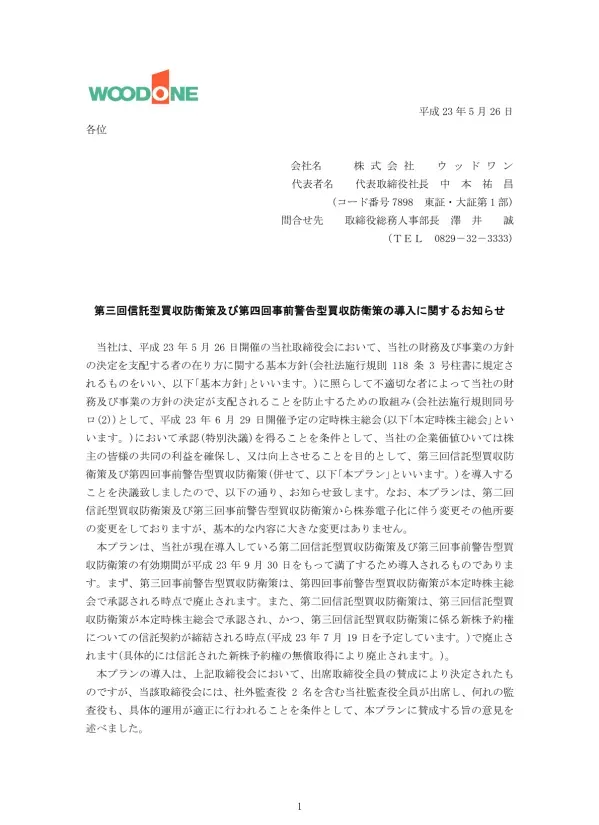
買収防衛策導入のお知らせ
文書情報
| 著者 | 株式会社ウッドワン |
| 会社 | 株式会社ウッドワン |
| 文書タイプ | プレスリリース |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 504.36 KB |
概要
I.第三回信託型買収防衛策及び第四回事前警告型買収防衛策の導入
ウッドワン株式会社は、不適切な者による企業価値の損なわれることを防ぐため、平成23年6月29日開催予定の定時株主総会において、第三回信託型買収防衛策と第四回事前警告型買収防衛策の導入を決定しました。これは、既存の防衛策の有効期限切れに伴う措置であり、新株予約権の発行・割当を伴います。本防衛策は、株主の共同の利益を確保・向上させることを目的としており、株式取得や公開買付けといった敵対的買収への対応策として機能します。特に、株主への株式売却強要や不当な買収条件を阻止するための仕組みです。 みずほ信託銀行が信託業務に携わります。
1. 導入の目的と背景
平成23年5月26日開催の取締役会において、第三回信託型買収防衛策と第四回事前警告型買収防衛策の導入が決定されました。これは、会社法施行規則118条3号に基づく基本方針に照らし、不適切な者による経営支配を防止するための措置です。既存の第二回信託型買収防衛策と第三回事前警告型買収防衛策の有効期限(平成23年9月30日)が満了するため、新たな防衛策が必要となりました。本プランは、企業価値の維持・向上、ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的としています。 具体的には、不適切な株式の大量買付けによる経営支配の試みを防ぎ、株主の皆様に不利益を及ぼすような買収行為を阻止することを目指しています。既存の防衛策からの変更点は、株券電子化に伴う修正などですが、基本的な内容は変更ありません。
2. 既存防衛策の廃止時期
第三回事前警告型買収防衛策は、第四回事前警告型買収防衛策が本定時株主総会で承認された時点で廃止されます。第二回信託型買収防衛策は、第三回信託型買収防衛策が本定時株主総会で承認され、かつ、第三回信託型買収防衛策に係る新株予約権についての信託契約が締結された時点で廃止されます。この信託契約は平成23年7月19日を予定しており、信託された新株予約権の無償取得によって廃止されます。この廃止プロセスは、新しい防衛策がスムーズに機能し、既存の防衛策の重複による混乱を避けるための重要なステップです。 スムーズな移行により、企業の安定的な経営と株主への利益還元を継続することを目指しています。
3. 企業価値と利害関係者への配慮
ウッドワングループは、林業・総合木質建材製造・住宅設備機器製造における長年の経験、知識、情報、そして顧客、取引先、地域社会からの信頼を企業価値の基盤としています。これらの関係者との信頼関係なくしては、企業価値の正確な把握や向上のための施策の策定、成果予測は困難です。そのため、経営を支配する者は、これらの企業価値の源泉と利害関係者との信頼関係を十分に理解し、中長期的に株主の共同の利益を追求する者でなければなりません。 近年増加している、株式を買い集め自己利益のみを追求するような、株主への株式売却の事実上の強要、または真の企業価値を反映しない低価格での売却を強いるような買収行為は、企業価値ひいては株主の共同の利益を著しく損なうと認識しています。 このような行為に対する防衛策として、本プランが導入されることになります。
4. 本プランの導入と株主総会への付議事項
本プランの導入は、平成23年6月29日開催予定の本定時株主総会での承認(特別決議)を条件としています。 具体的には、①第三回信託型買収防衛策の導入と、対抗措置として用いる新株予約権の発行に関する議案、②第四回事前警告型買収防衛策の導入と、対抗措置として用いる新株予約権の無償割当て(決定権限の取締役会への委任に関する議案)の二点が株主総会に付議されます。 この株主総会での承認は、本プランの導入にとって不可欠なプロセスです。 株主の皆様の理解とご賛同を得ることが、企業価値の維持・向上、ひいては株主の皆様の利益に繋がることを強く願っています。
5. 本プランによる対抗措置の詳細
本プランに基づく対抗措置は、原則として信託された新株予約権の無償交付ですが、買収の態様や租税法等の法令上の制約を考慮し、新株予約権の無償割当てを行う可能性もあります。 どちらの対抗措置も同時に発動することはありません。取締役会は、意向表明書受領後10日以内に、買収提案者等に対して必要な情報を求める本必要情報リストを交付し、情報提供を求めます。取締役会は、外部専門家の助言を得て、買収提案者等の属性や買収内容を評価・検討し、買収条件に関する交渉や代替案の提示を行います。 評価期間は、公開買付けの場合最長60日間(情報提供完了通知発送日から)、その他の場合は取締役会が決定します。評価期間の延長は、最長30日間可能です。
II.基本方針と企業価値の保護
本買収防衛策導入の背景には、ウッドワンの企業価値の源泉である林業、総合木質建材製造、住宅設備機器製造における長年の経験、知識、顧客・取引先との信頼関係を維持・向上させるという強い意志があります。 不適切な株式取得によりこれらの関係が損なわれることを懸念しており、株主の共同の利益を最優先した判断を下すことを目指しています。取締役会は、買収提案の内容を十分に評価し、必要に応じて買収条件の交渉や代替案の提示を行います。
1. 企業価値の源泉と保護の必要性
ウッドワン株式会社の企業価値は、林業、総合木質建材製造、住宅設備機器製造における長年の経験、蓄積された知識・情報、そして顧客、取引先、地域社会からの信頼の上に成り立っています。これらの要素は、企業活動を支える重要な基盤であり、適切に理解し尊重することが不可欠です。これらの理解と信頼関係なくしては、企業価値の正確な把握や、将来に向けた企業価値向上のための戦略策定、その成果の予測は非常に困難です。 したがって、会社の財務および事業の方針決定を支配する者は、ウッドワンの企業価値の源泉と、それを支える利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、中長期的な視点から企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を真摯に追求する者でなければなりません。この基本方針に基づき、不適切な経営支配を防ぐための取り組みとして、買収防衛策の導入が決定されました。
2. 不適切な買収行為への懸念
近年、上場企業に対する大規模な株式買付けにおいて、株式を買い集め、濫用的な会社運営を行い、多数派株主として自己の利益のみを追求するケースや、株主に対して株式の売却を事実上強要したり、真の企業価値を反映しない低価格での売却を余儀なくさせるような買収行為が見られます。このような行為は、企業価値を著しく損ない、株主の皆様の共同の利益を害する可能性があります。 ウッドワンは、こうした不適切な買収行為によって、長年培ってきた企業価値の基盤が脅かされることを危惧しています。 そのため、企業価値の保護と株主利益の最大化を図るため、適切な防衛策を講じる必要性があると判断しました。
3. 取締役会の責任と役割
上場企業であるウッドワンの株式は、株主と投資家の皆様による自由な取引が認められています。しかしながら、大規模な買付けに対する最終的な判断は株主の皆様が行うべきです。 それでも、買収提案があった場合、取締役会は株主の皆様が適切な判断を行うために必要な情報を収集・提供するだけでなく、買収条件や買収後の経営方針などが、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものかどうかを自ら評価・検討する責務があります。 評価の結果、買収条件や買収後の経営方針が企業価値や株主の共同の利益を損なうと判断された場合は、買収提案の内容を改善させるべく、買収提案者と交渉することが取締役会の責務です。平成23年3月末時点で、ウッドワンの議決権の約25.1%は経営者とその資産管理会社等が保有していますが、経営方針と異なる買収が行われた場合、その条件や後の経営方針によっては、経営者等の議決権保有比率にかかわらず、株主、顧客企業、取引先、地域社会など全ての利害関係者に影響が及ぶ可能性があります。
III.本プランの仕組みと対抗措置
本プランは、特定大量保有者や特定大量買付者による公開買付けなど、株主に不利な株式取得が行われた場合に発動します。取締役会は、特別委員会の勧告を尊重し、新株予約権の無償交付または無償割当てといった対抗措置を講じます。この対抗措置は、買収防衛策として、不当な買収を阻止し、企業価値と株主の利益を守るための重要な役割を果たします。 情報開示を徹底し、透明性を確保することで、株主意思を尊重した運営を目指します。
1. 本プランの概要と手続き
本プランは、会社に対する買収等の提案があった場合に、取締役会が買収提案者等に対して情報提供を求め、特別委員会の勧告を尊重しつつ、買収提案の評価・検討、買収条件に関する交渉、株主への代替案提示、そして必要に応じて対抗措置の発動を行うための手続きです。 具体的には、買収提案者とそのグループの詳細な情報開示を求め、その内容を評価・検討します。取締役会は、買収が企業価値や株主の共同利益を損なうと判断した場合、買収条件の交渉や代替案の提示を行い、必要に応じて対抗措置を発動します。この対抗措置は、原則として信託された新株予約権の無償交付ですが、買収の態様や法令上の制約により、新株予約権の無償割当てを行う場合もあります。ただし、両方の対抗措置を同時に発動することはありません。 買収提案者からの情報提供後、取締役会は買収の是非を判断し、特別委員会に諮問、必要に応じて外部専門家の助言も得ながら、対抗措置の発動を決定します。
2. 情報開示と評価期間
取締役会は、買収提案者等から必要十分な情報(本必要情報)の提供を受け、それを評価・検討します。情報開示は、法令で定められている事項に加え、取締役会が適切と判断する事項についても株主・投資家の皆様に開示されます。 評価期間は、現金のみによる公開買付けで全株式を取得する場合、情報提供完了通知発送日から最長60日間です。その他の買収の場合は、買収内容に応じて取締役会が適切な期間を設定します。 取締役会は、やむを得ない事情がある場合、特別委員会の勧告に基づき、最長30日間評価期間を延長できます。延長する場合は、その日数と理由を速やかに情報開示します。特別委員会は、買収提案者等が本プランの手続きを遵守しなかった場合、または買収が一定の要件に該当する場合、対抗措置の発動を勧告します。 一度不発動を勧告した後でも、状況変化があれば、改めて発動を勧告する可能性があります。
3. 特別委員会の役割と株主への情報開示
取締役会の恣意的判断を排除し、客観的な評価・検討を行うため、特別委員会が設置されます。 特別委員会は、買収提案者等が本プランの手続きを遵守しなかった場合、または買収が株主への株式売却を事実上強要するケース、買収条件が企業価値に鑑みて著しく不十分または不適当なケースなど、一定の条件に該当する場合に、対抗措置の発動を勧告します。 この勧告は、原則として信託された新株予約権の無償交付ですが、状況によっては新株予約権の無償割当てを勧告することもあります。 特別委員会による評価・検討の結果、および取締役会の最終的な決定は、株主の皆様に透明性高く開示されます。この情報開示は、株主の皆様が適切な判断を行うために必要不可欠です。 この仕組みは、取締役会の恣意的な行動を抑制し、株主利益を最大限に保護することを目指しています。
IV.新株予約権の行使条件と組織再編
新株予約権は、特定株式保有者が現れた場合にのみ行使可能です。行使により、新株予約権保有者はウッドワンの株式を取得できます。 会社が組織再編行為(合併、分割など)を行う場合、新株予約権は再編対象会社の新株予約権に置き換えられます。 新株予約権は、買収防衛策の重要な要素であり、その行使条件は厳格に定められています。
1. 新株予約権の行使条件
新株予約権の行使は、特定大量保有者または特定大量買付者が発生した場合に限定されます。特定大量保有者とは、会社が発行する株券等の保有割合が20%以上となった保有者を、取締役会が認めた者です。特定大量買付者とは、公開買付けにより会社が発行する株券等の買付けを行い、買付け後におけるその者の所有割合(特別関係者の割合を含む)が20%以上となると取締役会が認めた者です。 これらの特定大量保有者または特定大量買付者が現れ、その事実が取締役会で認識され、公表されてから10日間経過した後に初めて新株予約権を行使できます。公開買付けの場合は、公開買付開始公告日から10日間経過後です。 取締役会が新株予約権を取得する場合、法定の手続きに従い、取締役会が別途定める日をもって取得します。非適格者以外の株主から新株予約権を取得し、当社株式を交付する際には、株主は行使価額相当の金銭を支払うことなく、1個の新株予約権につき1株の当社株式を受領します。ただし、この場合、表明保証条項、補償条項等の誓約を含む書面提出が求められます。
2. 新株予約権の取得と株式交付
取締役会が新株予約権を取得する決定をした場合、法定の手続きに従い、取締役会が別途定める日をもって取得します。 この際、非適格者(ウッドワンセキュリティーズホールディングスおよびその信託銀行・信託会社)以外の株主から新株予約権を取得し、その代わりに当社株式を交付する場合があります。この場合、株主は行使価額相当の金銭を支払うことなく、1個の新株予約権につき1株の当社株式を受領します。 株主が当社所定の新株予約権行使請求書を提出の上、1株あたり1円を支払った場合は、1個の新株予約権につき1株の当社株式が発行されます。 しかし、金銭の支払いや手続きを経ない場合、他の株主による新株予約権の行使により、保有する当社株式の経済的価値や議決権比率が希釈される可能性があることに留意が必要です。
3. 組織再編における新株予約権の取扱い
会社が合併(当社が消滅する場合)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(組織再編行為)を行う場合、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権が交付されます。 この再編対象会社の新株予約権の交付は、会社法236条1項8号に基づき行われ、吸収合併契約、新設合併契約など、それぞれの契約書に、再編対象会社新株予約権を交付する旨が明記されている場合に限ります。 残存新株予約権保有者には、それぞれのケースに応じて、会社法236条1項8号イからホまでに掲げる株式会社(再編対象会社)の新株予約権が交付されます。 この手続きは、組織再編後も株主の権利が適切に保護されるよう、細心の注意を払って行われます。
V.本プランの有効期間と廃止
本買収防衛策の有効期間は約3年間(平成26年9月30日まで)ですが、株主総会の決議により、いつでも廃止可能です。これは、デッドハンド型やスローハンド型とは異なり、株主意思を尊重した設計となっています。 法令改正等にも対応するため、必要に応じて修正・変更が行われます。
1. 有効期間
第三回信託型買収防衛策の有効期間は、本定時株主総会で承認され、かつ、第三回信託型買収防衛策に係る新株予約権についての信託契約が締結された時点(平成23年7月19日を予定)から平成26年9月30日までです。第四回事前警告型買収防衛策の有効期間は、本定時株主総会で承認された時点から平成26年9月30日までです。 有効期間は約3年間と定められており、これはいわゆるサンセット条項です。この期間設定は、買収防衛策の有効期間を明確に示し、株主の皆様への透明性を高めることを目的としています。また、このサンセット条項は、防衛策が永続的に運用されることを防ぎ、状況に応じて柔軟に対応できるよう考慮されたものです。
2. 廃止手続き
有効期間満了前であっても、株主総会または株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合は、本プランはその時点で廃止されます。 この廃止条項は、株主の皆様の意思を尊重し、必要に応じて柔軟に防衛策を解除できる仕組みを確保するためのものであり、株主主権を重視した設計となっています。 取締役会は、株主総会の決議によって、いつでも本プランを廃止できる権限を有しており、これはデッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策とは大きく異なる点です。 つまり、特定の株主グループが取締役会を掌握したとしても、容易に本プランを廃止できる仕組みが設けられているということです。
3. プランの修正 変更
取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会決議の趣旨に反しない場合、特別委員会の承認を得た上で、本プランを修正または変更することができます。 この修正・変更の対象となるケースは、本プランに関する法令や有価証券上場規程の新設・改廃を反映する場合、誤字脱字などの修正が必要な場合、株主に不利益を与えない範囲での変更などです。 この柔軟な対応策は、法令改正や市場環境の変化などに対応し、本プランの有効性を継続的に維持することを目的としています。常に株主の利益を最優先し、適切な対応を取れるよう、十分な検討と承認プロセスを経ることで、プランの機能維持を図ります。
