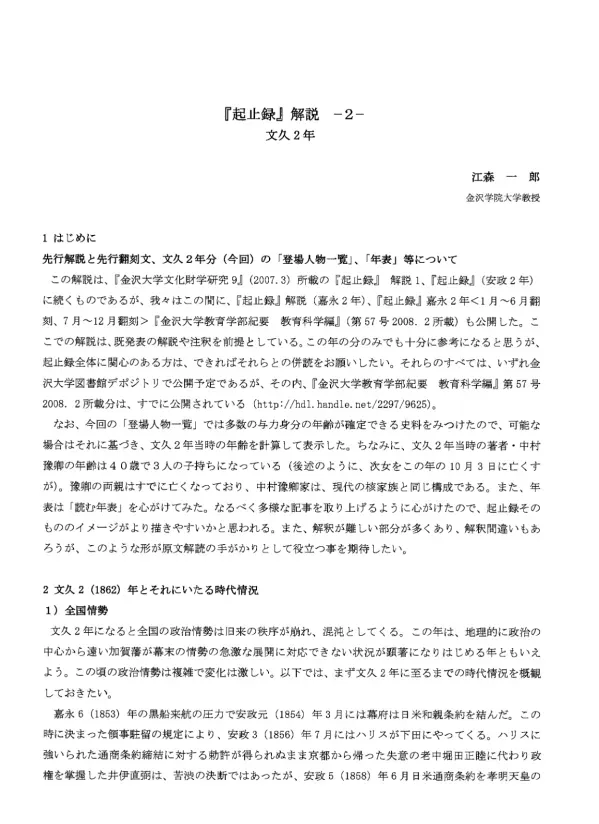
起止録(文久2年)解説:加賀藩と競争社会
文書情報
| 著者 | 江森一郎 |
| 学校 | 金沢学院大学 |
| 専攻 | 文化財学 |
| 場所 | 金沢 |
| 文書タイプ | 解説論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.21 MB |
概要
I.文久2年 1862年 の加賀藩における社会 政治情勢と中村豫卿の起止録
この文書は、文久2年(1862年)の加賀藩における中村豫卿の起止録を分析したものです。幕末の動乱期、特に安政の大獄や黒船来航以降の急激な社会変動が、加賀藩にも大きな影響を与えた様子が詳細に記されています。物価高騰、コレラなどの疫病流行、そして藩内における政治的緊張の高まりといった、当時の厳しい生活状況と社会不安が克明に描写されています。起止録は、加賀藩下級役人である中村豫卿の日々の生活、仕事、家族関係、そして社会情勢への関わりを記録しており、身分制度や藩政の実態を理解する上で貴重な一次資料となっています。重要な人物としては、中村豫卿自身に加え、その周囲の人物や、坂下門外の変、寺田屋事件といった出来事に関連する人物なども含まれます。 特に、加賀藩における武士の生活、経済状況、社会関係といった側面を詳細に理解する上で重要な情報が記載されています。
1. 文久2年の加賀藩を取り巻く情勢と社会情勢
この節では、文久2年(1862年)の加賀藩における社会・政治情勢が、主に全国的な出来事を背景に解説されています。まず、嘉永6年(1853年)の黒船来航から安政5年(1858年)の日米通商条約締結までの経緯が簡潔にまとめられています。これは、その後の国内の急激な物価高騰や社会不安の伏線として重要な位置づけになっています。文久元(1861)年以降の京都を中心とした政情不安も触れられており、長州藩の航海遠略策の挫折や、坂下門外の変、寺田屋事件、そして高杉晋作らによる英公使館焼き討ちといった事件が、当時の混乱を象徴する出来事として挙げられています。安政6年(1859年)からの自由貿易開始による物価高騰(米価の推移も示されている)は、社会不安の大きな要因の一つとして強調されており、これらの出来事が加賀藩にも大きな影響を与えたことが示唆されています。さらに、幕府による参勤交代制の緩和といった政策も、幕藩体制の変化を象徴する出来事として言及されています。これらの出来事は、文久2年の加賀藩の状況を理解する上で重要な背景情報を提供しています。
2. 中村豫卿の日常生活と仕事 公事場勤務を中心とした記録
この節では、中村豫卿の文久2年の日常生活と公事場での仕事が、起止録に基づいて詳細に記述されています。3月28日の公事場再任をきっかけに起止録が再開されたことが記されており、その後の勤務状況や、検使御用への関与、そしてその職務の限定に関する記述も見られます。具体的な仕事内容や、同僚との交流、上司からの指示などが、日記形式で簡潔に記されています。また、公事場での事件に関する記述があり、馬廻りと与力2名が処分された大きな事件があったことが示唆されていますが、詳細は不明です。さらに、西坂成庵先生の死去とその弔いの様子も記述されており、師弟関係の変化も垣間見ることができます。これらの記述は、当時の加賀藩下級武士の日常業務の具体的な内容、職場の雰囲気、人間関係などを詳細に示しています。また、公事場という特定の職場における出来事を中心に、社会情勢との関連も示唆する記述も含まれています。
3. 家族 近隣関係 そして社会との関わり 疾病 教育 経済
この節は、中村豫卿の家族、近隣住民との交流、そして社会との関わりについて、起止録に基づいた記述が中心となっています。家族については、3人の子供たちの成長や、次女の死といった悲劇的な出来事が記されています。妻の厳しい生活状況や、近隣住民との助け合いなども垣間見ることができます。子供たちの教育についても触れられており、素読や謡の指導といった教育の様子が示されています。経済的な側面としては、借金や内職、そして頼母子会への参加など、当時の武士の経済的困難と助け合いの様子がわかります。「御取扱銀」「会所銀」「聖堂銀」といった経済的支援制度の存在も示唆されています。また、井口佐太右衛門に関する事件についても記述があり、当時の武家女性の財産権に関する示唆を含んでいます。これらの記述は、当時の武士の家族生活、教育、経済状況、そして社会保障制度といった多様な側面を垣間見せてくれる貴重な資料となっています。特に、家族の日常や経済状況、近隣との関係といった記述は、当時の社会構造を理解する上で非常に重要な意味を持っています。
4. 加賀藩における社会変動と時代認識 身分制度と兵制改革
この節では、文久2年の加賀藩における社会変動、特に身分制度と兵制改革への対応について考察されています。加賀藩における身分制度の実態と、与力からの平士への昇進例(坂井権五郎、板坂二衛門など)が詳細に説明されています。これは、当時の社会流動性や能力主義的な側面を示唆しています。さらに、文久2年9月27日の西洋兵器採用という軍制改革が取り上げられ、その背景や、伝統的な兵法との併存という時代認識の遅れが批判的に論じられています。これは、単なる西洋式兵器の導入だけでなく、近代的な兵法や組織改革が必要であったという指摘につながっています。この節は、加賀藩における社会変動、特に身分制度と兵制改革への対応を分析し、当時の時代認識の限界を浮き彫りにしています。また、司馬遼太郎の「競争的原理の作動」という記述を引き合いに出し、日本の歴史的特殊性を示唆する考察も含まれています。これらの記述は、加賀藩の社会構造や改革への取り組み、そして時代認識の課題を理解する上で不可欠な情報です。
II.加賀藩における身分制度と社会移動
加賀藩の身分制度は厳格なものでしたが、起止録からは、与力などの下級武士が、能力と実績によって平士に昇進する例が多数見られたことが分かります。例えば、坂井権五郎や板坂二衛門といった人物の経歴は、当時の社会移動の可能性を示す好例です。彼らは、公事場勤務を通じて能力を認められ、家禄の増加や身分向上を果たしています。このことは、幕末期の加賀藩において、必ずしも厳格な身分制度が固定的なものではなく、一定の流動性があったことを示唆しています。 この社会移動の側面は、武士の生活や経済状況を理解する上で重要な要素となります。
1. 加賀藩における身分制度の実際と流動性
この文書では、一見厳格に見える加賀藩の身分制度が、実際には一定の流動性を有していたことを示唆する記述が複数見られます。特に、下級武士である与力層からの平士への昇進事例が注目されています。文書では、坂井権五郎と板坂二衛門の経歴が詳細に紹介されています。坂井権五郎は、公事場での長年の勤務と記録整理の功績により、段階的に家禄を増やし、最終的に本組与力から組外に抜擢されています。板坂二衛門も同様に、公事場での働きぶりによって家禄を増やし、平士に昇格しています。これらの事例は、加賀藩において、能力と実績が身分向上に繋がる可能性を示しており、単なる世襲制ではなく、一定の能力主義的な側面があったことを示唆しています。さらに、文中では、早川数之助、音地左盛、坂井伊太、早崎清右衛門といった、同様の経歴を持つ人物が他にも存在したことが指摘されており、与力層からの平士への昇進が、加賀藩においては決して稀なケースではなかったことがわかります。これらの事例は、加賀藩の身分制度の流動性を示す重要な証拠であり、当時の社会構造を理解する上で重要な視点となります。
2. 与力層の特性と社会的地位
文書は、加賀藩における与力層の特性とその社会的地位について言及しています。一般的な武士層が数代に渡り地位や収入が固定されていた中で、与力層は「お目見え以上に取立てられる特典」があったとされています。この特典は、職務上の必要性に加え、与力層の人材確保に大きく貢献したと考えられます。その結果、与力層には有能な人材が集まり、藩政における実務を担う重要な役割を果たしていたと推測できます。この記述から、加賀藩の行政機構において、与力層が担っていた役割の重要性、そしてその地位の特殊性が浮き彫りになっています。また、七手組や人持組といった下級家臣からの抜擢登用も示唆されており、能力主義的な人材登用が行われていた可能性も示唆されています。これらの記述は、加賀藩の身分制度における与力層の特異性を明確にし、その役割と社会的地位の複雑さを示す重要な情報となっています。
3. 具体的な事例分析 坂井権五郎と板坂二衛門
この節では、坂井権五郎と板坂二衛門の経歴が、加賀藩における身分制度と社会移動の具体的な例として詳細に分析されています。坂井権五郎は、公事場での長年の勤務経験と功績を認められ、家禄の増加と身分の向上を果たしました。彼の経歴は、公事場での定役という地道な仕事から、弓矢奉行への昇進というキャリアパスを示しており、能力と努力によって社会的地位を向上させることが可能であったことを示しています。一方、板坂二衛門は、養子縁組から出発しながらも、公事場での活躍により家禄を増やし、最終的に平士に昇格しました。彼の経歴は、必ずしも家柄や出身が社会的地位を決定するものではなく、努力次第で身分向上を達成できる可能性を示唆しています。これらの具体的な事例を通して、加賀藩における身分制度の流動性と、能力主義的な側面が強調されています。これらの記述は、抽象的な議論ではなく、具体的な人物像とキャリアパスを示すことで、加賀藩の身分制度の理解を深める上で極めて重要な役割を担っています。
III.疫病流行と社会不安
文久2年の加賀藩では、コレラが流行し、多くの死者が出ました。起止録には、コレラによる死亡や、麻疹、天然痘などの伝染病の流行が記録されており、当時の医療体制や人々の生活への影響が分かります。また、コレラ流行に伴い、デマが飛び交ったり、社会不安が高まった様子も記されています。これらの記録は、幕末期の衛生状況や、人々の疫病に対する恐怖、そして社会不安の度合いを知る上で貴重な情報となります。特に、コレラや麻疹といった疫病の流行が、加賀藩の社会に与えた影響を分析する際に重要な要素となります。
1. コレラの大流行と社会への影響
文久2年8月下旬から金沢でコレラが大流行したことが、起止録に記録されています。コレラの症状や、その感染拡大によって生じた社会不安の様子が克明に記されています。コレラは、軽症の場合は下痢が数日で治まるものの、重症の場合は激しい下痢と嘔吐を繰り返し、脱水症状、血行障害、そして死亡に至るケースもあったと記述されています。 起止録では、コレラによる死者が増加していく様子が淡々と記録されており、当時の人々の恐怖と無力感が伝わってきます。閏8月9日から11日にかけて行われた「送り出し」祭礼についても触れられていますが、祭礼の様子よりも、コレラで次々と人が亡くなっていく様子が中心的に描かれています。 中村豫卿自身も8月28日に「痂痢」を患っており、コレラの症状と一致する記述が見られます。この記述から、コレラが当時の人々の生活に深刻な影響を与えていたことがわかります。また、コレラの流行に伴い、下級役人の間でもデマが流布したことが記されており、伝染病への恐怖と社会不安の高まりがうかがえます。コレラ流行は、当時の医療体制の限界と社会の脆弱さを浮き彫りにする重要な出来事として記録されています。
2. その他の伝染病と医療事情
コレラ以外にも、麻疹や痘瘡(天然痘)の流行が起止録に記されています。特に、中村豫卿の次女が10月3日に病死したことが記されており、その死の直前には、複数の医師が往診に訪れている様子がわかります。麻疹については、中村豫卿の長女と豫卿自身も発症するも、何らかの予防接種と考えられる「豆口」によって、重症化を免れた可能性が示唆されています。痘瘡については、豫卿の嫡子・民作が発症し、上田玄伯ら複数の医師による治療を受けたことが記述されています。 これらの記述から、当時の医療事情が必ずしも十分ではなかったこと、そして伝染病が多くの人の命を奪っていた厳しい現実が読み取れます。「行灯に赤紙張り等」という記述は、当時の痘瘡治療における一般的な対処法を示しており、当時の医療状況の一端を示す貴重な資料となっています。 また、西坂成庵先生の麻疹による死や、その弔いの様子も描かれており、当時の風習や人々の死生観についても理解を深めることができます。これらの記述を通して、当時の疫病流行の状況と、限られた医療資源の中で人々がどのように対応していたのかがわかります。
IV.家族の日常と経済状況
中村豫卿の起止録には、彼の家族の日常の様子も記録されています。子供たちの教育や病気、妻の内職、そして家族間の交流などが記されています。経済的には、借金を抱えながらも生活を維持していた様子が伺えます。頼母子会への参加や、会所銀、聖堂銀といった藩の制度を利用していたことも記されています。これらの記録は、幕末期の武士の家庭生活、経済状況、そして藩の社会保障制度などを理解する上で貴重な資料となっています。
1. 家族構成と日常 3人の子供と厳しい生活
中村豫卿は文久2年当時40歳で、妻と3人の子供(長男・民作、長女・友、次女・覚)と暮らしていました。両親は既に亡くなっており、現代の核家族と同様の構成です。しかし、その生活は決して楽なものではありませんでした。祖父母の援助がなく、幼い3人の子供を抱えながら、妻は内職に励んでいたと推測されます。この厳しい生活状況は、次女・覚の病死の記述からも推察できます。次女の病状悪化から死に至るまでの様子が詳細に記されており、妻の苦労や、姉(妹?)である大島稼亭夫人の協力なども伺えます。妻は慶応2年(1866年)に病死しており、文久2年は、豫卿一家にとって特に厳しい時期であったことがうかがえます。子供たちの病気や死亡といった出来事が、日記に克明に記録されており、当時の武士家庭の現実を深く理解する上で重要な資料となります。また、妻の死後も、子供たちと観音院へ参詣する記述などから、豫卿の信仰心や家族への愛情も見て取れます。
2. 子育てと教育 長男民作の教育への関与
起止録には、中村豫卿が長男・民作の教育に熱心に関わっていた様子が記されています。民作は数え年で10歳。豫卿は、民作に素読や温習をさせ、閏8月には「蒙求」の復習をさせています。また、謡の初歩指導も行っていたことが示されています。9月9日の重陽の節句には、丹羽椎渓を招き、民作を連れて清水山へ出かけた様子も記されています。これらの記述から、豫卿が長男の教育に積極的に関与し、教養を身につかせようとしていたことがわかります。教育内容は、漢文の素読や古典の学習、そして謡といった教養に重点が置かれており、当時の武士階級の教育観の一端を垣間見ることができます。 これらの記述は、当時の武士階級における教育方法や、父子の関係、そして教育に対する価値観などを理解する上で重要な情報となります。特に、「せがれ」という呼びかけや、教育内容の詳細な記述は、当時の親子の日常を詳細に示す貴重な資料と言えるでしょう。
3. 経済状況と社会との繋がり 借金 内職 頼母子会
起止録からは、中村豫卿一家が経済的に厳しい状況にあったことがわかります。文書には、「御取扱銀」や「地廻会所銀」「聖堂銀」といった、金銭の貸与や返済に関する記述が複数見られます。これらの記述から、豫卿一家が借金に頼りながら生活を維持していた可能性が示唆されます。「地廻」という仕事に関連して金銭を借りていたことも示唆されており、当時の武士の経済的な苦労が読み取れます。また、妻による内職の存在も示唆されており、家計を支えるための努力が伺えます。さらに、頼母子会への参加についても記述があり、これは、互いに助け合うことで生活の安定を図ろうとしていた当時の社会構造の一端を示すものです。同姓会への参加なども記されており、近隣住民や同僚との助け合いによって生活を維持していたことがわかります。これらの記述は、当時の武士階級の経済的実態や、社会的な繋がり、そして互助的な制度などを理解する上で貴重な資料となります。特に、頼母子会といった互助組織の活動は、当時の社会構造を理解する上で重要な要素となります。
4. 隣近所との関係と事件への関与 井口佐太右衛門の件
起止録には、近隣住民との交流や、事件への関与の様子も記録されています。特に、井口佐太右衛門に関する事件は、豫卿の日常に大きな影響を与えていたことがわかります。この事件に関連して、豫卿は井口家の家財の処分を手伝ったり、板坂二郎大夫に「銀子」を送ったり、示談交渉を行ったりするなど、積極的に関わっています。この事件を通して、当時の人間関係の複雑さと、事件解決における周囲の関与の様子がわかります。「お脇ま」と呼ばれる女性とその財産権をめぐる問題も関わっており、江戸時代の武家女性の自立した財産権に関する記述は、磯田道史の『武士の家計簿』といった研究とも関連づけることができます。 また、斉藤判太夫一家との頻繁な交流についても記されており、家族ぐるみの親密な関係が伺えます。これらの記述は、当時の社会における隣人関係や、事件解決におけるコミュニティの役割、そして人々の繋がりについて理解を深める上で重要な情報となります。
文書参照
- 金沢大学教育学部紀要教育科学編(第57号)
