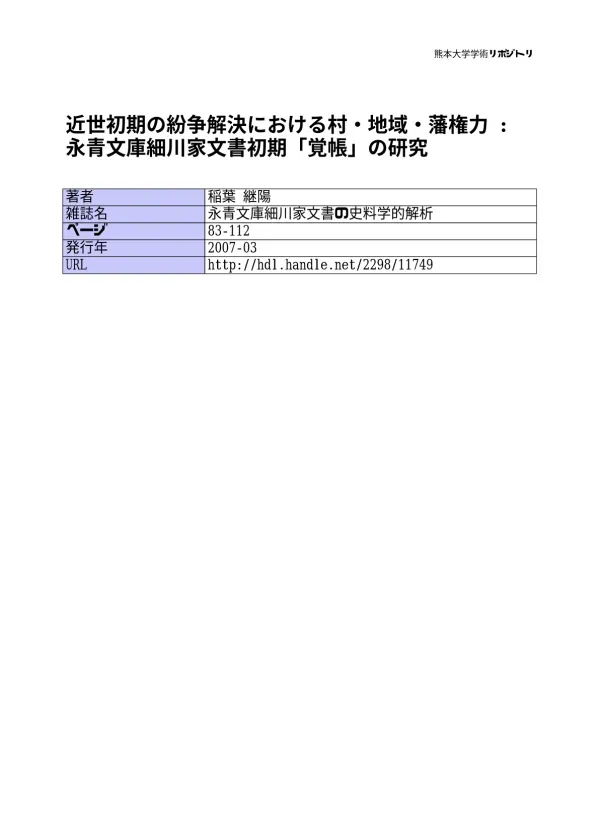
近世紛争解決:細川家文書覚帳から見る村と藩権力
文書情報
| 著者 | 稲葉 継陽 |
| 学校 | 熊本大学 |
| 専攻 | 歴史学、日本史 |
| 文書タイプ | 研究論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.55 MB |
概要
I.中世後期から近世初期の村共同体と山相論
本研究は、中世後期から近世初期の【伝統日本社会】における【村共同体】の役割と、領地境界を巡る【山相論】に焦点を当てている。当時の【村共同体】は、年貢・公事を集団で請負い、財政・訴訟能力を持ち、共有財産を所有する法人格のような存在であった。【山相論】、特に山野用益や灌漑用水に関する紛争は、村共同体の自立性と近隣村との交渉、調停による自律的な紛争解決プロセスを特徴づけていた。熊本藩領久住と岡藩領朽網郷の【藩境相論】を事例に、この社会構造を分析する。
1. 近世日本社会における村共同体の性格
この節では、近世日本社会を支えた村共同体の特徴が詳細に説明されています。近年の研究成果を踏まえ、村共同体は年貢・公事を領主に対して集団で請け負う集団として描かれ、独自の財政機能、訴訟能力を有し、近隣村との協約を結び、共有財産を所有し、経済活動の主体として機能していたことが強調されています。 16世紀までに広く成立し、近世社会を通じて社会の基礎団体として存続したと記述されています。この法人格のような村共同体の存在は、後の山相論などの紛争解決において重要な役割を果たしたことを示唆しています。 また、山野用益や灌漑用水をめぐる紛争が、村共同体を常に悩ませる問題であったことも指摘され、これらの紛争の経過や解決方法の中に、村共同体とそれを取り巻く社会や権力の歴史的特質が反映されているとされています。 研究者自身も、中世後期から近世初期にかけての実力行使を伴う山野・用水相論を分析し、村共同体間の交渉や近隣村の調停による自律的な紛争解決と秩序確立が可能であったことを確認し、強調している点が述べられています。これは、村共同体の内部的な結束力と外部との交渉能力の高さを示す重要な証拠となります。
2. 領域支配と村共同体の関係
本節では、伝統日本社会の形成期におけるもう一つの特徴として、村共同体を基礎とした領域支配の確立が取り上げられています。16世紀の戦国大名領国制から近世大名の領域統治へと発展していく過程において、村共同体がその基盤として機能していた点が強調されています。領域統治を実現する権力体の形成条件としては、古代からの国制(国郡制)、在地領主制の発展、国人一揆の変質ないし構造化といった様々な要因が検討されています。 この領域支配の確立は、村共同体の地理的領域の維持と、その領域内における経済活動や社会秩序の維持に深く関わっていたと考えられます。 また、この領域支配の枠組みの中で発生する山相論のような紛争は、村共同体の自立性と藩の権力との複雑な関係性を理解する上で重要な手がかりとなります。 文書資料として、熊本藩の地域支配担当部局である郡方が作成した「覚帳」が紹介され、この資料が、当該社会の歴史的特質と藩当局の文書管理・活用の実態を明らかにする上で有効であるとされています。特に、熊本藩領久住手永と岡藩領朽網郷の間で発生した山相論の分析に、「覚帳」が重要な役割を果たすことが示唆されています。
3. 手永制度と地域行政機構
この節では、郡と村の中間に位置する地域行政機構である「手永」制度について説明されています。山本郡を除き、各郡には2~6の手永が設置され、その規模は大きく異なっていました。各手永には惣庄屋が置かれ、多くは在地の有力者が任命されていました。手永会所は年貢収納や地域行政の中核として機能し、手永内には村庄屋・村役人が存在し、村は手永内における年貢・諸役の請負主体として位置づけられていました。この手永制度は、村共同体と藩の行政機構との関係、そして領地支配の実際を理解する上で重要な要素となります。 惣庄屋の存在は、村共同体内部の意思決定や外部との交渉において重要な役割を果たしたことを示しています。また、手永会所の機能は、藩の支配体制と村共同体の経済活動との結びつきを示すものであり、村共同体が単なる被支配者ではなく、藩の行政機構と密接に連携しながら機能していたことを示唆しています。 この手永制度は、後の山相論の解決過程においても重要な役割を果たしており、惣庄屋や村役人が紛争の解決に積極的に関わっていたことが分かります。
II.熊本藩領久住と岡藩領朽網郷における山相論の事例分析
17世紀の熊本藩領久住町・飛森村と岡藩領朽網郷石原村の間で発生した【山相論】を分析する。この相論は、薪採取を巡る【実力行使】(百姓による集団的な山道具の奪取)から始まり、領地境界の確定、そして【正保国絵図】の作成にまで影響を及ぼした。紛争の第一報は、久住郡代役所の【御郡奉行小林次兵衛】への報告から始まり、惣庄屋や村役人の役割が重要であることが分かる。この事例を通して、【村共同体】の領域秩序維持の仕組みと、藩当局の関与のあり方が明らかにされる。
1. 久住と朽網郷における山相論の発端 秋日山事件
この節では、熊本藩領久住手永と岡藩領朽網郷の間で発生した山相論の具体的な事例として、秋日山における事件が詳細に分析されています。久住町の百姓4名が秋日山で薪を採取中に、竹田領石原村の百姓らと衝突し、鉈や斧を奪われるという事件が発生しました。この事件の第一報は、久住郡代役所の御郡奉行小林次兵衛に伝えられ、その報告書が「覚帳A」として残されています。事件報告者として「筑紫庄内」という人物が登場し、彼は久住手永惣庄屋の弟であることが示唆されています。 事件の特徴として、百姓が集団で実力行使を行い、山道具を奪取するという点が挙げられています。また、事件発生から御郡奉行への報告まで2日間のタイムラグがあり、その間に惣庄屋らが百姓の報復感情の沈静化と竹田領側との交渉を試みていたと推測されています。 この事件は、山相論における実力行使と、それを取り巻く村共同体や地域有力者の対応を示す重要な事例となっています。特に、御郡奉行が事件の初動対応に直接関わっていなかった点は、村共同体による自律的な紛争解決の試みが優先されていたことを示唆しています。 更に、奪われた山道具を取り返すべく、久住側の百姓らが秋日山に再び赴こうとした事実も示されています。これは、17世紀初頭の近江国における山論における社会的ルール(山道具を取り返せなければ、その領域に対する相手方の支配を認める)と関連付けて考察されています。
2. 正保国絵図作成と久住 朽網郷間の境界問題
この節では、正保国絵図の作成に関連した久住と朽網郷間の境界問題が取り上げられています。正保国絵図作成の指令を受けた熊本藩は、久住手永惣庄屋に、竹田領・玖珠郡松平領の庄屋と共に境界を現場確認し報告するよう命じました。久住山は肥後領と竹田領、直入郡と玖珠郡の境界に位置する重要な地点でした。 久住村庄屋と山ノロは、岡藩領朽網郷有氏村の千石庄屋権左衛門に境界確認を依頼しますが、権左衛門は当初これを拒否します。しかし、再三の要請を受け、百姓を連れて現場に現れ、古老の証言により境界を示す地名9箇所を提示しました。久住側は、同様の方法で境界を主張しますが、「同心」(合意)には至りませんでした。 この境界確認の失敗は、正保国絵図作成において、久住山周辺の境界線が曖昧なまま残されたことを意味します。これは、当時の領域秩序が、村共同体の合意に基づいて決定されるべきものであったことを示唆しています。 さらに、三俣山が肥後領・竹田領、竹田領・松平領の境目として挙げられ、法花院も係争地であったとされ、これらの場所についても境界画定は達成されなかったことが述べられています。このことは、豊後国絵図作成作業に影響を与えた重要な事実となります。
3. 貞享相論における紛争解決への試みと限界
この節では、貞享年間における秋日山を中心とした山相論の解決過程が分析されています。熊本藩は、藩の役人や御郡奉行を直接交渉に当たらせるのではなく、近隣の肥後藩領野津原手永の惣庄屋野津原次兵衛に交渉を委任しました。次兵衛は、岡藩領今市町の千石庄屋今市伝左衛門と交渉しますが、伝左衛門は秋日山が竹田領であるとの認識を示し、有氏組の百姓らの意見を聴取した上で改めて協議することを約束しました。 熊本藩は、伝左衛門が「論所」を否定し、排他的用益権を主張した場合に備え、想定問答集を用意していました。この想定問答集は、過去の文書や正保国絵図の鬮引きの裏事情を含めた情報を提示するものでした。 しかし、7月5日に行われた伝左衛門との最終交渉は、熊本藩の予想を大きく超えるものでした。伝左衛門は、秋日山が「論地」であるという熊本側の主張を初めて耳にし、「不審千万」であると述べました。これは、熊本藩の想定を超えた事態であり、近隣惣庄屋を介した交渉による紛争解決は失敗に終わったことを示しています。 この失敗は、藩当局によるトップダウンの紛争解決策の限界を示す重要な事例となっています。
4. 稲葉右京亮の仲介による紛争の終結
この節では、臼杵藩主稲葉右京亮の仲介による山相論の解決が記述されています。熊本藩は、秋日山を「論所」として維持しない限り、紛争の継続と公儀レベルでの問題化は避けられないと判断し、元禄元年に稲葉右京亮に仲介を依頼しました。 熊本藩家老は、臼杵城で稲葉右京亮に口上を述べ、秋日山は古くからの「論所」であり、双方とも用益を停止すべきであると主張しました。 稲葉右京亮の見解は、紛争解決に何らかの成案はなく、双方の百姓による境界画定は困難であると判断し、秋日山を含む3ヶ所の係争地を「論所」として双方の用益を停止するのが妥当であるというものでした。 竹田領からの侵入があった場合の報告義務、そして熊本藩側も「論所」への介入をしないことを約束しました。 この仲介によって、秋日山は「論所」として双方とも手出しをしない地となり、紛争は終結に向かいました。この解決策は、藩主レベルの介入によって、現実の領地境界の曖昧さを認めた上で、紛争を事実上凍結させるという形をとっています。
III.正保国絵図作成と領域秩序
【正保国絵図】の作成過程において、久住と朽網郷の村々による境界確認が行われた。しかし、両村の【惣庄屋】間の交渉は難航し、【同心】(合意)に至らなかった。特に、三俣山は肥後、竹田、松平の三家領の境界に位置し、その帰属が争点となり、最終的に【鬮引き】によって形式的に決定された。この事例は、【国絵図】が現実の領域秩序を完全に反映せず、形式的な統一性を優先する側面を示していることを示唆している。
1. 正保国絵図作成と領地境界の確認
この節では、将軍家光の命による正保国絵図の作成過程において、久住山周辺の領地境界確認がどのように行われたかが詳細に説明されています。豊後国のような小藩が分立する地域では、各藩が分領内の絵図を作成し、それらを統合して一国の絵図を完成させる必要がありました。そのため、熊本藩は久住手永の惣庄屋に、竹田領および玖珠郡松平領の庄屋と共に境界を現地で確認し、報告するよう指示を出しました。久住山は肥後領と竹田領、直入郡と玖珠郡の境界に位置しており、その領域秩序の確認は絵図作成に不可欠でした。 久住村庄屋と山ノロは、岡藩領朽網郷有氏村の千石庄屋権左衛門に境界確認を依頼しますが、権左衛門は当初、現地での確認を拒否し、代わりに古老の証言による境界を示す地名9箇所を提示しました。 この過程は、正保国絵図作成における、現地住民による境界確認の試みと、その困難さを浮き彫りにしています。 特に、権左衛門による現地確認の拒否は、当時の境界認識における曖昧さと、村共同体間の合意形成の難しさを示唆する重要な出来事となっています。 この出来事は、正保国絵図が、必ずしも現実の領域秩序を正確に反映しているわけではないことを示す重要な事例として扱われています。
2. 三俣山と法花院周辺の境界問題
この節では、三俣山と法花院周辺の境界問題が正保国絵図作成とどのように関わっていたかが論じられています。三俣山は、肥後領・竹田領、竹田領・松平領の境目に位置し、法花院はその麓にありました。これらの地域は、古くから係争地であり、正保国絵図作成時においても、現地住民による境界画定は達成されませんでした。 三家領境目において、現地の村役人や百姓は境界画定を成し遂げられず、「論地」として国絵図に表記せざるを得なかった点が強調されています。これは、当時の国絵図作成において、現実の領域秩序よりも形式的な統一性が優先された可能性を示唆しています。 幕府側の国絵図作成責任者である大目付井上筑後守は、三俣山の麓口をいずれかの領分に向けて描くよう三家の担当役人に指示しました。担当役人は、やむなく鬮引きによって麓の方向を決定するという、極めて形式的な方法をとりました。 この鬮引きによる解決は、現実の領域秩序を反映したものではなく、形式的な解決策に過ぎなかったことを示しており、公儀による国土領有の性格と、現実の地域社会における領域秩序との乖離を浮き彫りにする事例となっています。
IV.貞享相論と紛争解決プロセス
貞享年間の相論では、熊本藩は【近隣の惣庄屋】(野津原手永の野津原次兵衛)を介して岡藩領との交渉を試みた。しかし、交渉は失敗に終わり、最終的には【臼杵藩主稲葉右京亮】の仲介によって、紛争地は「【論所】」(相互不可侵領域)として扱われることで解決を見た。この過程は、紛争解決における【村共同体】、近隣惣庄屋、藩当局、そして隣接藩の重層的な関与を示している。
1. 近隣惣庄屋を介した交渉の試み
貞享相論の解決策として、熊本藩はまず、当事者である久住手永と岡藩領の直接交渉を避け、近隣の肥後藩領野津原手永の惣庄屋、野津原次兵衛に交渉を委任しました。 野津原次兵衛は、岡藩領の宿場町である今市町の千石庄屋、今市伝左衛門に接触し、秋日山と先行していた瀧水村・下瀧水村間の国境相論について交渉を始めました。 熊本藩は、正保国絵図作成時や過去の相論に関する文書を次兵衛に渡し、交渉の指針としました。 秋日山については、古くから「論所」であり、双方とも薪等の採取を控えるべきであるという熊本側の主張が伝えられました。しかし、竹田領側の認識と食い違いがあり、竹田側が秋日山への排他的用益権を主張する可能性も考慮されていました。 この交渉は、藩当局が直接介入するのではなく、近隣惣庄屋を仲介役として紛争解決を試みた点に特徴があります。これは、当時の社会構造において、近隣地域間のネットワークが紛争解決に重要な役割を果たしていたことを示唆しています。 しかし、この近隣惣庄屋を介した交渉は、後述するように、最終的には失敗に終わります。
2. 交渉の失敗と 論地 としての秋日山の維持
今市伝左衛門は、秋日山が「論地」であるという熊本側の主張に驚き、竹田領の山役人が常駐していることから、秋日山は竹田領だと認識していると回答しました。 伝左衛門は、有氏組の百姓や村役人の意見を聴取した上で再度協議することを約束しましたが、この時点で熊本藩による近隣惣庄屋を介した交渉は実質的に失敗に終わりました。 熊本藩は、伝左衛門が「論所」であることを否定し、排他的用益権を主張してきた場合に備え、5箇条に及ぶ想定問答集を用意していました。この問答集には、正保国絵図の鬮引きの裏事情も含めた情報が含まれており、証拠提示を求められた場合にも対応できるよう準備されていました。 しかし、この準備にもかかわらず、交渉は決裂し、熊本藩は秋日山を「論所」として維持せざるを得ませんでした。 これは、藩当局による近隣惣庄屋を介した紛争解決策が、必ずしも有効とは限らないことを示しており、藩の権力と地域社会の力のバランス、そして紛争解決における限界を示す事例となっています。 この状況下で、熊本藩は新たな紛争解決策として、臼杵藩主稲葉右京亮の仲介を仰ぐことになります。
3. 臼杵藩主稲葉右京亮による仲介と紛争の終結
熊本藩は、秋日山を「論所」として維持しない限り、山相論の継続と公儀レベルでの問題化は避けられないと判断し、臼杵藩主稲葉右京亮に仲介を依頼しました。 元禄元年に、熊本藩の家老は臼杵城で稲葉右京亮に口上を述べ、秋日山を含む3ヶ所の係争地の絵図を提示しました。 熊本藩は、秋日山を古くからの「論所」とし、双方とも用益を停止すべきだと主張しました。 稲葉右京亮は、双方の百姓による境界画定が困難であり、仮に画定できたとしても将来、紛争が再発する可能性があると判断し、3ヶ所の係争地を全て「論所」として双方の山用益を停止するのが妥当であると結論付けました。 さらに、竹田領からの「論所」への侵入があった場合には、稲葉右京亮自身に報告するよう指示が出されました。 この稲葉右京亮の仲介によって、秋日山は「論所」として双方とも手出しをしない地となり、紛争は事実上終結しました。 この事例は、藩境を越えた山相論の解決において、近隣藩主の仲介が重要な役割を果たしたことを示しています。また、この解決策は、現実の領地境界の曖昧さを認めた上で、紛争を事実上凍結させるという、当時の紛争解決における特有の方法を示しています。
V.熊本藩の文書管理と覚帳
熊本藩の【郡方】は、過去の【山相論】に関する文書を「【覚帳】」として体系的に管理・活用していた。これは、紛争発生時の情報収集、解決策の立案、そして今後の対応に役立てられた。【覚帳】は、藩の文書管理システムと、藩当局による紛争処理の実態を明らかにする重要な史料である。宝暦改革以降、【覚帳】の内容や作成方法に変化が見られる。
1. 郡方の文書管理と紛争解決への活用
この節では、熊本藩の地域支配担当部局である郡方の文書管理と、山相論などの紛争解決への文書活用の実態が分析されています。郡方は、役所に蓄積された過去の文書(「古キ書付共」)を、紛争発生時に証拠として活用していました。 これらの文書は、惣庄屋や村役人から提出されたものや、郡方自身で作成したもので、案件ごとに検索可能なように整理・保管されていたと考えられます。紛争が再燃した場合には、これらの文書の内容を総括し、紛争解決に役立てていました。 紛争解決に一定の成果を挙げると、その経緯と関連文書を写した記録(「覚帳」)を作成し、保管することで、将来的な紛争発生への備えとしていました。 本研究で用いられた「覚帳」も、このような郡方の文書管理システムによって作成・保存されたものです。 この「覚帳」の分析を通じて、熊本藩の文書管理システムと、藩当局による紛争処理の実態が明らかにされています。 郡方は、単に情報を収集し、決定事項を実行するだけでなく、歴史的な経緯や証拠となる文書を積極的に活用することで、紛争解決に臨んでいたことが分かります。
2. 覚帳 の内容と変化
本節では、「覚帳」の内容とその変化について考察されています。 分析対象となった初期の「覚帳」は、個別案件に関する情報を集成したものでした。しかし、宝暦改革期(18世紀中葉)以降、手永制度の改革に伴い、「覚帳」の内容と作成方法に変化が生じました。 宝暦改革期以降は、個別案件に関する情報に加え、手永から郡方に上申された所務や地域開発に関する大量の案件についての情報を継続的に記録した「覚帳」が作成されるようになりました。 この変化は、公共機能の肥大化と、地域社会と藩当局との間の機能分担、あるいは地域社会から藩当局への委託状況の変化を反映していると考えられます。 幕末まで継続して作成されたこれらの「覚帳」は、地域社会と藩当局との関係、そして地域社会における行政機能の変容を理解する上で極めて重要な歴史資料となります。 「覚帳」の変化は、単なる文書管理システムの変化ではなく、社会構造の変化を反映していることを示しています。
VI.結論 村共同体の自律性と国制 国絵図
本研究は、17世紀の【伝統日本社会】において、【村共同体】が独自の領域秩序を維持し、藩当局との間で複雑な相互作用を展開していたことを明らかにした。【山相論】の解決過程は、【村共同体】の自律性と藩によるトップダウンの政策の両方が複雑に絡み合ったものであった。【国絵図】は、形式的な領地境界を示す一方で、現実の領域秩序と乖離した側面を持つことも示された。
1. 情報伝達と意思決定における郡方と惣庄屋の役割
この節では、熊本藩における山相論の解決過程において、郡方と惣庄屋の役割がどのように連携していたかが論じられています。 藩当局(郡方役人、奉行衆、家老衆)が竹田領境に関する情報を把握できたのは、すべて在地の惣庄屋が現地御郡奉行に申告した情報に基づいていました。 正保国絵図作成に必要な境界情報、相論発生時の状況、竹田領の状況、過去の相論で奪取した山道具の所在、相論の歴史的経緯といった情報は、すべて惣庄屋と村役人が口上書として御郡奉行に報告し、そこから熊本藩の郡方へと伝達されました。 家老衆の寄合はこれらの情報を基に方針を決定し、その決定は御郡奉行を経由して惣庄屋に伝えられ、実行されました。 当事者百姓の籠への拘禁・解放も惣庄屋の責任で行われていました。 つまり、家老衆が最終的な決定権を持っていたとしても、現地での情報収集、紛争の沈静化、竹田領との交渉といった重要な役割は、惣庄屋と村役人が担っていたことがわかります。 村レベルや手永レベルでの百姓の集会が頻繁に行われ、近隣惣庄屋間の連絡も緊密に行われていたと推測されます。これは、村が藩の単なる下請け機関ではなかったことを示しています。なぜなら、相論の解決は久住手永の村々の百姓自身も望んでいたことだからです。
2. 覚帳 の機能と藩政文書の分析
この節では、熊本藩の文書管理システムと、「覚帳」の役割が分析されています。 藩当局は、情報提供と決定事項の執行を現地に任せていたわけではなく、郡方の役人が役所に蓄積された「古キ書付共」の中から、相論に関する証拠文書を探し出し、家老衆の寄合に提供していました。 郡方は、惣庄屋や村役人から提出された文書や、自ら作成した文書を案件ごとに整理・保管し、紛争が再燃した場合にはそれらを活用していました。 紛争解決に成果を挙げると、その経緯と関係文書を写した「覚帳」を作成・保管し、将来の活用に備えていました。 本研究で用いられた「覚帳」は、このシステムによって作成された重要な史料であり、その分析を通じて、藩の文書管理システムと紛争処理の実態が明らかになっています。 宝暦改革期(18世紀中葉)以降は、個別案件の情報に加え、地域開発に関する情報を継続的に記録した「覚帳」も作成されるようになり、幕末まで継続しました。これは、肥大化する公共機能と地域社会と藩当局との関係の変化を示す重要な資料です。
