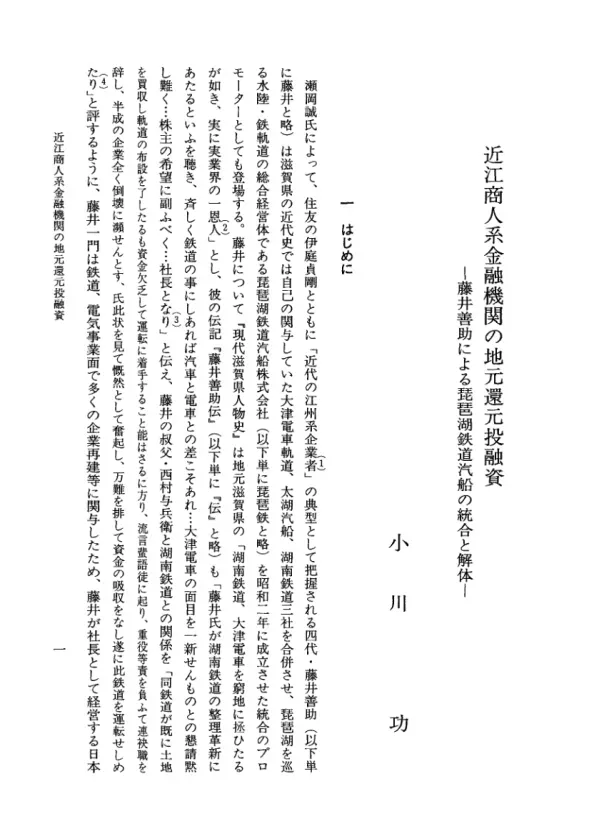
近江商人系金融機関と琵琶鉄:地元還元投融資
文書情報
| 著者 | 川功 |
| 学校 | 不明 |
| 専攻 | 経済史、鉄道史 |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 5.05 MB |
概要
I.藤井善助と湖南鉄道の再建
藤井善助氏は、資金難に陥り経営危機にあった湖南鉄道の再建に大きく貢献しました。地元・滋賀県神崎郡五個荘村出身の実業家である藤井氏は、社長に就任し、会社の整理改革を行い、鉄道の運転開始を実現させました。この成功は、近江商人の資金力や、西村与兵衛氏などの地元有力者との連携によるところも大きいです。湖南鉄道は、明治45年設立、大正2年全線開業の軽便鉄道で、八日市と近江八幡を結んでいました。当初は資金調達に苦しみ、工事の中断も経験しました。しかし、藤井氏のリーダーシップと地元金融機関の支援によって、見事に復活を遂げました。重要なキーワード:藤井善助、湖南鉄道、西村与兵衛、八日市、近江八幡、近江商人、再建
1. 湖南鉄道の設立と初期の苦境
湖南鉄道は、地方交通機関の発達を企図した西村与兵衛、大阪戸田猶七などの豪商らによって設立されました。しかし、設立当初から資金不足や工事の遅延に悩まされ、「困難鉄道」と揶揄されるほどでした。『京都日出新聞』も、工事の遅延や風評被害に触れています。 明治45年4月の創立後、大正元年9月に着工し、大正2年12月に全線開業しましたが、この過程では資金調達に大きな困難を抱えていました。 大正2年9月には、改軌費用を借入しようとしたものの、経済界の不振により借入が困難となり、一時工事は中止せざるを得ませんでした。 この資金難の中で、湖南鉄道沿線の呉服商である西村黒田衛が、個人借入という形で資金援助を行っています。これは、地元金融機関からの借入ではなく、個人借入であることから、湖南鉄道の信用度の低さを示唆していると考えられます。 西村与兵衛は、湖南鉄道の取締役として、総株数の40.2%を保有し、同社の主導権を握るほどの影響力を持っていました。 これらの困難を乗り越えるため、関係者は資金調達に奔走し、増資も断行するなど、様々な対策が取られました。
2. 藤井善助による再建と経営改革
湖南鉄道の経営難を打開すべく、神崎郡五個荘村出身の実業家である藤井善助氏が社長に就任しました。 『現代滋賀県人物史』は、藤井氏を地元滋賀県の湖南鉄道・大津電車を窮地から救った実業界の第一人者と評価しています。一方、藤井氏の自伝『藤井善助伝』では、湖南鉄道の整理革新を依頼され、社長に就任した経緯が述べられています。 藤井氏の叔父である西村与兵衛氏も、湖南鉄道の再建に大きく貢献した人物として挙げられています。 すでに土地を買収し軌道の布設を終えていたものの、資金不足により運転開始が不可能な状況を見て、藤井氏は資金調達に尽力し、鉄道の運転開始に成功させました。 この成功は、藤井氏の優れた経営手腕と、西村与兵衛氏を始めとする地元有力者や金融機関の協力を得た結果であると言えます。 藤井氏の経営方針は、ぼろ会社の立て直しに長けたものであり、『大津市三十年史』にも、藤井氏の経営方針によって湖南鉄道が順調になったと記されています。
3. 湖南鉄道の竣功とその後
大正2年12月21日、湖南鉄道の竣功式が八日市町の清楽館で開催されました。藤井善助氏が式辞を述べ、工事報告が行われた後、八日市芸舞妓の手踊りや花火、相撲などの余興が行われました。 しかしながら、竣工検査においては「到底その難輸塞を開始する事難」と判断されるほど、設備が完全ではなかったという記述もあります。 当初は25日の営業開始を予定していましたが、鉄道院の監査で多数の修理箇所が発見されたため、竣功式は21日に行われ、営業開始は翌日に延期されました。 竣工式後も、湖南鉄道は経営上の課題を抱え続けました。 自動車による併用運行も試みられましたが、初期の混乱や公道での運行管理の困難さから、開業6ヶ月で46円余の損失を計上するなど、大きな課題を抱えることとなりました。これらの事実から、湖南鉄道の再建は容易ではなかったことが分かります。
II.大津電車と京阪電気鉄道との合併
大津電車は、大津市と坂本を結ぶ軌道会社でしたが、経営難に陥り、最終的に京阪電気鉄道に合併されました。大津電車の設立には、大倉組や才賀藤吉氏などの有力企業・人物が関わっていました。当初は官営鉄道の路線借用にも成功しましたが、坂本線延伸計画は難航しました。京阪との合併は、藤井氏と京阪の太田光煕氏らの交渉によって実現しました。この合併は、滋賀県の政治状況や、江若鉄道などの周辺鉄道との関係も複雑に絡み合っていました。重要なキーワード:大津電車、京阪電気鉄道、大津市、坂本、大倉組、才賀藤吉、太田光煕、江若鉄道、合併
1. 大津電車の設立と初期の経営
大津電車は、大津市と石山間の免許線を有する地元住民によって設立されましたが、明治45年3月には免許線の失効が迫っていました。この状況下、東京の大倉組から今井多三郎氏が買収を持ちかけ、京阪、大倉組、そして個人投資家との三社均分経営でスタートしました。京阪の社長、太田光煕氏は、運賃収入増加への期待を語っています。しかし、『大津市三十年史』によると、建築費の高騰と乗客収入の少なさから経営難に陥ったとされています。大倉組は主要取引商社として資材供給を行い、才賀藤吉氏は創立以来実株主として関与していました。才賀電機商会は、大津電車だけでなく、京津電気軌道など周辺の電気軌道事業にも関与しており、電気機器の供給や工事請負など、多大な貢献を果たしていました。才賀藤吉氏自身も大津電車の社債を引き受けており、その深い関与が窺えます。技術者陣も才賀電機商会員が中心であったと記録に残っています。このように、大津電車の設立と初期経営には、大倉組や才賀藤吉氏など、複数の有力企業・個人が関わっていたことが分かります。
2. 官営鉄道線区の借入と坂本線延伸計画
大津電車は、大津市と膳所町間の軌道敷設にあたり、家屋の密集や住民の苦情から工費の高騰を懸念し、官営鉄道である東海道本線の支線(馬場~大津間)の借用を鉄道院に請願しました。この請願は、官営鉄道線区の借用という、官民混合経営の特殊な形態であり、山陽鉄道への宇品線貸し渡しなどの事例と比較されています。しかし、軌間の異なる鉄道の共用は例が少なく、認可は困難を極めました。大津の小関忠太郎氏が鉄道院への交渉に尽力し、最終的に認可を得ることができました。その後、大津電車は、大津と坂本を結ぶ路線の特許を取得し、延伸計画を進めました。しかし、坂本への延伸計画は、琵琶湖畔の名勝地の風致を損なう懸念から難航しました。滋賀県当局からも、水運による代替案が示唆されるなど、計画は容易に進みませんでした。
3. 京阪電気鉄道との合併とその後
大津電車は、昭和初期の経済不況下、経営難に陥り、最終的に京阪電気鉄道に合併されました。田中博氏は、京都電灯越前線とほぼ同時期に傍系事業として大津電車を経営していたと回想しています。合併は、京阪と大津電車のトップ、太田光煕氏と藤井善助氏の間で行われた交渉の結果、実現しました。この合併は、湖南鉄道の買戻し問題や、慰労金の交付を巡る激しい議論もあったとされています。合併後、大津電車は京阪単独の路線となりました。合併に関する決定は、琵琶鉄の従業員や重役にも驚きをもって受け止められ、合併後の従業員との争議や、無配当決定などの問題も発生しました。 この合併は、大津電車にとって、経営再建の道ではありましたが、同時に独立性を失う結果となりました。
III.琵琶湖鉄道汽船株式会社の成立と解体
大津電車と太湖汽船、湖南汽船などを合併して設立された琵琶湖鉄道汽船株式会社は、水陸両方の交通機関を統合した総合経営体でした。しかし、坂本線の不振や経営難が続き、最終的には京阪電気鉄道に合併されました。この合併においては、藪田勘兵衛氏などの地元有力者も関わっていました。合併過程では、従業員の解雇や争議、そして比叡山鉄道や湖南鉄道の扱いを巡る様々な問題が発生しました。重要なキーワード:琵琶湖鉄道汽船株式会社、太湖汽船、湖南汽船、京阪電気鉄道、藪田勘兵衛、比叡山鉄道、湖南鉄道、合併
1. 琵琶湖鉄道汽船株式会社の設立と統合
昭和2年、大津電車軌道、湖南汽船、太湖汽船などの統合により、琵琶湖鉄道汽船株式会社(琵琶鉄)が設立されました。この統合は、藤井善助氏を筆頭としたグループの主導によるもので、水陸両面の交通機関を統合した総合経営体を目指していました。 しかし、この統合は容易ではありませんでした。特に、湖南汽船と太湖汽船の間には、激しい競争と値下げ合戦が繰り広げられており、両社の合併は困難を極めました。昭和2年の株主総会では、小林卯三郎氏から湖南汽船の合併について質問が出されましたが、藤井氏は京阪電車が多数の株式を保有している現状を理由に、実現は困難であると回答しました。 一方、大正15年11月には太湖汽船が、収入の減少を打破するため、大津電車軌道との合併を決定しています。その後、琵琶鉄は、大津電車軌道、湖南汽船などを吸収合併し、資本金の増加手続きを完了しました。昭和3年2月には、藤井氏が会長、藪田勘兵衛氏が社長に就任しました。この統合によって、琵琶湖周辺の交通網の一体化が図られたものの、様々な課題を抱えたままスタートを切ったと言えるでしょう。
2. 経営難と京阪電気鉄道との合併交渉
琵琶湖鉄道汽船は、大津~坂本間の電鉄延伸による収入が予想を下回り、経営難に陥りました。琵琶湖汽船の社史は、坂本延長線の不振を経営危機の原因の一つとして挙げていますが、詳細は触れられていません。『滋賀県史』では、京阪電鉄の巧妙な戦略の前に敗北を喫したと記されています。 大正12年以降、無理な配当を続け、約70万円の赤字を抱えるなど経営は深刻な危機に瀕していました。 この状況下で、京阪電気鉄道との合併交渉が始まりました。交渉は、琵琶鉄の実権を握る藤井善助氏と京阪の太田光煕氏の間で、旧湖南鉄道の扱いや慰労金などをめぐり、激しい議論が交わされました。 合併に至る経緯は、藤井氏と太田氏による極秘交渉の結果であり、藪田勘兵衛氏ですら合併成立を知ったのは仮契約締結直前だったとされています。 合併の決定は、琵琶鉄の従業員に衝撃を与え、合併に伴う解雇問題や争議も発生しました。
3. 合併の成立と八日市鉄道の設立
昭和3年10月、琵琶鉄の臨時株主総会で京阪電気鉄道との合併が承認されました。合併契約には、旧湖南鉄道部分の他の会社への譲渡が含まれていました。 この決定を受けて、旧湖南鉄道を継承する新たな会社として、八日市鉄道株式会社の設立準備が進められました。発起人として藤井善助氏、藪田勘兵衛氏らが名を連ね、藤井氏の主導で準備が進められました。 当初、湖南鉄道は藤井善助氏らによって琵琶鉄から買戻され、その後宇治電(近江鉄道)に譲渡されるという見解もありましたが、近江鉄道側は合併に消極的で、電化費用などを理由に合併交渉は不成立に終わりました。 最終的に、藤井氏らによって資本金100万円の八日市鉄道が設立され、湖南鉄道は買収されました。 琵琶鉄の合併は、藤井善助氏の長期にわたる事業活動の集大成であり、同時に、その活動の終焉を示すものでした。 藤井氏は合併後、会長に就任しましたが、翌年引退しています。
IV.八日市鉄道の設立
琵琶湖鉄道汽船の合併後、藤井善助氏らは旧湖南鉄道の事業を引き継ぐために八日市鉄道を設立しました。これは、琵琶湖鉄道汽船が京阪に合併される際に、湖南鉄道の部分を分離させた結果です。八日市鉄道設立には、藤井氏、藪田氏、そして小梶九郎兵衛氏などが関わっていました。この設立は、地元の八日市の経済活性化にも貢献するものでした。しかし、近江鉄道との合併は実現しませんでした。重要なキーワード:八日市鉄道、藤井善助、藪田勘兵衛、小梶九郎兵衛、八日市、湖南鉄道、近江鉄道
1. 琵琶鉄設立と合併の経緯
琵琶湖鉄道汽船株式会社(琵琶鉄)は、大津電車軌道、湖南汽船、太湖汽船などの合併によって昭和2年に設立されました。この統合のプロモーターとして藤井善助氏が活躍しました。 しかし、合併に至る過程は容易ではありませんでした。特に、湖南汽船と太湖汽船の間には激しい競争があり、それまで水陸交通機関の統合は試みられてきましたが、成功には至っていませんでした。 昭和2年の湖南鉄道株主総会では、水陸交通機関の統一の必要性と、湖南汽船の合併について議論されました。 藤井善助氏は、京阪電車が湖南汽船の株式を多く保有しているため、合併は困難であると説明しました。 一方、太湖汽船は、収入の減少を理由に大津電車軌道との合併を決定し、琵琶鉄設立へとつながりました。 設立後、藤井善助氏は会長、藪田勘兵衛氏が社長に就任しました。 この合併は、交通機関の統合という大きな目標を達成したものの、同時に様々な問題の始まりでもありました。
2. 経営難と京阪への合併
琵琶鉄は、大津~坂本間の電鉄延伸による収入が予想を大きく下回り、経営難に陥りました。 この経営悪化は、琵琶鉄の社運を左右するほどの深刻なものでした。 その結果、京阪電気鉄道との合併という決断に至ります。 合併交渉は、藤井善助氏と京阪の太田光煕氏との間で行われ、旧湖南鉄道の扱い、慰労金の支払いなどで激しい議論が交わされたとされています。 合併は、藤井氏と太田氏による極秘交渉の結果、急転直下で決まったとされ、琵琶鉄の役員の一部も合併成立を知ったのは直前だったと伝えられています。 合併後、旧湖南鉄道は八日市鉄道として分離されました。 しかし、合併は従業員への解雇、給料や解雇手当の減額問題を引き起こし、争議へと発展しました。 合併は、経営再建の手段ではあったものの、社内や従業員との間には大きな軋轢を生む結果となりました。
3. 八日市鉄道の設立とその後
琵琶鉄と京阪電気鉄道の合併後、琵琶鉄の鉄道部門のうち、京阪が経営しない旧湖南鉄道の部分は、他の会社に譲渡されることになりました。 その事業を引き継ぐため、藤井善助氏らの主導で八日市鉄道の設立準備が進められました。 発起人には、藤井善助氏、藪田勘兵衛氏、北川弥一氏、小梶九郎兵衛氏らが名を連ねています。 設立当初から、湖南鉄道の株は藤井氏ら元所有者の手に帰属し、将来的には宇治電に譲渡されるという見方もありました。 しかし、近江鉄道との合併は、電化費用などの問題から実現せず、最終的に八日市鉄道は独立した会社として存続することとなりました。 永源寺自動車なども八日市鉄道と関連する会社として存在しており、地域の交通網維持に貢献したと考えられます。この八日市鉄道の設立は、琵琶鉄の合併という大きな出来事の後に、新たな展開を示す重要な出来事だったと言えます。
