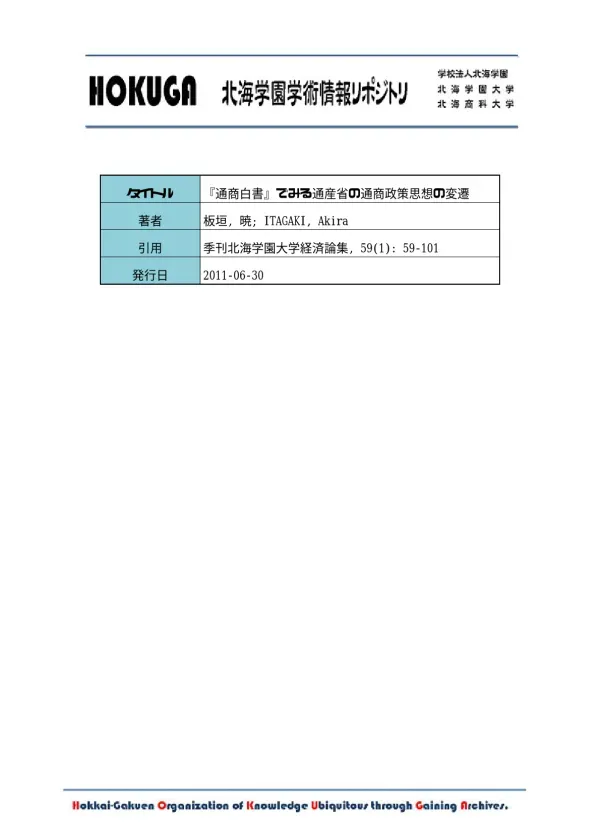
通商白書分析:通産省通商政策の変遷
文書情報
| 著者 | 板垣暁 |
| instructor/editor | 尾高煌之助 (一橋大学・法政大学) |
| 学校 | 北海学園大学 |
| subject/major | 経済学 |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.93 MB |
概要
I.年代の貿易自由化と通産省の産業政策 国際収支 の黒字化と政策転換
1960年代の貿易自由化と国際収支の恒常的な黒字化により、通産省の産業政策への介入手段と正当性が弱まりました。これにより、政策の焦点は輸出振興から成熟産業の課題、特に対外摩擦の軽減へとシフトしました。1960年代後半までは、輸入代替と輸出振興という貿易立国の思想が通産省の産業政策を支配していましたが、外貨準備高の急増(1971年に100億ドル突破)を背景に、輸出拡大一辺倒の戦略は終焉を迎えました。
1. 1960年代の貿易自由化と国際収支黒字化の影響
1960年代における貿易自由化と国際収支の恒常的な黒字化は、通産省の産業政策に大きな変化をもたらしました。多くの研究が指摘するように、それまで産業への介入を主導してきた通産省は、この経済状況の変化により、産業への介入手段と正当性を失いつつありました。 貿易自由化によって、これまで保護されていた国内産業は国際競争にさらされることとなり、通産省による保護政策の必要性が薄れていったのです。同時に、国際収支の黒字化は、外貨準備の急増(1971年には100億ドルを突破)という結果を生み出し、輸出拡大による外貨獲得という従来の政策目標の優先順位が低下しました。この変化は、1960年代半ばを境に顕著になり、それまでの「国際収支の天井」という制約が解消されたことが大きな要因の一つです。輸出増加が日本の潜在成長率と実成長率の乖離を解消する役割を果たしていた時代から、新たな経済状況への対応が求められるようになったのです。 この黒字化によって、通産省の産業政策は、輸出振興から、成熟産業の課題、特に強い日本企業が引き起こす対外摩擦への対応へとシフトしていきました。具体的には、1981年以降、貿易収支が恒常的に大幅な黒字を計上したことに伴い、輸入拡大による対外不均衡の是正が政策課題として浮上します。1960年代末までは、輸入代替と輸出振興という貿易立国の思想が通産省の産業政策を強く支配していましたが、この段階で大きな転換期を迎えたといえるでしょう。
2. 貿易立国思想と産業政策の転換
1960年代末まで、通産省の産業政策は「貿易立国」という思想、すなわち輸入代替と輸出振興によって日本経済を発展させるという考え方に強く支配されていました。 これは、戦後日本の経済状況を反映したものでした。戦後しばらくの間、日本経済の成長は国際収支の天井によって制限され、潜在的な成長力は十分に発揮されていませんでした。しかし、1965年以降、日本の輸出品の国際競争力が高まり、恒常的な経常黒字が計上されるようになると、この状況は一変します。輸出の増加が、日本の潜在的成長力と実際の成長を一致させる役割を果たすようになったのです。この変化は、通産省の産業政策にも大きな影響を与え、輸出拡大一辺倒の政策から、より多角的な視点を取り入れた政策へと転換を促す契機となりました。 国際収支の黒字化によって、単純に輸出を増やし、資源輸入のための外貨を稼ぐという戦略は、もはや必要ではなくなりました。 むしろ、1981年以降は、貿易収支の恒常的な大幅な黒字が新たな課題を生み出し、輸入の拡大による対外不均衡の是正が政策の中心に据えられるようになっていったのです。この段階で、通産省の産業政策は、輸出振興という従来の枠組みを超え、より複雑で多様な課題に対応していく必要に迫られたと言えるでしょう。
II.保護貿易主義への警戒と自由貿易体制維持
通産省は、自由貿易体制の維持を基本目標として掲げ、保護貿易主義の台頭を最大の障害と認識していました。特に、アメリカ国内の保護貿易主義的な動き(1960年代末から顕在化)や、通商法301条、スーパー301条の適用には強い警戒感を示し続けました。1980年代以降は日米貿易摩擦が深刻化し、アメリカからの市場開放圧力が強まりました。この中で、通産省は内需拡大による対外不均衡是正を主張しつつも、アメリカの経済構造にも問題があると指摘するようになりました。
1. 自由貿易体制維持と保護貿易主義への警戒
通産省は、自由貿易体制の維持を基本目標としていましたが、その最大の障害として保護貿易主義の台頭を捉えていました。1981年の通商白書では、世界的な景気低迷と失業増加により各国で保護主義的な動きが強まっていると指摘し、世界貿易秩序が大きな危機に直面していると警告しています。この警戒感は2001年まで継続され、通商白書においても、自由・多角・無差別を原則とするGATT(のちのWTO)機能の強化が繰り返し求められています。特に、1991年版では米国経済の退潮の中で国際的に保護主義が顕在化する懸念が強く示されています。アメリカ国内における保護貿易主義的な思想は1960年代末から見られ、通産省はこれに対して強い懸念を示していました。しかし、初期の経済摩擦は「集中豪雨的輸出」と呼ばれる日本の輸出急増に対するアメリカ国内関係業界からの反発が主な原因であり、日本の関係業界による輸出自主規制によって一時的に鎮静化されました。 この状況は、通産省が自由貿易体制維持のために保護貿易主義に断固として反対する姿勢を貫いていたことを示しています。 自由貿易体制の維持は、通産省の政策の中心であり、保護貿易主義への警戒は、長年に渡る彼らの政策の基本姿勢であったと理解できます。
2. 日米貿易摩擦と通産省の対応
1980年代に入ると、日米間の貿易摩擦が激化しました。特に、アメリカの対日貿易黒字の拡大は、アメリカによる対日批判を招く大きな要因となりました。レーガン政権誕生以降、アメリカ政府は日本への市場開放圧力を強め、自由貿易主義を掲げながらも、貿易相手国への市場開放・輸入促進を求める姿勢を強化しました。1982年にはレーガン大統領が日本の市場開放が不十分だと不満を漏らし、相互主義への理解を示唆しました。これを受け、通産省は次第に対外不均衡の原因をアメリカ側の経済構造にも求めるようになりました。1989年版通商白書では、「対外不均衡の是正に必要なアメリカ経済の構造調整」という節を設け、アメリカの対外不均衡拡大の背景として、民間・政府両部門における超過需要構造、国内製造業における供給能力不足、企業の短期業績指向、M&Aの活発化などを分析しています。さらに、日本の輸出産業の強い価格競争力やコスト削減努力、新商品の開発なども要因として挙げ、日米間の国際競争力、企業行動の差異を指摘しています。 しかし、通産省は対外不均衡の原因をアメリカだけに求めたわけではなく、内需拡大による持続的成長が引き続き重要な課題であると主張し続けました。 同時に、通商法301条やスーパー301条の適用に対しては、国際ルールからの逸脱の可能性を懸念し、強い警戒感を示していました。
III.円高と内需主導型経済への転換
1970年代後半の急激な円高を受け、政府は為替介入を放棄。これ以降、日本経済は内需主導型成長に転換しました。目標とした7%成長には届きませんでしたが、1978年は石油危機後初めて内需中心の景気回復が実現しました。しかし、輸出の伸び悩みと輸入拡大により、対米貿易黒字は1980年代に急拡大し、アメリカからの批判を招く結果となりました。
1. 1970年代後半の急激な円高と政府の対応
1970年代後半、日本経済は急激な円高に見舞われました。この円高に対し、政府は為替介入を放棄するという政策を選択しました。この政策転換の背景には、それまでの輸出主導型経済から内需主導型経済への転換という思惑があったと考えられます。 為替介入を放棄した結果、1970年代後半には円相場は急速に高騰し、戦後初めて1ドル200円台を割り込む事態となりました。この円高は、日本の輸出産業に大きな打撃を与え、輸出の伸び悩みを引き起こしました。 一方で、円高は輸入拡大を促進し、1979年には日本の貿易黒字が減少に転じ始めます。しかしながら、この円高と為替介入放棄が日本経済にどれほどの影響を与えたのか、文書からは明確な結論は読み取れません。
2. 内需主導型経済への移行と新たな課題
為替介入の放棄後、日本経済は1978年から内需を中心とした成長を遂げ始めました。目標としていた7%成長には届きませんでしたが、物価安定が続く中で、石油危機以降初めて内需を中心とした着実な景気回復が実現しました。これは、輸出依存型経済からの脱却に向けた大きな一歩と言えるでしょう。しかし、この内需主導型経済への転換は、新たな課題をもたらすことになります。輸出の伸び悩みが続く一方で、輸入は拡大し続け、結果として対米貿易黒字は1980年代に入ると急速に拡大しました。この対米貿易黒字の拡大は、アメリカによる対日批判を招き、日米貿易摩擦の深刻化に繋がったのです。 目標とした7%成長には届かなかったものの、1978年の景気回復は、石油危機以降、初めて内需を中心とした着実な回復であったと評価されています。この内需主導型経済への転換は、円高という外的要因と、政府による為替介入放棄という政策決定が複雑に絡み合った結果として実現したと言えるでしょう。
IV.地域統合への対応 EUとNAFTA
通産省は、EUとNAFTAといった地域統合に対して、当初はGATTの自由・無差別原則への反する可能性を懸念していました。特に、アンチダンピング措置の濫用や、原産地規則の強化には警戒感を示しました。しかし、1990年代後半以降、通産省は地域統合への姿勢を転換し、多角的通商システムを補完するものとして積極的に対応していく必要性を認識するようになりました。EUに関しては、当初の懸念が杞憂に終わったと判断しました。
1. EUへの対応 警戒感と杞憂
1993年版通商白書において、通産省はEUの通商政策について、域内の物理的、技術的、財政的障壁の除去が進んだと一定の評価を与えつつも、アンチダンピング制度の積極的な活用には警戒感を示していました。濫用が保護主義につながる可能性を懸念していたのです。しかし、1988年から1992年までのアンチダンピング措置調査の増加率と、1992年から1997年までの増加率を比較すると、後者の方が小さいことがわかります。これは、EU成立後、アンチダンピング措置調査件数は増加しているものの、その伸びは低く抑えられていたことを示唆しています。 通産省は、EUの地域統合が、①貿易転換効果、②GATTの求心力の低下、③保護主義的手段の適用機会の増大、④バーゲニングパワー濫用の可能性といったマイナスの影響をもたらす可能性も懸念していました。しかし、アンチダンピング措置の増加傾向は世界全体でも見られる現象であり、EU地域内での増加が地域統合によるものとは断定できません。結果的に、この点に関する通産省の懸念は杞憂に終わったと言えるでしょう。 この分析は、通産省が地域統合による保護主義的な動きを警戒しつつも、その影響を冷静に分析しようとしていた姿勢を示しています。
2. NAFTAへの対応 警戒感と懸念
NAFTA協定に対しても、通産省は警戒感を示していました。その懸念点は主に二つあります。一つ目は、NAFTAがアジア諸国、特に東南アジア諸国に与える負の影響です。アメリカがメキシコとの貿易を拡大すれば、東南アジア諸国は対米貿易を減らす可能性があり、さらにNAFTAの利益がアジアからメキシコへの製造拠点シフトを促進するというアメリカの非公式な示唆は、北米から東南アジアへの直接投資のメキシコへのシフトを招き、東南アジア経済に大きな影響を与える可能性があると懸念されました。 二つ目は、NAFTAの原産地規則の強化です。NAFTAは自動車部品の現地調達比率を段階的に引き上げるなど、GATTとの整合性に疑義があり、今後の運用に強い警戒感を持つべきだと指摘していました。 これらの懸念は、NAFTAがもたらす潜在的な保護主義的な傾向や、地域統合による貿易構造の変化への懸念を反映しています。通産省は、地域統合によるメリットとデメリットを総合的に評価しようとする姿勢を示していましたが、NAFTAに関しては、警戒感が強いことが見て取れます。
V.APECと東アジア経済 相互依存関係の深化
通産省はAPECによる貿易自由化を評価し、東アジア経済の発展が世界経済の安定に貢献すると考えていました。日本と東アジア諸国との間の直接投資、貿易、分業の進展による相互依存関係の深化を重視し、アジア経済の発展を日本経済にとって極めて重要と認識しました。関税障壁、非関税障壁の撤廃についても、APECの役割を高く評価しました。 各国の個別行動計画(IAP)に基づく取り組みが成功したと評価しています。具体例として、韓国の外資誘致法制定(1998年)、マレーシアの輸入税免除(1999年)などが挙げられます。
1. APECの役割と東アジア経済への期待
通産省は、APEC(アジア太平洋経済協力)の役割を高く評価していました。1991年版通商白書では、APECの役割を①本地域経済に関する重要課題の協議、②分野別協力プロジェクトの推進と位置づけつつも、特に自由貿易体制の一層の拡大を推進する観点から、アジア太平洋地域において開放的な協力のモデルを示していくことが重要だと強調しています。 1989年版では、アジア地域における競争のダイナミズムを維持しつつ潜在的成長力を実現していくことが、発展途上国の発展のみならず世界経済の安定的な発展に貢献すると述べられており、アジア諸国を世界経済の安定化に重要な存在として認識していたことがわかります。 通産省は、GATT/WTOの自由・無差別原則に反する地域主義的な考え方には強い懸念を抱いていましたが、APECについては、自由で開かれた貿易と投資を促進する場として肯定的に捉えていました。これは、APECが自主的な取り組みを重視し、個々の参加国(メンバー)が個別行動計画(IAP)に基づいて貿易・投資障壁の削減・撤廃に取り組む枠組みであったためです。関税障壁や非関税障壁の削減・撤廃の事例が多く見られたことも、APECの成果として評価されています。
2. 東アジア経済と日本の相互依存関係の深化
アジア経済は、日本経済と密接な関係にあります。1981年版通商白書では、日本は環太平洋地域の安定と繁栄に協力することが、資源輸入に大きく依存する日本にとって経済安全保障の観点からも重要だと述べられています。この時点では、アジア諸国は日本にとって資源供給国としての側面が強かったと考えられます。しかし、1990年代に入ると、アジア諸国の産業高度化と技術向上により、日本との関係は単なる資源供給国を超えた、より深い相互依存関係へと変化していきました。 アジア経済の発展が日本経済の浮沈に大きく影響を与えるようになり、アジアの発展が日本経済の発展にとってより重要になったと認識されるようになりました。通産省は、直接投資、貿易、分業の進展を通じた日本と東アジア間の相互依存関係の深化が日本経済全般に好影響を与えてきたと認識し、この関係を維持しつつ相互発展を遂げていくべきだと考えていました。 具体的には、韓国の外資誘致促進法(1998年)やマレーシアの輸入税免除(1999年)のような政策を例に挙げ、アジア諸国の経済発展を促進する動きを評価しています。これらの政策は、アジア経済の高度化と、日本との経済連携強化に貢献したと見なされていたと考えられます。
VI.WTOと多国間交渉 多角的通商システムの課題
通産省は、WTOの設立を高く評価しましたが、WTO紛争解決手続の有効性には懸念を示しました。特に、アメリカによる一方的な措置や国内法の域外適用には問題があると指摘しました。1990年代後半以降、地域・二国間交渉(FTA/EPA)を多国間交渉を補完する手段として捉えるようになり、その理由として、新しいルール構築の迅速性、多国間交渉への刺激効果、ノウハウ・経験の蓄積、日本企業の競争力強化、バランスのとれた国際貿易秩序の形成などを挙げています。 ODAについても、東アジア地域の経済発展促進に活用していくことを求めていました。
1. WTO設立と通産省の評価
1997年版通商白書では、1995年のWTO(世界貿易機関)設立を高く評価し、WTO協定が捕捉する範囲の拡充と組織の整備により、WTOは広範な通商問題を取り扱い紛争を解決する場として、名実ともに世界通商システムの中核たる機関になったと述べています。WTOの設立は二国間の通商関係に大きな影響を与え、各国はWTO協定に照らして判断し、WTOの紛争解決手続を視野に入れた二国間交渉を行う姿勢を強めていると分析しています。しかし、2001年版では、WTOの紛争解決手続が強化された後も、米国による一方的な措置や国内法の域外適用の濫用は減少しておらず、その問題点がさらに明確になっていると懸念を示しています。また、WTO加盟国の増加は自由貿易の拡大につながる一方で、加盟国数増加と交渉項目の多様化により、WTOにおける機動的な交渉や合意形成が困難になっているという問題点も指摘しています。このことは、WTOが理想的な機能を果たしているとは限らないという通産省の認識を示しています。
2. 地域主義の台頭と多国間交渉への対応変化
1990年代後半から、通産省は地域・二国間交渉のあり方に関する認識を変え始めました。1999年版通商白書では、地域連携・統合は自由化ルールの先行整備や域内経済成長促進といったメリットを持つ一方、排他的な性格によって健全な競争や資源配分を阻害する懸念もあると指摘しています。しかし同時に、地域連携・統合の拡大を踏まえ、懸念される弊害を防ぎつつ、より柔軟かつ建設的に対応していく必要性が高まっていると明記し、従来の方針転換を示しました。 この方針転換の背景には、EUの事例で当初懸念されたような状況が生じていないこと、そして地域主義の世界的な広がりによって乗り遅れることが日本経済にとって不利益になるという認識がありました。特に後者は、2001年版でも理由として挙げられており、1990年代後半に初めて起きた変化として認識されています。 通産省は、地域・二国間交渉を多国間交渉を補完する場として捉え始め、その理由として、①新しいルールの迅速な構築、②多国間交渉の活性化、③ノウハウ・経験の蓄積、④日本企業の競争力強化、⑤バランスのとれた国際貿易秩序の形成などを挙げています。この転換は、世界経済の変化への対応として、より柔軟で積極的な姿勢を示すようになったことを意味します。
