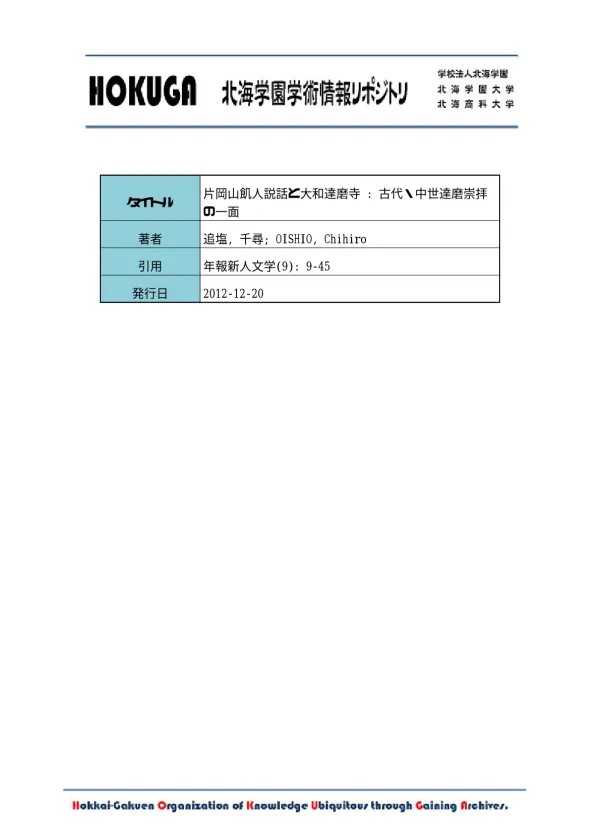
達磨寺と片岡山飢人説話:古代中世の達磨信仰
文書情報
| 著者 | 追塩 千尋 |
| 専攻 | 日本文学 |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.90 MB |
概要
I. 達磨寺 Daruma ji Temple の起源と 聖徳太子 との関わり
一般的には鎌倉初期、慶政による創建とされる【達磨寺】だが、確実な史料は14世紀以降。それ以前は伝承に頼る部分が大きい。しかし、聖徳太子と【達磨】への崇拝、及び寺の実際を探る上で、七世紀の【片岡山飢人説話】が重要な手がかりとなる。この説話は、『日本書紀』にも見られ、平安初期の『上宮聖徳太子伝補闕記』では飢人が神秘的な容貌と記述されている。飢人=達磨説は、10世紀の『聖徳太子伝暦』で確固たる地位を占めるようになるが、「若達磨歟」と断定は避けられている点に注意が必要。一方、飢人=文殊説も存在し、12世紀初頭の『俊頼髄脳』で確認できる。
1. 達磨寺創建と史料の不足
達磨寺は一般的に鎌倉初期、慶政による創建とされていますが、明確な史料が現れるのは14世紀以降です。それ以前の確実な史料は非常に少なく、大部分は伝承に頼るしかありません。しかし、これらの伝承は聖徳太子と達磨に対する崇拝の様子、そして達磨寺の実態を探る上で重要な手がかりとなるため、無視できません。特に、本稿では達磨寺の淵源を探る上で、七世紀の片岡山飢人説話が重要な役割を果たすと考えられます。この説話は、いくつかの文献に断片的に記されており、その解釈をめぐって様々な議論が展開されてきました。
2. 片岡山飢人説話と飢人 達磨説
片岡山飢人説話は、『楽遺文』、『七代記』、『大唐国衡州道場釈思禅師七代記』などに言及されています。特に注目すべきは、『楽遺文』の「彼飢者蓋達磨歟」という注記です。これは、達磨が南岳慧思に東方への教化を勧め、達磨自身は先に東方へ渡り、慧思は聖徳太子として再生したという説話に基づいています。『日本書紀』では飢人の容貌や言動は詳しく述べられていませんが、『上宮聖徳太子伝補闕記』では、飢人の容貌が神秘的に描写されており、達磨との関連性を示唆しています。ただし、『日本書紀』や他の太子伝には達磨は直接登場しません。一方で、藤原氏による記述や、『和漢朗詠集』、『袋草紙』などにも、達磨と聖徳太子との関わりを示唆する記述が見られます。これらの記述は、飢人=達磨説の形成過程を理解する上で重要です。
3. 飢人 文殊説と達磨崇拝の様相
飢人=達磨説とは別に、飢人=文殊説も存在します。この説は、『俊頼髄脳』を基準とすれば12世紀初頭には確認できますが、それ以前の『喜撰式』にもその片鱗が見られます。喜撰法師の生没年は不詳なため、その真偽は定かではありませんが、もし真作であれば、飢人=文殊説は10世紀には存在していた可能性があります。平安末期までの飢人=達磨説は、日本における達磨崇拝の一つの側面を示しています。しかし、この達磨崇拝は太子信仰に包含されており、達磨自身は独立した崇拝の対象ではなかったと言えるでしょう。『今昔物語集』にはインド・中国における達磨の様々な逸話が収録されており、達磨の教えや人物像を多角的に理解する上で参考になります。また、12世紀には達磨像が日本に伝わっていた可能性も示唆されており、達磨=観音説なども存在したようです。
4. 聖徳太子伝暦 とその他の関連文献
10世紀初頭成立と考えられる『聖徳太子伝暦』は、飢人=達磨説を明確に記述した重要な文献です。しかし、そこでは「七代記云。飢人者。若達磨歟」と留保付きの表現を用いており、飢人を達磨と断定していない点に注意が必要です。10世紀末の『日本往生極楽記』、『三国伝』なども飢人=達磨説に言及しています。これらの文献は、飢人説話が太子伝の中にどのように位置づけられていったのか、また、その解釈がどのように変化していったのかを理解する上で不可欠な資料です。更に、栄西の『興禅護国論』は、慧思と達磨の関係を論じる中で太子説話に触れており、臨済宗と曹洞宗における達磨崇拝の違いにも言及している点は興味深いところです。日蓮の著作には達磨への批判的な記述も見られ、禅宗と法華経の教えとの関係、そして達磨像の扱われ方について、多様な解釈が存在していたことがわかります。
II. 達磨 崇拝の展開と寺勢の変遷
平安末期までの【達磨】崇拝は太子信仰に包含される形で展開。達磨自身の自立した崇拝は限定的だった。禅宗の祖師としての【達磨】の認識が一般に広まる過程を検証する必要がある。片岡山の古墳が【達磨】の墓という認識も存在し、それは【達磨】崇拝の一端を示す。12世紀末の『建久御巡礼記』では、片岡山の廟が太子の飢人との出会い、すなわち【達磨】の化身との遭遇の場とされている。また、『沙石集』には【達磨】廟への参籠体験が記されている。慶政は1239年、古墳の上に石塔を建立し、寺を整備。興福寺の訴えにより、仙海は配流となるなど、寺の隆盛と衰退を繰り返す。
1. 平安末期までの達磨崇拝 太子信仰との関係
平安末期までの達磨崇拝は、聖徳太子信仰に包含される形で展開されました。達磨自身を独立して崇拝する動きは限定的であり、禅宗の祖師としての達磨の認識が天台宗内部にとどまらず一般に広まる過程を詳細に検証する必要があります。片岡山の古墳が達磨の墓だとする認識も一部にはあり、それが達磨崇拝の一つの側面を示唆しています。しかし、この段階では、達磨信仰は、より広く浸透していた太子信仰に付随する形で存在していたと考えるのが妥当です。 この事実は、当時の宗教的・文化的状況を反映しており、異国の宗教である禅宗を、既に強い基盤を持っていた太子信仰と結びつけることで、より円滑に受け入れられやすかった可能性を示唆しています。
2. 十二世紀末の 建久御巡礼記 と達磨廟
12世紀末に記された『建久御巡礼記』は、達磨寺に関する貴重な史料です。この記録によると、片岡山には三重の塔のような廟があり、聖徳太子が飢人と出会った場所だとされています。この飢人が達磨の化身であるという解釈が、この時点で既に成立していたことを示唆しています。また、この廟の発掘や修築に放光寺や信貴山の僧侶が関わっていたという記述もあり、太子ゆかりの寺院としての達磨寺の宣伝・アピールという側面も考えられます。これらの記述は、達磨崇拝が、単なる宗教的な信仰を超えて、地域社会に深く根付いた文化現象として認識されていた可能性を示唆しています。 特に、当時の僧侶たちが達磨廟に積極的に関与していた事実は、達磨への信仰が、単なる学問的な興味や宗教的な議論を超えて、現実の社会活動に深く関わっていたことを示しています。
3. 沙石集 の記述と達磨崇拝の広がり
『沙石集』は、建久御巡礼記に続く、達磨寺に関する貴重な同時代の記録です。この書物には、達磨廟への参籠体験が記されており、当時の参詣者の信仰の深さや、達磨への崇敬が広く社会に浸透しつつあったことを示しています。 また、この記述は、達磨が禅宗の盛んな現代においてもなお、人々の信仰の対象として記憶され、その霊験が信じられていたことを示唆しています。 このことは、達磨崇拝が単なる宗教的な信仰にとどまらず、人々の日常生活や精神生活に深く根付いていたことを示す重要な証拠となります。 さらに、片岡山に存在したとされる達磨の墓という認識も、達磨崇拝が一定の広がりを見せていたことを示す傍証と言えるでしょう。
4. 慶政による達磨寺の整備と寺勢の変遷
慶政は延応元年(1239年)に達磨寺を訪れ、古墳の上に石塔を建立し、達磨と聖徳太子の像を安置するなど、寺を大規模に整備しました。この整備は、達磨寺の歴史において重要な転換期となりました。 また、興福寺による達磨寺の破壊事件(嘉禎二年、もしくは嘉元三年の誤りと考えられる)は、当時の禅宗寺院と南都寺院の勢力争いを示す出来事であり、達磨寺が当時、無視できないほどの勢力を持っていたことを示しています。 仙海という僧侶は達磨寺の隆盛に貢献しましたが、その活動が行き過ぎたため興福寺の訴えにより配流となりました。この事件は、達磨寺の寺勢と、当時の宗教勢力間の複雑な関係を示す重要な史実です。その後、足利義満の時代には荒廃していた達磨寺は、室町幕府の援助を受けて再び整備され、永享7年(1435)には『達磨寺中興記』が作成されるに至りました。
III. 達磨寺 に関する史料と発掘調査
14世紀以降、【達磨寺】に関する史料が増える。『達磨寺歴代興衰記』、『達磨寺中興記』などが重要な史料。特に『中興記』は、永享7年(1435)南禅寺僧惟肖得巖によるもので、石幢に刻まれた碑文。 足利義満の時代には荒廃していたが、室町将軍の援助を受けて再興。2002年の発掘調査では、13世紀中頃以前の水晶製五輪塔形舎利容器が発見されている。これらの史料と発掘調査は、【達磨寺】の歴史と【達磨】、【聖徳太子】との関わりを解明する上で貴重な情報源となる。
1. 14世紀以前の史料不足と伝承の重要性
14世紀以前の達磨寺に関する確実な史料は非常に少なく、大部分は伝承的な史料に頼らざるを得ません。しかし、これらの伝承は、聖徳太子や達磨に対する崇拝の様相、そして達磨寺の実態を理解する上で重要な手がかりとなります。そのため、伝承を単なる逸話として片付けるのではなく、歴史的背景や宗教的思想と関連づけて慎重に検討していく必要があります。特に、七世紀の片岡山飢人説話は、達磨寺創建の起源を探る上で重要な役割を果たしています。この説話に関する記述は複数の文献に散見されますが、それらの記述を比較検討することで、説話の成立過程や、人々の解釈の変化を明らかにすることができます。
2. 主要な史料 達磨寺歴代興衰記 達磨寺中興記 など
14世紀以降は、達磨寺に関する史料が比較的多く見られるようになります。『達磨寺歴代興衰記』、『達磨寺中興記』は、その中でも特に重要な史料です。『達磨寺中興記』は永享7年(1435年)に南禅寺僧惟肖得巖によって記され、文安5年(1448年)には石幢に刻まれています。この史料は、達磨寺の興亡の歴史を詳細に記しており、寺の整備や再興に関する過程を理解する上で不可欠です。また、『聖徳太子伝暦』の注釈書である『聖誉鈔』や『太子伝玉林抄』も、達磨寺に関する貴重な情報を提供しています。これらの史料を総合的に分析することで、達磨寺の変遷をより詳細に明らかにし、その歴史的意義を解明することができます。さらに、達磨寺は古墳の上に建立されているため、発掘調査による考古学的アプローチも重要です。
3. 建久御巡礼記 沙石集 などの同時代観察
建久2年(1191年)の『建久御巡礼記』には、片岡山の達磨廟に関する記述があります。この記述は、達磨廟が聖徳太子と深く関わっていることを示唆し、その神聖性を強調しています。また、放光寺や信貴山の僧侶たちがこの廟に関与していたことも記されており、当時の宗教勢力間の関係や、達磨信仰の広がりを推測する手がかりとなります。『沙石集』は、達磨廟への参籠体験を記した同時代の別の記録です。これらの史料は、14世紀以前の達磨寺の様子を知る上で非常に貴重であり、後世の解釈や伝承との比較検討を通して、より正確な歴史像を構築することが期待されます。 特に、これらの記述から、達磨信仰が当時の人々の生活や信仰に深く関わっていた様子が伺えます。
4. 発掘調査と考古学的知見
達磨寺は古墳の上に建立されているため、発掘調査による考古学的知見も重要です。2002年の発掘調査では、13世紀中頃以前の水晶製五輪塔形舎利容器が発見されています。この発見は、達磨寺の歴史を解明する上で重要な考古学的証拠となります。 発掘調査によって得られた遺物や遺構は、史料だけではわからない情報を提供し、達磨寺の歴史像をより立体的に理解する上で欠かせません。これらの考古学的知見と文献史料を統合的に分析することで、達磨寺の創建から中興までの歴史像をより明確に描き出すことができます。今後のさらなる発掘調査が、達磨寺の歴史解明に大きく貢献すると期待されます。
IV. 太子信仰 と 達磨 崇拝の融合と葛藤
初期の【達磨寺】では、異国の僧である【達磨】を日本に浸透させるため、既に広く信仰されていた【聖徳太子】と結びつける必要があった。そのため、太子信仰が主体で、【達磨】崇拝は従属的な位置づけにあった。 しかし、日蓮などの批判に見られるように、禅宗と法華経の教えとの相克、そして【達磨】への様々な解釈が存在した。 栄西や道元といった高僧の思想においても、【達磨】崇拝の受け止め方は異なっていたことがわかる。
1. 太子信仰と達磨崇拝の融合 初期の達磨寺
初期の達磨寺においては、達磨崇拝は聖徳太子信仰と深く結びついていました。これは、異国の僧である達磨を日本社会に受け入れやすくするため、既に広く信仰されていた太子信仰と関連付ける必要があったためと考えられます。そのため、達磨寺では太子信仰が主となり、達磨崇拝はそれに付随する形をとっていました。 この融合は、宗教的な布教戦略という側面も持ちますが、同時に、異なる宗教や思想がどのように共存し、影響し合っていたのかを示す重要な事例でもあります。 この関係は、後世の達磨寺や達磨崇拝のあり方にも大きな影響を与えたと考えられます。
2. 達磨崇拝の広がりと禅宗の台頭
達磨が禅宗の祖師であるという認識が、天台宗内部にとどまらず一般に広まるにつれて、達磨崇拝の様相も変化していきました。しかし、その広がりは必ずしも均一ではなく、地域や宗派によって異なる解釈や信仰の形が見られました。片岡山の古墳が達磨の墓だとする認識も、達磨崇拝が一定の広がりを持っていたことを示す一つの証左です。 しかし、達磨崇拝が独立した信仰として確立するまでには、時間を要したと考えられます。 これは、禅宗が日本社会に定着し、その影響力が拡大していく過程と密接に関連していると言えるでしょう。 特に、日宋交流を通して、達磨像や関連する思想が日本に伝来したことは、達磨崇拝の広がりを促進する要因となりました。
3. 日蓮の批判と達磨像への異論
日蓮は、達磨を批判的に捉えていました。日蓮の著作には、達磨を法華経の教えを知らない人物、あるいは一乗誹謗の罪がある人物として批判する記述が見られます。これは、禅宗と法華経の教えの間に存在した相克、そして達磨への様々な解釈の存在を示唆しています。 日蓮の批判は、達磨崇拝に対する異論や批判が存在したことを示す重要な史料です。 この批判は、達磨像を本尊とする禅宗への批判という側面だけでなく、当時の宗教思想における多様な立場や、宗教間の競合といった社会的な文脈を理解する上で重要な手がかりを提供します。 ただし、日蓮の記述は真蹟ではないものも含まれるため、解釈には注意が必要です。
4. 臨済宗 曹洞宗における達磨崇拝の違い
臨済宗と曹洞宗では、達磨崇拝のあり方に違いが見られました。栄西は慧思と達磨の関係に触れていますが、飢人説話には触れていません。一方、道元は太子信仰そのものを確認できないため、それに付随する達磨崇拝も高揚しなかったと考えられます。 これらの違いは、各宗派の思想や歴史的背景、そして太子信仰との関わり方の違いに起因すると考えられます。 このことは、達磨崇拝が単一の信仰形態ではなく、宗派や地域によって多様な形で受け継がれ、解釈されてきたことを示しています。 各宗派における達磨像の位置づけや、その信仰のあり方を詳細に検討することで、日本における達磨崇拝の多様性をより深く理解することができるでしょう。
