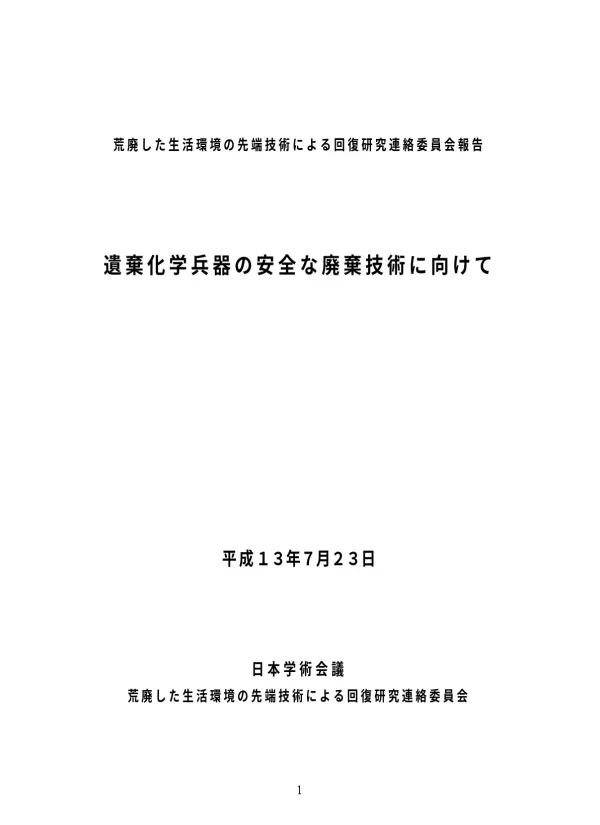
遺棄化学兵器廃棄:安全技術確立への道
文書情報
| 著者 | 古田 勝久 |
| 学校 | 日本学術会議 |
| 専攻 | 先端技術による生活環境回復研究 |
| 出版年 | 2001 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.69 MB |
概要
I.化学兵器禁止条約と遺棄化学兵器問題
本資料は、1997年4月29日に発効した化学兵器禁止条約に基づき、中国に遺棄された旧日本軍の化学兵器の廃棄処理問題を詳細に扱っています。条約は締約国に対し、自国が他国の領土に遺棄した化学兵器の廃棄を義務づけており、日本政府は内閣府遺棄化学兵器処理担当室を 中心に、中国政府との協力の下、廃棄事業に取り組んでいます。主要な化学剤としては、マスタードガス、ルイサイト、ジフェニルシアノアルシン、ジフェニルクロロアルシンなどが挙げられます。特に、吉林省敦化市ハルバ嶺地区には約67万発の化学砲弾が埋設されていると推定されています。
1. 化学兵器禁止条約の概要と日本の立場
1993年1月にパリで署名開放され、1997年4月29日に発効した化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(化学兵器禁止条約)について説明されています。この条約は、締約国が現在保有する化学兵器の廃棄のみならず、過去に他国の領土に遺棄した化学兵器の廃棄も義務付けています。条約発効に伴い、日本は第二次世界大戦後に中国に残された旧日本軍の化学兵器を廃棄する責任を負う遺棄締約国となりました。内閣府遺棄化学兵器処理担当室が中心となり、中国政府との協力の下、廃棄事業の計画と実行が進められています。この事業の学術的基盤形成のため、日本学術会議の下に「遺棄化学兵器の安全な廃棄技術の研究促進小委員会」が2000年11月に設置され、検討が開始されたことも記されています。 条約の目的は化学兵器の完全廃絶であり、日本の批准は国際社会の平和と安全への貢献として位置付けられています。 また、大量破壊兵器の不拡散と軍縮が緊急課題であるとの認識が示されています。
2. 中国における遺棄化学兵器の現状と課題
中国には、第二次世界大戦後に残された旧日本軍の化学兵器が多数存在しており、これが日本の主要な課題となっています。これらの遺棄化学兵器は、住民の安全確保のため1950年代に中国側によって集積・埋設されました。 吉林省敦化市ハルバ嶺地区は、最大の埋設サイトとして知られ、日本側推定で約67万発の化学砲弾が埋設されているとされています。埋設サイトは中国東北部以外にも、北京周辺や南京周辺などにも確認されています。未発掘の場所も存在する可能性が示唆されています。 これらの化学兵器の処理は、日中両国の協力の下で行われており、その具体的な取り組みや技術的な課題、安全対策などが詳細に説明されています。 特に、ハルバ嶺地区の処理計画や、処理における技術的な困難さ、経済的な側面、そして周辺住民への影響や説明責任といった問題点が強調されています。
3. 化学兵器禁止条約下の化学兵器関連活動への制限
化学兵器禁止条約では、防護活動、医療、研究などの平和目的のための特定化学物質(表1剤)の生産・保有は認められていますが、年間1トンまでと制限されています。年間100g以上のこれらの化学剤を製造する施設は、OPCWへの申告義務があり、国際査察を受けます。日本においては、陸上自衛隊化学学校が研究目的で年間10kgを上限にこれらの化学剤を合成・利用することが条約上および法律上認められています。 この条項は、平和目的での研究開発活動と、化学兵器の拡散防止を両立させるための規定として説明されています。また、軍の保有する化学剤防護・除染技術を平和目的の化学兵器廃棄に活用する例として、ベルギーの取り組みが紹介されています。 ベルギーでは、老朽化した化学兵器の処理に軍の能力を活用し、周辺住民への説明責任も果たしている点が、日本の取り組みの参考として示唆されています。
II.第一次世界大戦と化学兵器の使用
第一次世界大戦では、ドイツ軍による塩素ガス攻撃を皮切りに、マスタードガスなど30種類以上の化学剤が使用され、130万人以上の死傷者を出しました。この悲惨な経験は、化学兵器の禁止に向けた国際的な動きを加速させました。
1. 化学兵器の初使用と悲惨な結果
第一次世界大戦中の1915年4月22日、ドイツとオーストリア軍がイギリスとフランス連合軍に対し、168トンもの塩素ガスを用いた攻撃を行いました。これが化学剤が兵器として本格的に使用された最初の事例です。この攻撃は非常に悲惨な結果をもたらし、その効果を目の当たりにしたフランスとイギリス軍も、化学兵器の開発に積極的に取り組むようになりました。大戦終結までに、窒息剤に加え、青酸ガス(血液剤)やマスタードガス(びらん剤)など、30種類以上の化学剤が単独または混合物として使用されました。マスタードガスは、皮膚への激しいびらん作用に加え、吸入による肺組織の壊死を引き起こすなど、その危険性から「化学兵器の王」とも呼ばれ、大戦後も大量生産されました。しかし、純粋な硫黄マスタードは融点が比較的高く、低温のヨーロッパ戦線では固化してしまい、その欠点を補うため、他の化学物質を混合して改良が加えられました。1915年から1918年までに使用された化学兵器の総量は12万4200トン(砲弾換算で約6600万発)に達し、130万人の死傷者、うち約10万人が死亡したと推定されています。この大量の死傷者は、化学兵器の使用が戦局に大きな影響を与えることを各参戦国に認識させました。特にロシアは対ドイツ戦で多くの犠牲者を出し、化学兵器の生産・貯蔵に力を入れるようになりました。一方、化学戦争の悲惨さは、化学兵器の使用禁止を求める機運を高めることにも繋がりました。
2. ジュネーブ議定書と化学兵器禁止条約への道
第一次大戦での化学兵器の使用は、100万人以上の死傷者、10万人以上の死者という悲惨な結果をもたらしました。この経験を踏まえ、国際連盟は1925年にジュネーブ議定書を作成し、戦闘行為における化学兵器の使用を禁止しました。しかし、この議定書は使用の禁止に留まり、生産・開発・保有については規定がありませんでした。そのため、その後も化学兵器の製造・配備は続けられました。包括的な化学兵器の禁止は遅々として進みませんでしたが、1969年にウ・タント国連事務総長が「化学・細菌兵器とその使用の影響」という報告書を提出したことが転機となりました。この報告書を契機に、ジュネーブ軍縮委員会で化学兵器・生物兵器の全面禁止に関する議論が始まり、1984年には米国が化学兵器禁止条約の案文を提出しました。1989年にはフランス政府主催の「化学兵器禁止に関する国際会議」が開催され、140ヶ国以上が参加するなど、世界的な関心を集めました。これらの動きを経て、1992年9月に国連軍縮会議において「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(化学兵器禁止条約)が全会一致で採択され、翌1993年1月にパリで署名のために開放、そして四半世紀に渡る議論を経て1997年4月29日に発効しました。
III.第二次世界大戦以降の化学兵器開発と国際的な規制
第二次世界大戦中は表立った化学兵器の使用はありませんでしたが、サリン、ソマン、タブン、VXガスなど、より強力な神経剤が開発されました。その後、OPCW(化学兵器禁止機関)の設立や化学兵器禁止条約の採択を経て、化学兵器の開発、生産、貯蔵、使用は国際的に禁止されました。しかし、日本は遺棄締約国として、中国国内の遺棄化学兵器の処理に責任を負っています。
1. 第二次世界大戦における化学兵器開発の現状
第二次世界大戦中、ヨーロッパ戦線では表立った化学兵器の使用はありませんでしたが、世界各国で新たな化学兵器の開発と製造が進められました。化学剤の種類も変化し、窒息性剤、血液剤、びらん剤に加え、ドイツで開発されたタブン、ソマン、サリンといった有機リン系の神経剤、そしてイギリスとアメリカで開発されたVXガスのような、極めて高い致死性を持つ神経剤が登場しました。この化学兵器開発競争は、東西冷戦下において米ソ両国を中心に1980年代まで続きました。第一次大戦で使用された化学兵器とは異なり、より高度で、致死性の高い化学兵器が開発されたことが示されています。特に、有機リン系神経剤の開発とその危険性の高さが強調されています。これらの開発競争は、国際的な緊張を高め、化学兵器禁止条約の締結へとつながる重要な背景となっています。
2. ジュネーブ議定書の限界と国際的な規制強化
第一次世界大戦での化学兵器使用の悲惨な結果を受けて、1925年に国際連盟はジュネーブ議定書を作成し、化学兵器の使用を禁止しました。しかし、この議定書は使用のみを禁止し、生産、開発、保有については規定がありませんでした。そのため、化学兵器の製造と配備はその後も続けられました。ジュネーブ議定書では不十分だった化学兵器の包括的な禁止に向けて、1969年のウ・タント国連事務総長による報告書を契機に、ジュネーブ軍縮委員会で活発な議論が行われました。1984年には米国が化学兵器禁止条約の案文を提出、1989年にはフランス政府主催の国際会議が開催され、世界的な関心を集めました。これらの国際的な議論と努力が結実し、1992年9月に国連軍縮会議において化学兵器禁止条約が全会一致で採択されました。この条約は、化学兵器の完全廃絶を目的とし、その生産、使用などを禁止するだけでなく、廃棄についても規定しています。この条約は、長年にわたる国際的な努力の成果であり、国際社会における化学兵器の脅威に対する認識の高まりを示しています。
IV.化学兵器廃棄処理における技術的課題とアカデミズムの役割
遺棄化学兵器の安全かつ効率的な処理には、地質学、土木工学、化学工学、環境工学など多様な分野の高度な技術が必要です。特に、マスタードガス等の加水分解や、超臨界水酸化法などの処理技術の開発、そして分析法の確立が重要です。アカデミズムは、これらの技術開発、安全性の確保、リスク評価、住民への情報発信など、様々な側面で重要な役割を果たします。化学工学会などの学協会も、情報共有や研究協力の推進に貢献しています。
1. 遺棄化学兵器処理に必要な多様な技術
中国に遺棄されている化学兵器の安全かつ効率的な処理には、非常に幅広い科学技術の活用が不可欠です。地質学、土木工学、建築学、機械工学、分析化学、計測工学、金属工学、火薬学、有機化学、物理化学、化学工学、安全工学、環境工学など、多岐にわたる専門分野の知識と技術が求められます。さらに、処理過程全体を円滑に進めるためのプロジェクトマネジメントや、住民とのコミュニケーションを円滑に進めるためのリスクコミュニケーションの知識も重要になります。これらの技術開発には、アカデミズムの積極的な関与が不可欠であり、その意義が強調されています。特に、マスタードガス等の加水分解反応に関する研究や、超臨界水酸化法といった高度な処理技術の開発、そして正確な分析法の確立が重要な課題として挙げられています。これらの技術開発は、単一の分野の知識だけでは達成できず、複数の分野の専門家が協力して取り組む必要があることを示しています。
2. アカデミズムの貢献と研究体制
遺棄化学兵器の処理において、アカデミズムは技術開発のみならず、安全性の確保、環境への影響評価、経済性評価、さらには国際政治的な側面への助言など、多様な役割を担います。理工学系の専門知識は処理方法の開発や安全性の確保に不可欠であり、農学、医学、薬学などの分野は環境保全や人体への影響評価に貢献します。また、処理施設の立地選定、経済的な費用対効果の分析、そして国際的な協力体制の構築といった問題には、人文・社会科学系の知見も重要になります。これらの多様な分野の連携が、安全で効率的な処理を実現するための鍵となります。そのため、専門家間の情報交換と交流を促進するために、2000年11月に「遺棄化学兵器廃棄研究会」が設立されました。化学工学会などの学協会が中心となり、情報共有、意見交換、研究協力体制を構築することで、アカデミズムからの幅広い参加を促し、技術開発を加速させることを目指しています。研究会設立の背景には、個々の研究者・技術者の意欲だけでは十分な人材確保が難しいという現状への対応策と、安全確保や周辺住民への説明責任といった課題への対処が含まれています。
V.大久野島と化学兵器処理の実績
広島県の大久野島は、旧日本軍の化学兵器製造工場があった場所です。戦後、帝人株式会社が化学兵器の処理を行い、米国第8軍のウィリアムソン大佐も指揮にあたりました。処理方法は、蒸気注入、火炎放射器による焼却、熱油洗浄など多岐に渡り、ヒ素を含む化合物についても、光和精鉱株式会社が処理を行いました。
1. 大久野島における化学兵器処理の概要
瀬戸内海の広島県沖にある大久野島は、旧日本陸軍の化学兵器製造工場があった場所として知られています。第二次世界大戦終戦時、大久野島にはマスタードガス1451トン、ルイサイト824トン、くしゃみ剤(DC、DA)958トン、催涙剤7トンが貯蔵されていたとされています。戦後、これらの化学兵器の処理は帝人株式会社が請け負い、その作業は帝人社史にも記録されています。処理作業には、米国第8軍からウィリアムソン大佐が派遣され、指揮にあたっていました。処理方法は、化学剤の種類や状態によって異なり、蒸気注入による化学剤の溶出、火炎放射器による焼却、熱油洗浄による除染、建物の解体などが行われました。処理過程で発生したヒ素を含む廃棄物については、ヒ素廃棄物の処理許可を持つ光和精鉱株式会社(北九州市)が処理を担当し、広島県と北九州市の職員、そして2人の学識経験者からなる安全管理委員会が設置され、処理作業を監視しました。大久野島はその後、厚生省(現環境省)に移管され、国民休暇村として活用されています。この事例は、大規模な化学兵器処理における様々な技術的課題と安全管理の重要性を示す貴重な事例として提示されています。
2. 化学兵器処理における具体的な方法と課題
大久野島での処理作業は、化学剤製造施設の処理と海洋投棄処分が主なものでした。施設の処理では、まず蒸気を注入して化学剤を溶出し、排出される蒸気と凝縮水はさらし粉や苛性ソーダ溶液で処理されました。その後、火炎放射器で残留化学剤を焼却除染し、建物を解体、焼却しました。海洋投棄では、化学剤の漏洩なども発生しましたが、処理は完了しました。大量に残存したくしゃみ剤はコンクリート枠の壕に埋没し、海水とさらし粉の混合物を注入して処理されました。貯槽底部に残存していた50トン以上の化学剤残査は、熱油洗浄装置と焼却炉を使って処理されました。この際、催涙棒や催涙筒も同時に処理されました。ヒ素を含むジフェニルアルシン酸の処理は、光和精鉱株式会社が担当し、北九州市の指導の下、産業廃棄物に準じた処理が行われました。これらの処理方法と結果から、様々な化学兵器の処理における技術的な難易度や安全対策の必要性が示されています。また、廃棄物処理における環境への影響も考慮されていることが分かります。
VI.化学兵器廃棄処理における技術的側面と安全管理
遺棄化学兵器の処理は、砲弾の発掘、鑑定、分析、処理、廃棄という工程から成り立ちます。各工程において、安全性の確保が最優先であり、自動化・無人化技術の導入が求められています。また、ピクリン酸などの爆発性物質の取り扱いには、細心の注意が必要です。処理プラントの設計においては、有害物質の排出基準値を満たすだけでなく、不測の事態への備えも重要です。様々な処理方法が検討されていますが、中和処理法、焼却処理法、超臨界水酸化法などのメリットとデメリットを比較検討する必要があります。
1. 化学兵器廃棄処理工程と安全管理の重要性
遺棄化学兵器の処理は、発掘、鑑定、分析、処理、廃棄という複数の工程から成り立っています。各工程において、作業員の安全確保が最優先事項であり、作業の自動化、無人化、遠隔化が強く求められています。特に、約70万発という大量の砲弾を処理することを考えると、迅速性も重要な要素となります。現状の鑑定作業では、人の目による外観検査とX線写真による内部検査が行われていますが、錆除去、寸法計測、X線鑑定台への固定など、危険を伴う作業が含まれます。これらの作業の自動化は、安全性の向上に大きく貢献します。また、処理プラントの設計においては、有害物質の排出基準値をクリアすることはもちろんですが、プラントの不調時や人的ミスによる有害物質の排出リスクへの対策が不可欠です。 処理過程全体を通して、安全管理体制の徹底が求められています。
2. 処理技術の現状と課題 様々な処理方法の比較検討
化学兵器の処理方法としては、焼却処理法、中和処理法、超臨界水酸化法などが挙げられていますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。焼却処理法は処理能力が高いものの、有害な排出ガスが発生する可能性があります。中和処理法は排出ガスを大幅に低減できる一方で、大量の排水が発生し、その処理が課題となります。超臨界水酸化法は、完全な無機化が可能というメリットがありますが、高圧下での運転が必要なため、固体状物質の供給や材質選定が困難です。また、ナトリウム塩が混在する場合、結晶状固体の析出による閉塞やスケール付着などの問題も懸念されます。生物処理法は、まだベンチスケールのテスト段階であり、ヒ素を含む有機化合物の処理には適用が困難です。どの処理方法を選択するにしても、環境への影響や、処理後の廃棄物の安全な管理などを考慮する必要があります。 処理方法の選定にあたっては、それぞれの技術的な特性、経済性、安全性を総合的に評価する必要があります。
3. 分析とリスク管理 長期的な視点と安全対策
分析対象物質は、マスタード、ルイサイト、ジフェニルシアノアルシン、ジフェニルクロロアルシンなど、主に4種類の化学兵器の有効成分ですが、50年以上の経年変化によって成分が変化している可能性があり、新たな物質の生成も予想されます。マスタードやルイサイトの焼却ではダイオキシンが発生する可能性があり、ルイサイトやジフェニルシアノアルシン、ジフェニルクロロアルシンはヒ素化合物であるため、焼却過程でのヒ素の揮散や化学処理過程での排水への溶解も懸念されます。これらの物質を検出するための高感度かつ正確な分析法の開発と、適切なサンプリング方法の確立が重要です。ガスクロマトグラフやガスクロマトグラフ質量分析計が主な分析手段ですが、安定した測定値を得るための誘導体化などの技術も必要になります。また、分析に使用する標準物質の入手も容易ではないため、その確保も課題です。さらに、処理手順の変更管理や、作業工程における時間的なずれへの対応、関係者への情報共有など、リスク管理体制の構築も重要であり、全体コストの抑制も課題として挙げられています。
