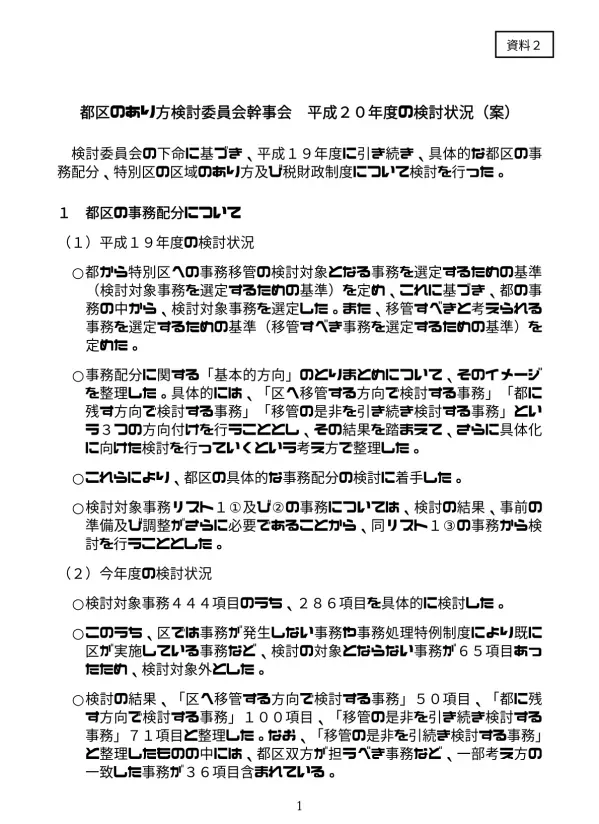
都区事務配分:20年度検討状況
文書情報
| 著者 | 都区のあり方検討委員会幹事会 |
| 出版年 | 2008 |
| 文書タイプ | 報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 657.26 KB |
概要
I.東京23区の区域再編に関する都区協議の現状と課題
本資料は、東京都と23特別区による東京23区再編に関する検討委員会の記録をまとめたものです。協議の中心は、特別区区域再編と事務配分のあり方に関する議論です。東京都は、日常生活圏の拡大、行財政基盤強化、行政改革推進、税源偏在是正の4つの視点から再編の必要性を主張しています。一方、特別区側は、各区の独自性を尊重し、基礎自治体としてのあり方を構築する中で主体的に判断すべきとの立場を示しています。 具体的な事務配分については、都と区の意見が一致しない項目が多く、移管の是非を引き続き検討する事務として保留されているものが多数存在します。 検討過程では、東京商工会議所や森記念財団、浅見泰司教授らの再編案なども参考資料として提示され、議論の材料となっています。 人口50万人以上の規模を想定した東京都の評価や、夜間人口を対象とした行政サービスに関する各区比較なども重要な論点となっています。 地方分権改革の動向も考慮する必要があり、今後の協議の行方は不透明です。
1. 都と区の対立する立場 23区再編への異なるアプローチ
東京都と23特別区は、東京23区の区域再編に関して対立する立場を取っています。東京都は、日常生活圏の拡大、行財政基盤の強化、行政改革の推進、税源偏在の是正という4つの観点を提示し、再編の必要性を訴えています。これに対し、特別区側は、23区が統一的な見解を持つ問題ではなく、それぞれの区や地域のあり方に係わるものであると反論。都区の役割分担を明確にした上で、それぞれの区が基礎自治体として主体的に判断すべきだと主張しています。この対立は、再編議論における大きな障壁となっています。東京都は「再編を含む区域のあり方について、議論が必要である」という合意に基づき、真摯な議論を促していますが、特別区側の自主性重視の姿勢との間で溝が見られます。平成19年度には事務配分の検討において方向付けができなかった項目が158項目にのぼるなど、具体的な合意形成には至っていません。今後の協議において、この根本的な立場の違いをいかに克服していくかが重要な課題となります。
2. 事務配分の難航 都と区の意見対立と今後の課題
事務配分の検討においては、都と区の間で多くの意見の相違が見られました。上水道や公共下水道といった事業は、事業全体を一体的に処理する必要性から都に残すべきだと東京都は主張する一方、特別区側は複数区による共同処理で区が担えると反論しています。東京都は、区への移管にはメリットを明確に示すよう求めていますが、区側は、都でなければできない理由がない限り、まずは区に移管する方向で検討すべきだと主張し、意見の対立が解消されずにいます。この様な状況から、児童相談所設置などの児童福祉関連事務や、更生相談所設置などの身体障害者福祉関連事務など、多くの項目が「移管の是非を引き続き検討する事務」として保留されています。特に、指定区間外国道管理などに関する事務は、都道の一部を区が担うかどうかの議論が難航しており、従来の「引き続き検討」とは異なるニュアンスを持つ重要な論点となっています。これらの事務配分に関する問題を解決するためには、都と区の双方が柔軟な姿勢で議論を進めることが不可欠です。
3. 特別区再編案の多様性と比較検討 諸外国の制度との比較も視野に
特別区の区域再編案は、都心部や中心部を統合する案、中心部と周辺部を統合する案、全区域を統合する案など、様々な類型が提示されています。東京都は、これらの再編案の概要や、夜間人口を対象とした行政サービスに関する各区の人口千人当たりの職員数や歳出額の試算結果を提示し、質疑応答を行っています。 さらに、森記念財団や浅見泰司教授らの再編案、東京商工会議所の提言「東京23区部を一体とする新たな『東京市』へ」といった民間機関からの提案も参考資料として提示されています。特別区の昼夜間人口比率や就業・通学者の自区内完結率の状況を他都市と比較する資料や、東京都自治制度懇談会報告と特別区制度調査会報告の比較分析、これらの報告に対する様々な意見も検討材料として挙げられています。 諸外国の大都市制度(ロンドン、パリ、ニューヨーク、ソウルなど)との比較を通して、東京23区の再編問題に対する多様な視点を提示し、議論を深める試みが見られます。 これらの多様な情報と比較検討を通じて、最適な再編案を選択していく必要があります。
II.都区間の事務配分に関する議論
事務配分に関する議論では、上水道や公共下水道など、事業全体の一体的処理が必要な事務は都に残すべきか、複数区による共同処理で区に移管できるか、といった論点が争点となっています。 都側は、移管によるメリットを示すよう求めており、区側は、都でなければできない理由がなければ区に移管すべきだと主張しています。 検討対象事務は多数あり、都と区の評価が一致しない項目は、移管の是非を引き続き検討する事務として分類され、今後の詳細な検討が必要です。 議論では、児童福祉や障害者福祉に関する事務、都市計画、建築許可など、多くの分野で都区間の意見対立が見られました。 国への法改正要請も視野に入れた慎重な検討が求められています。
1. 上水道 公共下水道事務に関する議論 都と区の対立と妥協点の模索
東京都と23特別区の間では、上水道と公共下水道に関する事務の配分について激しい議論が交わされました。東京都側は、これらの事務は事業全体の一体的処理が必要なため、「都に残す方向で検討する事務」とするべきだと主張しました。これに対し、特別区側は、複数区による共同処理が可能であれば区が担える事務であり、「区に移管する方向で検討する事務」とするべきだと反論しました。特別区側は、都でなければできない明確な理由がない限り、まずは区への移管を検討すべきだと主張し、東京都側は移管のメリットを示すよう求めるなど、両者の間には大きな隔たりがありました。 最終的には、都側の評価は特別区の人口規模が50万人以上の場合を想定したものであり、その点を踏まえつつ、具体的な留意点を協議の上、「区へ移管する方向で検討する事務」として整理されました。しかし、この合意に至るまでには、相当の議論と妥協が必要であったことが伺えます。今後の具体的な事務移管に向けた協議においても、同様の困難が予想されます。
2. 児童福祉 障害者福祉関連事務 移管の是非に関する継続検討
児童相談所設置など児童福祉に関する事務、更生相談所設置など身体障害者の福祉に関する事務などについても、都と区の間で意見が対立しました。これらの事務については、都と区の評価が分かれ、「移管の是非を引き続き検討する事務」として分類されました。具体的には、児童福祉関連事務のうち2項目と、身体障害者福祉関連事務のうち5項目が継続検討の対象となっています。 このことは、これらの分野における都と区の役割分担について、まだ合意に至っていないことを示しています。これらの事務の移管は、住民サービスの質や効率性に大きな影響を与える可能性があるため、慎重な検討が必要不可欠です。 今後の検討においては、住民ニーズや事業効率性、財政負担など多角的な視点からの評価と、都と区の積極的な情報共有と合意形成が求められます。
3. その他の事務 移管方向 保留 継続検討の分類と今後の調整
その他の多くの事務についても、都と区の間で様々な議論が行われました。その結果、いくつかの事務は「区へ移管する方向で検討する事務」として整理されましたが、一方で「移管の是非を引き続き検討する事務」として保留されたものも多く存在します。例えば、都区の意見が一致しなかった「住宅改良区域内の建築行為の許可などに関する事務」や「被災市街地復興支援地域内の建築行為許可などに関する事務」などは、とりあえず「移管の是非を引き続き検討する事務」として分類されましたが、別途整理方法の工夫が必要とされています。「都市計画決定に関する事務」や「住宅街区整備事業の認可などに関する事務」なども同様です。 これらの事務については、今後の検討において、都と区の双方から出された留意点を踏まえ、より具体的な議論を行い、最終的な結論を導き出す必要があります。 さらに、検討対象外となる事務や、事務の性質や関連事務の整理状況から基本的な方向性の整理が可能な事務については、都区の事務局で調整の上、今後の幹事会で確認される予定です。
4. 都と区の評価不一致事例と今後の対応 法改正の可能性も視野に
協議においては、「中央卸売市場の開設などに関する事務」や「一級河川の管理などに関する事務」など、都と区の評価が一致しなかった項目も複数ありました。これらの事務については、「移管の是非を引き続き検討する事務」として分類され、別途整理方法の工夫が必要とされています。 また、「特定周辺整備地区の指定などに関する事務」など、都区の評価が分かれた項目も存在し、これらも「移管の是非を引き続き検討する事務」として整理されています。 これらの事例は、都と区の間で事務の役割分担に関する認識に相違があることを示しています。今後の議論では、これらの相違点を解消するために、それぞれの事務の特性や、事業効率性、住民サービスの質など様々な観点を総合的に考慮した上で、より詳細な検討が必要となるでしょう。必要に応じて、国への法改正要請も視野に入れて検討を進める必要があると示唆されています。
III.特別区区域再編案の現状と比較検討
特別区区域再編案については、都心部統合、中心部・周辺部統合、全区域統合など様々な類型が提示されています。 森記念財団や浅見泰司教授らの案、東京商工会議所の提言なども参考に、昼夜間人口比率や就業・通学者の自区内完結率、人口規模・財政規模の格差拡大といった要因も考慮した上で検討が進められています。 諸外国の大都市制度(ロンドン、パリ、ニューヨーク、ソウル)との比較なども行われ、行政区域と経済圏の一致しないことによる不都合なども議論の対象となっています。 これらの再編案に基づくシミュレーション結果も提示され、再編後の特別区の姿や行政圏との関係などが検討されています。
1. 再編案の基本類型と民間機関の提案 多様なアプローチの検討
東京都による特別区区域再編案の検討では、都心部・中心部を統合する考え方、中心部・周辺部を統合する考え方、全区域を統合する考え方、その他といった基本的な類型が示されています。 この検討においては、東京都議会の行財政改革基本問題特別委員会の資料なども参考とされ、多角的な視点からの検討が行われています。 さらに、民間研究機関からの具体的な再編案も重要な情報源となっています。財団法人森記念財団の「東京・『6都市+自主区』まちづくり会議構想」、浅見泰司教授他による「東京23区の再編」といった提案は、それぞれの基本認識、検討視点、再編案といった観点から詳細に検討されています。東京商工会議所が発表した「東京23区部を一体とする新たな『東京市』へ」という提言も、重要な参考資料として議論に取り入れられています。これらの多様な再編案は、それぞれ異なるメリット・デメリットを持つため、それぞれの案を比較検討し、最適な再編案を選択することが必要です。 特に、これらの再編案が既存の行政圏や住民の日常生活圏にどのような影響を与えるのかという点について、綿密な検討が求められています。
2. 再編案に基づくシミュレーション 行政圏との関係性と課題
検討委員会では、提示された様々な再編案について、シミュレーションが行われています。 具体的には、再編後の特別区がどのような姿になるのか、行政圏との関係がどうなるのかといった点について、図表を用いて分析されています。 これらのシミュレーションは、再編案の具体的な効果や影響を予測し、その妥当性を検証する上で重要な役割を果たしています。 シミュレーションの結果、再編案によっては、住民の日常生活圏との整合性や、行政サービスの提供効率性に課題が生じる可能性も示唆されています。 そのため、シミュレーション結果を踏まえ、住民への影響を最小限に抑え、行政効率性を向上させるための具体的な対策を検討していく必要があります。 また、シミュレーションの精度を高めるためにも、さらなるデータ収集や分析が必要となるでしょう。
3. 諸外国の大都市制度との比較 制度設計における参考事例
東京23区の再編問題を検討する上で、諸外国の大都市制度との比較も重要な要素となっています。 資料では、ロンドン(イギリス)、パリ(フランス)、ニューヨーク(アメリカ)、ソウル(韓国)といった大都市の制度と、東京の制度を比較することで、それぞれの国の地方自治制度、都市の自治制度、都市を構成する団体の自治制度、地域自治組織について分析が行われています。 この比較を通して、それぞれの制度の長所・短所を明確にし、東京23区の再編における最適な制度設計に活かしていくことが目指されています。 諸外国の制度を参考に、東京23区の再編によってどのような効果が期待できるのか、あるいはどのような課題が予想されるのかを明らかにすることで、より効果的かつ現実的な再編計画を策定することが期待されます。 ただし、各国の社会・経済状況や歴史的背景が異なるため、単純な比較だけでは不十分であり、それぞれの国の制度の特徴を丁寧に分析し、日本の状況に適応可能な要素を抽出し、検討していく必要があります。
