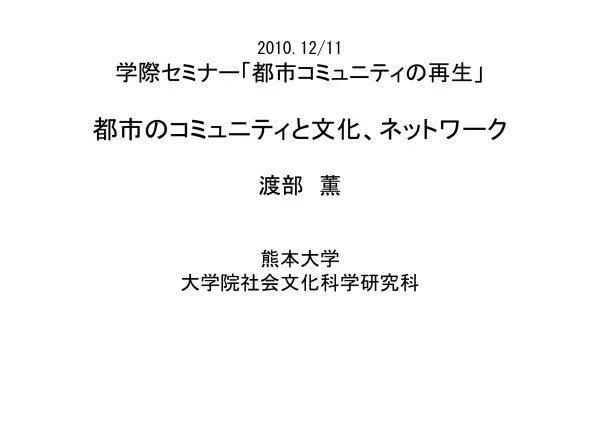
都市コミュニティ再生:文化・ネットワーク視点
文書情報
| 著者 | 渡部 薫 |
| 専攻 | 都市計画、社会学、経済学など |
| 文書タイプ | 学際セミナー講演資料 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 664.53 KB |
概要
I.都市コミュニティの再生と多様なネットワーク 文化 と 経済 の視点
本講演は、経済的活力と創造性を導く都市のあり方を、都市再生という文脈で考察しています。特に、多様なコミュニティ(地縁的、職場のコミュニティ、テーマ・コミュニティなど)と、文化、ネットワークの三要素に着目し、それらの相互作用による地域活性化の可能性を探っています。創造都市論の視点を取り入れ、Jane Jacobs、Charles Landry、Richard Floridaらの研究成果も参照しながら、都市計画、文化政策、そしてコミュニティビジネスの成功事例(長浜市の黒壁事例など)を分析することで、持続可能な都市再生のための戦略を検討しています。
1. 講演の目的と都市コミュニティの多様性
このセクションでは、講演の目的として経済的活力と新たな創造性を導く都市の姿を模索し、その上で都市コミュニティをどのように捉えるべきか検討することが示されています。都市コミュニティは、自治会のような地縁的な結合だけでなく、職場コミュニティやテーマ・コミュニティなど、多様なコミュニティの複合体として定義されています。これらの多様なコミュニティの相互作用が、都市の活性化に重要な役割を果たすという考え方が示唆されています。 具体的には、経済的活性化、創造性、そして文化とネットワークという2つの視点を導入することで、多様なコミュニティの相互関係と、それらが都市再生にどう寄与するかを分析する枠組みが提示されています。都市コミュニティを単一的なものではなく、多層的で複合的な構造体と捉えることが、本講演の重要な出発点となっています。様々なタイプのコミュニティが複雑に絡み合い、都市全体の活力に影響を与えている点を明確に示しています。
2. 文化経済とコミュニティ ネットワークへの経済学的関心
このセクションでは、現代社会における「文化経済時代」という文脈の中で、文化が都市再生において重要な役割を担っていることが強調されています。特に、経済パフォーマンスにおけるローカルコミュニティとネットワークの重要性が指摘されており、シリコンバレーを例に、地域内のネットワークが創造性とイノベーションを生み出す原動力となることが説明されています。変化の激しい市場への柔軟な対応や産業クラスターの形成においても、ローカルなコミュニティにおける知識の共有と創造、暗黙知の活用が不可欠であると論じられています。コミュニティとネットワークは明確に区別されず、相互に作用しあいながら経済活動に影響を与えていると捉えられています。ローカルな知識の共有や暗黙知の創造・共有・伝播が、経済的パフォーマンス向上に大きく貢献する可能性が示唆されています。これは、単なる経済活動だけでなく、地域固有の文化や知識が経済的価値を生み出すという文化経済的な視点に基づいています。
3. ジェーン ジェイコブスの主張と都市の多様性
このセクションは、ジェーン・ジェイコブスの都市論、『アメリカ大都市の死と生』を引用し、都市の多様性の重要性を強調しています。ジェイコブスは、現代の都市計画が清潔さや安全性、快適さといった機能を過度に追求することで、都市コミュニティの複雑で濃密な社会的関係や多様性を損なってきたと批判しています。都市の多様性は、単に多様な人々が存在するということではなく、多様な人々が様々な形で結びつき、重層的で複合的なコミュニティを形成している状態として捉えられています。この多様なコミュニティ群が相互に結びつき、ネットワークを形成することで、新しいアイデアやイノベーションが生まれると論じています。これは、都市計画において、機能的な効率性だけでなく、人々の交流や多様な文化的要素を重視する必要性を示唆しています。多様なアクター間の相互作用が、都市の活力と創造性を生み出す根源であるという考え方が示されています。
4. 創造都市とコミュニティ ネットワーク 定義と条件
このセクションでは、「創造都市」の定義と条件について、チャールズ・ランドリーとリチャード・フロリダの主張を交えながら解説しています。創造都市は、脱工業化や知識社会化といった経済社会構造の変化への自律的な対応策であり、都市の持続可能な自立戦略として位置付けられています。創造都市のガバナンスの中核となるのは「創造性」であり、市民、企業、自治体、NPOなど様々なアクターの潜在能力を引き出し、活用することが重要だとされます。ランドリーは自由で創造的な文化活動の展開と文化インフラの充実を、フロリダは創造的階級を惹きつける魅力的な環境の構築を、それぞれ創造都市形成の鍵として挙げています。創造都市の条件としては、異質な要素の受容、アクター間の創造的なネットワーク、アクターの創造的潜在能力を高める機会、そして創造活動を支える社会的・文化的基盤の形成などが挙げられています。創造都市戦略は、これらの要素間のインタラクティブな関係を重視した総合政策であるべきだと結論付けています。
II.多様なアクターと ネットワーク による 創造性 の促進
都市の多様性、すなわち異質なアクター(市民、企業、自治体、NPOなど)が、複雑なネットワークを形成することで、創造性とイノベーションが生まれることを強調しています。異なる背景を持つ人々の交流と相互作用が、新しいアイデアや事業を生み出す原動力となることを、モントリオールの文化創造企業(Ubisoft、Cirque du Soleilなど)と地域のコミュニティの連携事例を基に説明しています。さらに、英国のリヴァプールやマンチェスターにおけるポピュラー音楽シーンのネットワーク構造も分析し、都市全体が一つのネットワーク組織として機能する可能性を示唆しています。キーワード:産業クラスター、暗黙知。
1. モントリオールの文化創造企業と地域コミュニティの連携
このセクションでは、カナダ・モントリオールを例に、文化創造企業と地域コミュニティの連携による創造性促進について論じています。UbisoftやCirque du Soleilといった世界的に有名な文化創造産業が立地するモントリオールでは、これらの企業が巨大な研究開発部門を持たず、その創造的能力は都市内の多様なコミュニティに依存している点が指摘されています。クリエイティブな人材は、専門家コミュニティに加え、趣味的なコミュニティにも属しており、これらのコミュニティが人材供給源として、そして文化創造能力の源泉として機能している様子が説明されています。企業はプロジェクト運営においてこれらのコミュニティから人材を調達し、コミュニティで育まれた能力を活用する「プロジェクト・ネットワーク」を形成することで、創造性を維持・発展させていると分析されています。このモデルは、企業とコミュニティの密接な連携が、創造性とイノベーションを促進する上で非常に重要であることを示唆しています。
2. 英国における文化産業と文化コミュニティのネットワーク
英国のリヴァプールやマンチェスターにおけるポピュラー音楽シーンが、オーディエンスを中心とした文化コミュニティ、ミュージシャン、音楽事業者、音楽ジャーナリスト、演奏空間などが複雑に絡み合ったネットワークを形成し、音楽活動を支えている事例が紹介されています。この事例は、特定の文化産業を取り巻く、多様なアクターによる強固なネットワークの重要性を示しています。これらのネットワークは、単なる人的繋がりを超え、情報や資源の共有、そして相互作用を通して、文化産業の活性化、ひいては地域経済の活性化にも大きく貢献していると考えられます。このセクションは、特定の産業だけでなく、より広範な文化活動においても、コミュニティとネットワークの連携が創造性とイノベーションを促進する鍵となることを示しています。
3. ネットワーク組織としての都市 柔軟性と創造性の源泉
このセクションでは、複数の個人、集団、組織が特定の共通目的のために、社会ネットワークを媒介に柔軟に結合する「ネットワーク組織」という概念が導入されています。この組織形態は、境界があいまいで(ボーダレス)、分権的・自律的に意思決定できるという特徴を持ち、変化への柔軟な対応と自己革新能力の高さ、そして高い創造性と革新性を備えていると説明されています。モントリオールやマンチェスターの事例は、都市全体が一つのネットワーク組織として機能している状態を示していると捉えられています。これは、都市の活性化には、階層的な組織構造ではなく、水平的で柔軟なネットワーク構造が不可欠であるという考え方を示しています。 様々なアクターが自律的に活動しながらも、相互に連携することで、都市全体の創造性を高め、持続的な発展を可能にしているという視点が提示されています。
III. 文化政策 と コミュニティ ビジネス による 地域活性化 成功事例分析
長浜市の黒壁事例は、コミュニティビジネスと文化政策(秀吉博覧会など)が地域活性化に貢献した好例として分析されています。衰退した中心市街地の再生において、ガラス事業を中心とした店舗展開と文化イベント開催により、市民参加型のネットワークが形成され、観光客増加と経済効果をもたらしました。この事例から、非営利的な活動が地域の魅力を生み出し、事業の利益にも繋がるコミュニティビジネスの成功モデルが示されています。キーワード:経済活性化。
1. 長浜市の黒壁 コミュニティ ビジネスと地域活性化
このセクションでは、滋賀県長浜市の「黒壁」を事例に、コミュニティ・ビジネスと文化政策がどのように地域活性化に貢献したかを分析しています。1989年、衰退した中心市街地の再生を目的として、保存建築物を利用したガラス事業を中心とした店舗展開が開始されました。その後、黒壁の理念に賛同する事業者の参入により、34店舗に及ぶ「黒壁グループ」が形成されました。黒壁の活動は、ガラスの製作・展示・販売だけでなく、建物の活用を通じた街並みの保存・整備にも貢献しており、来街者数は1989年の約10万人から2001年には200万人を超えるまでに増加しました。黒壁は、単なる事業活動にとどまらず、長浜のまちづくり推進ネットワークの中核として機能し、多くの市民活動組織の誕生と、黒壁を中心としたまちづくりネットワークの形成を促しました。これは、事業の利益追求と同時に、地域社会への貢献を両立させた成功事例と言えるでしょう。非営利的な側面が地域活性化を促進し、それが事業の持続可能性を支える好循環が生まれている点が注目されます。
2. 秀吉博覧会とネットワークの複合化 新たな事業創成への契機
1996年に開催された「北近江秀吉博覧会」は、長浜市の歴史・伝統・まちづくりの方向性を再確認し、新たな発展の契機となるイベントでした。1000人を超えるボランティア参加など、多くの市民が積極的に関与しました。黒壁グループ、青年会議所、商店街、市役所、市民活動団体、高齢者など、普段はあまり接点のなかった様々な人々が協働する経験は、市内のネットワークを複合化させる上で重要な役割を果たしました。秀吉博覧会は、共通の目的・理念を掲げることで、市民の長浜に対する思いを引き出し、市民参加と協働を促進しました。それまで点在していた様々なネットワークが交差し、複合化されたことで、新たな事業創成や地域活性化の土壌が形成されたと分析されています。イベントを契機とした市民参加とネットワークの複合化が、地域活性化に大きく貢献した好例と言えるでしょう。
3. 黒壁事例とグラスゴーのヨーロッパ文化首都 文化政策の効果
黒壁の事例と、英国グラスゴーのヨーロッパ文化首都選定事例は、文化政策や文化プロジェクトが地域活性化に及ぼす効果を考察する上で重要な比較対象となっています。長浜市の黒壁は、コミュニティ・ビジネスとしての成功モデルを示しており、地域の魅力を生み出すことで事業そのものの利益にも繋がっている点が強調されています。一方、グラスゴーは、戦後の経済衰退を克服するため、文化都市という新しいイメージ戦略を採用しました。この戦略は、地域社会内部で論争を巻き起こす一方、地域アイデンティティの活性化に繋がりました。ヨーロッパ文化首都イベントへの参加と、文化都市イメージに関する論争は、地域住民を結びつける力となり、当初は限定的であった文化都市構想への支持を、地域全体へと拡大させました。これらの事例は、文化政策が地域活性化に貢献する際に、単なるイベント開催だけでなく、市民参加や地域ネットワークの形成が不可欠であることを示唆しています。
IV.都市のイメージ戦略と 地域アイデンティティ の活性化 グラスゴーの事例
グラスゴーのヨーロッパ文化首都選定は、都市イメージの変革と地域アイデンティティの活性化に貢献した事例として紹介されています。当初は限定的であった文化都市構想への支持が、イベントへの参加や議論を通じて、地域住民全体へと拡大しました。このプロセスにおいて、様々なコミュニティが結びつき、ネットワークが形成されたことが示されています。
1. グラスゴーの戦後経済と文化都市戦略
このセクションは、スコットランドの中心都市であるグラスゴーの戦後経済の衰退から始まる。エディンバラと並ぶ大都市であったグラスゴーは、戦後、経済的に大きな打撃を受けました。この状況を打開するために、グラスゴーは「文化都市」という新たな地域イメージ戦略を採用することになります。この戦略は、単なる経済活性化策ではなく、都市のアイデンティティを再構築し、地域住民の意識を変革しようとする、より包括的な取り組みであったことが分かります。 経済的な衰退という厳しい状況下で、新たな地域イメージを打ち出し、地域住民の意識改革と経済再生を同時に目指した、大胆な戦略転換が試みられたことがわかります。
2. 文化都市イメージと地域アイデンティティの活性化 論争と統合
「文化都市」という新しい地域イメージは、グラスゴーの地域社会内部で様々な論争を引き起こしました。この論争は、地域アイデンティティを巡る様々な意見や立場が顕在化した結果であり、決してネガティブな現象ではありませんでした。むしろ、この論争のプロセスを通して、地域住民の文化都市に対する関心が高まり、多様なコミュニティが関与するようになりました。ヨーロッパ文化首都という大規模なイベントへの取り組みは、地域住民の参加と協働を促し、文化都市というイメージを共有する基盤を築きました。当初はビジネス界、行政関係者、芸術家などに限られていた文化都市への積極的な支持が、このイベントと論争を通して他のコミュニティにも広がり、地域全体のアイデンティティを活性化させたのです。論争を通して、地域住民の意見や考え方が共有され、共通のビジョンが形成された点が注目されます。
