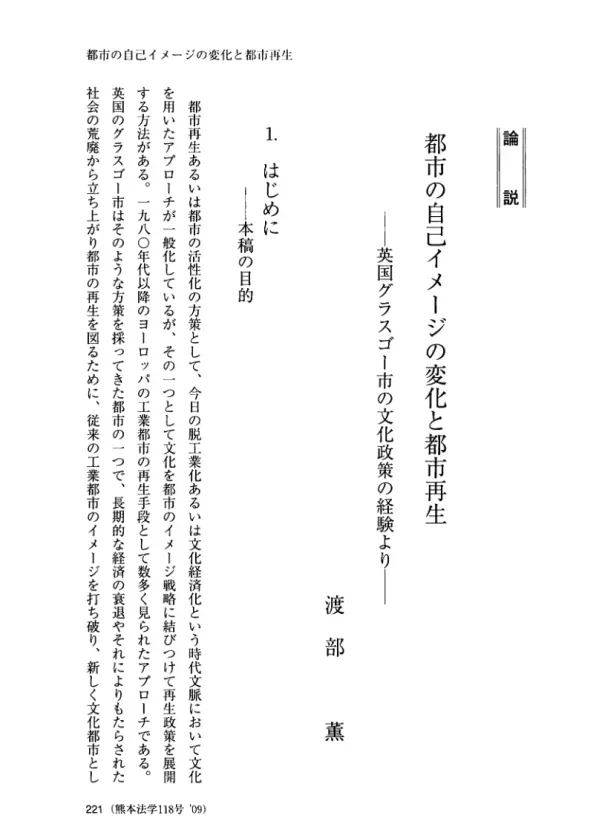
都市再生:自己イメージ変容と文化政策
文書情報
| 著者 | 渡部 |
| 専攻 | 都市計画、地理学、文化政策関連分野 |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.41 MB |
概要
I.都市イメージの変化と都市再生 グラスゴー市 の事例研究
本論文は、都市再生における都市イメージの重要性、特にイメージ戦略が地域活性化に及ぼす影響を、英国グラスゴー市の事例を通して検証する。グラスゴー市は、1980年代以降の脱工業化政策として、文化政策を積極的に導入し、イメージの再構築を試みた。従来の工業都市のイメージから、文化都市へと変貌を遂げる戦略である。
1. グラスゴー市の現状と都市再生への課題
20世紀初頭、グラスゴーは造船業などを中心とした重工業都市として発展しましたが、第一次世界大戦後から経済は低迷。第二次世界大戦後の復興期にも、新しい産業は台頭せず、重工業への依存は続きました。1960~70年代には製造業が衰退し、高い失業率に悩まされるようになります。この経済的衰退は社会の荒廃をもたらし、都市再生が喫緊の課題となりました。従来の工業都市としてのネガティブなイメージを払拭し、新たな発展の道を模索することが必要不可欠でした。この状況を打開するため、グラスゴー市は1980年代以降、文化政策による都市再生という新たなアプローチを採用することになります。これは、観光客や投資を誘致し、サービス産業や新たな産業の創出を促進するための戦略的転換でした。長年の経済低迷と社会問題からの脱却、そして都市イメージの刷新が、文化政策導入の背景となっています。
2. 文化政策導入の背景と都市イメージ戦略
グラスゴー市が文化政策を導入した背景には、長年にわたる経済低迷とそれに伴う社会問題への対応、そして、都市イメージの転換という明確な目的がありました。約40年間続いた政治的分裂も、新しい経済基盤を求める共通の認識によって克服され、労働党の市政運営下で脱工業化政策、ひいては文化政策が本格的に開始されます。この文化政策の中核は、都市イメージ戦略です。古くからの工業都市としての負のイメージを払拭し、文化都市としての魅力的なイメージを内外に発信することで、観光客や投資を呼び込み、経済の活性化を図ろうという狙いがありました。この戦略は、既存のイメージを覆すための積極的な取り組みであり、単なるイメージアップキャンペーンではなく、都市再生のための包括的な戦略の一部として位置付けられています。そのため、具体的な文化施設の整備、歴史的遺産の活用、都市景観の改善など、多角的な施策が展開されました。
3. 文化政策による経済的再生と社会変容
グラスゴー市の文化政策は、当初想定された外部への効果(観光客誘致、投資促進)に加え、地域社会自体の変容という重要な副次的効果をもたらしました。サービス産業、特に観光業の拡大、新産業の創出といった経済的な再生は、文化政策によって醸成された肯定的な都市イメージと、それを支える地域社会の活性化があってこそ実現したと考えられます。新しい都市イメージは、市民に肯定的なメッセージを与え、地域への誇りや愛着を育むことに貢献しました。この自己イメージの変化は、地域社会全体の活性化、経済活動の活発化、そして新しい産業への取り組みを可能にする土壌を形成したのです。したがって、グラスゴー市の文化政策は、経済再生という直接的な目標だけでなく、社会変容という間接的な効果も大きく生み出したと言えるでしょう。この成功要因を分析することは、他の都市の再生政策を考える上で重要な示唆を与えます。
II.地域イメージの変化と地域社会への影響
地域イメージの変化は、住民の自己イメージにも影響を及ぼす。グラスゴー市では、新たな都市イメージの提示によって、市民の地域に対する意識やアイデンティティに変化が生じ、これが地域社会の変容を促したと推測される。この過程では、新しい都市イメージの受容、疑問、拒否といった多様な反応が見られた。文化政策によるイメージ戦略は、単なる外部へのアピールにとどまらず、市民自身の地域への肯定的な見方を醸成する役割を果たした。
1. 地域イメージの定義と先行研究
地域イメージとは、地域に関する様々な解釈可能性の中から選択的に構成された表象であり、同時に何らかの意味付与がなされたものと定義されます。例えば、グラスゴー市はかつて工業都市として認識され、19世紀には力や技術、繁栄を象徴していましたが、70~80年代には公害や衰退といったネガティブな意味合いを持つようになりました。地域イメージは、外部からの視点と住民自身の視点(自己イメージ)の両方を含み、両者の相互作用によって住民間の共通認識が形成されます。先行研究では、ケヴィン・リンチの研究以降、都市計画や地理学の分野で地域イメージの構成要素(住民意識、空間構造、環境要因)に関する研究が多く行われてきました。しかし、地域活性化との関連では、外部からのイメージに関する議論が中心であり、住民の自己イメージの変化とその影響については十分に検討されていませんでした。本稿では、この点を補完し、地域イメージの変化が地域社会に与える影響を理論的に考察します。
2. 新しい地域イメージへの市民の反応
新しい地域イメージが提示された時、市民はどのように反応するのでしょうか。それは、自分たちの地域についての再定義であり、地域に対する意味づけの変化を意味します。個々の市民は、それぞれ異なる関心の度合いで地域イメージを持っていますが、新たに提示されたイメージは、その既存のイメージに揺らぎをもたらす可能性があります。考えられる反応としては、A. 新しいイメージを受容する、B. 新しいイメージに疑問を呈する、C. 新しいイメージを拒否する、D. 無関心といった四つのタイプが挙げられます。単純な拒否反応(C)は少なく、多くの場合、新しいイメージに対して問いを発する(B)反応が伴うと考えられます。この反応は、地域社会にどのような影響を与えるのでしょうか。地域イメージは地域についての意味づけを提示するものであるため、新しいイメージの受容は、その意味づけに伴う反応を通して地域社会に変化をもたらすと考えられます。
3. 解釈主義的社会学の視点からの考察
新しい地域イメージの受容と地域社会への影響を解釈主義的社会学の視点から考察します。解釈主義社会学は、個人の行為や社会的関係における主観的な意味を重視し、社会的世界は人間主体による意味づけによって構成されると主張します。この視点からすると、新しい地域イメージの意味の提示は、市民の地域に対する意味づけへの意識を高め、既存の解釈枠組みを修正したり、新たな意味を問う動きを促したりすると考えられます。しかし、解釈主義社会学には、主観的な意味を重視しすぎるあまり、物質的な活動や客観的な構造を軽視する傾向があるという批判もあります。本稿では、意味づけの重要性を認めつつも、都市の経済的再生という現実的な目標を考慮し、意味と具体的な活動の両面を重視した考察を進めます。新しい地域イメージの受容は、単なる認知的な変化ではなく、具体的な行動や社会関係の変化をもたらすという点を明らかにする必要があります。
4. 地域イメージの受容と地域文化の変容
戦略的に提示された新しい地域イメージは、地域に関するメッセージを含んでいます。市民は、その意味を額面通りに受け入れるか、独自の解釈を加えるかは別として、そのイメージを受容します。しかし、新しいイメージに付与された意味が、既存の解釈枠組みでは処理できない場合、その意味の受容に伴い、解釈枠組み自体が変化します。これは、市民の地域に関する意味づけの受容によって、解釈枠組みが変化することを意味します。坂下の議論を援用すると、組織成員の手持ちの意味体系の変化が集合的に現れるとき、組織文化の変容を意味すると考えられます。同様に、地域住民の解釈枠組みの変化が集合的に、間主観的に現れるとき、地域文化の変容を意味します。しかし、イメージの受容だけで地域文化が変化するのか、変化するとしてもどの程度なのかという疑問が残ります。イメージの受容という認知的な現象が、人々の行動や関係にどう影響するのかを検討する必要があります。
5. 地域における解釈枠組みの間主観化と地域アイデンティティ
地域イメージの受容に伴う解釈枠組みの変化が、地域社会全体で共有される(間主観化される)ためには、どのような条件が必要でしょうか。地域が市民にとって重要な環境として認知され、市民間の相互作用が活発に行われる状況が必要です。通常、地域に対する関心や帰属意識は希薄ですが、何らかの契機によって共通の関心が生まれ、市民間の相互作用を通じて地域に対する認知枠組みが活性化される必要があります。そのような状況下で、地域メンバーとしての自己認識が共有され、生活基盤としての共通認識が生まれることで、地域文化の共有化が可能になります。しかし、新しい地域イメージの受容は必ずしもスムーズではありません。既存の解釈枠組みとの葛藤が生じ、地域の意味づけをめぐる議論や競合が起こる可能性があります。この過程を通して、地域アイデンティティが再構築されると考えられます。
III.グラスゴー市の文化政策 イメージ戦略 と経済的成果
グラスゴー市の文化政策は、イメージ戦略と経済的活性化を目的とした。ヨーロッパ文化首都の開催やマイルズベター・キャンペーンといったイメージ向上キャンペーンが展開され、観光客誘致や投資促進に成功した。文化施設整備などの文化環境の改善も進められ、サービス産業や創造産業の発展にも繋がった。しかし、文化政策はエリート層に偏向する傾向があり、市民全体への影響にはばらつきがあった点も指摘されている。
1. 文化政策の展開 イメージ戦略を中心とした取り組み
1980年代以降、グラスゴー市は経済構造の変動を背景に、脱工業化政策の一環として文化政策を導入しました。約40年にわたる市政の政治的分裂を乗り越え、民間セクターの活性化を目指したネオリベラルな政策の流れの中で、文化政策が都市再生戦略の中核となりました。この政策は明確な青写真に基づいて展開されたわけではなく、手探り的な要素もありましたが、その中心は都市イメージ戦略でした。既存の工業都市としての負のイメージを払拭し、活気と繁栄に満ちた文化都市という新しいイメージを創造することが、経済再生のための重要なステップと位置づけられました。そのため、1983年に開始されたマイルズベター・キャンペーンを始めとするイメージ・キャンペーンや、1990年のヨーロッパ文化首都開催など、大規模なイベントが展開されました。これらの施策は、グラスゴー市の内外に新しいイメージを提示し、観光客や投資家を誘致することを目的としていました。同時に、都市景観の改善や文化施設の整備といったハード面での取り組みも進められました。グラスゴー・シティ・イニシアティブなどの都市開発プロジェクトもこの政策の一環として実施され、都市環境の向上に貢献しました。
2. ヨーロッパ文化首都と文化イベントの創設
グラスゴー市は1990年のヨーロッパ文化首都に選出されました。これは、国際的な知名度向上と文化ツーリズムの促進を目的とした戦略的な選択でした。それまでヨーロッパ文化首都となった都市は、アテネやパリなど、既に国際的な評価を得ている都市でしたが、グラスゴーは文化首都という称号を、文化都市としての地位を確立するためのステップとして活用しようとしたのです。そのため、文化首都年においては、英国内外からの注目を集める大規模なイベントの開催が重視されました。旅行会社によるスコットランドツアーではグラスゴーが十分に注目されていなかったため、国際ジャズ・フェスティバル、合唱祭、フォーク・ミュージック&ダンス・フェスティバルといった新たな文化イベントが創設されました。これらのイベントは、グラスゴーの文化的豊かさを内外にアピールし、文化ツーリズムの拡大に貢献しました。また、グラスゴー・ガーデン・フェスティバルなど、国家的な規模のイベントも開催され、成功を収めました。これらのイベントは、グラスゴーの新しいイメージを、特に旅行者の間で広める上で重要な役割を果たしました。
3. 文化政策の経済的成果と課題
グラスゴー市の文化政策は、経済的な成果を挙げました。マイャズコフの調査によると、ヨーロッパ文化首都年は、純収益と雇用創出に大きく貢献しました。観光産業の拡大も著しく、1999年には全産業の7%を占めるまでに成長しました。さらに、デジタル・メディア・クォーターやグラスゴー・サイエンス・センターといった新たな文化施設の整備、そして知識集約型産業の発展も目覚ましく、経済の多角化が進みました。しかしながら、文化政策の支出総額は膨大であり、その正確な数字は把握できていません。文化政策は、経済再生という目的のための手段として利用された面があり、イベントは経済的利益やメディア効果、ツーリストへのアピールを重視した傾向が見られました。そのため、エリート的な芸術家に偏向した支援になってしまったのではないかという批判も存在します。また、文化政策が富裕層と貧困層の格差拡大に繋がったという指摘もあり、文化政策の公平性や包括性という課題も残されています。
4. 文化政策の意義と今後の展望
グラスゴー市の文化政策は、都市イメージの改善、文化消費の拡大、ツーリズムの発展、そして新産業の創出など、多様な効果をもたらしました。これらの変化は、文化政策単独によるものとは言い切れませんが、少なからず文化政策が貢献したことは明らかです。文化政策のロジックは、イメージ戦略を軸に消費環境を整え、新規投資を誘致し、新産業を形成するというものでした。実際には、イメージ・キャンペーンを強力に推進し、文化施設の整備、文化活動の振興、イベント開催などを統合的に進めることで、文化環境と消費環境が整備されました。その結果、文化消費やツーリズムが拡大し、新しいイメージに基づく新規投資が誘発され、創造産業を含む新たな産業が発展したと考えられます。しかし、この成功は、単なるイメージ戦略だけでなく、市民の自己認識の変化や地域社会の活性化という要素も大きく関わっていたと考えられます。新しいイメージは、市民に肯定的なメッセージを与え、地域への誇りや自信を取り戻すことに貢献したのです。この点をさらに深く検証していく必要があります。
IV.地域イメージ再構築と地域社会の変容 グラスゴー市 の経験から
グラスゴー市の事例分析から、新たな地域イメージの受容は、市民の解釈枠組みの変化、ひいては地域文化の変容につながる可能性が示唆される。ただし、この変化はスムーズではなく、既存のイメージとの葛藤や、地域の意味づけをめぐる議論を引き起こす。グラスゴー市では、文化都市という新しいイメージをめぐる論争が活発に行われ、これが地域アイデンティティの再構築を促したと結論づけられる。重要なのは、イメージ戦略に加え、具体的な政策やプロジェクトが、地域社会の活性化を後押しした点である。
1. グラスゴーにおける地域イメージの再構築と経済再生
グラスゴー市は、長期間にわたる経済低迷と社会問題からの脱却を目指し、文化政策を中心とした都市再生戦略を展開しました。この戦略において、地域イメージの再構築は重要な役割を果たしました。従来の工業都市としてのネガティブなイメージを払拭し、「活気があり、繁栄した大都市」という新しいポジティブなイメージを創造することで、外部からの投資や観光客の誘致を促進しようとしたのです。このイメージ戦略は、単に外部へのアピールにとどまらず、グラスゴー市民自身の自己認識にも大きな影響を与えました。新しい文化的なイメージは、市民に肯定的なメッセージを与え、地域社会全体の活性化を促す土壌を形成したと言えるでしょう。結果として、ツーリズムを中心としたサービス産業の拡大、そして新しい産業の創出という経済的な再生に繋がったと考えられます。この成功事例は、地域イメージ再構築の重要性を示唆しています。
2. 新しい地域イメージの受容と地域文化の変容メカニズム
新しい地域イメージが提示された際、市民はそれをどのように受け止めるのか、そしてそれが地域社会にどのような影響を与えるのかを考察します。論文では、新しいイメージの受容、疑問の呈示、拒否、無関心といった市民の反応パターンを提示しています。しかし、単純な拒否反応は少なく、多くの場合、新しいイメージに対する疑問や問いを発する反応が見られると推測されます。この新しいイメージの受容は、解釈主義的社会学の視点から考察されます。提示された新しい意味は、市民の地域に対する意味づけを促し、既存の解釈枠組みを修正、あるいは新たな解釈枠組みの採用につながる可能性があります。この解釈枠組みの変化が、集合的に共有されると、地域文化の変容へと繋がるという仮説が立てられています。この仮説の妥当性を検証するために、グラスゴー市の文化政策の経験が分析されます。地域イメージの変化は、地域社会の変容を導く一つの契機に過ぎないという点も考慮しなければなりません。
3. グラスゴー文化政策における地域アイデンティティの再構築
グラスゴー市の文化政策は、イメージ・キャンペーンを中心に展開され、新しい文化的なイメージは市民にも向けられました。市民は、整備された文化環境や様々な文化イベント、そしてメディアによる肯定的な報道を通して、新しいイメージを経験的に理解し、受け入れるようになりました。この過程で、グラスゴーという地域の意味づけをめぐる議論が活発化し、地域アイデンティティの再構築の動きが喚起されたと考えられます。「グラスゴーのグラスゴー」という展示イベントや「ザ・シップ」という演劇イベントは、グラスゴーの歴史や産業遺産に関する議論を巻き起こし、地域文化の多様な解釈が生まれました。この過程は、地域アイデンティティの再構築に大きく貢献したと言えるでしょう。しかし、文化政策は、エリート的な芸術家に偏向する傾向や、富裕層と貧困層の格差拡大といった批判も受けています。この点も踏まえて、地域イメージ再構築と地域社会変容のメカニズムを多角的に考察する必要があります。
4. 解釈枠組みの共有化と地域社会変容の課題
グラスゴーにおける地域イメージの再構築が、地域社会の活性化や経済再生につながったという推論を、地域イメージの変化が地域社会の変容を導くメカニズムに関する議論を用いて検討します。新しい地域イメージの受容が、地域文化の変容をもたらすかどうか、地域に対する関心が希薄な中で地域の意味づけをめぐる動きがどのように起こるのか、そして、意味のある相互作用がどの程度起こるのかといった課題が挙げられます。特に、解釈枠組みの共有化については、地域社会全体のコンセンサス形成が必ずしも必要ではなく、多様な意見や考え方の競合が地域文化の変化の契機となる可能性も示唆されています。グラスゴー市の文化政策は、市民の間で「文化都市」というイメージをめぐる論争や、地域の意味づけに関する多様な意見を引き起こしました。これらの相互作用が、地域文化の変容にどのように貢献したのかを、より詳細な調査を通して検証していく必要があります。また、文化政策以外の要因も考慮し、地域イメージの変化が地域社会変容に与えた影響を総合的に評価する必要があります。
V.結論 都市再生 における イメージ戦略 の有効性
グラスゴー市の事例は、都市再生においてイメージ戦略が重要な役割を果たすことを示している。文化政策による都市イメージの再構築は、経済的効果に加え、市民の自己イメージや地域への帰属意識を高める効果をもたらした。ただし、成功には、市民参加を促す政策運営や、多様な市民の意見を反映することが不可欠である。
1. グラスゴー市における地域イメージ再構築の成果と課題
グラスゴー市の都市再生における地域イメージ再構築の効果と課題について考察します。文化政策を中心とした一連の取り組みは、地域社会の活性化と経済再生に繋がり、市民のグラスゴーに対するイメージは大きく改善されました。観光客の増加や新規投資の誘致、そして創造産業の発展といった経済的成果は、イメージ戦略の成功を示しています。しかし、この成功は、文化政策のロジックに沿った展開だけでなく、創造された新しい地域イメージが市民の自己認識に変化を与え、地域社会の活性化を導いたという点にも注目する必要があります。つまり、新しいイメージは外部へのアピールだけでなく、市民自身の地域に対する肯定的な見方や誇りを育む役割を果たしたと言えるでしょう。一方、文化政策が富裕層と貧困層の格差拡大に繋がったという指摘もあり、イメージ戦略の効果は市民全体に均等に及んだとは言えない可能性も示唆されています。この点については、今後のより詳細な分析が必要となります。
2. 地域イメージ再構築のメカニズム 仮説の検証と検討事項
グラスゴー市の事例を通して、地域イメージの再構築が地域社会の変容を導くメカニズムを検討します。論文では、新しい地域イメージの受容が地域文化の変化をもたらすか、地域への関心が希薄な中で地域の意味づけをめぐる動きがどのように起こるのか、そして、意味のある相互作用がどの程度起こり、解釈枠組みの共有化に繋がるのかといった点が論点として挙げられています。これらの点に関して、グラスゴー市の文化政策の分析を通して仮説の妥当性を検証していきます。新しい地域イメージの受容は、市民個人の解釈枠組みの変化から始まり、それが集合的に、間主観的に現れることで地域文化の変容へと繋がると考えられます。しかし、この過程はスムーズではなく、既存のイメージとの葛藤や、地域の意味づけをめぐる議論や競合が伴う可能性があります。グラスゴー市でも、文化都市という新しいイメージをめぐって市民の間で様々な議論や批判が巻き起こりました。これらの議論が、地域文化の変容にどのような影響を与えたのかを分析する必要があります。
3. グラスゴー事例からの結論 イメージ戦略と地域社会変容
グラスゴー市の事例分析から得られた結論をまとめます。グラスゴーの地域イメージの再構築は、文化政策と関連する経済政策を伴いながら、地域社会の活性化と経済再生につながる社会変容を導きました。新しい地域イメージは、地域の変化を促す一つの契機であり、それ自体が変化を生み出すものではありません。重要なのは、意味づけとともに具体的な活動、つまり文化政策などの行動が伴うことで、地域の文化が実質的に変容することです。グラスゴーでは、文化政策が様々な意味づけを排除・圧倒することで、「文化都市」というイメージが市民に浸透していったと考えられます。新しいイメージは、地域カテゴリー(グラスゴー)について「文化都市」という意味づけを行うことを意味し、市民の間で地域の意味づけをめぐる競合や論争を引き起こしました。この競合を通して、希薄化していた地域への関心が覚醒され、地域アイデンティティの再構築が促進されたのです。しかし、この解釈枠組みの共有化が地域全体で均等に起こったかどうかは、さらなる検証が必要です。また、文化政策の効果をより正確に評価するためには、政策以外の要因も考慮した分析が必要となるでしょう。
