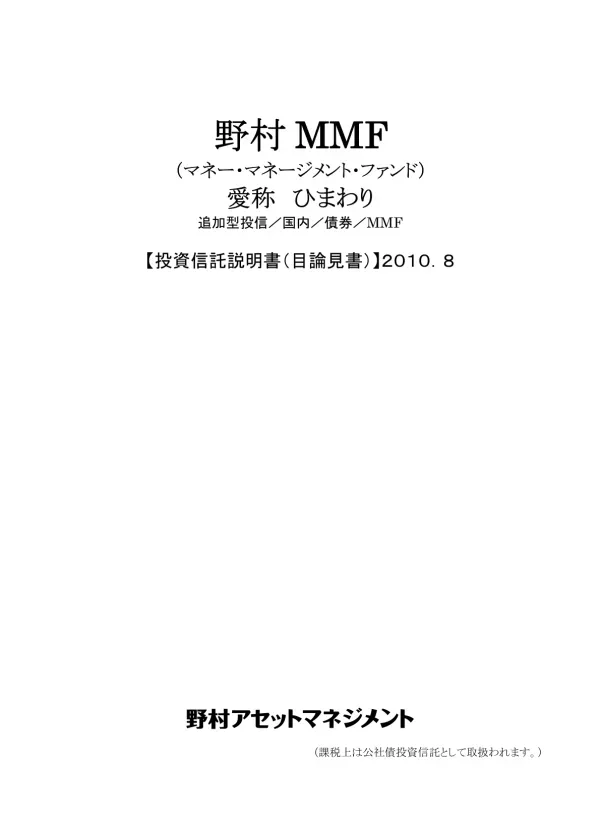
野村MMFひまわり:概要と投資情報
文書情報
| 著者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 文書タイプ | 目論見書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.06 MB |
概要
I.投資方針とリスク Investment Policy and Risks
野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)、愛称「ひまわり」は、元本確保を重視した低リスク投資を目指した短期投資ファンドです。主に残存期間1年以内の国内外の公社債やコマーシャルペーパーなどに投資し、分散投資を行います。毎月分配され、分配金は自動的に再投資されます。為替リスクを回避するため、外貨建資産への投資は円貨で約定・決済するものに限定します。ただし、信託財産の効率的な運用のため、一部解約時の支払資金の手当てや再投資のための資金借入れを行う場合があります。(コール市場を含む)。
1. 元本安全性の重視 Emphasis on Principal Safety
野村MMFの投資方針は、まず第一に元本の安全性を重視することです。このため、残存期間が短い、好利回りの国内外の公社債やコマーシャルペーパー、そして金融商品などに投資することで、価格変動リスクを最小限に抑えようとしています。具体的には、主に残存期間1年以内の有価証券や金融商品への投資を重視しており、投資家の元本を確実に守り抜くことを最優先事項としています。また、国債や政府保証付債券といった、信用力の高い債券への投資も積極的に行われ、リスク管理の徹底が図られています。投資適格格付(長期格付でBBB格以上、同等と判断されるものを含む)の債券も投資対象に含まれており、厳選された高品質な債券への投資によって、安定した運用を目指しています。さらに、外貨建資産への投資は、為替リスクを完全に回避するために、円貨で約定し円貨で決済される取引のみに限定されています。これにより、為替レートの変動によって生じる損失の可能性を排除し、投資家の資産を守るための万全の対策がとられています。このように、野村MMFは、徹底したリスク管理と元本重視の運用によって、投資家の安心と安全を確保することを目指しています。
2. 分散投資とデリバティブの利用 Diversification and Use of Derivatives
野村MMFは、リスクを分散させるため、分散投資を積極的に行っています。債券については、一発行体あたりの組入れ比率をファンドの純資産総額の10%を上限としており、特定の発行体に過度に依存しないよう配慮されています。これにより、個々の発行体の信用リスクがファンド全体に与える影響を最小限に抑えることができます。さらに、デリバティブ(先物取引、オプション取引、スワップ取引)の活用についても言及されていますが、その利用はあくまでヘッジ目的のみに限定されており、有価証券等の価格変動リスクを回避するためのツールとして用いられる点が強調されています。積極的な運用による収益追求ではなく、リスク軽減を目的とした慎重な運用姿勢が明確に示されています。デリバティブ取引は、市場環境の変化による損失の可能性も孕んでいるため、そのリスクを完全に排除するわけではないものの、リスクヘッジを効果的に行うことで、ファンド全体の安定性を高めようとしています。投資対象およびデリバティブの運用に関するより詳細な情報は、約款に記載されているため、投資を検討する際には約款の内容を十分に理解することが重要です。
3. 資金の借入れに関する規定 Regulations Regarding Borrowing of Funds
信託財産の効率的な運用と安定性を確保するため、野村MMFでは、一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を含む)を行うことが認められています。ただし、この借入金は有価証券等の運用には一切使用されず、あくまで支払資金の確保のためのみに利用される点が明確にされています。この規定は、ファンドの流動性を維持し、投資家の解約要求に迅速に対応するための措置として位置付けられています。一部解約の際には、保有する有価証券等の売却や償還によって支払資金を調達しますが、迅速な対応のために一時的に資金を借り入れることが可能になっています。借入期間は、解約代金支払開始日から有価証券等の売却代金や償還金の受取日までの期間に限定され、その期間が20営業日以内である場合にのみ適用されます。また、借入金額の上限は、信託財産の純資産総額の10%とされており、過剰な借入によるリスクを回避するための措置も講じられています。このように、資金の借入れに関する規定は、ファンドの流動性と安定性を両立させるための重要な要素となっています。
II.投資対象と運用 Investment Targets and Management
主な投資対象は、残存期間1年以内の国債、政府保証付債券、投資適格格付(長期格付BBB格以上)の債券、および金融商品です。一発行体あたりの債券組入れはファンド純資産総額の10%を上限とします。デリバティブ(先物取引、オプション取引、スワップ取引)は、ヘッジ目的のみに限定して利用します。ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資に配慮します。具体的な投資対象とデリバティブの運用指図・目的・範囲については、約款をご確認ください。
1. 主要投資対象 Main Investment Targets
野村MMFは、元本確保を重視した運用を行うため、主に残存期間1年以内の国内外の公社債やコマーシャルペーパー、そしてその他金融商品に投資します。具体的には、国債、政府保証付債券、投資適格格付(長期格付BBB格以上、同等と判断されるものを含む)の債券などが投資対象となります。これらの債券は、比較的信用リスクが低く、価格変動も少ないとされているため、元本保全の観点から適切な投資対象と考えられています。また、コマーシャルペーパーも投資対象に含まれており、短期的な資金運用ニーズに対応する柔軟性も備えています。さらに、投資する有価証券や金融商品は、主として残存期間1年以内のものと限定することで、金利変動リスクや信用リスクを最小限に抑える戦略をとっています。これら多様な投資対象への分散投資によって、リスクを低減し、安定的な運用成果を目指しています。ただし、投資対象の詳細やデリバティブの運用指図、目的、範囲については、個別の約款を参照する必要があります。
2. 分散投資の徹底 Thorough Diversification
ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資が徹底されています。特に債券については、一発行体あたりの組入れ比率がファンドの純資産総額の10%を上限としています。これは、特定の発行体の債券に過度に集中投資することを避け、信用リスクを分散させるための重要な措置です。仮に特定の発行体が債務不履行に陥った場合でも、その影響をファンド全体に及ぼすことを最小限に抑えることができます。分散投資は、リスク管理において非常に重要な要素であり、野村MMFでは、この点に細心の注意を払って運用が行われています。投資対象の選定にあたっても、多様な種類の債券や金融商品をバランスよく組み入れることで、リスクの分散を図っています。これにより、市場環境の変化や個々の発行体の状況に左右されにくい安定した運用を目指しています。投資対象に関するより詳細な情報や、具体的な投資戦略については、ファンドの約款を参照することで、より詳しい内容を理解することができます。
3. デリバティブのヘッジ目的利用 Hedging Purpose Use of Derivatives
野村MMFは、デリバティブ(先物取引、オプション取引、スワップ取引)を運用に活用していますが、その目的はあくまでリスクヘッジに限定されています。価格変動リスクを軽減するために、デリバティブ取引を用いることで、ファンド全体の安定性を高める戦略です。デリバティブ取引は、適切に利用することでリスクを抑える効果がありますが、一方で、市場の動向によっては大きな損失を被る可能性も秘めています。野村MMFでは、この点について十分に認識しており、デリバティブ取引はあくまでヘッジ目的のみに限定して使用され、積極的な投資には用いられません。具体的なデリバティブ取引の運用指図、目的、範囲については、ファンドの約款に詳細な規定が設けられています。投資家は、約款の内容を十分に理解した上で、このファンドへの投資を判断する必要があります。リスク管理の観点から、デリバティブ取引の適切な運用が、ファンド全体の安定性維持に大きく寄与すると考えられます。
III.分配金と償還 Dividends and Redemption
信託財産から生じる利益は、原則として毎日分配されます。毎月の最終営業日に1ヶ月分の分配金(税引後)が自動的に再投資されます。償還は、信託終了日後1ヶ月以内に委託者の指定する日から行われます。償還金と償還にかかる受益権に帰属する収益分配金は、販売会社の営業所等で受益者に支払われます。一部解約は、請求受付日の翌営業日の前日の基準価額で計算されます。30日未満の解約には、1万口につき10円の信託財産留保額が課せられます。
1. 毎日の分配金と毎月の再投資 Daily Distributions and Monthly Reinvestment
野村MMFは、信託財産から生じる利益を原則として毎日分配することを特徴としています。日々決算を行い、その日の利益を全額分配する仕組みです。ただし、計算期末に損失が発生した場合(収益が費用を下回った場合)は、その損失額は繰越欠損金として次期に繰り越されます。毎月の最終営業日には、前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの1ヶ月分の分配金がまとめて支払われます。この際、分配金に対する税金が差し引かれた上で、自動的に再投資される仕組みとなっています。この自動再投資機能により、投資家は分配金を管理する手間を省き、複利効果による資産形成を効率的に進めることができます。毎日の分配金支払と毎月の自動再投資は、このファンドの大きな魅力の一つであり、短期的な資金運用や、安定的な収益を得たい投資家にとって有利な仕組みと言えます。毎日の分配金は、流動性の高さを示しており、必要に応じて迅速に資金を換金できるメリットもあります。
2. 償還と一部解約 Redemption and Partial Redemption
信託の終了時には、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額が償還金として支払われます。償還金に加え、償還にかかる受益権に帰属する収益分配金も合わせて支払われます。償還金の支払いは、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から開始され、販売会社の営業所などで受け取ることができます。ただし、委託者自身の募集分については、委託者から直接受益者へ支払われます。一部解約の際には、請求受付日の翌営業日の前日の基準価額に基づいて解約価額が算出されます。受益者は、解約に伴い、口座が開設されている振替機関等に対して、信託契約の一部解約と受益権の抹消を申請する必要があります。30日未満で解約する場合、1万口につき10円の信託財産留保額が、解約される信託元本から差し引かれ、信託財産に返戻されます。この留保額は、ファンド残高の安定的な推移を図るための措置として設けられています。解約代金の支払いは、原則として解約申込受付日の翌営業日から開始されます。
IV.受益権と手続き Beneficial Interests and Procedures
受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。受益証券は、やむを得ない事情がある場合を除き発行しません。1円以上、販売会社によっては1円単位で申込みが可能です。取得申込者は、販売会社に振替機関等の口座を申し出ます。換金の請求は、振替受益権で行います。ファンドに関する租税、信託事務処理費用、受託者の立替金利息は受益者負担です。売買委託手数料、先物取引費用などはファンドが負担します。
1. 受益権の帰属と受益証券 Attribution of Beneficial Interests and Beneficial Certificates
野村MMFの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることで確定します。受益権は振替口座簿に記録されることで初めて成立し、受益証券は、やむを得ない事情がない限り発行されません。これは、電子的な記録システムによって受益権の管理を行うことで、効率的な運用とコスト削減を実現しているためです。受益証券がない場合でも、振替口座簿に記録されている受益権の口数によって、受益者の権利と義務が明確に定められます。そのため、従来の有価証券のように紙媒体の受益証券を発行する必要がなく、管理の手間やコストを削減できます。また、無記名式や記名式の形態もないため、単純で分かりやすい受益権の管理体制が構築されています。これは、電子記録システムによる効率的な管理を可能にするためであり、投資家にとって、より簡素で分かりやすい手続きを提供することを目的としています。ただし、振替機関の指定が取り消された場合や、やむを得ない事情がある場合は、例外的に受益証券が発行される可能性があります。
2. 取得申込手続きと換金手続き Acquisition Application Procedures and Redemption Procedures
取得申込者は、販売会社に取得申込と同時に、または事前に振替機関等の口座を申し出る必要があります。申込金支払方法等によっては、1円単位での申込も可能ですが、1円単位での申込ができない場合もあるため、詳細は「申込手続きの概要」を参照する必要があります。買付単位は原則として1円以上です。取得申込者に係る口数は、申し出た口座に増加として記載・記録されます。換金(一部解約)を希望する受益者は、口座が開設されている振替機関等に対して、委託者による信託契約の一部解約と引き換えに、解約に係る受益権の口数と同口数の抹消を申請する必要があります。換金は、振替受益権を用いて行われます。金融商品取引所における取引停止等のやむを得ない事情がある場合は、買付および換金のお申込み受付を中止、または取り消す場合があります。これらの手続きは、社振法(社債、株式等の振替に関する法律)の規定に基づいて行われます。手続きの詳細については、別途提供される資料などを参照する必要があるでしょう。
3. 費用負担 Cost Burden
ファンドに関する租税、信託事務処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担となります。これらの費用は、ファンドから支払われます。具体的には、受益者一人ひとりが負担すべき費用であり、ファンドの運用にかかる様々なコストを反映したものです。一方、ファンドに関する組入有価証券の売買委託手数料、その手数料に係る消費税相当額、先物取引・オプション取引費用、外貨建資産の保管費用などは、ファンドから支払われます。これは、ファンドが投資家の利益を最大限に確保するために、積極的にコストを管理していることを示しています。手数料や費用に関する詳細な情報は、ファンドの約款やパンフレットなどに記載されているため、投資前にそれらを確認し、自身の負担額を理解することが重要です。透明性の高い費用体系によって、投資家は安心して投資判断を行うことができます。
V.リスク管理と内部管理体制 Risk Management and Internal Control System
野村アセットマネジメント株式会社は、ファンドを含む投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織を有しています。受託会社または再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。SAS70に基づく内部統制の有効性についての監査人による報告書も受領しています。金融商品取引所の取引停止などやむを得ない事情により、買付・換金のお申込み受付を中止または取消す場合があります。
1. 受益権の帰属と管理 Attribution and Management of Beneficial Interests
野村MMFの受益権は、社債等の振替に関する法律(社振法)の規定に基づき、指定された振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることで帰属が決定されます。このため、従来のような紙の受益証券は、やむを得ない事情がない限り発行されません。受益権の管理は、電子的な記録システムによって行われ、効率性とコスト削減が実現されています。 受益権の形態は、無記名式や記名式といった区別はなく、簡素化された管理体制となっています。このシステムは、平成19年1月4日から適用されており、それ以降に追加信託された受益権についても同様の管理方法が適用されます。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情を除き、受益証券を発行しません。受益者は、委託者がやむを得ない事情により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行を請求することはできません。 この電子的な記録システムによる管理は、投資家にとって、より簡素で効率的な手続きを提供することを目的としています。
2. 申込手続きの概要 Outline of Application Procedures
取得申込者は、販売会社に対して取得申込と同時に、または事前に受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出る必要があります。この口座に、取得申込者に係る受益権口数の増加が記載または記録されます。買付単位は1円以上です。ただし、販売会社によっては、申込代金の払込方法などによって1円単位での申込も可能ですが、必ずしも1円単位での申込を受け付けているとは限らないため、詳細は販売会社に確認する必要があります。換金(一部解約)を希望する受益者は、口座が開設されている振替機関等に対して、委託者による信託契約の一部解約と引き換えに、解約に係る受益権口数と同口数の抹消を申請する必要があります。この手続きによって、振替機関等の口座において受益権口数の減少が記載または記録され、換金手続きが完了します。換金は、振替受益権を用いて行われます。金融商品取引所の取引停止、その他やむを得ない事情により、買付や換金のお申込み受付を中止、もしくは取り消す場合があります。
3. 費用負担に関する規定 Regulations on Cost Burden
ファンド関連の租税、信託事務処理費用、受託者の立替金利息は、受益者の負担となり、ファンドから支払われます。これは、ファンド運営に必要な諸経費を受益者で負担する仕組みです。一方、ファンドに組入れられた有価証券の売買に伴う売買委託手数料、それに係る消費税相当額、先物取引やオプション取引に必要な費用、外貨建資産の保管費用などは、ファンドが負担します。これは、ファンドが運用コストを適切に管理し、投資家の利益を最大限に確保するための仕組みです。 これらの費用負担に関する詳細な規定は、約款に記載されているため、投資を検討する際には、約款をよく読んで内容を十分に理解する必要があります。透明性のある費用体系によって、投資家は安心して投資判断を行うことができます。
