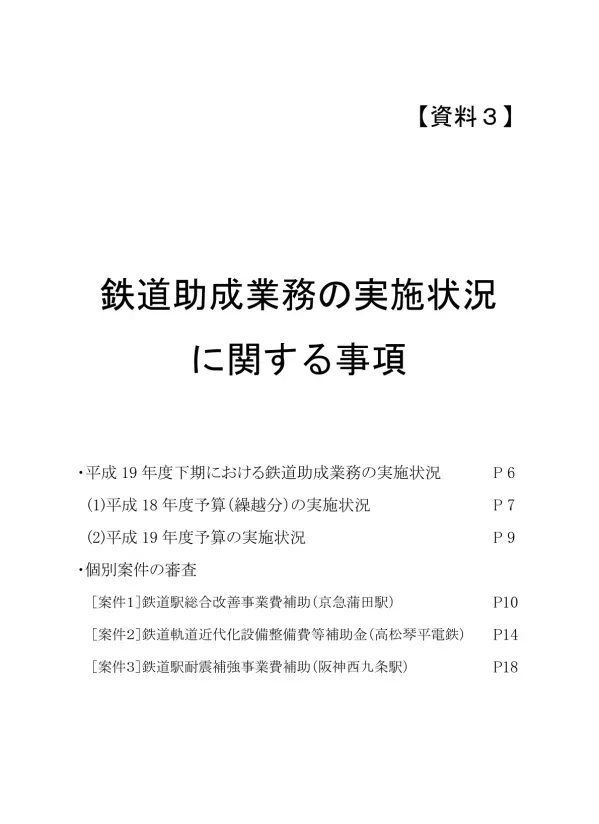
鉄道助成金事業の実施状況
文書情報
| 専攻 | 交通政策、公共事業管理など |
| 出版年 | 2007 |
| 文書タイプ | 報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.53 MB |
概要
I.平成19年度 鉄道助成事業実施状況概要
本資料は、平成19年度下期における鉄道助成事業の実施状況をまとめたものです。主な助成事業としては、新幹線高度化、新線調査、LRTシステム整備、地下高速鉄道整備、ニュータウン鉄道整備、鉄道駅総合改善(都市一体化)、都市鉄道利便増進、地下駅火災対策、鉄道駅耐震補強、鉄道技術開発、鉄道防災、軌道近代化などが挙げられます。これらの事業には、幹線鉄道、都市鉄道、貨物鉄道などが含まれ、安全対策投資やサービス改善を目的として、多額の補助金が交付されています。特に、京急蒲田駅の高架化事業では、乗換え利便性向上、バリアフリー化、踏切廃止による交通渋滞解消などの効果が期待されています。補助金額は事業によって大きく異なり、例えば京急蒲田駅の高架化事業には約17億2千万円の補助金が交付されています。高松琴平電鉄の再生計画では、車両更新、分岐器の重軌条化などの設備投資を行い、経営状況の改善を目指しています。また、阪神電気鉄道西九条駅の耐震補強事業では、鉄道駅利用者の安全確保と災害時の緊急応急活動拠点機能の確保が目的です。
1. 平成19年度鉄道助成事業の全体像
平成19年度下期における鉄道助成事業の実施状況が、本資料の中心となっています。新幹線高度化、新線調査、LRT整備、地下鉄整備、ニュータウン鉄道整備、駅総合改善、都市鉄道利便増進、地下駅火災対策、鉄道駅耐震補強、鉄道技術開発、鉄道防災、軌道近代化など、多様な事業に補助金が交付されています。これらの事業は、新幹線、幹線鉄道、都市鉄道、貨物鉄道などを対象としており、鉄道利用者の安全性と利便性の向上、地域活性化、防災対策といった多様な目的を達成することを目指しています。 特に、平成18年度予算の繰越分と平成19年度予算の実施状況が詳細に示されており、各事業の予算額、執行額、確定額、不用額、繰越額といった数値データが掲載されています。 これらのデータから、各事業の進捗状況や課題などを分析することが可能です。 補助金の交付決定状況と額の確定状況も明記されており、事業の進捗管理に役立つ情報となっています。
2. 主要事業別補助金内訳と執行状況
資料では、幹線鉄道等活性化事業費補助金(幹線鉄道・貨物鉄道、都市鉄道・乗継円滑化)、地下高速鉄道整備事業費補助金、ニュータウン鉄道等整備事業費補助金、鉄道駅総合改善事業費補助金(都市一体化)、都市鉄道利便増進事業費補助金、新線調査費等補助金(本四連絡橋、調査)、地下駅火災対策施設整備事業費補助金、鉄道駅耐震補強事業費補助金、地下鉄等災害情報基盤整備事業費補助金、譲渡線建設費等利子補給金、都市鉄道整備事業資金、鉄道技術開発費補助金、鉄道防災事業費補助金、鉄道軌道近代化設備整備費等補助金といった、具体的な事業名と予算額が示されています。平成18年度予算の繰越分と平成19年度予算それぞれについて、当初予算、変更後予算、執行額、額の確定、不用額、繰越額が千円単位で明示されています。これにより、各事業における補助金の執行状況を数値データに基づいて詳細に把握することができます。 また、平成17年度予算の繰越分についても同様にデータが提示されており、複数年度にわたる事業の推移を分析する上で重要な情報となっています。
3. 平成18年度及び17年度予算繰越分の実施状況
平成18年度と17年度予算の繰越分についても、同様のフォーマットで実施状況が報告されています。 災害復旧事業費補助金、LRTシステム整備費補助金、踏切保安設備整備費補助金、地方鉄道新線運営費補助金などの事業が記載され、それぞれについて当初予算、変更後予算、執行額、確定額、不用額、繰越額が示されています。 特に、都市鉄道利便増進事業費補助金や新幹線鉄道整備事業費補助金など、大規模な事業の進捗状況が詳細に示されており、予算執行の効率性や課題を分析する上で重要なデータとなっています。 新幹線鉄道整備事業資金や整備新幹線建設推進高度化等事業費補助金といった、新幹線関連事業の状況も確認できます。これらのデータは、過去の予算執行状況を把握し、今後の予算計画に反映させる上で重要な役割を果たします。 また、本四連絡橋関連の新線調査費等補助金についても、その執行状況が示されています。
II.主要事業と補助金の内訳
資料には、様々な鉄道事業への補助金が記載されています。新幹線鉄道整備、地下高速鉄道整備、ニュータウン鉄道等整備、幹線鉄道等活性化事業(幹線鉄道、貨物鉄道、都市鉄道)、鉄道駅総合改善事業、都市鉄道利便増進事業、地下駅火災対策施設整備、鉄道駅耐震補強事業、鉄道技術開発事業、鉄道防災事業など、多岐にわたる事業に補助金が交付されています。それぞれの事業の予算額、執行額、繰越額などが詳細に示されており、補助金の使途を明確に把握することができます。特に、平成18年度予算(繰越分)と平成19年度予算の実施状況が比較されており、事業の進捗状況を分析することができます。 具体的な補助金額は事業規模によって大きく異なり、数億円から数十億円に及ぶものもあります。
1. 幹線鉄道 都市鉄道等の活性化事業
資料には、幹線鉄道等活性化事業費補助金が複数項目記載されています。一つ目は幹線鉄道と貨物鉄道を対象としたもので、平成19年度当初予算は5億6100万円、最終的に約4億900万円が執行され、約1億5000万円が翌年度に繰越されています。二つ目は都市鉄道と乗継円滑化を対象としており、当初予算は1億1420万円、約9億4100万円が執行されています。これらの事業は、鉄道の効率的な運行や利便性向上に資するもので、多額の補助金が投入されていることがわかります。 数値データからは、当初予算と最終執行額に差が生じている事業も存在し、予算執行における柔軟性や課題が示唆されます。 乗継円滑化を目的とした事業は、利用者にとって重要な要素であり、そのための投資が積極的に行われていることがわかります。
2. 都市鉄道整備と利便性向上事業
地下高速鉄道整備事業費補助金は、平成19年度に約19億1500万円が執行され、ニュータウン鉄道等整備事業費補助金は、約3億9800万円が執行されています。都市鉄道利便増進事業費補助金は、平成19年度に約1億3000万円が執行されています。これらの事業は、都市部の交通網整備や利便性向上に貢献するものであり、莫大な予算が投じられていることがわかります。 特に地下高速鉄道整備事業は、大規模な事業であることが予算額から明らかです。 ニュータウン開発と連携した鉄道整備や、既存都市鉄道の利便性向上のための事業など、多角的なアプローチがなされていることがわかります。数値データの比較を通して、各事業の進捗状況や効率性を分析することが可能です。
3. 鉄道駅の安全 機能向上事業
鉄道駅総合改善事業費補助金(都市一体化)は、平成19年度に約8億6700万円が執行されています。これは、鉄道駅のホームやコンコースの拡幅など、駅機能の総合的な改善を目的とした事業です。また、地下駅火災対策施設整備事業費補助金は、平成19年度に約17億8900万円が執行され、鉄道駅耐震補強事業費補助金は、約2億5200万円が執行されています。これらの事業は、鉄道利用者の安全確保を目的としたものであり、耐震化や防災対策への投資が積極的に行われていることを示しています。特に、地下駅火災対策は、安全対策上重要な事業であり、多額の予算が組まれていることがわかります。 駅総合改善事業は、都市計画と連携した取り組みであり、街づくりにも貢献する事業であることがわかります。
4. その他の鉄道関連事業
新線調査費等補助金(本四連絡橋)は、約1万5800万円が執行されています。これは、新たな路線の建設に向けた調査費用です。地下鉄等災害情報基盤整備事業費補助金は、平成19年度に約1億円が執行されています。譲渡線建設費等利子補給金は、約7億4300万円が執行されています。都市鉄道整備事業資金は、約12億円が執行されています。鉄道技術開発費補助金は、約11億6500万円が執行されています。鉄道防災事業費補助金は、約8億1200万円が執行され、鉄道軌道近代化設備整備費等補助金は、約7万3600万円が執行されています。これらの事業は、鉄道インフラの維持管理、技術開発、防災対策など、鉄道事業の持続的な発展に不可欠なものです。 各事業の予算規模は大きく異なり、事業の重要度や規模を反映していると考えられます。 これらの数値データは、鉄道事業の現状と将来計画を考える上で重要な情報となります。
III.京急蒲田駅高架化事業
京急蒲田駅の高架化事業は、本線と空港線間の平面交差解消を目的としています。この事業により、乗換え利便性の向上、バリアフリー化の促進、28箇所の踏切廃止による交通渋滞の解消、安全性の向上、そして地域発展への貢献が期待されています。平成19年度には、高架橋製作・設置、仮上り線敷設などの工事に対し、約17億2千万円の補助金が確定しています。事業期間は平成13年度から平成24年度までとされています。
1. 事業の背景と目的
京急蒲田駅は、本線と空港線が平面交差しており、空港線との乗継ぎの不便さ、踏切渋滞による地域問題、ダイヤ設定上の制約などが課題となっていました。この状況を改善するため、平成13年度から平成24年度にかけて、本線と空港線の高架化事業が行われました。この事業の目的は、本線と空港線間の乗換え利便性の向上、エレベーター等の設置によるバリアフリー化、28箇所の踏切廃止による交通渋滞解消、安全性の向上(踏切事故の防止)、そして地域分断の解消による魅力ある街づくりです。 これらの課題は、地域住民の生活や経済活動に大きな影響を与えており、抜本的な改善策が必要とされていました。高架化は、これらの問題を総合的に解決する効果的な手段として期待されていました。
2. 事業概要と効果
事業期間は平成13年度から平成24年度まで、総事業費は113億円です。主な工事内容は、高架橋の製作・設置、仮上り線の敷設などです。事業効果としては、本線と空港線間の乗換え利便性の向上、バリアフリー化、踏切廃止による交通渋滞解消、安全性の向上、地域発展などが期待されています。具体的には、羽田空港へのアクセス利便性向上として、品川方面~羽田空港間ラッシュ時の直通便が6本/時から9本/時へ、横浜方面~羽田空港間ラッシュ時の直通便が0本/時から6本/時へ増加する見込みです。 これらの効果は、地域社会全体にプラスの影響を与え、生活の質向上や地域経済の活性化に貢献すると期待されています。 高架化による景観の変化なども、街の印象を大きく変える可能性があります。
3. 平成19年度補助金と工事状況
平成19年度の補助金(確定額)は17億2000万円です。補助対象事業費は、高架橋製作・設置、仮上り線敷設などを含みます。資料には、平成20年5月に撮影された工事現場の写真が掲載されており、高架橋の建設状況がわかります。写真からは、駅山側ビルから品川方面、横浜方面から駅部、駅部から仮設高架橋を走行中の車両、駅部高架上から品川方面といった、様々な角度からの高架橋建設の様子が確認できます。これらの写真から、事業の進捗状況を視覚的に把握することができます。 高架化事業は、大規模な土木工事を伴うため、計画通りに工事が進捗しているかどうかの確認が重要です。 写真からは、工事の規模感や進捗状況を具体的にイメージすることが可能です。
IV.高松琴平電鉄の再生計画
高松琴平電鉄は、民事再生法申請を経て再生計画を策定しました。この計画では、車両更新(京急の中古車両を改造、冷房化率100%達成)、分岐器の重軌条化など、利用者利便向上と安全性の向上を目指した設備投資が行われています。これらの事業には補助金が活用されており、経営状況の改善、旅客収入の増加、輸送人員の増加が期待されています。会社概要としては、営業キロ60.0キロ、車両数85両です。
1. 高松琴平電鉄の概要と沿革
高松琴平電鉄株式会社は、香川県高松市に本社を置く企業で、資本金は2億5000万円です。昭和18年11月に会社設立、昭和61年4月にバス部門を分社化しました。平成13年12月には「コトデンそごう」の破綻に伴い民事再生法を申請、平成17年7月に民事再生手続が終結しています。事業内容は鉄道事業、自動車運送事業、土地建物の売買及び賃貸業など多岐に渡ります。営業キロは60.0キロ、車両数は85両です。平成17年2月には四国発のICカード乗車券「IruCa」を導入しています。これらの情報から、高松琴平電鉄が地域社会に深く根ざした企業であり、歴史と変遷を経て現在に至っていることがわかります。 特に、民事再生法申請とその後の終結は、経営状況の大きな転換点であったと考えられます。
2. 再生計画の目的と内容
高松琴平電鉄の再生計画は、「ことでん活性化計画」としてまとめられています。計画の目的は、速達性・定時性の向上、利便性の向上、輸送力増強、そして経営状況の改善です。ICカード乗車券の普及促進に加え、利用者利便向上に資する設備投資を実施し、鉄道事業の経常黒字化を目指しています。具体的な内容として、車両の更新(京急の中古車両4両を改造、冷房化率100%達成)、分岐器の重軌条化(37kgから50kgNへ重レール化)などが挙げられています。これらの整備により、旅客収入増加と輸送人員増加が期待されています。 計画全体では、安全性の向上と利便性の向上を両立させ、持続的な経営を目指すという意思が示されています。 補助金は、これらの計画遂行に重要な役割を果たしています。
3. 再生計画における補助金と整備効果
再生計画における具体的な整備項目には、車両の更新(補助率1/3)、分岐器の重軌条化(補助率1/3)が含まれています。車両更新では、中古車両の改造により冷房化率100%を達成し、サービス改善を図ります。分岐器の重軌条化では、37kgから50kgNへの重レール化により、保安度向上を目指します。これらの事業には、合計1億3639万9千円の補助金が投入されています。整備効果としては、車両更新による旅客収入の増加と輸送人員の増加が期待されています。 この計画では、補助金が効果的に活用され、経営の健全化とサービス向上に繋がるような整備が計画されていることがわかります。 パークアンドライド駐車場・駐輪場の整備も平成17年度に実施されており、利用者利便の向上に貢献しています。
V.阪神電気鉄道西九条駅耐震補強事業
阪神電気鉄道西九条駅では、鉄道駅利用者の安全の向上と災害時における緊急応急活動拠点機能の確保を目的とした耐震補強事業が行われています。補助金は、柱・基礎等の耐震補強(ブレース、耐震壁の設置等)に充てられます。補助の対象となるのは、乗降客数が1日1万人以上の駅、かつ折返し運転が可能な駅、または複数路線が接続する駅です。
1. 事業の目的と対象駅
阪神電気鉄道株式会社西大阪線西九条駅の耐震補強事業は、鉄道駅利用者の安全を図り、発災時における鉄道駅の緊急応急活動拠点機能を確保することを目的としています。補助金の対象は、主要な鉄道駅(地下駅を除く)で、乗降客数が1日1万人以上、かつ折返し運転が可能な駅、または複数路線が接続する駅です。西九条駅はこれらの要件を満たす駅であるため、耐震補強事業の対象となっています。 この事業は、地震などの災害発生時に、鉄道駅の機能を維持し、緊急時の対応拠点としての役割を果たすことを目指しています。そのため、駅構造体の耐震性能を高めることが重要となります。
2. 補助金の仕組みと内容
補助金の仕組みは、大きく分けて2種類あります。一つ目は、駅の改良整備・保有を業務とする第三セクターなどが主体となる場合で、国(鉄道・運輸機構経由)からの補助金が交付されます。二つ目は、鉄道事業者自身が第三セクターの場合で、JR(北海道・四国・九州)や東京地下鉄なども対象となり、国からの補助金が交付されます。 阪神電気鉄道は、このいずれかの仕組みを通じて補助金を受け、耐震補強事業を実施しています。 補助金は、駅施設の耐震補強整備に係る費用の一部を補助するものです。 補助金の交付額は、事業計画や審査結果によって決定されます。
3. 事業の概要と工事内容
事業の概要は、鉄道駅利用者の安全の向上と発災時の緊急応急活動拠点機能の確保です。そのため、駅施設の耐震補強整備が行われます。平成19年度の補助金審査額が資料に記載されていますが、具体的な金額は明記されていません。工事内容は、柱の補強(鋼板巻き立て、RB、一面)などが含まれると示唆されています。 西九条駅は、多くの利用者がいる重要な駅であるため、耐震補強工事は、鉄道の安全運行を確保する上で不可欠な事業と言えます。 工事の具体的な内容や進捗状況については、さらに詳細な資料が必要となります。
