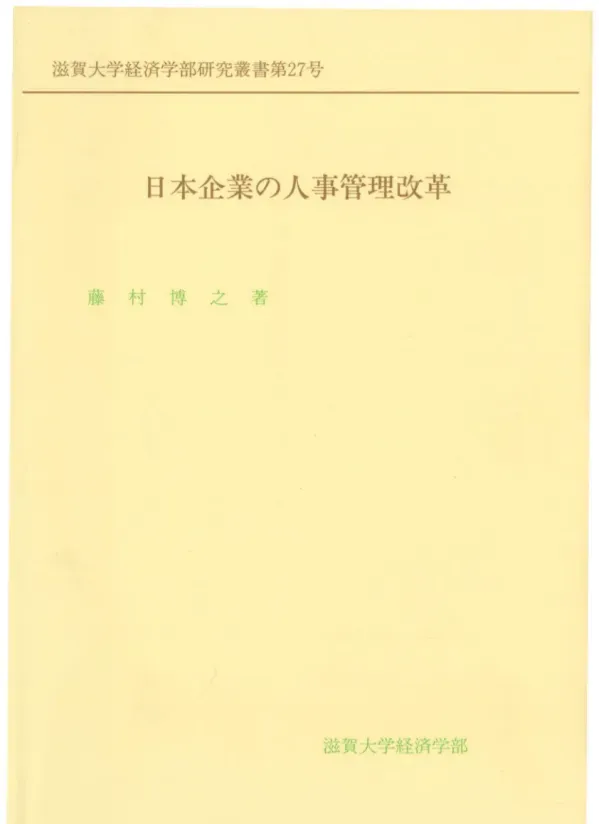
長期雇用と労働意欲:鉄鋼業の分析
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 6.08 MB |
| 専攻 | 人事管理、労働経済学 |
| 文書タイプ | 研究論文、報告書 |
概要
I.日本の企業における 終身雇用制 の現状と課題 人員削減 と 人材育成
長引く不況により、日本企業は人員削減を余儀なくされ、特にホワイトカラー、中でも管理職の削減が目立ちました。その背景には、団塊世代の管理職増加、バブル景気時の過剰雇用、管理職の非組合員化による抵抗の少なさ、そして高い人件費負担があります。しかし、今回の不況は、需要の回復が遅く、世界市場での競争激化や円高による低価格製品流入、海外生産拠点への移転など、従来の不況とは異なる要因が複雑に絡み合っています。こうした状況下、本書では日本企業の人材問題、特に長期雇用の維持と能力開発について考察します。
1. 人員削減の背景 長期化する不況と企業の対応
長引く需要低迷と不況は、日本企業の雇用問題を深刻化させ、人員削減に追い込む企業が続出しました。過去の不況と異なる点は、ホワイトカラー、特に管理職層が削減の主要対象となったことです。この背景には、①団塊世代の管理職増加による人員過剰、②バブル景気時の間接部門(企画・研究開発など)の過剰人員配置、③管理職の非組合員化による労働組合の抵抗の弱さ、④管理職層の高い人件費負担という4つの要因が挙げられます。 特に、管理職の人件費は企業経営にとって大きな負担であり、削減対象となりやすい背景となっています。 これらの要因が複雑に絡み合い、日本企業は深刻な人員削減問題に直面していると言えるでしょう。 今後の企業経営においては、人件費の最適化と同時に、人材の有効活用という観点からの抜本的な対策が求められます。
2. 今回の不況の特殊性 グローバル化と国内需要の減少
今回の不況は、単なる景気後退以上の複雑な要因が絡み合っています。景気底打ち後も需要の回復は遅々として進まず、個人消費の伸び悩みや企業設備投資の低迷が続きました。冷戦構造崩壊後の世界市場の競争激化と急速な円高は、低価格の海外製品の大量流入を招き、国内企業の売上減少に繋がりました。同時に、日本企業はコスト削減のため、海外への生産拠点移転を進め、国内需要は海外に流出する一方でした。これは、単なる国内需要の減少ではなく、グローバル化という大きな流れの中で、日本企業が競争力を維持するために苦渋の決断を迫られた結果と言えます。この構造変化は、従来の雇用慣行の見直しを余儀なくさせ、日本の雇用制度全体に大きな影響を与えました。
3. 企業の生き残り戦略 人材重視の経営
厳しい状況下でも、利益を上げている企業が存在します。それらの企業に共通するのは「ヒトを大切にする」という経営姿勢です。最先端の技術や設備だけでは、新しいアイデアや売れる商品は生まれません。創造性と実行力を持った人材こそが、企業の成長を支える原動力です。 本書では、このような人材重視の経営が、不況下でも企業の成果を上げる上で不可欠であることを主張しています。最新のコンピューターを導入するだけでは、イノベーションは生まれません。真の競争優位性を築くには、人材育成と人材活用が重要であるというメッセージが、このセクションからは読み取れます。
4. 終身雇用制の幻想と現実 高度経済成長と雇用慣行の変化
日本において終身雇用制が広く信じられてきた背景には、高度経済成長期の人材不足があります。1950年代後半から1970年代半ばにかけて、日本経済は著しい成長を遂げ、人材不足が長期にわたって続きました。そのため、定年まで勤められることが当たり前となり、企業も従業員も人員削減はありえないという幻想を抱くようになりました。しかし、これは幻想であり、現実には終身雇用を適用される労働者は少なく、近年は企業業績の悪化や長期化する不況、そしてグローバル化による競争激化によって、この幻想は大きく揺らいでいます。特に、人件費負担の軽減を迫られる経営者の増加は、日本の雇用制度全体の見直しを迫る大きな要因となっています。
5. 日本企業の経営方式と雇用の安定 日本的経営への再考
1980年代には、日本の経営方式、特にジャストインタイムや改善活動などが海外でも高く評価され、注目を集めました。第1次、第2次オイルショックを乗り越え、高い経済パフォーマンスを維持できたのは、日本企業の独自の経営方式によると考えられていました。しかし、MIT生産性調査委員会などの研究も示唆するように、労働者を大切にしてこなかったアメリカ企業の生産性低下の例から、従業員が能力を十二分に発揮できる環境を作る必要性が改めて認識されています。 このセクションでは、日本の経営方式の長所と短所を改めて検証し、持続可能な雇用と企業の成長を両立させるための新たな方策を探ることが必要であると示唆しています。
II. 長期雇用 慣行と労働者の 労働意欲
長期雇用慣行は、従業員の労働意欲を高め、企業の教育訓練への投資を促進し、ひいては企業競争力強化に繋がるという利点を検証します。鉄鋼労連の組合員意識調査などを参考に、長期雇用が労働者のモチベーションに与える影響を分析します。しかし、長期雇用は、必ずしも一つの会社に定年まで勤め続けることを意味するわけではありません。経済の活性化のためには、適正な労働移動も重要です。
1. 長期雇用慣行のメリットと労働意欲への影響
本書では、日本の企業における長期雇用慣行が労働者の働く意欲にプラスの影響を与えている点を検証しています。長期雇用は、企業が従業員の教育訓練に積極的に投資することを可能にし、従業員の能力向上と企業生産性向上に繋がるという利点があります。 従業員側も、長期的な雇用を前提として企業に貢献することで、自身の経済的安定と企業の成功を一体として捉える傾向があり、高いモチベーションを維持することに繋がります。鉄鋼労連の組合員意識調査などが用いられ、長期雇用慣行と労働意欲の関連性がデータに基づいて分析されています。この分析から、長期雇用慣行が日本企業の競争力を支える重要な要素であることが示唆されています。 しかしながら、このセクションでは、長期雇用が必ずしも一つの企業に定年まで勤め続けることを意味しないという点も強調されています。
2. 長期雇用の維持 企業グループ人事と労働組合の役割
日本の大企業では、個々の企業で長期雇用を維持することが困難になった場合でも、企業グループ全体で雇用の維持に努める傾向があります。この企業グループ人事の取り組みと、労働組合の役割が、このセクションの主要なテーマです。企業グループ人事の現状を把握し、労働条件の不利益変更に対する労働組合の保障についても考察されています。 大企業は、企業グループ内での人員配置転換などを通じて、長期雇用の維持に努力している実態が示されています。しかし、企業グループ内での雇用維持には、労働組合の協力が不可欠であり、労働組合が労働条件の不利益変更に対してどこまで保障しているかという点が分析の焦点となっています。これは、長期雇用を守るための現実的な方策と、その限界を示唆しています。
3. 労働移動の必要性と条件 公的資格の役割
長期雇用を重視する一方で、経済の活性化のためには適正な労働移動が不可欠であると主張されています。このセクションでは、労働移動の条件を、公的資格の取得という観点から考察しています。 長期雇用は、一つの企業に固執することを意味するものではなく、個人の能力を活かせる場への移動を促進する仕組みが必要であると示唆しています。 公的資格の取得が、労働移動を円滑にするための重要な要素として取り上げられており、ビジネスキャリア制度などの将来性についても言及しています。 これは、個人のキャリア形成と経済の活力維持の両面を考慮した、より柔軟な雇用システムの必要性を示唆するものです。
III. 企業グループ人事 と 労働組合 の役割
大企業は、個々の企業での長期雇用維持が困難な場合でも、企業グループ全体で雇用を維持しようとしてきました。本書では、その実態と、労働条件の不利益変更に対する労働組合の取り組みを分析します。長期雇用慣行の重要性を認めつつも、個人の能力と企業のニーズのミスマッチが生じた場合の労働移動の円滑化についても論じます。1993年発足した**職業能力習得制度(ビジネスキャリア制度)**の将来性についても考察します。
1. 企業グループ人事の現状と長期雇用維持への取り組み
日本企業、特に大企業においては、個々の企業における長期雇用維持が困難になった場合でも、企業グループ全体として雇用を維持しようとする動きが見られます。このセクションでは、企業グループ人事の取り組みについて詳細に分析しています。単一企業での雇用維持が難しい状況下でも、グループ全体で雇用を確保しようとする努力は、日本の雇用システムにおける重要な特徴の一つです。 企業グループ人事の具体的な取り組み内容やその実態、そしてその効果や限界について考察することで、長期雇用維持に向けた企業の戦略と課題が浮き彫りになります。企業グループ内での人員配置の柔軟性や、異動による雇用維持の試みなどが分析対象となります。この取り組みが、日本企業の長期雇用慣行を支える重要な役割を果たしている一方、その持続可能性や課題についても考察されている点が重要です。
2. 労働組合の役割 労働条件の不利益変更への対応
長期雇用維持において、労働組合の役割は非常に大きいです。このセクションでは、労働条件の不利益変更に対する労働組合の対応について分析しています。特に、組合員レベルの人員削減に対する労働組合の抵抗は強いものの、管理職は非組合員であるため抵抗が少ないという点が指摘されています。 労働組合は、組合員の雇用を守るために、企業側との交渉や紛争解決に積極的に関わっています。しかし、管理職のように非組合員の場合、労働組合の保護範囲外となるケースも存在し、その点も考慮した分析がなされています。 労働条件の不利益変更に対する労働組合の保障範囲、交渉力、そしてその限界について、具体的な事例やデータに基づいた考察が展開されています。これは、労働組合の役割と影響力、そして今後の課題を理解する上で重要なセクションです。
3. 労働移動と公的資格 ビジネスキャリア制度の将来性
長期雇用が重要である一方、経済の活性化のためには適正な労働移動が不可欠です。このセクションでは、労働移動の条件を公的資格の取得という観点から考察し、1993年10月に発足した「職業能力習得制度(ビジネスキャリア制度)」の将来性についても検討しています。 特定企業内で培われたホワイトカラーの能力を、社会的に通用する形で評価し、労働移動を促進するための制度としてビジネスキャリア制度が位置づけられています。 この制度が将来、有効に機能するためには、いくつかの課題を克服する必要があると指摘されています。既に存在する公的資格の効果を分析することで、ビジネスキャリア制度の成功のための鍵となる要素を探る試みがなされています。これは、日本の労働市場における人材流動性の向上と、個人のキャリア形成を支援する制度設計の重要性を示唆しています。
IV. 中高年 従業員の活用と 人材育成 の課題
不況下では、中高年従業員の人件費負担が経営上の問題となります。「中高年は能力不足」という批判に対し、本書では企業の人材育成のあり方そのものを問いかけます。企業は、従業員の能力開発に責任を負っており、能力不足を指摘する前に、自社の人材育成方式を見直すべきです。人事考課の結果を従業員に説明せず、能力開発の意思決定権を企業が独占してきたこと、そして経済状況の変化への対応が遅れたことが問題点として挙げられます。中高年の活用のためには、能力形成における従業員の自己責任と企業の役割のバランス、そして公平な人事評価制度の構築が不可欠です。
1. 中高年従業員の過剰感と企業の課題 賃金負担と能力評価
不況下において、企業業績の悪化に伴い、中高年従業員の賃金負担が経営上の問題として浮上します。 中高年層は高い賃金を受け取っているにもかかわらず、十分な成果を上げていない、能力がないのに年功序列で高い地位と給与を得ているといった批判がなされるケースがあります。これは、終身雇用制崩壊論の根底にある中高年従業員の過剰感と密接に関連しています。 高齢化社会の進展に伴い、企業内における中高年従業員の割合は増加傾向にあり、彼らをいかに活用していくかが、今後の日本企業にとって重要な課題となっています。単純な人員削減ではなく、中高年従業員の能力を最大限に活かすための戦略が求められています。
2. 人材育成の失敗 従業員の自主性と企業の責任
企業側の人材育成における問題点として、人事考課の結果を従業員に説明しなかった点が挙げられます。毎年行われる成績査定の結果を隠してきたことで、従業員の能力開発に対する自主性が阻害され、自分の能力や企業内での位置づけを把握することが困難になりました。 従業員は、企業の指示に従って異動することによって将来の安定を図ろうとする傾向がありましたが、最近の状況変化を考えると、そのような暗黙の信頼関係はもはや成り立たなくなっています。 企業は、従業員の能力開発を一元的に管理してきたため、従業員は既存のやり方に固執し、変化への対応が遅れました。結果として、経済状況の変化に適応できず、能力を活かす場を失った中高年従業員が削減対象となるという事態が生じています。このことから、企業は、人材育成において従業員の自主性を尊重し、適切な情報提供を行うことが重要であると示唆されています。
3. 企業の論理と限界 業績と賃金の関係 人材育成の意思決定
企業は、従業員の限界生産力と賃金率が一致する限り、年齢を問題視しないという経済理論に基づいて経営を行うことができます。しかし、日本の長期雇用を前提とした賃金体系では、業績と賃金が毎年一致するとは限りません。若年層から中堅期にかけては業績より低い賃金を受け取り、中高年期に業績以上の賃金を受け取るという仕組みが一般的でした。この賃金体系が、中高年従業員の削減問題を複雑化させています。 さらに、人事考課の結果を曖昧にすることで企業は人材育成の意思決定権を独占してきました。 経済成長が順調な時代には問題ありませんでしたが、低成長時代には、企業の思惑が外れるリスクが高まり、既存事業の縮小・撤退によって従業員の能力を活かす場が失われるという問題が発生します。 そのため、企業は、業績と賃金の関係、人材育成の意思決定における従業員の参加、そして公平な評価制度の構築について、改めて検討する必要があると示唆されています。
4. 中高年層の活用と能力開発 自己責任と企業の役割
中高年層の活用において企業が最も問題とするのは、業績と賃金の関係です。しかし、これは企業の人材育成の失敗に起因する部分も大きいと言えます。 能力形成は従業員の自己責任面も重要ですが、企業は自己啓発の機会を提供するなど、従業員の能力開発を支援する役割を担っています。しかし、仕事の選定権が企業側にある以上、従業員の自己責任に帰すべき範囲は限定されます。 中高年層削減の理由として能力不足を挙げることがありますが、それは企業自身の人材育成の失敗を反映していると言えるでしょう。 この点を認識し、企業は情報公開による人事考課結果の説明、面接制度の活用による双方向の情報交換、そして従業員の能力開発における自己責任と企業の責任のバランスを再考する必要があります。 近年の傾向として、企業が従業員の信頼に応えられず、中高年層の削減を進めていることが問題視されています。
5. 企業文化と人材活用 効率性重視から創造性重視への転換
日本の企業、特に大企業は、これまで若年層の体力と気力、そして効率性を重視した組織運営を行ってきました。しかし、この効率性重視の文化は、中高年層の能力や経験を十分に活用できていない可能性があります。 「労働時間中にミスで働かない時間は申し訳ない」という自動車会社人事担当者の発言は、効率性追求の行き過ぎを示しています。 これからの時代は、効率性だけでなく、創造性や多様な人材の活用が重要になります。 女性社員の活躍が目覚ましい商品開発の現場を例に、生活者としての感覚を活かした商品開発の重要性が強調されています。 企業は、年齢や性別に関わらず、個々の従業員の能力を最大限に活かせるような、より柔軟で包摂的な組織文化を構築する必要があります。
V. 人事制度改革 柔軟な労働時間管理 と 評価制度
現状の人事管理制度に対する疑問の声が高まる中、本書では人事制度改革の方向性を模索します。フレックスタイム制や裁量労働制といった柔軟な労働時間管理の導入状況と課題、そして人事評価制度の改革の必要性を論じます。自己選択・自己責任を貫徹し、個人の意志を尊重する人事制度の構築を目指し、目標管理制度や年俸制などの導入における課題と対策を検討します。特に、評価制度の公平性、目標設定の合理性、部門間調整の難しさ、そして管理職の役割の重要性について深く掘り下げます。従業員の能力開発を促進し、モチベーションを高めるための具体的な方策を提案します。
1. 人事制度改革の必要性 自己選択 自己責任の原則
日本企業では、従来の人事管理方式に対する疑問の声が高まっています。従業員のやる気を維持し続け、能力を最大限に活用していくためには、これまでの方式の見直しが必要不可欠となっています。 人事制度改革の基本は、自己選択と自己責任の原則の徹底です。これは、個人の意志を尊重することに他なりません。 本書では、個人が自身の価値基準に基づいて判断できるようになり、仕事、家庭、地域社会のバランスを取り戻す必要性を強調しています。そのためには、人事評価制度の改革が不可欠であり、個々が「時間の主人公」になれるような仕組みづくりが求められています。 様々な新しい人事制度(年俸制、フレックスタイム制、リフレッシュ休暇制度など)が導入されていますが、それらは全て、従業員の仕事へのモチベーションを高めることを目的としています。しかし、これらの制度の導入だけでは、必ずしも問題が解決するとは限りません。
2. 柔軟な労働時間管理 フレックスタイム制の課題と改善点
フレックスタイム制は、従業員が出退勤時間を自己管理できる点で進歩した制度ですが、労働時間へのこだわりが強く残っており、改善の余地が大きいと指摘されています。 日本生産性本部生産性研究所の調査によると、フレックスタイム制導入後の問題点として、労働時間管理の手続きが煩雑になったことが挙げられています。従業員一人一人の出退勤時間を記録し、賃金計算を行う必要があるため、管理負担が大きくなっています。 フレックスタイム制や裁量労働制を効果的に機能させるためには、評価制度の改革に加え、仕事の進捗管理を従業員に任せること、適切な仕事量と納期を設定すること、そして労働者の自己管理能力を高めることが重要です。 管理職の教育も重要であり、フレックスタイム制の意義を理解していない管理職がいる限り、制度は十分に機能しません。労働時間管理の弾力化は、評価制度と同様に、多くの課題を抱えていると言えます。
3. 人事評価制度の改革 公平性と自己責任性の向上
柔軟な労働時間管理を実現するためには、人事評価制度の改革が不可欠です。 評価制度の見直しが必要だと考える人々は、評価制度全般にわたる大幅な改善を求めています。特に、評価結果の本人への説明、評価項目・基準の公開、評価者訓練の徹底など、「評価の公平性」に関する項目への要求が高いです。 現在の評価方法に不満を持つ人々は、評価がフェアではないと感じているため、改善を求めているのです。 評価制度の改革は、労働時間の弾力化と密接に関連しており、従業員の自己責任性を高め、何が評価されるのかを明確にすることが最も重要です。 目標管理制度は合理的ですが、労働法上の問題や部門間調整の難しさ、評価基準の明確化、管理職の役割の重要性などが課題として挙げられています。年俸制などの賃金制度についても、公平性の確保が重要なポイントとなります。
4. 目標管理制度の課題 目標設定 部門間調整 評価の公平性
目標管理制度は、一見合理的ですが、いくつかの課題があります。まず、目標の達成度によって報酬額を決める場合、個々の成果をどのように客観的に測定するかが問題となります。 さらに、労働法上の問題も無視できません。就業規則の不利益な変更は、裁判で無効となる可能性が高いため、目標管理制度に基づいた人事制度変更は慎重に行う必要があります。 部門間で目標の難易度が異なる場合、公平な評価が難しくなります。 そのため、評価項目と基準を事前に明確にし、評価者のばらつきを防ぐための考課者訓練が不可欠です。 管理職は、部下に目標を明確に示し、成果を的確に評価し、その理由を納得いくように説明する、そして評価結果と処遇を公正に結びつけるなど、非常に高い能力が求められます。
5. 新しい人事制度の現状と課題 モチベーション向上と制度の限界
近年、日本全国で様々な新しい人事制度が導入されています。賃金管理では年俸制、労働時間ではフレックスタイム制やリフレッシュ休暇制度、働く場所ではリゾートオフィスやサテライトオフィスなどが挙げられます。これらの制度は、従業員のモチベーション向上を目指したものです。 しかし、フレックスタイム制は、労働時間管理の手続きが煩雑になるなど、新たな課題も生んでいます。 人事担当者たちは、やる気を引き出すためのノウハウに溢れていますが、従業員の自己管理能力の向上、仕事の進め方における制約の解消、顧客や外部との調整、管理職の意識改革など、多くの課題が残されています。 これらの課題を解決し、従業員が能力を十分に発揮できる環境を整備するためには、人事評価制度の改革が不可欠です。 公平性のある評価制度を構築することが、人事制度改革の成功に繋がります。
