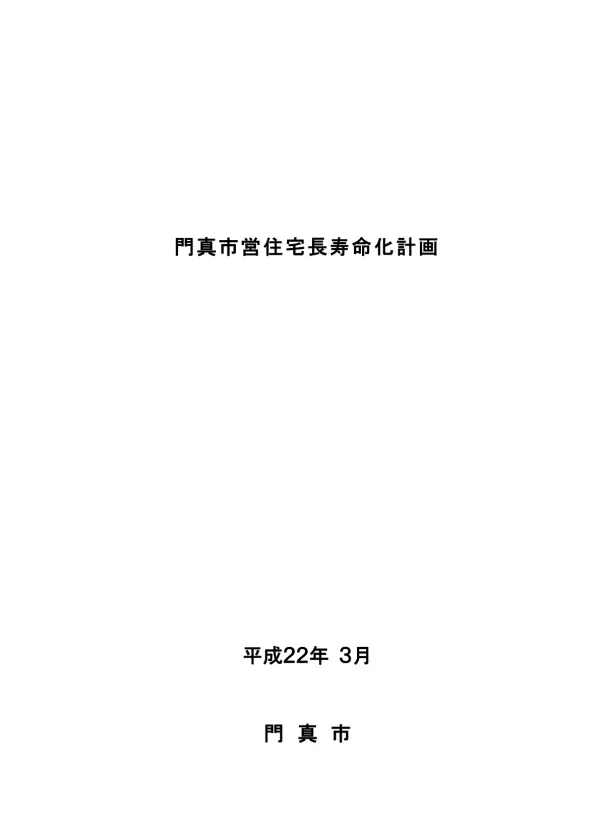
門真市営住宅長寿命化計画
文書情報
| 学校 | 門真市 (Kadoma City) |
| 専攻 | 都市計画、住宅政策、公共事業管理 (Urban Planning, Housing Policy, Public Works Management) |
| 場所 | 門真市 (Kadoma City) |
| 文書タイプ | 計画書 (Plan Document) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.41 MB |
概要
I.門真市の市営住宅 現状と課題
門真市は現在487戸の市営住宅を管理しており、その多くは昭和40年代に建設された老朽化が進む住宅です。高齢化が進む門真市において、これらの市営住宅ストックの有効活用は重要な課題となっています。特に、耐震性不足やバリアフリー化の遅れ、高額所得者や収入超過者の居住、空き家問題、そして常に高い応募倍率などが大きな問題として挙げられています。人口減少と世帯数の増加という現状も、住宅政策に影響を与えています。平成17年時点で人口は13万1,706人、世帯数は5万5,384世帯で、世帯人員の急速な縮小傾向が見られます。大阪府や近隣市と比較しても、門真市の民営借家の割合が高く、公営住宅の割合も高い点が特徴です。最低居住水準未満世帯の割合も大阪府平均より高い数値を示しています。
1. 市営住宅の現状と課題 戸数と老朽化
平成22年3月時点で門真市は487戸の市営住宅を管理しています。しかし、これらの住宅ストックの多くは昭和20~30年代、そして高度経済成長期の昭和40年代に建設されたものが約4割を占めており、老朽化が深刻な問題となっています。 老朽化によって、耐震性の不足や、非常時の二方向避難が確保されていない住棟、住戸規模や間取りと入居世帯の家族構成の不適合といった居住性の問題が顕在化しています。これらの問題は、安全性と居住性の両面から、早急な対応が必要な喫緊の課題です。市は、これらの市営住宅を『良好な社会的資産』として有効活用していく必要性を認識しており、建替えや改修、修繕といった対策を講じる必要性に迫られています。建物の長寿命化による費用と環境負荷の低減も重要な課題です。
2. 市営住宅の課題 入居管理と公平性
市営住宅の入居に関しては、真に住宅に困窮する世帯が適切に入居できていないという不公平感が問題となっています。収入超過者の存在や社会経済情勢の悪化による住宅困窮世帯の増加が背景にあります。住替えの努力義務はありますが、入居管理面での公平性の確保が大きな課題です。 また、市営住宅の応募倍率は常に高く、これは利便性の高さや建替えによる居住水準の向上によるものですが、一方で、この高い応募倍率への対応も重要な課題となっています。住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者への円滑な入居支援のため、人権部門、福祉部門と連携した取り組みが行われていますが、更なる改善が必要です。家族構成と住戸の間取りの不適合についても、適切な対応が求められています。
3. 市営住宅の課題 所有関係と居住水準
平成17年の国勢調査によると、門真市の持ち家率は48.8%と低く、民営借家率は40.2%と最も高い数値を示しています。公営・公団・公社住宅の割合も9.2%と他市に比べて高く、公的住宅への依存度が高いことが分かります。 居住水準に関しても、平成10年から15年にかけて最低居住水準未満世帯の割合は減少傾向にありますが、それでも大阪府よりも2ポイント近く高い数値となっており、改善が必要な状況です。特に、借家、特に公営住宅において最低居住水準未満世帯の割合が高いことが示唆されています。このことから、既存の住宅ストックの改善や、より質の高い住宅供給の必要性が浮き彫りになります。
4. 市営住宅の課題 人口動態と住宅供給
門真市の人口は平成2年の14万2,297人をピークに減少傾向にあり、平成17年には13万1,706人となっています。一方、世帯数は増加し続けており、平成17年には5万5,384世帯となっています。このため、世帯人員は急速に縮小傾向にあります。この人口減少と世帯数増加という現状は、住宅政策を考える上で重要な要素となります。 住宅の着工件数は平成16年をピークに減少傾向にあり、分譲住宅の割合が高いものの、持ち家の割合は増加し、借家の割合は減少しています。この動向は、市営住宅の需要と供給のバランスを考える上で重要な指標となります。特に、中堅ファミリー層への居住支援策の充実が求められます。
5. 市営住宅の課題 空き家問題と高額所得者対策
門真市の空き家率は平成10年、15年とも16%台と高く、これは他市に比べて高い割合です。空き家問題への対策も重要な課題です。また、収入超過者や高額所得者への対応として、収入認定通知書の送付とともに退去を促す説明文と、大阪府住宅供給公社、都市機構(UR)の住宅募集案内資料を送付する取り組みが行われています。しかし、より効果的な対策が必要とされています。 市営住宅は利便性の高い場所に位置しており、応募者も多いですが、高額所得者や収入超過者の存在は、真に住宅に困窮する世帯への公平な住宅供給を阻害する要因の一つとなっています。これらの課題に対処し、より効果的な公営住宅の運用を行うことが求められています。
II.高齢化と住宅政策
門真市では少子高齢化が急速に進んでいます。高齢化率は平成20年には20.5%に達し、全国および大阪府平均に近づいています。この高齢化は、バリアフリー対応や高齢者にとって安全で住みやすい住宅の必要性を高めています。既存の市営住宅ストックの改修や建替えにおいて、高齢化への対応は重要な要素となります。また、高齢者の居住の安定を図るための施策も必要不可欠です。
1. 高齢化の現状と加速
門真市においては少子高齢化が急速に進んでいます。年齢階層別人口の推移を見ると、団塊世代と団塊ジュニア世代の2つのピークが明確で、団塊世代の高齢化が進行している一方、若年世代の人口は5%前後と増加が見られません。高齢化率の推移は、昭和60年には5.5%と低かったものが、平成20年には20.5%に達しており、全国および大阪府の平均に迫る勢いです。このことから、門真市における高齢化は全国や府平均よりも急速に進んでいると言えるでしょう。この高齢化の現状は、高齢者向け住宅の必要性や、高齢者にとって住みやすい環境整備の必要性を強く示唆しています。特に、既存の住宅ストックの改修や建替えにおいて、高齢化への対応は重要な課題となるでしょう。
2. 高齢化に対応する住宅政策の必要性
急速な高齢化の進展は、住宅政策に大きな影響を与えます。高齢化が進む中で、高齢者が安全で快適に暮らせる住宅環境の整備が急務です。具体的には、バリアフリー化の推進、高齢者の居住ニーズに対応した住宅整備、そして高齢者にとって使いやすい住戸設計などが重要になります。 既存の市営住宅ストックについても、耐震性の強化、バリアフリー化の推進、エレベーター設置など、高齢化に対応した改修や建替えが必要不可欠です。また、高齢者向け住宅の供給拡大や、高齢者の円滑な住み替え支援なども重要な政策課題となります。これらの対策を通じて、高齢者が安心して暮らせる社会基盤の構築が求められます。高齢者の居住の安定を確保することは、高齢社会における重要な社会課題の一つです。
3. 住宅政策におけるその他の課題
高齢化対策と並行して、門真市では他の住宅政策課題にも取り組む必要があります。例えば、最低居住水準未満世帯の割合は、平成10年の11.1%から平成15年には8.7%に減少したものの、依然として大阪府平均より高く、改善が必要です。特に、借家、特に公営住宅において改善の余地が大きいと考えられます。 また、人口減少と世帯数の増加という現状も、住宅政策に影響を与えます。若い世代の転入と定住を促進するための魅力的な住宅地の整備、そして多様な世帯構成やライフスタイルに対応できる住宅の供給も重要な課題です。これらの課題への対応を通じて、快適で住みやすいまちづくりを進めていくことが求められています。
III.住宅の供給と需要
平成15年から19年にかけて、門真市の住宅着工件数は減少傾向にあります。分譲住宅の割合が高く推移していますが、持ち家の割合は増加傾向、借家の割合は減少傾向にあります。一方で、市営住宅への応募倍率は常に高く、需要と供給のバランスに課題があります。特に、中堅ファミリー層に対する居住支援策の充実が求められています。住宅確保要配慮者への配慮も重要であり、市は関係機関と連携して対応を図っています。
1. 住宅着工件数の推移と住宅の種類
平成15年から19年にかけての住宅の着工新設件数の推移を見ると、総数は平成16年をピークに減少傾向にあります。住宅の種類別に見ると、分譲住宅の割合が40~50%後半と高く推移しており、増減はあるものの、全体を占める大きな割合を維持しています。一方、持ち家の割合は平成18年までは10%台でしたが、平成19年には22.4%と増加傾向に転じています。これに対して、借家の割合は平成15年以降、徐々に減少傾向にあります。このデータからは、分譲住宅が住宅供給の大きな部分を占めていること、そして持ち家の割合が近年増加していることがわかります。借家需要の減少傾向も合わせて考慮すると、今後の住宅政策において、供給される住宅の種類とそのバランスをどのように調整していくかが重要な課題となります。
2. 住宅需要と供給のギャップ 市営住宅への高い応募倍率
門真市の市営住宅は、最寄り駅からのアクセスが良く、比較的新しい団地が多く、利便性が高いことから、常に応募倍率が高くなっています。この高い応募倍率は、市営住宅への需要が供給を大きく上回っていることを示しています。 特に、中堅ファミリー層に対する居住支援策の充実が求められています。 この需要と供給のギャップは、住宅政策における重要な課題であり、住宅供給の拡大や、より多くの世帯のニーズに対応できるような住宅政策の策定が必要となります。 また、住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者に対する円滑な住宅供給に向けた取り組みも進められていますが、需要の高まりに対応できるよう、更なる努力が求められています。
3. 所有形態の現状と課題 持ち家率の低さと借家率の高まり
昭和60年から平成17年までの所有関係別住宅数の推移をみると、持ち家率は昭和60年から平成7年までは43%前後で推移していましたが、平成12年以降は増加傾向にあります。一方、民営借家の割合は平成7年から17年の10年間で約5ポイント減少しています。平成17年の国勢調査では、門真市の持ち家率は48.8%と低く、民営借家率は40.2%と最も高い数値となっています。公営・公団・公社住宅の割合も9.2%と他市に比べて高いことから、門真市では住宅の所有形態に特徴があり、民営借家や公営住宅への依存度が高いことがわかります。この現状を踏まえ、将来的な住宅政策においては、持ち家率の向上や、多様なニーズに対応できる住宅供給のあり方が検討課題となります。
IV.門真市の将来像と都市計画
門真市の将来像は「人・まち “元気” 体感都市 門真」です。この将来像を実現するために、魅力ある住宅地の整備、駅周辺の拠点づくり、住宅と産業の共存、密集市街地改善など、様々な課題に取り組む必要があります。特に、市営住宅跡地の有効活用は、都市環境改善に大きく貢献する可能性を秘めています。 耐震化、バリアフリー化、そしてストック長寿命化といった視点も、将来計画に不可欠です。
1. 門真市の将来像 目指す都市イメージ
門真市の将来像は「人・まち “元気”体感都市 門真」と定義されています。この将来像を実現するために、市民が誇りに思う新たな都市イメージの形成を目指し、オンリーワンのまちづくりプロジェクトの推進が課題として挙げられています。具体的には、市の中心的な都市機能や商業機能、公開緑地機能などを複合的に備えた北西部まちづくり整備ゾーンの整備を核として、市の顔づくりを進めることが計画されています。 この計画では、快適で便利な都市生活の創造、そして市民生活環境の確保が重要な柱となっています。 安全で安心な暮らし、便利で快適なまちなか、人や環境に優しい美しいまちづくりといった基本政策が掲げられており、これらの実現に向けた具体的な施策が展開されています。
2. 都市計画における住宅政策 既存住宅地の整備と新規開発
都市計画においては、住宅地の整備が重要な課題です。北部・南部地域の一部の既成住宅地は、良好な住宅環境を備えた住宅地として修復・再整備を促進し、南部地域の旧集落や低層住宅地は自然との調和を保ちつつ維持・保全に努める計画です。新たな住宅開発においては、良好な住環境を有した住宅地形成の誘導に努めます。 具体的には、幸福町・垣内町・中町地区まちづくりにおける住宅供給、府営門真住宅の建替えに伴う民間住宅の供給、木造賃貸共同住宅が密集する地区での住宅の建替えなどが挙げられており、家族で定住できる住宅の供給を誘導することが目指されています。これらの施策を通じて、魅力ある住宅地を形成し、若い世代を中心とした転入と定住を促進することで、バランスの良い年齢構成の都市づくりを目指すことが示されています。
3. 都市計画における市営住宅の役割 跡地の有効活用とストック長寿命化
市営住宅の建替えや改修にあたっては、福祉施策やまちづくり施策との連携を図り、多様な住宅や地域の活性化につながる施設等の導入が検討されています。市営住宅跡地は貴重な都市資産であることから、住宅密集市街地問題の克服に有効活用される予定です。 また、既存の市営住宅ストックの長寿命化も重要な課題です。耐震診断の結果に基づき、耐震性の不足する住棟やバリアフリー未整備の住棟については、早期に改修や建替えによる住宅整備水準の向上を進める必要があります。市営住宅入居者の高齢化も進んでいるため、バリアフリー等のニーズに合わせた整備が不可欠です。 これらの取り組みを通じて、安全で安心な住まいを提供し、快適な市民生活環境を確保することが目指されています。
