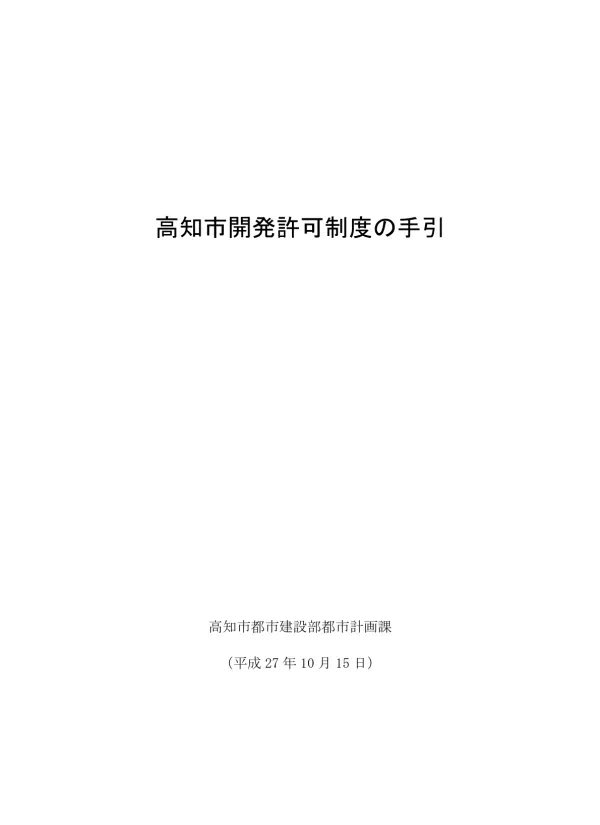
開発許可申請の手引き
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.19 MB |
| 専攻 | 都市計画 |
| 文書タイプ | 手引き |
概要
I.第1章 開発許可制度の概要 高知市 における 開発許可 の必要性と種類
高知市で都市計画法に基づく開発行為を行う場合、開発許可が必要となるケースが多いです。特に、市街化区域内では、開発区域面積が1,000㎡以上の開発行為は原則として市長の許可が必要です。市街化調整区域では、開発行為だけでなく、建築物の新築・改築・用途変更なども厳しく制限され、原則として建築許可が必要です。開発許可申請の際には、道路、下水道などの公共施設の整備状況や、宅地の安全性などが法第33条の基準に適合している必要があります。宅地造成等規制法や高知市土地保全条例に基づく許可・届出も必要となる場合があります。
1. 市街化区域内の開発許可
市街化区域において、開発区域の面積が1,000㎡を超える開発行為を行う場合は、原則として市長の開発許可が必要です(法第29条)。この許可を得るためには、開発計画が道路、下水道、公園などの公共施設の整備状況、宅地の安全性、工事施工能力など、法第33条の基準に適合している必要があります。開発区域の面積が1,000㎡未満であっても、開発行為が連続して行われ、合計面積が1,000㎡以上になる場合は、開発許可が必要となる可能性があります。 その他、宅地造成等規制法に基づく宅造許可や、高知市土地保全条例に基づく届出が必要な場合もあります。開発許可の要否については、個別案件ごとに判断されるため、高知市都市計画課へのご相談が推奨されます。
2. 市街化調整区域内の許可
市街化調整区域内では、開発行為を行う場合だけでなく、開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新設なども厳しく制限されています。そのため、これらの行為を行う場合は原則として建築許可が必要です。市街化調整区域で開発行為を行う場合は、法第33条の基準に加え、法第34条の立地基準にも適合しなければなりません。開発区域内における建築物等の用途変更についても、市長の許可が必要です(法第42条)。また、開発許可を受けた開発区域以外の区域において、開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新設を行う場合も、市長の許可が必要です(法第43条)。開発行為の定義や、開発区域の範囲については、この手引きの他の章で詳しく説明されています。
3. 開発許可申請に関する注意事項
この手引きは、都市計画法に基づく開発許可申請の手続きを円滑に進めるための基準をまとめたものです。しかし、この手引きに該当する場合でも、開発申請の要否は個別案件ごとに判断されます。そのため、不明な点や具体的な申請手続きについては、高知市都市計画課に必ずご相談ください。 特に、開発区域の面積、開発行為の定義、開発区域の範囲の判断は複雑な場合があります。必要に応じて、土地の登記簿、線引き日以前の航空写真、固定資産税課税台帳などの資料を提出する必要があるかもしれません。 また、宅地造成等規制法や高知市土地保全条例などの関連法規にも注意が必要です。これらの条例に基づく許可や届出が必要となるケースもあります。
II.第2章 開発行為の定義 開発行為 とは何か
開発行為とは、都市計画法第4条第12項で定義されるように、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」です。建築物の建築や特定工作物(コンクリートプラント、アスファルトプラントなど政令で定められたもの)を目的とし、かつ土地の区画形質(地盤高の変更、区画の分割・統合など)を変更する行為が該当します。単なる権利区画の変更や、既存建築物の除却のみなどは、開発行為に該当しない場合があります。開発区域面積が1000㎡未満でも、開発行為が連続して1000㎡を超える場合は開発許可が必要になる可能性があります。
1. 開発行為 の法的定義
この章では、都市計画法における「開発行為」の定義を解説します。法第4条第12項では、「開発行為」を「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義しています。この定義から、開発行為には、建築物や特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更が含まれることが分かります。 ただし、建築物の建築等を目的としない造成行為は、必ずしも開発行為に該当するとは限りません。そのような場合は、宅地造成等規制法に基づく宅造許可や、高知市土地保全条例に基づく届出が必要となる可能性があります。 また、建築物等の建築を目的とする場合でも、土地の区画形質の変更がない場合は、開発行為には該当しません。 区画形質の変更とは、地盤の高さを変える行為や、土地を分割・統合する行為などを指します。単なる権利区画の変更や、切土、盛土等の造成工事を伴わない、形式的な区画の分割・統合は区画の変更に該当しません。
2. 建築物の建築 と 特定工作物 の解釈
「建築物の建築」については、法第4条第10項を参照する必要があります。一方、「特定工作物」は、法第4条第11項、政令第1条第1項、第2項で定義され、「周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(第一種特定工作物)」または「大規模な工作物(第二種特定工作物)」とされています。第一種特定工作物には、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなどが含まれ、第二種特定工作物には、1ha以上のゴルフコース、野球場、墓園などが含まれます。 運動・レジャー施設の中には、特定工作物に該当しないものもあります。博物館法に規定する施設や、ピクニック広場、キャンプ場、スキー場などは、必ずしも特定工作物とはみなされません。危険物の貯蔵や処理に供する工作物も特定工作物に含まれる可能性があります。これらの定義は、開発行為の判断に重要な要素となります。
3. 区画形質の変更 の詳細
「土地の区画形質の変更」は、区画の変更と質の変更に大別されます。「区画の変更」とは、公共施設の新設、付替え、廃止などによって土地を分割または統合する行為です。公共施設には、道路、公園、下水道などが含まれます。具体的には、地盤高の変更(50cm以上)、修景施設の設置・変更・撤去、既存擁壁の補強・積み直し、建築基準法に基づく道路後退などが該当します。一方、「質の変更」とは、農地や池沼などの宅地以外の土地を宅地にするなど、土地の性質を変える行為を指します。高知市では、市街化区域内で質の変更を行う面積の合計が1,000㎡以上の場合、開発許可申請の手続きが必要となります。 既存の建築物が建築確認で建築敷地とされた土地、線引き日以前から宅地として利用されていた土地などは、「質の変更」とはみなされません。開発行為に該当するかどうかは、これらの定義を基に、個々のケースで慎重に判断する必要があります。
III.第3章 開発区域の範囲 開発許可申請 に必要な 開発区域 の確定
開発許可申請では、開発区域の正確な範囲を定める必要があります。開発区域は、都市計画法第4条第13項で定義され、建築物の敷地、特定工作物の敷地、附属の駐車場、公共施設用地、造成行為を行う土地などが含まれます。隣接地との関係も重要で、同一所有者の一団の土地であれば、隣接地も開発区域に含まれる場合があります。ただし、既に宅地として利用されている土地や、農地、露天駐車場などは、場合によっては開発区域から除外できる可能性があります。開発区域の判断は複雑なため、高知市都市計画課への相談が推奨されます。
1. 開発区域の定義と対象範囲
開発許可申請において、開発区域の明確な範囲を定めることは非常に重要です。法第4条第13項では、「開発区域」を「開発行為をする土地の区域」と定義しています。この開発区域には、建築物の敷地や特定工作物の敷地が含まれます。さらに、それらの敷地と一体的に利用される附属の駐車場なども開発区域に含まれます。 公共施設の用に供される土地、例えば既存道路や水路の付け替えによる土地なども開発区域に含まれます。造成行為を行う土地も原則として開発区域となりますが、建築目的がないと判断され、かつ隣接地の土地所有者が異なる場合は、開発区域から除外できる場合があります。 開発区域に隣接し、所有者が開発区域内の土地所有者と同一で、隣接地の開発行為に伴い区画形質が変更される土地も、開発区域に含める必要があります。同一土地所有者の一団の土地で、建築物の除却後に区画の変更となる土地は全て開発区域とみなされます。ただし、すでに宅地として利用されている土地や、農地、露天駐車場などは、条件によっては開発区域から除外される場合があります。
2. 開発区域からの除外と一体利用の考え方
既に宅地として一定の土地利用がなされている土地(適法に建築された建築物の敷地で引き続き利用される土地)は、開発区域から除外できる場合があります。同様に、農地、露天駐車場、資材置場などとして一定の土地利用がなされている土地も、開発区域から除外できる可能性があります。これは、同一土地所有者の一団の土地であっても、宅地以外の用途で利用されることが明らかな土地に該当する場合です。 隣接する農地などを一体で造成する場合、全体を開発区域とするのが基本的な考え方ですが、個別案件ごとに判断されます。隣接地との境界が確定していない場合なども、開発区域からの除外を検討する必要があります。開発区域に隣接する同一所有者の土地で、区画形質の変更が伴わずに建築物を建築できる土地も、開発区域から除外できます。土地保全条例による届出がなされたまま造成行為が完了していない土地や、無許可で造成している土地などは、時期を問わず全体を開発区域とみなします。
3. 開発区域の判断と相談窓口
開発区域の範囲の判断は、個々のケースによって複雑なため、高知市都市計画課へのご相談が強く推奨されます。開発申請の要否は、提示された事例を参考に、個別案件ごとに判断されます。 開発区域の範囲を判断する際には、土地の登記簿、線引き日以前の航空写真、固定資産税課税台帳などの資料が活用されます。 敷地の一部を分割して別の敷地として建築する場合、既存建築物が引き続き利用される場合は、新築建築物の敷地を開発区域とします。敷地を拡張して増築する場合は、建築敷地全体が開発区域となります。附属の駐車場についても、建築物の敷地と一体的に利用される場合は開発区域に含める必要がありますが、形質の変更がない場合は、開発区域に含まれない場合があります。不明な点があれば、必ず都市計画課にご相談ください。
IV.第4章 開発行為等が完了した土地の隣接地の扱い 隣接地の 開発行為 と一体性
既に開発行為が完了した土地(A地)に隣接する土地(B地)で、一定の条件を満たす開発行為が行われる場合、A地とB地を合わせた区域を開発区域として扱う場合があります。この一体性の判断は、開発行為の開始時期、機能的一体性、土地所有者、土地利用形態など、複数の要素を総合的に考慮して行われます。具体的な判断基準は複雑なため、高知市都市計画課への相談が必要です。 開発行為の完了時期は、開発許可取得、宅地造成等規制法の許可、位置指定、建築確認などの取得日によって異なります。
1. 開発行為の一体性に関する基準
この章では、既に開発行為等が完了または継続している土地(A地)に隣接する土地(B地)における開発行為等が、A地との一体性を有する場合の取り扱いについて説明します。 A地とB地で開発行為等が一体性を有すると判断される場合、A地とB地を合わせた区域全体を開発区域として扱います。この一体性を判断する基準は、まず、B地における開発行為等の開始時期がA地における開発行為等の完了後1年以内であること、そして、A地とB地が法令上の手続き不要な造成行為が行われた土地を含む場合にも適用されます。 A地の開発行為等の完了時期は、開発許可を受けた場合は工事完了公告日、宅地造成等規制法の許可を受けた場合は検査済証の発行日、位置指定道路の場合は位置指定日、建築確認を受けた場合は建築確認日となります。ただし、建築確認を受けたが計画が中止され建築が行われていない場合は、開発行為等の完了とはみなされません。 A地とB地の一体性は、隣接地として機能的に一体と認められる場合、あるいは土地利用形態などから客観的に判断して実質的に一つの開発行為と認められる場合に成立します。例えば、開発者などが異なっていても、一団の土地として区画変更され一体販売されるケースなどが該当します。
2. 一体性判断における注意事項
A地とB地の一体性を判断する際には、いくつかの注意事項があります。まず、A地およびB地には、法や条例の手続きが不要な造成行為(駐車場目的などの建築目的以外の区画形質の変更)が行われた土地が含まれる可能性があります。 しかし、A地とB地の間で、がけ等による高低差が著しく、一体として使用することが困難な場合は、B地は隣接地として扱われません。 A地とB地の一方の区域に区画形質の変更がなく、かつ一体利用されない区画がある場合、またはA地とB地全体を検討しても法第4条第12項に規定する開発行為に当たらない場合は、開発区域として扱う必要はありません。 開発行為等の完了時期や、一体性の判断基準は複雑なため、不明な点については高知市都市計画課にご相談ください。
