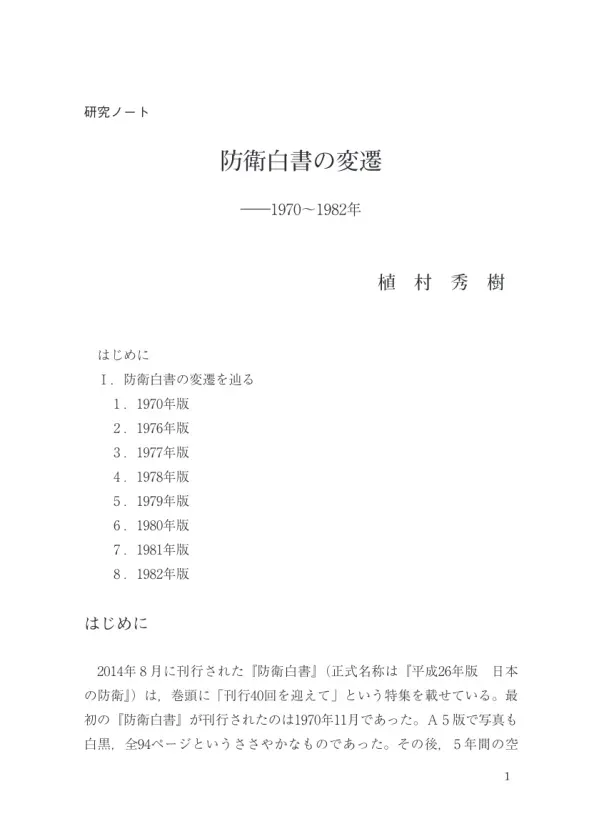
防衛白書変遷史:40年を辿る
文書情報
| 学校 | 大学名(不明) |
| 専攻 | 政治学、国際関係学、歴史学など |
| 出版年 | 不明(2014年版防衛白書を参照していることから、それ以降と推測) |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 研究論文、論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.96 MB |
概要
I.最初の防衛白書 1970年 と国民意識
1970年、中曽根康弘元首相(当時防衛庁長官)の下で最初の防衛白書が刊行されました。この時代は、国民の厭戦感や旧軍のイメージが強く、自衛隊への風当たりが厳しい状況でした。「日米安全保障条約」への反対を唱えていた中曽根氏ですら、白書刊行に慎重な意見が庁内にありました。しかし、国民の理解と支持が不可欠と判断し、白書発行を推進しました。白書の内容は、国際情勢の不安定さを強調し、専守防衛の必要性を訴えるものでした。国民の防衛意識を高めるため、「国を守る心」を説く内容も見られます。当時としては、まだ集団的自衛権や積極的平和主義といった概念は明確に示されていませんでした。
1. 最初の防衛白書の刊行と政治的背景
1970年、敗戦から25年、自衛隊発足から16年という節目の年に、中曽根康弘氏(当時防衛庁長官)によって最初の防衛白書が刊行されました。しかし、この時点では国民の間には未だ強い厭戦感や旧軍への負のイメージが存在し、自衛隊に対する批判的な意見も根強かったため、白書刊行自体が防衛庁内部ではタブーとされていたとされています。中曽根氏は、国会での野党の追及や国民の不必要な疑心を招く可能性を懸念する声もあったにも関わらず、国の防衛には国民の理解と積極的な支持が不可欠との信念から、白書の刊行を推進しました。この最初の白書には、大臣による前書きすら存在せず、その内容も、当時の国民意識を反映した、やや回りくどい表現で始まっている点が注目されます。 これは、武力による防衛という考え方が、当時まだ国民に十分に浸透していなかったことを示唆しています。
2. 1970年版防衛白書の内容と国民への訴え
1970年版防衛白書は、国際情勢の不安定さを強調する記述から始まりました。朝鮮戦争、中印国境紛争、中ソ国境紛争、ベトナム戦争など、アジアにおいても武力紛争が頻発していた現実を指摘し、国連への平和維持への依存だけでは不十分であると主張しています。白書の第1部では、「安全保障のための人類の努力」と題し、国際連合の理想と現実、集団安全保障体制、軍事技術の進歩、そして最後に「国を守る心」について論じています。「われわれは、わが民族の共同生活体や国土の安泰と繁栄を願い、独立と平和の維持されることを祈ってやまない」という記述は、国民の平和への希求を反映している一方、「われわれ国民は、不正な侵略からわれわれの国民共同生活体や国土を守るため、国をあげて最善の抵抗を尽さなければならない」と、国民一人ひとりに防衛への責任を訴える記述も含まれています。 この部分では、愛国心を「郷土への愛着」や「国が栄えよとの人間自然の情」と定義しつつも、国家の危急には身を挺して国を守る熱意が必要であると強調しています。 この記述は、後の「単一民族国家」論への批判につながるものとして、興味深い対比をなしています。
3. 国を守る心 と国民的合意の難しさ
1970年版防衛白書は、国民の防衛意識を高めるために「国を守る心」という概念を提示しました。 しかし、この概念は、個人の責任感を「国」に対する「務め」へと転化させ、「愛国心」として「国家」に回収する構造を示しており、必ずしも国民の共感を完全に得られるものではなかった可能性も示唆しています。 「国を愛する」ことと「国家の危急」に際して身を挺して国を守ることは、必ずしもイコールではないという歴史的、国民的実感とのずれが存在した可能性が読み取れます。「黒い雨」における元兵士の言葉「わしらは国家のない国に生まれたかったのう」は、この「国」と「国家」の差異を象徴的に示すものとして挙げられています。 また、民族文化の保護を国民の義務として位置づける記述も、個人を基礎とする日本国憲法の精神との整合性について疑問を投げかける内容となっています。このことから、当時の日本における国民的合意形成の困難さが伺えます。
II.防衛白書における防衛政策の変遷 1970年代後半 1980年代
1970年代後半から1980年代にかけて、防衛白書は、日米安全保障体制の強化、防衛力整備計画の策定、自衛隊の統合運用強化、そして国民への理解促進に重点を置いていました。ソ連の軍事力増強への対応、基地問題への対処、そして憲法と自衛権の解釈をめぐる議論が重要なテーマでした。特に、坂田防衛庁長官時代の白書では、国民への意見聴取を重視し、国民の理解を得るための努力が強調されています。日米防衛協力の枠組みも強化され、海外派兵に関する政府見解も明確化されていきました。この期間、総合安全保障という概念も登場し、軍事と非軍事両面からのアプローチが重視されるようになりました。 愛国心や「国を守る心」といった概念も、国民の防衛意識を高める文脈で繰り返し登場します。
1. 防衛力整備計画と国民への説明責任
1970年代後半から1980年代にかけての防衛白書では、防衛力整備計画の策定と、その国民への説明責任が重要なテーマとなっています。それまでの5か年計画方式から、「防衛計画の大綱」へと移行した背景には、ソ連の軍事力増強という国際情勢の変化だけでなく、経済財政上の制約や、将来的な若年隊員の確保の困難さといった国内事情も考慮されていました。坂田元防衛庁長官は、防衛力整備計画の策定にあたって、国民の意見を様々な段階で聴取し、国民の合意形成を目指したプロセスを重視していたと述べています。これは、長年防衛庁内部に存在した消極的な雰囲気を打破し、国民の理解を得るための積極的な姿勢を示すものでした。しかし、国民の防衛問題への関心の低さや、平和憲法という歴史的背景は、防衛庁・自衛隊にとって依然として高い壁となっていました。
2. 日米安全保障体制の強化と役割分担
防衛白書では、日米安全保障体制の強化と、その枠組みにおける日本の役割分担が繰り返し強調されています。坂田元防衛庁長官とシュレシンジャー米国防長官との会談を契機に、「日米防衛協力のための指針」が策定され、防衛庁長官と米国防長官との間で年1回の会談を行うことで合意されました。これは、有事の際の防衛協力について日米間で協議する仕組みがなかった状況を改善するための一歩でした。 しかし、白書では国連の集団安全保障と日米安全保障条約などの「共同防衛」の区別が明確でない点も指摘されており、日米安保体制への依存度が高まっていることが示唆されています。 「安保ただ乗り」論への反論も試みられていますが、日本の安全保障が日米安全保障体制に大きく依存しているという認識が、日本の防衛負担増大への国民の理解を得る上で有効に機能していた可能性も示唆されています。 鈴木善幸首相とレーガン大統領の日米首脳会談後の共同声明で「適切な役割分担が望ましい」とされたこと、およびソ連の軍備拡張に対抗する米国の軍拡への日本の参加が、この認識を背景としていると考えられます。
3. 自衛隊の統合運用と国民への防衛意識啓発
防衛白書は、自衛隊の統合運用強化についても触れています。陸・海・空自衛隊間のセクショナリズムが強く、統合運用が遅々として進まなかった現状を認めつつ、統合演習の積極的な推進により、強固な連携と統合運用のための基盤を確立していく必要性を訴えています。 また、国民の防衛問題に対する関心の低さを憂慮し、有事法制の整備を訴える一方で、自衛隊自身の統合運用体制の不備も同時に指摘している点は興味深いです。 白書では、「国民一人一人が侵略に抵抗する意思、国を守る気概を持つこと」「憲法に則り必要最小限度の防衛力を着実に整備すること」「日米安保条約を堅持すること」を3本の柱として提示しており、国民一人ひとりの防衛意識の向上と、日米安保条約の有効活用を強く求めています。 さらに、基地問題についても、都市化の進展に伴い、従来の農山漁村部から都市部へと問題の様相が変化していることを指摘し、土地の効率的利用や生活環境の保全といった都市問題の一環として捉える必要性を強調しています。 沖縄における米軍基地の整理・縮小・返還問題についても、その進捗状況と課題が指摘されています。
III.日米安全保障体制と日本の役割 1970年代後半 1980年代
日米安全保障条約は、防衛白書の主要テーマであり続けました。当初は国連の集団安全保障への依存を否定しつつも、日米安保体制への依存を認める記述がみられ、次第にその依存度を高める記述へと変化していきました。特に、ソ連の軍事力増強を背景に、日米安全保障体制は日本の安全保障にとって不可欠なものとして位置づけられ、その強化が繰り返し強調されました。 日米防衛協力に関する具体的な協議の場も設けられ、役割分担の議論も進展していきます。しかし、この体制への「安保ただ乗り」論への反論も、白書の中で試みられました。
1. 日米安全保障体制への依存と 安保ただ乗り 論への反論
1970年代後半から1980年代にかけての防衛白書において、日米安全保障体制は日本の安全保障にとって極めて重要な位置づけを占めていました。初期の白書では、国連の集団安全保障体制の不備を指摘しつつ、日米安全保障条約の意義を認めながらも、一方的な依存ではないことを強調していました。しかし、時代が進むにつれ、ソ連の軍事力増強や国際情勢の変化を背景に、日本の防衛力の不足を補うために日米安全保障体制への依存度が徐々に高まっていきました。白書では、核兵器の脅威や大規模侵略への対処能力において、米国への依存を明確に示す記述が見られます。このことは、日米安保体制の強化が、そのまま米国への依存強化を意味するのではないかという疑問も生じさせます。 一方で、白書は「安保ただ乗り」論への反論も試みており、日本が外交、経済などの非軍事的手段を通じて国際平和に貢献していること、そして自国の安定がアジアの安定に不可欠であるとの認識に基づき、自衛の範囲内で防衛努力を払っていることを強調しています。この記述は、日米安全保障体制への依存を正当化するための論拠として機能していると考えられます。
2. 日米防衛協力の強化と協議メカニズムの構築
日米安全保障体制をより実効性のあるものとするため、防衛協力に関する具体的な協議メカニズムの構築が図られました。坂田防衛庁長官とシュレシンジャー米国防長官との会談は、その重要な転換点となりました。この会談では、日米安保協議委員会の枠内で新たな協議の場を設け、防衛庁長官と米国防長官が原則として年1回会談を行うことで合意されました。 これにより、「日米防衛協力のための指針」が策定され、自衛隊と米軍間の共同作戦計画の研究などが進められました。 しかし、当時の日米安全保障協議委員会は、米国側が国務長官や国防長官ではなく、駐日米国大使と太平洋軍司令官(あるいはその代理)によって構成されていたことから、防衛庁長官と米国防長官が直接会談を行うという合意は、当時の日米関係において画期的な出来事であったと言えます。 この新たな協議メカニズムの構築は、日米間の安全保障協力の深化を示す一方、日本側の防衛負担の増大を招く可能性も孕んでいました。
3. 役割分担論議と日本の防衛負担の増大
日米安全保障体制における役割分担の議論は、日本の防衛負担の増大と密接に関連していました。鈴木善幸首相とレーガン大統領の日米首脳会談後の共同声明では、日本の防衛と極東の安定確保のために「日米両国において適切な役割分担が望ましい」と宣言されました。 この声明を受けて、日本の防衛負担増大を国民に納得させるために、日本の安全保障が日米安全保障体制に大きく依存しているという認識が強調されたと考えられます。 これは、ソ連の軍備拡張に対抗するレーガン政権の軍拡に日本も加わることを正当化する論拠として機能していた可能性があります。 白書においても、日米安保体制に高い位置づけを与え、その意義を防衛にとどまらないものとして説明することで、日本の負担増大への国民的合意形成を図ろうとする姿勢が読み取れます。 しかし、このアプローチは、米国への依存強化を意味するものであり、その点についての批判的な視点は、白書からは読み取れません。
IV.防衛白書における国民意識と愛国心
防衛白書は、国民の防衛意識を高めることを重要な目的としていました。初期の白書では、国民の厭戦感を払拭し、自衛隊への理解を深める必要性を訴えていました。しかし、時代と共に、単なる「愛国心」の喚起ではなく、より多角的なアプローチが必要となることが認識されます。国民一人ひとりの責任感、自由と平和な生活を守るための意思、そして「国を守る気概」が、防衛への積極的な参加へと繋がるという考え方が提示されました。 ただし、「民族」という概念は慎重に扱われ、日本国憲法の精神との整合性にも配慮が払われていました。
1. 国民意識の変化と防衛への関与
防衛白書は、国民の防衛意識、特に「国を守る心」や「愛国心」の醸成に大きな関心を払っていました。初期の白書では、戦後日本の厭戦感や旧軍への負の遺産を踏まえ、自衛隊への理解促進と防衛への積極的な関与を促す記述が見られます。 「国を守る心」は、国民一人ひとりが不正な侵略から国土と生活を守るため、最善の抵抗を尽くす義務を指し、祖先と子孫への責任、愛国心の発露として位置づけられています。この「愛国心」は、郷土への愛着や国家の平和的発展への願いといった普遍的な感情と、国家の危機に際して身を挺して国を守る熱意を包含した、複雑な概念として描写されています。 しかし、この「国を守る心」や「愛国心」という概念は、個人の責任感を国家への奉仕という枠組みに収斂させる構造を示しており、必ずしも国民全体の共感を完全に得られるものではなかった可能性も示唆されています。 井伏鱒二の『黒い雨』における「わしらは国家のない国に生まれたかったのう」というセリフは、この「国」と「国家」の概念の差異、そして国民の複雑な心情を象徴的に示しています。
2. 愛国心 の概念と防衛政策への影響
防衛白書における「愛国心」の概念は、時代とともに変化しています。初期の白書では、国民の防衛意識を高めるための手段として、やや単純化された「愛国心」の概念が用いられていましたが、次第に、より多角的で複雑な定義が提示されるようになります。 「偏狭で、排他的な愛国心」は避けられ、「美しい郷土への愛着」や「生活共同体の平和的発展への願い」といった、より普遍的で包摂的な「愛国心」の解釈が強調されていきます。「国を守る気概」という概念も登場し、国民一人ひとりが自らの手で国を守ろうとする意思、そして防衛政策に積極的に参加・協力するという意志が重要視されるようになりました。 しかし、この「国を守る気概」も、個人の責任感を国家への「務め」として定義づけ、最終的には「国家の危急に際し、力を合わせて国を守る」という、国家への奉仕を強く求める方向へと導かれています。 この「国を守る」という概念と「国家の危急」に際しての行動が必ずしも同一ではないという点も、歴史的教訓として留意されている点が注目されます。
3. 国民的合意形成の困難さと防衛政策の課題
防衛白書は、国民の防衛問題への無関心や感覚的な拒絶という風潮を懸念しつつも、防衛力が戦争のための手段ではなく、戦争を防止するための平和維持手段であるという理解が進みつつある点を評価しています。 しかし、防衛に関する国民的合意が十分に得られていないという現実も認識されており、防衛問題は容易に政治的・社会問題となりやすいという課題が指摘されています。 基地問題はその典型的な例であり、イデオロギー的な反対運動や土地利用問題、環境問題などが複雑に絡み合った、時代と共に変化する課題として認識されています。 沖縄における米軍基地の整理・縮小・返還問題も、その象徴的な例であり、返還後も米軍基地が沖縄の土地の大部分を占めている現状は、国民的合意形成の困難さを示す象徴となっています。このことは、防衛政策を進める上で、国民との間の継続的な対話と理解促進が不可欠であることを示しています。
V.主要人物
中曽根康弘 (Nakasone Yasuhiro), 坂田, 三原朝雄, 栗栖弘臣, 金丸信, 鈴木善幸, ロナルド・レーガン, 安倍晋三
1. 中曽根康弘
中曽根康弘元首相は、最初の防衛白書刊行当時の防衛庁長官でした。憲法改正を唱え、日米安全保障条約の批准に反対する立場を取りながらも、国民の理解と支持なしに国の防衛は成り立たないという信念から、白書刊行を推進しました。2014年版白書への寄稿では、当時の国民意識における厭戦感や旧軍のイメージ、そして自衛隊への強い批判的風潮に触れ、白書刊行が防衛庁内部でタブーとされていた状況を説明しています。 東日本大震災後の自衛隊の活動に対する国民からの称賛を踏まえつつ、国際協調主義に基づく積極的平和主義を述べていますが、安倍政権のそれとは異なる評価をしている点を指摘しています。1970年版白書には大臣による前書きがなく、その内容は国際情勢の不安定さを強調し、国民の防衛意識を高めるために「国を守る心」を説くものでした。後に「単一民族国家」論で批判を浴びる中曽根氏ですが、1970年当時はこの点が問題視されることは少なかったとされています。
2. 坂田
坂田氏は、防衛力整備計画の策定において国民への意見聴取を重視した人物として描かれています。国民の各界各層から寄せられる意見を踏まえながら計画を練り上げ、国民の大方の合意を得られることを目指していました。国民全員の納得は不可能だと認識しつつも、国民との対話を通して防衛政策を進める姿勢を示したことが、白書の中で強調されています。 また、坂田氏はシュレシンジャー米国防長官との会談を主導し、日米安保協議委員会の枠内で新たな協議の場を設け、防衛庁長官と米国防長官との間で年1回の会談を行うことで合意に導きました。これは、「日米防衛協力のための指針」策定につながる画期的な出来事でした。 さらに、坂田氏は「国民一人一人が侵略に抵抗する意思を持つこと」「憲法に則り必要最小限度の防衛力を整備すること」「日米安保条約を堅持すること」を、防衛の3本の柱として挙げ、日米安保条約を実効性のあるものにするための政策を推進しました。
3. その他の主要人物
この文書では、他に三原朝雄(坂田の後任防衛庁長官)、栗栖弘臣(統合幕僚会議議長、「超法規発言」で問題となった)、金丸信(防衛庁長官、栗栖氏の事実上の解任に関与)、鈴木善幸(首相、日米同盟論議に関連)、ロナルド・レーガン(米国大統領、日米首脳会談で役割分担を宣言)、安倍晋三(首相、2015年の安全保障体制に関する国会質疑で、40年前からの政府見解を踏襲)といった人物も言及されています。 これらの主要人物の言動や政策決定は、防衛白書の内容や方向性に大きな影響を与えており、それぞれの役割を理解することが、防衛白書の変遷を分析する上で重要です。特に、栗栖氏の「超法規発言」とその後の対応は、防衛庁内部における文民統制の問題や、防衛政策に関する情報公開のあり方に関する議論を促した出来事として、白書の中で取り上げられています。
