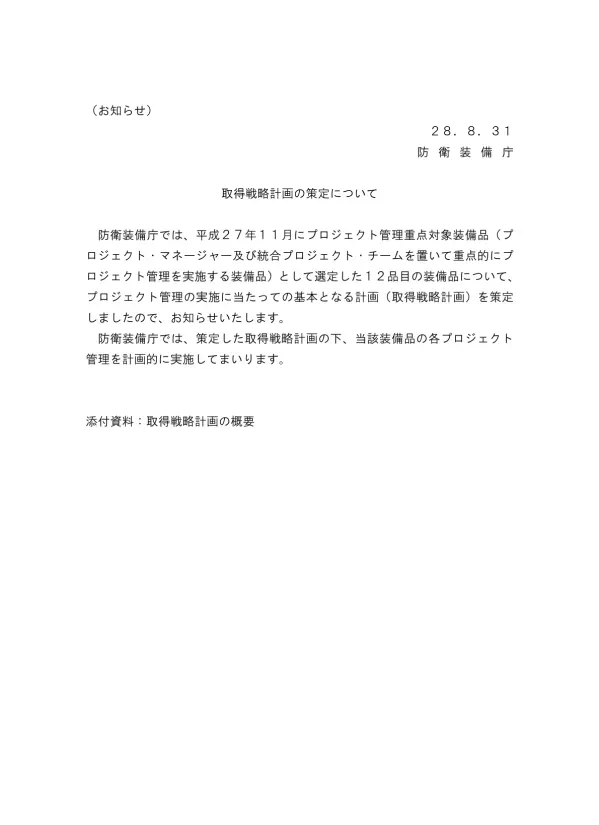
防衛装備取得戦略:SM-3ブロックⅡA
文書情報
| 著者 | 防衛装備庁 |
| 文書タイプ | お知らせ |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 319.97 KB |
概要
I.弾道ミサイル防衛システム強化のための取得戦略計画
防衛装備庁は、北朝鮮の弾道ミサイル能力向上への対応として、我が国全域を防御可能な即応態勢・同時対処能力・継続対処能力強化のための弾道ミサイル防衛システムの取得戦略計画を策定しました。計画には、21インチロケットモーターによる推進能力増大、2波長シーカーによる識別能力向上などの機能・性能向上、ならびに日米の所要に対応した生産体制構築が含まれます。**ライフサイクルコスト(LCC)**の削減も重要な課題です。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、北朝鮮の弾道ミサイル能力向上を踏まえ、我が国の弾道ミサイル対処能力の総合的な向上を図ることです。具体的には、我が国全域を防護できる即応態勢、同時対処能力、そして継続的に対処できる能力の強化に資することを目指しています。これは、増大する北朝鮮のミサイル脅威に対して、日本の防衛力を強化し、国民の安全を確保するための喫緊の課題への対応として位置づけられています。計画は、既存システムの能力向上だけでなく、将来的な脅威に対処できるよう柔軟性を考慮した設計となっています。 この計画は、日本が独自に開発した技術だけでなく、同盟国であるアメリカ合衆国との協力体制の下、開発・生産体制の構築も視野に入れています。日米間の緊密な連携は、技術的側面のみならず、費用対効果を高める上でも重要な要素となります。計画策定にあたっては、最新の技術動向を常に把握し、必要に応じてシステムの能力向上を検討していく体制を構築することが不可欠です。そのため、継続的な情報収集と分析が計画実行の成功に不可欠な要素となります。
2. 取得プログラムの目標
取得プログラムの目標は、弾道ミサイル防衛システムの機能・性能を向上させることです。具体的には、21インチロケットモーターによる推進能力の増大と、2波長シーカーによる識別能力の向上を掲げています。これにより、ミサイル迎撃の精度と確実性を大幅に向上させることが期待されます。 また、日米両国のニーズに対応した生産体制の構築も重要な目標です。これは、安定的な装備品の供給を確保し、迅速な対応を可能にする上で不可欠な要素となります。 ただし、現時点では予定していない仕様変更や性能向上は、この計画には考慮されていません。これは、計画の無駄を省き、効率的な資源配分を実現するためです。コスト削減と計画の確実な実行を両立させるためには、綿密な計画立案と、日米両国間の情報共有・協力体制の構築が不可欠です。開発段階から量産・配備段階まで、各段階での綿密なコスト管理とリスク評価を行うことで、予算の無駄遣いを防ぎ、国民の税金の有効活用を図ります。計画の進捗状況は、定期的に評価・見直しを行い、必要に応じて修正を加えることで、変化する安全保障環境に対応していきます。
3. ライフサイクルを通じて考慮すべき事項
この取得プログラムでは、ライフサイクル全体を通して考慮すべき重要な事項として、量産・配備段階への円滑な移行とコスト低減が挙げられています。海上発射試験などの成果を踏まえ、量産・配備段階への移行判断を行い、必要な処置を講じることが重要です。 コスト低減に関しては、日米間で策定されたコスト低減方策を着実に実施し、価格の透明性を確保することが求められます。これは、国民の税金が効率的に使われていることを確認するため、極めて重要な項目です。透明性確保のため、取得プロセスにおける各段階でのコストの内訳を明確に示し、国民への情報公開を積極的に行うことが必要です。また、技術開発の進歩や国際情勢の変化に対応するため、ライフサイクル全体を通して柔軟性を持たせた計画である必要があります。そのため、定期的な見直しを行い、必要に応じて計画の修正を行う体制を構築することが不可欠です。 将来にわたる維持管理コストについても、綿密な計画が必要です。保守部品の調達や技術者の育成など、長期的な視点に立った計画を策定し、システムの運用能力を維持することが重要です。これにより、国民の安全を長期的に確保するための基盤を築くことができます。
II.中距離地対空火力整備計画
島嶼部への侵攻などへの対応として、中距離地対空火力の整備計画が策定されました。敵の巡航ミサイル・空対地ミサイル攻撃からの部隊・施設の防御、戦略上の要域の保護を目的とし、将来的な技術動向への対応、国内防衛産業・技術基盤の維持を重視しています。**中SAM(改)**までの技術基盤維持も考慮されています。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、島嶼部への侵攻など様々な事態に効果的に対応できるよう、縦深・多層な対空火網を構築することです。特に、中距離対空火力は、敵の巡航ミサイルや空対地ミサイルなどの攻撃から部隊や施設、そして戦略上の要域にある政経中枢や重要施設を防御するために不可欠な能力です。 近年、周辺国の軍事力の増強や、新たな脅威の出現により、我が国の安全保障環境は厳しさを増しています。そのため、この中距離地対空火力の整備は、日本の防衛力を強化し、国民の安全を確保する上で極めて重要な役割を担います。本計画では、既存の防衛システムとの連携を強化し、より強固な防衛体制を構築することを目指しています。 また、この計画は、単なる装備品の調達にとどまらず、将来的な技術動向への対応も考慮に入れています。これは、防衛システムの有効性を維持し、常に最新の脅威に対応できる能力を備えるため、極めて重要な要素となります。計画においては、国内防衛産業および技術基盤の維持・強化にも配慮することで、日本の防衛産業の自立性を高め、国際的な競争力強化にも繋がることを目指しています。
2. 将来の中距離地対空火力分野における技術動向への対応
本計画では、将来の中距離地対空火力分野における技術動向への対応を重視しています。国内防衛産業および技術基盤の動向を把握するとともに、対象となる脅威の能力向上を含め、諸外国の技術動向を継続的に情報収集し、必要に応じてシステムの能力向上などに反映していく計画です。 これは、常に変化する国際情勢と技術革新に対応し、日本の防衛力を維持・向上させるために不可欠な取り組みです。情報収集は、公開情報だけでなく、国際協力や防衛関連機関との連携を通じて行い、最新の技術動向や潜在的な脅威を的確に把握することを目指します。 特に、中SAM(改)まで維持されてきた中距離地対空火力分野における技術基盤の維持という観点は、長期間にわたるシステム運用と維持に必要な技術的基盤を確保する上で重要な意味を持っています。 この技術基盤の維持は、単なる技術の継承にとどまらず、将来のシステム開発や改良への基礎となるものであり、日本の防衛力にとって不可欠な要素です。そのため、国内の技術者育成や研究開発への投資も継続していく必要があると考えられます。
III.広域監視能力強化のためのグローバルホーク取得計画
我が国の領海・領空から離れた地域の情報収集、事態緊迫時の常時継続的な警戒監視等を行うため、グローバルホークの取得計画が策定されました。計画には、各種センサ搭載、飛行安全性の確保、確実な情報収集能力構築、共同部隊の新編、運用基盤整備、効果的な要員教育・維持整備態勢管理が含まれます。**ライフサイクルコスト(LCC)**を考慮した計画となっています。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、我が国の領海・領空から比較的離れた地域の情報収集能力と、事態が緊迫した際の空中での常時継続的な警戒監視能力を強化することにあります。現有装備では困難な、広域における常続監視態勢を強化することで、周辺海空域の安全確保を一層万全にすることを目指しています。これは、近年増加している領空侵犯や海洋進出といった脅威への対応として、極めて重要な役割を担っています。 この計画は、単なる装備品の導入だけでなく、効果的な情報収集・監視体制の構築、そしてそれらを支える運用体制の整備を包括的に目指しています。 既存の監視システムでは対応が困難な広範囲かつ高度な監視能力の獲得は、日本の安全保障にとって大きな前進となります。リアルタイムでの情報収集・分析能力は、迅速な意思決定と適切な対応を可能にし、潜在的な脅威への早期対処に貢献します。そのため、この計画は、単なる装備調達にとどまらず、運用体制の整備や人材育成といった要素も含めた総合的な取り組みとなっています。
2. 取得プログラムの方針
取得プログラムの方針は、大きく分けて3つの柱から成り立っています。まず、各種センサを搭載可能なグローバルホークの取得です。これは、広範囲かつ高精度の情報収集を可能にするために不可欠な要素です。次に、飛行安全性の確保と確実な情報収集能力の構築です。これは、安全かつ信頼性の高い情報収集を確保するために、運用面での様々な対策を講じることを意味します。そして最後に、効果的・効率的な要員教育や維持整備態勢の管理です。これは、高度な技術を必要とするグローバルホークを安全かつ効果的に運用していくために不可欠な要素です。 これらの要素は相互に関連しており、それぞれの要素が効果的に機能することで、初めて広域監視能力の強化が実現可能となります。特に、高度な技術を持つグローバルホークの維持管理には、専門的な知識と技術を持った要員育成が不可欠です。そのため、計画には、人材育成プログラムや維持整備体制の構築に関する詳細な計画も含まれています。 また、この計画は、米国政府との緊密な協力の下に進められます。グローバルホークの取得は、米国政府からの提案価格等を基に決定され、運用・維持についても米国政府からの情報や自衛隊が保有する同種機器の価格などを参考に計画が立案されています。
3. ライフサイクルコスト LCC
ライフサイクルコスト(LCC)は、グローバルホークの取得計画において重要な要素です。しかし、資料からは、具体的なLCCの数値は明示されていません。これは、計画段階においてまだ多くの不確定要素が残されているためだと考えられます。 具体的なLCCを算出するには、運用期間中の維持費や修理費など、様々な要素を正確に予測する必要があります。そのため、計画の策定段階では、あくまでも概算での見積もりにとどまり、今後の詳細な検討によって、LCCは変更される可能性があります。 今後、計画が進むにつれて、より詳細なコスト分析が行われ、LCCに関する情報が公開されることが期待されます。国民の税金の有効活用のためにも、コスト管理は重要であり、透明性のあるコスト開示が求められます。 地上装置の経費は、量産・配備段階の航空機の区分に含まれると明記されており、コスト算定において、細かな項目まで考慮されていることがわかります。
IV.水陸両用作戦能力獲得のための車両取得計画
島嶼部侵攻への迅速な対応として、海上艦艇からの部隊投入、上陸・奪回・確保を可能にする水陸両用車の取得計画が策定されました。取得・維持管理に加え、補給整備基盤と教育訓練基盤の整備も含まれます。**ライフサイクルコスト(LCC)**の抑制も重要視されています。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、島嶼部への侵攻があった場合、海上艦艇から部隊を速やかに投入し、上陸、奪回、確保を行うための水陸両用作戦能力を獲得することにあります。これは、離島防衛の強化という喫緊の課題に対応するための重要な計画です。近年、周辺国の軍事行動が活発化する中で、離島防衛の重要性はますます高まっており、迅速な対応能力の確保は、日本の安全保障にとって不可欠となっています。 この計画は、敵の侵攻に対する抑止力強化と、万一の事態発生時の対処能力向上を両立することを目指しています。水陸両用作戦能力の向上は、敵の不意打ち攻撃に対する防御能力を高め、早期の対応を可能にします。 また、この計画は、単なる装備品の導入にとどまらず、運用体制の整備や人材育成といった要素も含めた、より広範な視点での取り組みとなっています。水陸両用作戦は、高度な訓練と連携が必要な複雑な軍事行動であり、その実施には、適切な訓練施設や教育プログラムの整備が不可欠です。
2. 取得プログラムの方針
取得プログラムの方針は、海上から島嶼等に部隊を上陸させるための水陸両用車の迅速な取得・維持管理の実施です。これは、迅速な対応能力を確保するために、効率的な取得プロセスと維持管理体制の確立が不可欠であることを意味します。 さらに、この計画では、水陸両用車の取得と並行して、補給整備基盤と教育訓練基盤の整備も同時に行うことが明確に示されています。これは、取得した装備を効果的に運用し、その能力を最大限に発揮するためには、適切な補給整備体制と高度な訓練を受けた人員の確保が不可欠であることを示しています。 迅速な取得と並行したインフラ整備は、導入後の運用開始をスムーズに行うための重要な要素となります。 また、この計画では、コスト効率の良さも考慮されていると考えられます。 資料からは具体的なコストに関する数値は明示されていませんが、取得と同時に維持管理体制や教育訓練体制を整備するという計画から、ライフサイクルコストの観点からも最適な計画が目指されていると推測できます。
3. ライフサイクルコスト LCC
この計画では、ライフサイクルコスト(LCC)に関する具体的な数値は示されていません。これは、計画の段階において、まだ多くの不確定要素が残されているためと考えられます。しかし、資料から、LCCを考慮した計画であることは明らかです。 取得計画の際には、初期費用だけでなく、運用期間中の維持費や修理費、そして最終的な廃棄費用まで含めた全体的なコストを考慮することが重要です。 コストの透明性を確保し、国民の理解を得るためには、将来的にLCCに関する詳細な情報が公開されることが期待されます。 弾薬の費用は、保有数量が推定される懸念があるため、公表されていないと明記されており、情報公開における慎重さも伺えます。
V.新型護衛艦取得計画
周辺海域の防衛、海上交通安全確保、国際平和協力活動等の機動的な実施のため、情報収集・警戒監視・哨戒・沿岸防備・対機雷戦など多様な任務に対応可能な新型護衛艦の取得計画が策定されました。船体のコンパクト化・省人化、長期的な運用を見据えた防衛生産・技術基盤の維持、効率的な整備・補給態勢構築などが計画の柱です。**ライフサイクルコスト(LCC)**は、構想段階では未確定です。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、周辺海域の防衛、海上交通の安全確保、そして国際平和協力活動などの機動的な実施に資することです。常続監視や対潜戦などの各種作戦を効果的に遂行するための能力を確保することを目指しています。これは、我が国を取り巻く安全保障環境の厳しさを踏まえた上で、海洋における防衛力を強化するための重要な計画です。 近年、海洋進出や領海侵犯といった脅威が増加する中、海上における警戒監視能力の強化は、日本の安全保障にとって喫緊の課題となっています。この計画は、最新の技術と戦略を駆使することで、これらの脅威に効果的に対処できる能力を構築することを目指しています。 この計画では、単なる装備品の導入だけでなく、周辺海域における防衛力の強化、そして国際社会への貢献という、二つの重要な目的を達成することを目指しています。周辺海域の安全確保は、我が国の経済活動や国民生活の安定に不可欠であり、国際平和協力活動への積極的な参加は、国際社会における日本の役割を強化することにも繋がります。
2. 取得プログラムの方針
取得プログラムの方針は、多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化及び省人化を両立させた新たな護衛艦を所要数取得することです。これは、限られた資源の中で、高い戦闘能力と効率的な運用を両立させるための戦略的な判断です。 近年、防衛装備においては、小型化・省人化によるコスト削減と、多機能化による戦闘能力向上という相反する要求が求められています。この方針は、これらの要求をバランス良く満たすことを目指したものです。 コンパクト化と省人化は、運用コストの削減と、より少ない人員での運用を可能にすることで、維持管理コストの抑制にも繋がります。多様な任務への対応能力向上は、高度な情報収集能力や、様々な状況に対応できる柔軟なシステムの構築を必要とします。 この計画では、複数の任務に対応できる汎用性の高い護衛艦を導入することで、限られた予算の中で、より多くの任務に対応できるよう効率性を追求しています。
3. ライフサイクルコスト LCC
この計画では、ライフサイクルコスト(LCC)は構想段階では未確定要素が多いため、定められていません。しかし、取得計画の段階からLCCを考慮し、将来的な維持管理コストを抑制するための検討が行われていることが示唆されています。 LCCを抑制するためには、設計段階から運用・維持コストを考慮した設計にする必要があり、船体のコンパクト化や省人化なども、この観点から検討されていると考えられます。 護衛艦の建造においては、初期費用だけでなく、運用期間中の燃料費、整備費、人件費など、多岐にわたる費用がLCCに含まれます。これらの費用を最小限に抑えつつ、高い戦闘能力を維持することが、この計画の重要な課題となります。 将来、計画が具体化していくにつれて、LCCに関するより詳細な情報が公開されることが期待されます。国民の税金の有効活用という観点から、透明性のあるコスト管理が重要となるでしょう。
VI.新多用途ヘリコプター UH X 取得計画
陸上自衛隊のUH-1Jヘリコプターの後継として、島嶼侵攻事態、ゲリラ・コマンド攻撃事態、大規模災害、国際平和協力活動など幅広い任務に対応可能な**新多用途ヘリコプター(UH-X)**の取得計画が策定されました。国内企業と海外企業の共同開発、開発費・量産・維持経費の抑制、部品枯渇防止などが考慮されています。**ライフサイクルコスト(LCC)**の削減が目指されています。
1. 取得プログラムの目的
このプログラムの目的は、陸上自衛隊のUH-1Jヘリコプターの後継機として、新多用途ヘリコプターUH-Xを取得し、幅広い任務に対応できる航空輸送能力を確保することです。島嶼部侵攻、ゲリラ・コマンド攻撃、大規模災害、国際平和協力活動など、様々な事態に対応できる空中機動、航空輸送、患者後送、人命救助、住民避難、支援物資空輸といった任務を想定しています。これは、日本の安全保障環境の変化と、災害対応能力の向上という二つの重要な課題への対応として位置づけられます。 UH-1Jの後継機として、UH-Xは、より高度な能力と多様な機能を備えることが期待されています。島嶼部における作戦行動や、災害発生時の迅速な対応には、ヘリコプターの高い機動性と輸送能力が不可欠であり、UH-Xはその要件を満たす重要な装備となります。 また、この計画は、単なるヘリコプターの取得にとどまらず、国民の安全と福祉の向上、そして国際社会への貢献という、より広範な目的を包含しています。災害対応能力の向上は、国民の生命と財産を守る上で極めて重要であり、国際平和協力活動への貢献は、国際社会における日本の役割を強化する上で重要な役割を果たします。
2. 取得プログラムの方針
取得プログラムの方針は、大きく3つの柱から成り立っています。まず、現有装備UH-1Jの後継として新多用途ヘリコプターUH-Xを取得することです。これは、老朽化したUH-1Jを更新し、最新の技術と能力を備えたヘリコプターを導入することで、部隊の運用能力を向上させることを目指しています。 次に、効率的な開発を進める観点、そして防衛生産・技術基盤の維持の観点から、国内企業と海外企業が共同で民間機の開発と並行してUH-Xの開発を行うことです。これは、開発コストの抑制と、日本の防衛産業の技術水準向上を両立させるための戦略的なアプローチです。民間機の開発と並行して行うことで、技術開発のリスクを分散し、開発期間の短縮やコスト削減を図ることも期待されます。 そして最後に、開発費と量産・維持経費の抑制、そして部品枯渇の予防です。これは、UH-Xのライフサイクル全体を通してのコストを抑制し、長期的な運用を可能にするために、重要な要素となります。部品枯渇の予防は、長期間にわたる運用を確保するために不可欠であり、計画においては、部品供給体制の確保にも十分な配慮が払われています。
VII.重輸送ヘリコプター能力強化計画
CH-47JAの輸送能力を補完・強化し、島嶼部への攻撃への対応を念頭に迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保するため、重輸送ヘリコプター能力強化計画が策定されました。**ライフサイクルコスト(LCC)**は、詳細な情報が提示されています。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、島嶼部に対する攻撃への対応を念頭に、迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保し、実効的な対処能力を向上させることです。具体的には、CH-47JAの輸送能力を、巡航速度や航続距離といった観点から補完・強化することで、より迅速かつ大規模な人員や物資の輸送・展開を可能にする航空輸送能力の確保を目指しています。 島嶼部への迅速な対応は、我が国の安全保障にとって極めて重要です。離島は、地理的に分散しており、迅速な物資輸送が困難な場合が多いです。この計画は、そのような地理的制約を克服し、島嶼部への迅速な対応を可能にするための重要な取り組みとなります。 この計画では、既存のCH-47JAの能力を補完・強化することで、より効果的な防衛体制の構築を目指しています。CH-47JA単体では対応が難しい大規模な輸送任務や、長距離輸送任務に迅速に対応できる能力の獲得は、日本の防衛力の強化に大きく貢献するでしょう。 また、この計画は、将来的な脅威への対応も視野に入れていると考えられます。技術革新や国際情勢の変化を踏まえ、常に最新の状況に対応できる柔軟なシステムの構築が、この計画の成功に不可欠です。
VIII.哨戒機P 1取得計画
我が国周辺海域における常続監視、対潜戦などの作戦を効果的に実施するため、哨戒機P-1の取得計画が策定されました。国内製造、国内技術基盤の活用、国内の後方支援体制の確保などが計画に盛り込まれています。**ライフサイクルコスト(LCC)**の抑制、航空機と地上システムとの整合性確保が重要課題となっています。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、我が国周辺の海域における常続監視や対潜戦などの各種作戦を、艦艇と一体となって効果的に実施するために必要な能力を確保することです。これは、我が国を取り巻く安全保障環境の厳しさを踏まえ、海洋における防衛力を強化するための重要な計画です。 近年、領海侵犯や潜水艦による活動など、我が国周辺の海域における安全保障上の脅威は増加傾向にあります。これらの脅威に効果的に対処するためには、高度な情報収集能力と、迅速な対応能力を備えた哨戒機が不可欠です。P-1哨戒機は、これらの要件を満たす重要な装備であり、その取得は、日本の海洋防衛力の強化に大きく貢献します。 この計画は、単なる装備品の導入にとどまらず、哨戒活動の効率化と、より効果的な作戦遂行体制の構築を目指しています。P-1哨戒機は、高度なセンサー技術と情報処理能力を備えており、広範囲な海域を効率的に監視し、潜在的な脅威を早期に発見することが可能です。また、艦艇との連携強化も重要な要素であり、より緊密な連携体制を構築することで、日本の海洋防衛力を飛躍的に向上させることを目指しています。
2. 取得プログラムの方針
取得プログラムの方針は、コスト抑制、形態管理、そして装備品の継続的な能力向上という3つの柱から成り立っています。コスト抑制のためには、民生品の活用や搭載装備品の仕様共通化などが検討されています。これは、防衛装備品の調達コストを削減し、より効率的な予算執行を実現するための重要な取り組みです。 形態管理においては、航空機、艦艇システム、そして地上システムとの整合性を図ることが重視されています。これは、システム全体の効率性と運用性を高めるために不可欠な要素です。 そして、装備品の継続的な能力向上のためには、運用ニーズを適時適切に反映できる体制の強化が求められています。これは、技術革新や脅威の変化に対応し、常に最新の能力を維持するために不可欠な要素であり、そのため、柔軟で迅速な対応体制の構築が必要です。 これらの要素は、それぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合っています。それぞれの要素が効果的に機能することで、初めてP-1哨戒機の能力が最大限に発揮され、日本の海洋防衛力強化に貢献できるのです。特に、国内技術基盤を活用した開発・製造、国内での後方支援体制の整備は、日本の防衛産業の維持・発展にも大きく貢献すると考えられます。
3. ライフサイクルコスト LCC
この計画では、ライフサイクルコスト(LCC)は10,020億円とされています(詳細は付紙を参照)。これは、P-1哨戒機の取得から運用終了までの全期間における費用を網羅したもので、計画の策定にあたっては、このLCCを抑制するための様々な工夫が凝らされていると考えられます。 LCCの抑制策としては、民生品の活用や搭載装備品の仕様共通化などが挙げられます。これらは、コスト削減に大きく貢献する重要な要素です。 また、LCCの透明性を確保することも重要です。国民の税金が効率的に使われていることを確認するためにも、取得プロセスにおける各段階でのコストの内訳を明確に示し、国民への情報公開を積極的に行うことが必要です。 LCCは、単なる数字ではなく、国民の安全と日本の防衛力の維持に繋がる重要な指標です。そのため、計画の策定から運用終了まで、常にLCCを意識した効率的な運用管理体制の構築が不可欠です。
IX.対潜ヘリコプターSH 60K能力向上型取得計画
我が国周辺海域における常続監視や対潜戦などの作戦を効果的に実施するために必要な能力を確保するため、SH-60K能力向上型の取得計画が策定されました。国内開発・製造、国内技術基盤の活用、国内後方支援体制の確保が計画に含まれます。**ライフサイクルコスト(LCC)**は10,020億円とされています。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、我が国周辺の厳しい安全保障環境を踏まえ、周辺海域における常続監視や対潜戦などの各種作戦を効果的に実施するために必要な能力を確保することです。これは、潜水艦などによる脅威への対処能力を強化し、日本の海洋安全保障をより強固にするための重要な計画です。 近年、周辺国の潜水艦活動が活発化するなど、我が国の安全保障環境は厳しさを増しています。これらの脅威に対処するためには、高度な対潜能力を備えたヘリコプターが不可欠です。SH-60K能力向上型は、最新の技術を導入することで、対潜能力を大幅に向上させることが期待され、日本の防衛力を強化する上で重要な役割を果たします。 この計画は、単なるヘリコプターの能力向上にとどまらず、周辺海域における安全保障体制全体の強化を目指しています。高度な対潜能力は、敵潜水艦の行動を抑制し、我が国の海上交通の安全を確保することに貢献します。また、国際的な平和維持活動への貢献も視野に入れた、より広範な視点での取り組みとなっています。
2. 取得プログラムの方針
取得プログラムの方針は、SH-60K能力向上型を国内で開発・製造し、搭載装備品等の研究開発は主として国内技術基盤を活用し、後方支援も主として国内に基盤を確保することです。これは、日本の防衛産業の技術力向上と雇用創出、そして防衛産業の自立性を高めることを目的としています。 国内での開発・製造は、日本の技術力を向上させ、高度な防衛装備品の開発能力を維持・強化するために重要です。また、国内企業への発注は、雇用創出にも繋がり、経済活性化にも貢献します。 国内技術基盤の活用は、技術の蓄積と、将来的なシステム改修や維持管理の容易化にも繋がります。国内で整備・修理を行うことで、迅速な対応が可能となり、運用効率の向上が期待されます。 後方支援を国内に拠点を置くことで、迅速な部品供給や技術支援が確保され、システムの稼働率向上に貢献します。これは、万が一の事態発生時にも、迅速な対応を可能にする上で極めて重要な要素です。
3. ライフサイクルコスト LCC
この計画におけるライフサイクルコスト(LCC)は、10,020億円とされています(詳細は付紙を参照)。これは、SH-60K能力向上型の開発から運用終了までの全期間における費用を網羅したものです。LCCを考慮した上で、コスト抑制、形態管理、そして装備品の継続的な能力向上という方針が示されています。 コスト抑制のためには、民生品の活用や搭載装備品の仕様共通化などが検討され、形態管理においては、航空機と地上システムとの整合性が図られています。 継続的な能力向上のためには、運用ニーズを適時適切に反映できる体制の強化が求められ、これらは、LCCを抑制しつつ、効果的な能力向上を実現するための重要な要素となります。 LCCに関する詳細な情報は付紙に記載されているため、この概要説明からは具体的な内容までは触れられていませんが、この計画全体を通して、コスト意識の高さが伺えます。
X.F 35A戦闘機取得計画
F-4後継機として、F-35A戦闘機の導入計画が策定されました。整備計画、経費、技術的事項などを一元的に管理し、効率的な取得を目指します。国内企業の参画拡大なども考慮されています。**ライフサイクルコスト(LCC)**の削減と透明性が重視されます。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、F-4戦闘機の後継機としてF-35A戦闘機を導入し、各種事態における実効的な抑止力、そして対処の前提となる航空優勢を確実な獲得と維持を図ることです。これは、我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえ、航空戦力における優位性を維持・強化するための重要な計画です。 F-4戦闘機は長年にわたって日本の防空を担ってきたものの、老朽化が進み、近代的な戦闘機に更新する必要性が高まっています。F-35Aは、最新のステルス技術や高度な情報処理能力を備えた第五世代戦闘機であり、その導入は、日本の航空戦力における質的向上に大きく貢献すると期待されています。 この計画は、単なる戦闘機の導入にとどまらず、日本の航空自衛隊の戦闘能力を維持・強化し、周辺国からの脅威に対する抑止力強化、そして万が一の事態への対処能力の向上に繋がることを目的としています。 航空優勢の確保は、地上部隊や艦艇の作戦行動を支援し、国民の安全と日本の領土を守る上で極めて重要です。F-35Aの導入は、日本の安全保障をより強固にするための重要な柱となるでしょう。
2. 取得プログラムの方針
取得プログラムの方針は、各種整備計画、経費、技術的事項などを一元的にまとめ、着実かつ効率的にF-35Aを取得することです。これは、複雑な戦闘機導入計画を円滑に進めるために、計画全体の効率化とリスク管理を重視したアプローチです。 F-35Aは、高度な技術と複雑なシステムを備えているため、その導入には綿密な計画と管理が必要です。整備計画、経費、技術的事項などを一元的に管理することで、計画の遅延やコスト超過を抑制し、効率的な導入を目指します。 また、この計画では、国内企業の参画拡大なども考慮されています。これは、日本の防衛産業の育成と技術力の向上、そして雇用創出といった経済効果も期待できる要素です。 さらに、この計画は、ライフサイクルコスト(LCC)の削減と透明性を重視しており、国民の税金の有効活用を図るための取り組みが重視されていると推測できます。
3. ライフサイクルコスト LCC
この計画では、ライフサイクルコスト(LCC)のベースラインが示されています。具体的な数値は22,287億円とされていますが、これはあくまで現時点での見積もりであり、今後変更される可能性があります。 LCCは、F-35Aの取得から廃棄までの全期間にわたる費用を網羅したものであり、計画の策定にあたっては、このLCCを抑制するための様々な工夫が凝らされていると考えられます。 LCCの抑制策としては、国内企業の参画拡大によるコスト削減や、効率的な維持管理体制の構築などが挙げられます。 また、LCCの透明性を確保することも重要であり、国民の税金が効率的に使われていることを確認するためにも、取得プロセスにおける各段階でのコストの内訳を明確に示し、国民への情報公開を積極的に行うことが必要です。
XI.次期戦闘機開発計画
2030年代以降の航空優勢確保と各種航空作戦遂行に必要な能力を確保するため、次期戦闘機の開発計画が策定されました。国際共同開発の可能性も含め戦略的な検討が推進され、国内開発、国際共同開発、輸入・ライセンス国産といった選択肢が検討されています。関連技術研究の推進、諸外国との交渉が重要となります。
1. 取得プログラムの目的
この取得プログラムの目的は、F-2戦闘機の退役が始まる2030年代以降を見据え、我が国の上空および周辺空域における航空優勢を確保し、各種航空作戦遂行に必要な能力を確保することです。これは、我が国に対する侵攻に対する実効的な抑止力と対処力を強化するための重要な計画です。 F-2戦闘機の老朽化に伴い、その更新計画が不可欠となっており、次期戦闘機は、日本の航空自衛隊の主力戦闘機として、日本の防空体制の維持・強化に重要な役割を果たすことになります。 この計画では、単なる戦闘機の更新にとどまらず、将来的な安全保障環境の変化にも対応できる柔軟性と、高度な戦闘能力を備えた戦闘機の開発を目指しています。 次期戦闘機の開発は、日本の防衛産業の技術力向上と国際的な競争力強化にも貢献することが期待されます。また、この計画は、日本の安全保障政策における重要な柱であり、国民の安全と日本の平和を維持するために不可欠な取り組みです。
2. 取得プログラムの方針
取得プログラムの方針として、国際共同開発の可能性も含め、実証研究を含む戦略的な検討を推進することが挙げられています。これは、最適な開発方法を選択するために、様々な可能性を検討していくことを意味します。 国内開発、国際共同開発、輸入・ライセンス生産など、様々な選択肢の中から、我が国にとって最適な方法を選択するために、綿密な検討が行われます。 この検討には、技術的な側面だけでなく、経済的な側面や政治的な側面も考慮に入れられる必要があります。国際共同開発を選択する場合、同盟国との協力体制の構築や、技術情報の共有なども重要な要素となります。 また、平成30年度までに開発に関する判断など必要な措置を講ずるための検討を実施し、取得方法の選択についても、我が国にとって最適な選択肢を追求することが計画に示されています。これは、計画の遅延を防ぎ、効率的な開発・取得を行うために、重要なステップとなります。
3. ライフサイクルを通じて考慮すべき事項
ライフサイクルを通じて考慮すべき事項として、関連技術研究の着実な推進と、最適な選択肢を追求するための諸外国との交渉が挙げられています。 関連技術研究としては、X-2をはじめとする将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンに基づく研究開発が継続的に行われます。これは、次期戦闘機の開発に不可欠な技術基盤を構築するため、重要な取り組みです。 最適な選択肢を追求するための諸外国との交渉は、国際共同開発などの可能性を検討する上で重要です。これは、技術協力や情報共有を通じて、より効率的な開発・取得を実現するため、必要なプロセスとなります。 これらの検討は、単なる技術的な側面だけでなく、政治的・経済的な側面も考慮に入れながら、総合的に判断される必要があります。そのため、関係各省庁や同盟国との緊密な連携が不可欠となります。 計画全体を通して、技術開発の進捗状況や国際情勢の変化を常に注視し、必要に応じて計画を修正していく柔軟性も求められます。
