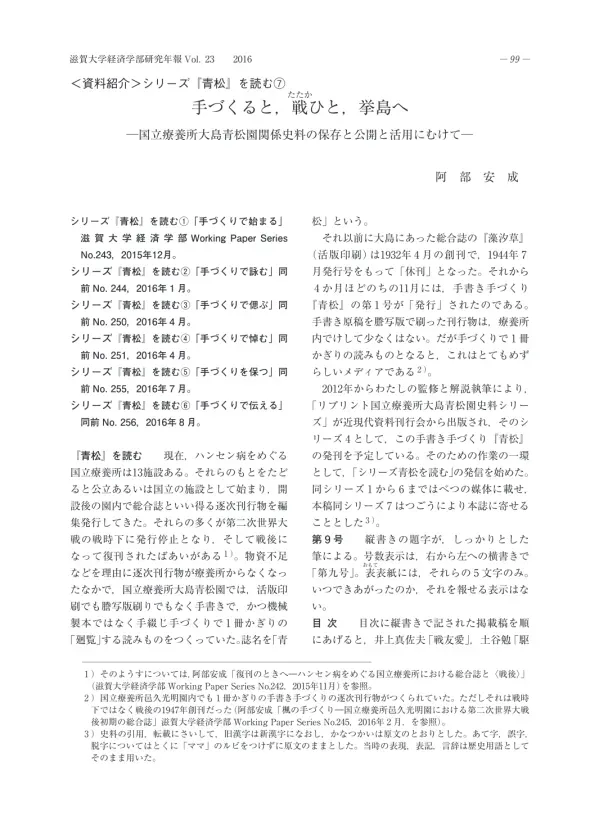
青松:戦時下の手書き療養所誌
文書情報
| 著者 | 阿部 安成 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 経済学 |
| 場所 | 滋賀 |
| 文書タイプ | Working Paper |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.52 MB |
概要
I.戦時下における国立療養所 青松 誌 戦友愛と患者の生活
第二次世界大戦下の国立療養所大島青松園で発行された手書きの総合誌『青松』は、印刷用紙不足の中、手づくりで作成された貴重な資料です。本誌はハンセン病患者と職員が共同で編集し、戦時下の厳しい状況下での生活や、戦友愛の精神、そして園長先生を中心とした園全体の結束を記録しています。掲載内容は、短歌や俳句、小品文、園内活動報告など多岐に渡り、機雷監視や防空壕建設といった国民奉仕活動への参加も記されています。特に、園長先生への深い敬愛と感謝の念が多くの文章に表れており、その温かい人情が感じられます。重要な登場人物として、園長先生、井上氏、土谷氏、小見山氏、笠居氏などが挙げられ、彼らの作品を通して、当時の患者の精神状態や生活の様子が詳細に伺えます。沖縄戦や本土空襲といった戦況も報告されており、戦時下の現実と、療養所内のコミュニティの繋がりを同時に垣間見ることができます。 この『青松』誌は、国立療養所における戦時下の記録として、極めて重要な歴史的資料といえます。
1. 青松 誌の発行と背景
現在、ハンセン病療養所は13施設存在しますが、多くは公立または国立施設として始まり、園内報のような逐次刊行物を発行していました。しかし、第二次世界大戦下の物資不足により、多くの施設で刊行が停止されました。大島青松園では、活版印刷や謄写版印刷ではなく、手書き、手綴じという、まさに手作りによる『青松』誌が発行されました。これは、戦時下における貴重な記録であり、印刷用紙の不足という厳しい状況下で、情報発信を継続しようとした療養所の強い意志を示しています。この手作りの『青松』誌は、戦時下のハンセン病療養所の生活を伝える上で、極めて重要な資料と言えるでしょう。紙の不足は深刻で、謄写版印刷の原稿用紙の裏面、さらには内用薬票の裏面まで活用するほどでした。これは、単なる記録誌ではなく、戦時下における情報伝達手段、そして患者の精神を支えるための重要な役割を担っていたことを示唆しています。
2. 戦友愛と園内生活
井上氏の寄稿は、新聞や雑誌で強調される『戦友愛』を話題に、大島青松園における戦友愛について論じています。戦局の悪化の中で、国民は親子、兄弟、夫婦間の愛情で助け合う必要性を説き、大島における具体的な事例を記しています。防空壕建設や機雷監視という、園の奉仕者一同による勤労奉仕活動が詳細に記述されています。雨の日も風の日も、黙々と任務に当たる聯合奉仕団員たちの労苦に対する感謝と、慰問金品の寄贈がラジオを通して発表される様子が描かれ、園全体で困難を乗り越えようとする一体感が伝わってきます。また、防空壕と機雷監視哨周辺で咲く「美しくも香り高い人情の花」という表現は、困難な状況の中でも見られる人々の温かい繋がりを象徴的に表現しており、戦友愛の精神が具体的な行動を通して表れていることを示しています。そして、個々の患者の生活や、園長先生を中心とした園全体の結束が、具体的なエピソードを通して示されています。
3. 患者の日常と心情
土谷氏の作品「虫」は、腹痛に苦しむ患者の心情を、ユーモラスでありながら切実な表現で描いています。短歌が随所に挿入され、患者の内面世界を巧みに表現する新たな試みが見られます。顕微鏡検査への不安、医師との会話、物資不足による苦悩など、患者の日常の細部がリアルに描かれています。一方、実在の人物が登場する場面もあり、膳箱を病室まで運んでくれる詰所の仲間との温かい交流が描かれています。37歳になった「私」の回想や、黒住教の神官をしていた過去なども語られ、患者の複雑な人生背景も垣間見ることができます。馬鈴薯の食糧配給や農作業に関する記述からは、厳しい生活環境下での患者の現実的な生活状況が分かります。故郷を失い、混沌とした思考に苦しむ作者の葛藤や、安住の地を求めるさまが克明に描写されています。そして、沖縄や都市の災害への思い、思想と行動の分離への葛藤など、複雑な感情が表現されています。
4. 園長先生と職員 そして患者の結束
園長先生への深い敬意と感謝の念が、多くの文章や詩歌に表現されています。園長先生は、患者の幸福のために真剣に考え、常に患者の側に寄り添う存在として描かれています。長田氏の寄稿では、園長先生を「お父さん」と呼び、その献身的な医療活動と、協和会設立時の支援への感謝が述べられています。園長先生は、香川での赤痢大流行の際にも、日頃の研究成果を活かして撲滅に貢献したとされ、その功績が称賛されています。また、空襲警報発令下での園長先生の行動や、高松への救護活動への参加が報告されています。これらのエピソードは、園長先生の献身的な姿勢と、園内における強い信頼関係を示すものです。園長先生を中心とした温かいコミュニティが、戦時下における患者の精神的な支えとなっていたことが明確に示されています。そして、患者の生活を支える職員の多忙な様子も描かれ、園全体の結束が強調されています。
II. 青松 誌における文学作品 短歌 俳句 小品文
『青松』誌には、短歌や俳句、小品文など、様々な文学作品が掲載されています。これらの作品は、戦時下の厳しい状況下で生活する患者の心情や、彼らの日常の様子を反映しています。特に、土谷氏の作品は、ユーモラスな表現と短歌の挿入が特徴的で、患者の日常生活の描写に新たな手法を取り入れています。一方、笠居氏の短歌は、戦争の現実と、患者の心情を繊細に表現しています。これらの作品を通して、個々の患者の内面世界を垣間見ることができます。また、多くの作品において園長先生や職員への敬愛、感謝の気持ちが表現されており、園内の強い結束が伺えます。これらの作品は、戦時下のハンセン病患者たちの精神的な支えとなっていたと考えられます。
1. 短歌 戦時下の心情と日常
『青松』誌には多くの短歌が掲載されており、それらは戦時下の厳しい生活の中で、患者の心情や日常を表現しています。例えば、笠居誠一の短歌は、故郷を思う気持ちや、戦況への不安、そして日常の些細な出来事を織り交ぜながら、繊細な表現で心情を吐露しています。 具体的な情景描写、例えば「夕茜消え残る明るさ宵待ちの花咲く浜に松葉杖つきて彳つ」や、南瓜の栽培の様子などが、当時の生活環境を想像させます。また、機雷監視という任務に就く患者の心情を表現した短歌もあり、国への奉仕という意識と、自身の病を抱える現実との葛藤が垣間見えます。これらの短歌は、単なる詩歌ではなく、当時の患者の生活や感情を深く理解するための重要な手がかりとなります。さらに、短歌の批評も掲載されており、作品に対する多様な解釈や、作者の表現技術に対する評価などが示されています。これは、園内における文学活動が活発に行われていたことを示唆しています。
2. 小品文 ユーモラスな表現と現実の葛藤
土谷氏の作品「虫」は、腹の虫(腹痛)を題材にしたユーモラスな小品文です。顕微鏡検査への不安や、医師とのやり取り、物資不足といった現実的な問題が、軽妙なタッチで描かれています。 短歌が織り込まれた構成は、土谷氏独特の表現方法であり、これまでになかった新たな試みです。 また、病室での温かい友情や、患者の日常の様子が生き生きと描写されています。例えば、「病人らしく扱って、膳箱まで病室に運んでくれる部屋の友情が涙ぐましい」という記述からは、患者の間で支え合おうとする温かい気持ちが伝わってきます。これらの小品文は、戦時下における患者の生活と心情を、ユーモラスな表現を通してリアルに伝え、読者に深い共感を呼び起こします。同時に、物資不足や病気の苦悩といった現実的な問題も描かれ、当時の生活環境の厳しさを改めて認識させます。
3. その他の文学作品と批評
『青松』誌には、短歌や小品文の他に、俳句や児童作文なども掲載されています。これらの作品は、様々な表現方法を通して、戦時下における患者の生活や心情を多角的に捉えさせてくれます。 また、掲載作品に対する批評も存在しており、特に短歌の批評は輪番制で行われていたことが分かります。これらの批評は、作品に対する客観的な評価や、多様な視点からの解釈を示し、園内における活発な文学活動の一端を垣間見ることができます。 例えば、機雷監視という任務を遂行する患者の心情を描いた短歌に対する批評では、「おだやかにすぎる」といった具体的な指摘があり、より力強い表現への期待が読み取れます。 これらの作品群と批評は、『青松』誌が、単なる記録誌にとどまらず、園内における文学活動の場として重要な役割を果たしていたことを示しています。そして、それらを通して、患者の内面世界を深く理解するための貴重な資料となっています。
III.園内組織と活動 協和会と農作業
『青松』誌には、園内の組織や活動の様子も記録されています。特に、園内の患者自治組織である協和会の活動や、農作業を通しての患者たちの生活が詳細に描かれています。協和会の会則は、皇国臣民としての規範を示しており、戦時下の社会状況を反映しています。一方、農作業は、食糧生産の役割だけでなく、患者の生活の維持、そして精神的な支えとなる重要な活動であったことがわかります。これらの記述を通して、戦時下におけるハンセン病患者たちの集団生活と、その維持のための工夫が明らかになります。また、協和会や農作業を通して、患者同士、そして職員との協力体制が築かれていたことが分かります。
1. 協和会 患者自治と戦時下の規範
大島青松園には、入園者協和会という患者自治組織が存在していました。その会則には、「本会は大島青松園長の監督指導の下に 皇恩に感謝し国家社会の同情に応へ皇道の精神に則り会員相協和し厚生翼賛の実を挙くるを以て目的とす」と記されており、戦時下の国家体制下における患者の規範を示しています。 協和会は、園長先生からの理解と支援を得て発展し、患者の生活向上に貢献していた様子がうかがえます。しかし、同時に、会則には「協和会総則第三条の精神並本細則に違反したると認めたるときは総代は評議員会の承認を経て其団体の解散,集会並事業の停止を命することを得」という記述もあり、戦時下の厳格な統制下での活動であったことも示唆しています。 会則の内容からは、協和会が単なる親睦団体ではなく、園内秩序の維持、患者の生活改善、そして国家への奉仕という明確な目的意識を持って活動していたことがわかります。また、様々な団体活動が認められ、それらに対する監督や規制も行われていたことが伺えます。
2. 農作業 食糧生産と患者の生活
青松園では、馬鈴薯栽培などの農作業が重要な活動の一つでした。馬鈴薯は主食であり、農事委員の査定に基づき、供出量や報奨金制度が設けられています。 これは、戦時下の食糧事情の厳しさと、園内における食糧自給の努力を示すものです。 三十人の農作者による馬鈴薯栽培の様子や、その収穫量、そして報奨金制度などが詳細に記述されています。これら記述から、農作業が単なる食糧生産にとどまらず、患者の生活維持、そして勤労意欲の維持という重要な役割を担っていたことがわかります。また、農作業以外にも、養豚、養兎、果樹園、農園、花園の管理など、様々な活動が園内で行われていたことが示唆されています。 これらの活動は、患者自身の生活の維持だけでなく、園全体の経済的な自立にも貢献していた可能性があります。さらに、室長規定や隣組細則といった内部規律の存在も示されており、園内における秩序維持と共同生活の重要性が改めて認識されます。
IV.園長先生と職員 患者の支え
『青松』誌を通じて、園長先生と職員の患者の生活に対する献身的な姿勢が強く感じられます。園長先生は、医療活動のみならず、患者の生活や精神面にも配慮し、園全体の結束を導いています。職員もまた、患者の生活を支えるために尽力しており、その温かい人情が数々の文章や詩歌に表れています。 園長の郷里や経歴、そして空襲時の行動など、具体的なエピソードが記されており、彼の人物像がより鮮やかに描かれています。 職員や園長と患者との良好な関係は、戦時下の厳しい状況においても、患者の精神的な支えとなっていたと考えられます。 これらの記述は、国立療養所における人々の繋がりと、その重要性を示しています。
1. 園長先生の献身と患者の信頼
『青松』誌には、園長先生に対する患者の深い敬愛と感謝が繰り返し表現されています。園長先生は、患者の幸福のために真剣に尽力し、その姿勢は患者の生活の様々な場面で見て取れます。長田穂波の寄稿「園長をたたふ!」では、園長先生を「お父さん」と呼び、医師としての献身的な医療活動、特に協和会の設立時における理解と支援への深い感謝が述べられています。 園長先生は、単に医療を提供する存在としてだけでなく、患者の生活全般を支え、精神的な支柱となっていたことが分かります。 また、園長先生の出身地や学友とのエピソードなども紹介されており、園長先生の人となりや、その人間的な魅力が垣間見えます。空襲時の行動についても記述があり、園長先生が自ら危険を冒してまで患者のために尽力していたことが分かります。 この記述からは、園長先生と患者の間の強い信頼関係と、園長先生のリーダーシップが、戦時下の困難な状況下でも園内の結束を保つ上で重要な役割を果たしていたことが伺えます。
2. 職員の献身的な支援
園長先生だけでなく、職員全体が患者の生活を支えるために尽力していたことが、様々な記述から読み取れます。 例えば、患者の検便を気遣う医師の姿や、病室に膳箱を運んでくれる詰所の仲間たちの温かい行動などが描かれています。 また、空襲時における職員の対応や、高松への救護活動への参加、そして日常業務における献身的な姿勢などが、断片的にではあるものの、記されています。 これらの記述からは、職員が単なる業務従事者としてではなく、患者の生活に寄り添い、支える存在として、園内コミュニティに深く関わっていたことがわかります。 さらに、職員が自分の時間を割いて患者のために読書をしてあげようとする様子や、原稿の代筆を申し出る場面なども見られ、患者の生活を多方面からサポートする職員の温かい人情が感じられます。 これらの記述は、園長先生と職員、そして患者たちの強い結束と、相互扶助の精神が、戦時下における厳しい生活の中で、患者の支えとなっていたことを示しています。
