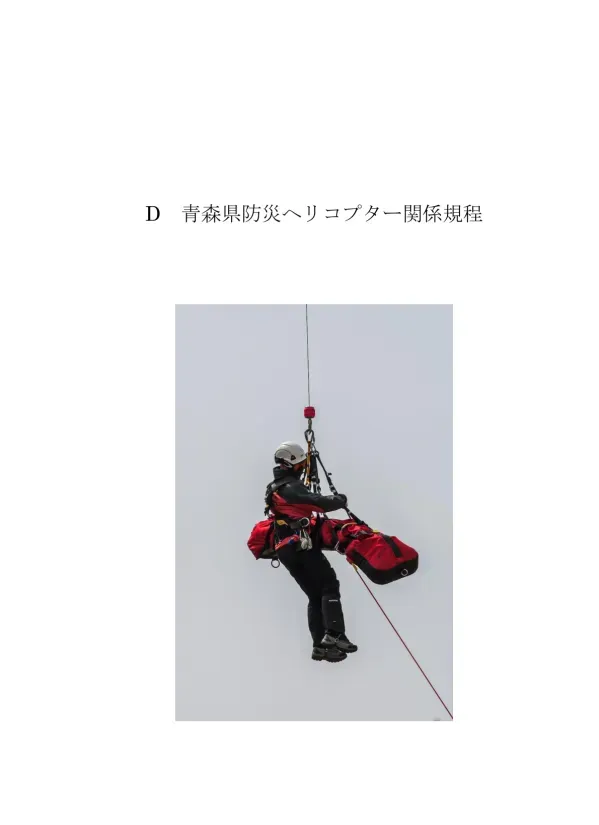
青森県防災ヘリ運航管理要綱
文書情報
| 学校 | 青森県 (Aomori Prefecture) |
| 専攻 | 防災 (Disaster Prevention) |
| 場所 | 青森県 (Aomori Prefecture) |
| 文書タイプ | 要綱 (Outline/Regulation) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.82 MB |
概要
I.運航管理体制 Unkou Kanri Taisei 運航管理責任者と総括管理者の役割
本規程は青森県防災ヘリコプターの運用に関するもので、運航管理責任者と総括管理者の役割を明確に規定しています。運航管理責任者は、緊急運航を含む日常業務の指揮、飛行場外離着陸場の確保、防災ヘリコプターの安全管理、航空事故発生時の対応などを担います。一方、総括管理者は、防災ヘリコプターの使用承認、安全管理体制の確立、近隣県との相互応援体制の構築などを担当します。両者は連携し、青森県内の消防防災業務を円滑に遂行する責任を負います。
1. 運航管理責任者の役割と権限
運航管理責任者は、青森県防災航空センターに常駐する職員を配置し、消防防災業務の遂行を担います。具体的な業務内容は、防災ヘリコプターの通常運航管理に加え、緊急事態発生時の迅速な対応が求められます。第6条の2では、県内で震度6弱以上の地震や大津波警報発令時などの大規模災害発生時には、災害対策本部設置下で防災危機管理課長が対応を行うと規定されていますが、それ以外の状況下では、運航管理責任者の指示、判断が最優先されます。特に、緊急運航の決定、実施、そして災害状況の総括管理者への迅速な報告は、運航管理責任者の重要な責務です。通常運航中の緊急事態発生時には、直ちに緊急運航に移行する指示を出す権限を持ち、その迅速な判断と行動が要請されます。さらに、飛行場外離着陸場の確保と維持管理も、円滑な消防防災業務遂行のため、運航管理責任者の重要な任務の一つとして挙げられます。法第79条ただし書及び法第81条の2に基づき、市町村と協議の上、適切な離着陸場所を確保し、その実態を常に把握する必要があります。防災ヘリコプター及び格納施設の適正な管理、そしてヘリコプターの性能を最大限に発揮できる状態を維持することも、運航管理責任者の重要な役割です。
2. 総括管理者の役割と責任
総括管理者は、青森県防災ヘリコプターの運用全体を監督する立場にあり、その責任は重大です。防災ヘリコプターの使用承認を決定する権限を持ち、使用目的、使用内容などを審査した上で、適切と判断した場合にのみ承認が与えられます。承認時には、一般行政利用取扱要領または市町村防災訓練等取扱要領に定める通知書、もしくは青森県防災ヘリコプター使用承認書(様式第6号)を交付します。 大規模災害時における消防防災業務への対応策として、ヘリコプターを保有する近隣県や消防機関等との相互応援体制の構築にも尽力する必要があります。これは、防災ヘリコプターの整備点検中や大規模災害発生時において、迅速かつ効果的な対応を可能にするため不可欠な体制です。また、法第19条第1項に基づき、一定の資格を有する技術者による防災ヘリコプターの安全性確認を義務付けており、安全性の確保を最優先事項としています。航空関係法令と国土交通大臣の定める防災ヘリの運用限界等指定書に基づき、消防防災業務の適正な執行体制と航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を図る責任も担います。
3. 運航指揮者との連携と情報伝達
運航管理責任者と運航指揮者は密接に連携し、防災ヘリコプターの運用を円滑に進めていきます。運航指揮者は、防災ヘリの搭乗中に得た重要な情報を運航管理責任者に報告する義務を負い、業務終了後には運航状況を詳細に記述した飛行報告書(様式第7号)を作成し、同様に報告しなければなりません。緊急運航要請を受けた場合は、直ちに対応する出動体制を整える必要があります。運航管理責任者は、災害の状況や現場の気象状況などを確認し、出動の可否を決定、運航指揮者への指示と要請者への回答を迅速に行う必要があります。この連携と情報伝達は、安全かつ効率的な防災ヘリコプターの運用に不可欠であり、迅速な意思決定と的確な情報伝達によって、災害への対応能力が大きく左右されます。特に、航空事故発生の恐れがある場合や発生した場合は、人命と財産の保護を最優先し、速やかに運航管理責任者と最寄りの航空局空港事務所に状況を報告しなければなりません。これは、迅速な救助活動と事故調査に繋がる重要な情報伝達です。
II.防災ヘリコプターの使用申請と承認 Bōsai Herikoputā no Shiyō Shinsē to Shōnin
青森県防災ヘリコプターの使用を希望する市町村、消防機関、県内各課は、用途、内容を明記した申請書を総括管理者に提出する必要があります。申請書の種類は、一般行政活動用、市町村防災訓練用、その他があり、提出期限もそれぞれ異なります。総括管理者は申請内容を審査し、承認するか否かを決定します。青森県防災ヘリコプター使用申請書(様式第5号)は、一般申請の場合に使用されます。
1. 防災ヘリコプター使用申請の手続き
青森県防災ヘリコプターの使用を希望する者は、事前に使用予定表を提出する必要があります。その後、使用目的や内容に応じて、適切な申請書を総括管理者へ提出する必要があります。申請書は、市町村防災訓練等への利用のための運航に関する取扱要領、または一般行政利用のための運航に関する取扱要領に定められた様式を使用します。 第17条では、使用予定表提出済みの者が防災ヘリを使用する場合、各要領に定められた期限までに、それぞれの要領に規定されている申請書を提出する必要があると明記されています。これは、一般行政活動や市町村防災訓練など、防災ヘリコプターの利用目的によって、異なる申請手続きが求められることを意味しています。 また、上記以外の目的で防災ヘリコプターを使用する場合には、青森県防災ヘリコプター使用申請書(様式第5号)を、使用日の1ヶ月前までに総括管理者へ提出する必要があります。この申請書は、様々な利用目的を網羅するために用意されており、申請者にとって、申請内容の明確化と提出期限の厳守が求められます。
2. 使用申請書の提出期限と種類
防災ヘリコプターの使用申請には、明確な提出期限が設けられています。市町村、消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合が実施する消防防災訓練活動、または県が実施する一般行政活動に防災ヘリを使用する場合、それぞれの要領に定められた期限までに、それぞれの申請書を提出する必要があります。これは、運用計画の調整や訓練場所の飛行条件の調査などに時間を要するため、十分な準備期間を確保する必要があるためです。 第16条では、緊急運航を除く防災ヘリの使用を予定する者は、市町村防災訓練等取扱要領または一般行政利用取扱要領に定められた申請書を提出する必要があると規定しています。 これにより、申請者は、それぞれの利用目的に合わせた申請書を、正確に、そして期日までに提出する責任を負うことになります。 また、申請書の種類も利用目的に応じて異なります。一般行政活動に使用する場合は「青森県防災ヘリコプター使用申請書(様式第2号)」、市町村防災訓練の場合は「青森県防災ヘリコプター訓練出動申請書(様式第2号)」が使用され、申請内容もそれぞれに合わせた記述が必要です。 これらの申請書の提出期限と種類を正確に理解することで、申請手続きにおける混乱を防ぎ、円滑な防災ヘリコプター運用に貢献します。
3. 総括管理者による使用承認と審査
総括管理者は、提出された防災ヘリコプター使用申請書を審査し、使用の可否を決定します。第18条では、総括管理者は申請内容(使用目的、使用内容等)を審査し、適当と認めれば承認すると規定されています。この審査においては、申請内容の妥当性、安全性、運用計画との整合性などが考慮されます。 申請内容が不十分であったり、安全性の懸念があったり、運用計画と整合性がない場合には、申請は却下される可能性があります。 そのため、申請者は、申請書に必要事項を漏れなく正確に記入し、安全対策を十分に考慮した計画を立てる必要があります。 総括管理者は、承認した際には、一般行政取扱要領または市町村防災訓練等取扱要領に定める通知書、もしくは青森県防災ヘリコプター使用承認書(様式第6号)を交付します。これは、防災ヘリコプターの使用が正式に承認されたことを示す重要な書類であり、使用者はこれを基に運用を進めることになります。 この承認プロセスは、防災ヘリコプターの適切な運用と安全確保に不可欠であり、申請者と総括管理者間の連携が重要となります。
III.安全管理 Anzen Kanri 航空安全と隊員の健康管理
防災ヘリコプターの安全運航を確保するため、航空関係法令と国土交通大臣の定める運用限界等指定書を遵守した安全管理体制が構築されています。運航指揮者は、飛行中の安全確認、航空事故発生時の対応、航空隊員へのブリーフィング等を行い、航空事故防止に努めます。また、航空隊員の健康管理も重視され、航空隊員は日頃から健康管理に努め、安全管理に支障がある場合は運航業務に従事させません。定期的な活動要領の見直しも、安全運航の向上に役立てられています。
1. 運航上の安全管理と航空事故防止
総括管理者は、航空関係法令と国土交通大臣が定める防災ヘリの運用限界等指定書に基づき、消防防災業務の適正な執行体制と航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期さなければなりません。これは、防災ヘリコプターの運用における基本的な事項であり、常に最新の安全に関する技術や関係法令、事例などを収集・分析し、航空隊員に周知徹底させることが求められます。活動要領、活動基準、マニュアルなどを整備し、これらを遵守することで安全性を確保します。運航指揮者は、防災ヘリの運航にあたって、機体、装備、資器材、気象状況、離着陸場、運航重量などを確認し、運航の安全を確保する責任を負っています。さらに、運航に関わる航空隊員に対してブリーフィングを行い、活動内容、装備、資器材の状況、健康状態などを確認し、安全に疑義がある場合は是正措置を講じなければなりません。航空隊員自身も、搭載資器材の固縛などを行い機内安全を確保し、飛行中や目標接近時には周囲を監視し、危険を察知したら速やかに機長に報告する必要があります。これらの徹底した安全管理体制によって、航空事故の発生を未然に防ぎ、安全な運航を確保することが目指されています。
2. 航空事故発生時の措置と報告義務
防災ヘリの故障、気象の急変などにより航空事故が発生する恐れがある場合、または発生した場合、運航指揮者は人命・財産に対する危難の防止に最善を尽くし、万全の措置を講じなければなりません。同時に、その状況を運航管理責任者と最寄りの航空局空港事務所に直ちに報告する義務があります。これは、迅速な救助活動や事故原因の究明に不可欠な対応であり、報告の遅れは重大な結果を招く可能性があります。 事故発生時の対応は、運航指揮者の迅速な判断と行動が求められ、その責任は非常に大きいです。 また、総括管理者は、法第19条第1項に基づき、一定の資格を有する技術者による防災ヘリの安全性確認を義務づけられています。これは、防災ヘリコプターの安全性を常に高いレベルで維持するための重要な手続きです。 これらの規定は、航空事故の発生を最小限に抑え、万一発生した場合でも被害を軽減するための対策を明確に示しており、安全管理体制の重要性を改めて認識させます。
3. 航空隊員の健康管理と規律
航空隊員の健康管理は、安全な防災ヘリコプターの運航に不可欠です。航空隊員は、日頃から健康管理に努め、厳正な規律と心身の錬成を図る必要があります。これは、常に最高の状態で業務に臨むため、そして安全な飛行を確保するためには不可欠です。運航指揮者は、航空隊員の健康状態に問題があり、安全管理に支障をきたす可能性があると判断した場合には、防災ヘリの運航やその他の活動に従事させるべきではありません。これは、航空隊員の健康状態が、防災ヘリコプターの安全性に直接影響する可能性があることを示しています。 航空隊員の健康管理は、個人の責任だけでなく、運航指揮者を含むチーム全体の責任であり、継続的な健康管理と適切な対応によって、安全な運航の維持に貢献します。 さらに、運航管理責任者は、最新の安全に関する技術や関係法令、事例などを積極的に収集・分析し、航空隊員に周知徹底することで、安全運航と航空隊員の安全確保の向上に努める必要があります。これは、安全管理体制の継続的な改善と向上を促す重要な要素となっています。
IV.緊急消防援助隊との連携 Kinkyū Shōbō Enjō tai to no Renkei
大規模災害発生時には、緊急消防援助隊との連携が重要となります。本計画では、緊急消防援助隊航空部隊の青森県内への円滑な活動支援を目的とし、ヘリベース(青森空港など)、フォワードベース、ランディングポイントの設定、地上支援活動員の招集、燃料供給体制、情報連絡体制などを詳細に規定しています。調整本部と青森県災害対策本部が連携し、防災ヘリコプターを含む航空機の運用調整を行います。航空支援員の活用も想定されています。
1. 緊急消防援助隊航空部隊の受入れ体制
青森県において大規模災害が発生し、消防組織法に基づく緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援体制について、本計画は詳細に規定しています。特に、緊急消防援助隊航空部隊が円滑に活動できる体制の確保に重点が置かれています。青森県防災航空センター所長またはヘリベース指揮者は、緊援隊航空部隊の応援要請があった場合(緊急消防援助隊の基本計画第4章1(3)で定める災害、または要請要綱第7章に基づく迅速出場に該当する地震・大津波警報を含む)、青森空港管理事務所長に対し、緊援隊航空部隊の受入れを依頼します。これは、ヘリベース(青森空港)への受入れ体制を確立し、迅速な対応を行うための重要な手順です。青森空港が使用できない場合や被災地が遠隔地の場合は、調整本部が被災市町村等とヘリベース指揮者と協議の上、代替ヘリベースやフォワードベース、ランディングポイントを選定します。地上支援活動員の参集場所は、青森県防災航空センター所長またはヘリベース指揮者が指定します。燃料供給についても、多量の燃料が必要な場合は、調整本部がフォワードベースを管轄する消防長または消防署長に対し、消防法に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱の承認に関する調整を行い、ヘリベース指揮者が燃料の搬送を依頼するなど、詳細な手順が規定されています。
2. 情報連絡体制と連携機関
緊急消防援助隊との連携において、迅速かつ的確な情報伝達は不可欠です。応援要請後、消防庁、緊援隊航空小隊等との情報連絡は、ヘリベース指揮者、調整本部、航空機運用調整班の連携によって行われます。ヘリベース指揮者は、ヘリベース状況などの情報を様式1「受援航空隊情報提供FAX」により、緊援隊航空部隊と消防庁航空担当に速やかに情報提供します。情報伝達手段は、防災行政無線、有線電話、FAX、電子メールなどを原則としますが、有線途絶時には衛星電話を活用します。青森県航空隊は、応援要請が決定し調整本部が設置された場合、全体受援計画第8の規定に基づき、調整本部員として航空隊員を派遣します。受入れに困難が生じた場合は、速やかに消防庁航空担当へ連絡します。 連携機関としては、調整本部、青森県災害対策本部連絡調整部対策班(航空機運用調整)、被災地管轄消防本部、医療対策部、DMAT、フォワードベース(ランディングポイント)管理者、院内ヘリポートを有する病院等施設管理者などが挙げられ、これらの機関との綿密な連携によって、円滑な活動が確保されます。 また、航空支援員に関する協定に基づき、青森県内からの地上支援活動員招集も規定されており、航空支援員の招集が困難な場合は消防職員が招集されます。
3. ヘリベース フォワードベース ランディングポイントの設定
緊急消防援助隊航空部隊の活動拠点となるヘリベース、フォワードベース、ランディングポイントの設定についても、本計画で詳細に規定されています。ヘリベースは、災害の終始を通じて緊援隊航空部隊のヘリコプター運用に関する指揮を行い、駐機、整備、給油、装備、宿泊などが可能な拠点です。通常は空港やヘリポートに設置されますが、状況に応じて公園や河川敷などの野外に設置されることもあります。フォワードベースは、被災地近傍の飛行場外離着陸場に設置され、ヘリベースに都度帰投することなく航空活動を安全かつ効率的に継続することを目的としています。ランディングポイントは、緊急着陸場所として利用され、青森県庁ヘリポートが原則ですが、災害救助活動上の必要性から機長の判断で変更可能です。これらの拠点の設定は、ヘリベース指揮者と調整本部、そして被災地管轄消防本部など関係機関との協議によって決定され、迅速かつ的確な災害対応を実現するために不可欠な要素です。 さらに、燃料供給についても、ヘリベース、フォワードベース、ランディングポイントにおける燃料補給が必要な場合、備蓄燃料一覧表を参考に、調整本部がヘリベース指揮者、災対本部対策班と協議の上、搬送を決定します。これは、航空機の継続的な運用を確保するために重要な要素です。
