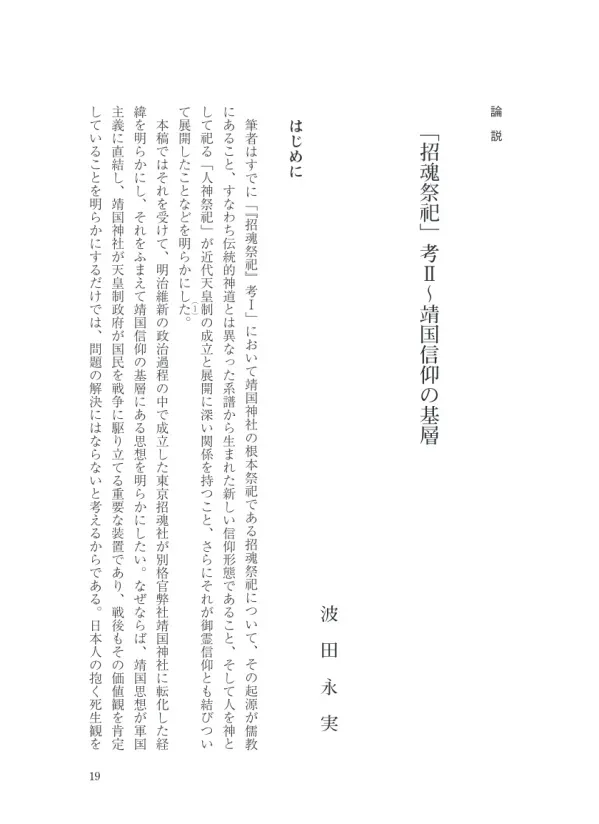
靖国信仰の理解:祭祀考
文書情報
| 学校 | 大学名(不明) |
| 専攻 | 歴史学、宗教学、または関連分野 |
| 場所 | (不明) |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.07 MB |
概要
I.東京招魂社から靖国神社へ 創設と変遷
本稿は、明治維新期の政治状況下で設立された東京招魂社が、如何にして別格官幣社【靖国神社】へと変貌を遂げたのかを考察します。当初、幕末維新期に生まれた新しい信仰形態である【招魂祭】(特にその起源が儒教にある点)を執り行う施設として設立された招魂社は、軍部の強い関与の下、国家施設としての性格を帯びていました。佐賀の乱や西南戦争といった士族反乱、さらには台湾出兵などによる戦死者増加は、招魂社の重要性を高め、祭祀制度の見直しを促しました。陸軍省は、招魂社を「永世不朽の一大社」として位置づけ、神官の設置を強く働きかけ、最終的に明治12年(1879年)、東京招魂社は【靖国神社】と改称され、別格官幣社に列格しました。初期の靖国神社運営は陸軍省が中心となり、神職は内務省が管轄するという体制でした。
1. 東京招魂社の創設と初期の曖昧な位置づけ
明治維新後の政治過程において、東京招魂社は政府主導で創設されました。この招魂社は、幕末維新期に出現した新しい葬祭儀礼である『招魂祭祀』を恒常的に執り行うための施設として設立されました。しかし、この招魂祭祀は伝統的神道の枠組みからは逸脱したものであり、その位置づけは曖昧なままでした。当時の中心人物の一人である津和野藩士福羽美静も神祇官に所属していましたが、東京招魂社は創設当初から軍部が深く関与する国家施設という側面も持ち合わせていました。神祇行政が神祇官から神祇省、さらに内務省へと移行する中で、東京招魂社の性格も変化していったことがわかります。特に、社司や社掌の職務権限の曖昧さが、その初期の不安定な位置づけを示しています。文献『靖国神社誌』や『靖国神社百年史』は、この創設期の様子を理解する上で重要な資料となります。
2. 士族反乱と海外派兵 招魂社の重要性増大
佐賀の乱、西南戦争、台湾出兵、江華島事件など、明治初期の士族反乱や海外派兵は、政府軍兵士の大量戦死をもたらしました。これにより、東京招魂社は政府にとってより重要な役割を担うことになります。戦死者の招魂式と合祀が相次ぎ行われるようになり、祭祀制度の見直しが必要となる状況が生まれます。本文では、それぞれの事件における戦没者数と招魂祭の執行日が時系列で示されています。これらの出来事が、招魂社の祭祀規模の拡大、そして後の靖国神社への発展に繋がる重要な転換点であったことがわかります。これらの出来事の記録は、靖国神社の歴史を理解する上で重要な要素となります。
3. 陸軍省による神官設置の働きかけと靖国神社への昇格
東京招魂社を「永世不朽の一大社」として位置付けるべく、陸軍省は神官の設置を強く求めます。陸軍省は太政官に何度も伺書を提出しますが、当初は「社格がない」ことを理由に拒否されます。しかし、陸軍省は粘り強く働きかけ、東京招魂社が別格官幣社に昇格することを目指します。 最終的には、内務省や海軍省からの賛同を得て、明治12年(1879年)6月4日、東京招魂社は【靖国神社】と改称され、別格官幣社に列格されました。この過程において、神官の設置、神社の運営、そして経費負担に関する陸軍省、内務省、海軍省間の役割分担などが協議され、初期の靖国神社運営の原型が形成されていきます。札幌神社や函館八幡宮を参考に、神官の内務省管轄、維持管理の陸軍省担当といった案も提示されました。この経緯は、靖国神社の特殊な地位形成を理解する上で不可欠な情報です。
4. 靖国神社の財政と特別な地位の確立
靖国神社の設立は、松方デフレの真っ只中であり、神社の財政基盤は脆弱でした。「保存金」の支給は1917年まで続けられましたが、建築修繕などの経理は陸軍省の専任とされ、他の官国幣社とは異なる特別な扱いがなされました。これは太政官制から内閣制への移行期、帝国議会開設、帝国憲法制定という時代背景と関連しています。靖国神社は、別格官幣社という位置づけでありながら、他の同格の神社とは異なり、経費面でも特別な対応がなされました。この特別な扱い、そして陸軍省を中心とした運営体制が、後の靖国神社の政治的・社会的影響力の増大に繋がっていったと推察できます。資料としては『靖国神社百年史 資料編』等が挙げられます。
II.靖国信仰の本質 賀茂百樹 葦津耕次郎論争
昭和9年(1934年)、民間の神道家である【葦津耕次郎】が靖国神社における仏式供養を提案したことに端を発する【賀茂百樹】との論争は、【靖国信仰】の本質を浮き彫りにします。葦津は神仏融合による靖国神社祭神の慰霊を主張しましたが、賀茂百樹ら神道界は、既に神格を得た祭神に仏教の回向は不要と強く反論しました。この論争は、戦死者への弔いの在り方、そして靖国神社が戦死者の死の意味付けを独占しようとする姿勢を明らかにするものでした。この論争における賀茂の論理は、戦死を「名誉」「大歓喜」と意味付けることで国民を靖国信仰に結び付け、悲しみを抑圧する役割を果たしたと分析できます。 【賀茂百樹】と【葦津耕次郎】の主張は、国家神道における「正統」と「異端」という構図で捉えることもできます。
1. 葦津耕次郎の仏式供養提案と賀茂百樹との対立
昭和9年(1934年)11月、民間神道家の葦津耕次郎は、靖国神社において仏教各宗派による仏式供養を提唱しました。これは、靖国神社の祭神に対する仏式の回向・供養を行うことであり、「靖国会」という組織を設立して神仏提携による慰霊を推進しようとするものでした。しかし、当時の靖国神社宮司である賀茂百樹はこれに強く反発し、神道界全体を巻き込む大論争へと発展しました。この論争の発端は、既に神格を得ている靖国神社の祭神に対して、改めて仏教の回向によって成仏させようとする葦津の提案に、神道界が強い反発を示したことにあります。神道界の圧倒的多数意見は、靖国参拝は「回向」ではなく「崇敬」であると捉え、仏式供養を拒否しました。この論争は、靖国信仰の基層にある思想、特に戦死者の死の捉え方に関する重要な問題点を浮き彫りにしました。
2. 葦津耕次郎の宗教観と神仏融合の主張
葦津耕次郎は、靖国神社の祭神の中に仏教徒も多く含まれていることを指摘し、神社と仏教の融合を主張しました。彼は、この主張を「神仏融合」であり「神仏混合」ではないと強調しています。葦津の考えは、日本国民倫理の中心である神社と、日本民族の多数派の宗教である仏教との密接な関係を重視するものでした。彼は、靖国神社における仏教僧侶の正式参拝を提唱する理由として、戦死者の多くが仏教徒であったこと、そして遺族の深い悲しみを慰める必要性を挙げています。さらに、仏教の回向や供養は荒魂を慰藉し、向上させることを目的としており、靖国神社の祭神を安堵させることに繋がるという考えを示しています。しかし、これらの主張は当時神道界から激しい批判を浴びることになります。安藤国重によるパンフレット発行や、全国神職会機関誌編集者による批判などがその例です。
3. 賀茂百樹の反論と靖国信仰の国家神道的解釈
賀茂百樹は、仏教の回向は靖国神社の祭神にとって不要であり、「我が国の祭祀の精神とは全く相容れざること」だと反論しました。彼は、靖国祭神は天皇の御拝によって最高の神として安堵しており、他人の回向を待つ必要はないと主張しました。賀茂の論理は、靖国祭神への「崇敬」としての参拝は許容するものの、「冥福を祈る回向」は許さないというものでした。赤沢史朗は、この問題点を「戦死者の死の意味付けを靖国神社が独占しようとしている」と指摘しています。さらに、賀茂の著述と推定される『靖国神社御祭神遺族の栞』では、戦死を「国家の大生命」への「溶け込み」と捉え、「永遠無窮の幸」を享受するものとして表現しています。この賀茂の論理は、戦死を「名誉」「大歓喜」と意味づけることで国民を靖国信仰に結び付け、家族の悲しみを抑圧する役割を果たしていたと考えられます。大原康夫の『忠魂碑の研究』は、日清・日露戦争期の招魂祭が神仏合同で行われた例を紹介しており、靖国信仰の多様な側面を提示しています。
4. 論争の結末と靖国信仰の本質 感情の錬金術
最終的に、仏教各宗派は昭和10年(1935年)春の大祭に神式で靖国神社に参拝しました。これは、賀茂百樹の主張が事実上受け入れられた結果です。賀茂は、仏式供養の概念を狭義に解釈することで、この結果を正当化しようとしています。しかし、この論争は靖国信仰の本質を問うものでした。筆者は、賀茂の論理を国体論的な「正統」、葦津の立場を「異端」と捉え、この論争を「正統」による「異端」の排除と見なしていました。高橋哲哉の『靖国問題』では、「靖国祭祀=感情の錬金術」という視点から、靖国信仰が悲しみを抑圧し、戦死を顕彰する国家の祭祀であると分析されています。しかし、この分析には疑問が残ります。この論争は、靖国神社が戦死者の死の意味づけをどのように独占しようとしたか、そしてそのことが靖国信仰の本質にどのように関わっているかを考える上で重要な示唆を与えてくれます。
III.戦後の靖国信仰 変容と課題
戦後、靖国信仰は変容を遂げました。「英霊の顕彰」が強調され、【江藤淳】や【小堀桂一郎】らの靖国論に見られるように、祖霊信仰との関連付けや、「死者との共生感」の強調を通して、靖国神社が日本の文化・伝統、ひいては「国の持続」に不可欠な存在として位置付けられるようになりました。しかし、戦犯合祀問題など、依然として靖国神社をめぐる議論は続いており、【靖国信仰】の在り方、特に「開かれた慰霊」の可能性が問われています。江藤淳は、柳田国男の民俗学的視点を取り入れ、靖国祭神を祖霊信仰の系譜に位置付けることで、戦後の靖国信仰の継続を正当化しようとしています。
1. 戦後の靖国信仰の変容 顕彰の強調と平和への転換
戦後、靖国信仰は大きな変容を遂げました。特に、1960年代頃から『日本遺族新聞』のスローガンからも「恒久平和」という言葉が消え、「英霊の顕彰」が強調されるようになりました。近年はさらに「顕彰」の側面が強まっている傾向が見られます。この変化は、敗戦後の日本社会における新たな価値観の反映と言えるでしょう。従来の「戦死の大歓喜」といった国家神道的な解釈は、戦後の平和主義的社会風潮の中で受け入れられにくくなり、「平和の礎」としての戦死者の位置づけへと変化を遂げています。戦後の平和と繁栄が戦死者の犠牲の上に成り立っているという認識から、彼らは「英霊」として崇敬されるべき存在となったのです。しかし、この変化は靖国信仰の全体像を捉える上での一部に過ぎず、より複雑な要素が含まれていることを理解する必要があります。
2. 江藤淳 小堀桂一郎の靖国論 死者との共生と和解の文化
戦後の靖国信仰を代表する論者として、江藤淳と小堀桂一郎の靖国論が挙げられます。江藤は中曽根内閣期の靖国神社公式参拝問題に関わった人物であり、「生者の視線と死者の視線」という論考で、死者の魂と生者の魂の行き交いが日本の文化・伝統を形成しているという独自の視点から靖国信仰を論じています。彼は柳田国男の思想を援用し、死者が生者を見守り続け、生者はねんごろに祭りを繰り返すことで死者へ慰撫しなければならないという考え方を示しています。また、小堀は靖国祭祀を「伝統的な和解の心」が働く政治的妥協策と位置づけています。両者の論考は、靖国神社が単なる宗教施設を超え、日本のアイデンティティや文化の連続性を担保する存在として捉えられている点を示しています。特に、江藤の「英霊の眼が見詰めている」という感覚は、戦後における靖国信仰の新たな側面を浮き彫りにしています。
3. 靖国信仰の閉鎖性と 開かれた慰霊 への課題
江藤・小堀らの靖国論は、靖国信仰が日本固有の文化・伝統に根ざしたものであり、外部からの干渉を拒否すべきであるという結論を示唆しています。これは、靖国信仰が日本社会内部の閉じた円環の中で維持されている現状を反映していると言えるでしょう。特に「戦犯」合祀問題において、この閉鎖的な姿勢が顕著に現れています。しかし、論文の筆者は、靖国神社の問題点をこの閉鎖性に見ており、「開かれた慰霊」の可能性を探る必要性を提起しています。靖国神社の在り方、そして靖国信仰が日本近代、東アジア、そして世界においてどのような意味を持つのかを問い直すことが、今後の重要な課題となります。 「開かれた慰霊」とは何か、そして靖国神社はどのようにその役割を果たすべきなのかという問いは、現在もなお議論の的となっています。
