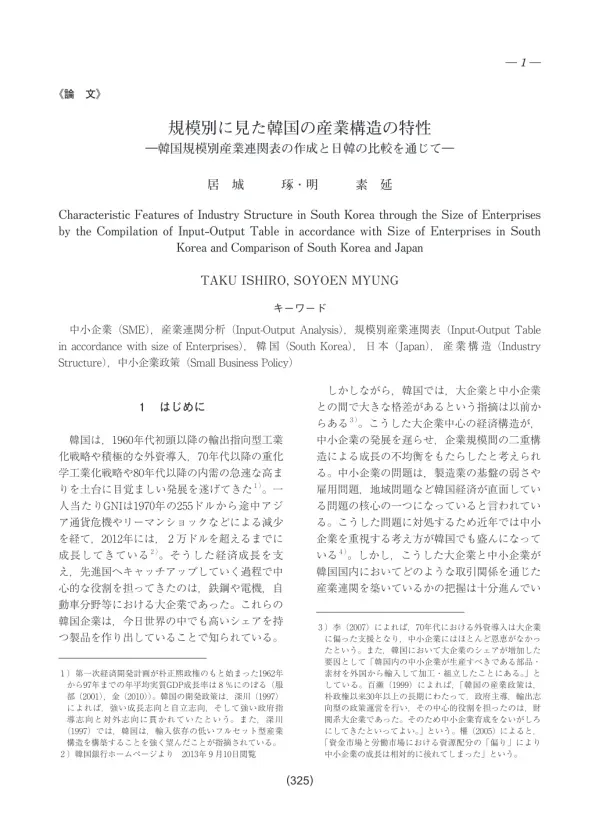
韓国中小企業の産業連関分析
文書情報
| 学校 | 流通経済大学 |
| 専攻 | 経済学(推定) |
| 文書タイプ | 論集論文(推定) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.21 MB |
概要
I.韓国の産業構造と中小企業 大企業との格差と産業連関
本論文は、2005年の韓国の規模別産業連関表を作成し、日本との比較分析を行うことで、韓国経済における中小企業(중소기업)の現状と課題を明らかにすることを目的としています。特に、大企業(財閥系大企業を含む)と中小企業間の取引関係、産業構造の変化、そして地域経済への影響に焦点を当てています。韓国経済は、輸出指向型工業化戦略や積極的な外資導入によって目覚ましい発展を遂げましたが、その過程で大企業中心の経済構造が形成され、中小企業との格差が拡大しました。近年、韓国政府は中小企業重視の政策を推進していますが、その効果や大企業との産業連関の実態については、更なる分析が必要です。本研究では、投入係数や国産化率(RS比率、ORM比率)といった指標を用いて、日韓両国の産業構造、特に機械工業(電機、輸送機械)と軽工業における大企業・中小企業間の取引関係を詳細に比較検討しています。
1. 韓国経済の高度成長と大企業中心の産業構造
1960年代以降、韓国は輸出指向型工業化戦略と積極的な外資導入により著しい経済成長を遂げました。一人当たりGNIは1970年の255ドルから2012年には2万ドルを超えるまでに増加しました。この成長を牽引したのは、鉄鋼、電機、自動車などの分野における大企業です。これらの企業は世界的に高い市場シェアを誇っています。しかし、同時に大企業と中小企業の間に大きな格差が存在するという指摘が長年されています。この大企業中心の産業構造は、中小企業の発展を阻害し、経済成長の不均衡をもたらしたと分析されています。中小企業を取り巻く問題は、製造業の基盤の弱さ、雇用問題、地域問題など、韓国経済の核心課題と深く関わっています。近年、韓国では中小企業を重視する政策が盛んになっていますが、大企業と中小企業の取引関係、すなわち産業連関の実態解明は未だ不十分です。この点に着目し、本研究では韓国の規模別産業連関表を作成し、日本との比較分析を通して、韓国経済における中小企業の現状と課題を明らかにします。
2. 大企業と中小企業の格差 過去の産業政策と現状の課題
韓国における大企業と中小企業の格差は、過去の産業政策と深く関連しています。李(2007)の研究によると、1970年代の外資導入は主に大企業に偏っており、中小企業にはほとんど恩恵がなかったと指摘されています。また、大企業のシェア拡大には、中小企業が生産すべき部品や素材を海外から輸入して加工・組立する点が大きく影響しているとしています。百瀬(1999)は、韓国の産業政策は朴政権以来30年以上、政府主導の輸出指向型政策が中心であり、その主役は大企業であったと分析、中小企業育成が軽視されてきた点を指摘しています。権(2005)は、中小企業庁が作成する規模別産業連関表の分析が毎年の中小企業白書で公表されているものの、研究論文として発表されていない点を指摘しています。こうした先行研究を踏まえ、本研究は、大企業と中小企業の生産誘発関係、機械工業における国産化率や両者の関係、軽工業における中小企業から大企業への取引関係といった仮説を立て、検証を進めます。朴槿恵政権以降の中小企業重視の政策動向も、この格差是正に向けた重要な背景となっています。
3. 韓国規模別産業連関表の作成と分析方法
本研究の中核となるのは、2005年を対象とした韓国の規模別産業連関表の作成と、日本との比較分析です。この産業連関表を作成するために、統計庁の「鉱工業統計調査報告書」や日本の規模別産業連関表の情報などが活用されました。分析にあたっては、RS比率(地域内供給比率)とORM比率(地域内市場指向比率)といった指標を用いて、地域経済における企業の役割を分析します。さらに、産業間のつながりを確認するために、投入係数(輸入分を差し引いたもの)も用いて、大企業と中小企業間の取引関係を詳細に分析します。特に、生産誘発効果、感応度係数、影響力係数などを用いて、大企業と中小企業の相互作用を多角的に検証することで、韓国の産業構造における中小企業の位置づけを明らかにすることを目指します。また、下田・藤川・渡邉(2005)の研究を参考に、1985年から2000年の規模別産業連関表を用いた分析結果も考慮に入れ、経済のサービス化、中小企業の輸出依存度、中間投入率などの観点から分析を行います。
II.韓国中小企業の現状と政策 時代背景と課題
1960年代の輸出促進政策では、軽工業を中心に大企業・中小企業ともに成長しました。しかし、1970年代の重化学工業育成政策以降、中小製造業の雇用と付加価値額の割合は大幅に減少。1980年代には輸出増加で雇用・事業体数は増加しましたが、1990年代の国際化・自由化、そして1997年のアジア通貨危機を経て、中小企業のシェアは伸び悩み、大企業との格差は拡大しています。中小企業基本法の改正や中小企業振興法、中小企業技術革新促進法など、様々な政策が実施されてきましたが、課題は依然として残っています。特に、輸出主要品目の変化(1980~90年代の衣類、船舶から近年の半導体、無線通信へのシフト)も中小企業を取り巻く環境の変化を反映しています。
1. 韓国中小企業の経済における割合と推移
韓国経済において中小企業が占める割合は非常に高く、2010年の時点で全企業体数の99.9%、全従業員数の86.8%を占めていました。しかし、その割合は時代とともに変遷しています。1960年代には、政府の輸出促進政策の下、労働集約的な軽工業(繊維産業など)が中心となり、大企業と中小企業の輸出はともに増加し、両者の格差は小さかったと考えられます。1966年には中小企業基本法が制定されています。しかし、1970年代の重化学工業育成政策以降、状況は一変しました。1973年までに中小製造業の従業員数は66.4%から39.4%に、付加価値額は52.8%から27.2%へと大幅に減少しました。これは、重化学工業への産業構造の変化に伴い、中小企業のシェアが縮小したことを示しています。その後、1985年以降は中小製造業の従業員数と付加価値額は増加に転じ、1995年にはそれぞれ68.9%、46.3%にまで回復しました。しかし、1997年のアジア通貨危機以降は、その増加傾向は鈍化し、2011年には従業員数76.7%、付加価値額47.3%という状況でした。事業体数の割合は1963年から2011年まで常に96%以上を維持していました。
2. 韓国中小企業政策の変遷 時代背景と対応策
韓国では、大企業と中小企業の格差問題が顕在化する中、1970年代後半から本格的な中小企業政策が展開されました。1970年代半ばまでは、中小企業の事業体数は低迷・減少傾向にありました。この時期には、1975年の中小企業系列化促進法、1978年の中小企業振興法などが制定され、中小企業基本法も改正され、中小企業の範囲が従業員数200名未満から300名未満へと変更されました。1980年代には、中盤以降の好況により輸出が大幅に増加し、輸出依存度が高まりました。その結果、中小企業の雇用と事業体数は増加し、1981年には中小企業製品購買促進法、1982年には中小企業優先業種選定及び中小企業固有業種制度が本格的に実施されました。1990年代は国際化・自由化が進展しましたが、韓国の賃金上昇により、繊維、履物、衣類などの労働集約的な中小企業の主要輸出品目は、中国などの低賃金国との価格競争で劣勢となりました。そのため、産業構造は低付加価値、労働集約型から高付加価値、技術集約型へと変化しました。2000年代に入ると、情報通信、自動車、化学などの大企業の主要輸出品目は好調でしたが、内需の伸び悩みやグローバル化の遅れにより、中小企業と大企業の格差はさらに拡大しました。2000年には中小企業基本法が改正され、中小企業の範囲が従業員数300名未満または資本金80億ウォン以下となりました。近年では、2012年に中小企業技術革新促進法が改正され、中小企業の技術流出を防ぎ、安定的な技術開発と経営を支援する政策が強化されています。
3. 中小企業の輸出動向と主要品目の変化
韓国の中小企業の輸出は、時代とともに変化してきました。1980年代と1990年代には、衣類、船舶、履物、木材、魚類などが主要な輸出製品でした。しかし、近年は半導体や無線通信機器など、より技術集約的な製品へとシフトしています。この変化は、グローバル化や技術革新、そして韓国経済全体の産業構造変化を反映したものであり、中小企業が生き残るためには、高付加価値製品への転換や技術開発への投資が不可欠であることを示唆しています。中小企業庁による規模別貿易統計は2006年から公開され、1995年から2011年までの地域別・国別の輸出統計が提供されています。2009年以降は、中小企業、中堅企業、大企業、その他に区分され、より詳細な分析が可能となっています。このデータは、韓国中小企業の輸出構造を理解する上で重要な情報源であり、本研究でも活用されています。これらの輸出動向の背景には、前述したような、韓国経済の高度成長、産業構造の変化、そして政府による中小企業政策の変遷が複雑に絡み合っていると言えます。
III.韓国の規模別貿易統計と産業連関表の作成
韓国の中小企業の規模別貿易統計は2006年から公開されていますが、規模別産業連関表の分析は十分ではありません。本研究では、2005年を対象に韓国の規模別産業連関表を作成しました。データソースには、統計庁の「鉱工業統計調査報告書」などが用いられ、日本の規模別産業連関表の情報も参考にしています。分析には、生産誘発、投入係数、感応度係数、影響力係数、RS比率、ORM比率といった指標を用いて、大企業・中小企業間の取引構造を分析し、日本との比較を行いました。
1. 韓国の規模別貿易統計の現状と課題
韓国の中小企業に関する規模別貿易統計は、中小企業庁によって2006年に初めて一般公開されました。現在(2013年時点)では、1995年から2011年までの地域別・国別の輸出統計が公開されています。ただし、公開データの範囲や分類には時間的な変化があり、2009年以前は中小企業と大企業の2区分だったものが、2009年以降は中小企業、中堅企業、大企業、その他の4区分に細分化されています。中堅企業の定義は、中小企業の範囲に含まれない、相互出資制限企業を除いた大企業とされています。この規模別貿易統計は、韓国中小企業の輸出構造を分析する上で重要なデータとなりますが、輸入に関するデータの公開状況や、より詳細な分類に関するデータの不足など、分析を進める上で課題も残されています。特に、中小企業の国際競争力や、大企業との取引関係をより詳細に把握するためには、より充実した統計データの整備が必要となるでしょう。 この統計データの不足は、韓国経済における中小企業の役割を正確に評価する上で障壁となっています。
2. 2005年韓国規模別産業連関表の作成 データと方法
本研究では、韓国の産業構造を大企業と中小企業の規模別に分析するために、2005年の韓国規模別産業連関表を作成しました。この産業連関表の作成には、統計庁の「鉱工業統計調査報告書(5人以上)」が主要なデータソースとして用いられています。この報告書から、規模別の生産額、付加価値額、最終需要額、中間投入額を推計しました。規模別の中間財取引については、日本の規模別産業連関表の情報も参考に、推計が行われています。具体的には、2005年産業連関表(全国版)の中間投入(需要)内生部門計、付加価値部門計、最終需要計を、鉱工業統計調査報告書の規模別付加価値額を用いて規模分割し、大企業と中小企業それぞれの列(行)和を固定値として目標値を求めています。付加価値計、営業剰余、固定資本減耗などは、鉱工業統計調査報告書の規模別付加価値額から算出されています。最終需要項目と付加価値項目の推計においては、大企業と中小企業の分割比率を統計庁の報告書から取得し、産業連関表の規模分割を行っています。日本の中小企業性製品(大企業性製品)の定義を参考に、韓国の製品についても分類を行っています。
3. 産業連関表分析のための指標 RS比率 ORM比率 国産化率
作成された韓国の規模別産業連関表の分析には、複数の指標が用いられています。RS比率(the ratio of regional supplying)は、ある産業が地域内からどれだけ投入を受けているかを示す指標であり、ORM比率(the ratio of orientation towards the regional market)は、その産業が地域内へどれだけ産出しているかを示す指標です。これらの指標は、地域経済における企業の役割を把握する上で有効です。さらに、本研究では、直接・間接の自給率を国産化率として計算しています。これは、ある産業が生産を行う際に、国内の中間財をどれだけ投入しているかを示す指標であり、その産業における国内サプライチェーンの強さを示唆します。この国産化率は、特に機械工業(電機、輸送機械)において、韓国と日本を比較分析する上で重要な指標となります。 これらの指標を用いた分析により、韓国の産業構造における大企業と中小企業の役割、特に地域経済への貢献度や相互依存関係の強さを明らかにすることを目指しています。また、これらの指標は、日本における先行研究(例えば、Romero and Santos(2007)の研究)を参考に用いられています。
IV.日韓比較分析 仮説検証と結論
本研究では、以下の3つの仮説を検証しました。1. 韓国では日本以上に大企業への生産誘発が大きい。2. 韓国の機械工業では、国産化率や大企業・中小企業間の関係が弱い。3. 韓国の軽工業では、中小企業から大企業への取引関係が強い。結果、仮説1は必ずしも支持されず、軽工業では日本以上に中小企業への生産誘発が大きいことが示されました。仮説2は、国産化率は低いものの、投入係数の観点からは大企業・中小企業間の関係が強い可能性を示唆しました。仮説3は支持され、感応度係数や影響力係数の高いことから、中小企業と大企業の相互の強い取引関係が確認されました。この分析から、韓国経済においては、軽工業及び中小企業の役割が依然として大きいことが示唆されます。
1. 仮説の設定と分析の枠組み
本研究では、韓国の規模別産業連関表を用いた日韓比較分析を行い、3つの仮説を検証します。最初の仮説は、大企業・中小企業間の生産誘発関係において、韓国では日本以上に大企業への生産誘発割合が高いというものです。2つ目の仮説は、電機・輸送機械といった機械工業において、韓国は日本と比べてRS比率(地域内供給比率)や国産化率が低く、ORM比率(地域内市場指向比率)も低く、大企業と中小企業の関係も弱いというものです。3つ目の仮説は、軽工業においては、感応度係数などを用いた分析で、韓国では日本と比べて中小企業から大企業への取引関係が依然として強いというものです。これらの仮説検証を通じて、韓国の産業構造における大企業と中小企業の相互関係、特に規模別産業連関の実態を明らかにすることを目指します。分析には、生産誘発係数、投入係数、感応度係数、影響力係数、RS比率、ORM比率、国産化率といった様々な指標が用いられ、2005年を対象とした韓国の規模別産業連関表と日本のデータとの比較が行われます。
2. 生産誘発効果に関する仮説検証 軽工業における中小企業の重要性
大企業・中小企業の生産誘発関係に関する仮説(韓国では日本以上に大企業への生産誘発が大きい)については、必ずしも支持されませんでした。特に軽工業においては、日本以上に中小企業での生産誘発が大きいという結果が得られました。この結果は、韓国経済において軽工業、ひいては中小企業の果たす役割の大きさを示唆しています。機械工業(電機・輸送機械)などでは、大企業への生産誘発効果が大きくなる傾向が見られる一方、軽工業においては、中小企業への波及効果が顕著であることが示唆されています。これは、韓国の産業構造において、軽工業分野における中小企業の生産活動が、経済全体への波及効果において重要な役割を果たしていることを意味します。この結果は、韓国の産業政策において軽工業分野の中小企業振興を軽視できないことを示唆するものです。
3. 機械工業と軽工業における日韓比較 投入係数と取引関係
機械工業(電機・輸送機械)に関する仮説(韓国は日本と比べRS比率、国産化率、ORM比率が低く、大企業と中小企業の関係も弱い)については、RS比率や国産化率は確かに日本より低いものの、投入係数の分析からは、電気機械に関しては必ずしもそうとは言い切れない結果となりました。国産化率は日本の方が高いものの、域内投入係数の観点からは、韓国の大企業・中小企業間には日本以上に強い取引関係がある可能性が示唆されました。軽工業に関する仮説(中小企業から大企業への取引関係が強い)は、感応度係数や影響力係数の高さから支持されました。しかし、それらの係数が共に高いことから、単なる系列的な取引関係だけでなく、中小企業と大企業間の相互的な取引関係も強いと考えられます。このことは、韓国の軽工業における中小企業が、大企業との緊密な連携の下で生産活動を行っていることを示唆しています。 全体として、韓国の産業構造は、日本と比較して軽工業、特に中小企業の占める割合が大きく、それらが韓国経済を支える上で重要な役割を果たしていることが示唆されました。
4. まとめと今後の課題
本研究では、2005年韓国規模別産業連関表を作成し、日本との比較分析を通じて韓国の産業構造における大企業と中小企業の関係を多角的に検証しました。その結果、軽工業分野における中小企業の重要性、機械工業における大企業・中小企業間の意外なほど強い関係、そして軽工業における中小企業と大企業の相互的な強い取引関係が明らかになりました。しかし、本研究は2005年時点の一時点的な分析であるため、時系列的な分析の必要性、雇用表の規模分割による雇用問題への分析、地域間の規模別産業連関表の作成による地域間格差分析など、今後の課題が残されています。これらの課題に取り組むことで、韓国経済における中小企業の役割をより深く理解し、より効果的な中小企業政策の立案に貢献することが期待されます。特に、韓国経済の持続的な発展のためには、中小企業の活性化が不可欠であることを改めて認識させられます。
V.今後の課題
今後の課題として、2005年単年の分析にとどまらず、時系列分析による検証、雇用表の規模分割による雇用問題への分析、そして地域間の規模別産業連関表作成による地域問題への分析が挙げられます。これらの分析を通じて、韓国の中小企業政策の更なる効果的な推進に貢献することを目指します。
1. 時系列分析による産業構造変化の解明
本研究は2005年時点の韓国の規模別産業連関表に基づいて行われたため、その結果の解釈には限界があります。より詳細な分析、そして動的な産業構造変化の把握のためには、時系列的なデータに基づく分析が不可欠です。複数年の規模別産業連関表を作成し、時間経過に伴う産業構造の変化、特に大企業と中小企業の相互関係、そしてそれぞれの産業における生産誘発効果や投入構造の変化を詳細に分析することで、より精緻な政策提言を行うことが可能になります。具体的には、過去数年間のデータを用いて、産業構造における変化のトレンドを明らかにし、その要因を分析することで、より効果的な中小企業支援策の検討に繋がります。 また、時系列データを用いることで、政策効果の検証も可能となり、より実効性のある政策立案に貢献できるでしょう。
2. 雇用問題への規模別分析 産業連関表と雇用表の統合
韓国経済における中小企業の課題として、雇用問題が挙げられます。本研究では産業連関表を用いて産業構造を分析しましたが、雇用問題をより深く理解するためには、雇用表と産業連関表を統合した分析が必要です。規模別に分割された雇用表を作成し、産業連関表と組み合わせることで、各産業における雇用創出効果、大企業・中小企業間の雇用格差、そして各産業の雇用構造の変化などを分析できます。この統合分析によって、韓国の雇用政策における課題をより具体的に明らかにし、効果的な雇用創出のための政策提言を行うことが期待できます。特に、中小企業における雇用創出の促進策を検討する上で、この規模別雇用データは不可欠な情報となります。
3. 地域間格差の分析 地域別規模別産業連関表の作成
韓国経済におけるもう一つの重要な課題は地域間格差です。本研究では全国レベルの規模別産業連関表を用いた分析を行いましたが、地域レベルでの分析を行うことで、地域間の産業構造の違い、大企業と中小企業の地域分布、そして地域経済における両者の役割をより詳細に把握することができます。そのため、韓国の主要地域を対象とした地域別規模別産業連関表を作成することが重要です。この地域別データを用いることで、地域経済における大企業と中小企業の役割の違いを分析し、地域特性に合わせた効果的な中小企業支援策を検討することが可能になります。地域間の産業連関の強弱を分析することで、地域経済活性化のための政策立案にも貢献できると考えられます。 特に、地域経済の活性化に貢献する中小企業の育成支援策を効果的に設計する上で、この地域レベルでの分析は極めて重要となります。
